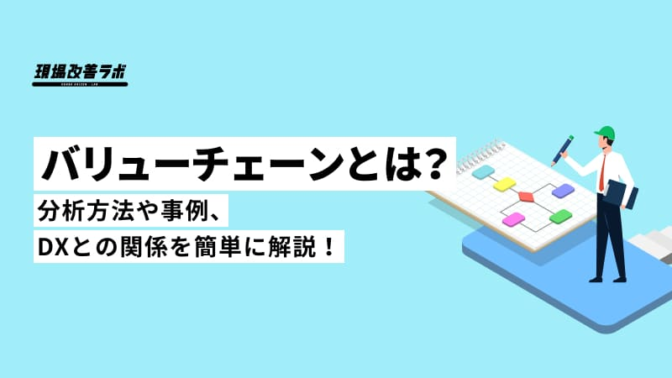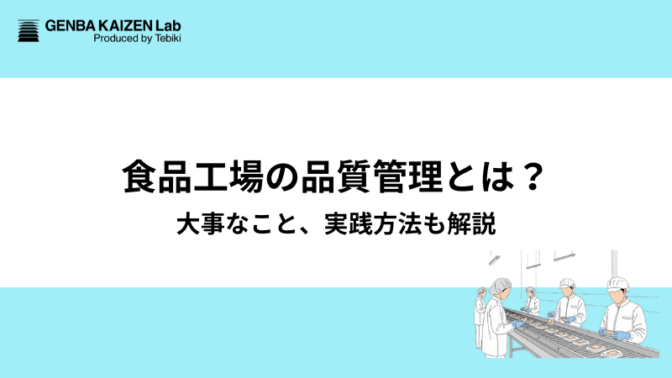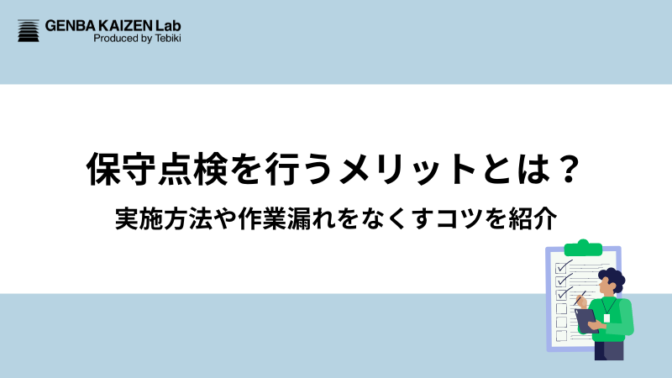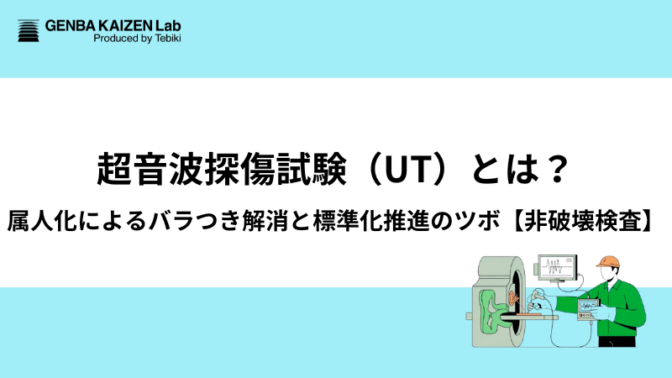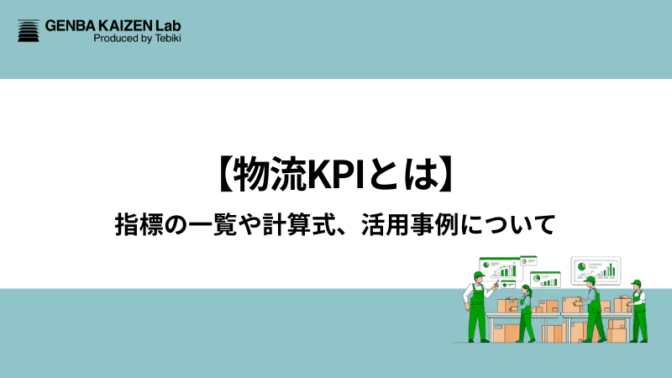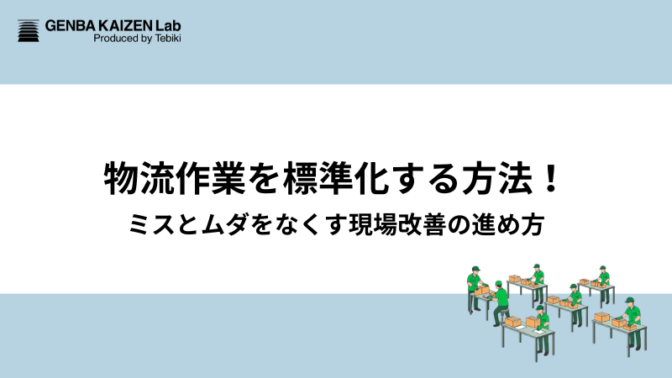かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を展開する現場改善ラボ編集部です。
快適なオフィス環境、良好な人間関係、効率的な働き方など、従業員が最大限のパフォーマンスを発揮するための職場環境の改善は、企業にとって重要な課題です。
本記事では、職場環境改善に役立つ具体的な7つの対策を紹介します。さらに、改善に向けた注意点や、すぐに実践できる職場環境改善の「基礎」を固める方法も解説しますので、是非ご一読ください。
目次
職場環境の改善とは?
職場環境の改善とは、一体どのようなことを指すのでしょうか?簡単に言うと、従業員がより快適に、そして安全に働けるように、職場全体の環境を整えることです。
具体的には、次のようなものが含まれます。
【物理的な環境】照明の明るさ、室温、騒音、オフィス家具の配置など
【人間関係】上司や同僚とのコミュニケーション、チームワーク、ハラスメントの防止など
【仕事の量と質】業務量、残業時間、仕事の難易度、責任の範囲など
【働き方】フレックスタイム制度、リモートワーク、休暇の取得しやすさなど
職場環境は、従業員の健康やモチベーションに大きく影響します。快適な環境で働くことは、従業員のストレスを軽減し、集中力や生産性を高めることに繋がります。
また、労働安全衛生法第三条では、事業者には快適な職場環境の実現が責務として求められています。
”事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。”
つまり、職場環境の改善は、法律で定められた義務であると同時に、企業にとって従業員の ウェルビーイングを守るための重要な取り組みと言えます。
職場環境が悪い状態とは?
では、具体的にどのような状態が「職場環境が悪い」と言えるのでしょうか?いくつかの例を挙げながら見ていきましょう。
1. 物理的な環境が整っていない
- 照明が暗くて目が疲れる
- 室温が適切に管理されておらず、夏は暑すぎ、冬は寒すぎる
- 騒音がひどく、集中できない
- 椅子や机などのオフィス家具が古く、体に負担がかかる
このような環境では、従業員は体調を崩しやすくなるだけでなく、仕事への集中力も低下してしまいます。
2. 職場の人間関係が悪い
- 上司や同僚からのパワハラやいじめがある
- 相談しにくい雰囲気があり、悩みを打ち明けられない
- チームワークが悪く、協力し合えない
人間関係の悪化は、従業員のストレスを増大させ、メンタルヘルスの問題を引き起こす可能性があります。
3. 業務量や働き方に問題がある
- 業務量が多く、常に残業や休日出勤を強いられる
- フレックスタイム制度やリモートワークが導入されておらず、柔軟な働き方ができない
- 仕事の評価が不公平で、モチベーションが低下する
このような状況では、従業員は仕事とプライベートのバランスを崩し、心身の健康を損なうリスクが高まります。
これらの問題を放置しておくと、従業員の離職率増加や生産性低下に直結するかもしれません。企業は、問題点を把握し、改善に向けて積極的に取り組む必要があります。
職場環境を改善すべき4つの理由
職場環境の改善は、単に従業員のためだけではありません。企業にとっても、多くのメリットをもたらす重要な取り組みです。
職場環境を改善すべき理由は、主に以下の4つが挙げられます。
- 生産性の向上
- 人手不足解消
- 従業員のストレス軽減
- 労働災害の防止
生産性の向上
従業員が働きやすい環境を作ることは、業務の生産性向上に直結します。快適な温度、整理整頓された作業スペース、体への負荷が考慮されたオフィス家具などは、従業員の集中力や作業効率を高めるために欠かせません。
逆に、職場環境が悪いと、従業員はストレスを感じやすくなり、集中力が低下し、ミスが増加するなど、生産性が低下する恐れもあります。
また、「5S活動」(整理・整頓・清掃・清潔・躾)を徹底することで、無駄な時間や労力を削減し、業務効率を改善できます。
関連記事:業務改善につなげる「5S活動」の進め方!目的や事例、アイデアも解説
人手不足解消
職場環境が整っていると、人材の流出を防げます。従業員の満足度が向上し、離職率が低く、定着率が高まるためです。
これは、人手不足の解消に大きく貢献します。また、職場環境の改善は、企業のイメージ向上にも繋がります。働きやすい環境が整っている企業は、求職者にとって魅力的であり、優秀な人材を獲得しやすくなります。
従業員のストレス軽減
職場環境は、従業員の心身の健康に影響を与えます。職場環境が良好であれば、ストレスが軽減され、心身の健康が保たれます。
逆に、職場環境が悪いと、ストレスが増加し、メンタルヘルスの問題や体調不良を引き起こすかもしれません。従業員のストレス軽減は、休職や離職の防止、医療費の削減などにも繋がり、企業にとっても大きなメリットです。
労働災害の防止
職場環境を整えることは、労働災害発生のリスクを減らすことにも繋がります。例えば、5Sを徹底することは、作業場の整理整頓に繋がり、転倒や落下などの事故防止に役立ちます。
また、適切な照明や換気の確保は、従業員の健康状態を良好に保ち、労働災害のリスク削減に効果的です。
労働災害は、企業にとって大きな損失をもたらします。職場環境の改善は、労働災害を未然に防ぎ、安全な職場を作るために欠かせません。
職場環境を改善するための7つの対策
職場環境の改善には、様々なアプローチがあります。ここでは、具体的な対策を7つに分けてご紹介します。
- 物理的な職場環境の整備
- 業務の属人化を防ぐマニュアルの整備
- 安全衛生教育の実施
- 従業員のメンタルヘルスケア
- コミュニケーションの促進
- 働き方改革の推進
- フィードバックと評価制度の見直し
物理的な職場環境の整備
快適な作業スペースは、集中力や生産性を高める上で重要です。オフィス環境の改善としては、以下のようなものが挙げられます。
【照明】明るすぎず暗すぎない、適切な照明の設置
【温湿度】夏は涼しく、冬は暖かく、快適な温度を保つ
【空調】換気を適切に行い、新鮮な空気を保つ
【家具】椅子や机など、体に負担の少ないオフィス家具の導入
【騒音対策】集中しやすいよう、騒音を軽減するための対策
例えば、夏場に野外での作業が発生するような工場では、熱中症予防などの暑さ対策が欠かせません。
業務の属人化を防ぐマニュアルの整備
職場環境を整えるためには、業務の偏りがないようにすることも大切です。特定の従業員に業務が集中し、負担が大きくなってしまうと、残業や休日出勤が増え、心身の健康を損なう可能性があります。
業務の属人化を防ぎ、複数人が対応できる体制を作る必要があります。業務内容を明確化し、誰でも理解できるようなマニュアルを整備することが重要です。
属人化を防ぐためのマニュアルには、「動画マニュアル」の活用がおすすめです。動画マニュアルは、文字や写真といった情報で口頭だけでは説明できない細かな手順や動作を分かりやすく伝えられます。動画マニュアルであれば、わからないところも繰り返し学習できるので知識が定着します。
『より詳しく動画マニュアルのメリットを知りたい!』という方は、ガイドブック「動画マニュアルで現場の教育をかんたんにする方法」をご覧ください。
安全衛生教育の実施
安全衛生教育は、従業員の健康と安全を守る上で欠かせません。職場環境と安全衛生教育は密接に繋がっています。
従業員が安全に関する知識や意識を高めることで、事故や怪我を未然に防げます。安全衛生教育の内容としては、以下が挙げられます。
- 労働災害の発生状況
- 危険予知の訓練
- 安全作業の方法
- 健康管理
定期的な安全衛生教育の実施は、従業員の安全意識向上に繋がり、安全な職場環境づくりに貢献します。
従業員のメンタルヘルスケア
従業員のメンタルヘルスにも配慮が必要です。定期的なストレスチェックの実施や、カウンセリング制度の導入など、従業員の心の健康を守るための取り組みが重要です。
【ストレスチェック】従業員のストレス状況を把握し、適切な対策を講じる
【カウンセリング制度】悩みを抱える従業員が相談できる窓口を設ける
【産業医の配置】専門的な立場から、従業員の健康管理をサポートする
【健康管理プログラム】 健康に関する教育やセミナーなどを実施し、従業員の健康意識を高める
【福利厚生の充実】ジム利用補助、健康診断、メンタルヘルスプログラムなど、健康的な生活をサポートする福利厚生を導入する
企業は、従業員の心身の健康を守るためのサポート体制を整える必要があります。
コミュニケーションの促進
良好なコミュニケーションは、働きやすい職場環境を作る上で欠かせません。上司と部下が定期的に1on1ミーティングを行い、個々の従業員の悩みやアイデアを共有できる場を設けることも大切です。
また、従業員同士が気軽に意見交換できるような雰囲気作りも必要です。
【1on1ミーティング】上司と部下が定期的に面談を行い、コミュニケーションを促進する
【意見交換会】従業員同士が自由に意見交換できる場を設ける
【社内イベント】懇親会やレクリエーションなど、親睦を深めるためのイベントを開催する
コミュニケーションを活性化すれば、従業員同士の相互理解を深め、働きやすい環境を作れます。
働き方改革の推進
柔軟な働き方を推進し、従業員が仕事とプライベートのバランスを取りやすくすることも、職場環境改善の重要な要素です。
【フレックスタイム制度】従業員が自分のライフスタイルに合わせて勤務時間を調整できるようにする
【リモートワーク】場所にとらわれずに働ける環境を提供する
【有給休暇の取得促進】従業員が休暇を取得しやすくして、心身の健康を維持できるようにする
働き方改革を進めることで、従業員のワークライフバランスが改善され、仕事へのモチベーション向上やストレス軽減に繋がります。
フィードバックと評価制度の見直し
従業員のモチベーションを高め、成長を促進するためには、公平で透明性の高い評価制度の導入が重要です。
【評価制度の見直し】業績や能力だけでなく、プロセスや行動も評価するような制度を導入する
【フィードバック】定期的にフィードバックを行い、従業員の成長を支援する
建設的なフィードバックを行う文化を根付かせることで、従業員が自分の評価に納得し、成長を実感できる環境を作れます。
職場環境を改善するメリット
職場環境の改善は、従業員だけでなく、企業にとってもメリットをもたらします。ここでは、職場環境改善によって得られる具体的なメリットを5つご紹介します。
- チームワークの強化
- 企業イメージと採用力の向上
- イノベーションの促進
- 顧客満足度の向上
- 法的リスクの低減
チームワークの強化
良好な職場環境は、従業員同士が自然と協力し合える雰囲気を作り出します。ストレスの少ない環境で、オープンなコミュニケーションが促進されると、従業員同士の信頼関係が深まり、より強いチームワークが生まれるためです。
お互いに協力し合うことで、業務効率が向上し、課題解決にも繋がります。
企業イメージと採用力の向上
働きやすい職場環境は、企業のイメージアップに大きく貢献します。
求職者にとって、職場環境は企業を選ぶ際の重要な要素です。快適で働きがいのある環境が整っている企業は、求職者から魅力的に映り、優秀な人材を獲得しやすくなります。
結果として、企業全体のレベルアップ、競争力強化に繋がります。
イノベーションの促進
健康的で、互いに支え合うような職場環境では、従業員一人ひとりが自分の才能を最大限に発揮し、新しいアイデアを積極的に提案できるようになります。
失敗を恐れずに挑戦できる雰囲気があることで、創造性や革新性が育まれ、イノベーションが促進されます。
顧客満足度の向上
従業員のモチベーションやエンゲージメントは、顧客満足度に直結します。職場環境が改善されると、従業員はより高いモチベーションとエンゲージメントを持って仕事に取り組むことができるからです。
その結果、顧客に対してより質の高いサービスを提供でき、顧客満足度の向上に繋がります。
法的リスクの低減
労働安全衛生法では、快適な職場環境の実現が事業者の責務として定められています。職場環境を改善することで、この法的責務を果たすことができます。
また、職場環境が整っていれば、労働災害などの発生リスクを低減させることが可能です。これは、企業にとって、トラブルや訴訟のリスクを低減することに繋がります。
職場環境を改善する際に注意する3つのポイント
職場環境の改善は、ただ闇雲に進めるのではなく、いくつかのポイントを押さえることが重要です。効果的に、そして持続的に職場環境を改善していくために、注意すべき3つのポイントをご紹介します。
- 従業員の声を反映させる
- 長期的な視点を持つ
- 改善の優先順位を設定する
従業員の声を反映させる
職場環境改善の目的は、従業員がより働きやすい環境を作ることです。
改善施策を計画する際には、従業員の声やニーズを反映させることが非常に重要です。従業員が実際にどのような問題を感じているのか、どのような改善を望んでいるのかを把握するために、アンケートやヒアリングなどを実施し、その結果を分析しましょう。
例えば、アンケートでは「職場環境に関する満足度」「改善してほしい点」「働き方に関する要望」などを質問項目に含めます。ヒアリングでは、より具体的な意見や要望を聞くことができるためです。
従業員の声を丁寧に収集し、分析することで、本当に必要な改善施策が見えてきます。
長期的な視点を持つ
職場環境の改善は、一度実施すれば終わりというものではありません。短期的な効果を狙うのではなく、長期的な視点を持って、継続的に取り組むことが重要です。
一時的な対策ではなく、効果が持続するような仕組みやルールを作ることが大切です。
例えば、「ノー残業デー」を設けるだけでなく、業務効率化のためのツールを導入したり、フレックスタイム制を導入するなど、根本的な働き方改革を進めるようにしましょう。
また、施策の効果を定期的に測定し、必要に応じて改善を続けることで、より効果的な職場環境改善を実現できます。
改善の優先順位を設定する
多くの企業にとって、時間や費用、人員など、リソースには限りがあります。限られたリソースを有効に活用するためには、改善施策に優先順位をつけることが大切です。
まず、現状における課題を分析し、最も影響の大きい課題から取り組むようにしましょう。改善の効果を早期に実感し、従業員のモチベーション向上にも繋げられます。
例えば、「従業員満足度調査」の結果、最も不満度が高かったのが「長時間労働」だったとします。まずは残業時間を削減するための対策を優先的に実施する、といった具合です。
また、新たな施策を導入する際は、従業員にとって負担にならないよう、十分に配慮する必要があります。
職場環境改善には、まず5S活動から
職場環境の改善に取り組む際に、最初に取り組むべきものが「5S活動」です。5S活動とは、整理・整頓・清掃・清潔・躾の5つのSからなる、職場環境改善のための基本的な活動です。
職場環境の改善において、まさに「基本中の基本」となります。
職場環境を改善する5S活動の進め方
5S活動によって職場環境を改善することで、以下のようなメリットがあります。
【労災リスクの減少】整理整頓された職場では、転倒や落下などの事故のリスクを減らせる
【業務の効率化】必要なものがすぐに取り出せるようになり、業務効率がアップする
【従業員の意識向上】5S活動を通して、従業員の職場環境に対する意識を高められる
職場環境の改善を目的とした5S活動では、まず「どのような職場にしたいのか」というゴールを明確に設定することが重要です。
5S活動の推進におすすめなのが「動画マニュアル」
動画マニュアルは、文字や写真といった二次元的な情報、口頭説明だけでは伝えきれない細かな手順や動作を視覚的に分かりやすく伝えられる手段です。
具体的な手順や作業の流れを映像で示すことで、細かい動作や注意点を直感的に把握させることが可能です。配属間もない新人や外国人でも視覚的に動きを学ぶことができます。
また、正しい内容で一度動画マニュアルを作成すれば、同じ情報を何度でも繰り返し伝えることも可能です。座学やOJTで起きる「教える人によって内容がバラつく」課題を防ぐことができます。
動画マニュアルがあることで、使用する従業員は先輩社員などに都度質問をしなくても、自身のペースで分からない部分を繰り返し見返せます。繰り返しの学習を行えることで習慣として定着し、結果的に「躾」「標準化」が進んでいる現場に繋がります。
『より詳しく動画マニュアルのメリットを知りたい!』という方は、以下のガイドブック「動画マニュアルで現場の教育をかんたんにする方法」をご覧ください。
>>>動画マニュアルはなぜ教育課題を解決できる?そのメリットとは
5S活動を推進し、職場環境の改善に役立つ「tebiki」
5S活動を推進している現場産業を中心に、多くの現場で活用されている動画マニュアルのツールが「現場教育システムtebiki」です。
現場教育システム「tebiki」は、動画編集未経験者でもかんたんに動画マニュアルが作成できるツールです。以下のような機能を取り揃えており、5Sにまつわる社内的なルールや作業手順など、教育工数を削減しつつも分かりやすく従業員に伝えることが可能です。
- 動画の音声を自動で字幕化
- 日本語字幕を100ヵ国語以上に自動翻訳が可能
- 現場の教育に必要な機能を厳選したシンプルで使いやすい編集画面
- テスト機能を活用した理解度の可視化
- オフライン再生機能で通信環境が悪い現場でも使用できる
- スキルマップ作成機能で従業員のスキル取得状況を可視化
- レポート機能で従業員の学習状況を可視化
上記以外のtebikiに関する詳細な機能や、具体的なプランなどを詳しく知りたい方は以下より紹介資料をご覧ください。
まとめ
この記事では、職場環境の改善について、その重要性から具体的な対策、そして改善によって得られるメリットまでを幅広く解説しました。
職場環境の改善は、従業員にとっても企業にとっても、多くのメリットをもたらす重要な取り組みです。快適なオフィス環境の整備、良好な人間関係の構築、効率的な働き方の実現など、改善の内容は多岐にわたります。
全ての対策を一度に行うことは難しい場合もあるでしょう。現状における課題を分析し、優先順位を決めながら、段階的に改善を進めていくことが大切です。
特に、業務に偏りがあり、特定の従業員に残業や休日出勤が集中している場合は、早急な対策が必要です。業務の属人化を防ぐため、マニュアルを整備し、複数の人が対応できる体制を作ることで、業務の偏りを解消し、従業員の負担を軽減できます。
職場環境の改善は、継続的な取り組みです。従業員の声に耳を傾け、状況に合わせて柔軟に対応していくことで、より良い職場環境を実現し、企業の成長へと繋げていきましょう。


-2.png)