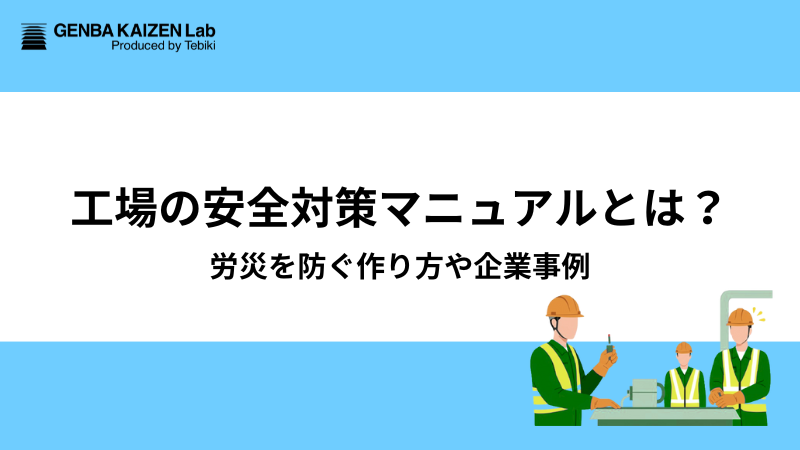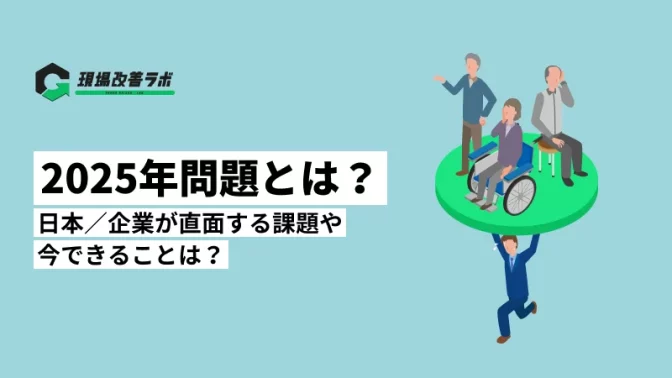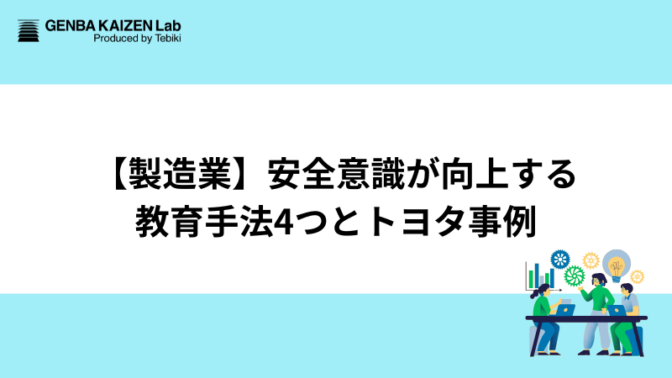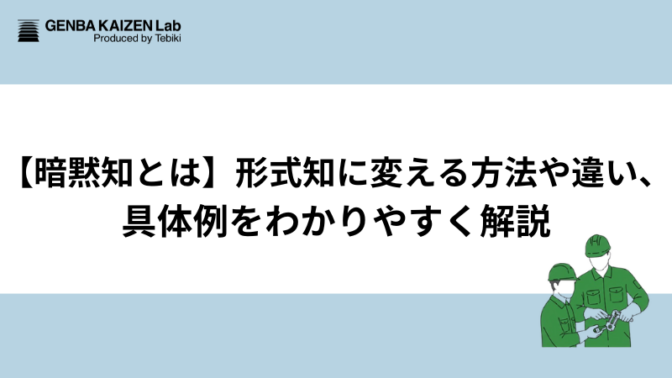工場向け動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
工場や製造現場で欠かせないのが「安全対策マニュアル」です。しかし実際には、紙や文字だけの分厚いマニュアルが読まれず形骸化し、労災やヒヤリハットの温床になっているケースが少なくありません。厚生労働省のデータでも、労働災害による死傷者数は依然として高水準で推移しており、企業には法的な安全配慮義務も課せられています。
本記事では、安全マニュアルの目的と重要性を整理しつつ、ありがちな失敗例と効果的な作成の3大原則を解説します。さらに、動画マニュアルを活用した成功事例や、盛り込むべき項目の見本も紹介。「現場で本当に使える」安全マニュアル作りの方法を解説します。
※労災を撲滅するための安全対策やマニュアル作りの重要なポイントのみを、以下の資料に凝縮してまとめています。本格的な安全対策を検討している方はあわせて参考にしてみてください。
▼知っておきたい工場の安全対策▼
・工場の労災ゼロを実現する、安全教育の新常識
・ヒューマンエラー による労災を未然防止する安全教育
目次
工場の安全対策マニュアルとは?本質的な目的と重要性
工場での安全対策マニュアルは労災防止と教育効率化に欠かせない文書であり、目的と意義を理解することが重要です。そこで、以下の2点について解説します。
- 安全対策マニュアルの目的と重要性
- 【注意】紙マニュアルは労災の温床
安全対策マニュアルの目的と重要性
安全対策マニュアルとは、工場における労働災害を未然に防ぐための文書です。作業手順を標準化し、従業員の安全意識を高め、企業の社会的責任を果たす役割を担います。
厚生労働省の統計によると、令和6年の労働災害による死亡者数は746人で過去最少でしたが、休業4日以上の死傷者数は135,718人と4年連続で増加しました。死傷者数の増加傾向は、工場における安全対策が依然として不十分であることを意味していると考えられます。
また、労働安全衛生法では企業に従業員への安全配慮義務が定められており、マニュアル作成は法的責務の範囲です。しっかりと整備されたマニュアルがあることで、現場の作業者は迷うことなく安全手順を守れるようになり、教育コストの削減や生産性の向上にもつながるでしょう。
【注意】紙マニュアルは労災の温床
工場で長年用いられてきた紙の安全対策マニュアルは、現代の現場には適していません。理由は、紙や文字だけでは「安全な作業」と「危険な作業」の違いを十分に伝えきれないからです。
特に工具の扱い方や力加減といったカンコツは文章では理解が難しく、誤解が事故の原因になります。さらに、外国人労働者が増加している工場では、紙のマニュアルを翻訳するだけでは細かなニュアンスが伝わりません。その結果、教育の質に差が生じ、安全意識の浸透も不十分となります。
関連資料:カンコツが伝わる! 『現場で使われる』作業手順書のポイント
実際、安全対策に成功している多くの工場では「一目で正しい手順が理解できるマニュアル」を実現するため、動画マニュアルを導入しています。映像であれば危険箇所や動作を直感的に理解でき、誰が見ても同じ行動が取れる環境を整えることが可能です。
動画を通じた安全対策の効果や事例は、以下の資料で解説しています。
>>「安全意識が高い製造現場はやっている! 動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例」を見てみる
安全対策が浸透していない工場にありがちな「間違ったマニュアル整備」4つの例
工場では安全対策のためにマニュアルを整備しますが、方法を誤ると逆効果になることもあります。ここでは具体的に以下の「間違ったマニュアル整備」4つの例について解説します。
- 失敗例①:紙と文字だけで作ったが、結局読まれず形骸化する
- 失敗例②:ベテランの「カン・コツ」や危険のニュアンスが伝わらない
- 失敗例③:人によって解釈が異なり、作業が標準化されない
- 失敗例④:外国人材への教育が進まず、安全意識に差が生まれる
失敗例①:紙と文字だけで作ったが、結局読まれず形骸化する
工場の安全対策で多いのが、紙と文字だけに依存したマニュアルです。分厚く文字ばかりのマニュアルは、必要な情報をすぐに見つけにくく、いざという時に役立ちません。
また、更新作業は印刷や差し替えが必要で手間が大きく、現場の実態と乖離しやすい傾向があります。実際、多くの現場では「マニュアルの作成や改訂に膨大な負担が発生している」という声が聞かれます。
結果として、古い手順が使われ、事故や労災につながる危険性が増します。工場の安全対策を有効にするには、紙中心の管理から脱却し、内容が伝わるマニュアルを効率的に作る仕組みが必要です。
例えば製造業の児玉化学工業株式会社は、膨大な紙マニュアルはあったものの「理解されない」「伝わらない」ことから、すべて動画マニュアル(tebiki現場教育)に置き換え、形骸化しないマニュアル作りを進めています。参考として、同社が実際に作成した動画マニュアルを以下に掲載します。
▼「ヤスリでバリをとる」動画マニュアル▼
※「tebiki」で10分で作成
上のような複雑な業務作業も、動画で手順をおさめれば「誰が見ても同じ解釈」になるので、円滑なコミュニケーションを促せます。ちなみに本動画は、製造業の現場教育に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」で作成されています。tebikiのサービス詳細や導入事例についてはサービス資料をご覧ください。
>>>かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育サービス資料」を見てみる
失敗例②:ベテランの「カン・コツ」や危険のニュアンスが伝わらない
工場の安全対策では、ベテラン作業者の「カンコツ」をマニュアルで伝えることが課題です。安全作業の核心である工具の握り方や機械の異常音などの感覚は、文字や写真では正確に伝わりません。そのため、結局OJTに頼らざるを得ず、教育の属人化が進みます。
カンコツや危険なニュアンスを伝えるにはOJTは必須ですが、OJT教育に傾倒しすぎると、教育者の教え方のばらつきや違いによって理解度に差が生まれ、安全対策が十分に浸透しない結果につながります。
すなわち安全対策につながるマニュアル作成のポイントは、カンコツがいかに伝わりやすく整備できているかもポイントになるのです。
文字だけでは伝わらないベテランの「カンコツ」をマニュアルや作業手順書で伝えるための作り方は、以下の資料でも詳しく解説しているのでよければ参考にしてみてください。
▼関連資料▼
・「カンコツが伝わる! 『現場で使われる』作業手順書のポイント」
・“伝わらない”“属人化している”カンコツ作業を標準化する最適解
失敗例③:人によって解釈が異なり、作業が標準化されない
工場で作られる安全対策マニュアルには「慎重に」「適切に」など曖昧な表現がよく使用されます。しかし、曖昧な表現は人によって解釈が異なるため、作業のばらつきを生み出します。その結果、手順不遵守や自己流の危険な作業を誘発し、品質や安全レベルの標準化が進みません。
特に危険作業では、解釈のズレが労災や重大事故につながる可能性があります。安全対策を徹底するには、具体的かつ明確な行動基準を記したマニュアルが欠かせません。
例外として、資格を持っている従業員や、特定の知識や経験がある従業員のみが遂行できる業務については、専門性や安全性を担保するために業務の標準化を避けた方がよいケースはあります。しかし、ほとんどの業務では標準化を行うべきでしょう。
標準化が進まないと属人化のリスクが進み、最終的には安全性だけでなく現場の生産性全体の低下にも直結します。属人化を解消し安全や生産性の向上を実現するには、以下の資料も参考になるため、あわせてご覧ください。
>>>「製造現場の属人化リスク 標準化を促進して生産性を高める 実践的な方法とは」を見てみる
失敗例④:外国人材への教育が進まず、安全意識に差が生まれる
工場の安全対策で特に課題となるのが、外国人スタッフへの教育です。日本語のマニュアルを多言語に翻訳するには大きなコストと時間がかかり、さらに翻訳では細かなニュアンスが伝わらず、重大な事故につながるリスクがあります。
実際、日世株式会社では外国人スタッフが増える中で、紙の日本語マニュアルでは理解が不十分となり、教育者が1回2時間、週2〜3回の研修を行う大きな負担が発生していました。
※最終的に同社はマニュアルを、字幕の自動翻訳機能がついた動画マニュアル作成ツール(tebiki現場教育)に置き換え、研修時間は1/10に削減され、教育効率が飛躍的に向上しました。さらに、を活用したことで、外国人スタッフの理解度テストの正答率は100%に到達。これまで伝わらなかった安全の要点が確実に浸透するようになり、工場全体の安全意識の底上げに成功しました。
特に製造業や工場といった現場教育は、多国籍人材が混在しているケースが多く、文字に頼らないマニュアル整備が求められています。動画マニュアルの導入効果や事例の詳細が知りたい方は、以下の資料もあわせて参考にしてみてください。
関連資料:外国人労働者に「伝わらない」を解決した動画マニュアル活用事例集
工場における安全対策マニュアル作りの「三大原則」
工場の安全対策マニュアルを効果的に機能させるには、現場で実際に使われる工夫が欠かせません。ここでは前章の失敗例を踏まえた上で以下の3つの原則を紹介します。
- 原則①:視覚的で、直感的に理解できること
- 原則②:誰が見ても同じ解釈・同じ動作ができること
- 原則③:必要な時に、いつでも・どこでもアクセスできること
原則①:視覚的で、直感的に理解できること
工場の安全対策マニュアルは、文字だけでは十分に伝わりません。人間の脳はテキストよりも画像や映像を記憶しやすく、視覚情報が安全意識の定着につながります。そのため、写真や図、イラストを積極的に用い、一目で危険箇所や正しい手順が理解できるようにすることが重要です。
特に作業現場では、数秒で情報を把握できるかどうかが事故防止の分かれ目になります。特に、マニュアル整備が現場の安全性を左右する工場や製造業では、動画による安全対策のマニュアルが多く導入されています。製造業における動画マニュアルの導入事例は多く存在するため、導入効果や事例を参考にしたい方は以下の資料もあわせて参考にしてみてください。
原則②:誰が見ても同じ解釈・同じ動作ができること
工場の安全対策マニュアルは、曖昧な表現を排除することが欠かせません。「慎重に」や「適切に」といった言葉は、人によって解釈が異なり、危険な自己流作業を誘発します。
そのため「誰が・何を・いつ・どこで・なぜ・どのように」の5W1Hを具体的に記載することが大切です。例えば「レバーを強く押す」ではなく「両手で体重をかけ、レバーを45度まで下げる」と示せば、誰でも同じ動作を再現できます。
さらに、動画や写真を組み合わせれば、解釈の余地をなくすことが可能です。安全対策は「同じ理解と同じ行動」を全員が実行して初めて機能します。明確で具体的なマニュアルがあれば、工場の作業は標準化され、事故のリスクを大幅に減らせるでしょう。
関連資料:製造業での労災ゼロを達成する従業員の安全意識を向上させる安全教育
原則③:必要な時に、いつでも・どこでもアクセスできること
工場の安全対策マニュアルは、「いつでもすぐに取り出せること」が重要です。マニュアルが必要なタイミングで瞬間的に確認できる環境こそが、事故を未然に防ぐためです。
例えば製造業の株式会社テック長沢では、製造現場の各作業場にタブレットが設置されており、作業場に貼られているQRコードをタブレットで読み込むと作業内容が動画で流れるようになっています。

これにより、必要なタイミングですぐにマニュアルにアクセスし、正しい作業内容がチェックできます。作業に不慣れた新人従業員でもパートの方でも、動画と同じように作業を推進できるため、正しい安全作業の手順を踏んで業務にあたれるのです。
※同社がQRコード読み込みで流している動画マニュアルは「tebiki現場教育」です。
このように、作業時に必要なマニュアルがその場で読める体制でなければ、マニュアルはいずれ形骸化します。読まれないマニュアル整備は避けなければならないので、本当に現場で使われるマニュアル作りが、現場の安全を確保するうえで非常に重要なのです。
安全マニュアルの伝達手段と「動画」が最適解である理由
工場で安全対策を徹底するには、マニュアルをどのように伝えるかが重要です。ここでは代表的な以下の手段を比較し、なぜ動画が最適解なのかを解説します。
- 手段1:動画マニュアル
- 手段2:紙・PDFのマニュアル
- 手段3:ExcelやPowerPointでの電子化
手段1:動画マニュアル
工場の安全対策を実効性のあるものにするには、動画マニュアルの導入が効果的です。動画は動きや音を伴うため、工具の扱いや危険の兆候など、文字や静止画では伝わりにくい「カンコツ」を直感的に理解できます。
動画では視覚的に危険箇所を認識できるため、原則①(視覚的で、直感的に理解できること)を十分満たします。さらに、正しい作業手順を映像で示すため、人による解釈のブレがなく、誰が見ても同じ動作を再現可能。原則②(誰が見ても同じ解釈・同じ動作ができること)も十分に満たせます。
加えて、クラウド型の動画マニュアルツールを使えば、スマートフォンやタブレットから現場で即時に確認できるため、原則③(必要な時に、いつでも・どこでもアクセスできること)も実現します。
特に製造業の現場では複雑な動作が多く、外国人労働者への教育が難しくなる要因となります。しかし動画であれば、言葉が十分に伝わらなくても映像から手順の理解が可能です。
例えば「児玉化学工業株式会社」では「言葉がなくても理解できる」動画を整備し、外国人教育を効率的に進めています。参考として、実際に同社の現場従業員が作成した動画マニュアルを以下に掲載します。
▼動画マニュアルの例▼
※「tebiki」で作成
安全対策が徹底できている現場は、動画による安全手順の標準化を進めている企業が多いです。動画マニュアルによる安全対策の推進の詳細を知りたい方は、以下の資料もあわせて参考にしてみてください。
関連資料:安全意識が高い製造現場はやっている! 動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例
手段2:紙・PDFのマニュアル
工場の安全対策において、紙やPDFのマニュアルは従来から多く使われています。写真や図を掲載することである程度の視覚化は可能ですが、動きや音といった危険のニュアンスは伝わりにくく、原則①(視覚的で、直感的に理解できること)を十分に満たすとは言えません。
また、必要な情報を探すにはページをめくる必要があり、アクセス性も低く、原則③(必要な時に、いつでも・どこでもアクセスできること)は不十分です。さらに、更新の際には印刷や配布、旧版の回収が必要となり、現場に古い情報が残ってしまうリスクが高まります。
特に大規模工場では、改訂作業が追いつかず、最新の安全手順が反映されないまま作業が行われることも珍しくありません。紙やPDF形式のマニュアルは「作ったら終わり」となりやすく、現場での活用度が下がり、結果として形骸化しやすいと言えるでしょう。
安全対策を強化するには、紙やPDFだけに依存するのではなく、視覚的で更新性の高い手段と組み合わせることが求められます。
手段3:ExcelやPowerPointでの電子化
工場の安全対策マニュアルをExcelやPowerPointで電子化する企業も多いでしょう。ExcelやPowerPointは比較的使いやすく、初期費用を抑えられる点でメリットがあります。また、クラウドで共有すればアクセス性も多少は向上します。
しかし、ファイルのバージョン管理が煩雑になりやすく、古い版が残るリスクがあります。さらに、動画や画像を埋め込むことで情報を充実させることは可能ですが、ファイルサイズが大きくなり、スマートフォンなどで閲覧する際には動作が重くなる傾向があります。そのため、原則③(必要な時に、いつでも・どこでもアクセスできること)を満たすのは難しいのが実情です。
加えて、ExcelやPowerPointは作業手順を「静止情報」として示すのが中心で、動きやニュアンスを伝えるのには限界があります。原則①や②を満たすには不十分であり、「たまに見る程度」の補助的な手段として活用するのが現実的と言えるでしょう。
したがって、工場の安全対策を徹底するための有効な手段は「動画」であることが言えます。
安全対策マニュアルの整備に成功している工場事例
そこで、安全対策マニュアルの整備に成功している工場事例として以下の3社を紹介します。
- コスモ石油株式会社の事例
- 児玉化学工業株式会社の事例
コスモ石油株式会社の事例
コスモ石油株式会社は、国内有数の石油精製・販売企業としてガソリンや灯油などの供給を担い、堺製油所は京阪神エリアにおける重要拠点です。
同社が最も重視するのは「安全第一」で、危険物を扱う以上、安全教育の徹底が不可欠でした。しかし現場では、専門的な内容をテキストや紙のマニュアルで伝えるのに限界があり、OJTに頼らざるを得ず、教育者の負担や教育時間の増加が大きな課題となっていました。
そこで同社は「動画マニュアル(tebiki現場教育)」を導入し、労災事例や保全作業を映像化。複雑な作業を視覚的に学べる仕組みを整えました。その結果、教育の均一化と効率化が進み、労災防止の意識向上にも成功。現場にマニュアルを持ち込む手間も省け、教育担当者の負担軽減と安全レベルの底上げを実現しました。
関連資料:安全意識が高い製造現場はやっている! 動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例
児玉化学工業株式会社の事例
児玉化学工業株式会社は、1946年創業の化学メーカーで、自動車部品や住宅設備、水回り製品、さらにゲームパッケージなど幅広い分野を手掛けています。
同社の現場では安全対策マニュアルの整備に大きな課題がありました。紙の要領書は膨大で、外国人従業員には日本語が伝わりづらく、ベテランの暗黙の了解に頼った教育は属人化を招き、危険の温床となっていました。
そこで同社は「動画マニュアル(tebiki現場教育)」を導入し、作業手順や安全ルールを映像で見える化。外国語字幕機能も活用し、誰でも同じ内容を理解できる体制を整えました。
その結果、手順書作成の工数は紙の1/3に削減され、ルールの統一と作業標準化が進行。新人や外国人スタッフへの教育効率が飛躍的に高まり、工場全体の安全意識と品質改善につながりました。
関連資料:安全意識が高い製造現場はやっている! 動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例
【見本あり】工場の安全対策マニュアルに盛り込みたい項目
工場の現場では「すぐに使える安全マニュアルが欲しい」という声が多く聞かれます。そこでここでは、特定業種に限定しない「一般的な安全作業手順書」に盛り込むべき必須項目を、表形式で整理しました。
まずは下記の見本を基に、自社の状況に合わせてカスタマイズしてみてください。
| 項目 | 内容例 |
|---|---|
| ① 表紙・基本情報 | 作業名、手順書番号、版数、作成日、承認者など |
| ② 目的 | 労働災害防止や作業品質確保のための目的を明記 |
| ③ 適用範囲 | 適用される部署、作業内容、対象従業員を明確化 |
| ④ 作業に必要な 保護具・設備・工具 | ヘルメット、安全靴、保護メガネ、専用工具など |
| ⑤ 作業手順 | ステップごとに「誰が」「何を」「どう行うか」を明記 |
| ⑥ 危険・有害要因と 安全上の注意点 | 巻き込まれ、感電、墜落などリスクとその対策を記載 |
| ⑦ 異常時の措置 | 機械故障や体調不良時の対応手順・連絡先 |
| ⑧ 関連文書 | 関連するリスクアセスメント、点検表など |
| ⑨ その他 | 作業前点検や作業後の片付け手順など必要に応じて追記 |
これはあくまで基本的な骨子です。各工場の実態やリスクアセスメントの結果に基づき、項目を追加・修正することが重要です。表形式で整理するだけでも現場での視認性が高まり、作業者が迷わず確認できるマニュアルになるでしょう。
工場の安全対策マニュアル整備に推奨されるのは「動画マニュアル」
工場における安全対策マニュアルは、本来「労災防止」と「現場の安全意識向上」を目的としています。しかし多くの工場では、紙や文字中心のマニュアルが読まれず、形骸化しているのが現状です。その原因は、作業者にとって内容が「伝わらない」ことにあります。
現場で本当に活きるマニュアルの原則は、「視覚的で直感的に理解できること」「誰が見ても同じ解釈ができること」「必要な時にすぐアクセスできること」の3点です。3原則を十分に満たすのが動画マニュアルです。危険のニュアンスや熟練者のコツも映像なら一目で伝わり、安全レベル向上と教育効率化を実現できます。
製造業や工場に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」は、現場従業員が手軽にスマホで撮影から編集が可能なので、本来の業務や稼働時間を圧迫せずに、安全対策のマニュアル整備を推進できます。tebiki現場教育の詳しい機能や導入効果・事例は以下のサービス資料からご覧いただけますので、参考にしてみてください。
>>工場向け動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」のサービス資料を見てみる
参照元