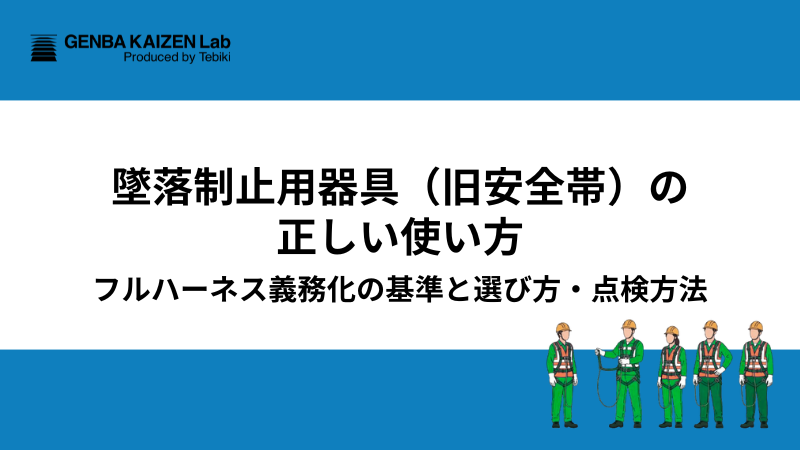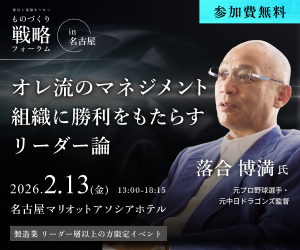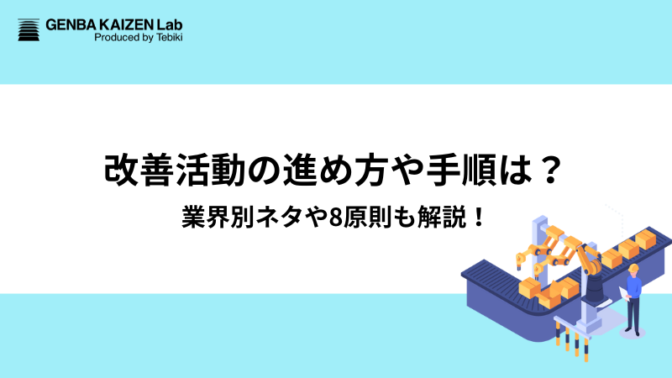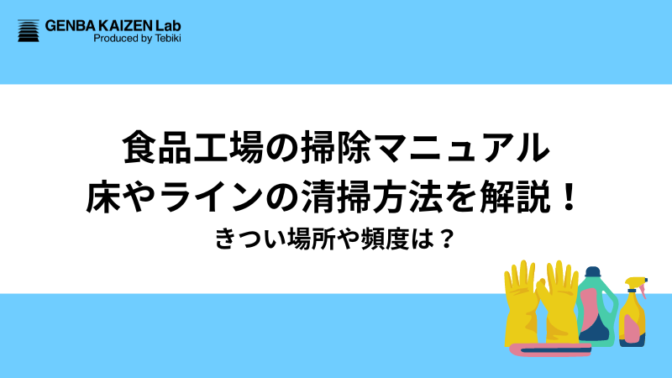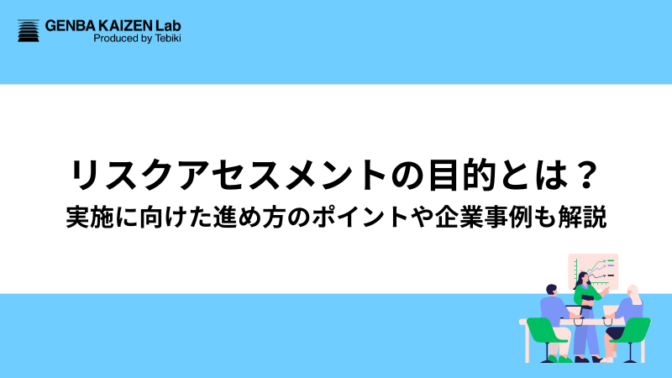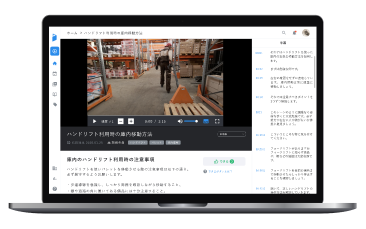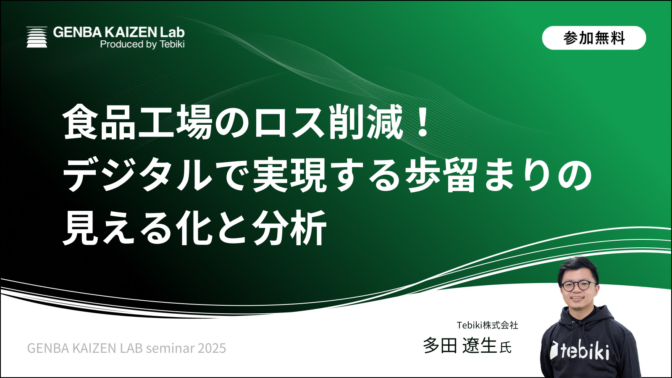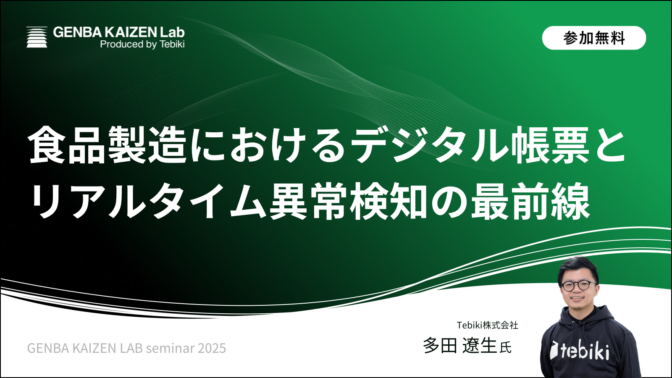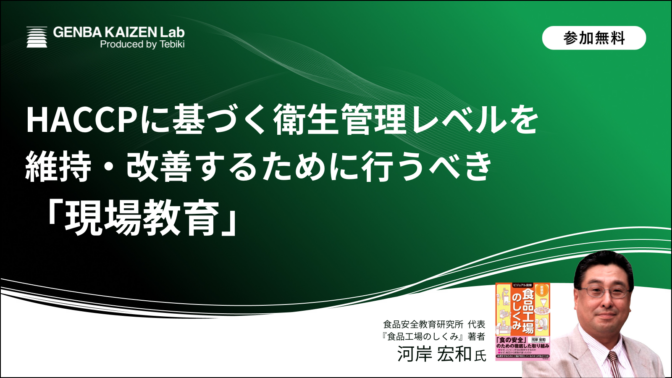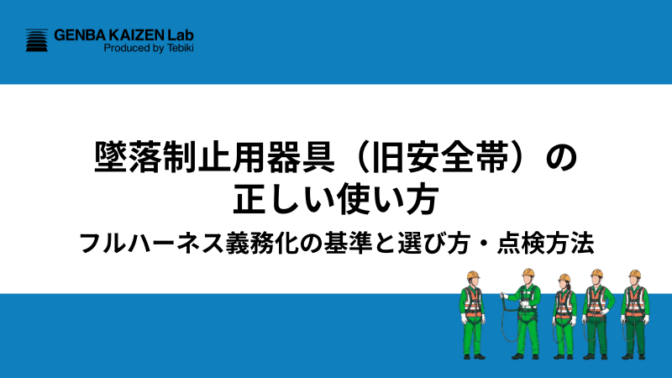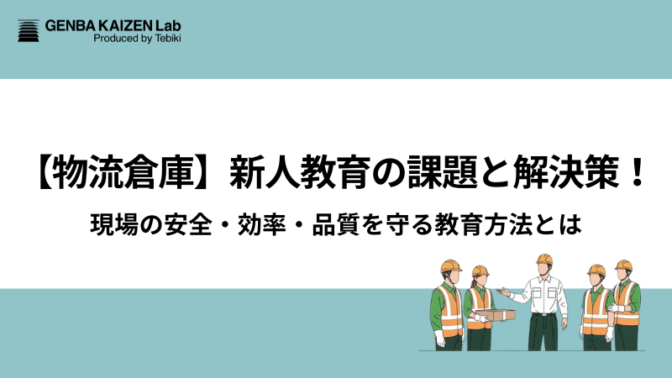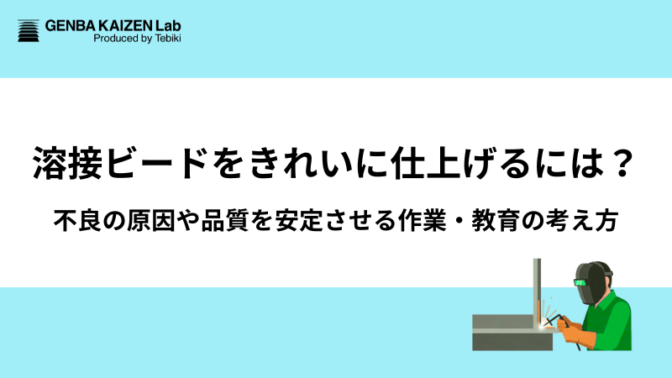かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を展開する現場改善ラボ編集部です。
高所作業の命綱である「安全帯」は法改正により、現在は「墜落制止用器具」へと名称が変わりました。そして旧規格品の使用は法令違反となります。さらに2022年の猶予期間終了を経て、現場では「フルハーネス型」の使用が原則義務化されました。
一方で「自分の現場に合う器具がわからない」「正しい装着方法を指導できない」という悩みを抱いている方は多いと思います。そこで本記事では、新規格に基づく選び方や装着手順の基礎から、事故を防ぐ点検・教育ノウハウまでを網羅的に解説します。現場の安全管理と法令遵守を徹底するために、本記事をぜひお役立てください。
なお、両者の厳密な違いについては後述しますが、本記事では現場での分かりやすさを考慮し、法令上の「墜落制止用器具」を便宜上「安全帯」と表記します。名称は旧来のものを使用していますが、解説内容はすべて最新の法規制(新規格)に対応しています。
目次
- 1 安全帯とは?高所作業に必要な墜落制止用器具の基礎知識
- 2 安全帯(墜落制止器具)の種類と構造
- 3 安全帯(墜落制止器具)のフルハーネス原則化と法規制・規格のポイント
- 4 フルハーネスの正しい装着方法
- 5 フック・ランヤードの正しい使い方と掛け方
- 6 ランヤード・ショックアブソーバの正しい選び方
- 7 高所作業で起こりやすい安全帯(墜落制止器具)の誤使用と事故リスク
- 8 安全帯(墜落制止器具)の使用前・使用後の点検方法と交換目安
- 9 安全帯(墜落制止用器具)の正しい使い方が「現場で再現できない」理由
- 10 安全帯(墜落制止用器具)の正しい使い方は「動画」でわかりやすく教育!
- 11 まとめ
- 12 【補足】安全帯(墜落制止器具)の器具併用について
安全帯とは?高所作業に必要な墜落制止用器具の基礎知識
高所作業の命綱である安全帯は、法改正により「墜落制止用器具」へと名称が変わり、現在はフルハーネス型の使用が原則化されています。現場の安全を守るために必須となる、器具の定義や使用基準などの基礎知識を以下の4つの順に解説します。
- 安全帯の定義と役割(墜落・落下防止のための器具)
- 安全帯と墜落制止用器具の違い
- 安全帯・墜落制止用器具の使用が必要な高さ・場所
- 高所作業における安全帯使用の重要性
安全帯の定義と役割(墜落・落下防止のための器具)
高所作業において、作業者の命を物理的に守るのが安全帯です。一般的には「安全帯」と呼ばれ続けていますが、これは高所からの墜落や転落を防ぐための保護具全般を指します。そして、労働安全衛生法の改正に伴い、2019年からは法令用語として「墜落制止用器具」という名称に統一されました。*1
安全帯の最大の役割は、万が一足場から足を踏み外した際に、身体を空中で保持して地面への激突を防ぐことです。厚生労働省のガイドライン(全文)*2に基づくと、フルハーネス型墜落制止用器具は「墜落を制止する際に身体の荷重を肩、腰部及び腿等複数箇所において支持する構造の部品で構成される墜落制止用器具をいう」と定義されています。そのため、現在は従来の腰ベルト型ではなく、肩や腿を含む全身を支えるフルハーネス型が主流となりました。
安全帯と墜落制止用器具の違い
現場では今でも「安全帯」という呼び名が定着していますが、法律上はその範囲が大きく変更されました。かつての「安全帯」という定義には、電柱作業などで体を支える「U字つり」も含まれていました。
しかし、法改正後の「墜落制止用器具」という定義からは、「U字つり専用器具」が除外されています。これは、U字つりがあくまで姿勢を保持するためのものであり、墜落時の衝撃に耐える機能を持たないためです。つまり、「昔の安全帯=今の墜落制止用器具」ではないという点に注意が必要です。
現在、「墜落制止用器具」として認められるのは、「フルハーネス型」と「胴ベルト型(一本つり)」の2種類のみです。もし「U字つり」だけで高所作業を行えば、それは墜落制止用器具を使用していないとみなされ、法令違反となります。
※本記事で「安全帯」と表記する場合は、新しい規格に適合した「墜落制止用器具」のことを指します。
安全帯・墜落制止用器具の使用が必要な高さ・場所
墜落制止用器具の使用義務が発生する高さは、労働安全衛生規則第518条*3により「2メートル以上」と定められています。さらに重要なのが、高さに応じた器具の使い分けです。同法の施行令に基づくと、高さが6.75メートルを超える箇所では「フルハーネス型」の使用が完全義務化されました。これは、胴ベルト型では落下距離よりも低い位置で宙吊りになった際、地面に激突するリスクや内臓圧迫の危険があるためです。
また、建設業においては、より安全を期して「5メートル以上」からフルハーネス型の墜落制止用器具を着用するのが一般的です。2メートル以上の高所であっても、作業床がない場合や囲いの設置が困難な場所では、必ず墜落制止用器具を使用しなければなりません。現場管理者や職長は、作業箇所の高さを正確に把握し、適切な器具を指示することが求められます。
高所作業における安全帯使用の重要性
建設現場における死亡災害の中で、最も多い原因が「墜落・転落」で、厚生労働省の労働災害統計*4を見ても、死亡災害全体で25.2%を占めています。また、死亡には至らなくとも、安全帯を正しく使用していない状態で落下すれば、内臓破裂や脊髄損傷など、取り返しのつかない事態を招く恐れがあります。
また、一度の事故が起きれば、被災者本人の人生だけでなく、家族の生活や会社の社会的信用まで失いかねません。特に中小企業においては、労災事故による指名停止処分が経営の存続に関わる可能性もあるでしょう。現場の全員が「ルールを守ることが、仲間や企業を守ることになる」という意識を持つように現場を作り上げてください。
安全帯(墜落制止器具)の種類と構造
現場で使用される墜落制止用器具は、国の規格である「JIS T 8165」*5に基づき、厳格に設計・分類されています。さらに、日本安全帯研究会*6の実証データを踏まえ、種類と構造について以下の4点を解説します。
- フルハーネス型と胴ベルト型(腰ベルト式)の違い
- 器具の基本構造(ハーネス・ベルト・バックル)
- D環の役割と正しい位置
- 墜落制止の仕組みと衝撃が身体に与える影響
フルハーネス型と胴ベルト型(腰ベルト式)の違い
現在、JIS規格では、墜落制止用器具を明確に以下の2つに分類しています。
- A種(フルハーネス型):墜落制止用の標準規格。
- B種(胴ベルト型):A種が使用できない場合に限る代替品。
あくまで「A種」が基本であり、胴ベルト型は例外的な扱いであることを理解しましょう。その最大の理由は、日本安全帯研究会が指摘する「身体への衝撃」の違いにあります。胴ベルト型は墜落時に腰一本で全体重を支えるため、腹部に荷重が集中し、内臓損傷などのリスクが高まります。
対してフルハーネス型は、肩・腿・骨盤など複数箇所で衝撃を分散させる構造です。前節でも解説した通り、厚生労働省のガイドライン全文でも、フルハーネス型を原則としています。法令適合(JIS規格)の観点からも、人体の保護(衝撃分散)の観点からも、現在はフルハーネス型を選ぶのが正解です。
器具の基本構造(ハーネス・ベルト・バックル)
フルハーネス型は、JIS規格によって各パーツの強度や名称が細かく定義されています。身体を支える「主ベルト」、胸部などの「副ベルト」、そして長さを調整する「バックル」が主な構成要素です。
JIS規格では、こうした部品に対して厳しい強度試験や、振動で緩まないための性能試験を課しています。現場で特に注意すべきなのは、作業者の体格に合ったサイズの選定です。日本安全帯研究会の資料では、身長と体重に基づく適用サイズ(S・M・Lなど)の目安が示されています。
もしも、サイズが合っていないと、規格通りの強度が発揮できず、墜落時に身体がすっぽ抜ける恐れがあります。また、装着時にはバックルが確実に連結され、緩みがないかを点検するようにしてください。
D環の役割と正しい位置
背中にある「D環」は、ランヤードを接続する唯一の接点であり、JIS規格でも11.5kN以上の強度が求められる重要パーツです。しかし、いくらD環自体が頑丈でも、装着位置がズレていれば命取りになります。
日本安全帯研究会は、D環の正しい位置を「肩甲骨のほぼ中央」と定義しています。位置が適切でないと、墜落時に身体が不自然な方向に引っ張られ、深刻な傷害を招く恐れがあるからです。
例えば、位置が低すぎると身体が逆さま(頭が下)になり、上すぎるとベルトで首を圧迫する危険性があります。JIS規格では、墜落後の姿勢が「頭部が上になること」を求めています。
安定姿勢を保つためにも、装着時は必ずD環が背中の中心に来ているか、バディチェックで確認し合いましょう。
墜落制止の仕組みと衝撃が身体に与える影響
墜落制止用器具の役割は、落下エネルギーを人体が耐えられるレベルまで抑えることです。JIS規格では、人体に加わる衝撃荷重を以下の基準以下にするよう定めています。
- 第1種(タイプ1):4.0kN以下
- 第2種(タイプ2):6.0kN以下
日本安全帯研究会の実証実験によると、フルハーネス型は衝撃を全身に分散させることで、上記の基準をクリアしています。特定部位へのダメージを防ぐとともに、宙吊り状態での「サスペンショントラウマ(血流障害)」の発症を遅らせる効果もあります。
「JIS規格の数値を満たしている」ということは、すなわち「身体が壊れないように設計されている」という意味と言えるでしょう。
安全帯(墜落制止器具)のフルハーネス原則化と法規制・規格のポイント
2022年1月の猶予期間終了に伴い、旧規格の安全帯は使用不可となり、現在はフルハーネス型が原則義務化されています。法令*1やガイドライン*7に基づき、管理者が絶対に把握しておくべきポイントや規格基準について以下の4点を解説します。
- 労働安全衛生法施行令改正の概要
- 高さ6.75m超でフルハーネスが義務化された理由
- 墜落制止用器具に関する規格・基準(JIS・厚労省指針)
- 特別教育が必要な作業・対象者
労働安全衛生法施行令改正の概要
2019年の労働安全衛生法施行令の改正により、法令用語が従来の「安全帯」から「墜落制止用器具」へと変更されました。改正の最大のポイントは、「U字つり用胴ベルト」が墜落制止用器具の定義から完全に除外されたことです。厚生労働省『墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン』*7によると、墜落制止用として認められるのは「フルハーネス型」と、一定条件下での「胴ベルト型(一本つり)」のみです。
かつてのようにU字つり用安全帯だけで高所作業を行うことは、現在では明確な法令違反となります。2022年1月2日以降、旧規格品の使用は全面的に禁止されました。「昔から使っているから」という理由は一切通用せず、違反した場合は事業者だけでなく作業者も罰則の対象となる可能性があります。現場管理者は、作業員が隠れて旧規格品を使用していないか、厳格なチェックが必要です。
高さ6.75m超でフルハーネスが義務化された理由
厚生労働省の改正された政令およびガイドラインでは、高さが6.75メートルを超える場所での「フルハーネス型」使用が完全義務化されました。「6.75メートル」という数字は、フルハーネス型を使用した場合の落下距離(自由落下距離4m+ショックアブソーバの伸び1.75m+余裕1m)を合算した値に由来します。
つまり、6.75メートル以下でフルハーネス型を使うと、地面に激突するリスクがあるため、例外的に「胴ベルト型」の使用が認められていると言えます。逆に言えば、6.75メートルを超える高さでは、地面激突のリスクがなく、かつ胴ベルト型では内臓損傷の危険が高いため、フルハーネス型の使用が義務となります。
また、胴ベルト型は墜落時に腹部を強く圧迫し、内臓損傷のリスクが高いことも禁止の理由です。日本安全帯研究会の資料でも、フルハーネス型による衝撃分散が生存率を高めると示されています。
なお、建設業においては安全マージンを確保するため、高さ5メートル以上からフルハーネス型を使用することが推奨されています。
墜落制止用器具に関する規格・基準(JIS・厚労省指針)
現在使用できる器具は、厚生労働省の「墜落制止用器具の規格」および「JIS T 8165」*5に適合した「新規格品」のみです。新規格品は、耐衝撃性能の試験方法などが強化されており、旧規格品とは安全性能が全く異なります。
また、JIS規格(*5)では、部品の強度や構造についても詳細に定めています。コスト削減のために安価な輸入品や規格外品を選ぶことは、コンプライアンス違反のリスクを負うだけでなく、万が一の際に労災認定で不利になる可能性もあるので注意しましょう。
特別教育が必要な作業・対象者
フルハーネス型を使用して作業を行う労働者に対し、事業者は「特別教育」を実施する義務があります*7。対象となるのは、「高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところ」でフルハーネス型を使用する場合です。
教育カリキュラムは、学科4.5時間、実技1.5時間の計6時間と定められています。特別教育では、器具の正しい装着方法や点検、落下時の措置などを学びます。未受講の作業者に業務を行わせた場合、労働安全衛生法違反として罰せられるため注意してください。
「ベテラン職人だから教育は不要」という特例は一切ありません。該当する作業者全員の受講記録を確実に管理し、現場入場時の確認を徹底するよう心がけてください。
フルハーネスの正しい装着方法
フルハーネス型墜落制止用器具も、正しく装着できていなければ意味がありません。厚生労働省のガイドライン*7に基づき、現場で徹底すべき装着手順とチェックポイントを以下の順で解説します。
- 装着前に確認すべきポイント
- フルハーネスの装着手順(ベルトの締め順)
- 腰・脚・胸ベルトの適正な位置と調整方法
- バックル・D環の装着状態チェック
装着前に確認すべきポイント
装着前に必ず部品の欠損やベルトの状態を確認してください。厚生労働省のガイドラインでは、装着時の確認事項として「取扱説明書を確認し、安全上必要な部品が揃っているか確認すること」を求めています。特に注意すべきは、前回使用時の「ねじれ」や「絡まり」が残っていないか、ベルトに摩耗や溶解などの損傷がないかという点です。
もしも、バックルが破損していたり、縫製がほつれていたりする器具を使えば、墜落時の衝撃に耐えられません。また、自分専用の器具でない場合は、サイズ調整が前任者のままになっていないかも確認が必要です。体に合わない器具は、いざという時に機能しないばかりか、作業中の動きを妨げて事故の原因にもなります。
フルハーネスの装着手順(ベルトの締め順)
フルハーネス型は、正しい順序で装着することで「ねじれ」や「着け間違い」を防げます。まずはハーネスのD環(背中の連結部)を持ち、ベルト全体の絡まりを解いてから、リュックを背負うように肩に通します。次に、腿(もも)ベルト、胸ベルトの順にバックルを連結していくのが基本の流れです。
厚生労働省のガイドラインにおいても、「通常2つ以上のバックルがあるが、これらの組み合わせを誤らないように注意して着用すること」と警告されています。特に左右の腿ベルトを交差させてしまったり、裏返しで連結したりするミスは現場でよく見られます。
最近主流のワンタッチバックルは便利ですが、カチッと音がするまで確実に差し込まれているかを目視と手ごたえで確認してください。手順をルーチン化することで、朝の忙しい時間帯でも装着ミスをゼロにできます。
腰・脚・胸ベルトの適正な位置と調整方法
装着において最も重要なのは、ベルトを「緩みなく、あるべき位置」に固定することです。厚生労働省のガイドラインでは、「墜落制止時にフルハーネスがずり上がり、安全な姿勢が保持できなくなることのないように、緩みなく確実に装着すること」と強く指導しています。
現場では動きやすさを求めてベルトを緩めがちですが、これは非常に危険です。緩みがあると、墜落時にベルトが激しくずれて身体がすっぽ抜けたり、胸ベルトが首元まで上がって呼吸困難になったりする恐れがあります。
また、同ガイドラインには「胸ベルト等安全上必要な部品を取り外さないこと」とも明記されています。胴ベルトを併用する場合は、墜落時に足の方へ抜けないよう、腰骨の位置で確実に固定してください。「少しくらい緩くても」という油断が、命取りになることを肝に銘じましょう。
バックル・D環の装着状態チェック
全てのベルトを締め終えたら、最後にバックルとD環の状態を再確認します。バックルについては、ガイドラインで「ベルトの端はベルト通しに確実に通すこと」と定められています。ベルトの余り部分がぶらついていると、足場や突起物に引っかかり、転倒や予期せぬ事故を招くからです。
そして、命綱を繋ぐ「D環」の位置確認も忘れてはいけません。D環が背中の中心(肩甲骨の間)からズレていると、墜落時に身体がバランスを崩し、横転や逆さま状態で宙吊りになる危険性があります。
しかし、背中の状態は自分では見えません。そのため、作業前には必ず同僚同士で確認し合う「バディチェック(相互点検)」を徹底してください。「バックル良し、D環良し」と声を掛け合うことで、ミスを防ぐだけでなく、チーム全体の安全意識も高まります。
フック・ランヤードの正しい使い方と掛け方
高所作業での事故を防ぐためには、器具を「正しく使う」ことが絶対条件です。しかし現場では、誤ったフックの掛け方が原因で、器具が破損してしまうケースが後を絶ちません。日本安全帯研究会*6に基づき、フックとランヤードの正しい取り扱いについて以下の4つの視点から解説します。
- 高所作業でのロープ使用時の注意点
- 墜落制止用として機能させるためのポイント
フックの正しい掛け方・NG例
フックを使用する際は、必ず「フックの縦軸(中心)方向に引張荷重がかかる」ように掛けてください。フックは縦方向の力には強い反面、横方向の「曲げ荷重」や、外れ止め装置への「押さえ荷重」には弱く作られています。そのため、構造物に押し付けられて外れ止め装置に力が加わるような掛け方は、フックの変形や破損を招くため厳禁です。
特に注意すべきNG例が、フックをロープ自体に直接掛ける「回し掛け」です。もしも「回し掛け」をした場合、フックに横方向の力が加わり、破断する恐れがあります。また、ランヤードがねじれた状態で外れ止め装置に絡むと、予期せぬ力で装置が外れるリスクもあります。フックに無理な力がかからない「正しい向き」で掛かっているかを常に意識してください。
柱・構造物への取り付け方法
ランヤードを取り付ける際は「できるだけ高い位置」にある「堅固な構造物」を選んでください。高い位置に掛けることで落下距離を短く抑えられ、地面への激突リスクを減らせます。逆に、斜めの筋交いなど「フックが滑り落ちるような箇所」に取り付けるのは危険です。
日本安全帯研究会は、墜落時にフックが滑って金具等に激突すると、衝撃荷重が増して、フックが変形して墜落を阻止できなくなる可能性があると指摘しています。
また、H鋼の角など鋭利な部分にロープが触れる場合も注意が必要です。角に当たった状態で墜落するとロープが切断される恐れがあるため、必ず「布などで養生」を行ってください。
高所作業でのロープ使用時の注意点
高所作業においてランヤードや親綱を使用する際は「振り子現象」と「使用人数」に注意が必要です。フックを掛ける位置が作業場所から横に離れすぎていると、墜落時に身体が大きく振られ、壁や構造物に激突する恐れがあります。こうした事態を防ぐため、フックは可能な限り「自分の作業位置の直上(頭上)」に取り付けるのが原則です。
また、現場に設置された垂直親綱や水平親綱を使用する場合、その定員を守ることも重要です。日本安全帯研究会によれば、「垂直・水平親綱の1スパンを利用する作業員は、必ず1人にすること」と明記されています。複数の作業員が同時に同じスパンを使用すると、万が一の際に親綱の強度が不足したり、他の作業員を巻き込んだりする危険があるからです。
親綱を使う際は、他の人が同じ区間にいないかを確認してからフックを掛けるルールを徹底しましょう。
墜落制止用として機能させるためのポイント
ランヤードを選定する際は、フックを掛ける高さに合わせて「適切なショックアブソーバの種別」を使い分けてください。具体的には、腰より高い位置に掛ける場合は、第1種(タイプ1)ランヤード、足元など低い位置に掛ける場合は第2種(タイプ2)ランヤードの2種を使い分けましょう。
もし足元にフックを掛ける作業で「第1種」を使ってしまうと、落下距離が伸びて地面に激突したり、衝撃吸収が間に合わなかったりするリスクがあります。
鉄骨組立などで両方の作業が混在する場合は、「フルハーネス型」を選定した上で、「第2種(タイプ2)」を使用することが推奨されています。
ランヤード・ショックアブソーバの正しい選び方
墜落制止用器具の性能に影響するランヤードとショックアブソーバは、適切なものを選べば転落事故を防げます。ここでは主に厚生労働省のガイドライン*7を参考にして正しい選び方として以下の4点を解説します。
- ランヤードの種類と構造(ロープ・フック)
- ショックアブソーバ第一種・第二種の違い
- 最大使用質量と体重・装備重量の考え方
- 作業高さ・作業場所に応じた選定ポイント
ランヤードの種類と構造(ロープ・フック)
ランヤードには主に「巻取式」と「ロープ式(伸縮式含む)」の2種類があり、作業内容に応じた使い分けが重要です。現場での取り回しや安全性に直結するため、それぞれの特徴を把握しておく必要があります。厚生労働省のガイドラインでも、作業環境に適した選択が推奨されています。
巻取式は、ストラップが常に巻き取られるため、移動時に構造物へ引っ掛かるリスクが少ないのが利点です。一方、ロープ式や伸縮式は軽量で安価なものが多く、持ち運びの負担が少ないというメリットがあります。
また、フックやロープの素材・強度についても、JIS規格で厳格に定められています。高所での溶接作業では熱に強い素材を選ぶなど、環境特性も考慮しなければなりません。
ショックアブソーバ第一種・第二種の違い
ショックアブソーバを選ぶ際の基準は「フックを掛ける高さ」が腰より上か下かという点です。基準を間違えると、墜落時に十分な衝撃吸収性能が発揮されず、身体に致命的なダメージを与える恐れがあります。日本安全帯研究会では、以下の基準で明確に区分しています。
- 第一種(タイプ1): 腰より高い位置に掛ける専用(衝撃荷重4.0kN以下)
- 第二種(タイプ2): 足元など低い位置にも掛ける兼用(衝撃荷重6.0kN以下)
もしも、足元に掛ける可能性がある作業で「第一種」を使ってしまうと、落下距離が伸びて許容荷重を超えてしまいます。逆に、腰より高い位置にしか掛けないなら、第一種の方が身体への衝撃は少なくて済みます。
鉄骨組立などで足元へのフック掛けが避けられない場合は、迷わず「第二種」を選定してください
最大使用質量と体重・装備重量の考え方
器具を選定する際は、自分の体重と装備品を含めた総重量が、製品の最大使用質量を超えないようにする必要があります。厚生労働省のガイドラインでは、選定要件として、使用可能な最大質量(85kg用または100kg用など)が記されています。許容質量を超えて使用すると、墜落時にショックアブソーバが底突きし、身体への衝撃が増えてしまうので、こうした基準を必ず順守してください。
例えば、体重70kgの人が15kgのフル装備(腰道具や工具)を身に着ければ、総重量は85kgになります。 この場合、85kg用の器具ではギリギリであり、安全マージンを考えれば100kg用を選びましょう。また、100kgを超える体格の良い作業者の場合は、特注品や130kg対応品などを手配しなければなりません。
「自分は標準体型だから大丈夫」と思い込まず、全装備状態で体重計に乗り、実際の総重量を把握することをおすすめします。
作業高さ・作業場所に応じた選定ポイント
ランヤード選びの最後の決め手は、「落下距離」と「作業床の高さ」のバランス計算です。フルハーネス型は安全性が高い反面、落下距離が長くなる傾向があり、低層での使用には注意が必要です。
厚生労働省のガイドラインによると、一般的なフルハーネス(ランヤード長1.7m)の落下距離は約4〜6mにもなります。そのため、高さ6.75m以下の作業で、かつ下に障害物がある場合は、地面に激突するリスクが生じます。
このような低層作業では、落下距離を短くできる「ロック機能付き巻取式ランヤード」の使用がおすすめです。ロック機能があれば、落下直後にストラップの繰り出しが止まり、最短距離で制止できるからです。
また、どうしても地面に到達してしまう高さ(6.75m以下)に限り、例外的に胴ベルト型の使用が認められています。現場の高さと器具のスペック(落下距離)を照らし合わせ、最も安全を確保できる組み合わせで選定してください。
高所作業で起こりやすい安全帯(墜落制止器具)の誤使用と事故リスク
現場では、安全帯に対する慣れや知識不足から誤った使い方が横行し、それが致命的な事故につながるケースが後を絶ちません。ありがちな誤使用とリスクを以下の4つの順に解説します。
- ベルトのねじれ・緩みが招く危険
- D環位置・ランヤード接続ミスのリスク
- 正しく装着しない場合に起こる身体への衝撃
- 「フルハーネスの方が危険」になるケースとは
ベルトのねじれ・緩みが招く危険
フルハーネス型において、ベルトの「ねじれ」や「緩み」は命に関わる重大な欠陥です。厚生労働省のガイドラインで「墜落制止時にフルハーネスがずり上がり、安全な姿勢が保持できなくなることのないように、緩みなく確実に装着すること」と明記されています
もしベルトが緩んだ状態で墜落すると、衝撃の瞬間にハーネスが激しく動き、身体がベルトからすっぽ抜けて地面に落下する恐れがあります。また、ねじれたベルトは身体に食い込みやすく、墜落の衝撃が一点に集中することで、肋骨骨折や内臓損傷などの二次被害を引き起こしかねません。
D環位置・ランヤード接続ミスのリスク
背中の「D環」の位置ズレやランヤードの誤接続は、墜落時の姿勢を崩し、死亡率を大きく上げる要因となります。日本安全帯研究会は、D環の適正位置を「肩甲骨のほぼ中央」としています。
この位置が適切でないと、墜落時に身体が回転して頭部から落下したり、首が絞まったりする危険性が高まります。また、ランヤードのフックを誤った場所に掛ける「誤接続」も深刻な問題です。厚生労働省のガイドラインでは、「フック等を誤って環以外のものに掛けることのないように」と注意喚起しています。
例えば、工具ホルダー用のリングや、強度の低いベルト通しにフックを掛けてしまうケースです。こうした墜落時の荷重に耐えられず、瞬時に破断します。
正しく装着しない場合に起こる身体への衝撃
JIS規格に基づく試験では、人体にかかる衝撃荷重を4.0kN(タイプ1)または6.0kN(タイプ2)以下に抑えるよう設計されています。しかし、こうした基準はベルトが所定の位置にあり、全身で荷重を受け止めることが前提です。
例えば、腿ベルトが緩すぎると、墜落に股間部へ強烈な衝撃が集中し、大腿動脈の損傷や生殖器への損傷を招きます。また、胸ベルトを外し忘れたり、位置が高すぎたりすると、落下時に首を圧迫して窒息するリスクがあります。
「痛い思い」で済むか、「取り返しのつかない怪我」になるかは、正しく装着で決まると言っても過言ではありません。
「フルハーネスの方が危険」になるケースとは
一般的に安全性が高いとされるフルハーネス型ですが、使用条件を誤れば、逆に胴ベルト型よりも危険な状況を招くことがあります。その典型例が、落下距離の計算ミスによる「地面への激突」です。ガイドラインによると、フルハーネス型はショックアブソーバの伸び(最大1.75m)やハーネスの伸びを加味するため、胴ベルト型よりも落下距離が長くなります。
具体的には、高さ6.75メートル以下の低層作業でフルハーネス型を使用し、かつフックを足元などに掛けた場合、ランヤードが伸び切る前に地面に叩きつけられるリスクがあります。こうした事態を防ぐため、法令では6.75メートル以下の作業で地面到達の恐れがある場合に限り、胴ベルト型の使用を認めています。
安全帯(墜落制止器具)の使用前・使用後の点検方法と交換目安
見た目に異常がなくても、経年劣化や過去の衝撃で強度が低下している場合があります。そこでここでは安全帯の点検のポイントと、廃棄の決断基準を以下の順に解説します。
- 使用前点検のチェック項目
- 使用後に確認すべき状態
- 衝撃を受けた場合の対応と廃棄判断
- ランヤード2年・その他3年の交換目安
使用前点検のチェック項目
作業を始める前には、ベルトや金具に異常がないかを目視と手触りで確認します。ベルト部分は「切り傷」「摩耗」「熱による溶融」がないかが重要なチェック項目です。特に、バックルの噛み合わせ部分や、縫製部分(ステッチ)にほつれがある場合は、本来の強度が発揮できません。また、フックの外れ止め装置がスムーズに動くか、リベットにガタつきがないかも確認してください。
ランヤードについては、ロープのより戻しやねじれがないかを見ます。巻取式の場合は、ストラップを急激に引いたときにロック機能が正常に作動するかどうかも、使用前のチェック項目です。
使用後に確認すべき状態
一日の作業を終えた後も、器具の状態を確認してから片付ける習慣をつけましょう。現場では、塗料や油、泥などが付着しやすいですが、こうした汚れを放置すると素材の劣化を早めます。特に酸やアルカリ性の薬品が付着した場合は、ベルトの強度が著しく低下する恐れがあるため、すぐに拭き取る必要があります。
また、雨や汗で濡れたまま放置すると金具が錆びたり、ベルトがカビたりする原因になるので、使用後は風通しの良い日陰で乾燥させ、直射日光(紫外線)が当たらない場所に保管しましょう。
衝撃を受けた場合の対応と廃棄判断
一度でも墜落時の衝撃を受けた器具は、外見上に変化がなくても「即廃棄」してください。再び落下すると荷重に耐えられず、墜落制止できない可能性があります。内部の繊維が断裂していたり、金属疲労が蓄積していたりするためです。衝撃を受けた器具は二度と使われないように、ベルトを切断するなどして廃棄処分してください。
ランヤード2年・その他3年の交換目安
安全帯には、「耐用期間(寿命)」が設定されています。基本的に使用開始から「ランヤードは2年」であり、「ハーネス本体は3年」です。これは、紫外線や空気中の水分による経年劣化を考慮した期間であり、仮に一度も使わずに保管していたとしても強度は低下していきます。
現場管理を徹底するためには、器具の使用開始年月をラベルに記入し、交換時期を可視化することが有効です。期限が過ぎた器具を使用し続けて事故が起きた場合、管理責任を問われるリスクも高まります。「壊れてから買い替える」のではなく、「期限が来たら買い替える」という意識を徹底してください。
安全帯(墜落制止用器具)の正しい使い方が「現場で再現できない」理由
講習で習ったはずの「正しい使い方」が現場では守られないことがあります。ここまでは理論を述べてきましたが、ここからは現場で実際に起きている問題を以下の順に深掘りします。
- 細かい作業や複雑な作業が文章や図だけでは伝わりきらない
- 現場ごとに違う作業環境・構造物への対応が難しい
- 逼迫した工期や多忙さが原因で安全手順が形骸化する
- 経験の浅い作業者への教育が不十分
細かい作業や複雑な作業が文章や図だけでは伝わりきらない
安全帯の装着や点検には、文字や静止画だけでは伝えきれない「感覚的なコツ」が多く存在します。例えば、「緩みなく確実に装着」という指示も、実際にどの程度の締め付けが正解なのかは個人差が出やすい箇所です。
「手のひらがギリギリ入る程度」という目安も、実際に経験しなければ加減を掴むことは難しいでしょう。また、移動時のフック掛け替えのタイミングや高所での身体の安定させ方といった動的なスキルは、マニュアルの行間にある「現場の勘所」です。
紙の資料を配るだけでは、若手には「やったつもり」の誤った動作が定着してしまいます。
現場ごとに違う作業環境・構造物への対応が難しい
厚生労働省のガイドラインと、実際の現場環境には大きなギャップがあります。「腰より高い位置に掛ける」のが原則ですが、頭上に堅固な構造物がない現場や、手すりが強度の低い単管パイプしかないケースも多々あります。
また、足場が複雑に入り組んでいて二丁掛けが物理的に難しい場所など、マニュアル通りにいかない場面で事故リスクが高まることもあるでしょう。こうした「想定外」の状況下で、作業員が自己判断で無理な体勢をとったり、強度が不明な場所にフックを掛けたりすることが事故の引き金になります。
管理者は「ルールを守れ」と一辺倒に言うだけでなく、現場ごとのリスクアセスメントを徹底し、「この現場ならここに掛ける」という具体的な解決方法を示す必要があります。
逼迫した工期や多忙さが原因で安全手順が形骸化する
どんなに完璧な安全ルールも、現場の「余裕のなさ」の前では無力化してしまう現実があります。工期に追われる現場では、「いちいちフックを掛け替えていたら仕事にならない」という心理が働き、安全手順が省略されがちです。推奨される「二丁掛け」も、頻繁な移動を伴う作業では手間が増えるため、監視の目が届かない場所では「一本掛け」や「無胴綱」が横行する要因となります。
また、装着前の点検も、朝礼後の慌ただしさの中で形式的なものになり、ベルトの摩耗や劣化が見過ごされるケースもあり得るでしょう。安全管理を作業員の心がけだけに頼るのではなく、余裕を持った工程管理や、使い勝手の良い軽量な器具の選定など、組織的なバックアップが必要です。
経験の浅い作業者への教育が不十分
現場における事故の原因は、知識と経験が不足している作業者が、十分な指導を受けずに高所作業に従事してしまうこと、つまり教育不足です。フルハーネス型を使用する作業者に対し「特別教育」の実施を義務付けていますが、これはあくまで最低限の基礎知識に過ぎません。実際の現場では、教科書には載っていない判断が求められる場面が連続します。
しかし、人手不足の現場では、OJTが十分に行われないまま、「見て覚えろ」という古い体質で放置される作業員もいます。これでは、先輩によって教え方が違うという混乱が生じ、正しい手順が定着しません。未熟な作業者を守るためには、教育の質を均一化し、経験年数に応じた段階的なスキルアップの仕組みを構築することが急務です。
ここまで、安全帯の正しい使い方が「現場で再現できない」理由として4つ挙げましたが「できない」から「できる」現場にする方法として最もおすすめなのが動画マニュアルです。
安全帯(墜落制止用器具)の正しい使い方は「動画」でわかりやすく教育!
高所作業での墜落・転落事故を根本から防ぐには「ヒト」への対策が欠かせません。法改正でフルハーネス型が義務化されるなど設備やルールを整えても、それを扱う「ヒト」の行動にバラつきがあれば事故は防げません。ここでは具体的に「ヒト」の対策としてできる以下の4つを、動画活用という観点から紹介します。
- 装着方法・フックの掛け方・点検手順を一目で確認
- 現場・教育・安全管理で繰り返し使える実践的な教材
- 現場に潜む危険を見たままに伝えられる
- 動画マニュアル「tebiki」なら作成・更新も簡単!
装着方法・フックの掛け方・点検手順を一目で確認
「作業者によるバラつきをなくす」は「誰がやっても同じ結果(安全な状態)にする」つまり「標準化する」と同じ意味です。
しかし、手順書にある「ベルトを緩みなく締める」や「フックを適切な位置に掛ける」といった言葉は、読み手の感覚に依存するため、個人の勝手な解釈を許してしまいます。その結果、「自分では締めたつもり」という抜け穴が生まれます。
こうした「解釈のズレ」に対し、株式会社近鉄コスモスでは「正しい作業」と「誤った作業」を対比させた動画マニュアルを導入し、成果を上げています。
「正しい開梱」動画は、刃物の向き、段ボールの固定位置、手の位置、安全距離といった細かい動作をわかりやすく解説。「誤った開梱」動画では、不安定な持ち方や刃物の危険な扱いなど、現場で起こりやすい不安全動作を映像化しています。
建設・製造現場でも同様に、安全帯使用時の「安全な状態」と「危険な状態」を映像で比較すれば、言葉の壁がある外国人材でも「何がダメなのか」を視覚的に理解できます。
現場・教育・安全管理で繰り返し使える実践的な教材
現場特有の「慣れ」や「先輩の背中を見て覚える」ことに依存した教育も、事故のリスクを高める要因です。人に頼る指導では、教え方が指導者によって異なり「ベルトはこれくらい緩くても大丈夫」といった間違った自己流が広まる危険性があります。
こうした属人化の解消に成功したのが、児玉化学工業株式会社です。同社は作業の微妙な力加減や角度を動画化し、言葉では表現しきれない暗黙知を可視化しました。
▼動画マニュアルによる標準化の例▼
安全帯の日常点検における「ベルトの摩耗具合」や「金具の変形チェック」などを動画化し、「同一の手本」を用意することで、指導者による教育のブレをなくせます。また、入場時の教育や送り出し教育で繰り返し使用できるため、教育担当者の負担軽減にもつながります。
※本動画は、現場教育に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」で作成されています。tebikiのサービス詳細や導入事例についてはサービス資料をご覧ください。
>>>かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育サービス資料」を見てみる
現場に潜む危険を見たままに伝えられる
目に見えないリスクを「可視化」することも必要です。文字だけのヒヤリハット報告書では、実際の高所作業の危険性がリアルに伝わらず、「自分は落ちない」との過信をなくせません。特に一瞬で命に関わる高所作業では、危険な状況を動画で再現して見せることが効果的です。
「フックを足元にかけると、落下時の衝撃荷重で身体に何が起こるか」「不適切な装着で宙吊りになるとどうなるか」という因果関係を映像で突きつけられると、作業員は理屈ではなく「怖さ」を感情で理解します。
明和工業株式会社では作業場にディスプレイを設置し、QRコードで即座に動画マニュアルを呼び出せる仕組みを設けており、誰でも迷わず標準作業を実行できる環境が整えられています。これを安全帯の教育に応用すれば、
- この使い方の何が危険なのか?
- 墜落時にどのような衝撃を受けるのか?
をその場で理解でき、安全意識を根付かせられると思います。

動画マニュアル「tebiki」なら作成・更新も簡単!
「動画を作るのは難しそう」「編集する時間がない」といった現場の悩みも、「tebiki現場教育」なら解決できます。特別な機材や編集スキルは一切不要で、誰でも直感的に「伝わる」マニュアルを作成・運用可能です。
「tebiki現場教育」なら普段行っているOJTや、熟練者の模範作業をスマートフォンで撮影し、クラウドにアップロードするだけでマニュアル作成がスタートします。最新の音声認識技術が説明の声を自動で字幕化するため、一文字ずつテロップを入力する手間はかかりません。安全帯のフックを掛ける手元や、点検時の視線の動きなど、文章では表現しづらい細かな動きもカンタンに教材化できます。
また、「tebiki現場教育」なら自動翻訳機能を使えば、100ヶ国語以上の言語に字幕で翻訳可能です。言葉の壁があり、日本語の細かいニュアンスが伝わりにくい外国人スタッフに対しても、母国語で安全ルールを正しく理解してもらえます。
「tebiki現場教育」なら現場のルール変更や法改正があった場合でも、動画を最初から撮り直す必要はありません。字幕のテキストを修正するだけで音声を自動生成する機能や、動画の一部をカット・追加する機能により、常に最新の情報を現場に届けられます。
「作って終わり」ではなく、現場の変化に合わせて無理なく「運用し続けられる」のがtebikiの大きな強みです。
まとめ
法改正により、高所作業では「墜落制止用器具(フルハーネス型)」の使用が原則となりました。命を守るには、高さや体重に合った器具を選び、正しく装着することが必須です。しかし、現場での誤使用や形骸化を防ぐには、個人の意識だけでなく「教育の仕組み化」が欠かせません。
言葉や静止画では伝わりにくい装着のコツや危険性は、動画マニュアルでの可視化が効果的です。誰が指導しても同じ質を保てるよう「tebiki」などで手順を標準化し、現場全員が迷わず安全に行動できる環境を構築してください。
【補足】安全帯(墜落制止器具)の器具併用について
現場では「ハーネスはA社、ランヤードはB社」といったメーカーの異なる組み合わせを見かけることがあります。しかし、命を預ける器具において、こうした混用は安全性を保証できるか疑問が残るのは事実です。ここではJIS規格やメーカー保証の観点から、併用時のリスクと考え方を以下の順に解説します。
- 異なるメーカー製品を組み合わせる際の考え方
- 強度・規格適合の確認ポイント
- 安全管理者・事業者が確認すべき事項
異なるメーカー製品を組み合わせる際の考え方
厚生労働省の「墜落制止用器具の規格」*8第7条では、「墜落制止用器具の部品は、的確に、かつ、容易に緩まないように接続できるものでなければならない」と定められています。理論上は、各部品が規格適合品であり、確実に接続できれば併用は可能です。
しかし、多くのメーカーは取扱説明書で「同一メーカーの純正セット使用」を推奨しています。これは、メーカーが自社製品同士で第8条の落下試験を行い、安全性能(トルソーの保持や衝撃荷重の基準値クリア)を保証しているためです。他社製品との組み合わせでは、接続部の「相性」による不具合(外れ止め装置への干渉など)が発生しても、メーカー保証の対象外となるリスクがあります。
強度・規格適合の確認ポイント
併用する場合、最も重要なのは強度の統一です。第4条では、フルハーネスやランヤードの部品ごとに強度が定められていますが、製品全体としての性能は「最も弱い部品」に依存します。
特に注意すべきは「コネクタ(フック等)」と「ショックアブソーバ」の適合性です。第6条でコネクタには「適切な外れ止め装置」が求められていますが、他社製D環との組み合わせで無理な力が加わり、この機能が損なわれる恐れがあります。
また、第8条第3項に基づくショックアブソーバの種別(第1種・第2種)や第9条で表示が義務付けられている「使用可能な質量の最大値」が、ハーネス本体の性能と矛盾していないかも必ず確認してください。新規格(墜落制止用器具)と旧規格(安全帯)の混用は、構造規格が異なるため絶対に行ってはいけません。
安全管理者・事業者が確認すべき事項
事業者は、第3条等の構造要件を満たす器具を使用させる義務があります。併用器具を使用させる場合、万が一の事故時に「規格適合性の証明」が困難になるリスクがあります。
特に第9条の表示義務に基づき、各部品の製造年月や種別を確認し、「システム全体として安全か」を判断する必要があります。安全管理者は原則として「セット支給」を徹底し、やむを得ず併用を認める場合は、接続部の物理的干渉や、総重量(体重+装備)が各部品の許容範囲内に収まっているかを個別にチェックする体制を整えてください。
参考元/引用元
*1:厚生労働省『安全帯が「墜落制止用器具」に変わりました。(平成31年2月1日施行)』
*2:厚生労働省『安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!』
*3:e-GOV『労働安全衛生規則第518条』
*4:厚生労働省『令和6年 労働災害発生状況について』
*5:日本産業規格の簡易閲覧『JIST8165:2018 墜落制止用器具』
*6:日本安全帯研究会『墜落制止用器具の選定と正しい使い方』
*7:厚生労働省『墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン』
*8:厚生労働省『墜落制止用器具の規格』