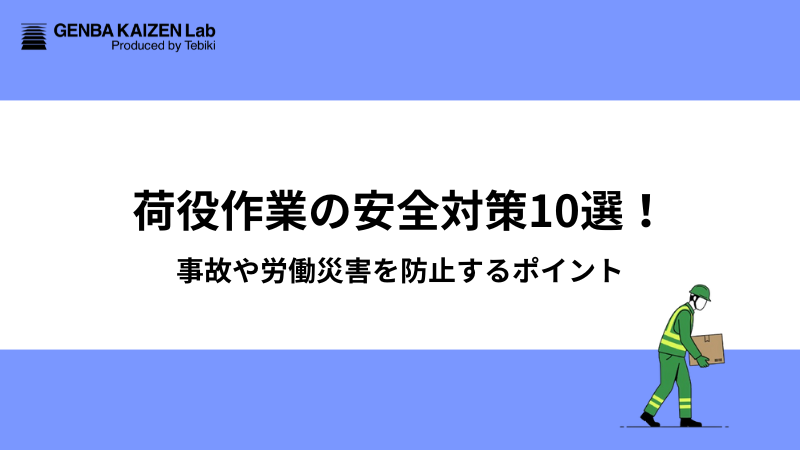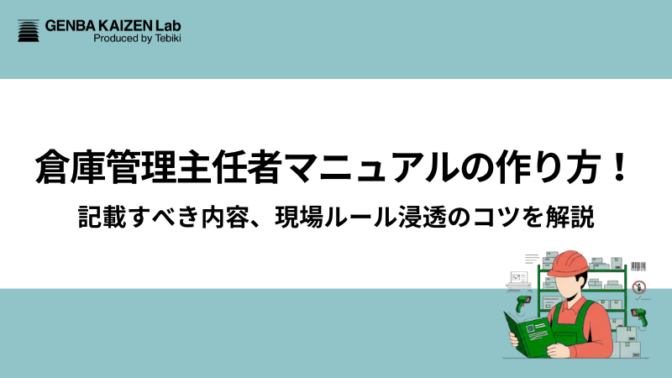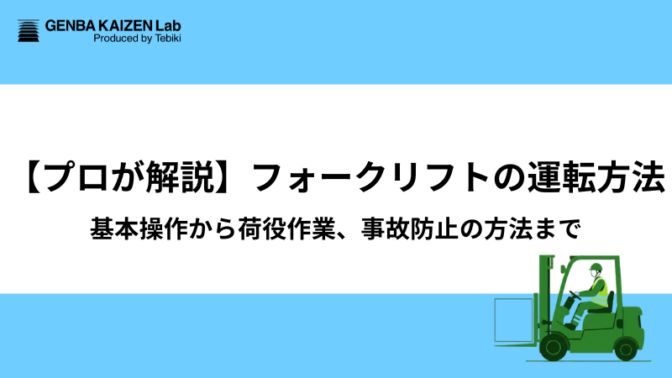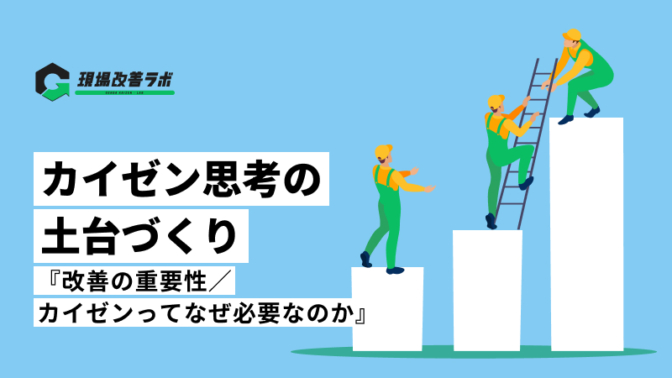物流業で役立つかんたん動画マニュアル「tebiki現場教育」を展開する現場改善ラボ編集部です。
荷役作業を行う現場の管理責任者や安全衛生担当者の皆様は、「さまざまな事故リスクに対し、どのような安全対策を講じればよいかわからない」「職場の労働災害をゼロにしたい」といったお悩みを抱えてはいないでしょうか。
その目標を達成するためには、過去の事故事例からリスクを学び、ソフト・ハード両面から有効な安全対策を講じることが重要です。
そこで本記事では、荷役作業に15年以上携わる筆者が発生頻度の高い事故事例を解説するとともに、厚生労働省のガイドラインから抜粋した具体的な安全対策や労災を防止するコツをご紹介します。
さらに、最も基本的で効果的な安全対策である「安全教育」の手法や成功事例についてまとめた別紙の資料もご用意しておりますので、以下のリンクをクリックし本記事と併せてご覧ください。
>>安全意識が高い現場はすでにやっている!安全意識を高める安全教育・対策事例をみる
目次
荷役作業における労働災害の発生状況
労働災害の発生状況からその傾向を把握し、自社の安全環境を見直すことは非常に重要です。
厚生労働省がまとめた「令和5年労働災害発生状況の分析等」によると、陸上貨物運送事業における労働災害は事故の型別に以下の通り発生しています。
▼令和5年 陸上貨物運送事業における労働災害発生状況(事故の型別)▼
| 事故の型 | 死亡者数(人) | 死傷者数(人) |
|---|---|---|
| 交通事故(道路) | 48 | 861 |
| 墜落・転落 | 25 | 4,207 |
| はさまれ・巻き込まれ | 9 | 1,674 |
| 転倒 | – | 2,960 |
| 動作の反動・無理な動作 | – | 2,902 |
| 激突され | – | 828 |
| 激突 | – | 1,153 |
| 崩壊・倒壊 | 5 | – |
| 飛来・落下 | 4 | – |
| その他 | 19 | 1,630 |
| 合計 | 110 | 16,215 |
荷役作業時の災害に絞って見ると、「交通事故(道路)」を除いた場合、死亡災害では「墜落・転落」や「はさまれ・巻き込まれ」が上位を占めています。死傷災害(休業4日以上)においても同様の傾向ですが、こちらでは「動作の反動・無理な動作」、いわゆる「ギックリ腰」なども多く発生している点は見逃せません。
もし貴社の現場でこれらの事故につながる危険因子が存在する場合、早急な対策が必須です。次項では、この状況を踏まえ、荷役作業時に発生する可能性が高い事故事例を紹介します。
>>目指せゼロ災!従業員の安全意識を向上させる安全教育の事例やポイントについてはこちらをクリック!
荷役作業時に発生する可能性が高い8つの事故事例
安全な職場環境を構築し労働災害を未然に防ぐためには、過去に実際に起こった事故を参考にすることが効果的です。
本項では、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署がまとめた資料「陸上貨物運送事業における重大な労働災害を防ぐためには」から、荷役作業時に発生する可能性が高い事故事例を、以下の4つのカテゴリに分けてご紹介します。
- トラック / 荷台からの墜落や転落
- トラック / 荷台での荷崩れ
- フォークリフトとの接触や不適切な運転
- トラック後退の接触
>>現場の213名に聞いた「ヒヤリハット事例・対策集」を知りたい方はこちらをクリック!
トラック / 荷台からの墜落や転落
荷役作業時の死亡災害の原因として特に多いのが、トラックの荷台などからの墜落・転落によるものです。具体的な事例を2つ紹介します。
【事例①】足を滑らせてリアバンパーから転落(死亡事故)
コンビニエンスストアへの配送中、被災者は荷台コンテナ内を整理していました。段ボール箱を一つ抱えたまま、リアバンパーに足をかけて後ろ向きに降りようとした際、足を滑らせて約52cmの高さから転落。頭部を強打し、死亡に至っています。なお、被災者は保護帽を着用していませんでした。
【事例②】テールゲートリフターから転落(死亡災害)
トラック後部のテールゲートリフターに乗り、工業用油200ℓが入ったドラム缶を降ろす作業中、被災者は何らかの理由で高さ約110cmの高さから転落し、死亡する事故が発生しました。この事例でも、被災者は保護帽を着用していませんでした。
トラック / 荷台での荷崩れ
荷崩れによる死亡災害も、荷役作業時に多い事故原因の一つです。具体的な事例を2つ紹介します。
【事例③】固定ベルトを外した途端に多くの角材が落下(死亡災害)
トラック(ウイング車)に積まれた角材180本の束の積み付け状況を確認していた被災者。点検のためにラッシングベルトを緩めたところ、角材の束が崩れ、その下敷きとなって死亡しました。この事例でも、被災者は保護帽を着用していませんでした。
【事例④】ドラム缶とともに転落、ドラム缶が被災者に直撃(死亡災害)
トレーラーコンテナの奥から、トラック荷台で待つフォークリフトまでドラム缶を移動させていた被災者。しかし、雪が残り非常に滑りやすい状態だったコンテナ内部で誤って足を滑らせてしまいます。被災者はドラム缶とともに落下し、直撃を受けて死亡しました。
フォークリフトとの接触や不適切な運転
荷役作業の効率化に欠かせないフォークリフトですが、一歩間違えれば人の命を奪う危険な要因にもなります。フォークリフト使用時における死亡災害の事例を2つ紹介します。
関連記事:フォークリフト事故・労災の実態:事例や発生件数・原因について
【事例⑤】フォークリフトアップ(上昇)時、コールドロールボックスパレットが倒れ被災者が下敷きになる(死亡災害)
オペレーターがフォークを上昇させた際、誤ってそばにあったコールドロールボックスパレットにフォークを引っ掛けて転倒させてしまいました。その転倒した先で作業を行っていた被災者が、パレットの下敷きとなり死亡しています。
【事例⑥】歩行者立入禁止エリアにいた被災者がフォークリフトと接触(死亡災害)
コンテナへの荷積み場所でフォークリフトがバック走行を行った際、歩いていた被災者に接触し、死亡させる事故が起きました。被災現場は社内ルールで「歩行者立入禁止エリア」と定められていましたが、被災者はそのルールを守らずに立ち入っていた状況です。
トラック後退の接触
ここまでに紹介した事故原因に比べ発生率は低いものの、トラック後退時の接触も、荷役作業時に発生する可能性が高い死亡災害の一つです。具体的な事故事例を2つ紹介します。
【事例⑦】トラック後退誘導時にトラックと電柱の間に挟まれる(死亡災害)
運転手の助手として、路地で引っ越しトラックの後退誘導を行っていた被災者が、トラックと電柱の間に挟まれて死亡する事故が発生。当該トラックにはバックモニターが装備されていたものの、運転手は事故当時、それを使用していませんでした。
【事例⑧】トラックの荷役作業指示中に後進してきた別のトラックに接触(死亡災害)
トラックAの運転手へ荷役作業の指示を出していた被災者。そこへ別の作業を終えたトラックBが、事業所で禁止されている後進で移動してきたため、存在に気づかれず接触、死亡する事故となりました。なお、事故は視界が悪く薄暗い夕方に発生しています。
荷役作業で実施すべき安全対策【厚生労働省のガイドラインから抜粋】
事故事例を通じて自社の作業環境に潜むリスクを把握しただけでは、事故を防ぐことはできません。具体的な対策を講じ、実行することが不可欠です。
本項では厚生労働省のガイドライン「荷役作業での労働災害を防止しましょう!」「陸上貨物運送事業における重大な労働災害を防ぐためには」から抜粋した具体的な安全対策を、以下の2つの側面からご紹介します。
- ソフト面で(教育や仕組み)で有効な安全対策
- ハード面(設備や機械)で有効な安全対策
それぞれ前項で紹介した事故事例と照らし合わせながら見ていきましょう。
ソフト面(教育や仕組み)で有効な安全対策
作業手順やルールが記載されている手順書を整備する
安全を最優先した作業手順を定めた手順書を作成し、その遵守を徹底することで、事故のリスクを最小限に抑えることができます。例えば、前項の【事例①】では、「荷物を持ったまま後ろ向きに荷台から降りない」というルールを手順書で明確に定めていれば、墜落死亡事故は防げたかもしれません。
関連記事:【見本あり】倉庫作業マニュアルの作り方:使われる作業手順書を整備するには?
ここで重要なのは、「いかにわかりやすい手順書・マニュアルを整備できるか?」という点です。手順書を整備しても現場の作業者が理解できず、形だけの存在になってしまっては意味がありません。専門用語が多すぎたり、文字ばかりで読みづらい手順書では、作業者が「守りたい」と思えるものにはならないのです。
図解や写真、さらには動画を活用して視覚的に理解できるようにすることで内容が浸透しやすくなり、結果として安全行動の定着につながります。
例として、実際の動画マニュアル(フォークリフトのNG操作)をお見せします。
※動画マニュアル「tebiki」で作成
動画で見せることで、フォークリフトの操作での危険な操作をやってはいけないNG集としてまとめ、新人・熟練者問わずにかんたんに理解できる内容になっています。
マニュアルを動画化するメリットや実際のサンプル動画についてもっと知りたい方は、以下のリンクをクリックし別紙の資料をご覧ください。
>>物流業の事例から学ぶ!動画マニュアルを使った安全教育の取り組みとサンプル動画をみる
安全作業の標準化を進める
ルールを定めたら、全員が同じように安全な作業を行えるよう「標準化」することが重要です。【事例⑧】のように『本来は禁止されている後進移動』といった個人の判断による不安全行動をなくし、誰が作業しても安全が保たれる状態を目指しましょう。特にOJTでは、指導者による内容のばらつきを防ぐためにも標準化された手順が不可欠です。
このとき、重要なのは現場で「暗黙のルール」となっている慣習や省略手順を洗い出すことです。長年の経験で培われたやり方が必ずしも安全とは限らず、事故の火種になる場合があります。そうした曖昧なルールを形式知化し手順書や動画マニュアルに落とし込むことで、誰もが同じ基準で作業できるようになります。結果として教育のばらつきがなくなり、安全性と生産性の両立が実現するのです。
”暗黙知”となった安全ルールや作業手順を言語化し、標準化するコツについては以下の資料も併せてご参照ください。
>>“伝わらない”“属人化している”カンコツ作業やルールを標準化する「最適解」をみる
発生したヒヤリハットを記録して共有する
重大事故の多くは、ヒヤリハットの積み重ねの先で発生します。【事例⑤】のようなフォークの誤操作も、事故に至らないケースは現場で起きているはずです。このような「ヒヤリ」とした体験を報告・収集し、原因と対策を全員で共有することで、同様の重大事故を未然に防ぐことができます。
ヒヤリハット共有に報告書の提出を採用している企業も多いかと思いますが、一部の現場では「報告書の作成が手間」「報告すると怒られそう」と、報告を避けてしまうケースも散見されます。
こうした事態を防ぐべく、現場改善ラボではすぐに使える「ヒヤリハット報告書」が内包されたヒヤリハット事例・対策集の資料をご用意しております。是非お役立てください。
>>そのまま使えるヒヤリハット報告書付き!現場の213名に聞いた「ヒヤリハット事例・対策集」をみてみる
KYT(危険予知訓練)で危険への意識を醸成する
荷役作業では、転倒や落下といった重大事故につながるリスクが常に存在します。その対策として有効なのがKYT(危険予知訓練)です。KYTは作業に潜む危険を事前に洗い出し、対策を共有することで安全意識を高める取り組みです。
例えば【事例④】のように作業前に「雪で床が滑りやすい」という危険を予測し、「足元に注意して慎重に運ぶ」と確認していれば、転倒事故を未然に防げた可能性があります。危険を予知し合う習慣を持つことが危険への感受性を高め、荷役作業の安全確保に直結します。
KYTは口頭や書類配布で実施されることも多いですが、文章やイラストだけでは現場の危険や事故の原因が伝わりづらく、「行ったのにイマイチ安全意識が育たず形骸化する…」というケースもよく耳にします。
形骸化しがちなKYTを変える「〇〇」を活用した次世代のKYTの手法や事例について知りたい方は、以下のリンクをクリックし別紙のガイドブックをご参照ください。
>>ゼロ災を達成!形骸化したKYTから脱却する「〇〇」を活用したKYTとは?
リスクアセスメントを実施して危険を可視化・排除する
リスクアセスメントとは、作業に潜む危険性を洗い出し、評価・低減する手法です。【事例③】では、「ラッシングベルトを緩めると荷崩れする」というリスクを事前に評価し、「複数の作業員で支えながらベルトを外す」などの対策を講じていれば、死亡災害は防げたはずです。科学的なアプローチで危険を排除します。
有効なリスクアセスメント術を知りたい方は、下記リンクから元労基署長が解説した動画を視聴してみてはいかがでしょうか。
>>動画で学ぶ!:現場のキケンを見極める『リスクアセスメント術』を見てみる
作業時の指差呼称を徹底する
指差呼称は確認対象を指で差し、声に出して確認することで意識レベルを高め、ヒューマンエラーを防ぐ安全行動です。【事例⑦】のようにバックモニターがあっても見落とすケースは起こり得ます。「バックモニターよし!」「後方よし!」と呼称を徹底することで、確認行動を確実なものにします。
関連記事:【事例あり】指差呼称とは?効果はある?正しいやり方や定着させる教育方法
トラックやフォークリフトを操作する際は誘導員を配備する
トラックの後退時やフォークリフトの死角が多い場所では、専門の誘導員を配置することが有効です。【事例⑦】のような悲劇的な事故を防ぐためにも運転者と誘導員であらかじめ合図を決め、連携して安全を確保します。また【事例⑥】のような接触事故を防ぐため、周囲の作業員の侵入を監視する役割も担わせるとよいでしょう。
ハード面(設備や機械)で有効な安全対策
保護帽や安全靴を着用する
【事例①】~【事例③】の死亡災害では、いずれも被災者が保護帽を着用していませんでした。落下物や転倒時の衝撃から頭部を守る保護帽や重量物から足先を守る安全靴の着用は、被害を最小限に抑えるための必須アイテムです。あご紐を締めるなど、正しい着用を徹底させましょう。
安全帯(墜落制止用器具)を活用する
「労働安全衛生規則 第521条(安全帯等の取付設備等)」によると、トラックの荷台など、高さ2m以上の場所で作業する際は、墜落制止用器具(旧:安全帯)の着用が法律で義務付けられています。
第521条
事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
2 事業者は、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。
【事例②】のようにテールゲートリフター上での作業もこれに該当します。フルハーネス型を正しく使用することで、万が一の墜落・転落事故から作業員の命を守ります。
昇降設備や作業床を設置する
「労働安全衛生規則 第518条(作業床の設置等)」にあるように、荷台からの安全な昇り降りのために、可搬式の昇降設備(タラップ等)を設置することが推奨されます。
第518条
事業者は、高さが2メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
【事例①】のように、荷物を持って不安定なリアバンパーから飛び降りるような危険な行動をなくし、安全な昇降経路を確保します。また、荷台上で安全に作業するための作業床の設置も有効です。
効果的な安全対策を実施している企業の好事例
荷役作業の安全対策を考える上で、オフィス通販「アスクル」や日用品EC「LOHACO」の物流機能を担う総合物流企業「ASKUL LOGIST株式会社」の事例が参考になります。
同社では多様な人材が在籍する中、OJTの指導品質のばらつきや、辞書のように分厚い紙マニュアルに頼った教育に限界を感じていました。紙媒体では荷物の持ち方といった危険な動作のニュアンスが伝わりにくく、教える側の負担も大きい状況だったのです。
そこで同社は、動画マニュアル(tebiki)を導入。動画と自動翻訳機能を活用し、国籍や経験に関わらず誰でも直感的に安全ルールを学べる環境を整備しました。結果として、新人教育の時間を従来の2時間から30分へと大幅に短縮。指導者による教育品質のばらつきも解消され、現場の負担軽減と作業の標準化を同時に実現しています。
この取り組みは、危険予知やヒヤリハット事例の共有にも動画が活用できるなど、動きを伴う荷役作業の安全対策を考える上で多くの示唆を与えてくれる好事例です。
同社が導入した「動画マニュアル」の活用メリットやおすすめの作成ツールについては、以下の資料で詳しく解説しています。
>>物流業界の生産性向上・安全の確保を助ける「動画マニュアル」について学ぶ
まとめ|荷役作業の安全対策は動画マニュアルでの周知が効果的
本記事では荷役作業において労働災害や事故を防ぐため、実際の事故事例を交えながら10の具体的な安全対策を解説しました。
- 作業手順やルールが記載されている手順書を整備する
- 安全作業の標準化を進める
- 発生したヒヤリハットを記録して共有する
- KYT(危険予知訓練)で危険への意識を醸成する
- リスクアセスメントを実施して危険を可視化・排除する
- 作業時の指差呼称を徹底する
- トラックやフォークリフトを操作する際は誘導員を配備する
- 保護帽や安全靴を着用する
- 安全帯(墜落制止用器具)を活用する
- 昇降設備や作業床を設置する
自社の作業環境に合った安全対策を着実に実行し、継続していくことが重要です。
また、本記事で紹介したASKUL LOGIST株式会社のように動画マニュアル(tebiki)を導入すれば、効率的に従業員に荷役作業の安全対策を周知することができます。動画マニュアルを簡単に作れる「tebiki」についてより詳しく知りたい方は、以下の画像をクリックし是非サービス資料をご覧ください。
引用元/参照元
・厚生労働省「令和5年労働災害発生状況の分析等」
・厚生労働省「荷役作業での労働災害を防止しましょう!」
・厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「陸上貨物運送事業における重大な労働災害を防ぐためには」
・厚生労働省「労働安全衛生規則(抄)」