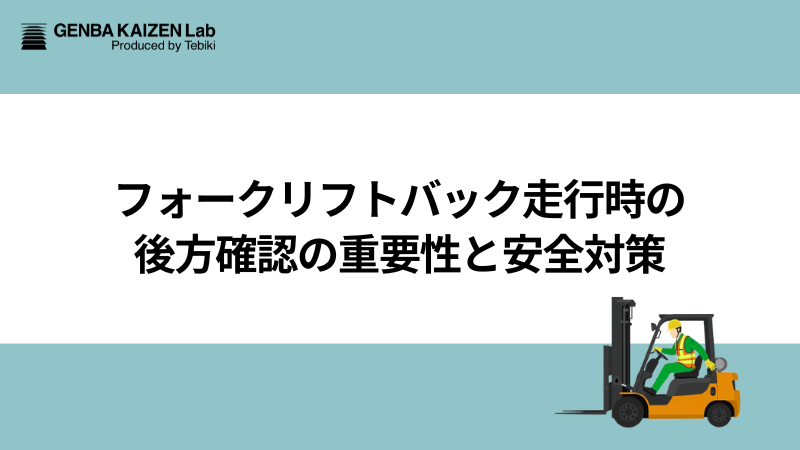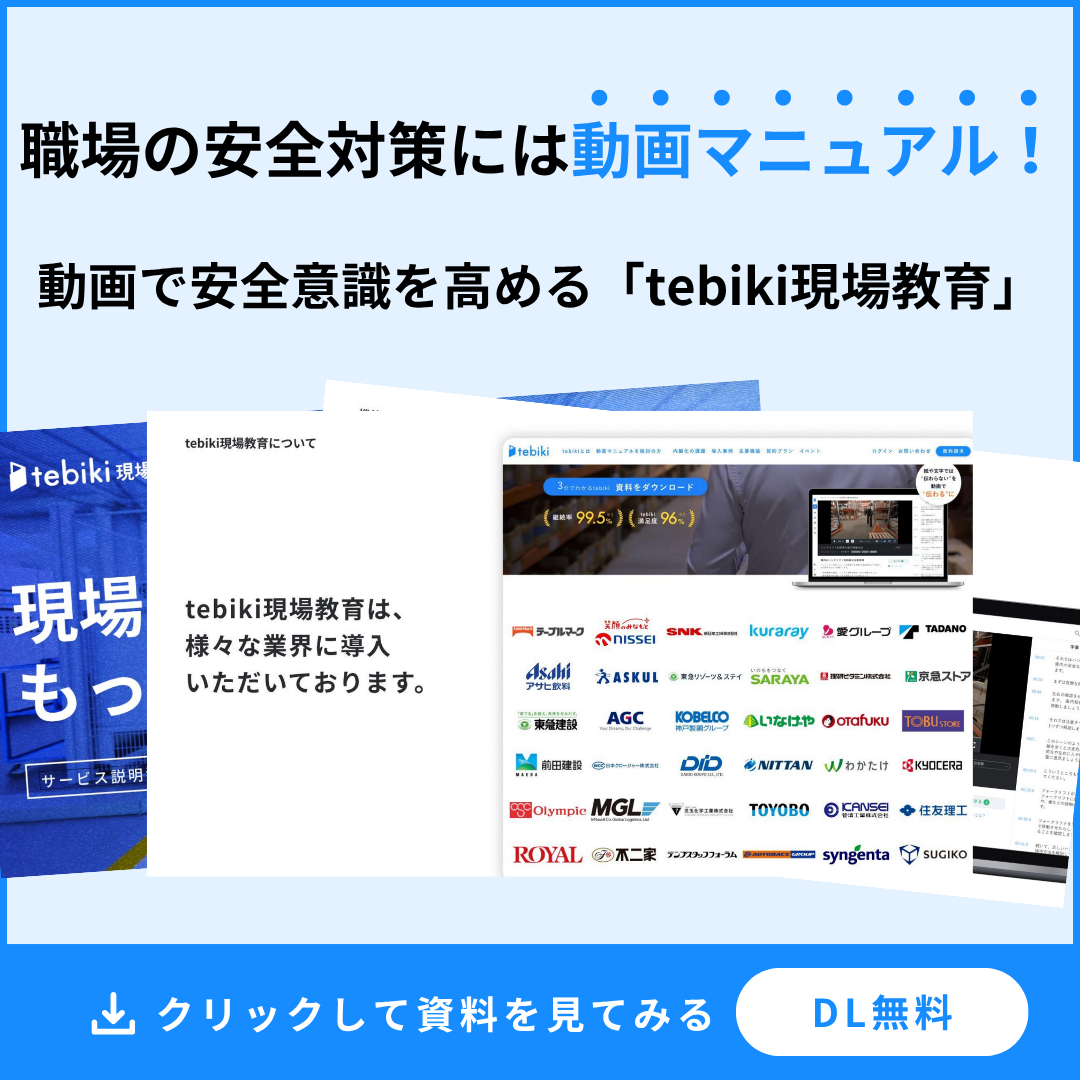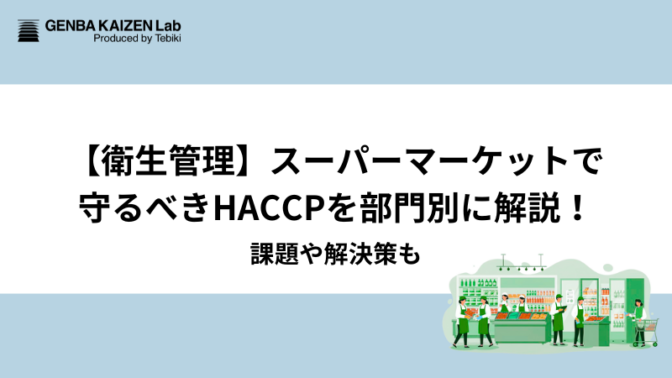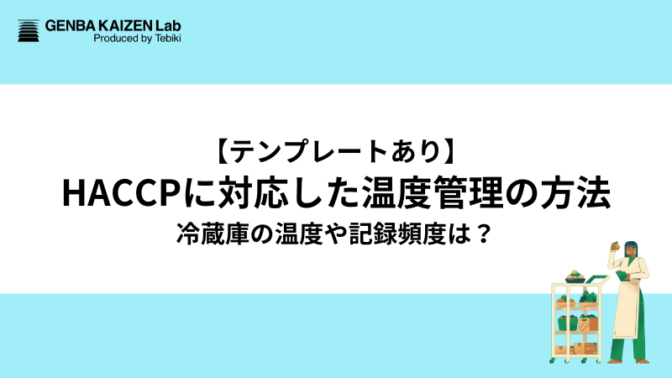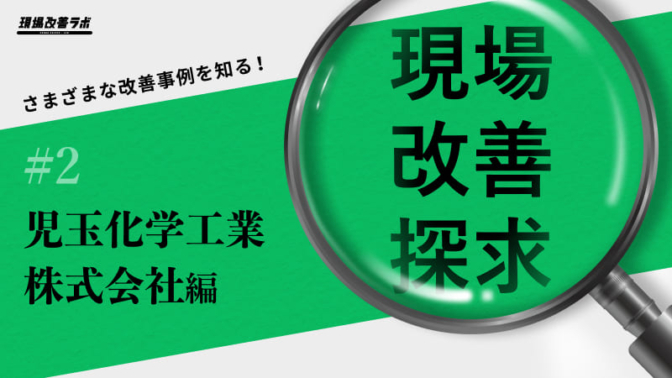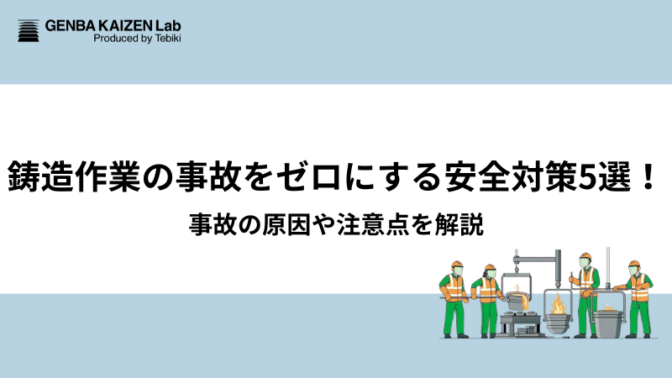物流業・倉庫業に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
フォークリフトを使用する倉庫や作業現場の責任者様や安全衛生担当者様の中には、「後方確認を怠ったことによる事故やヒヤリハットがなくならない」「何か良い対策方法はないだろうか」といったお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
フォークリフトは倉庫や現場作業の効率を上げるために欠かせないマテハン機器です。しかしその一方で、一度操作を誤ると大きな事故につながる危険性も秘めています。
そこで本記事では、フォークリフト業務に15年以上携わっている筆者が後方確認の基本的な情報から、事故を防止するための具体的な対策までを分かりやすくご紹介します。フォークリフトの後方確認に関する正しい知識が身につき、貴社で取るべき対策をご理解いただける内容ですので是非ご覧ください。
▼物流現場の安全意識を高める教育・対策事例集について知りたい方はこちらをクリック!▼
目次
フォークリフトのバック走行前に後方確認を怠るリスク
特にカウンターバランス式のフォークリフトは構造上死角が多いため、バック走行時には通常以上の安全確認が求められます。
後方確認を怠ることでどのようなリスクが生じるのか、以下3つのポイントで解説します。
- 後方確認を怠ると死亡事故にもつながりかねない
- フォークリフト事故の発生原因
- 後方確認不足が原因で発生した事故事例
後方確認を怠ると死亡事故にもつながりかねない
後方確認を怠ることはヒヤリハットや物損事故、労働災害はもちろんのこと、最悪の場合は人の命を奪う事態にもつながりかねません。
実際に厚生労働省が発表したデータによると、フォークリフトに起因する死亡災害は毎年20件以上も発生しています。
| 西暦 | 災害発生件数 | 死亡災害数 |
|---|---|---|
| 2023年 | 1,989件 | 22件 |
| 2022年 | 2,092件 | 34件 |
| 2021年 | 2,028件 | 21件 |
| 2020年 | 1,989件 | 31件 |
| 2019年 | 2,145件 | 20件 |
悲しい事故を防ぐためにも、フォークリフトを操作する全ての作業員に後方確認の徹底を指導する必要があります。
このように、後方確認の徹底を指導することは、悲惨な事故を防ぐための基本中の基本です。
しかし、「わかっているはずなのに、つい怠ってしまう」のが、この種の「不安全行動」の怖いところです。なぜ人は、基本であるはずの安全行動を繰り返してしまうのでしょうか。
その根本原因にアプローチするためには、人間の行動原理を解き明かす「行動科学」の視点が非常に有効です。指示や注意喚起だけでは防ぎきれない、繰り返される不安全行動を根本から断ち切るための決定的な防止網の構築方法について、以下の資料で詳しく解説しています。
>>繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網を見てみる
関連記事:【最新】フォークリフト事故の実態!事例や発生件数・原因について
フォークリフト事故の発生原因
厚生労働省「職場の安全サイト:労働災害統計」によると、フォークリフトに起因する事故の発生原因は以下のとおりです。
- はさまれ・巻き込まれ:22.7%
- 激突され:18%
- 墜落・転落:18%
- 転倒:17.2%
- 飛来・落下:11.7%
- その他:12.5%
この中で割合の大きい「はさまれ・巻き込まれ」や「激突され」は、後方確認の不足が原因で発生するケースも少なくありません。
このデータが示す通り、フォークリフト災害の多くは、運転者のささいな行動がきっかけで発生します。
「後方確認の不足」をはじめとする、こうした“うっかり”や“思い込み”による行動こそが「ヒューマンエラー」です。ルールを知っていても起きてしまうヒューマンエラーを防ぐためには、その発生メカニズムに焦点を当てた安全教育が不可欠です。
ヒューマンエラーによる労災を未然に防ぐための、効果的な安全教育の進め方について、以下の資料で詳しく解説しています。
>>ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育を見てみる
関連記事:「挟まれ・巻き込まれ災害」を防ぐ6つの方法!事例も解説
後方確認不足が原因で発生した事故事例
では、後方確認不足が原因で起こった事故にはどういったものがあるのか、厚生労働省「職場のあんぜんサイト:労働災害事例」に掲載されている事例と、筆者が過去に勤務していた職場で実際に発生した事例をご紹介します。
バック走行時に後方が死角になり作業者に接触
荷役作業中のフォークリフトが後進した際、後方でトラックの扉を開けていた別の作業員に気づかず接触し、挟まれて死亡するという労働災害が発生しました。
フォークリフトの後方はバランスウエイトがあるため死角が多く、特に危険です。死角の存在を正しく理解し、前進時以上に念入りな安全確認が求められます。
前方の貨物に気を取られ後方確認を怠り作業者の足を踏む
筆者が過去に勤務していた職場では、コンテナからのデバンニング作業中に後方の通路を歩いていた作業員に気づかずバックし、足を踏んで負傷させる事故がありました。
コンテナ内の貨物のバランスが不安定だったため前方に意識が集中し、後方確認がおろそかになったことが原因です。
貨物を移動させる際は注意すべき点が増えるため、一旦停止して指差呼称を行ったり、徐行運転をしたりするなど、通常以上の後方確認を徹底すべきでした。
このような後方確認不足で発生する事故は、安全教育による安全意識の向上により防ぐことが可能です。フォークリフトの安全教育の具体例や成功事例について知りたい方は、以下のリンクから別紙のガイドブックをご覧ください。
>>目指せゼロ災!フォークリフトの安全教育・対策事例集をみてみる(無料公開中)
フォークリフトの後方確認のやり方
次に、具体的なフォークリフトの後方確認の方法について種類ごとに解説します。
- リーチフォークリフトの後方確認手順
- カウンターバランス式フォークリフトの後方確認手順
リーチフォークリフトの後方確認手順
リーチフォークリフトは半身で立った状態で操作するため、体全体を使って進行方向を確認できるのが特徴です。
具体的な後方確認の手順は以下の通りです。
- 左右後方・真後ろ(後方全体)目視し、後方全体が見えるまで体・首をひねる
- 2秒間後方全体を目視確認する
- 進行方法である真後ろに、再確認の指差呼称を行う
関連記事:【事例あり】指差呼称とは?効果はある?正しいやり方や定着させる教育方法
カウンターバランス式フォークリフトの後方確認手順
カウンターバランス式はリーチフォークリフトと違い正面を向いて着座して操作するため、体全体で後方を確認することはできません。
ここでは、進行方向が「右後方」である場合の手順を解説します(左後方の場合は左右を入れ替えてください)。
- 進行方向と逆側の左後方を目視
- 真後ろが見えるまで体・首をひねる
- 2秒間真後ろまで目視
- 進行方向である右後方を目視
- 真後ろが見えるまで体・首をひねる
- 2秒間真後ろを目視します
- その後、右後方に再確認の指差呼称をします
フォークリフトのバック走行時の事故を防止するための対策
ここまで後方確認の重要性について解説してきましたが、ヒヤリハットや事故を撲滅するには効果的な対策を講じることが不可欠です。
具体的な対策として、以下の7つをご紹介します。
- 定期的な安全教育を実施し、安全への意識を高める
- フォークリフトの不安全行動を可視化する
- 後方確認の実施を仕組み化する
- フォークリフトの死角を把握する
- 作業エリアと歩行帯を分ける
- 5S活動を実施して、整理整頓された環境を維持する
- 安全対策グッズを活用する
一方で、どれだけ詳細な対策を講じたとしても、それが現場の従業員に守られなくては意味がありません。重要なのは、従業員1人ひとりが「事故を起こさないという意識・行動」を高い水準で持つことです。
従業員の安全意識を高めるフォークリフト安全教育の方法・事例については、以下のガイドブックをご覧ください。
>>目指せゼロ災!安全意識を高めるフォークリフトの安全教育・対策事例集をみてみる(無料公開中)
定期的な安全教育を実施し、安全への意識を高める
ヒューマンエラーに起因する事故を防ぐには、定期的な安全教育が不可欠です。
このとき重要なのがルールを教えるだけでなく、危険を「自分ごと」として捉えさせることです。バック走行に特化した危険予知訓練(KYT)の開催など継続的な教育を通じて、安全な運転を習慣化させましょう。
KYTは安全教育の手法として広く採用されている一方、「文字情報だけでは危険が伝わらない」「やって終わりで形骸化している」という現場もよく耳にします。そこで、形骸化したKYTから脱却する「次世代KYT」のやり方や具体例についてまとめた資料をご用意いたしました。安全意識向上のため、是非お役立てください。
>>脱ネタ切れ・マンネリ化!〇〇の活用で実現する形骸化しないKYTの方法や事例をみる(無料公開中)
フォークリフトの不安全行動を可視化する
経験や勘に頼った安全管理には限界があります。もしコストをかけられるのであればAIカメラやIoTセンサーなどのテクノロジーを駆使することで作業員の不安全行動や危険な状況を「可視化」し、客観的なデータに基づいて対策を講じるのは有効な手段のひとつです。
さらに、リフトごとの危険な接近回数やヒヤリハットの映像を分析することで、事故に至る前の段階でリスクの芽を摘むことができます。
繰り返される不安全行動には、「正しい手順が可視化されていない/習慣化されていない」というシンプルな原因が潜んでいます。不安全行動を減らし事故を未然防止する対策について、行動科学から解明した資料もご用意しておりますので、本記事と併せてご覧ください。
>>繰り返される不安全行動に終止符を!行動科学から編み出す「決定的防止網」についてみる(無料公開中)
後方確認の実施を仕組み化する
後方確認が特に重要な場面をあらかじめ特定し、その行動を「仕組み化」することで、確認漏れという危険因子を減らすことができます。
例えば、以下のようなルールを設けるのが効果的です。
- 作業エリアから歩行エリアを通過しなければならない時は、一旦停止し後方確認を十分に行ってから通過する
- バック走行で右左折する際は一旦停止し左右後方を確認し、指差呼称してから曲がる
これらのルールを仕組みとして徹底させることが、日頃の安全意識の向上にもつながります。仕組化するうえで欠かせない「従業員の安全教育」の手法や具体例について知りたい方は、以下のリンクをクリックしてください。
>>物流現場の安全意識を高める教育手法・対策事例集についてみる(無料公開中)
フォークリフトの死角を把握する
特に経験の浅い作業員には、フォークリフトのどこに死角があるのかを具体的に把握させることが事故防止につながります。例えば、目の高さまでマストを上げた時の前方や、カウンターウエイトの下などが代表的な死角です。
作業ごとにどのような死角が生じるのかをあらかじめ理解し、注意を払うよう指導することが重要です。
関連記事:フォークリフトの死角はどこ?事故を防止する対策や安全意識向上の秘訣
作業エリアと歩行帯を分ける
フォークリフトと作業員の接触事故を防ぐ最も根本的な対策が、「人車分離」の徹底です。通路をラインや色で明確に区分けしたりガードレールを設置することで、フォークリフトの走行エリアと歩行帯を物理的に分離しましょう。
ヒューマンエラーに起因する事故を未然に防ぐだけでなく、フォークリフトが効率的に走行できるため、生産性の向上にもつながります。
5S活動を実施して、整理整頓された環境を維持する
整理・整頓・清掃・清潔・躾の5S活動は、安全な作業環境の土台です。特に「整理・整頓」の徹底は、通路にはみ出した荷物との接触事故や、床の障害物による転倒リスクを低減します。
単なる清掃活動ではなく、決められたルールを守る「躾」を習慣化することで、従業員1人ひとりの安全意識を高めましょう。
▼事故の未然防止につながる「実践的な5S活動」の進め方について知りたい方はこちらをクリック!▼
安全対策グッズを活用する
人間の注意力を補う安全対策グッズの活用は、事故防止に極めて有効といえます。例えば、人や物に接近した時に光やブザー音で知らせてくれる「AIカメラ」は、おすすめの対策方法です。
1台あたり数十万円が必要となりますが、安全対策は単なるコストではなく、企業の資産と従業員を守るための「投資」と捉えることが重要です。
フォークリフトでバック走行する際の基本的な操作方法
事故防止の対策を講じることも大切ですが、それと同時に、作業員1人ひとりがバック走行の基本的な操作方法を正しく知り、実行することが事故防止の第一歩です。
この項ではフォークリフトでバック走行する際の基本として、以下の3つをご紹介します。
- バック走行の基本ルール
- バック走行の姿勢
- バック走行のコツ
バック走行の基本ルールは「まず確認」
バック走行に限ったことではありませんが、何よりもまず安全確認をすることが非常に重要です。特にバック走行は死角が多く、後方の状況が分からない状態から車両を動かすことになるため、危険が伴います。
具体的なルールは、先述の【フォークリフトの後方確認のやり方】でお伝えした手順でしっかりと安全確認をしてから、走行レバーを操作する、ということです。
筆者の経験上、慌てていると、どうしても先にレバーをバックに入れてから安全確認を行いがちです。この「逆の操作」が事故に繋がるため、十分な注意が必要です。
バック走行の姿勢はフォークリフトの種類により異なる
正しい姿勢で操作することは確実な安全確認に繋がり、結果として事故防止や体への負担軽減にもなります。ここでは、フォークリフトの種類別に正しいバック走行の姿勢を解説します。
カウンターバランス式フォークリフトの場合
カウンターバランス式フォークリフトは正面を向いて着座した姿勢で運転するため、体や首をひねって後方を見ながらバック走行するのが基本姿勢です。
具体的には左手でハンドルスピナーを握り、右手は右後方のフレーム(または取っ手)を持って体を支え、後方を向いた姿勢で走行します。
リーチフォークリフトの場合
リーチフォークリフトはカウンターバランス式とは違い、立った状態で乗車するため、体全体を進行方向に向けることができます。
バック走行時は体を後方に向け、右手で走行レバーを操作するのが正しい姿勢です。
バック走行のコツは「ゆっくり大きく曲がる」
バック走行時のコツは、右左折する際に「ゆっくり、大きく曲がる」ことを意識することです。
フォークリフトは乗用車と違い、後輪が曲がる「後輪操舵」であり、さらに後輪は90度近くまで旋回するため非常に小回りが利きます。これらの特性から、走行中に急なハンドル操作をすると、車体がほぼ直角に曲がってしまい、転倒や荷崩れの危険性が高まります。
バック走行で旋回する際は、この「ゆっくり、大きく」という意識を常に持つようにしましょう。
関連記事:【経験者が解説】フォークリフト運転上達のコツ!上手い人の特徴とは?
まとめ
後方確認を怠ることは、重大な事故に直結する危険な行為です。そのため、本記事でご紹介したような対策を通じて、全ての作業員が正しい方法で抜け漏れなく後方確認を実施するよう徹底することが、現場の安全を守る上で極めて重要となります。
本記事でご紹介した具体的な対策方法は以下の通りです。
- 定期的な安全教育を実施し、安全への意識を高める
- フォークリフトの不安全行動を可視化する
- 後方確認の実施を仕組み化する
- フォークリフトの死角を把握する
- 作業エリアと歩行帯を分ける
- 5S活動を実施して、整理整頓された環境を維持する
- 安全対策グッズを活用する
これらを実践し、全ての従業員が安心して働ける職場づくりを目指しましょう。
フォークリフトの安全教育・対策に役立つ事例/対策集について知りたい方は、以下の画像をクリックし別紙のガイドブックをご覧ください。