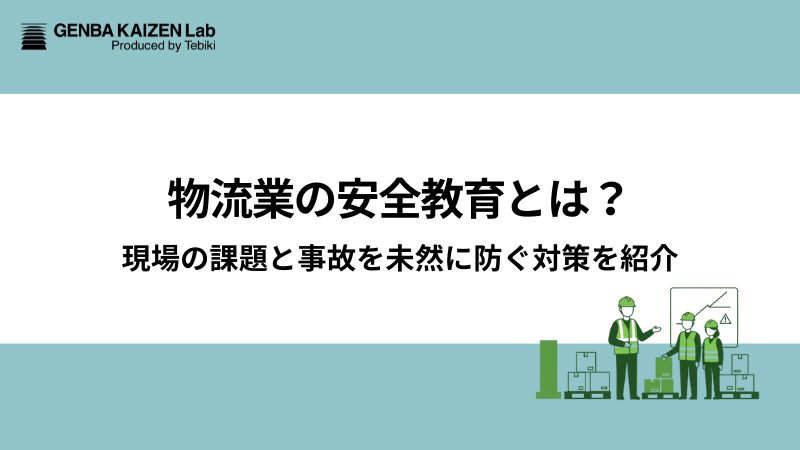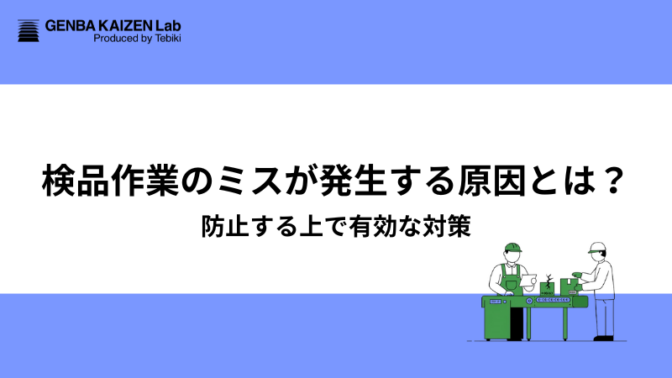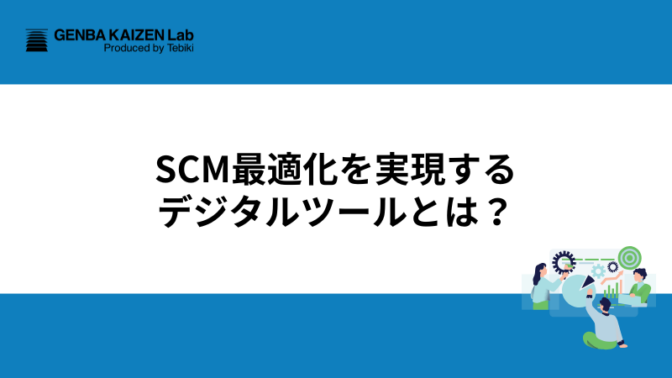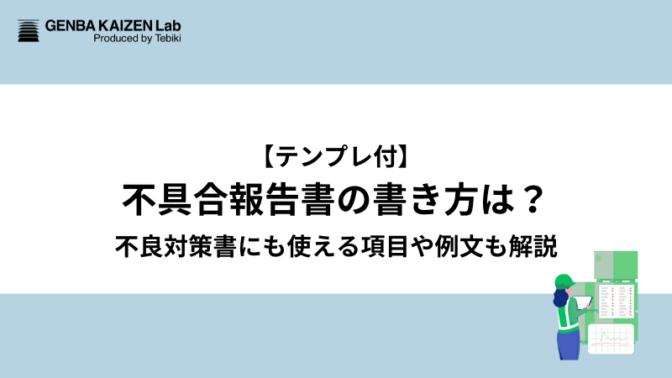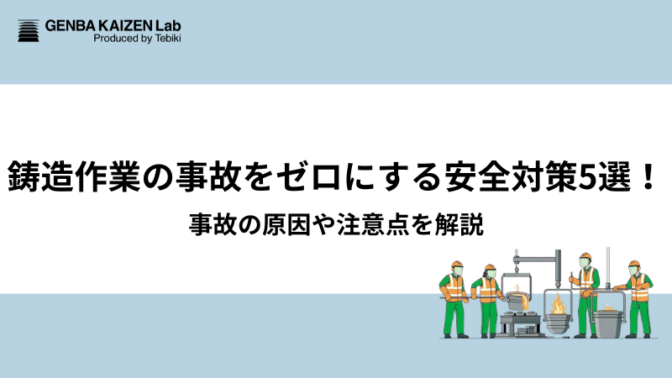かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する現場改善ラボ編集部です。
物流業の現場には多くの「危険」が潜んでおり、見過ごすと重大な事故や災害に発展する恐れがあります。これを防ぐには、現場のリスクや業務内容に即した安全教育を実施し、従業員一人ひとりの安全意識の向上と安全行動の定着につなげることが重要です。
本記事では物流現場で実施する安全教育の内容とともに、現場が抱える教育課題や事故を防ぐための対策について詳しく解説します。
なお、近年では安全教育の手段に「動画マニュアル」を採用する企業が増えています。動画を用いた安全教育は物流現場における危険な行為や状況を視覚的に伝えられるため、従業員の安全意識を効果的に高めることができます。
動画を活用した安全教育の事例や活用の効果については、本記事のほか以下の資料でも詳しく解説しています。ゼロ災達成に向け、是非お役立てください。
>>物流業の事例から学ぶ!動画マニュアルを使った安全教育の取り組みと成果についてみる
目次
物流業における安全教育の重要性
物流業界では、倉庫業や運送業など多岐にわたる業務で労働災害が発生しています。事故を未然に防ぎ、従業員が安全に働ける環境を確保するためには、現場における安全教育の徹底が不可欠です。
実際に物流現場では、どのような事故が発生しているのでしょうか。下表では、倉庫業・フォークリフト作業・運送業それぞれにおける労働災害の発生状況をまとめています。
▼倉庫業▼
| 年 | 労働災害(件) |
|---|---|
| 2020 | 685 |
| 2021 | 781 |
| 2022 | 821 |
| 2023 | 863 |
| 2024 | 909 |
倉庫業では2020年から2024年にかけて労働災害発生件数が増加傾向にあり、現場でのリスクが年々拡大していることが読み取れます。倉庫現場で発生する事故の種類としては、転倒や転落、激突、落下、挟まれ・巻き込まれなどが挙げられます。
関連記事:【作業別】倉庫・物流ヒヤリハット事例集!企業の対策例も解説
▼フォークリフト作業▼
| 年 | 死傷災害(件) | 死亡災害(件) |
|---|---|---|
| 2019 | 2,145 | 20 |
| 2020 | 1,989 | 31 |
| 2021 | 2,028 | 21 |
| 2022 | 2,092 | 34 |
| 2023 | 1,989 | 22 |
こちらはフォークリフト作業に起因する労働災害について、2019年から2023年にかけての死傷災害・死亡災害の発生件数をまとめたものです。死亡災害数は年によってばらつきがある一方、死傷災害数は常に2,000件前後で推移しており、現場での負傷リスクは依然として高い状況が続いています。
関連記事:【最新】フォークリフト事故の実態!事例や発生件数・原因について
▼陸上貨物運送業▼
| 年 | 死傷者数(人) | 死亡者数(人) |
|---|---|---|
| 2020 | 15,815 | 87 |
| 2021 | 16,732 | 95 |
| 2022 | 16,580 | 90 |
| 2023 | 16,215 | 110 |
| 2024 | 16,292 | 108 |
運送業においては、死傷者数・死亡者数ともに高止まりの状態が続いています。荷役時の転落や転倒、交通事故などが主な原因で、現場の安全管理と従業員への教育体制の強化が急務となっています。
これらのデータが示す通り物流業界では労働災害の発生リスクが高く、実効性の高い安全教育と現場に即した実施方法が極めて重要となります。具体的にどのような事故が労働災害を引き起こしているのか、次章では物流現場で発生しやすい事故事例について解説します。
【作業別で見る】物流現場でよくある事故とその原因
物流現場では転倒や転落、機械との接触などの事故が日常的に発生しています。これらは多くの場合、重大事故につながる前段階の「ヒヤリハット」の積み重ねが原因であり、事故防止には現場で起こりやすいヒヤリハットを把握しておくことが重要です。
ここでは、物流現場における事故・ヒヤリハットの事例を物流業に従事していた筆者の経験をもとに、作業別に紹介します。現場でとるべき対策にも言及しておりますので、是非KY活動などにお役立てください。
>>物流業の事例から学ぶ!ゼロ災に向けた安全教育の取り組みと成果を見たい方はこちらをクリック!
倉庫作業中の事故・ヒヤリハット事例
荷役作業や梱包作業など、倉庫作業中に起こりやすい事故・ヒヤリハットの事例をまとめています。
| 事故事例 | ヒヤリハット事例 | 主な原因 |
|---|---|---|
| 荷物の落下による負傷 | 棚から荷物が落ちそうになったが、とっさに支えて事故には至らなかった | ・棚への過積載 ・ロケーション管理不足(重い荷物を高所に置いていた) |
| 高所からの転落 | 高所作業中に脚立のバランスが崩れ、危うく転落しそうになった | ・脚立の設置場所が不安定だった ・安全帯やヘルメットを使用しなかった |
| カッターナイフによる負傷 | 梱包作業中にカッターナイフの刃が勢いよく滑り、指を切りそうになった | ・軍手を着用していなかった ・セーフティカッターを使用していなかった |
倉庫作業中の事故を防ぐには、まずは荷物の重量や棚の耐荷重を管理し、重い荷物は下段に配置することで落下事故のリスクを減らすことが有効です。高所作業も多い場合は脚立を必ず平らな場所に設置し、安全帯やヘルメットを着用して転落を防止します。
関連記事:倉庫整理の悩みを解決!5Sに基づく基本手順と劇的に改善するコツ
また、梱包作業の際は必ず軍手を着用し刃が自動で戻るセーフティカッターを使用することで、カッターによる負傷を防ぎましょう。
フォークリフト作業中の事故・ヒヤリハット事例
フォークリフト作業中に起こりやすい事故・ヒヤリハットの事例をまとめています。
| 事故事例 | ヒヤリハット事例 | 主な原因 |
|---|---|---|
| 作業員との接触 | バック走行中に作業員と接触しそうになったが、相手がすぐに避けたため事故には至らなかった | ・周囲の確認を怠っていた ・フォークリフト後方が死角になり、作業員に気づけなかった |
| 傾斜地での転倒 | 方向転換時にバランスを崩しかけたが、作業者がすぐに操作を調整して転倒には至らなかった | ・運転技術が不十分だった ・誘導員を配置していなかった |
フォークリフトによる事故を減らすには、まず作業員との接触を防ぐことが重要です。死角となりやすい後方の確認を徹底するほか、走行ルートと作業員の通路を分けるといった物理的な対策が有効です。
また、傾斜地などでの転倒を防ぐには速度を落として慎重に操作することを基本とし、定期的な技術研修で運転スキルを維持・向上させる必要があります。加えて特に不安定な場所を走行する際は、誘導員を配置して安全を確保しましょう。
フォークリフト事故の実態や事例については以下の記事でも詳しく解説しています。本記事と併せてご覧ください。
関連記事:フォークリフト事故・労災の実態:事例や発生件数・原因について
トラック運転中の事故・ヒヤリハット事例
輸送時のトラック運転で起こりやすい事故・ヒヤリハットの事例をまとめています。
| 事故事例 | ヒヤリハット事例 | 主な原因 |
|---|---|---|
| 路面凍結によるスリップ事故 | ブレーキをかけた瞬間にタイヤがスリップしたが、対向車が来ておらず、事故には至らなかった | ・路面凍結により道路が滑りやすくなっていた ・ブレーキをかける力が強かった |
| 車体の横転・転落 | 急カーブで荷物が偏り、車体が傾いたが、転倒には至らなかった | ・カーブでの速度管理が不足していた ・荷物の固定が不十分だった |
トラック運転による事故は死亡事故にもつながりかねない重大なインシデントです。これを防ぐには、まずスリップ事故対策として事前に道路状況を確認し、凍結の危険があるルートは極力回避します。やむを得ず走行する際はタイヤチェーンやスタッドレスタイヤを装着し、急ブレーキを避ける慎重な運転を徹底することが不可欠です。
また車体の横転・転落を防ぐためには、運転操作と荷物の管理が重要になります。カーブの手前で十分に減速し、急ハンドル・急ブレーキを避けることはもちろん、積荷が崩れないようラッシングベルトでしっかりと固定しましょう。
物流現場の事故・ヒヤリハット事例をさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
関連記事:【作業別】倉庫・物流ヒヤリハット事例集!企業の対策例も解説
物流事故を未然に防ぐ! 安全教育の内容と実施方法
物流現場に潜む「危険」を回避し事故や災害を未然に防ぐには、従業員の役割や業務内容に応じた安全教育の実施が不可欠です。ここでは、倉庫担当者・フォークリフト作業者・トラックドライバーを対象とした安全教育の内容と、具体的な実施方法をご紹介します。
倉庫担当者への安全教育・安全対策
倉庫作業に関する安全教育・安全対策の一例を下表にまとめています。
関連記事:倉庫作業の安全対策12選:事故防止を実現する物流企業事例も紹介
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 危険予知(KY)活動 | 作業中の潜在的なリスクを察知し、事前に予防措置を講じる訓練。単なる注意喚起ではなく、具体的な事故防止策を検討し、現場で確実に実行するよう指導する |
| 重量物の取り扱い | 従業員の腰痛や落下事故を防止するために、荷物の重さ制限(人力で運ぶ限界)や正しい持ち上げ方、運搬時の姿勢など実践を交えて指導する |
| 脚立・はしごの使用方法 | 脚立の天板に乗らない、足もとがぐらつく場所に立てない、昇降時は両手で手すりを持つなど、基本的な安全ルールや正しい使用方法を指導する |
| ヘルメットの着用 | 作業中は必ずヘルメットを着用し、落下物や衝撃から頭部を保護するよう指導する |
| 倉庫内の通路・荷役エリアの整理整頓 | 通路に荷物や資材を置かない、不要な道具や廃材を片付けるなど、5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)を徹底し、転倒や衝突のリスクを軽減する |
| 熱中症対策 | 作業場の温度・湿度管理、水分補給や休憩のタイミング、適切な服装などの熱中症対策を呼びかけ、従業員が安全かつ健康に働ける環境を確保する |
上記の教育・対策のうち、KY活動を採用している現場は特に多いのではないでしょうか。KY活動は正しく行えば従業員の危険感受性を高められる一方、活動そのものが目的になり形骸化したり、文章では現場に潜む危険が上手く伝わらないといったお悩みもよく耳にします。
そこで、形骸化したKYTから脱却する「次世代のKY活動」についてまとめた資料をご用意いたしました。従来のKY活動にありがちな課題を解決し、事故を未然防止する安全教育を実現されたい方は是非ご覧ください。
>>ゼロ災達成のヒントに!形骸化した活動から脱却する次世代型「〇〇によるKY活動」についてみる
フォークリフト作業者への安全教育
フォークリフト作業者への安全教育は、厚生労働省通達の「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」を基に、以下の科目に関する教育を実施します。
| 科目 | 範囲 |
|---|---|
| 最近のフォークリフトの特徴 | (1)フォークリフトの構造上の特徴 (2)各種荷役運搬方法の特徴 |
| フォークリフトの取扱いと保守 | (1)フォークリフトによる作業と安全 (2)フォークリフトの点検・整備 |
| 災害事例及び関係法令 | (1)災害事例とその防止対策 (2)労働安全衛生法令のうちフォークリフトに関する条項 |
なお物流現場では、フォークリフトによる労災を防ぐ安全教育の手段に「動画マニュアル」の導入が増えています。正しい操作手順だけでなく、何をどうやったら危険やヒヤリハットにつながるのかも可視化(危険の見える化)できるため、安全意識や危険意識が浸透する教育アプローチとして有効とされています。
動画マニュアルによるフォークリフト安全対策の具体的な効果や企業事例は、下記の資料「動画マニュアルを活用したフォークリフトの安全教育・対策事例」で解説しているので、併せてご参照ください。
>>「動画マニュアルを活用したフォークリフトの安全教育・対策事例」を見てみる
トラックドライバーへの安全教育
トラックドライバーへの安全教育は、国土交通省通達の「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」を基に実施します。この指針において12の指導・監督内容が規定されていることから、ドライバーに対する安全教育内容は「法定12項目」と呼ばれています。
▼法定12項目▼
- 事業用自動車を運転する場合の心構え
- 事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項
- 事業用自動車の構造上の特性
- 貨物の正しい積載方法
- 過積載の危険性
- 危険物を運搬する場合に留意すべき事項
- 適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況
- 危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法
- 運転者の運転適性に応じた安全運転
- 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因並びにこれらへの対処方法
- 健康管理の重要性
- 安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法
トラックドライバー安全教育の内容を詳しく知りたい方は、国土交通省が作成した以下のマニュアルもご参照ください。
参考資料:自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル
【共通】安全教育の実施方法
物流業界の安全教育は、主に以下の3つの実施方法があります。いずれの方法も実際の業務で安全に作業を行うための知識・技能の習得を目的としていますが、教育の種類によって伝えられる内容や習得のしやすさに差があるため、現場の特性や社内のリソース、従業員の習熟度に応じて最適な方法を選択することが大切です。
| 教育方法 | 例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 紙教材を用いた教育 | ・紙のマニュアル ・チェックリスト | 基本的な知識の確認や情報共有に有効 |
| 動画教材を用いた教育 | ・動画マニュアル ・eラーニング | 現場作業の動作や手順が映像化され、直感的に理解できる |
| 外部の安全教育講習 | ・専門機関や団体が実施する講習 | 経験豊富な講師のもとで、最新の法令や業界標準に基づく内容を学べる |
上記のうち、特におすすめなのは「動画マニュアル」です。最大の理由は、学習効果の高さと教育の均質化です。動画は実際の動きを映像で見せるため経験や言語を問わず誰にでも伝わりやすく、指導内容のばらつきを防ぎます。また、従業員がいつでも反復学習できる点もメリットです。
紙教材や外部講習と組み合わせその「中核」として活用することで、安全教育全体の効率と質を向上させることができます。
すでに安全教育に動画を活用している企業の事例や、実際のマニュアルサンプルをご覧になりたい方は以下のリンクから別紙の資料を入手しお役立てください。
>>安全意識が高い現場はもう採用している!動画を活用した安全教育の取り組みを見たい方はこちらをクリック!
物流業の安全を脅かす4つの教育課題
物流現場における安全教育の重要性は高まっているものの、実際には次のような課題を抱えている現場も多く、安全対策が十分に機能していないケースが見られます。
これらの教育課題について以下で詳しく解説します。
教育内容が形骸化・属人化している
物流現場でよく見られるのが、「安全教育を実施すること」自体が目的となり、従業員が現場で活かせる実践的内容となっていないケースです。現場の状況は常に変化しているにもかかわらず、一度設計した安全教育を使い続けてしまい、内容が形骸化している現場も少なくありません。
また、教育内容や手法を各指導者の経験や判断に依存し、教育の質にばらつきが生じるケースも見受けられます。このような状況では従業員によって危険予知能力や安全行動に差が生まれ、現場全体の安全レベルの底上げが難しくなります。
教育の形骸化・属人化を防ぐにはマニュアルや教材を定期的に見直し、常に現場に即した内容に更新することが大切です。
外国人労働者や短時間労働者への対応が不足している
物流業界では、外国人労働者や短時間労働者といった多様な人材が働いており、こうした層への安全教育が十分に行われていないことも課題となっています。
言語の違いや理解度の差、教育に充てられる時間などを考慮せず、すべての人材に一律の安全教育を実施しても、十分な理解や習熟を得ることはできません。その結果、全員が同じ安全基準で作業できず、労働災害につながる事故やヒヤリハットのリスクが増大してしまいます。
こうした理解度や習熟度の差をなくすには、多言語対応のマニュアルや短時間でも理解しやすい動画教材など、従業員の状況に応じたツールを活用するのが有効です。
事故・ヒヤリハット事例が共有されていない
現場で実際に起こった事故やヒヤリハットの事例は、安全教育や事故防止対策を検討するうえで非常に重要な資料となります。しかし、こうした情報が横展開されず、同じミスが繰り返されるケースも少なくありません。
事故やヒヤリハットを軽視するような現場では、従業員が「危険」を正しく認識できず、重大な事故を引き起こす危険性が高まります。ヒヤリハットを含む事故事例を定期的に共有する時間を設け、実際の事例を“生きた教材”として教育に組み込むことが大切です。
現場作業を最優先する組織風土がある
慢性的な人手不足や長時間労働といった課題を抱えている物流業界では、現場作業を優先するあまり、従業員への安全教育を後回しにすることがあります。目先の業務や数字を重視する現場は、何よりも作業効率や生産性を優先するため、ヒヤリハットに気づいても対応しない、そもそも気づかないということもあり得ます。
教育機会が不足すると、従業員一人ひとりの安全意識が向上せず、現場の安全が脅かされます。これを防ぐには現場優先の文化を変える必要があり、安全教育を業務の一部としてスケジュールに組み込むなど、後回しにできない仕組みをつくるのが効果的です。
安全教育の課題を解決するには「動画」が有効
紙のマニュアルや口頭説明だけでは、作業の細かな動きや注意すべきポイントを十分に伝えきれず、従業員の安全意識が育ちにくいという課題があります。そこで有効なのが、動きを直感的に理解できる「動画」を活用した教育方法です。
安全意識の向上とわかりやすいマニュアル整備が安全教育のカギ
物流現場では、日々の作業に潜む「危険」をいかに減らし、事故や災害を未然に防ぐかが大きな課題となります。この課題を解消するには、現場で働く一人ひとりの安全意識を高める必要があり、誰もが一目で理解できるマニュアルの整備が欠かせません。
単に情報を伝えるだけでなく、従業員が実際の作業手順や危険なポイントを理解し、現場で正しい行動を取れるようにする仕組みが必要です。
ここでおすすめな手段である「動画」について、次章では詳しく解説します。
物流業の安全教育に「動画」がおすすめな理由
物流現場では「動き」が業務ノウハウの中心となり、荷物の積み方やフォークリフトの操作方法、検品作業の手順など、細かな動作一つひとつに安全や効率を左右するポイントが含まれています。しかし、紙のマニュアルではこうした「動き」を正確に伝えるのが難しく、受け手によって理解に差が生じたり、習熟度にばらつきが出たりすることがあります。
この点、動画を用いた安全教育であれば、標準的な作業手順を正しく伝えられるだけでなく、危険な動作や禁止事項を実例として示すことも可能です。
例として、「フォークリフトのNG運転例」を動画でマニュアル化したものをお見せします。
※「tebiki現場教育」で作成しています
動画であれば「どのような動作が危険なのか?」を見たままに伝えられるため、従業員の安全意識や業務理解がより深まります。
本サンプル動画の作成に使用されたかんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」なら、現場の担当者がスマートフォンで撮影するだけで、誰でもかんたんに動画教材を作成・編集できるため、手間なく効果的な安全教育が可能です。
動画を活用するメリットや実際の導入事例について知りたい方は、以下のリンクから詳しい資料をご覧ください。
>>安全意識が高い現場はもう採用している!動画を活用した安全教育の取り組みを見たい方はこちらをクリック!
動画を活用した安全教育の事例
実際に動画マニュアル(tebiki現場教育)を導入し、安全教育の効率化や安全意識の向上につなげた事例をご紹介します。
株式会社ロジパルエクスプレス:安全品質意識の向上で労災防止
最初にご紹介するのは、、倉庫や車両などの自社資産を活用した物流サービスを提供している株式会社ロジパルエクスプレスの事例です。
| 課題 | tebiki現場教育導入後の効果 |
|---|---|
| ・拠点ごとにマニュアルやルールにばらつきがある ・安全品質を高めて事故やヒヤリハットを削減したい ・紙マニュアルの工数を削減したい | ・全拠点でルールやマニュアルを統一できる環境が整った ・業務上の危険や業務解像度が伝わりやすくなり、安全品質意識が向上 ・マニュアルを申請してから確認と承認までの時間が短縮 |
同社では紙ベースのマニュアルを運用していましたが、紙媒体だけでは伝えられる情報量に限りがあり、現場に正確な情報が行き届きにくいという課題を抱えていました。その結果安全面や品質面に影響が及び、実際に事故が発生する事例も見られました。
そこで動画マニュアル(tebiki現場教育)を導入し、全拠点の全従業員を対象に安全教育の教材として活用。細かい動作や業務上の危険をわかりやすく伝えられるようになり、従業員の安全品質意識の向上につながったといいます。
同社が活用した動画マニュアルについて詳しく知りたい方は、以下のリンクから別紙の資料をご覧ください。
>>同社が活用した動画マニュアル「tebiki現場教育」の機能詳細や事例をもっと見たい方はこちらをクリック!
株式会社フジトランスコーポレーション:教育で安全ルールを標準化
次にご紹介するのは、港湾運送事業や内航海運業、貨物利用運送事業、倉庫業など、さまざまな物流サービスを提供している株式会社フジトランスコーポレーションの事例です。
| 課題 | tebiki現場教育導入後の効果 |
|---|---|
| ・働き方改革推進のため、情報の共有や引き継ぎにかかる業務負荷を抑えたかった ・安全教育で動画を内製化するが作成に負担がかかっていた ・社内の各システムに対する問い合わせ対応に時間がかかっていた | ・tebikiによる動画化で教育工数が削減 ・パソコン操作に不慣れな社員でも教材が作れて安全教育の内容理解を標準化 ・tebikiへの誘導で問い合わせ対応工数を大幅に削減 |
同社では、安全教育を担当する講師によって伝え方のニュアンスが異なり、それによって受講者の受け取り方もばらつくという課題がありました。さらに動作や手順を口頭だけで正確に伝えることは難しく、従業員によって理解の差が生じやすい状況でした。
そこで同社が採用したのが動画マニュアル(tebiki現場教育)です。正しい内容を繰り返し視聴できる動画教育を導入したことで、講師側・受講者側の認識が一致するようになり、教育工数の削減に成功しました。また、tebikiは「誰でもかんたんに使える」ため、パソコンに不慣れな講師も負担なく教材を自作しているとのことです。
同社が活用した動画マニュアルについて詳しく知りたい方は、以下のリンクから別紙の資料をご覧ください。
>>同社が活用した動画マニュアル「tebiki現場教育」の機能詳細や事例をもっと見たい方はこちらをクリック!
まとめ
物流現場の安全教育は、従業員一人ひとりの意識と行動を変え、事故や災害といったトラブルの芽を摘む重要な取り組みです。紙のマニュアルや口頭説明だけでは伝えづらい細かな「動き」も、動画を活用した教育なら視覚的にわかりやすく、誰もが正しい手順や危険な行為を直感的に理解できるようになります。
物流・倉庫現場に特化した動画マニュアルツールなら、弊社が提供する「tebiki現場教育」がおすすめです。現場従業員が気軽にスマートフォンで撮影し、数分の編集でわかりやすい動画教材が完成するため、パソコンや動画編集が苦手な方でもかんたんに扱うことができます。現場の安全教育に「動画」を取り入れ、従業員の安全意識と安全行動を確実に定着させましょう。
引用元/参照元
・労働災害分析データ 倉庫業(PDF)|中央労働災害防止協会
・フォークリフトに起因する労働災害の発生状況(PDF)|日本産業車両協会
・労働災害発生状況|陸上貨物運送事業労働災害防止協会