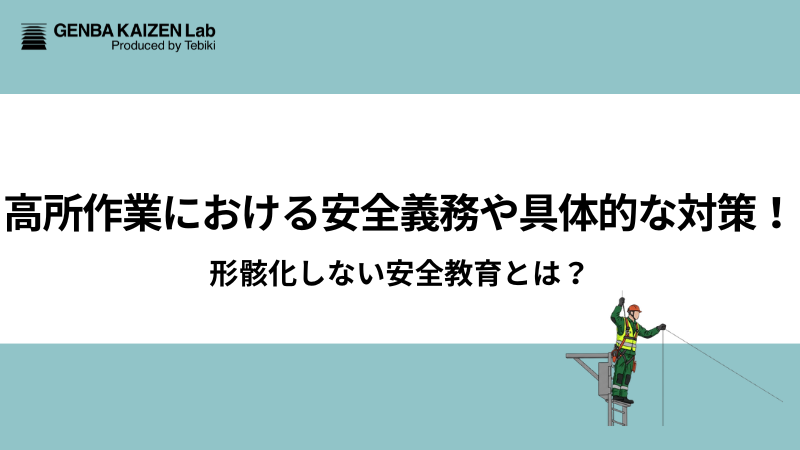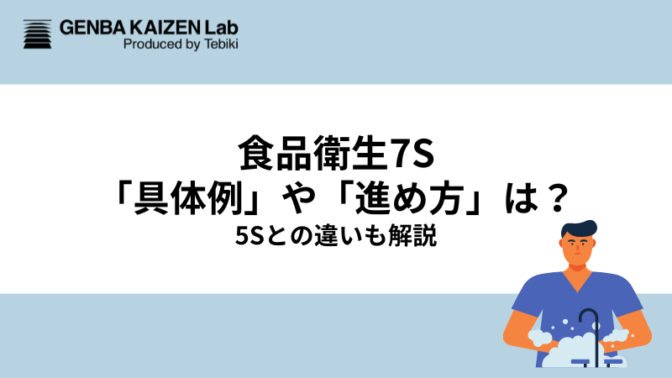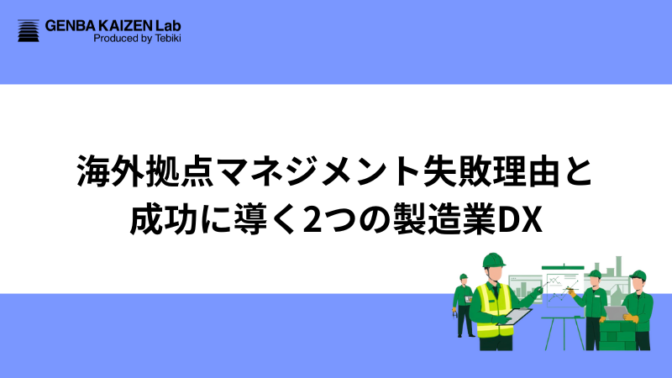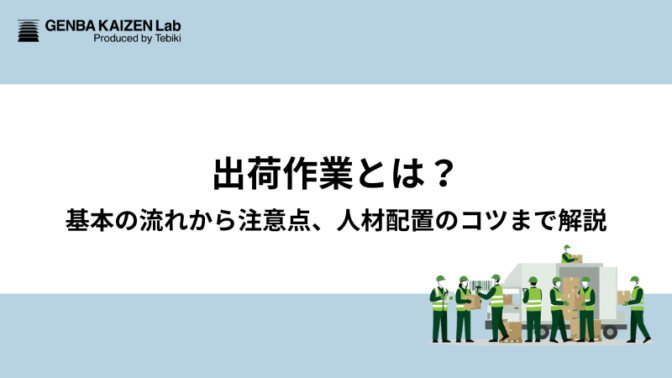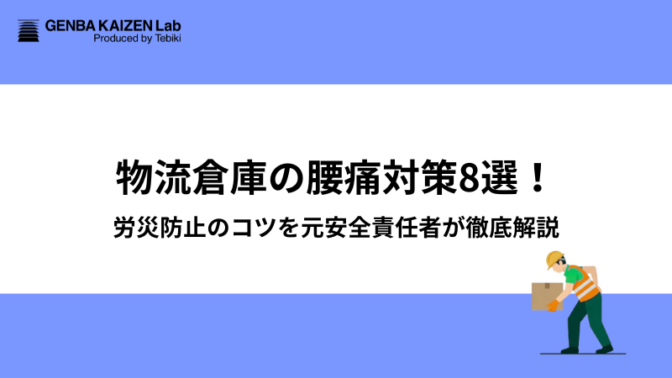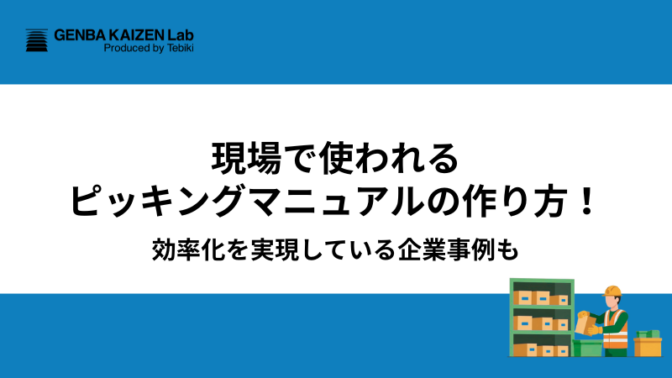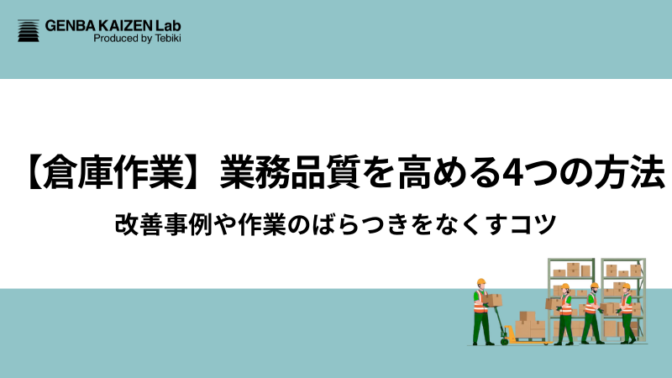安全教育に役立つかんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
高所作業とは、「高さ2メートル以上」で行う作業を指します。たとえ「少しの高さ」と感じても墜落によるリスクは非常に高く、ひとたび事故が起きれば命に関わる事態になりかねません。本記事では高所作業の定義や法的な安全義務、事故が減らない理由やその対策について解説します。
高所作業での事故を防ぐには、従業員の安全意識を高める適切な安全教育の実施がポイントです。しかし、一方的な教育の実施に終わり形骸化してしまうケースをよく耳にします。
従業員の安全意識に働きかける安全教育の手法については、本記事のほか下記のリンクから無料ダウンロード可能な資料でも詳しく解説しているため、併せてご覧ください。
>>ゼロ災達成に向けた「従業員の安全意識を向上させる安全教育」の進め方・事例をみる(無料公開中)
目次
高所作業とは?定義や義務を解説
高所作業とは「高さ2メートル以上」で行う作業のこと
高所作業とは「高さ2メートル以上」の作業を指します。労働安全衛生規則(以下安衛則)519条では、作業者の足元からの垂直距離が高さ2m以上の箇所で行う作業を高所作業と定め、事業者に対して墜落防止のための措置を義務付けています。
作業床(足場)や手すり、囲いの設置が原則であり、設置が困難な場合は防網の設置や墜落制止用器具(安全帯)の使用などの代替措置が求められます。
▼労働安全衛生法による高所作業・高所作業時に求められる対策▼
第五百十九条 事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
高所作業の種類
主要な高所作業の種類と考えられる危険について、表形式でまとめました。
| 作業種類 | 概要 | 主な高さ目安 | 主な危険・注意点 |
|---|---|---|---|
| はしご・脚立作業 | はしごや脚立に乗って行う点検・簡易作業 | 約2m〜5m | ・立ち位置の不安定 ・踏み外し ・三点保持の不徹底、滑り |
| 足場・作業床上作業 | 枠組足場や作業床上での組立・施工・点検 | 約2m以上 | ・足場の組立不備 ・手すり欠損 ・部材落下 |
| 機械・ロープによる作業 | 高所作業車やゴンドラ、ロープで保持しての点検・補修 | 約2m以上 | ・操作ミス ・機械故障 ・ワイヤーやアンカー摩耗 ・気象変化 |
上の表が示すように、高所作業には多様な形態があり、それぞれに特有の危険が伴います。
しかし、どのような作業であっても共通しているのは、「墜落・転落」という最も重大なリスクをいかに防ぐかという点です。そのため、作業の種類に関わらず基本的な安全原則を徹底することが事故を未然防止するカギだといえます。
安全ルールを徹底させる安全教育の秘訣について知りたい方は、以下のリンクから別紙のガイドブック(無料)をご覧ください。
>>安全ルールの徹底は「安全意識の向上」から!ゼロ災達成に向けた安全教育の手法・事例をみる(無料公開中)
高所作業に伴う安全義務
事業者は、高所作業における墜落等の危険を防止する義務があります。作業床や手すりの設置が求められ、設置が困難な場合は防網や要求性能を満たす墜落制止用器具の使用といった代替措置を講じなければなりません。
加えて、器具や取付け設備の定期点検・記録管理、特別教育や作業計画に基づくリスクアセスメントの実施、悪天候時の作業中止判断など、教育と管理の両面で安全体制を維持する責務があります。
主な安全義務については、以下の通りです。また、特別教育を社内で実施するうえでのポイントや進め方についてまとめた資料もご用意しておりますので、本記事と併せてご活用ください。
>>元労基署長監修!社内実施による本質的な特別教育の進め方をみる(無料・修了証フォーマット付き)
墜落制止用器具の使用義務(安衛則第520条・521条)
墜落制止用器具の適切な使用は、事業者と労働者双方に課せられた重要な義務です。
事業者は安全な器具と作業設備を準備し、労働者はその指示に従って正しく使用しなければなりません。さらに、両者が協力して日々の点検と管理を徹底することが安全の基本となります。
ロープ高所作業に関する規制と教育義務(安衛則第539条の2)
作業床が設置できない箇所でのロープ作業は、ライフライン設置や作業計画、特別教育が義務付けられています。事前の計画と教育が不十分だと重大災害につながるため、法令に沿った措置と教育実施が必要です。
フルハーネスの着用義務
高さ6.75m以上の作業床や手すりがない場所では、フルハーネス型の墜落制止用器具の使用が義務付けられています。また、建設業では5m以上、柱上作業では2m以上の作業においても、安全のためフルハーネス型の着用が強く推奨されます。使用する器具は、必ず安全規格に適合したものを選定してください。
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育(安衛法第36条の41)
フルハーネス型を用いて行う作業に従事する労働者に対し、事業者は特別教育(学科および実技)を実施する義務があります。教育の修了記録は、適切に保管してください。
18歳未満への就業制限
年少者(18歳未満)には高リスク業務への就業制限が設けられています。高所作業は危険有害業務に指定されており、18歳未満の者を従事させることは法律で禁止されています。事業者は年齢確認を徹底し、年少者を高所作業に就かせてはなりません。
高所作業で発生しやすい事故とその特徴
墜落・転落の主な事例とリスク要因
高所からの墜落・転落は死亡災害に直結する最も危険性の高い事故であり、特にはしごや脚立、足場からの事故が後を絶ちません。これらの事故は単一の原因ではなく、複数のリスク要因が連鎖して発生するケースがほとんどです。考えられるリスク例は以下の表のとおりです。
| 設備・環境的要因 | ・はしごや脚立の不適切な設置/使用 ・足場の組立不良や手すり等の保護設備の不備 ・安全器具の点検不足 ・経年劣化 ・強風や雨天など悪天候による作業環境の悪化 |
| 人的要因 | ・三点支持など安全の基本動作の不徹底 ・慣れや油断による危険行動や操作ミス ・疲労・体調不良による注意力の低下 |
| 管理的要因 | ・リスクアセスメントやKY活動の形骸化 ・安全教育/指導の不足や不統一 ・不十分な作業計画と無理な工期 |
これらの要因を洗い出し、多角的な視点から対策を講じることが不可欠です。対策として、安全な足場の設置や設備の点検、フルハーネスの適切な使用といった基本的な安全策の徹底が考えられます。
さらに、実効性のあるリスクアセスメントと継続的な安全教育を組み合わせ、ハード・ソフト・管理体制の三位一体で災害防止に取り組むことが重要です。
リスクアセスメントの進め方や再発防止策の立て方については、以下のリンクをクリックし元労基署長による解説動画をご覧ください。
>>現場のキケンを見極める『リスクアセスメント術』の進め方をみる(無料公開中)
道具・資材の落下による二次災害リスク
高所から工具や資材が落下する事故は、地上の作業員や通行人など第三者を巻き込む重大な二次災害を引き起こします。一度の不注意が、取り返しのつかない事態を招く危険性をはらんでいます。考えられるリスク例は以下の表のとおりです。
| 設備・環境的要因 | ・工具の落下防止措置の不備 ・資材の不安定な仮置きや過積載 ・足場の整理整頓不良 ・つま先板や防網の未設置や破損 |
| 人的要因 | ・道具や資材の不注意な操作 ・作業中の不意な接触や足払い ・工具の不適切な携行や収納 ・焦りや疲労による注意散漫/手順省略 |
| 管理的要因 | ・作業計画や手順の不備 ・悪天候時の中止基準の不徹底 ・安全教育やKY活動の不足 ・立入禁止措置や監視体制の不備 |
高所からの物体落下は作業者のヒューマンエラーだけでなく、使用する道具や作業環境、管理体制など、様々な要因が複合的に絡み合って発生します。対策としては、工具の確実な係留や落下防止ネットの設置、落下危険区域の立入制限を徹底するとともに、資材の固定方法を標準化して作業手順に組み込むことが重要です。
さらに、作業前の周知と地上側の通行管理、定期的な点検・記録によって再発を防止し、被害を最小化する運用が求められます。
一方で、「作業手順書はあるが読まれていない…」「安全ルールが遵守されない…」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。現場改善ラボでは、作業ルールを守らせる効果的な方法についてまとめたガイドブックもご用意しておりますので、併せてご覧ください。
>>“手順書通りにできない”から卒業!作業ルールを守らせる効果的な方法とは?(無料公開中)
高所作業での事故はなぜ繰り返される? 現場に潜む5つの「穴」
高所作業の事故は、決して単一のミスで起きるわけではありません。「これくらい大丈夫だろう」という小さな油断、見過ごされた機材の傷、共有されなかったヒヤリハットなど、複数の「穴」が不運にもつながったときに、墜落という最悪の事態を招きます。
毎年30人近くの作業員が、はしごや足場から命を落としている背景には、単なる個人の不注意では片付けられない構造的な5つの原因が潜んでいます。ここではそれらの原因を掘り下げ、具体的な対策へとつなげていきましょう。
「まだ使える」が命取りに。保護具・機材の管理不備
「このハーネスは少し擦り切れているがまだ使える」「点検記録は昨日も書いたから大丈夫だろう」といった慣れと自己判断が、いざという時に命綱の効果を失わせます。例えば、使用期限切れのランヤードや規格外のカラビナなどは、墜落の衝撃に耐えられません。本来ならば自分を守ってくれるはずの保護具が、最も危険な裏切り者へと変わってしまうのです。
このような事態を防ぐには、「自分は大丈夫」という思い込みを捨て、始業前点検をルールとして徹底することが有効です。少しでも異常を感じた保護具や機材は、勇気をもって使用中止する文化を根付かせることが重要だといえるでしょう。
「慣れ」と「疲れ」が生むヒューマンエラーや一瞬の油断
事故は作業に不慣れな新人だけでなく、手順を熟知したはずのベテランでも多く発生するといえます。毎日繰り返す作業だからこそ、「フックをかける」「足場を確認する」といった基本動作を無意識に省略してしまうのです。加えて、工期のプレッシャーや寝不足による疲労の蓄積は確実に判断力と集中力を奪い、普段ならしないはずの見落としを誘発します。
対策として、毎日行う作業だからこそ指差呼称で「フックよし!」などと安全動作を声に出して確認することが挙げられます。また、体調不良や寝不足を感じた際は正直に申告し無理せず作業を交替できるチーム体制を整えることが、事故防止の鍵となります。
「さっきまで大丈夫だった」が通用しない環境・気象条件の急変
高所の現場は、地上とは全くの別世界だと考えるべきです。例として、さっきまで晴れていたのに急な豪雨で足場が滑りやすくなったり、ビル風が突然吹き荒れて資材が煽られることが考えられます。また、夏の炎天下では汗でグリップが効かなくなり、鉄骨は火傷するほど熱くなります。こうした環境の急変は予測が難しく、いつも通りの手順だけでは対応しきれない危険をもたらすのです。
環境や気象条件の変化をコントロールすることは難しいですが、風速や雨量など作業を中断・中止する明確な基準をチーム全員で共有し、厳格に守ることで対策が可能です。天候が怪しいと感じた際は、個人の判断で作業を続行せず、必ず職長や責任者に報告・相談することを徹底するとよいでしょう。
現場と乖離したルールや組織的・管理的要因
朝礼では「安全第一」と唱和するのに、現場では「工期に間に合わせろ」という無言の圧力がかかるような現場では、安全ルールの徹底は難しいといえます。会社が作った立派な安全マニュアルも、現場の実態とかけ離れていれば「絵に描いた餅」になってしまいます。
安全担当者が名ばかりだったり、危険な状態を報告しても真剣に取り合ってもらえなかったりすれば、「ルールを守っても意味がない」という諦めが現場に広がり、安全意識を蝕んでいきます。
そのため、「安全が最優先」という方針を経営層や管理者が率先して行動で示すことが重要です。安全対策にかかる時間やコストを工期に織り込み、ルールを守った結果として作業が遅れても現場を責めない、という明確な約束をすることで、現場の作業員は初めて安心して安全ルールと向き合えるようになります。
「知らなかった」では済まされない情報の断絶
「昨日、あそこの手すりが少しぐらついて危なかった」「今日から手順が一部変更になった」といった生きた情報は、関係者全員に伝わらなければ事故を防げません。特に、足場、鉄骨、電気など複数の業者が入り乱れる現場では、業者間の連携不足が致命傷になりかねません。自分の仕事の都合だけを優先し、後の工程の作業員への危険を伝えない。そのコミュニケーション不足が、誰かの一生を台無しにする事故の引き金となるのです。
対策として、朝礼やTBM(ツールボックスミーティング)の場で、他業種の作業内容や危険箇所などを具体的に共有する時間を設けるとよいでしょう。特にヒヤリハットの事例は決して隠さず、「明日は我が身」として全員の教訓にする文化を育てることで、個々の作業員が持つ「危険へのアンテナ」の感度をチーム全体で高めることができます。
高所作業での事故を防ぐには?要因別でみる7つの対策
高所作業における墜落・転落事故は単一の原因ではなく、設備・環境・人・管理体制といった複数の要因が複雑に絡み合って発生します。そのため、事故を本質的に防ぐにはこれら複数の側面から多角的に対策を講じることが不可欠です。
本章では、事故防止策を「設備・環境」「人的」「管理的」の3つの要因に分類し、具体的な実践方法を解説します。
設備・環境的要因への対策
墜落事故において保護具や設備の不備は最後の命綱が機能しないことを意味し、軽微なスリップが死亡災害に直結するため、物理的な安全環境の確保は絶対的な基礎となります。そのため、以下のような対策を行うと良いでしょう。
- 安全規格に適合したフルハーネス型墜落制止用器具などを適切に選定する
- 「日次の使用前点検」「週次の詳細点検」をチェックリストを用いて義務付ける
- 損傷や使用期限が超過した器具はタグ表示などで識別可能にし、速やかに交換するフローを確立する
こうした取り組みは、万が一ヒューマンエラーが起きても設備が確実に作業員を保護するという安全の最低ラインを担保し、作業員が機材を信頼して作業に集中できるという効果が期待できます。
ヒューマンエラーを根絶することは難しいですが、上記のような対策や仕組化で限りなくゼロに近づけることが可能です。ヒューマンエラーによる労災を防ぐうえで欠かせない「エラーの検知と抑制」や具体的な対策について、以下のガイドブック内でも詳しく解説しているため是非ご覧ください。
>>ヒューマンエラーを未然防止するには?「エラーの検知と抑制」からみる実践的な対策をみる(無料公開中)
人的要因への対策
どれほど優れた設備やルールがあっても、それを使う「人」の慣れや油断、疲労といったヒューマンエラーが安全対策を無力化させる最大の要因です。そのため、以下のような対策を行うと良いでしょう。
- 過去の事故事例を動画や写真で共有し作業前のKY活動で具体的なリスクを確認することで、危険を「自分事」として認識させる
- 三点支持などの基本的な安全動作の習慣化を促す
- ルール化された休憩やセルフチェックを導入し、集中力低下の原因となる疲労を管理する
これらの対策によって、作業員の安全意識は「やらされ感」から「自らを守るための主体的な行動」へと変化し、危険を予測し自ら回避する能力が向上するため、予期せぬトラブルにも安全に対応できるという効果が見込めます。
従業員の安全意識を確実に高めるには、常日頃からの教育が非常に重要です。実践的で伝わりやすい安全教育の方法を知りたい方や、経験差に関わらず危険な作業を理解してもらい共通認識を持たせたいとお考えの方に向けた「安全教育のコツ」をまとめた資料もご用意しておりますので、本記事と併せご確認ください。
>>目指せゼロ災達成!従業員の安全意識を向上させる安全教育の方法・事例をみる(無料公開中)
管理的要因への対策
現場の個々の努力も、「工期優先」といった組織の風土や形骸化したルールの前では簡単に崩れてしまいます。安全をスローガンで終わらせず、組織として機能させる仕組みと文化を構築することが不可欠です。そのため、以下のような対策を行うと良いでしょう。
- 作業手順書(SOP)や作業許可証(PTW)で安全な手順を標準化し、強風時などの明確な作業中止基準を設ける
- 経営層が安全のための時間やコストを工期に織り込み、ルール遵守による遅れを責めない文化を醸成する
- 定期的な救助訓練の実施や、ヒヤリハット事例を共有して学ぶ改善サイクルを回す仕組みを構築する
これらの仕組みによって「安全を守ることが最も評価される」という心理的安全性が現場に生まれ、経営から現場までが一体となった、自律的かつ継続的に改善を続ける安全管理体制が構築され、重大災害のリスクを組織全体で本質的に低減させることができるのです。
ここで取り入れやすい対策として特におすすめしたいのが、ヒヤリハット事例の共有や報告の活性化です。ヒヤリハット報告は大きな予算や設備投資を必要とせず、現場に眠る「生きた危険情報」を掘り起こす最も効果的な手段だといえるでしょう。
ヒヤリハット報告を活性化させる報告書のフォーマットや、現場ですぐに使える事例集・対策集を入手されたい方は、以下のリンクをクリックし別紙の資料(無料)をご覧ください。
>>イラスト付きでわかりやすい!報告から教育まで行えるヒヤリハット事例・対策集をみる(無料公開中)
事故を防ぐ真の土台は「安全教育」にあり
これまで「設備・環境」「人的」「管理的」の3つの対策を解説しましたが、これら全ての土台となり、実効性を左右するのが「安全教育」です。どれほど優れたルールや設備を導入しても、それを使う個々の作業員が危険の本質と対策の重要性を心から理解していなければ安全対策は形骸化し、その効果は半減します。
ここでは、多くの現場が陥りがちな教育の課題を整理し、安全意識を「知っている」状態から「実践できる」状態へと引き上げるための、継続的な教育制度の設計と運用について解説します。
なぜ教育は形骸化するのか?「やりっぱなし」の教育が招く弊害
安全教育が現場に根付かない最大の理由は、教育が単発のイベントで終わってしまっている点にあります。これでは、せっかくの学びも時間と共に薄れてしまいます。具体的には、以下のような課題が障壁となっています。
- インプット偏重: 一方的な座学が中心で、実践的なスキルが身につかない
- 品質のばらつき: 指導者によって教え方や熱量が異なり、教育の質が安定しない
- 定着度の未測定: 理解度を確認する仕組みがなく、「分かったつもり」の作業員を放置してしまう。
- 反復性の欠如: 一度教えたきりで、知識や意識を維持するための継続的な働きかけがない
これらの課題を放置することは、現場の安全レベルの停滞を意味します。
安全教育の形骸化を避けるには「PDCAサイクル」の実践
教育の形骸化を防ぐには、PDCAサイクルに基づいた実践的な行動が求められます。特に安全意識を本質的に高めるにはその場限りの研修ではなく、継続的かつ体系的な教育の仕組み(制度)を設計することが不可欠です。
これは、学習の「計画(PLAN)」と「実行(DO)」のサイクルを明確に定義することから始まります。また、教育を「やりっぱなし」にしないためには学習効果を測定し、改善につなげる仕組みが欠かせません。これが学習における「評価(CHECK)」と「改善(ACT)」のサイクルです。
安全教育を進めるうえで取り入れたいPDCAサイクルの例について、以下の表にまとめました。
| PDCAサイクル | 目標 | 例 |
|---|---|---|
| PLAN:反復学習の計画 | 「やりっぱなし」を防ぎ、安全意識を継続的に向上させる学習計画を立てる | ・年次:関連法規や基本方針を学ぶ座学研修 ・四半期:事故事例や正しい器具装着法を学ぶ動画研修 ・月次:日常の危険箇所や基本動作を確認するチェックテスト |
| DO:多角的な学習の実行 | 多様な手法で「分かったつもり」を防ぎ、実践できるスキルとして定着させる | ・座学で「知識」を体系的にインプットする ・動画で危険を「イメージ」させ、自分事として捉えさせる ・実技訓練で保護具の装着などを「スキル」として体得させる |
| CHECK:習熟度の定量的評価 | 教育効果をデータで測定し、個々の習熟度を客観的に把握する | ・定期的な習熟度テスト(筆記・実技)を実施し、明確な合格基準を設定する ・個人の学習履歴をデータとして記録/管理する |
| ACT:評価結果に基づく改善措置 | 評価結果から課題を改善し、個人と仕組みの両面から全体の安全レベルを引き上げる | ・テストの不合格者に対して再教育を実施する ・多くの人が間違える問題があれば、教材や指導方法そのものを見直し改善する |
これらの実践により、安全意識の向上や安全ルール遵守の意識が芽生えるでしょう。次章では、このPDCAサイクルを効果的にサポートする「動画」や、おすすめのツールについて解説します。
形骸化しない安全教育には「動画の活用」がおすすめ
安全教育を継続的な改善サイクル(PDCA)として回す重要性を解説しましたが、その実行(DO)と評価(CHECK)の質を大きく左右するのが教材の分かりやすさです。従来の座学や紙のマニュアルだけでは、「指導者による品質のばらつき」や「危険な作業のニュアンスが伝わりにくい」といった壁に突き当たりがちでした。
こうした課題を解決し、教育を形骸化させないための強力なツールが「動画」の活用です。動画は安全という重要なテーマを誰もが直感的に理解できる形で伝え、教育の質を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。
動画の活用による効果
安全教育に動画を取り入れることで、具体的に以下のような効果が期待できます。
| 教育品質の標準化 | 熟練者の動きを動画化することで指導者による質のばらつきをなくし、常に最高レベルの教育を全員に提供 |
| 直感的・視覚的な理解の促進 | 文章では伝えにくい複雑な動作や危険の感覚を、映像で直感的に理解させ、「分かったつもり」を防ぐ |
| 時間や場所を問わない繰り返し学習 | スマートフォンなどから時間や場所を問わず必要な時に何度でも繰り返し学習でき、知識の定着を促進 |
| 言語や経験に左右されない教育の実現 | 視覚的な情報は言語の壁を超えるため、外国人労働者や経験の浅い若手にも効果的に教育可能 |
実際に、現場で使われている動画サンプルをお見せします。
▼フォークリフトの禁止事項を解説する動画マニュアル▼
特に危険性の高い操作については、「禁止事項」をテーマにした動画で具体的に解説しています。例えば、フォークの先端だけでパレットを不適切に扱ったり、急発進や急カーブをしたりといった危険な行為を「悪い見本」として映像と文字で明確に示しています。
個の動画は現場作業員がスマートフォン一台で手軽に撮影できる動画作成ツール「tebiki」を活用し、リアルで分かりやすい安全教育を実現しています。
tebikiの活用事例や実際の動画サンプルをもっと見たい方は、以下のリンクから別紙の資料(無料)をご覧ください。
>>安全意識が高い製造現場はやっている! 動画を活用した安全教育・対策事例をもっとみる(無料公開中)
動画マニュアル「tebiki」なら安全教育のPDCAすべてにアプローチ可能!
動画の有効性を最大限に引き出し、安全教育のPDCAサイクル全体を効率化するツールとして、現場向け動画マニュアル作成ツール「tebiki」があります。「tebiki」を活用することで、これまで解説してきた教育制度をスムーズに実現できます。
tebikiは、スマートフォンで撮影した動画に字幕やナレーションを簡単に追加できるため、スマートフォンで撮影するだけで現場の担当者が特別な機材や編集スキルなしに、そのまま教育用マニュアルを作成できます。
さらに、tebikiに搭載された以下の機能を活用することで安全教育のPDCAサイクルをスムーズに進行可能です。
| タスク機能 | 複数の動画を組み合わせた学習コースを作成し、対象者ごとに割り当てが可能です。 |
| レポート・テスト機能 | 誰が視聴したかをレポートで把握し、内容を理解できたかをテストで測定できます。 |
| スキルマップ機能 | 個人やチームごとの学習進捗を可視化し、誰に何の教育が不足しているかを一目で把握できます。 |
| 自動翻訳機能 | 1つの動画から多言語の字幕を自動生成・音声読み上げが可能。言語の壁なく安全教育を徹底し、チーム全体の安全レベルを均一化します。 |
実際に、動画マニュアル「tebiki」を取り入れた現場では、以下のような教育効果が現れています。
| コスモ石油株式会社 | OJT依存による教育負担の増大という課題を、危険作業や事故事例を周知する動画で解決し、新人や協力会社も含めた教育の効率化と標準化を達成 |
| 株式会社メトロール | 指導者による教育の質のばらつきという課題を安全衛生に関する内容を動画マニュアル化することで解決し、全社的な教育の均一化と現場の安全意識向上を実現 |
| 株式会社ロジパルエクスプレス | 拠点ごとのマニュアルの違いによる安全品質のばらつきという課題を手順を統一した検索性の高い動画で解決し、全社的な品質の標準化と現場での活用を促進 |
>>動画マニュアル「tebiki」の活用事例をもっと見たい方はこちらをクリック!(無料公開中)
動画マニュアルtebikiの豊富な機能や安心のサポート体制について詳しく知りたい方は、以下の画像をクリックして別紙の資料をご覧ください。
まとめ:高所作業の安全は、動画を活用した継続的な「教育サイクル」で築かれる
高所作業の事故は、ルールや設備を整えるだけでは防げません。安全対策の形骸化を防ぐ鍵は、教育を単発のイベントで終わらせず、継続的な「PDCAサイクル」として実践し、現場の安全意識を本質的に高めることです。
この教育サイクルを最も効果的に回すツールが、品質のばらつきなく直感的な理解を促す「動画」の活用です。本記事で解説した要因別の対策と、動画を活用した教育サイクルを実践し、真に安全な職場環境を築き上げてください。
本記事でご紹介した動画マニュアルtebikiの機能詳細や活用事例について詳しく知りたい方は、以下の画像をクリックして別紙の資料をご覧ください。
参照元
・労働安全衛生法 第519条
・厚生労働省 ロープ高所作業を行う事業者の皆さまへ
・中小建設業特別教育協会 フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
・厚生労働省 高校生などを使用する作業者の皆さんへ
・滋賀労働局 はしご等による墜落に関する統計資料