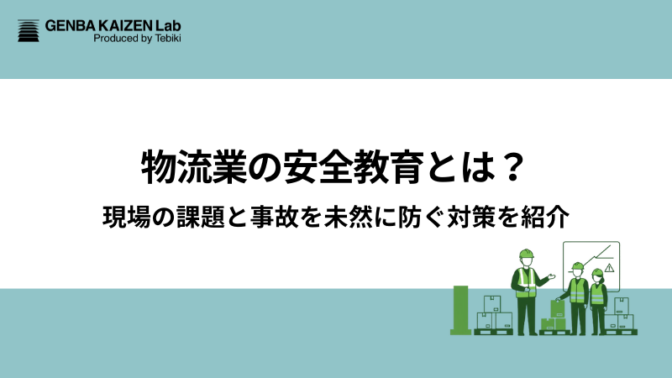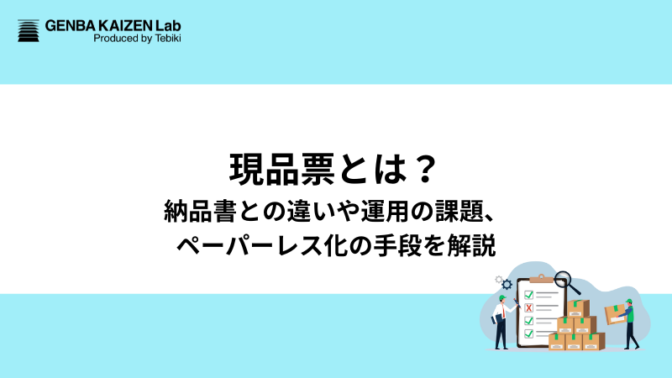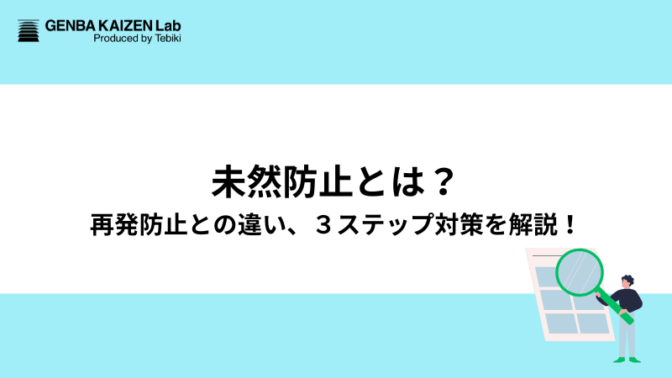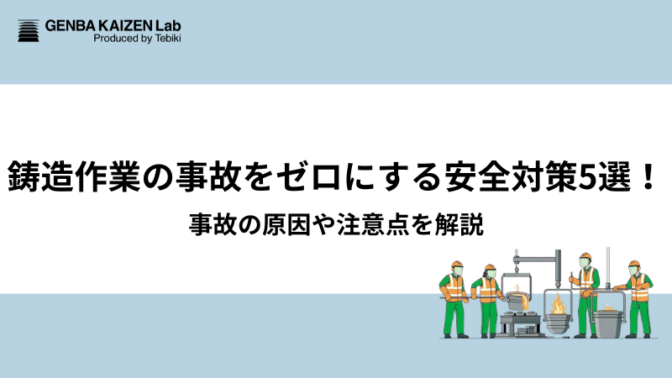かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を展開する現場改善ラボ編集部です。
新たに労働者を迎え入れる際、「雇入れ時安全衛生教育」は必須の教育です。これは法令で義務付けられているだけでなく、労働災害を防ぎ、職場の安全意識を高めるためにも欠かせません。しかし実施方法や対象範囲について正しく理解できていない方も多いはずです。
本記事では、教育の担当者・タイミング・教材選びや、事務職・派遣社員・外国人労働者への対応まで、実践に役立つポイントを詳しく解説します。
雇入れ時安全衛生教育は、雇用形態や職種、外国人労働者への対応など配慮すべき点が多く、現場の負担が大きくなりがちです。
教育の質を落とさず、動画を活用して効率的に実施・管理するための作成ツールについて、以下の資料で詳しく紹介します。
>>かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育サービス資料」を見てみる
目次
雇入れ時安全衛生教育とは?目的と法律での義務を解説
雇入れ時安全衛生教育とは、新たに採用した労働者に対し、安全かつ衛生的に働くための基本知識を教える教育です。労働安全衛生法に基づき、業種や雇用形態を問わず、全ての企業に義務付けられています。
経験のない新人労働者は、作業現場の危険性やリスクを十分に理解していないため、災害発生のリスクが高くなります。そうした労働災害を未然に防ぐためには雇入れ時にしっかりとした教育が必要です。法的義務として定められているだけでなく、企業が労働者の命と健康を守るうえでも不可欠な取り組みと言えるでしょう。
雇入れ時安全衛生教育の定義と労働安全衛生法における位置づけ
雇入れ時安全衛生教育は、労働安全衛生法第59条、および労働安全衛生規則第35条に基づく法的義務です。
(安全衛生教育)
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
(雇入れ時等の教育)
事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。
一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
六 整理、整頓とん及び清潔の保持に関すること。
七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
これらの法令により、労働者を新たに雇い入れた場合は業務の種類にかかわらず、必要な安全衛生に関する教育を実施しなければなりません。教育を怠った場合、企業は書類送検されるリスクもあり、実際に令和3年度には長野県内で47件の違反※1が指摘されました。また、違反すると労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金※2が科される可能性もあります。
参照元:厚生労働省「安全衛生教育を効果的に実施してください」※1
参照元:e-GOV「労働安全衛生法」※2
雇入れ時安全衛生教育の目的は、労働災害防止と安全衛生意識の醸成
雇入れ時安全衛生教育の主な目的は、労働災害の予防と安全衛生意識の醸成です。入社直後の労働者は、業務に伴う危険性や事故のリスクを十分に認識していないことが多く、災害が発生しやすい傾向にあります。そうしたリスクを減らすため、作業手順や危険箇所の説明、保護具の使用方法など、実務に即した教育が必要です。
また、安全への意識を高めることで、ヒューマンエラーの発生率も下げられます。職場全体の安全文化を根づかせる第一歩として、雇入れ時の教育は極めて重要な役割を果たしています。
2024年4月の労働安全衛生法で教育義務が拡大
2024年4月の労働安全衛生法改正により、雇入れ時の安全衛生教育に関する義務が強化されました。従来は一部業種において認められていた教育の省略が全業種で撤廃され、全ての労働者に対して教育の実施が求められるようになりました。
また、2023年には職長など現場指導者への安全衛生教育が必要な業種の範囲も拡大されています。これにより、企業はこれまで以上に体系的かつ実効性のある教育を実施する責任が求められます。
雇入れ時安全衛生教育は誰が・いつ・どのように行う?
雇入れ時安全衛生教育の具体的な実施方法をご紹介します。
雇入れ時安全衛生教育の担当者・対象者
雇入れ時安全衛生教育の実施義務は、労働安全衛生法により事業者に課せられています。ただし、実際の教育は職場の職長や安全衛生担当者が担うことも多く、民間の研修会社への委託や、最近ではe-ラーニングでの教育も可能です。
対象者は「新規雇用者」だけでなく、「作業内容が変更された労働者」や「これまで教育を受けていなかった労働者」も含まれます。常用・臨時・日雇いなどの雇用形態は問われず、すべての労働者が適切な教育を受けることが必要です。
雇入れ時安全衛生教育を実施するタイミング
雇入れ時安全衛生教育は、「業務に就く前」に必ず実施しなければなりません。教育を後回しにすることは、労働災害のリスクを高めるだけでなく、法令違反にもつながります。
教育の実施時期は極めて重要なので、新人が安全に作業を開始できるように現場に入る前のタイミングでしっかりと教育を行う必要があります。
雇入れ時安全衛生教育に必要な時間
雇入れ時安全衛生教育の実施時間に関しては、法律上で明確な時間数の定めはありません。重要なのは、労働者が実際に従事する業務や現場のリスクに応じた、必要十分な教育が行われることです。
単純作業であっても、高所作業や機械操作を含む場合は、それに応じた時間と内容で教育を設計しなければなりません。時間の長さよりも「教育の質」が問われるため、チェックリストや確認テストなどを活用し、理解度をしっかり把握することが重要です。
雇入れ時安全衛生教育に必要な教材
雇入れ時安全衛生教育の教材は、事業場の業務内容やリスクに応じて最適な内容を用意する必要があります。現場ごとにカリキュラムや資料を自作することが理想ですが、基本的な内容であれば公的なWebサイトからの流用です。
厚生労働省の「職場の安全サイト」では職種別・多言語対応の動画や資料も公開されています。また製造業であれば、「未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル」 も充実した内容です。
株式会社ロジパルエクスプレスでは、自社で動画教材を作成して、従業員への分かりやすい安全教育を実践しています。教材のテーマや内容によっては、動画で作成した教材を視聴するだけで安全意識を担保することができていると語っています。こうした取り組みは、理解促進だけでなく、教育の効率化や再教育にもつながる好事例です。
同社の事例を詳しく読んでみたい方は、以下のインタビュー記事もご覧ください。
>>「動画で全拠点の安全品質意識の向上と業務ノウハウの可視化を達成」を見てみる
雇入れ時安全衛生教育の8つの必須教育項目
労働安全衛生規則第35条では、以下の8項目の教育を行うことが求められています。
| 雇入れ時安全衛生教育8項目 労働安全衛生規則第35条より | 教育内容の具体例 |
|---|---|
| 1.機械等、原材料等の危険性⼜は有害性及びこれらの取り扱い方法に関すること | ・フォークリフトの爪の誤操作による挟まれ事故の危険性と取扱注意点 ・化学薬品(例:有機溶剤)の吸引による健康被害と保管方法 ・加工機械の可動部に巻き込まれるリスクと機械停止手順 |
| 2.安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取り扱い方法に関すること | ・非常停止ボタンの設置場所と操作手順防塵マスク ・防毒マスクの種類と装着方法の違い ・安全靴やヘルメットの正しい着用と定期点検の必要性 |
| 3.作業手順に関すること | ・高所作業時における安全帯装着の手順 ・機械の始業・終業時の安全確認フロー ・製品検査工程での標準作業の手順と注意点 |
| 4.作業開始時の点検に関すること | ・機械油の量や異常音など、運転前の始業点検リストの確認 ・工具や脚立などの備品チェックと破損確認方法 ・作業エリアの床面や通路の安全確認(滑り・障害物) |
| 5.当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及びその予防に関すること | ・長時間立ち作業による腰痛・脚のむくみの防止対策(ストレッチなど) ・パソコン作業による眼精疲労・肩こりへの対処法 ・化学物質取扱作業に伴う皮膚疾患やアレルギー予防の注意点 |
| 6.整理、整頓及び清潔の保持に関すること | ・使用済み工具の所定位置への返却ルール ・清掃時間の確保と共用部分の衛生維持(トイレ・休憩室など) ・廃材や空箱の分別・廃棄ルールの徹底 |
| 7.事故時等における応急措置及び退避に関すること | ・火災時の避難ルートと集合場所の確認訓練 ・切り傷・やけど等の軽傷に対する応急処置の方法 ・大地震発生時の初動対応と機械の停止手順 |
| 8.前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項 | ・特定化学物質の管理手順 ・感染症対策としてのマスク・手指消毒の徹底 ・高所作業におけるフルハーネス着用義務 |
1. 機械等、原材料等の危険性⼜は有害性及びこれらの取り扱い方法に関すること
業務に使用する機械や原材料には、火災、爆発、中毒などの危険・有害リスクが潜んでいます。雇入れ時には、それぞれの特性を理解し、安全に取り扱うための基本的な知識と注意点を教育する必要があります。リスクを正しく認識させることで、不注意による事故の未然防止につながります。
2. 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取り扱い方法に関すること
労働災害を防ぐためには、安全装置や有害物抑制装置、保護具の正しい使用が不可欠です。それぞれの機能や使用方法を具体的に教育し、異常が発生した場合の対応手順まで伝えることが求められます。
3. 作業手順に関すること
安全な作業遂行には、標準化された作業手順を正しく理解し、遵守することが欠かせません。雇入れ時には、業務ごとの手順やポイントを明確に説明し、なぜその手順が必要なのかまで理解させることが重要です。
なお、作業手順を説明する上で必要な作業手順書について、実際の現場で活用されずに形骸化する可能性もあるため、形骸化する理由を理解したうえで現場で使われるように工夫するのが大切です。
以下の資料では、作業手順書が形骸化する理由、現場で使われる作業手順書を作成するポイントなどをわかりやすく解説していますので、以下のリンクをクリックしてご覧ください。
>>「カンコツが伝わる! 『現場で使われる』作業手順書のポイント」を見てみる
4. 作業開始時の点検に関すること
作業開始前に機械や設備の異常がないか、点検を行う重要性と具体的な点検方法を教育します。点検の手順、チェックポイント、異常発見時の対応方法まで伝えましょう。
5. 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及びその予防に関すること
業務により腰痛やじん肺、熱中症などの健康リスクが発生する場合があります。これらの疾病リスクとその予防方法(例:適切な休憩、換気、保護具使用)について教育し、日常的な体調管理の意識づけを行うことが重要です。
6. 整理、整頓及び清潔の保持に関すること
職場の整理・整頓・清掃(5S活動)は、事故防止と快適な作業環境づくりに直結します。通路や作業場に物を置かない、機械周辺を常に清潔に保つなど、基本的なルールを教育し、日々の実践を促すことが大切です。5S活動について詳しく理解したい方は、こちらの記事か、5S活動の具体的な実践方法や5S活動を定着させて、生産性を上げる方法などを解説した専門家による動画をご覧ください。下のリンクをクリックすると動画をご覧頂けます。
7. 事故時等における応急措置及び退避に関すること
万が一事故や災害が発生した場合に、迅速かつ適切に行動できるかが被害を最小限に抑える鍵です。負傷者の応急手当方法や緊急避難経路、避難時の注意点を具体的に教育します。日頃からシミュレーションを重ね、緊急時に落ち着いて対応できる体制づくりが重要です。
8.前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全 又は衛生のために必要な事項
各職場特有のリスクや必要な安全衛生措置についても、個別に教育を行います。例えば、高所作業におけるフルハーネス着用義務や、特定化学物質の管理手順などが該当します。現場ごとの実態に即した内容を加えることで、より実効性のある教育が実現します。
事務職や派遣社員にも雇入れ時安全衛生教育は必要?
製造業の現場作業員に安全衛生教育が必要なのはもちろんですが、他の職種や派遣社員の場合はどうなのでしょうか?
事務職
事務職でも安全衛生教育は必要です。たとえば長時間のパソコン作業による腰痛や眼精疲労、災害時の避難行動など、リスクは少なくありません。2024年4月の労働安全衛生法改正により、省略は全業種で不可となり、事務職に対しても業務に応じた教育を確実に行う必要があります。
派遣労働者
派遣社員への雇入れ時安全衛生教育は、原則として派遣元の義務です。ただし、危険有害業務に従事させる場合には、派遣先に「特別教育」の実施義務があります。双方で教育がなされているか確認することが、労災防止の観点から重要です。
外国人労働者
外国人労働者にももちろん雇入れ時安全衛生教育が必要ですが、は言語や文化の違いから、安全教育の理解が難しいケースもあります。厚労省の「職場のあんぜんサイト」や「外国人労働者を雇用する事業部主のみなさまへ」では、多言語対応の教育資料が紹介されています。
また、外国人労働者を抱えている現場で発生しがちな教育課題を解消するポイントは、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。
関連記事:外国人労働者の教育課題はこう解決する!5つの指導ポイント
特別教育の必要性について
一定の危険を伴う業務には、安全衛生教育の内容を深めた「特別教育」が労働安全衛生法第59条第3項で義務付けられています。労働安全衛生法で定められた危険で有害な業務に従事する労働者に行う教育であり、41種類の業務で特別教育の実施が定められています。
41種類それぞれの特別教育によって、科目や時間が異なるため、規定については中央労働災害協会で公開されている「安全衛生特別教育規程」を事前にチェックしておきましょう。
なお、特別教育は、「外部機関で受講」「社内で教育実施」の2通りがあります。どちらが適しているのか詳しく知りたい方はこちらの記事か、元労基署長が監修した本質的な特別教育の進め方の資料をご覧ください。下の画像をクリックすると資料をご覧頂けます。
雇入れ時安全衛生教育の課題と効果的に行うポイント
雇入れ時安全衛生教育は、教育内容の形骸化や教育担当者の教え方に差が出てしまい、安全衛生への理解が不十分なまま、新人が現場に出てしまう恐れがあります。これを防ぐためには、教育の質と効率を両立させる工夫が必要です。
理解度が低いと労災につながる
雇入れ時安全衛生教育の理解度が低いまま作業を始めてしまうと、労働災害のリスクが大きく高まります。そのため、教育内容をただ説明するだけでなく、受講者がどこまで理解しているかを確認し、必要に応じて再説明や実地訓練を行うことが重要です。
理解度を向上させる取り組みとして、手順書やマニュアルの電子化(動画化)が活発化しています。実際に、トーヨーケム株式会社では、安全教育をはじめ属人化の解消や自律的な学習体制の構築に動画を活用し、労働災害の対策に向けた取り組む体制を構築しています。同社の事例を詳しく見てみたい方は以下のインタビュー記事をチェックしてみてください。
インタビュー記事:新人からベテランまで700名を超える組織教育のグローバルスタンダードを目指す
なお、同社以外にも様々な企業でマニュアルの動画化に取り組んでいます。その他の事例を見てみたい方は、動画マニュアルの活用事例をまとめて紹介している「活用事例集」をご覧ください。以下のリンクをクリックすると資料をチェックできます。
教育担当者の負担が大きい
安全衛生教育の実施内容は準備・説明・記録管理と多岐にわたり、現場の職長や総務担当の負担となりがちです。担当者の教育負担が増加してしまうと、本来の業務に手を付けられなくなってしまい、企業全体の生産性低下につながってしまうリスクも考えられます。
このようなリスクを防ぐためにも、教育負担を解消させるための工夫や取り組みが重要です。参考にしたい事例としては、ASKUL LOGIST株式会社があげられます。同社では、「映像を見て学べる」動画マニュアルを活用し、従業員の安全意識の向上や教育負担の軽減などを実現しています。
同社の事例を詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
>>「従業員数3,500名超・全国15拠点で動画マニュアルtebikiを活用!」を見てみる
効率的な雇入れ時安全衛生教育は「動画」の活用がおすすめ
雇入れ時安全衛生教育への動画の活用は以下のようなメリットがあります。
- 視覚・聴覚を使って直感的に理解できる
- 何度でも繰り返し視聴できるため定着率が高い
- 教育担当者の説明負担を軽減できる
動画を活用することによって、紙や口頭で説明するよりも視覚的に情報を得られ、安全に対する学びを深めることができます。また、動画であれば教育担当者からの説明も最小限で済むので、担当者の負担軽減にも繋がる点もポイントです。
実際に、ASKUL LOGIST株式会社やトーヨーケム株式会社などで安全教育に動画マニュアルが活用されていることからも、有効性の高さが伺えます。
かんたん動画マニュアル「tebiki」なら動画で効果的な安全衛生教育が可能
安全衛生教育に動画マニュアルを活用したい方には、動画マニュアルをかんたんにできる「tebiki現場教育」がおすすめです。tebiki現場教育には、現場の安全衛生教育を効果的に進められる様々な機能が搭載されています。
- 動画で統一された教育内容により属人化を排除
- 理解度に応じて繰り返し学習が可能
- 理解度テストや記録管理機能で教育効果を可視化
- 多言語対応で外国人労働者にも最適
- タブレット・PCからいつでも学習できる柔軟性
- 現場に即した実践的な内容で教育の定着率が高い
導入企業からは、「tebikiは単なる動画作成ソフトではなく“社員教育ツール”」という声もでるほど、現場教育に特化しており、安全意識を定着させる教育体制の整備が可能です。「tebiki現場教育」の機能や料金プランをより詳しく知りたい方は、以下のサービス資料もあわせてご覧ください。
>>かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育サービス資料」を見てみる
まとめ|雇入れ時安全衛生教育は“最低限”だけでは不十分。安全と定着の鍵に
雇入れ時安全衛生教育は法令遵守のためだけでなく、安全意識の定着や企業文化の浸透にも大きく関わります。形式的な説明に終始せず、現場での行動に繋がる内容こそが真の教育です。
その実現には、動画などを活用した省力化と質の両立が効果的です。まずはかんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」の無料トライアルを利用して、自社に合った教育手法を体験してみましょう。「tebiki現場教育」の機能や料金プランをより詳しく知りたい方は、以下をクリックして資料をご覧ください。