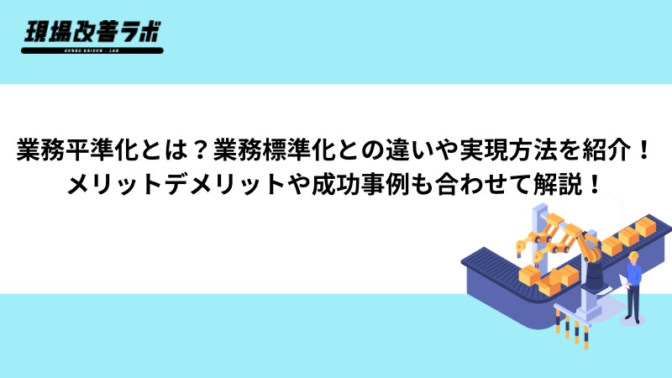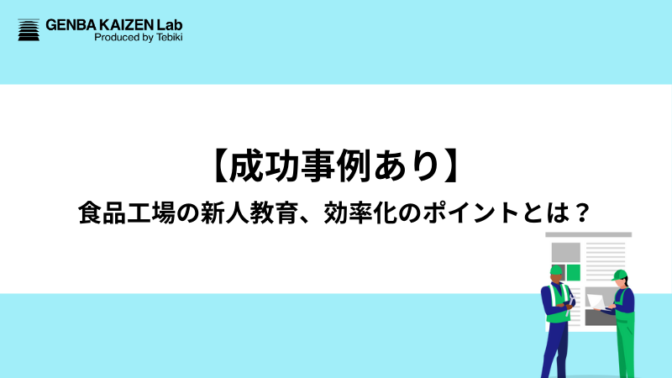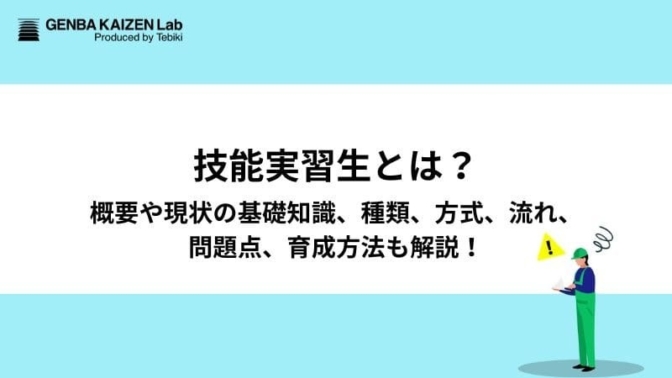かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」や、かんたんデジタル現場帳票「tebiki現場分析」を展開する現場改善ラボ編集部です。
ISO9001は、企業が自社のQMS(品質マネジメントシステム)を国際規格に則って構築・運用していることを証明する認証制度です。
本記事では、ISO9001認証取得の方法や費用、認証取得にかかる期間・費用・難易度について、ISO9001審査員補の山本 諭氏監修のもと解説します。
さらにISO9001運用にあたり、QMS構築に役立つツールも詳しく解説していきます。
▼監修者:株式会社エイシン・エスティー・ラボ 代表取締役 山本 諭

2004年化粧品容器の製造企業に入社。生産管理、品質管理の経験を経て、製造部門長に就く。100人の従業員をマネジメントする傍ら、独自の自動化で生産性を10倍に向上。生産管理システムの導入やISO9001の認証取得などにも積極的に取り組む。2020年(株)エイシン・エスティー・ラボを設立。ISOの認証取得支援や、財務改善、業務改善に加え、1on1による従業員のモチベーション向上支援に従事。
目次
ISO9001を取得するメリットは?取得数の推移や企業一覧
ISO9001は、品質管理の国際規格として広く認知され、多くの企業が導入しています。まず最初に、ISO9001の認証を取得するメリットや目的、取得企業数の推移、実際に認証を取得している企業の調べ方についてご紹介します。
『まずはISO9001に関する基礎知識を得たい』という方は、以下の関連記事をクリックしてご覧ください。
関連記事:【意味がない?】ISO9001とは?メリットや費用、やめた企業の理由
ISO9001を認証取得するメリットや目的
ISO9001の認証取得には、主に以下の3つのメリットがあります。
取引条件を満たし、ビジネスの機会を拡大
大手企業や公共事業の案件では、ISO9001の認証がないと取引自体が難しいケースがあります。
特に、自動車部品、電子機器、機械部品、食品などの製造業界では、製品の品質が直接的にビジネスの成果に影響するため、認証取得の有無が取引において重要視されます。
そのため、認証を取得すれば新規契約の機会を広げ、ビジネスの拡大に繋げることができます。
業務プロセスの改善
組織内の業務プロセスを国際規格の基準に合わせて見直すことで、品質不良といった不具合の発生を減少させ、コストの削減に繋がります。さらには、生産性向上も期待できます。
また、内部監査やマネジメントレビューを通じて、継続的な改善活動(PDCAサイクル)が実現しやすくなります。
国際競争力の向上
国際規格として認められたISO9001の認証を取得していることで、海外取引の際にも有利に働きます。グローバルなビジネス環境において、ISO9001は信頼性と確かな品質を証明する強力なツールとなります。
ISO9001を取得する企業数の推移
日本において、ISO9001の認証を取得している企業件数は、2007年をピークに減少傾向にあります。公益財団法人日本適合性認定協会(JAB)の認証組織検索で確認すると、2025年2月時点では22,294件にまで減少しており、全体として取得企業数が減少していることが確認できます。
この減少の主な要因の1つは、建設業界における取得件数の減少です。ISO9001の認証取得は、建設業において、公共事業の入札参加条件の1つとして求められてきました。しかし、近年では入札要件が緩和され、ISO9001の取得が必須ではなくなったことにより、多くの企業が更新を見送るケースが増えています。
またその他の業界でも、「文書作成や管理の手間が負担となっている」「審査費用などのコストが継続的にかかる」といった理由で、取得の見直しを検討する企業も少なくありません。しかし一方で、海外展開を進める企業や、取引先から認証取得を求められる企業にとっては、依然として重要な規格です。
特に製造業やサービス業では、安定した取得数が維持されています。また、近年ではデジタルツールを活用したQMS(品質マネジメントシステム)の効率的な運用が進んでおり、認証の取得や維持にかかる負担が以前より減っていると言えます。
ISO9001の取得にあたり課題となる、文書作成や管理の手間は「動画マニュアル」で効率化することも可能です。ISO9001の文書管理に動画マニュアルを活用する有効性は、別紙のガイドブックで詳しく解説していますので、以下のリンクをクリックしてご覧ください。
>>「ISO9001の文書管理に動画マニュアルを活用すべき理由」をPDF資料で見てみる
ISO9001を取得する企業例一覧と調べ方
日本適合性認定協会(JAB)の公式サイトでは、ISO9001の認証を取得している企業の一覧が公開されています。組織名や産業分類、都道府県などの条件で検索できるため、どの業種や企業が認証を取得しているのかを簡単に確認できます。
また、この情報は、新規取引先の選定にも役立ちます。例えば、品質管理体制が整った企業と取引したい場合や、競合他社の取得状況を把握したい場合にも有効な参考資料となります。
ここまでISO9001を取得する企業数など、実態について詳しく解説しました。次章では、実際に認証取得する場合の期間や費用、難易度を詳しくご紹介していきます。
ISO9001の認証取得にかかる期間や費用、難易度は?
ISO9001の認証取得は、企業の内部体制や取り組み状況により大きく異なります。ここでは、取得までの期間、費用、そして難易度について詳しく解説します。
ISO9001の認証取得にかかる期間
ISO9001の認証取得には、一般的に6か月〜1年程度が必要です。具体的なプロセスは以下の通りです。
- 現状分析(1~2か月)
- QMSの構築・運用(3~6か月)
- 内部監査とマネジメントレビュー(2~3か月)
- 外部審査と認証取得(2~3か月)
できるだけ早く認証を取得するためには、まず規格に適合していることを確実にすることが重要です。ISOの有効活用は取得後にじっくり取組むことも可能なため、初めから完璧を目指すよりも、審査での指摘事項を是正しながら改善していく方が取得期間の短縮に繋がります。
ISO9001の認証取得にかかる費用
ISO9001の認証取得には、QMSの構築費用と審査費用の大きく2つの費用がかかります。
ここでは、それぞれの費用について詳しく解説します。特に、QMS(品質マネジメントシステム)の構築費用については、「コンサルタントに依頼するパターン」と「自社で対応するパターン」の2つの方法を比較しながら説明します。
QMSの構築費用
1.コンサルタントに依頼するパターン
外部のコンサルティング会社を利用する場合、一般的に40万円〜80万円程度のコンサル費用がかかります。
専門的な知識や経験に基づいた効率的なアドバイスが受けられるメリットがありますが、自社で内製する場合と比べて費用は高くなります。
また、コンサルタントに依頼する場合でも、打ち合わせや情報提供などの社内対応は必要です。さらに、運用そのものは自社で行うため、「コンサルに丸投げできる」わけではないことを理解しておく必要があります。
2.自社で対応するパターン
ISO9001の専門知識を持った従業員が社内に在籍している場合、自社でQMS(品質マネジメントシステム)を構築することも可能です。
通常業務の合間に1日1時間程度の作業をしたと仮定すると、認証取得に必要な文書類を作成するのに約3か月程度が必要になります。1時間あたりの人件費を2,000円とした場合、約12万円の人件費がかかります。
| 作業時間と費用の試算:1日1時間×3か月(月20日稼働)=60時間×2,000円=12万円 ※現場の状況や作業効率により、変動はありますので、おおよその目安としてお考え下さい。 |
また、必須ではありませんが、内部監査員の養成のために外部の講習を受講する場合、3万円〜6万円程度の費用が追加で必要になることもあります。
これらを合わせると、完全に自社内で対応する場合は、およそ20万円前後の費用がかかることが想定されます。
審査費用
審査費用は、依頼する認証機関(審査を実施する外部機関)や、審査対象となる組織の規模(従業員数)によって異なります。一般的な目安として、以下の費用感となります。
- 従業員1~20名:40~70万円
- 従業員21~50名:75~95万円
- 従業員51~100名:100~120万円
また、ISO9001は認証取得後も定期的な審査が必要です。具体的には、1年に1回の維持審査と3年に1回の更新審査があります。それぞれの審査の費用感は、以下となります。
- 維持審査費用:新規審査の1/2程度
- 更新審査費用:新規審査の2/3程度
ISO9001認証の取得難易度
ISO9001認証取得の難易度は、以前に比べて大幅に下がっています。かつての審査では、形式的な基準に厳密に従うことが求められ、実務とかけ離れた指導を受けるケースもありました。
しかし、現在のISO9001では「実際に機能する品質マネジメントシステム」の構築が重視されており、会社の実情に合った仕組みを整えれば、小規模企業でも十分に認証取得は可能です。
今回ご紹介した取得期間や費用など、ISO9001ではさまざまな疑問を皆さんも感じるはずです。現場改善ラボでは、このようなISO9001でよくある質問を、Q&A形式で専門家が解説する動画を無料で公開中です。以下の画像をクリックして、解説動画もぜひご活用ください。
【手段別】ISO9001認証を取得する方法やポイント
ISO9001の認証を取得するには、社内でプロジェクトチームを結成し全社的に取り組むことが基本です。
ここでは、認証取得までの具体的な流れを、コンサルタントに依頼する場合と自社で内製する場合を比較しながら解説します。さらに、認証取得をスムーズに進めるためのコツについて詳しく説明します。
ISO9001認証を取得する流れ
ISO9001の認証を取得する場合、大きくは以下の流れで進めていきます。
それぞれのステップを詳しく解説しましょう。
1.ISO事務局の発足
まず、社内プロジェクトチーム(ISO事務局)を結成します。管理責任者の選任を行い、チーム全体で取り組む体制を整えます。自社で内製する場合は、ISOに関する知識や経験のあるメンバーを中心に選出する必要があります。
2.現状分析
現場の業務プロセスや管理体制の現状を分析し、ISO9001の要求事項とのギャップを明確にします。コンサルタントに依頼した場合は、ヒアリングに答える形で、現状分析が行われていきます。
ISO9001の要求事項は、以下の記事で詳しく解説しているので併せてご覧ください。
関連記事:【ISO9001】要求事項をわかりやすく解説!現場では何が必要?運用のコツとは
3.QMSの構築
品質方針や品質目標の設定、そして品質マニュアルや規定類、現場で使用する帳票類の作成を行います。
コンサルタントに依頼した場合、品質マニュアルや必要な規定類の作成をサポートしてもらえます。ただし、コンサルティング会社によって進め方が異なり、あらかじめ用意されたテンプレートを基に作成するケースもあれば、自社の業務運用に合わせてオリジナルのマニュアルを作成してくれるケースもあります。
そのため、コンサルティング会社を選ぶ際には、どのような方法で支援を行うのかを事前に確認することが重要です。品質目標の設定方法や品質マニュアルの作成方法、製造業の場合で必要になる帳票類については、参考情報として以下の記事をクリックしてご覧ください。
▼関連記事
・【ISO9001】品質目標の設定と達成計画の方法は?目標例も解説
・ISO9001に品質マニュアルは必要?手順や効率化方法も解説!
・【製造業】帳票の種類は?管理の手間を省くペーパーレス化や電子化を実現するツールを紹介
4.QMSの運用
QMSを構築するだけでは、ISO9001の認証を取得することはできません。作成した品質マニュアルや規定に基づき、実際の業務で運用し、PDCA(計画・実行・確認・改善)サイクルを回しながら継続的に改善していくことが必要です。
コンサルタントの支援を受ける場合でも、運用の主体はあくまで社内であり、自社の業務に根付いた形でQMSを定着させることが求められます。社内でQMSを定着させるための進め方やポイント、活用できるデジタルツールなどは、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:QMS(品質マネジメントシステム)を簡単解説!構築手順や内部監査の方法
5.内部監査とマネジメントレビューの実施
ISO9001の認証を取得するためには、内部監査とマネジメントレビューの実施が必須です。
これらは、QMSが適切に機能しているかを評価し、継続的な改善を推進するための重要なプロセスとなります。仮に、内部監査やマネジメントレビューを実施していない場合、重大な不適合と見なされ、審査を通過できない可能性があります。
コンサルタントに依頼した場合、内部監査員の教育や、会議の進行、資料作成の支援を受けられます。
内部監査やマネジメントレビューについては、以下の記事で詳しく解説しています。
▼関連記事
・【チェックリストあり】ISO9001内部監査とは?質問例や進め方などを徹底解説!
・【ISO9001】マネジメントレビューの要求事項とやり方、書き方などを解説
6.審査への対応と認証取得
内部体制が整った段階で、認証機関に対して審査の申請を行い、一次審査(文書審査)と二次審査(現地審査)に臨みます。審査の中で不適合が発見された場合は、是正処置を行うことで、認証取得の流れとなります。
なお、コンサルタントはオブザーバーとして審査に同席することは可能ですが、審査中に発言することは認められていません。そのため、コンサルタントに依頼した場合でも、審査時の対応はすべて社内メンバーで行う必要があります。
したがって、コンサルタントは事前に模擬審査を行い、想定される質問や対応方法を確認してくれることが多いです。
ISO9001の取得をスムーズに進めるコツ
認証取得を効率的に進めるためには、以下のポイントが重要です。
- 経営陣のコミットメント
- 明確な目的設定
- 社内教育や勉強会の充実
- デジタルツールの活用
経営陣のコミットメント
経営層自らがQMS構築の必要性を認識し、全社的な取り組みを推進することが成功の鍵です。経営層が積極的に支援することで、現場での取り組みもスムーズになります。
明確な目的設定
現場の抵抗感を減らし、納得して作業にあたってもらうことが大切です。
経営層は品質向上や顧客満足の向上を目的として導入を進めますが、現場の目線では、日々の業務に加えて、「手間が増える」「余計な仕事が増える」と捉えられがちです。そのため、ISO9001を導入する目的を明確にし、現場の業務にどう役立つのかを具体的に伝えることが重要です。
社内教育や勉強会の充実
すでに認証を取得している企業でも、実際の現場では、ISOの要求事項を従業員が十分に理解していない場合が多く見受けられます。その結果、QMSの運用が形骸化してしまっているケースは少なくありません。
こうした課題を解決するためには、事務局メンバーだけではなく、全従業員がISOの要求事項を深く理解するために、社内教育・勉強会を充実させる必要があります。
デジタルツールの活用
「動画マニュアル」や「デジタル現場帳票」などのデジタルツールを導入することで、業務の標準化や情報共有が大幅に効率化されます。デジタルツールは「文書化」の労力を削減する有力な手段となります。
次章ではISO9001、QMSの構築でこのようなデジタルツールがどのように有効か?詳しく解説します。「文書管理における動画マニュアルの有効性」は、以下のガイドブックで詳しく解説しているので、クリックしてご覧ください。
>>「ISO9001の文書管理に動画マニュアルを活用すべき理由」を見てみる
QMS(品質マネジメントシステム)の構築に有効な手段
従来のQMS構築では、紙ベースのマニュアルや帳票類を用いて情報共有を行うため、以下のような不便さや課題が多く存在していました。
| 情報の更新と共有の煩雑さ | 紙のマニュアルやExcelなどで記録を管理する場合、文書の改訂や更新に多大な手間がかかります。 また、最新版を全社員に周知するのも容易ではなく、現場で古い情報に基づいて作業してしまうリスクがあります。 |
| 現場での伝達のばらつき | 口頭指導、紙ベースの資料だけでは、作業の動きや細かいニュアンスを正確に伝えることが難しく、教育担当者ごとに説明内容が変わってしまうケースも少なくありません。 その結果、作業者の理解にばらつきが生じ、標準作業が徹底されにくくなります。 |
| 作業効率の低下 | 紙ベースの帳票管理の場合、書類の作成、配布、承認、集計といった業務プロセスが多く、管理者や担当者の手間が大きくなります。 これにより、実際の生産活動に割ける時間が減少し、現場全体の効率が低下することがあります。 |
これらの問題に対して、デジタルツールは大きな利便性をもたらします。さらに、こうしたデジタルツールの活用は、実際の審査の場面でも有効です。
審査員が、整備された情報を確認することで、現場での運用状況が正確かつ効率的に伝わるため、従来の紙の資料だけでは伝えにくかった実態や改善の成果をしっかりと把握できます。
これにより、審査での評価が高まり、ISO9001認証取得への道筋がより明確になるというメリットもあります。今回は代表的なツールとして「動画マニュアル」と「デジタル現場帳票」をご紹介します。
文書管理の効率化や業務標準化を推進する「動画マニュアル」
紙や文書ベースのマニュアルを活用する場合、管理や改訂などの工数がかかります。膨大なマニュアルや手順書を運用する現場の場合、この工数が大きな負担になります。
また、品質目標を達成するためには、作業の品質や生産性が担保された「標準作業」を、如何にして現場に落とし込めるかがカギを握ります。一方で、標準作業をOJTや座学のような口頭ベース、文書形式のマニュアルや手順書で共有しようとすると、以下のような課題が生じやすいです。
- トレーナーに教育工数がかかり、生産活動に割く時間が減ってしまう
- トレーナーによって言っている内容が異なり、作業者の混乱を招く
- マニュアルや手順書の作成/更新が追い付かず、標準作業の共有が進まない
- 文字や写真のような二次元的な情報では、三次元的な動きを伝えにくい
動画マニュアルで一度正しい内容で作成してしまえば、トレーナーに負担をかけずに「動き」を視覚的に伝えられます。また、業務内容に変更が出た場合は、該当箇所のみ差し替え・更新するだけで、現場全体に最新のマニュアルを共有することができます。
動画と聞くと『編集が難しそう…』と感じるかもしれませんが、誰でもかんたんに動画マニュアルを作成/活用できるツールがtebiki現場教育です。
動画マニュアルをかんたんに編集できる機能に加え、全プラン共通のアップロード本数無制限、スキルマップなどの人材スキル管理機能など、多くの機能を搭載しています。ISO9001取得や運用で有効な機能を抜粋すると以下の通りです。
- マニュアルの更新履歴を確認可能
- マニュアル公開時に多段承認を設定し、予期せぬ改訂/公開を予防
- 従業員の保有スキルなど要求事項に沿った力量管理が可能
- 教育計画の作成や教育訓練の記録が可能
より具体的なtebiki現場教育の機能やプラン、活用事例を詳しく知りたい方は、以下のリンクをクリックして概要資料をご覧ください。
>>ISO9001の運用に役立つ「tebiki現場教育」の概要を見てみる
現場で必要な帳票類の効率的な運用ができる「デジタル現場帳票」
現場帳票を運用する際、紙やExcelによって作成や記録、集計、分析を行うケースが多いです。しかし紙の帳票では以下のような付帯業務が生じ、現場の管理者に大きな負担が生じます。
- 現場帳票が日々膨大に発生し、管理者が1枚1枚目視で確認と承認をする手間がある
- 記入ミスを発見したら作業者に直接確認する手間が生じる
- 紙の現場帳票からExcelに集計/転記する手間がある
- Excelやマクロでデータ分析できる人が属人化する
このような記録はISO9001の取得/更新時や、QMSで要求されている品質目標の状況可視化などで必要になる一方、管理者に大きな負担を生じます。実際、ISO9001を認証取得する共栄工業株式会社では、紙の帳票運用によって1日2時間ほど管理者が集計業務を行う必要性があったとのことです。
同社ではこのような帳票運用をデジタル化したことで、1日の集計作業が約1分まで大幅に効率化することを実現しています。この業務改善を達成したツールが、かんたんデジタル現場帳票「tebiki現場分析」です。
紙ベースの帳票の場合、配布/記録/承認/集計/分析と多くの工数を必要としますが、tebiki現場分析であればスマートフォンやタブレットのような端末上で記録されたデータを、リアルタイムで管理者が確認/承認できます。
記録された定量的なデータは自動計算できるだけでなく、管理図やパレート図などグラフ機能があるため、確認段階で現場データを瞬時に可視化して分析を行うことが可能です。

詳細なtebiki現場分析の機能やプラン、活用事例は別紙の概要資料で詳しくご紹介しています。以下のリンクをクリックして、サービス概要資料をご覧ください。
>>ISO9001に基づいた効率的な業務フローを実現する「tebiki現場分析」の詳細を見てみる
まとめ
ISO9001の認証取得は、企業が品質向上に向けた取り組みを全社で推進し、信頼性の高い管理体制を構築するための大きな一歩です。
経営陣の積極的な支援と、内部監査・マネジメントレビューを含むPDCAサイクルの徹底が、認証取得の鍵となります。さらに、最新のデジタルツールを活用することで、現場の作業効率を飛躍的に高め、認証取得後も継続的な品質改善が実現できます。
各企業は自社の現状やリソースに応じた最適な方法を選択し、ISO9001の認証取得を通じて、顧客満足度の向上、ビジネスチャンスの拡大、そして持続可能な成長に繋げてください。今回ご紹介した「tebiki現場教育」と「tebiki現場分析」は、以下のフォームを入力いただくとサービス資料をご覧いただけます。
ぜひこの機会に参考情報としてご覧ください。