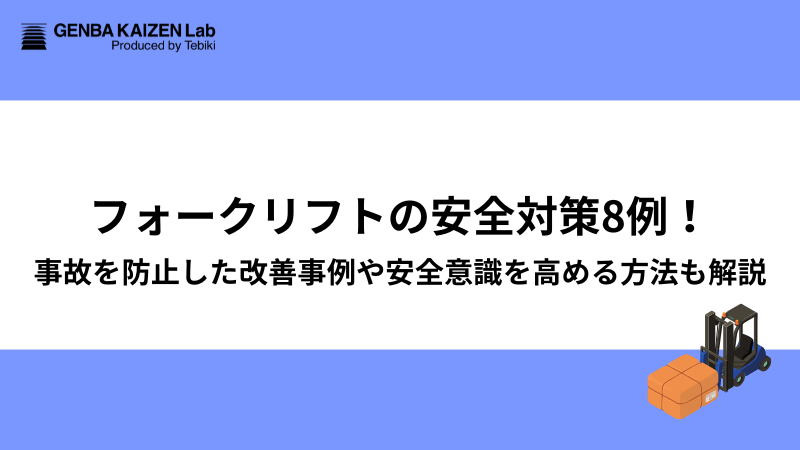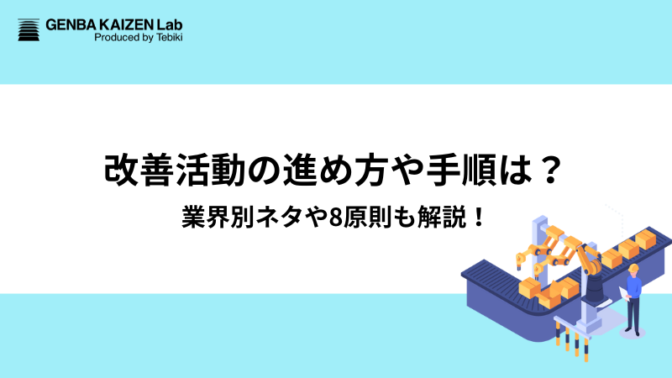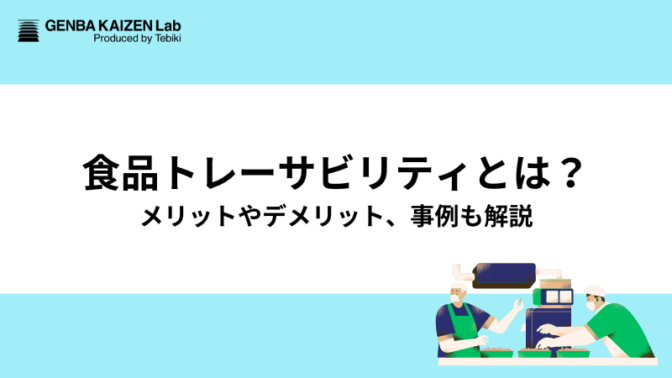かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
労働災害や重大事故の発生が後を絶たないフォークリフトは、多くの倉庫や物流現場で安全対策が求められています。そこで本記事では、フォークリフトの安全対策を8つ紹介するとともに、実際に安全対策を実施している物流企業の事例も解説します。
事故が起きてからでは取り返しがつかないので、本記事を通じて安全対策の具体的なアクションを起こしてみてください。
フォークリフトは一歩間違えると労災の温床になるため、安全教育や安全対策が必須ですが、そこで物流現場によく導入されているのが「動画マニュアル」です。「安全」や「危険」を視覚化し、安全を守るための作業/操作手順を見える化する動画マニュアルは、労災の未然防止に成功している多くの現場で導入されつつあります。
詳しくは、以下の「動画マニュアルを活用したフォークリフトの安全教育・対策事例」をご覧ください。新人作業員からベテラン社員まで、標準的に安全を守るため打ち手がまとめられています。
>>「労災ゼロを目指す!フォークリフトの安全教育・対策事例(PDF資料)」を見てみる
目次
フォークリフト事故の発生件数やよくある事故
「厚生労働省災害統計」によると、フォークリフトの事故発生件数は2023年が1,989件であり、前年2022年の2,092件と比べて減少しているものの、依然2,000件レベルで推移しています。直近10年以上にわたり同レベルで推移しており、年度によって多少の増減はあるものの全体的には減っていません。
フォークリフトの安全性の確保は、作業員の健康や命を守るのはもちろんのこと会社の信頼にも関わります。重大な事故が発生するのを防ぐべく、フォークリフトの安全意識を高める取り組みをおこなっていくのが重要です。
関連記事:フォークリフト事故・労災の実態:事例や発生件数・原因について
では、なぜフォークリフトに起因する事故が発生するのでしょうか。よくある事故には、以下のようなケースがあります。
転落・墜落事故
フォークリフトごとプラットホームから転落したり、駐車して降りる際に足元を踏み外して転落したりといった事故が発生しています。運転操作ミスが主な原因であり、安全意識の希薄さに加え、技量不足や体調不良などが複合的に関与している可能性があるでしょう。
また、フォークリフトの爪に人を乗せて作業し、墜落する事故も発生しています。フォークリフトは人を乗せる機械ではありませんが、パレットに人を乗せて作業するケースが存在します。フォークリフトの爪で持ち上げたパレットや台の上で人を昇降させる行為は労働安全衛生規則で禁止されており、遵守しなければなりません。
巻き込み事故
フォークリフトの運転中に、他の作業者を巻き込む事故が発生しています。目の前の荷物に意識がいくばかりに、死角に入った作業者に気づかず重大な事故が発生するケースがあるのです。
人を巻き込む、挟むといった事故はフォークリフトの死亡事故における大きな要因であり、十分な安全対策のもと作業に従事しなければなりません。
横転事故
作業中にフォークリフトが横転し、作業員が放り出される事故も発生しています。スピードを出した状態で急に方向転換したときや、荷物を高く持ち上げた状態で坂道を走行する際に起こり得るので注意が必要です。
放り出されると最悪の場合死亡事故になるケースもあり、十分な安全対策のもとで作業しなければなりません。
衝突事故
走行中のフォークリフトが、他の作業員に衝突する事故にも注意する必要があります。フォークリフト衝突事故の主な原因は以下のとおりです。
- 決められた安全対策やルールを遵守していない
- 作業エリアの明確化不足
- 作業者間のコミュニケーション不足
- フォークリフトの整備不良
このように、倉庫や物流現場では事故の危険源が多く潜んでいます。労働災害の引き金となるため、適切な対策を講じることが大切です。
関連記事:【事例あり】労働災害対策8選!職場で効果的な「安全意識向上の取り組み」とは
フォークリフト事故を引き起こす3つの原因
フォークリフトによる事故は、人的要因、機械的要因、環境的要因のいずれか、または複数が複合的に絡み合って発生します。
それぞれ詳しく解説します。
人的要因による事故
フォークリフト事故の主な原因の1つに「人的要因」が挙げられます。人的要因として挙げられる具体的原因は以下のとおりです。
安全操作・安全作業手順の不統一
現場での安全操作・安全作業手順の不統一によって、人為的な事故が起こる場合があります。作業する場所の広さや地形、フォークリフトの種類・能力に合わせて作業範囲やパレットの積み方などの安全作業手順を定めておくのが重要です。
定めた安全作業手順を全員が守り、フォークリフトを安全に操作する意識を高めた状態で作業に取り掛かる必要があります。
安全作業のようなルールが守られるようになる、手順書の活用方法やポイントは以下の資料で詳しく解説しているので、リンクをクリックしてご覧ください。
>>「“手順書通りにできない”から卒業!作業ルールを守らせる効果的な方法」を見てみる
運転者の不注意や誤操作
ハンドルやレバー操作のミス、アクセル・ブレーキの踏み間違い、前方不注意といったヒューマンエラーによってフォークリフトの事故が発生するケースがあります。
正しい運転技術を身につけてから作業に従事するのはもちろん、不注意や誤操作によるミスを防ぐ意識を高める活動や訓練も大切です。
関連記事:ヒューマンエラー対策13選!原因や製造業の対策例【種類や多い人、有名事故、トヨタの考え方】
安全確認の怠り(指差呼称の不徹底など)
指差呼称が徹底されておらず、事故が発生する場合があります。フォークリフトの現場講習で習う指差呼称ですが、実際の現場では疎かになっている事例も少なくありません。
フォークリフトに乗り込む前の前後左右の確認やシートベルトの着用などの安全対策を徹底し、巻き込み事故や転倒事故を減らしていきましょう。
機械的要因による事故
フォークリフト事故の主な原因の2つ目は「機械的要因」です。以下のような要因が挙げられます。
ブレーキの故障
フォークリフトのブレーキが故障し、重大事故が発生するケースがあります。ブレーキを踏み込んだ際に通常時と感覚が異なる場合には、早めに対処しておくのが大切です。
ブレーキが効かず停止できなくなると、人やフォークリフト同士の衝突事故が起こる恐れがあり注意しなければなりません。
フォークリフトの整備不良
フォークリフトの整備不良による事故も発生しています。メンテナンスや整備を怠ったまま長く放置すると、突然の故障によって事故の原因になるケースがあり注意が必要です。
異音がしたり、悪臭を放ったりといった普段と異なる点に気づいた際には早めに保守点検をおこないましょう。
ちなみにフォークリフトには、労働安全衛生規則に基づく定期自主検査(年次点検、月次点検)が義務付けられています。点検義務が遵守できているかどうかの見直しも重要です。
タイヤの摩耗
フォークリフトのノーパンクタイヤは一般的な車両のタイヤと比べて長持ちするのが特徴です。溝がすり減っても走行できるものの、タイヤの厚みが減ると車体への衝撃を吸収できず、結果各部に悪影響を及ぼす場合があります。
しっかり停止できなくなるばかりではなく、突然の不具合で正常に操作できず重大な事故につながる恐れもあり注意が必要です。
フォークリフトのタイヤには、一般的な車のタイヤと同様に摩耗限度を示すスリップサインを設けています。日頃からスリップサインを確認し、事故を未然に防ぐ意識を高めておくのが大切です。
日頃の点検で防げる事故も、確認漏れや判断ミスなどの「ヒューマンエラー」があれば発生してしまいます。
そのヒューマンエラーによる労災を未然に防ぐための、効果的な安全教育の進め方を以下の資料で解説します。
>>ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育を見てみる
環境的要因による事故
フォークリフト事故の主な原因3つ目は「環境的要因」です。以下のような要因が挙げられます。
作業場の整理・整頓(2S)不足
フォークリフトの事故を減らすには、作業場の整理・整頓(2S)も不可欠です。
作業場が整理されていないと、安全に走行できるスペースを確保できません。整理整頓されていない狭い場所では、壁とフォークリフトで持ち上げた荷物の間に作業員が挟まれるといった危険性が高まります。
さらに、作業場の整理整頓不足に運転者の経験不足や技術不足が加わると、より危険な状態になるので注意しなければなりません。
関連記事:2S(整理・整頓)を現場に定着させるには?改善のコツや活動事例を解説
狭い道路や見通しの悪い作業動線
フォークリフトの通り道が狭く見通しが悪いと、視野が狭まり死角が増えてしまいます。
積み降ろした荷物の影から突然人が飛び出してきて衝突するといったケースもあり、見通しの良い作業動線を確保するのが重要です。
また、狭い道路や見通しの悪い場所ではフォークリフト同士が衝突する危険性も高まります。
不適切な荷物やパレットの積み方
荷物やパレットの積み方によっても、重大な事故が発生するケースがあります。
作業の効率化を重視するばかりに、一度に大量な荷物やパレットを運ぼうとするとバランスが崩れ危険です。崩れた荷物が作業員を直撃すると、取り返しのつかない重大な事故に発展する恐れがある点に留意しておきましょう。
フォークリフトの安全対策や安全意識を高める取り組み
フォークリフト事故は、人的要因、機械的要因、環境的要因が複合的に絡み合って発生することを解説しました。そこでここからは、これら3つの要因を踏まえ、効果的な安全対策と安全意識向上のための取り組みについて見ていきましょう。
安全のための取り組みには全部で8つのポイントがあります。参考にしてみてください。
これらの安全対策を現場に浸透させ、従業員一人ひとりの安全意識を高める上で、効果的な安全教育の実施は欠かせません。
近年、特に注目されているのが、危険な状況や正しい手順を視覚的に分かりやすく伝えられる「動画マニュアル」を活用した教育です。
実際に製造業や物流業の企業が、動画マニュアルを使ってどのように安全教育に取り組み、どのような成果を上げているのか。具体的な事例を以下の資料でご紹介します。
>>~製造業・物流業の事例から学ぶ~動画マニュアルを使った安全教育の取り組みと成果を見てみる
動画マニュアルによる安全対策
物流の安全対策や労働災害の未然防止策としておすすめなのが「動画マニュアル」です。
例えば物流企業の「株式会社近鉄コスモス」は、フォークリフトの危険作業例を動画におさめ、安全教育の体制を整備しています。
▼フォークリフト操作の禁止事項を解説する動画マニュアル▼
※「tebiki」で作成
労働災害リスクがある作業を、文字や画像だけの作業手順書で新人作業員に伝えるのは危険なので、動画で視覚的に安全理解を促せる体制づくりが浸透しつつあります。
紙の手順書やマニュアルでは、こうした危険な作業や言語化できず、結局OJT頼みの教育体制となり教育担当者やベテラン社員の負担が大きくなります。したがって、動画マニュアルのような「1人でもある程度安全意識を高められる仕組みづくり」が安全対策に有効です。
ちなみに上記動画は、物流作業に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」で作成されています。tebikiの詳細機能や活用事例については以下のリンクからご覧いただけるので、あわせてご覧ください。
>>>物流作業に特化した動画マニュアル「tebiki現場教育」の詳しい機能や導入事例を見てみる
安全作業の標準化・安全教育体制の整備
フォークリフトの事故を防ぐには、安全作業を標準化するのが重要です。安全作業の標準化の例として、以下の内容が挙げられます。
- 爪を出した状態で前進走行しない
- 作業場で決められた制限速度を守る
- 前進走行する際は必ずパレットを1枚持つ
- 持ち上げた荷物の下に入らない
- フォークリフトの乗車席以外に人を乗せない
- バック走行時の後方確認の徹底
- フォークリフトから離れる際は鍵を抜く
- 作業時は必ず安全靴とヘルメットを着用する
- 構内を通行する際は安全通路を歩行し、荷物の影から飛び出さない
こうした標準ルールを現場で定義し、周知させる活動が大事になります。
併せて、安全教育体制も整備しておくのも大切です。作業員への安全教育が不十分だと、事故が発生する危険性が高まります。具体的には、以下の点について体制を整えておきましょう。
- 事故事例を安全教育に活用する
- 定期的に再教育を継続的に実施する
- 教育動画やオンライン教材を活用する
- 失敗事例(ヒヤリハット)の学びから安全教育を強化する
詳しくは、フォークリフトの安全教育で実施すべき具体的な内容や、社内で安全教育を展開するための方法がまとめられた記事も参考にすることをおすすめします。
フォークリフト4原則の遵守
フォークリフトの事故を防ぐには、以下4つの原則を徹底して守らなければなりません。
①走行速度を10km以下に制限する
労働安全衛生規則151条の5によって、最高速度が10km以上のフォークリフトは適正な速度制限を定めることが義務付けられています。
安全を優先するためにも、速度制限を10km以下に定めましょう。特に、カウンターリフトは最高速度が20~35kmにも達する場合があり、現場全員が徹底して守る意識が必要です。
②バック走行を基本とする
フォークリフトは、荷物を持ち上げて走行する際に前方の見通しが悪くなりやすい構造になっています。視界を確保するためには、バック走行を基本とするよう定めましょう。
ただし、バック走行は後方に気を取られてしまうばかりに、荷物の滑落による事故も発生しています。特に急ハンドルによって荷崩れする恐れがあり、荷物の状態にも気を配るようにしましょう。
③停止表示や指差し呼称を徹底して守る
フォークリフトの安全対策では、建物の出入り口や曲がり角など見通しの悪い場所には看板や標識を設置し、徹底して表示を守るのが有効な方法の1つです。
特に、危険箇所や一旦停止といった安全ルールは明確に表示しないと、口頭だけでは遵守できない場合があります。
併せて、指差し呼称の徹底した実施もフォークリフト事故防止で重要です。指差し呼称を義務付けて、習慣化するように安全意識を高めていきましょう。
④死角の安全確認を徹底する
フォークリフトの運転者から見える範囲以外に、死角になる位置の安全確認も大切です。
周囲の荷物や建物で見通しが悪いといった状況に加えて、フォークリフト前方のマストやサイドミラーで映らないなどの構造的な見えにくさも考慮して徹底的に安全確認を実施しましょう。
死角から突然人が飛び出してくる危険も考慮し、フォークリフトと人の通路を分けておくのも有効な手段です。また、フォークリフトにブザーや警告灯を設置し、音や光で危険を周囲に知らせる方法も安全対策の強化になります。
関連記事:フォークリフトの死角はどこ?事故を防止する対策や安全意識向上の秘訣
5Sの徹底
フォークリフトの安全対策では、作業スペースにおける「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」の5Sを徹底して実施するのも重要です。5Sを徹底すると、例えば以下のように安全が守られます。
- 整理整頓が行き届いていれば、通路が確保され、フォークリフトの接触事故を防げる
- 清掃が行き届いていれば、床の油汚れなどによる転倒事故を防げる
- しつけが行き届いていれば、安全ルールが守られ、不安全行動による事故を防げる
特に、多くのフォークリフトやトラックが出入りする物流倉庫においては、5Sを実施していないと作業を効率的に進められません。結果重大な事故が発生してしまうと、取引先の信頼を失ってしまいます。
安全と効率の基盤となる5Sですが、重要性は理解していても「現場に浸透しない」「継続できない」という悩みは尽きません。
5S・3定が定着しない現場の共通点と、活動を精神論ではなく「仕組み」として定着させるための核となる考え方を、以下の資料で解説します。
>>【事例つき】5S3定が浸透しない現場の共通点3つと仕組み化の「核」を見てみる
KY活動やヒヤリハット報告の実施
KY活動とは作業を想定したイラストシートなどを用いて危険予知し、対策を考える活動です。日常から危険源を察知するためには、訓練を重ねていく必要があるため、KYT(危険予知訓練)も実施することが大切です。
また、危険が発生したものの労災のような事故には至らなかった事象「ヒヤリハット」に基づいて安全対策を講じることも効果的です。フォークリフトのヒヤリハット事例集や対策については、以下の記事で詳しく紹介しているので、あわせて参考にしてみてください。
関連記事:フォークリフトのヒヤリハット事例集と対策まとめ!危険予知の事例もあわせて解説
ヒヤリハット防止には危険な事例を収集して書面で報告・記録するのが望ましく、「ヒヤリハット報告書」を作成するのをおすすめします。
「いつ・どこで・どうしていたとき・ヒヤリとしたこと」といった項目や想定原因、対策案などを記入する欄を設けた様式で作成して実施してみてください。
関連記事:ヒヤリハット事例を活かした事故やトラブルの防ぎ方は?危険を伝えるマニュアル作りも解説
フォークリフトと人員の作業動線を整理
フォークリフトと作業者が作業スペースで重なってしまうと、事故につながる危険性を高めてしまいます。
フォークリフトと作業者の動線を確認・整理し、未然に事故を防げるように改善していきましょう。誘導者を設置し、あらかじめ決めた合図に従って作業する方法も有効です。誘導者を設置する際は、以下の点について注意する必要があります。
- 誘導者は運転手から見やすい安全な位置で指示する
- 指示・合図は運転手が確認しやすい大きな声と動作でおこなう
- 誘導中に危険な状況が起こったら即座に作業を停止させる
- 作業中のフォークリフトに他の作業者を近づけさせない
- 誘導の終了を運転手にはっきり伝える
フォークリフトの定期メンテナンスや保全業務の組み込み
フォークリフトは、労働安全衛生規則によって月次点検と年次点検が義務付けられています。
フォークリフトを安全に使用するために必要な点検なので、必ず実施するようにしましょう。また、フォークリフトの正常な動作を維持するには、オイルチェックやタイヤの摩耗チェックなどの定期メンテナンスや、部品の交換・修理・点検といった保全業務も欠かせません。
関連記事:保守点検を行うメリットとは?実施方法や作業漏れをなくすコツを紹介
ドライブレコーダーの搭載
フォークリフトの事故を防止する安全対策として、ドライブレコーダーの導入も有効な方法です。万一事故が発生した際の状況を映像で記録でき、原因を検証するのに役立ちます。
分析した内容は、今後の対策強化や社員の安全教育にも活用可能です。また、ベテラン作業者の運転技術を社内で共有できる利点もあります。
ドライブレコーダーは一般的に乗用車用が知られていますが、フォークリフト用も販売されているのでチェックしておきましょう。1台のカメラで前後左右を撮影できる製品もあり、運転者や周囲の状況を把握するのに活躍します。
ここまで、フォークリフトの安全対策として主な取り組み内容を8つご紹介しました。次章からは、フォークリフトの安全対策に取り組んでいる企業事例を詳しくご紹介しますので、参考事例としてご覧ください。
フォークリフトの安全対策事例
フォークリフトの安全対策に力を入れている企業の事例をご紹介します。自社でも取り入れやすい施策・方法があれば、ぜひ導入を検討してみてください。
株式会社近鉄コスモス:安全作業や点検手順を動画マニュアル化
株式会社近鉄コスモスは、事業BPO・作業BPO・梱包作業などの事業を展開している物流企業です。フォークリフトの安全対策として動画マニュアルを活用しており、安全作業や点検手順などの詳細を映像で確認できるようにしています。
▼始業前のフォークリフト点検手順を解説する動画マニュアル▼
※「tebiki」で作成
始業前のフォークリフト点検手順では、ポイントになる箇所に字幕を入れてわかりやすく解説し、実際の点検手順を把握できるように工夫しているのが特徴です。
▼フォークリフトの禁止事項を解説する動画マニュアル▼
※「tebiki」で作成
フォークの基本動作を説明する動画では爪でパレットを押したり、荷物をフォークで持ち上げたまま離れたりなどのNG行為を字幕と共に説明しています。フォークリフトの安全対策について社内で共有するのであれば、動画マニュアルの導入を検討してみてください。
上記の動画はいずれも、物流現場に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」によって作られており、現場作業員がスマホ1つで撮影をしています。tebikiの詳しい機能や活用事例は、以下のリンクからPDF資料をダウンロードしてご覧ください。
>>>物流現場に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」のサービス資料を見てみる
株式会社フジトランスコーポレーション:安全教育のOJT工数を大幅に削減
株式会社フジトランスコーポレーションは、さまざまな分野で物流サービスを提供している総合物流企業です。船舶での貨物の積み卸しや倉庫内でのフォークリフト作業を教育する手段として、動画マニュアルを活用しており、安全教育のOJT工数を大幅に削減しています。
働き方改革を実現すべく動画マニュアルを導入したところ、業務の大幅な効率化も実現。工数を抑えながらより質の高い安全対策を社員に認識させるのに役立てています。
同社の安全対策事例について詳細に知りたい方は、以下のインタビュー記事をあわせてご覧ください。
インタビュー記事:働き方改革の手段としてtebikiを活用。複数の部門で工数の効率化を実現!
株式会社ロジパルエクスプレス:紙ベースのマニュアルから脱却し、安全ルールを統一
株式会社ロジパルエクスプレスは、倉庫や車両といった自社資産を活用した物流サービスを提供している企業です。動画マニュアルを活用して全拠点の従業員に動画教育を実施し、安全品質意識の向上に努め、事故やヒヤリハットを未然防止する環境を整えています。
また、各拠点の倉庫内作業やトラックドライバーなどの業務の現場作業マニュアルとしても動画マニュアルを活用。全国各地から集まってもらって研修を実施するのが難しいなか、隙間時間に動画で勉強できるとして高い効果を実感しているとのことです。
2024年2月1日時点で、全従業員の動画マニュアルの合計視聴時間は「710時間」と、動画マニュアルを大いに活用しており、今後さらに現場だけでなく他部署でも活用していく予定としています。
同社の安全対策事例について詳細に知りたい方は、以下のインタビュー記事をあわせてご覧ください。
インタビュー記事:動画で全拠点の安全品質意識の向上と業務ノウハウの可視化を達成
まとめ:フォークリフトの安全対策は「安全作業の可視化」が必須
フォークリフト事故は、人的・機械的・環境的要因が複合的に絡み合って発生します。事故を防ぐためには、8つの安全対策(動画マニュアルによる安全教育、安全作業の標準化、フォークリフト4原則の遵守、5Sの徹底、KY活動・ヒヤリハット報告の実施、作業動線の整理、定期メンテナンス、ドライブレコーダー搭載)が重要であり、これらを着実に実行することが求められます。
中でも、最も重要となるのが「安全作業の可視化」です。動画マニュアルを活用した安全教育は、危険な状況や正しい操作・手順を誰にでも分かりやすく視覚的に伝えることができます。これにより、OJTや紙マニュアルでは難しかった、知識の定着と均一な教育を実現し、結果として事故防止に大きく貢献します。
物流現場に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」は、フォークリフト作業における「安全の可視化」に特化した動画マニュアルを、現場でかんたんに作成・共有できるツールです。多くの物流企業で導入され、安全教育の質の向上と事故削減に実績を上げています。フォークリフト事故ゼロを目指すには、「安全作業の可視化」が不可欠であり、そのための最適な手段として「tebiki現場教育」の導入を強く推奨します。