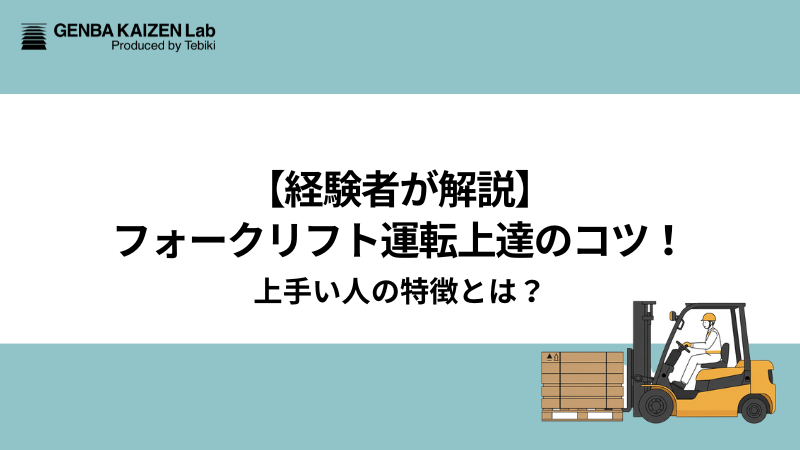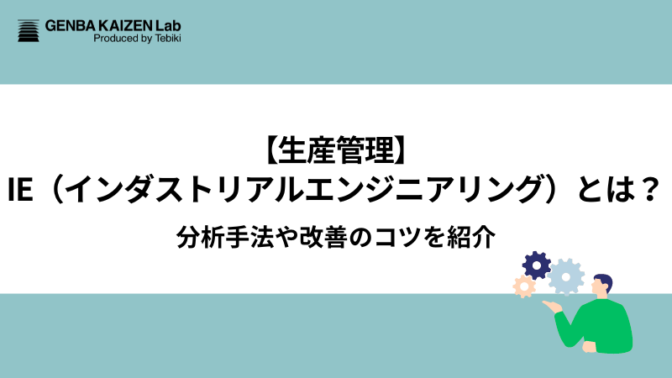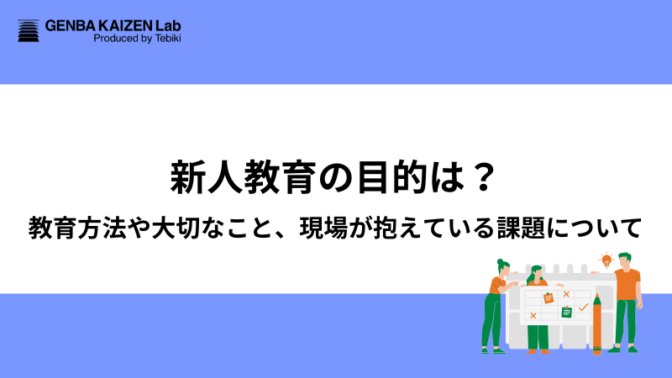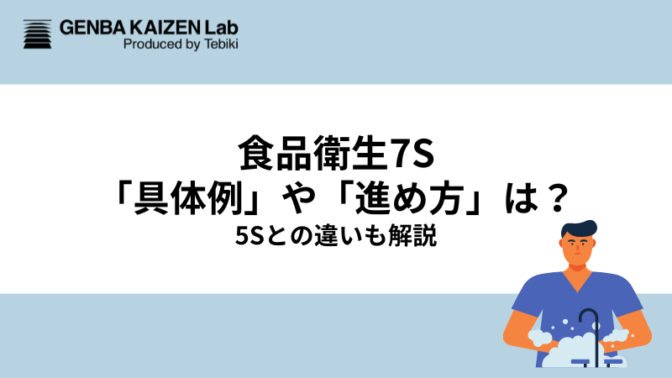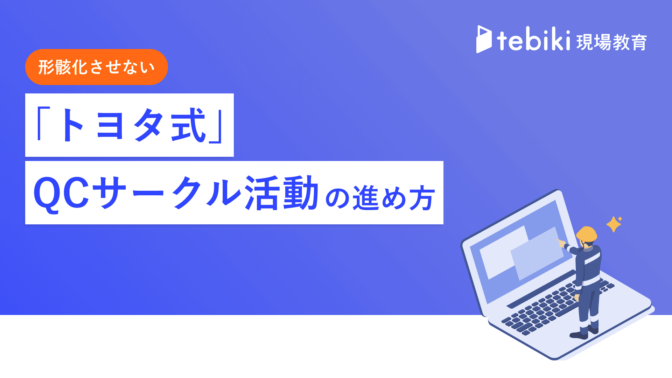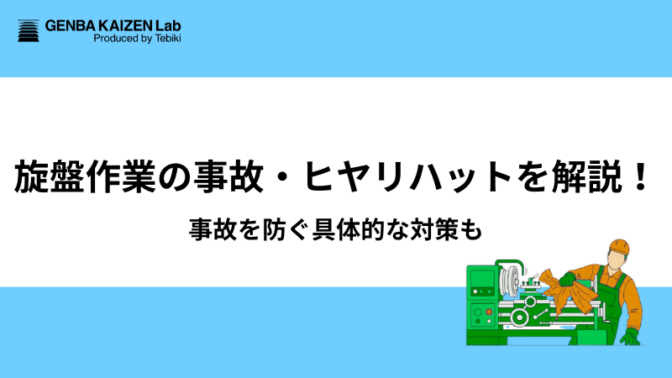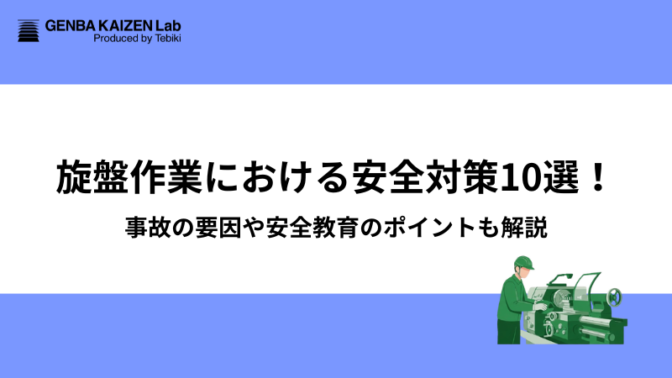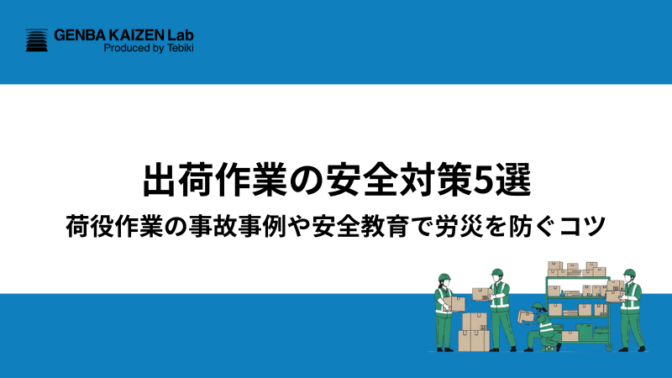かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
フォークリフト作業において、「レバー操作(特にツメの角度や高さの微調整)が感覚的に掴めない」「荷物の積み下ろし(荷役)がスムーズにできない」など、様々な悩みを抱えている方も多いと思います。
そこで本記事では、フォークリフト技能講習を修了したばかりの方や、フォークリフト作業に従事しある程度経験があるものの作業に自信がない方へ向けて解説します。
なお、本記事はフォークリフト作業に15年以上従事する筆者によって執筆されているため、すぐに実務で活用できる内容となっています。ぜひ最後までご一読いただき、フォークリフトの操作に自信を持ち、スムーズかつ正確に効率良く作業がこなせるようになるための参考にしてください。
このように、一人ひとりが操作のコツを掴み、自信を持って作業することは、安全性の向上に直結します。
それに加え、会社全体として安全な職場環境を構築するためには、組織的な安全教育の仕組みや、事故を未-然に防ぐための具体的な対策を講じることが不可欠です。
自社の安全対策や教育方法の改善に行き詰まりを感じているなら、解決のヒントとなる具体的な取り組みをまとめた、以下の資料をご覧ください。
>>目指せゼロ災!安全意識を高めるフォークリフトの安全教育・対策事例集を見てみる
目次
フォークリフトのコツを掴むまでにはある程度の慣れが必要
フォークリフトの運転技能講習を修了したからといって、いきなり実務レベルの運転や操作ができる人は少ないでしょう。
フォークリフトに限ったことではありませんが、何ごとも作業のコツを掴むまでにはある程度の慣れが必要です。その理由は、以下の2つです。
経験や勘に基づいた「カンコツ」を要するため
フォークリフトに限らず、乗り物の運転は経験が必要です。中でもフォークリフトは、日常的に動きを見たり操作するものではないので、上達するには実際の作業に近い環境で練習に励み、実務の中で経験を積むしかありません。
フォークリフト運転技能講習で教わることは基本動作の部分だけで、それだけでは実務レベルには達しないのが現実です。何度も繰り返し練習したり、実務をこなすことで「カンコツ(勘やコツ)」を掴むことが上達の近道です。
まさに、この「カンコツ」をいかに早く、そして安全に掴むかが、フォークリフト上達の鍵です。
しかし、個人の練習や経験だけに頼ると、上達のスピードに差が出たり、自己流の危険な操作が身についてしまったりする恐れがあります。熟練者の持つ「カンコツ」を組織の財産として、誰もが学べる形にすることが理想的です。
そのための強力なツールが、日々の作業の指針となる「作業標準書」です。「カンコツ」が伝わり、現場の誰もが「実際に使う」作業標準書の作成ポイントについて、以下の資料で詳しく解説しています。
>>カンコツが伝わる!「現場で使われる」作業標準書のポイントを見てみる
機種ごとに性能や操作性が異なるため
フォークリフトは、さまざまなメーカーが製造・販売していることに加え、オプションで機能を追加することもできるため、機種により性能や操作性が異なります。
例えば、カウンターバランス式であれば、フォークを左右にスライドさせられる「サイドシフト」の有無などが挙げられます。さらに、エンジン車と電気車、ギア式とトルコン式では操作方法が一部異なる場合もあります。
このようにフォークリフトと一括りにしても、操作性・性能・機能などが微妙に異なるため、それぞれの特性を掴むには慣れが必要なのです。フォークリフトの基本的な操作方法を改めて振り返りたい方は、基本操作がまとめられている以下の関連記事もご覧ください。
関連記事:フォークリフト基本操作マニュアル!作業手順書の例も紹介
フォークリフト操作を上達させるコツ
フォークリフト作業を少しでも早く上達させるためには、具体的なコツを知り意識しながら乗ることが重要です。ここの見出しでは、フォークリフト操作を上達させるコツとして、以下の2つに分けて詳しく解説します。
フォークリフト走行時のコツ
特にカウンターバランス式フォークリフトは、乗用車と同じ4輪車であるものの、走行時の仕組みが異なります。押さえておくべきポイントを、それぞれ見ていきましょう。
後輪操舵の感覚を掴む
フォークリフトと乗用車との最大の違いは、「後輪操舵」であることです。「後輪操舵」とは、ハンドルを旋回した際、後輪が曲がり舵を切る仕組みです。これにより、狭い場所でも小回りが利くというメリットがあります。
注意点として、前輪で舵を切る乗用車では内側の巻き込みに注意しなければならない一方で、フォークリフトは外側後方にある壁や物、従業員などへ接触する可能性がある点に注意が必要です。この特性を頭で理解し、意識しながら走行することで、フォークリフト操作の上達につながります。
なお、壁や物、作業員への接触や衝突しそうになるケースは、フォークリフト操作時によるあるヒヤリハットの事例です。その他のヒヤリハット事例や発生させないための安全対策について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
関連記事:フォークリフトのヒヤリハット事例集と対策まとめ!危険予知の事例もあわせて解説
車体ごとのブレーキのクセを理解する
事業所にあるフォークリフトの、「車体ごとのクセ」をつかむことも重要です。特に、カウンターバランス式のブレーキは、車体ごとにクセがある場合が多く、理解しておかなければ、事故を起こしかねません。
例えば、軽く踏んだだけで強力な制動力がかかる車体と、「あそび」が多くしっかりと深く踏み込まないと制動力が得られない車体では、力の入れ方が大きく異なります。初めての車体に乗る際は、ブレーキのクセを確かめるところから入りましょう。
必要以上にハンドルを切らない
走行時の具体的なコツとして、必要以上にハンドルを切らないことで、なめらかな走行が可能になります。
『後輪操舵の感覚を掴む』で説明した通り、フォークリフトは後輪操舵であるため、ハンドルを大きく切るほど車体後方が大きく外に振れることになります。旋回の径が大きいと、その分接触のリスクが高くなるのです。
加えて、旋回のためにハンドルを切った分、直進に切り替える時にハンドルを戻すために必要な動作も大きくなるのでロスが増えます。走行時は、最低限のハンドル操作で、なめらかな運転を意識してみましょう。
急発進・急ブレーキ・急旋回をしない
急発進・急ブレーキ・急旋回といった「急」のつく操作は、荷崩れや接触など、事故につながる可能性が高いため、フォークリフトを作業するうえで避けるべきです。
例えば、荷物が積まれたパレットを移動させている時に急旋回をしてしまうと、遠心力でパレット上の荷物が崩れてしまいます。また、急発進や急ブレーキについても荷物が崩れるリスクに加え、周囲で作業している従業員にとっては予期せぬ動きなので接触するリスクも生まれます。
操作に慣れていないほど「急」な操作が発生しやすいので、慎重な操作を心がけ、滑らかな運転ができるように心がけましょう。
なお、物流企業「株式会社近鉄コスモス」では、フォークリフト操作時のNG例を動画マニュアルにまとめて、いつでも視聴できるような環境を構築しています。
▼フォークリフトの基本動作NG例をまとめた動画マニュアルの例▼
※「tebiki」で作成されています
同社に限らず、物流現場ではフォークリフトの基本的な操作方法や操作するうえでのルールなどを動画で学習できるように整備している企業は多くなっています。
フォークリフトの複雑でカンコツを要する操作を文字や画像だけで表現するのは難しく、動画であれば視覚的な理解を促すことができるためです。
上記動画は、物流作業に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」で作成されています。詳細機能や活用事例については以下のリンクからご覧いただけるので、あわせてご覧ください。
>>>物流作業に特化した動画マニュアル「tebiki現場教育」の詳しい機能や導入事例を見てみる
荷役操作(リフト操作)時のコツ
フォークリフトの最大の特徴でもある「リフト操作」も要点を押さえ、意識して操作することで上達につながります。
押さえておくべきポイントを解説します。
フォークの水平を保つ
リフト操作は、フォークの水平を保つことが上達への第一歩です。
例えば、パレットに対してフォークが水平でなかった場合、パレットを押し込んでずらしてしまったり、最悪の場合パレット上の荷物を落下させたり、奥にあるものを破損させてしまう危険があります。
とはいえ、フォークの水平は「感覚」が重要であり、コツを掴むまではなかなか難しいものです。
慣れるまでは、自身が水平と感じた位置を、リフトから降りて目視で確認し、感覚と実際の角度のズレを知ることも、上達を早めるひとつの方法と言えます。
もし、車体に水平になった時点でティルト操作が自動で止まるボタンや、チルト具合がわかる針が付いていれば活用するのもよいでしょう。
パレットにフォークを差し込む際は慎重に行う
フォーク差し込み時に貨物事故が発生する可能性が高いため、どんなに慣れた人でもパレットにフォークを差し込む際は慎重になります。
フォークリフト作業歴15年以上の筆者でも、パレットにフォークを差し込む直前は、状況をしっかりと把握し、水平を確認してから慎重に差し込みます。そのため、パレットの前で一時停止し、的確にリフト操作してから慎重に差し込むよう心掛けましょう。
パレットごとの違いを把握する
事業所によっては、さまざまなサイズのパレットを取り扱うため、パレット1枚1枚の違いを把握することは、安全に作業する上で非常に重要です。
例えば、多くのパレットのサイズは「幅1.1m×奥行1.1m」であり、フォークの長さも1.1m前後に設定されていることが多く、その場合は根本までフォークを差し込んでも問題ないものの、パレットの奥行きが1.1mよりも短い場合は注意が必要です。
奥行き0.9mのパレットであれば、根本までフォークを差し込むとフォークがはみ出てしまうため、いつも通り根元までフォークを入れて作業すると、はみ出したフォークの先で奥の商品を傷つけてしまうことも。そのような事故は、特に初心者に多い傾向があります。
そのため、パレットのサイズや素材などの違いを理解し、フォークの差し込む角度や位置を適切に調整するなどの工夫をしてみましょう。
フォークリフト上達のための練習方法
フォークリフトの運転が上達するためには、練習が必要不可欠です。
ここでは、具体的な練習方法について、筆者が実際におこなったものを含めて以下の3つをご紹介します。
- 空パレットの積み降ろしを繰り返す
- パレットに不安定なものを乗せて走行
- 上手い作業員の操作方法を真似する
空パレットの積み降ろしを繰り返す
まずは、最もオーソドックスな練習方法として「空パレットをA地点からB地点へ1枚ずつ移動させる」ことを繰り返す練習がおすすめです。実際に、筆者が新人従業員にフォークリフトの練習を指示する際は、まずこの練習をしてもらいます。
その際、以下のことに注意しながら練習することで早く上達します。
- ズレがないようキレイに置く
- フォークを差し込む際と引き抜く際の水平を意識する
- チルトの角度等はリフトから降車し目視で確認する
- ロスなくスムーズに作業する
はじめは操作に慣れることが目的で、慣れてきたら細かな作業をスムーズに行えるようになるため反復しましょう。
パレットに不安定なものを乗せて走行、リフト操作を行う
次に紹介するのは、「フォークで抱えたパレットに不安定なものを置き走行する」ことで、走行時に事故を起こさないための練習です。
『急発進・急ブレーキ・急旋回をしない』で説明した通り、急発進や急ブレーキ、急旋回など「急」のつく作業は事故に直結します。なめらかな走行やリフト操作を身につけるために、この練習方法は効果的です。
その際、意識すべきポイントは以下の通りです。
- 「急」のつく操作をしない
- パレットに載せたものを絶対に転倒させない
- チルトの角度等はリフトから降車し目視で確認する
- ロスなくスムーズに作業する
「急」のつく操作とはどの程度なのか理解することで、実務でもスムーズでミスのない作業ができるようになります。
注意点として、乗せるものは落下しても問題がないものを選び、周囲に何もない広い場所で行うようにしましょう。
フォークリフトの運転が上手い作業員の操作方法を真似する
あなた自身が上手いと感じたり、周りからの評価が高い人のフォークリフトの運転をよく観察することも練習のひとつです。
フォークリフトが上手い人には、「作業が丁寧」「無駄がない」「事故を起こさない」などの特徴があり、作業をスムーズに進める方法や事故を起こさない術を意識し作業しています。もちろん、真似をするだけでなく、作業のコツや意識していることなどを聞いて試してみるのもよいでしょう。
また、上手い人の作業風景を動画にして共有することもポイントです。撮影するだけでなく、細かな解説を入れれば、今後も使える教育ツールとしての活用することもできるでしょう。
物流企業の「株式会社フジトランスコーポレーション」でも、フォークリフトの作業を動画で撮影し、社内に展開する形で運転スキルの標準化を進めています。同社の取り組みを詳しく知りたい方は、以下のインタビュー記事をご覧ください。
>>株式会社フジトランスコーポレーションのインタビュー記事を読んでみる
フォークリフトの運転が下手な人の共通点と上手い人の特徴
フォークリフトの運転が「下手な人」と「上手い人」には、どのような特徴があるのでしょうか。
それぞれ特徴を知ることで、あなたが「上手い人」になるためにやるべきことや「下手な人」にならないよう注意すべき点が見えてきます。以下の5つの項目に分けて、詳しく見ていきましょう。
- 運転(走行)操作
- 荷役操作(リフト操作)
- 安全意識
- 判断力
- 精神状態
運転(走行)操作
運転(走行)操作時からスキルの差がでるものです。
| 上手い人の特徴 | 下手な人の特徴 |
|---|---|
| ・前進、後進の切り替えがスムーズ ・切り返しが少ない ・最小限のハンドル操作 ・後輪蛇行の特性を理解している ・乗車時の姿勢が良い | ・急発進、急停止、急旋回が多い ・無駄な切り返しが多い ・不必要に大きなハンドル操作 ・後輪蛇行の特性を理解していない ・乗車時の姿勢が悪い |
荷役操作(リフト操作)
荷役操作の腕は、作業のスムーズさだけでなく、荷物の安全に直結します。
| 上手い人の特徴 | 下手な人の特徴 |
|---|---|
| ・フォークの水平位置を把握している ・最低限の操作で荷役する ・なめらかにレバー操作する ・衝撃が少なく静かに作業する | ・フォークの水平位置を把握していない ・無駄な操作が多い ・レバー操作が不自然(カックンなど) ・パレットを置く時などに大きな音(ガチャンなど)が鳴る |
安全意識
作業のスムーズさだけでなく、安全に作業することもフォークリフトの運転が上手い人の特徴です。
| 上手い人の特徴 | 下手な人の特徴 |
|---|---|
| ・状況に応じて的確な安全確認を行う ・各作業で事故の要因を探し対策する ・常に周囲の状況を把握している | ・操作に集中しすぎて周りが見えていない ・安全確認を忘れる |
フォークリフトの事故が発生する原因や安全意識を高める具体的な取り組み、安全作業マニュアルを作成するポイントなどについて詳しく知りたい方は、以下の関連記事もご覧ください。
▼関連記事▼
・フォークリフトの安全対策8例!事故を防止した改善事例や安全意識を高める方法も解説
・フォークリフト安全作業マニュアル!事故や労災を防ぐ操作方法
判断力
フォークリフトの運転が上手い人と下手な人では、判断力が大きく異なります。
| 上手い人の特徴 | 下手な人の特徴 |
|---|---|
| ・常に最悪の状況を想定して前もって対処する ・荷物の重さや形状、重心を考慮して安定した操作ができる ・進む、譲るなど、周囲とスムーズに連携が取れる | ・「大丈夫だろう」という安易な考え ・荷物の特性に対する配慮が足りず、不安定な操作になりがち ・周囲との連携がぎこちない |
精神状態
フォークリフトに限らず、乗り物の運転は運転手の精神状態の影響を大きく受けます。
| 上手い人の特徴 | 下手な人の特徴 |
|---|---|
| ・常に落ち着いており、感情の起伏が少ない ・集中力を一定に保っている | ・常に焦りや緊張がある ・集中力が途切れがち |
焦りや緊張といった精神状態は、運転操作における「不安全行動」の大きな要因です。
なぜ人は焦ると危険な行動をとってしまうのか、行動科学の視点からその心理メカニズムを解明し、事故を未然に防ぐ方法を解説します。
>>繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網を見てみる
フォークリフト操作のコツ上達や標準化を実現している企業事例
フォークリフト上達の「コツ」は、良い例だけでなく「やってはいけないNG例」から学ぶのも効果的です。
物流企業の株式会社近鉄コスモスでは、この考え方に基づき、フォークリフト操作の禁止事項やヒヤリハットにつながるNG操作を集めた動画を作成しています。
▼フォークリフト操作のコツ習得につながるNG集動画①▼
※「tebiki」で作成されています
言葉や文章では説明しにくい「危険な動き」とその理由を動画で具体的に示すことで、「では、どうすれば安全か」という正しい操作方法、すなわち「コツ」を強く意識できます。ベテランがOJTで指摘するような細かなNGポイントも、動画なら効率的に共有可能です。
ちなみに、これらのNG集動画は、現場従業員が物流現場に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」という動画マニュアル作成ツールで簡単に作成しています。
「tebiki現場教育」で、コツの習得を促すNG事例動画をどのように作れるか、詳細は以下のリンクから資料をご覧ください。
注意点:慢心による事故の発生
これまで解説してきたように、フォークリフトの運転を上達させるには「経験」が必要不可欠です。
しかし、経験を積み、操作や作業に慣れたことによる「慢心」には特に注意しましょう。
厚生労働省花巻監督署が発行したリーフレット「フォークリフトによる労働災害防止を徹底しましょう!」によると、過去5年間で「経験年数4~10年」の作業員による事故が38%と最も多く、「経験年数3年以内」の37%を上回る結果となっています。
これは、経験の浅い層だけでなく、中堅・ベテラン層においても相当数の事故が発生していることを示しており、「経験=安全」という単純な図式が成り立たないことを裏付けています。
このデータは、経験豊富な運転者ほど「慣れ」や「慢心」からくる事故のリスクが高いという、重要な事実を示しています。
このような、ルールを知っているにもかかわらず発生する事故の根本原因が「ヒューマンエラー」です。
したがって、中堅・ベテラン層への安全教育は、単なるルールの再確認ではなく、ヒューマンエラーがなぜ起きるのかというメカニズムに焦点を当てる必要があります。経験による油断を防ぎ、労災を未然に防止するための効果的な安全教育の進め方について、以下の資料で詳しく解説しています。
>>ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育を見てみる
まとめ
本記事では、フォークリフトの運転を上達させるコツについて徹底解説しました。記事内で紹介したコツをまとめると以下の通りです。
| フォークリフト走行時のコツ | 荷役操作(リフト操作)時のコツ |
|---|---|
| ・後輪操舵の感覚を掴む ・車体ごとのブレーキのクセを理解する ・必要以上にハンドルを切らない ・急発進、急ブレーキ、急旋回をしない | ・フォークの水平を保つ ・パレットにフォークを差し込む際は慎重に行う ・パレットごとの違いを把握する |
これらを意識して日々の作業に取り組むことが、フォークリフトの運転上達への近道です。また、動画で上手い従業員の実際の操作方法を学んだり、NG集を見ることで事故防止に努めることがあります。
そこでおすすめしたいのが、物流業に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」です。紙のマニュアルでは伝わりにくい細かな操作方法や、具体的なNG行動を効率的に学ぶことができます。
tebikiの詳細機能や活用イメージについて少しでもご興味がある方は、下の画像をクリックして、サービス資料をダウンロードしてみてください。