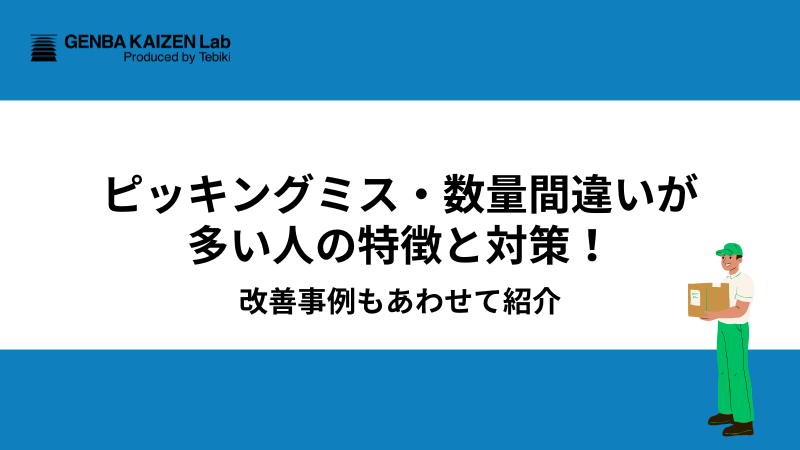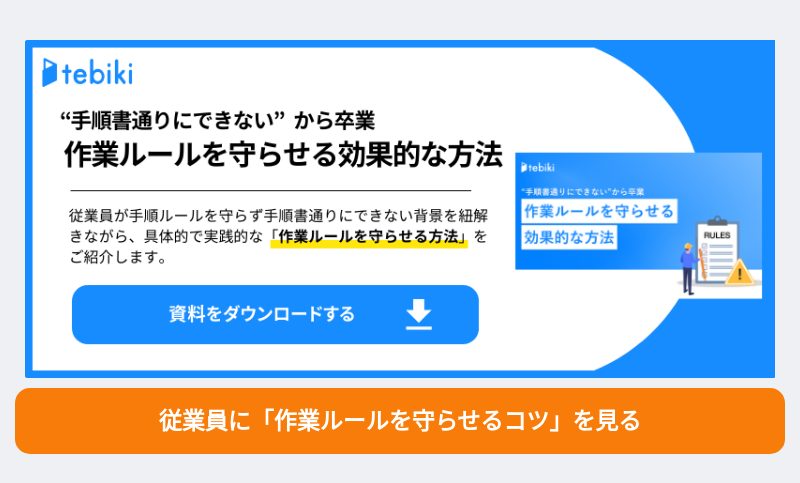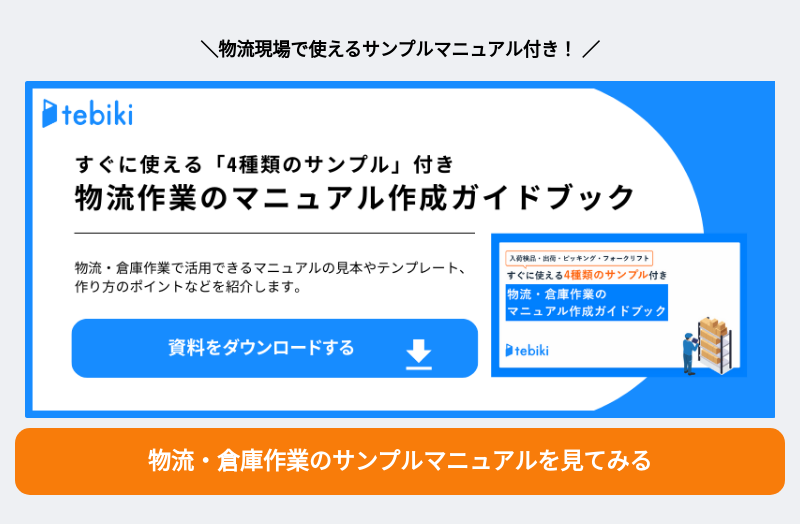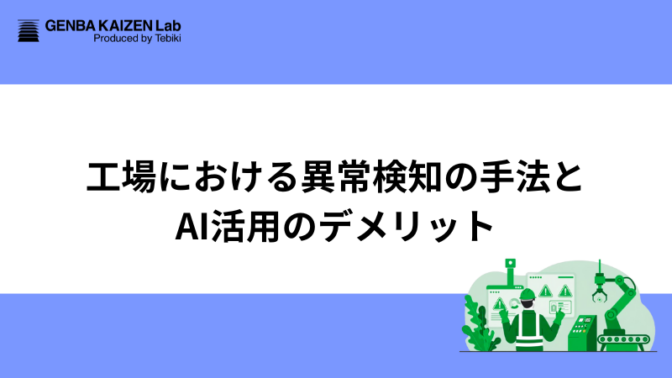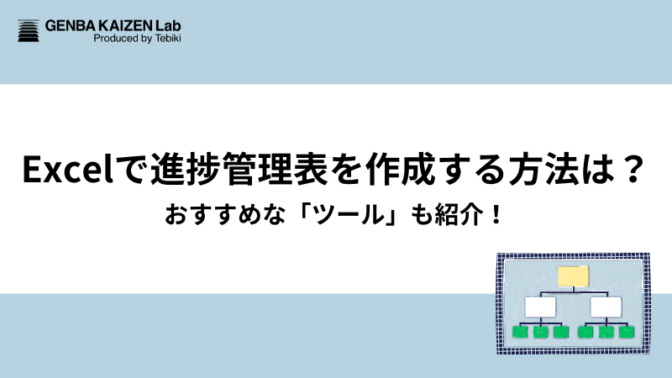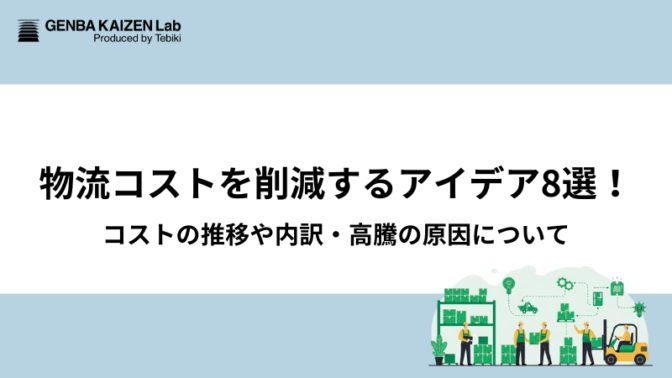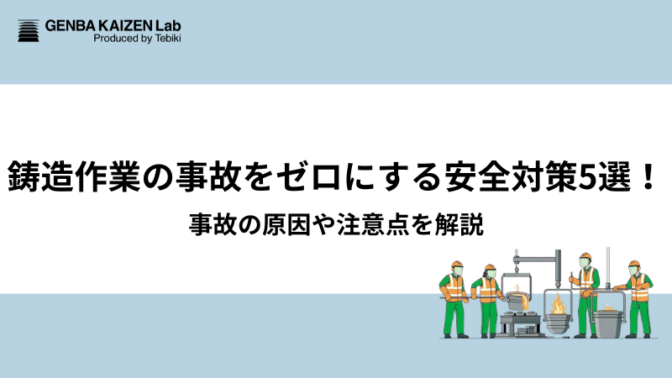かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
本記事ではピッキングミスや数量間違いが多い人の特徴、ミスが発生する要因と具体的な改善策について詳しく解説します。倉庫現場の作業改善に使えるヒントを多数まとめているので、是非ご参考ください。
なお倉庫や物流現場では、ピッキングミスを「注意」や「再教育」で防ぐのではなく、手順や基準を“仕組み化”して再発を防ぐ取り組みが広がっています。作業ルールを明確にし誰が行っても同じ品質を再現できる状態を整えることが、ヒューマンエラーの抑止に直結します。
ピッキングミスの原因から標準化の要点、改善事例までをまとめた資料を以下で紹介しています。現場改善のヒントを求める方は是非ご覧ください。
>>誤出荷ゼロへ!ヒューマンエラーによるピッキング作業ミスをなくす具体的な対策と改善事例を見る
※本記事は、元運送会社・大手家具メーカー物流担当者によって執筆・監修されています
目次
ピッキングミス・数量間違いが多い人の特徴
ピッキングミスや数量間違いが多い人によくある特徴の共通点は、以下3つの観点から分析できます。
- 「作業手順」に関する特徴
- 「商品知識」に関する特徴
- 「性格・特性」に関する特徴
それぞれの観点から、具体的な特徴を解説します。
しかしこうした個人の特徴だけでなく、「手順や基準が現場全体で統一されていない」という構造的な問題がミスの温床になっているケースも少なくありません。そこで注意や意識ではなく、仕組みでミスを防ぐために何が必要なのかを整理した資料も用意しています。
>>誤出荷ゼロへ!ヒューマンエラーによるピッキング作業ミスをなくす具体的な対策と改善事例を見る
「作業手順」に関する特徴
まず、ピッキング作業においてミスを頻発する人は、作業手順に問題があることが多いです。具体的には、以下のような特徴が挙げられます。
- 作業手順を正確に覚えていない、または自己流にアレンジしている
- ピッキングリストの確認を怠る、または見間違える
- 経験が浅く作業手順を理解していない
作業手順を正確に覚えていない、または自己流にアレンジしている
ミスが多い作業員は、明確なマニュアルがあっても作業手順を覚えていない、またはマニュアルを無視して自己流にアレンジした方法で作業している場合があります。そもそも作業手順とは、作業の標準化を目的にそれぞれの現場で定義されているはずなので、作業手順の遵守は必須です。
作業手順が遵守されないという状況は、様々な要因が重なっている場合も多く、要因を追求できたとしても改善まで実施するのが難しい場合もあります。
そこで参照してほしいのが、なぜ手順書通りに作業ができないのか、作業ルールを守ってもらうにはどうすべきなのかを体系的にまとめている以下の資料です。実際に、改善につながっている3社の企業事例も掲載しているのでヒントが得られるでしょう。下の画像をクリックして資料をダウンロードしてみてください。
ピッキングリストの確認を怠る、または見間違える
一般的にピッキング作業は、出荷する商品のリストが記載された「ピッキングリスト」をもとに商品を収集します。そのピッキングリストの確認を怠ったり、見間違えたりしてピッキングミスが発生するのはよくある事例です。
確認の怠りは「慣れ」からくる怠慢が原因でもあることが多く、中堅やベテラン社員によって発生するケースはよくあります。
こうした「ヒューマンエラー(人為的ミス)」は、物流現場や倉庫作業ではどうしても起きてしまいます。だからこそ、ヒューマンエラーが起きないための現場改善が重要です。そこで効果のある改善策の1つが「どうしてヒューマンエラーは起きるのか」「どうしたら再発防止がなされるのか」と真因を究明し、対策を練ること(=なぜなぜ分析)」です。以下のセミナー動画では、トヨタ自動車でもよく実践されていた「なぜなぜ分析」の具体的な進め方について解説されているので、ヒューマンエラー防止策を検討している方はあわせてご覧ください。
>>>セミナー動画「トヨタで学んだ『なぜなぜ分析』ヒューマンエラーに対するトヨタの考え方は?」を見てみる
やり方が分からないときに参照できるマニュアルがない
特に経験の浅い新人スタッフや新入社員が、作業手順が分からず手が止まるケースはよくあります。このとき、「正しい作業手順がすぐに参照できる状況にない」場合、ミスが多発しやすいです。
事前にどれだけ教育しているとしても、1人で作業が完結できるようになるまでは時間がかかります。だからこそ、「正しい作業手順がすぐに参照できる」状態を現場で作ることが重要です。
たとえば物流企業の「ソニテック株式会社」では、標準作業を動画におさめ、QRコードでいつでも動画マニュアルが確認できるような教育体制を整備しています。
QRコードをスキャンすることで作業コースを簡単に確認できる機能も、大変好評です。該当のコースや動画マニュアルを探す手間が省けるため、この機能は非常に便利です。ピッキング作業は各便ごとに作業内容が異なるため、それぞれの便に合わせたコースを設定しています。作業に不慣れな方や初めて作業をする方でも、QRコードをスキャンするだけで、該当の便の作業手順を動画でチェックでき、安心して作業を開始できるようになっています。
同社のように、現場の作業マニュアルに動画を活用する動きは製造業界全体にあります。動画マニュアルのリンクをQRコード化し、現場でQRコードを設置しておく、というような体制を構築すれば、不明点があった際にスマホでQRコードを読み取るだけで、その場ですぐに正しい手順を把握できます。
動画マニュアルが物流現場にもたらす効果、物流業界での活用事例などは以下の資料にまとめられています。下の画像をクリックしてぜひ資料をご覧ください。
「商品知識」に関する特徴
商品知識の欠如もピッキングミスや数量間違いが起こる人の特徴の1つです。具体例としては以下2つです。
- 商品の保管場所を把握していない、または頻繁に変わるため覚えられない
- 似ている商品の見分け方に詳しくない
商品の保管場所を把握していない、または頻繁に変わるため覚えられない
1つ目は、商品が置いてある場所に関するミスです。商品の保管場所を把握しておらず、勘違いして誤った商品を出荷してしまう、または、同じ商品でも保管場所が頻繁に変わるため商品を覚えられずにミスを引き起こすようなケースです。
保管場所が明確に分かるような現場改善、現場動線整備が重要だと言えます。
似ている商品の見分け方に詳しくない
同じメーカーの商品で「同じようなパッケージだが、よく見ると別の商品だった」ということはよくあります。それによるピッキングミスはたびたび発生するものです。
例えば同じ商品名のスティックシュガーでも「3g入り」と「5g入り」とでは異なる商品になるため、ミスが発生することが多いです。これらを一瞬で見分けるのは難しいです。こうした、商品ごとの違いがなかなか把握できないという点は、ピッキングミスを起こす人の特徴の1つです。
なお、商品の保管場所や見分け方など、作業の基礎となる部分の知識については、わかりやすいマニュアルや手順書を整備し、理解してもらえるような教育環境を整備することが解消する近道になります。
マニュアルが整備されていない、そもそもピッキングに関連したマニュアルが倉庫内に無いなどの場合には、マニュアルのサンプル、すぐに使えるフォーマットが付いたPDF資料「【すぐに使える4種類のサンプル付き】 物流・倉庫作業のマニュアル作成ガイドブック」をご覧ください。マニュアル作成のコツや企業事例も紹介しているので、マニュアル作成のヒントが得られるはずです。
「性格・特性」に関する特徴
作業員の性格や特性が原因で、ピッキングミスや数量間違いが発生することもあります。中でも、以下のような特徴がある作業員はミスする可能性が高くなる傾向にあるので、注意が必要です。
- 慎重さに欠ける、大雑把である
- 迅速な報連相(報告・連絡・相談)ができない
- 焦りやすく落ち着いて作業できない
慎重さに欠ける、大雑把である
ピッキングは小さなミスが大きな損害を生む繊細な作業です。そのため、慎重さに欠ける人や大雑把な性格の人は、ピッキングミスを起こしやすい傾向にあり、ピッキング作業に向かないと考えられます。マニュアル通り丁寧に作業できて、細かい気配りができる方が物流現場では活躍する傾向にあるのです。
いかに作業手順書どおりに業務を遂行できるかが鍵を握るわけですが、もし現場全体を通じて作業手順を守ってもらうための組織作りを検討している場合は、資料「“手順書通りにできない”から卒業 作業ルールを守らせる効果的な方法」もあわせてご覧いただくと、ピッキングミスを減らすための具体的なヒントが得られるでしょう。下の画像をクリックすると、ダウンロードできます。
迅速な報連相(報告・連絡・相談)ができない
経験の有無に関わらず、報連相の重要性を理解していても、実践できないケースが見られます。担当者個人の問題だけでなく、報連相を阻害する職場環境に起因する場合もあります。
焦燥感によって注意散漫になる
煩雑な作業、周囲からのプレッシャー、あるいは責任感の強さから、作業中に焦燥感を抱き、注意力が低下することがあります。こうした特徴は、ピッキングミスや数量間違いの直接的な原因となります。
ピッキングミスや数量間違いが生じる8つの原因
前章でご紹介した「ピッキングミスが多い人の特徴」から考えられるピッキングミスや数量間違いが発生する原因は、主に以下の3つに絞られます。
- 教育・人的要因
- 環境的要因
- 商品的要因
それぞれ深掘りしていきます。
教育・人的要因
ピッキングミスや数量間違いが生じる要因として、作業者への教育不足や作業者自身に問題があることが挙げられます。
それぞれ、具体的には以下のとおりです。
- 教育体制、マニュアルが整備されていない
- ヒューマンエラーの未然防止策が整備されていない
- 作業員の高齢化
教育体制やマニュアルが整備されていないから
作業員への十分な教育体制や作業マニュアルが完備されていないと、ピッキングミスや数量間違いがたびたび発生する可能性が高くなります。例えば、業務の進め方の教育手法がほとんど「OJT教育」に依存しているような現場は、教育担当者の教え方にバラつきが生じることが多く、結果的に新入社員の作業手順にバラつきが生じやすいです。
「現場改善ラボ」の会員を対象にした現場教育の実態調査(n=156)では、新人教育に対して課題を抱えていると回答した割合は全体の93%にも及びます。

【教育のばらつき/教育負担の削減が見込める”動画マニュアル”の有効性&活用事例】より抜粋
教育のバラつきやOJT担当者への教育負担など、現場での教育課題の根本には「OJT+紙マニュアル」の従来の教育手法にあります。以下の資料では、「OJT+動画マニュアル」の組み合わせによる教育手法について、4社の事例に触れつつわかりやすく解説しています。以下のリンクをクリックして資料を御覧ください。
>>教育のばらつき/教育負担の削減が見込める”動画マニュアル”の有効性&活用事例
ヒューマンエラーの未然防止策が整備されていないから
人間が作業している以上「ヒューマンエラー」は必ず発生します。一方で、「ヒューマンエラーが発生するのは仕方がない」と割り切るのではなく、未然防止策を徹底することでミスを限りなくゼロに近づけることができます。
ヒューマンエラーの未然防止策は「ミスが起きないように注意する」というような意識レベルの対策では成り立ちません。具体的かつ現実的な対策が必要です。つまり、ヒューマンエラーの発生メカニズムを知り、それを除去する打ち手を模索しましょう。その打ち手について解説されているセミナー動画「人に起因する品質不良の未然防止と具体的な対策」もご覧いただくと、ヒューマンエラー未然防止策のアイディアがいくつか浮かんでくるはずです。
>>>「ヒューマンエラー未然防止策」を無料セミナー動画で学ぶ
高齢作業員の割合が多いから
作業員の高齢化は、特にピッキング作業においてトラブルに直結します。その最大の理由は、多くの人が年を重ねるにつれて「目の衰え」が進行するからです。そのため高齢化が進んでいる現場では「老眼」が原因のピッキングミスが後を絶ちません。
ピッキングリストの文字を大きくするなど対策を講じても、ミスがなくならないのが現実です。
環境的要因
ピッキングミスや数量間違いが発生する要因として「環境」に問題があることも挙げられます。具体的には以下のような原因です。
- 適切な作業スペースが確保されていないから
- 整理整頓されていないから
- 暑さ・寒さ対策をしていないから
適切な作業スペースが確保されていないから
ピッキングするのに必要なスペースが確保されていないことも、ミスを引き起こす要因となります。なぜなら、商品を仮置きしたり、仕分けしたりする際に誤った場所に置いたり他の商品と混ざるリスクが高まるからです。
さらに、作業スペースに圧迫感があると、常にストレスを抱えた状況で作業することになりミスにつながります。
スペース不足によるミスやストレスを解消するには、作業環境を整える「5S・3定」の徹底が不可欠です。
しかし、活動が定着せず形骸化してしまう現場も少なくありません。精神論ではなく、5S・3定を組織の「仕組み」として浸透させるためのポイントを、以下の資料で解説します。
>>【事例つき】5S3定が浸透しない現場の共通点3つと仕組み化の「核」を見てみる
整理整頓されていないから
ピッキング作業を行う場所が整理整頓(2S)されていないと、ミスが起こる原因となります。なぜなら、不必要なものと必要なものの区別がつかず、結果的にピッキングミスや数量間違いを招いてしまうからです。
例えば、過去のピッキングリストが処分されず放置されており、当日使用するピッキングリストであると勘違いした結果、誤出荷となるケースです。
暑さ・寒さ対策をしていないから
作業現場の温度管理がされていないと、ピッキングミスが発生しやすくなります。その理由として、環境の悪さが作業員に以下のような影響を与えるからです。
| 環境 | 与える影響 |
|---|---|
| 暑い | ・不快感から集中力が低下する ・熱中症のリスクがある |
| 寒い | ・手がかじかみシール剥がしなど細かい作業が難しくなる ・防寒着で動きが制限される |
作業現場の温度管理を徹底することでミスの緩和につながります。
商品的要因
商品そのものに問題があることもミスを引き起こす要因です。具体的に以下のようなことが考えられます。
- 類似商品の見分けたが周知されていないから
- 商品名の表記がピッキングリストと外装で異なるから
類似商品の見分け方が周知されていないから
見た目が似た商品を、間違ってピッキングし誤出荷してしまう事例は非常に多いです。具体的には以下のようなことが考えられます。
- 容量違い(例:300mlと700mlで外装が異なる)
- 味や香りの違い(例:塩味とチーズ味で外装が異なる)
- サイズ違い(例:MサイズとLサイズで外装が異なる)
こうした細かい部分での見分け方でミスが出ないよう、現場レベルでどのように対策する必要があるのか、定義することが重要です。
例えば物流企業の「ソニテック株式会社」は、業務の種類ややり方が多様であるためにミスがどうしてもなくせない課題に当時直面し、改善策を模索されていました。
荷主や便によってピッキング作業が異なるため、その内容を教え、覚えることは大きな負担です。多様なピッキング方法を正確に理解し、迅速に作業できるようにするには、教育と実践的な経験が不可欠です。マンツーマン指導を行っているものの、作業内容の正確な伝達が難しく、ミスが発生することもしばしばあります。例えば、「商材の表面にシールを貼る」という指示が、誤って「横面にシールを貼る」という行動になるなど、指示の不明瞭さが課題となっています。
同社の詳しい事例や具体的な改善策についてインタビューした記事は以下のリンクからご覧いただけるので、あわせて参考にしてみてください。
インタビュー記事:3ヶ月間の直接指導を動画マニュアルで完全に置き換え、業務の効率化を実現
商品名がピッキングリストと外装で異なるから
商品外装に表記されている商品名と、ピッキングリスト上の商品名に相違があればミスの要因となります。「商品名が変わったが、ピッキングリスト上では旧名のままになっている」ことが主な原因であり、よくあるミスです。
商品名が変わった際にピッキングリストの表記も変わるような仕組み作り・工夫を、個々の現場で施さなければなりません。
ピッキングミスや数量間違いを減らす9つの対策・改善策
ここまで、ピッキングミスや数量間違いが多い人の特徴と、その要因について解説してきました。ここからは、ミスを改善するための具体的な対策を解説します。対策は主に以下3つに分類されます。
- 教育
- 作業環境の最適化
- システム導入
ただし、個人への教育や環境改善だけでは現場全体のミス率を大きく下げるには限界があります。根本的には、手順・ルール・基準を“誰が作業しても守れる形”に整えることが欠かせません。
こうした仕組みづくりの視点を含め、ピッキングミスの原因整理から標準化の進め方までをまとめた資料もご用意しています。より体系的に改善を進めたい方は是非ご参照ください。
>>誤出荷ゼロへ!ヒューマンエラーによるピッキング作業ミスをなくす具体的な対策と改善事例を見る
【教育】による対策
先述のとおり、人間が作業を行う以上「誤った作業手順」「ヒューマンエラー」は必ず発生します。しかしこれらは「教育」による対策で改善が可能です。ミスをなくすための教育改善手法としては、以下のような対策が挙げられます。
- 「現場で使われる」手順書・マニュアルを整備する
- ミス発生時の原因と再発防止策の共有をルール化する
- ベテラン社員から新人スタッフへ技術伝承する機会を設ける
「現場で使われる」手順書・マニュアルを整備する
作業手順のミスやヒューマンエラーを未然防止するには「業務標準化」が不可欠です。業務標準化を実現する主な手段が「作業手順書・マニュアルの整備」ですが、「手順書は整備しているが文字数が膨大で読まれない」「マニュアルを作ったものの最新手順に更新されていない」といった形骸化が起きている現場は少なくありません。
そこで近年導入されているのが、「膨大な文字が不要」かつ「誰が教えても同じ説明内容」の2つを満たす教育手法「動画マニュアル」です。複雑な作業手順を教育するには多くの情報量とマンツーマン指導が必要ですが、動画に置き換えることで多くの課題が解消され、「作業員が抵抗なく使えるマニュアル」が整備できます。
動画マニュアル導入の推進方法や現場改善事例については、資料「動画マニュアルで現場の教育をかんたんにする方法」で詳しくまとめられています。以下をクリックするとダウンロードが可能です。
>>動画マニュアルで現場の教育をかんたんにする方法を見てみる
ミス発生時の原因と再発防止策の共有をルール化する
2つ目の対策方法は、「ミス発生時の原因と再発防止策の共有をルール化する」ことです。そもそもどうしてピッキングミスや数量間違いが起きるのか、根本的な原因が分からなければ的確な対策は講じられません。
ミス発生時の原因を周知し、改善策が考えられるような組織作りができると理想です。
再発防止策が現場に浸透しない多くの原因は、以下の3つに大別されます。
・場当たり的なOJT(その場しのぎや口頭指導)
・読まれないマニュアル(形骸化)
・進まない技術伝承(スキルのばらつき)
これらを解消する術として有効なのが「再発防止策を見える化する教育体制」であり、多くの現場で「動画による教育(マニュアル)」が導入されつつあります。動画マニュアルを通じた再発防止策の浸透や事例の詳細は、以下の資料「再発防止策の『伝わらない』『守られないを解消する動画マニュアルの活用事例』でまとめられているので、あわせて参考にしてみてください。
>>資料「再発防止策の『伝わらない』『守られないを解消する動画マニュアルの活用事例』を見てみる
ベテラン社員から新人スタッフへ技術伝承する機会を設ける
3つ目の対策法は、ベテラン社員から新人スタッフへ技術伝承する機会を設けることです。ベテラン社員しか分からないカンコツや業務の割合が多くなればなるほど、従業員ひとりひとりの作業品質にバラつきが生じます。
こうした属人化はできるだけ排除しなければならず、現場改善の基本です。
属人化しているカンコツや技術を若手人材にどのように継承するのかについては、資料「“伝わらない”“属人化している”カンコツ作業を標準化する最適解」にまとめられています。以下のリンクをクリックするとダウンロードが可能です。
>>>技術継承する具体的な方法がまとめられた資料をダウンロードする
「作業環境の最適化」を図る対策
次に、作業環境の最適化によるピッキングミス対策について解説します。具体例として、以下のような方法で改善を図ることが可能です。
- 5S活動を徹底する
- 倉庫内レイアウトと作業動線を見直す
- 暑さ・寒さ対策をする
5S活動を徹底する
5S活動を徹底することで、ピッキングミスや数量間違いを減らせます。
5Sとは、整理・整頓・清掃・清潔・しつけの頭文字(S)からつけられたものです。物流の作業現場においては、「安全性」「効率性」「品質」「モチベーション」の向上に期待できます。
- 整理: 不要な物をなくし、ピッキング対象を明確化。
- 整頓: 保管場所を定め、表示を徹底。探しやすく取り出しやすい環境を実現。
- 清掃: 商品やラベルの汚れを除去し、誤認を防止。
- 清潔: 3Sを維持し、効率と正確性を保持。
- しつけ: ルール遵守の習慣化で、作業の標準化を促進。
例えば、棚に商品名と番号を大きく表示し、床に動線を引いて迷わず進めるようにします。毎日始業前に5分間清掃し、週に一度は在庫チェックと不要品処分を実施。これらをルール化し、全員で守る習慣をつけるような活動が例として挙げられます。
5S活動は生産性を高めるうえで重要なアプローチですが、具体的な推進方法はあまり知られていないことが少なくありません。そこで以下のセミナー動画「生産性を高める5S活動 正しい運用に欠かせない「重要なS」とは」が参考になるでしょう。生産性が低い現場の共通点から5S活動の本格的な実践方法まで解説されているので、以下のリンクをクリックして動画を視聴してみてください。
倉庫内レイアウトと作業動線を見直す
倉庫内レイアウトと作業動線を見直すことは、ピッキングミス削減に非常に効果的です。余裕をもったレイアウト設計は、作業者のストレスを軽減し、安全性と効率性を向上させます。
通路が狭かったり、何度も行き来する動線に問題があると、作業者は常にストレスを感じながら作業することになり、集中力低下やミスの誘発につながります。人とぶつかったり、無理な体勢で移動したりすることで、商品を落下させる事故につながる可能性も増え、商品の破損だけでなく、作業者の怪我にも繋がりかねません。
よく出る商品(Aランク)は入口近く、動線の短い場所に配置したり、ピッキングリストの順序と商品の配置を一致させたりする等、最適化できる余地がないかどうか見回りましょう。
暑さ・寒さ対策をする
作業場の温度、湿度を管理し、作業員が快適に作業できるような環境を整えるのも、ピッキングミスや数量違いを減らすのに重要です。対策がされていないと、暑さで集中力がなくなったり、寒さで手がかじかんで細かい作業ができなくなったりします。
特に冷房のない真夏の倉庫での作業は想像以上に暑く、時には命の危険すら感じるものです。「空調服」や「スポットクーラー」の導入など、簡単にできる対策もあるので検討してみてください。
【システム導入】による対策
ピッキングミス・数量間違いを防止する3つ目の対策「システム導入」を解説します。具体的な対策は以下3つですが、いずれも多くの物流現場で採用されている、高い効果が立証されている技術です。
- 「WMS(倉庫管理システム)」の導入
- 「DPS(デジタルピッキングシステム)」の導入
- ピッキングロボットの導入
「WMS(倉庫管理システム)」の導入
「WMS(倉庫管理システム)」は多くの物流倉庫で導入されているシステムのひとつです。
WMSとは、倉庫内の業務や在庫管理を効率化・最適化するための情報システムです。入庫から出庫までの一連の物流プロセスを、情報技術(IT)を活用してサポートします。
ひとくちにWMSといっても、最近はさまざまなタイプがあります。そのため、物流現場それぞれに合ったシステムを選ぶことが重要です。例えば、ハンディターミナルなどを用いたシステムであれば、ピッキングした商品とピッキングリストの内容を端末を用いて読み取り照合することで、商品の取り間違いや数量違いを検知しヒューマンエラーを防ぎます。
「DPS(デジタルピッキングシステム)」の導入
DPS(デジタルピッキングシステム)も、ピッキング作業においてミスを大幅に減らせるシステムです。DPSのよく使われている活用場面としては光によるピッキング指示です。ピッキングすべき商品の棚を光で照射し、作業員はそこに入っている商品をピッキングします。
とはいえDPSは大きな導入コストがかかるので、小規模な倉庫には導入しづらいという側面もあります。
ピッキングロボットの導入
ピッキングロボットは、その名の通り人間に代わってピッキング作業を行うロボットです。特に近年は、AI技術の発達によりめざましい進化を遂げています。
商品を掴み、積み付けまで行うアーム型や、商品棚を作業者の近くまで運んでくる走行型などがあります。人材不足の解消やヒューマンエラー解消に寄与するでしょう。
非常に便利なシステムですが、DPSと同様に莫大なコストがかかり、ロボット導入のために倉庫の設備を改善する必要があるなど、手軽に導入できないのが現実です。
ピッキングミスや数量間違いの解消を実現した物流企業の事例
物流企業の「ソニテック株式会社」は、作業品質にばらつきがあり、ピッキングや検品でのミスによる顧客クレームが課題の1つでした。多種多様な商品を扱うため、1つ1つ商品知識の習得をしなければならない状況が教育を困難にしており、ベテラン社員のノウハウも共有されていませんでした。
そこで導入したのが、「動画マニュアル(tebiki現場教育)」でした。ピッキング、検品、梱包などの作業手順や商品知識を動画で分かりやすく解説。これにより、新人はすぐに作業内容を理解し、ベテランのノウハウも共有され、作業品質が均一化されたのです。
▼物流業務のミス改善事例インタビュー動画▼
また、副次的な効果として、マニュアル作成の時間も削減できています。1つの動画マニュアルを作成するのに5分~10分程度の所要時間で済んでおり、紙の手順書よりも教育負担が軽減できていると言えるでしょう。特にtebiki現場教育のような動画マニュアル作成ツールは、現場作業員がスマホで気軽に撮影でき、編集もかんたんに実施できるため、動画編集に時間が取られるという本末転倒な事態も避けられています。
tebikiの詳しい活用事例や詳細な機能は、以下のリンクからダウンロードが可能です。
>>>物流現場に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」のサービス資料を見てみる
ピッキングミスをゼロにする教育体制整備には「動画」が有効
ピッキングミスをゼロにするには、作業者に正しい作業手順とスキルを習得させ、それを維持・向上させる教育体制の整備が不可欠です。そのための強力なツールとして、「動画マニュアル」の活用が非常に有効です。なぜ動画がピッキングミスの削減に効果的なのか、その理由を具体的に解説します。
複雑なピッキング業務を可視化、標準化できるから
ピッキング作業は、商品の種類、保管場所、数量、ピッキング方法など、多岐にわたる要素が絡み合う複雑な業務です。特に、多品種少量の商品を扱う倉庫では、作業手順が煩雑になりがちで、口頭教育(マンツーマン指導、OJT教育)や紙のマニュアルだけでは、正確に伝えることが困難です。
動画であれば、ベテラン作業者の正確なピッキング作業を、視覚的に、かつ具体的に示すことができます。「どの商品を」「どこから」「どのように」取り出し、「どこに」置くのか、一連の流れをそのまま見せることで、新人作業者でも容易に理解できます。これにより、作業手順の標準化が実現し、属人的な作業によるミスを減らすことができます。
ピッキング作業ではありませんが、例えば以下の動画は、「三井物産グローバルロジスティクス株式会社」で実際に活用されている、包装作業における動画マニュアルです。
▼包装作業を動画マニュアル化したサンプル動画▼
※現場従業員が「tebiki」で作成
このように、口頭では負担があるような作業も、動画におさめれば従業員1人で理解が可能です。ピッキング作業も同様の対策で、作業標準化が図れるでしょう。
教育担当者の日常業務に支障なく教育が進められるから
OJTやマンツーマン指導では、教育担当者は、自分の通常業務を中断して教育に時間を割かなければなりません。これは、教育担当者にとって大きな負担となり、業務効率の低下を招く可能性があります。
動画を活用した教育であれば、教育担当者は、動画を作成する初期段階での労力は必要ですが、一度作成してしまえば、あとは動画を視聴してもらうだけで教育が完結します。これにより、教育担当者は、自分の通常業務に集中することができ、生産性を向上させることができます。
外国人労働者の教育もスムーズに行えるから
近年の労働力不足を背景に、物流現場では外国人労働者の雇用が増加しています。しかし、言語や文化の違いから、教育が難航するケースも少なくありません。特に、ピッキング作業のような複雑な業務を、言葉だけで正確に伝えることは非常に困難です。
動画を活用した教育は、この問題を解決する有効な手段となります。動画は視覚的な情報が中心であるため、言葉が十分に理解できなくても、作業手順や注意点を直感的に理解することができます。
動画を活用した教育は、この問題を解決する有効な手段となります。動画は視覚的な情報が中心であるため、言葉が十分に理解できなくても、作業手順や注意点を直感的に理解することができます。
さらに、動画教育システムの中には、多言語字幕機能や自動翻訳機能を備えたものがあります。例えば動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」は、動画に挿入した日本語字幕が1クリックで100か国以上の言語に自動翻訳されます。
まとめ:ピッキングミスや数量間違いの改善には「業務標準化」と「教育体制の見直し」が鍵
ピッキングミスや数量間違いは、顧客からの信頼を失い、企業の損失に繋がる重大な問題です。これらのミスを減らすには、個人の注意に頼るだけでなく、「業務標準化」と「教育体制の見直し」が不可欠です。
業務標準化とは、誰もが同じ品質で作業できるよう、手順やルールを明確にし、共有することです。具体的には、作業手順書やマニュアルの整備、5S活動の徹底、倉庫内レイアウトや動線の最適化などが挙げられます。
しかし、手順書やマニュアルがあっても、内容が理解され、現場で活用されなければ意味がありません。そこで重要になるのが、教育体制の見直しです。従来のOJTやマンツーマン指導に加え、動画マニュアルを活用することで、教育の質と効率を大幅に向上させることができます。
動画マニュアルは、複雑な作業手順を視覚的に分かりやすく伝え、外国人労働者への教育もスムーズに行えます。また、教育担当者の負担を軽減し、日常業務への支障を最小限に抑えることができます。
ピッキングミスや数量間違いの改善、そして、物流現場全体の生産性向上を目指すなら、動画教育システム「tebiki現場教育」の導入をご検討ください。tebikiは、現場の誰もが簡単に動画マニュアルを作成・共有・管理できるツールであり、業務標準化と教育体制の強化を強力にサポートします。