かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を展開する現場改善ラボ編集部です。溶接ビードとは、溶接時に溶けたワイヤが冷えて固まることでできる「盛り上がり」のことです。溶接ビードの波紋の形状は、接合強度はもちろん、製品の美観や強度にも影響します。
しかし、現場では「きれいなビードの正解がわからない」「除去・仕上げの判断基準が曖昧」といった悩みが尽きません。
本記事では、ビードの定義や良否の判定基準、加工・仕上げ・品質管理で注意すべきポイントを解説します。さらに、個人の感覚に依存しがちな品質を安定させるための「標準化」といった手法についても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
溶接ビードとは?概要と基本的な役割
溶接ビードは形状から製品の強度や信頼性を判断できるため、外観検査において重要なチェックポイントとなります。ここではさらに深掘りして、溶接ビードについて次の4点を解説します。
- 溶接ビードの定義と役割
- 代表的な溶接方法とビードの特徴
- 溶接棒の使用によるビード形成
- 溶接方法によるビード品質の違い
溶接ビードの定義と役割
溶接ビードとは、接合部に形成される金属の波状の隆起を指します。JIS Z 3001-7(番号73102)*1に基づくと「1回の溶接パスによって作られる結果としての1回分の溶接部又は溶接金属」と定義されています。
溶接ビードの役割は主に2つあります。1つは、部材を物理的に接続し、設計通りの強度と気密性を確保することです。もう1つは、外観検査における品質判定の基準となることです。
波紋が均一なビードは、適切な電流や速度で施工されたことを示すため、内部欠陥のリスクが低いと判断できます。逆に形状がいびつであれば、強度不足や融合不良が疑われます。
代表的な溶接方法とビードの特徴
代表的なアーク溶接として主に挙げられるのは、以下の3つです。
- ティグ溶接(TIG)
- 半自動溶接(MAG/MIG)
- 被覆アーク溶接(手溶接)
採用する手法によって、ビードの外観や特性は大きく異なります。JIS Z 3001-7で分類されるティグ溶接は、整然とした「魚の鱗(うろこ)」状の波紋が特徴で、外観品質が重視されるステンレス製品などに適しています。
一方、マグ溶接などの半自動溶接は、溶着速度が速く生産性は高いものの、形状はやや凸型になりがちです。それぞれの工法の「正常な形」を理解していれば、見た目の違いだけで一概に「不良」と誤判断するリスクを防げるでしょう。
溶接棒の使用によるビード形成
ビードの盛り上がりは、JIS Z 3001-7で定義される「溶着」という現象から形成される溶接金属によって発生します。主に溶接棒やワイヤといった「溶加材」が溶融して形成されます。アーク熱によって母材の一部と溶加材が溶け合い、混ざってプール(溶融池)を作り、冷却されて固まるのが主な原理です。
特に被覆アーク溶接(手溶接)の場合、きれいなビードを作る難易度は高くなります。溶接棒は溶けるにつれて短くなるため、作業者は常に手元の高さを微調整しながら運棒しなければならないからです。こうした「棒を送る感覚」や「アーク長の維持」がズレると、ビード幅が不揃いになったり、スラグを巻き込んだりする原因となります。
溶接方法によるビード品質の違い
工法の違いは、表面だけでなく内部品質や強度特性にも違いが出ます。これは、JIS Z 3001-7(番号73345)で示される「溶接入熱」の大きさが異なるためです。例えば、大電流を用いるマグ溶接は時間あたりの溶着量が多いため、大型の構造物に適していますが、過剰な電流設定や遅すぎる速度は熱歪みを増大させます。
対してティグ溶接などの入熱を制御しやすい工法は、精密な仕上がりが可能ですが、厚板では「溶け込み不足」のリスクが高まります。外観がどれほどきれいでも、用途や材質に適さない工法を選べば、重大な強度不足につながる恐れがあると言えます。
設計者はこうした特性を考慮し、過剰な外観要求が強度低下を招かないか検討する必要があります。現場においても、「見た目」だけでなくて、工法特性に基づいた品質を見極める姿勢が重要です。
溶接ビードの種類・形状と外観品質
溶接ビードの外観は、採用する工法や作業者の技量によって異なり、当然守るべき基準も異なります。ここでは、種類や形状、さらに外観品質の基準について以下の3点を解説します。
- 溶接ビードの主な種類
- ビード形状の違いと特徴
- ビード幅と外観品質の関係
溶接ビードの主な種類
アーク溶接におけるビードは、運棒(うんぼう)の方法によって主に「ストリンガービード」と「ウィービングビード」の2種類があります。なぜ2種類があるかと言えば、目的や環境に応じて母材への熱影響や作業効率を適切にコントロールするためです。
具体的には、ストリンガービードは、溶接棒を横に振らず一直線に進める手法で形成されます。ビード幅が狭く、母材への入熱を抑えられるため、熱歪みを嫌う薄板の溶接などに適しています。一方、ウィービングビードは、溶接棒をジグザグや円状に揺らしながら進む手法で作られ、幅が広いのが特徴です。滑らかな波紋を作りやすいため、厚板の多層盛りや仕上げ層によく用いられます。
ビード形状の違いと特徴
ビードの断面形状、特に「余盛(よもり)」の高さと裾野の角度は、製品の寿命を決めるため、極めて重要です。なぜなら、必要以上に高く盛り上がったビードは、接合部の強度を高めるどころか、「応力集中」を引き起こして疲労破壊の原因になるからです。
実際、建築工事標準仕様書(JASS 6)*2に基づくと、ビード幅(B)に応じて余盛の高さ(h)には厳格な管理許容差が設けられています。例えば「Bが15mm未満の場合、hは3mm以下」「15mm以上25mm未満なら4mm以下」といった具合です。
逆に、極端に凹んだ形状や、母材との境界(止端部)が鋭角になっているものは、そこから亀裂が入るリスクが高まります。設計や検査の際は、「盛れば盛るほど強い」という認識を辞めて、規格に基づいた適切な高さを管理することが必要です。
ビード幅と外観品質の関係
幅が一定に保たれているビードは、溶接速度やアーク長、トーチの角度が常に適正範囲で維持されていたことを意味します。そのため、ビード幅の「均一性」は、溶接品質が安定しているかを見極めるバロメーターと言えるでしょう。
逆に、ビード幅が不揃いで波打っている場合、入熱量が不均一になっている可能性が高いです。内部に「溶け込み不足」や「ブローホール」といった欠陥が潜んでいるサインとも考えられます。
また、ウィービングを行う際は、神戸製鋼所の技術資料*3でも推奨されている通り「運棒の幅は棒径(心線径)の3倍まで」とするのがセオリーです。これを無視して幅を広げすぎると、ブローホールや融合不良といった欠陥が生じやすくなります。一方で、半自動溶接(MAG/CO2)の多層盛りなどでは、これ以上の幅でウィービングすることもあります。
なお、ここで制限されているのはあくまで「運棒の幅」であり、最終的なビード幅(棒径の4倍程度)とは区別して管理する必要があります。現場管理者の方は、こうした基準を個人の感覚や癖で片付けず、標準作業として数値化し、教育に落とし込みましょう。
溶接ビードの加工・仕上げ・品質管理のポイント
溶接ビードの品質管理は適切な条件設定から、規格に基づいた寸法管理、そして仕上げ加工に至るまで、一連のプロセス全体で作り込む必要があります。ここでは、現場で実践すべき以下の6点を解説します。
- 良好な溶接ビードを形成するための前提条件や溶接作業の流れ
- 溶接ビード品質の評価基準や寸法規格
- 仕上げ・加工工程で品質を左右する管理ポイント
- 溶接ビード品質を確認する検査方法
- 不良ビードが発生した場合の影響とリスク
- 不良を防ぐための是正・再発防止の考え方
良好な溶接ビードを形成するための前提条件や溶接作業の流れ
良好なビードを形成するためには、アークを発生させる前の「段取り」でほぼ決まると考えてください。なぜなら、母材表面の油分や錆、水分の付着は、ビード形状を乱すだけでなく、ブローホールなどの欠陥を招く原因になるからです。
作業手順としては、まず溶接箇所周辺(約20mm範囲)の不純物をワイヤーブラシ等で完全に除去してください。次に、WPS(溶接施工要領書)に基づき、適切な電流・電圧・速度を設定します。運棒では、一定のアーク長とトーチ角度を保つことが求められます。
特に若手技術者は、「一定の動作」が崩れやすいため、管理者は姿勢の安定化を意識させるように指導しましょう。
溶接ビード品質の評価基準や寸法規格
ビードの良し悪しを個人の感覚で判断するのは、品質トラブルの元なので、明確な数値基準に基づいた評価を行う必要があります。JASS 6(鉄骨工事)などの建築標準仕様書に基づくと、すみ肉溶接の脚長(きゃくちょう)は、設計図書(図面)において指定された寸法を確実に確保することが求められます。
また、ビード表面の欠陥についても厳格な外観検査基準があり、特にアンダーカットについては「深さ0.5mm以下」という許容差が定められています。現場管理においては、こうした基準値を超えないよう、電流や運棒の適切な管理が必要です。
仕上げ・加工工程で品質を左右する管理ポイント
溶接後の仕上げ加工は、製品の用途に応じて「残す・整える・除去する」を適切に判断しなければなりません。過剰な仕上げはコストが増え、さらに母材を削りすぎて強度不足(断面欠損)を招くリスクがあるからです。
例えば、サニタリー配管など衛生面が重視される場合は、ビードを除去し、バフ研磨で平滑にする必要があります。一方で、強度が最優先される構造物では、応力集中を防ぐために止端部(ビードの裾)のみをグラインダーで滑らかにし、余盛自体は残すケースもあります。
設計担当者は図面に仕上げ記号を明記し、現場作業者は「母材面まで削り込まない」ように、砥石の番手や当て方を管理することが重要です。
溶接ビード品質を確認する検査方法
完成したビードが要求品質を満たしているか、適切な検査方法を選定して確認します。基本となるのは「外観検査」です。これは、亀裂、ピット、アンダーカットの有無を目視で確認し、溶接ゲージで寸法を測る工程です。
表面に開口していない微細な割れが疑われる場合は、「浸透探傷試験」や「磁粉探傷試験」といった非破壊検査を実施します。こうした検査は特別な装置がなくても現場で比較的容易に行えるため、重要保安部品では必須とされます。
検査は作業中に異常があれば即座に止める「工程内検査」の意識を持つことが、手戻りを防ぐポイントとなります。
不良ビードが発生した場合の影響とリスク
形状不良のビードを放置することは、応力集中といった理由により、製品寿命を著しく縮める危険性があります。ビードの止端部が鋭角であったり、オーバーラップ(溶融金属が母材に被さる状態)していたりすると、その部分に力が集中し、疲労破壊の起点となります。
また、アンダーカット(母材の掘れ込み)は、実質的な板厚を減少させるため、設計強度が確保できなくなります。塗装製品においては、ビードの凹凸やスラグの取り残しが原因で塗膜が密着せず、早期の錆発生につながるケースも少なくありません。
たかが外観と思わず、ビードの乱れは「将来的な破損の予兆」であると認識し、厳格に管理する必要があります。
不良を防ぐための是正・再発防止の考え方
万が一不良が発生した際は、適切に除去・補修を行うとともに、根本原因を断つための再発防止策が必要です。補修においては、欠陥部分をグラインダーやガウジングで完全に除去してから再溶接を行うのは必須です。上から重ねて溶接しても、内部の欠陥は解消されません。
再発防止のためには、発生要因を「人・機械・材料・方法(4M)」の視点で分析します。例えば、特定の作業者だけ不良が多いなら、技量不足を補う教育が必要です。条件設定が原因なら、溶接機の設定値を標準化し、記録に残す仕組みを導入すべきでしょう。「なぜ起きたか」を個人の責任にせず、組織のルールや標準作業にフィードバックすることで、属人化を解消し、品質の安定化を図れます。
溶接ビードをきれいに仕上げるべき理由と実際の対策5選
溶接ビードの外観不良が招く強度低下のリスクなど、きれいに仕上げる理由として以下の5つが挙げられます。
- 外観不良による品質低下を防ぐため、溶接ビードの仕上げ基準を明確にする
- 使用環境や設計要求を踏まえ、溶接ビードを除去・仕上げすべきかを事前に判断する
- 要求品質に応じて、ビードを「残す・整える・除去する」を判断する
- 仕上げ目的に応じて、溶接ビード除去・加工方法を使い分ける
- 過剰なビード除去は強度低下を招くため、適切な除去量を管理する
外観不良による品質低下を防ぐため、溶接ビードの仕上げ基準を明確にする
きれいなビードとは「均一で欠陥がない状態」を指します。不揃いなビードや形状の乱れは、そこに応力が集中し、製品の寿命を縮める直接的な原因になるため、きれいなビードは定量的な数値で定義することが重要です。
例えば先述の通り、JASS 6(鉄骨工事標準仕様書)に基づくと、アンダーカットの深さは0.5mm以下という明確な許容差が定められています。また、神戸製鋼所の技術資料によれば、ウィービングの運棒幅は心線径の3倍以内に収めることが、ブローホール等の欠陥を防ぐセオリーとされています。
現場管理者はこうした数値を基準として指導すべきで、若手作業者に数値を満たすことを目標に練習を積ませましょう。
使用環境や設計要求を踏まえ、溶接ビードを除去・仕上げすべきかを事前に判断する
ビードをどの程度仕上げるかは、製品の用途や設置環境から逆算して決定しましょう。過剰な仕上げ加工はコスト増を招く一方、不十分な処理は塗装剥離や腐食、疲労破壊の原因になるからです。
食品機械であれば、洗浄性を確保するために完全な平滑化が求められますが、建築構造物では母材の厚みを確保する強度が優先されます。実際、繰り返し荷重がかかる部材では、ビードそのものを削るのではなく、応力が集中しやすい止端部のみを滑らかにする「トウ処理」が有効なケースも多々あります。
設計担当者は図面作成の段階で「なぜ仕上げるのか」という目的を明確にしてください。
要求品質に応じて、ビードを「残す・整える・除去する」を判断する
現場への指示は曖昧な「きれいに」ではなく「残す(As Welded)」「整える」「除去する」の3区分で具体化すべきです。指示が曖昧だと作業者に迷いが生じ、製品ごとの品質バラつきや、削りすぎによる強度不足などのトラブルにつながるからです。
具体的には、外観重視のカバー類は「除去」、強度が求められる構造材は形状を「整える」グラインダ加工、見えない箇所は「残す」といった使い分けをおすすめします。JIS Z 3090(溶接継手の外観試験方法)などを参考に、社内で「良品・不良品」の限度見本を作成して掲示するのも効果的です。
仕上げ目的に応じて、溶接ビード除去・加工方法を使い分ける
仕上げ加工を行う際は、目的に合致した工具と砥石の番手(粒度)の選定が必要です。適切な道具選びによって「研削焼け」による母材の劣化や深い傷による新たな欠陥の発生を防げます。
荒削りでビードの高さを落とすにはオフセット砥石が適していますが、最終的な表面仕上げには弾性砥石や多羽根ディスクの使用が良いと思います。特にステンレス鋼の場合は、鉄粉のもらい錆を防ぐため、専用の砥石を使い分けることも忘れてはいけません。
各工具の特性を理解し、工程ごとに使い分ける技術を習得しましょう。
過剰なビード除去は強度低下を招くため、適切な除去量を管理する
溶接強度は内部の断面積によって決まるため、ビードをフラットに仕上げる際、母材表面より削り込みすぎないよう厳重な管理が必要です。日本溶接協会*4で定義される「溶接継手の強度を求める基本式「Pmax = σw × a × leff」に基づくと、強度は以下の要素で決まります。
Pmax:最高荷重(N)
σw:溶接継手の強度(N/mm2)
a:のど厚(mm)
leff:有効溶接長さ(mm)
溶接した長さの上記のから分かる通り、耐えられる力Pmaxは、のど厚aに正比例します。すみ肉溶接において「のど厚」とは、ビード断面に内接する「三角形の高さ(理論のど厚)」のことです。
もしも、仕上げ加工でビードを深く削りすぎ「三角形の高さ」を減少させてしまうと、計算上の強度がダイレクトに低下することになります。「平らならきれい」という安易な判断は危険です。
あらかじめ「余盛高さは0mm以上」といった管理値を設け、必要なのど断面が確保されているか、溶接ゲージで確認する習慣をつけてください。
溶接ビードの不良を引き起こす構造的な要因と現場の限界
高性能な溶接機や詳細なWPS(溶接施工要領書)を整備しても、トーチを握る「ヒト」の操作にバラつきがあれば、均一で美しいビードは生まれません。ここでは、現場が抱える構造的な限界として、以下の4つの課題を解説します。
- 設定・動作のバラつき|溶接条件と作業手順の個人差
- 属人化した判断|経験値に依存する品質の不安定さ
- 認識のズレ|感覚に頼った技能伝承の限界
- 教育手法の課題|正解を即座に確認できない学習環境
設定・動作のバラつき|溶接条件と作業手順の個人差
「ビード品質のバラつきをなくす」ことは「誰がやっても同じ結果にする(標準化する)」ことと同義です。しかし、作業標準書に書かれた「適切な速度で」や「角度を保ち」といった言葉は、読み手の感覚に依存するため、個人の勝手な解釈を許してしまいます。
こうした「解釈のズレ」に対し、株式会社近鉄コスモスでは「正しい作業」と「禁止行為」を対比させた動画マニュアルを導入し、劇的な成果を上げています。
これを溶接現場に置き換えると、単に「きれいなビード」を見せるだけでなく、以下のような比較動画を作成することが効果的です。
「正しい開梱」動画は、刃物の向き、段ボールの固定位置、手の位置、安全距離といった細かい動作をわかりやすく解説。「誤った開梱」動画では、不安定な持ち方や刃物の危険な扱いなど、現場で起こりやすい不安全動作を映像化しています。
言葉の壁がある外国人材や未経験者でも「良いビード」と「悪いビード」の違いがどこにあるのかを視覚的に理解できるようになります。
属人化した判断|経験値に依存する品質の不安定さ
溶接特有の「音・光・熱」といった感覚(カン・コツ)に依存した教育も、ビード品質を不安定にさせる要因です。ベテランに頼る指導では、教え方が人によって異なり、クセまで伝承されてしまう危険性があります。
こうした属人化の解消に成功したのが児玉化学工業株式会社です。同社はドリル加工の微妙な力加減や角度を動画化し、言葉では表現しきれない暗黙知を可視化しました。
▼動画マニュアルによる標準化の例▼
溶接においても同様に、熟練工が見ている「プール(溶融池)の広がり方」や「アークの長さ」を接写した動画を「同一の手本」として用意することで、指導者の教え方のブレをなくし、組織全体のレベルを底上げできます。
認識のズレ|感覚に頼った技能伝承の限界
目に見えない欠陥リスクを「可視化」できていないことも問題です。文字だけの「不良対策書」や、完成後のビード写真だけでは、プロセスのどこに危険が潜んでいるかが伝わらず、「自分はできているつもり」という意識を変えられません。
特に、一瞬の判断遅れがブローホールなどの問題につながる溶接現場では、不良が発生するメカニズムを再現して見せることが効果的です。
「この角度だとスラグを巻き込む」「電流が高すぎると垂れる」という因果関係を映像で突きつけられると、作業者は理屈ではなく「品質を損なう怖さ」として理解します。結果として、感覚任せではなく、理論に基づいた丁寧な運棒が定着します。
教育手法の課題|正解を即座に確認できない学習環境
現場で迷ったときに「正解」を即座に確認できない環境も課題です。作業ブースにいながらにして、正しい設定や手順を確認できなければ、結局は記憶や勘に頼った作業になってしまいます。
明和工業株式会社では、作業場にディスプレイを設置し、QRコードで即座にその工程の動画マニュアルを呼び出せる仕組みを構築しており、誰でも迷わず標準作業を実行できる環境が整えられています。

これを溶接現場に応用すれば、
- この継手形状の適切な電流値は?
- この姿勢でのトーチ運びはどうやるのか?
といった疑問をその場で解決でき、手戻りや補修のムダを大幅に削減できるはずです。
溶接ビード品質を安定させるために求められる作業と教育の考え方
溶接品質の安定には、個人の技量に頼る「属人化」からの脱却が必要です。ここでは具体的に属人化脱却のための以下の4つの考え方を紹介します。
- 誰が作業しても同じ品質が得られる標準作業の設定
- 判断・動作・結果が一致している現場
- 作業を見える化し属人性を排除する
- 「理解」ではなく「再現」を前提とした教育
誰が作業しても同じ品質が得られる標準作業の設定
まずは「誰がやっても同じ結果になる」状態、つまり標準作業を確立しましょう。適切にといった曖昧な表現がバラツキの元凶です。若手が迷うのは、こうした定義が不足している証拠です。
実際に、溶接情報センターの規定では、電流・電圧だけでなく、層間温度や溶接速度まで詳細に条件を指定することが求められています。現場ではこうした基準に基づき「電流120A、トーチ角度45度」のように数値を明記したWPS(溶接施工要領書)を作成してください。数値という共通言語を持つことで、初めて品質管理が可能になります。
判断・動作・結果が一致している現場
現場全体で「判断基準・作業動作・最終品質」の3つを完全に一致させることが求められます。作業者がその場で合否を判断できなければ、知らず知らずのうちに不良品を作り続けることになるからです。設計者の意図が現場に伝わらなければ、ムダな仕上げ作業はなくなりません。
JIS Z 3090の溶接継手の外観試験方法*5などの基準に基づき、社内で明確な「限度見本(合否の境界線)」を作成・掲示することが有効です。日本溶接協会の講習会でも、基準の明確化は基本とされています。全員が同じ「正解」のイメージを共有し、そこへ至る正しい動作を遂行できる体制を作りましょう。
作業を見える化し属人性を排除する
ベテランの経験則に依存した属人化を解消するには、作業プロセスの徹底的な「見える化」が必要です。
溶接はJIS Q 9001(品質マネジメントシステム)において、製造後に欠陥が見つけにくい「特殊工程(Special Process)」に分類されます。つまり、結果の検査だけでなく、プロセス(作業中の動き)自体の妥当性確認が規格上も重視されていると言えます。
微細な手の動きやタイミングがブラックボックス化している現状を変えるため、熟練工の視線や溶融池の映像を用いた動画教材を整備しましょう。
「理解」ではなく「再現」を前提とした教育
教育のゴールは、知識を「理解させる」ことではなく、正しい動作を「再現させる」ことに設定すべきです。頭で理屈を分かっていても、実際の現場で手が正しく動かなければ、きれいなビードは描けないからです。座学だけで「分かったはずだ」と思い込むのは、管理者の誤解です。
先に挙げた株式会社近鉄コスモスなどの教育事例に基づくと、動画マニュアルを作業直前に確認させることによって、動作の定着率を向上させられます。スマホを活用し、正しい運棒のリズムを動画でなぞりながら作業できる環境を整えてください。手本をそのまま再現できる仕組みこそが、最も確実な品質保証となります。
溶接ビード品質を安定させる教育には「動画」が効果的
- 動画活用のメリット
- 動画を活用し品質不良や標準化に役立てている事例
動画活用のメリット
動画マニュアル導入の最大のメリットは、文字では表現しきれない「カン・コツ」を誰でも直感的に理解できる点です。
マニュアルに「丁寧に」と書いてあっても、その具体的な程度は読み手の解釈に委ねられてしまい、バラつきの原因になります。しかし、映像であれば工具の角度や動かすスピード、力加減といった「暗黙知」をありのままに伝えられます。
実際に、以下の児玉化学工業株式会社における作業動画をご覧ください。
ここでは、ヤスリを当てる微妙な角度や、樹脂の爪を折らないための繊細な手つきが、言葉による説明なしでも明確に分かります。
溶接のビード形成も同様に、プール(溶融池)の広がりやトーチ運びのリズムを動画で共有することが極めて効果的です。「見て真似る」環境を作ることで、若手の習熟スピードは飛躍的に向上し、組織全体の品質レベルが安定します。
動画を活用し品質不良や標準化に役立てている事例
自動車部品メーカーである上松電子株式会社では、外国人派遣社員への教育と品質管理において、「言葉の壁」と「紙マニュアルの限界」という製造業共通の課題に直面していました。
| 課題 | tebiki導入後の効果 |
|---|---|
| ・外国人指導が難航 ・紙で機微伝わらず ・不良見逃しが多発 ・部門間の連携不足 ・現場の会話が希薄 | ・言葉の壁を解消 ・視線の動きを再現 ・流出ゼロを達成 ・相互理解が深まる ・笑顔と会話が増加 |
同社では、塗装工程から組立工程への不良品流出(見逃し)が約500ppm発生しており、その原因の約4割がコミュニケーション不足や教育不足によるものでした。紙の手順書では「検査時の視線の動かし方」といった細かなニュアンスが伝わらず、指導者が「教えたつもり」でも、作業者は正しく理解できていない状況が続いていたと言います。
こうした課題に対し、同社は動画マニュアルツール「tebiki」を導入し、検査手順を可視化しました。「正しい動き」を動画で繰り返し見せることで、言語に依存しない標準化を実現。その結果、わずか5週間で不良流出率ゼロ(0ppm)を達成しました。さらに、動画作成を通じて組立班と塗装班の部門間連携が強化され、現場のコミュニケーションが活性化するという副次的な効果も生まれています。
>>同社が導入した動画マニュアル「tebiki現場教育」の紹介ページはこちら
まとめ
溶接ビードの品質は、製品の強度や信頼性を左右します。きれいなビードを安定して形成するには、個人の感覚に頼るのではなく、JISやJASSなどの規格に基づいた数値管理と標準化が必要です。
しかし、現場特有の「カン・コツ」は、言葉や紙のマニュアルだけでは伝わりにくいものです。そこで有効なのが、正しい動作を視覚的に共有できる「動画マニュアル」です。上松電子株式会社の事例のように、動画で手順を可視化することは、不良率の劇的な低減や技能伝承につながります。
まずは自社のビードの基準を明確にし、動画を活用した再現性の高い教育体制を整えてみてはいかがでしょうか。
参考元/引用元
*1:日本産業規格の簡易閲覧「溶接用語-第7部:アーク溶接」
*2:建築工事標準仕様書・同解説
*3:「ぼうだより」溶接ご法度集
*4:日本溶接協会「Q突合せおよびすみ肉溶接継手の強度を求める基本式を教えて下さい。」
*5:日本産業規格の簡易閲覧「溶接継手の外観試験方法」
*6:上松電子株式会社「「教えたつもり」をなくし、塗装工程の不良見逃し率を大幅に削減」
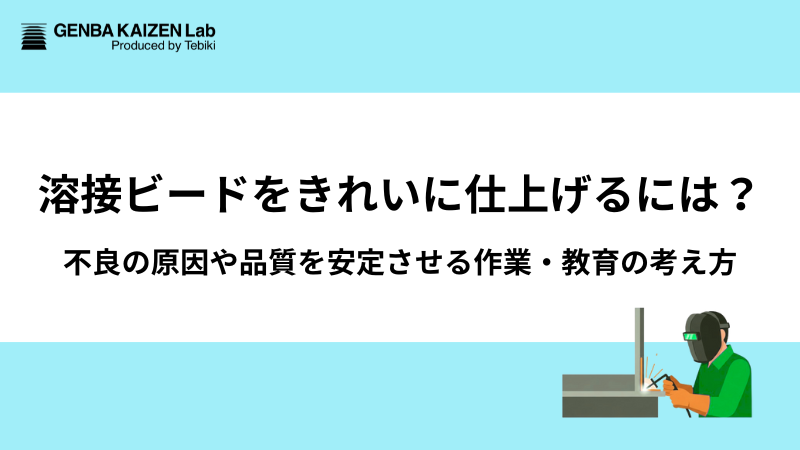
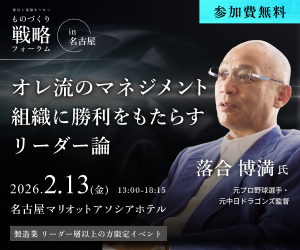

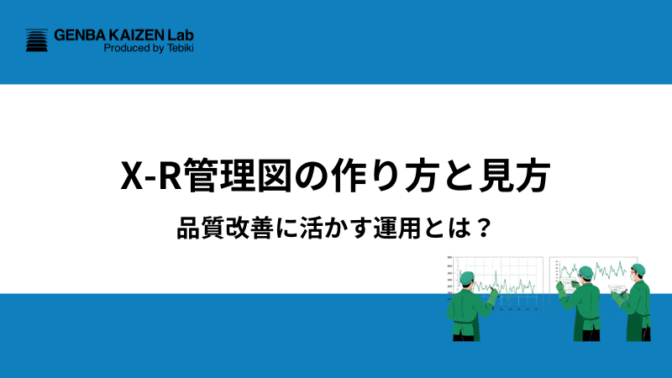




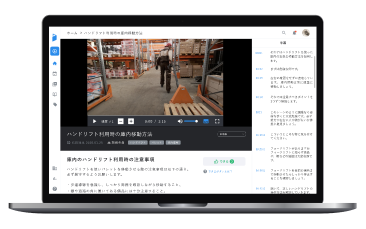



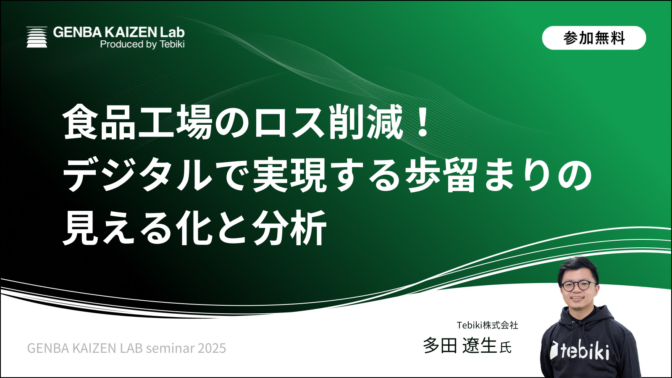
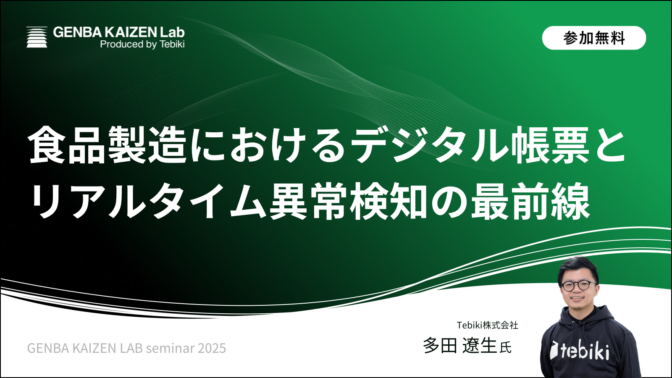
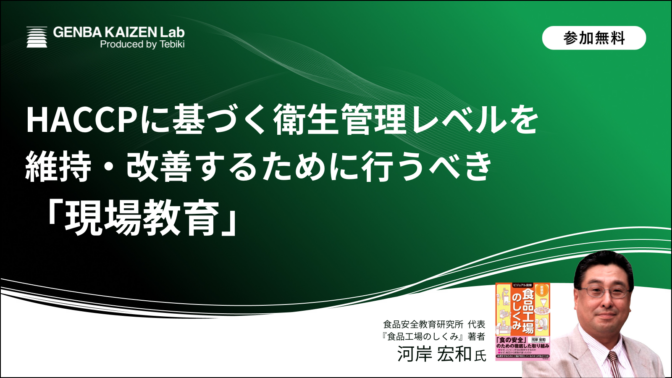
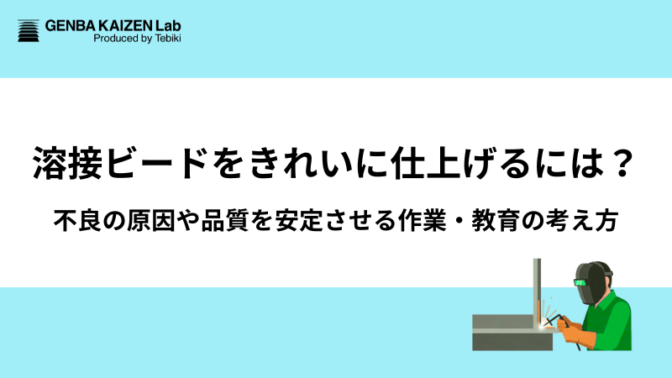

-672x378.png)