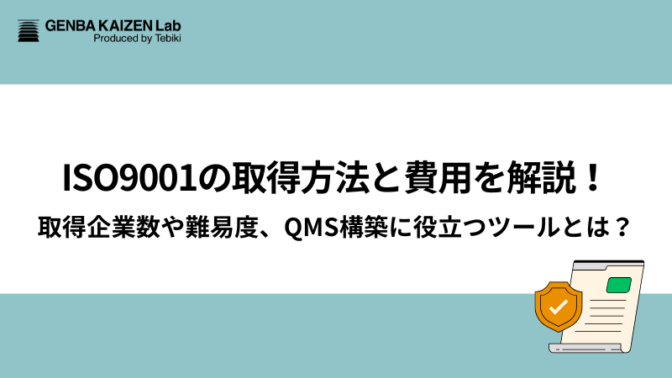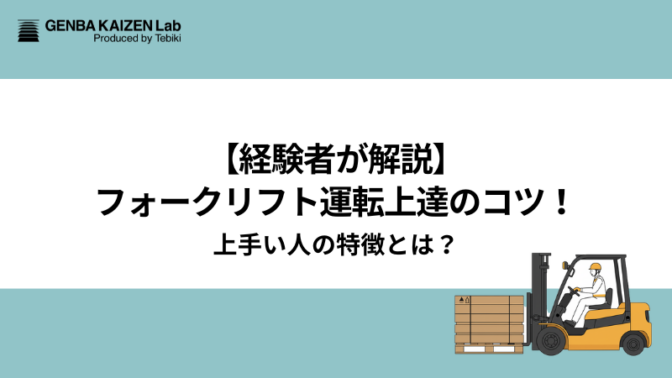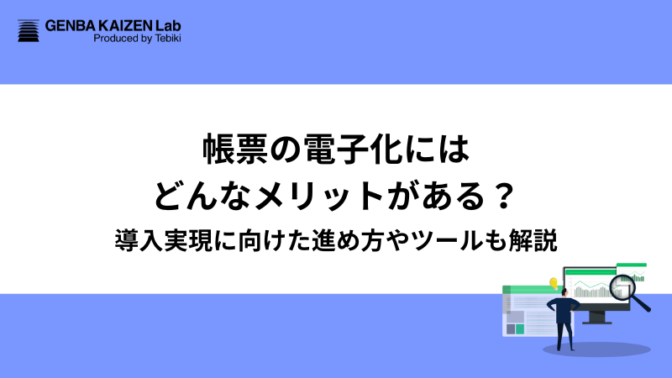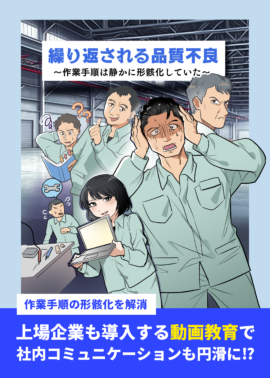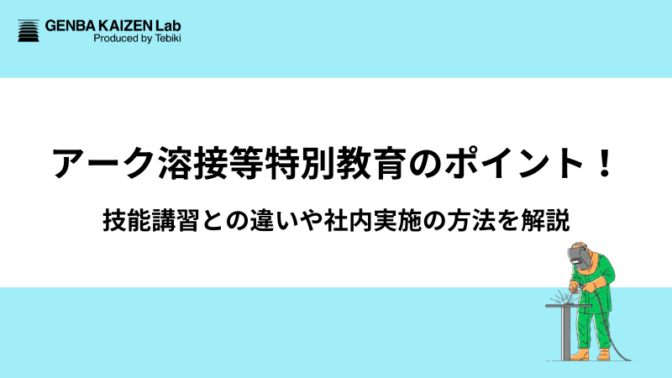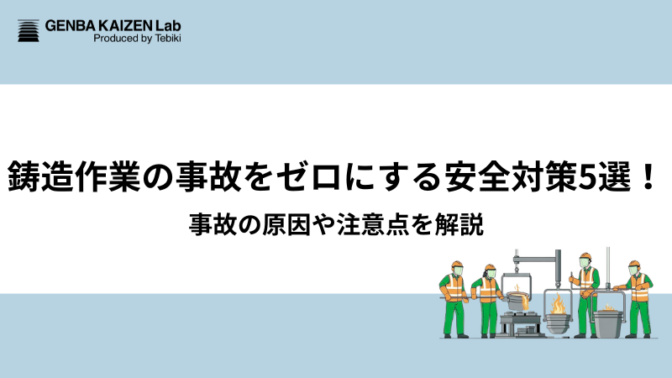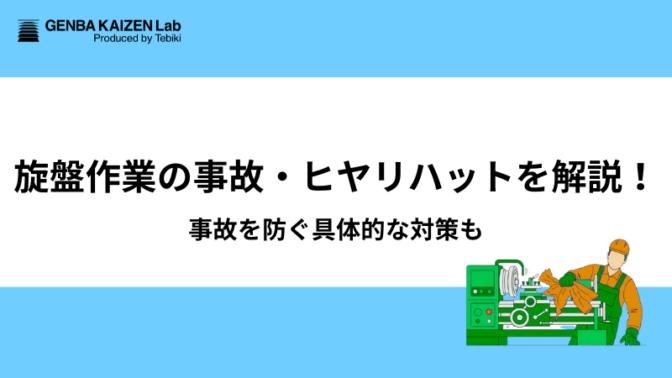工場向け安全対策の動画マニュアル「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
アーク溶接は放電現象を利用した金属加工のことで、感電・火災・ヒューム吸引など労災につながる危険を多く伴う作業です。厚生労働省の労働災害の資料でも事例が複数取り上げられ、現場では「事故を防ぐ安全対策」が課題となっています。
そこで本記事では、実際に工場の勤務経験がある筆者の観点も踏まえ、アーク溶接で実際に発生した事故事例やヒヤリハット例にもとづきながら、7つの安全対策と企業事例を紹介します。
なお昨今、「安全な作業手順を動画マニュアルで見える化し、標準化を進める」現場が増えており、工場における主要な安全対策として広く浸透し始めています。詳しい改善効果や事例は「 動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例(pdf)」をご覧ください。
労災が起きてからでは遅いので、ヒヤリハットで済んでいる現状のうちに安全対策を練ることが鍵を握ります。
>> 「動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例(pdf)」を見てみる
目次
アーク溶接とは?安全対策が重要な理由
アーク溶接とは、電極と母材の間に生じるアーク放電を熱源として金属を溶かし、冷却して接合する溶接方法のことです。建設現場では鉄骨構造や配管の溶接、製造業では主に機械部品の溶接に利用されています。
高温で金属を確実に結合できる一方で、作業中には電流による感電や高熱によるやけど、光線・粉じんによる健康被害のリスクを伴うのが特徴です。
労災の事例で後述するように、アークが発する強い光や熱、火花によって労働災害に認定されるケースが後を絶ちません。
そのため、アーク溶接に携わる企業では安全対策の徹底が必須であると言えます。
日々危険と隣り合わせである作業者だけではなく「作業者がアーク溶接で怪我や命を落とすことは絶対に防ぎたい」と思っている管理者や事務方も仕組み作りを行う上で安全対策の理解は重要だと言えるでしょう。
アーク溶接の作業工程に潜む4つの危険と注意点
アーク溶接は金属を確実に接合できる便利な加工技術ですが、主に以下の4つの危険が伴います。
- 感電
- 火花・高熱による火傷や火災
- 紫外線・赤外線による健康障害
- 溶接ヒューム・有害光線による健康障害
感電
アーク溶接では5Aから1,000Aまでの強い電流が流れ、わずか50mAで人体に危険が及びます。特に100mAを超えると致命的な事故となり得るため、アーク溶接での感電は命を落としかねません。
あり得る危険な行動として、濡れた手袋や汗をかいた作業服を利用することです。そうした絶縁性が低下した用具を利用すれば、電流が体内を通りやすくなります。
ホルダーやケーブルの被膜が破損している場合も感電の原因になります。溶接機の電源を切らずに溶接棒を取り替える行為は事故につながる典型的な感電事故の例です。
感電事故は労災の中でも死亡率が高く、厚生労働省の統計でも多く報告されています。そのため、作業前の設備点検と絶縁保護具の使用を徹底を心がけましょう。
※以下の資料では、危険作業における安全対策の新しい教育アプローチについて解説しています。
火花・高熱による火傷や火災
アーク溶接は5,000℃から20,000℃の高温を発生させます。そのため、火花やスパッタが作業環境に飛び散り、皮膚に火傷を負う事故や衣服への着火する可能性があります。
また、木材や布、紙など可燃物が周囲にあると、溶接作業中に火災が起こる可能性が極めて高いです。さらに、アセチレンやプロパンといった可燃性ガスや、有機溶剤の蒸気などが残っている場合、爆発につながります。
火花や高熱は必ず発生する現象であり、避けることはできません。そのため、危険から作業員の身を守るために、防炎シートや消火器を配置し、必ず初期消火ができる設備を整える必要があります。
紫外線・赤外線による健康障害
アーク溶接で発生する光には強い紫外線や赤外線が含まれ、短時間でも健康被害があります。特に、紫外線は目の角膜にダメージを与え、電気性眼炎と呼ばれる炎症を引き起こします。電気性眼炎は雪眼とも呼ばれ、強い痛みや充血、涙が止まらないといった症状が数時間後に現れる極めて危険な炎症です。
赤外線は皮膚に熱を与え、長期的には視力低下や白内障などの眼疾患の原因にもなります。特に溶接光は太陽光の数倍のエネルギーを持ち、無防備で直視すれば失明のリスクすらあります。
現場では溶接作業者だけでなく、近くにいる他の作業員も曝露の危険があるため、安全対策として遮光面や保護眼鏡、遮光カーテンの使用を徹底しましょう。
※以下の資料では、危険作業における安全対策の新しい教育アプローチについて解説しています。
溶接ヒューム・有害ガスによる健康障害
アーク溶接中には金属蒸気が冷却されて粒子化したヒュームが大量に発生します。粒子径は1µm以下と非常に小さく、呼吸器を通じて肺にまで到達し、短時間で発熱や頭痛といった健康被害を引き起こします。長期的にはじん肺や肺がんのリスクを高めることが報告されている危険な粒子です。
さらに、炭酸ガスをシールドガスとして使用する場合、一酸化炭素が発生し中毒の原因となります。一酸化炭素は無色無臭で気づきにくく、意識障害や痙攣を引き起こす危険性があります。
密閉空間や換気不足の現場で特に顕著に表れる問題なので、有害物質の安全対策として、防塵マスクや送気マスクの着用の徹底と局所排気装置といった設備投資を行いましょう。
アーク溶接による事故事例・ヒヤリハット例
アーク溶接による事故事例・ヒヤリハット例として厚生労働省が発表している以下の3つの事例を紹介します。
- 事例① 猛暑の中でのアーク溶接作業中に感電死
- 事例② 火花が燃料油に引火し火傷
- 事例③ 溶接棒の取替時にホルダー充電部に接触し感電
事例① 猛暑の中でのアーク溶接作業中に感電死
猛暑の工場内でアーク溶接作業中に感電死した事故が発生しています。被災者は汗で濡れた軍手と作業服を着用し、自動電撃防止装置のない溶接機を使用していました。結果として、溶接棒ホルダーから通電し体を経由して感電に至ったと推定されています。
原因は装置の未設置、保護手袋不使用、暑熱環境での換気不足、安全教育の欠如です。安全対策として、自動電撃防止装置の導入や乾いた保護具の着用、酷暑時の換気・送風、特別教育の実施が重要とされています。
アーク溶接の安全対策が行き届いていなかった典型的な事例です。
こうした「少しくらい対策を怠っても問題ない」との気の緩みが死亡事故につながるので、安全対策は作業者も管理者も意識しましょう。
※何度注意をしても不安全行動が繰り返される根本的な原因と対策について、行動科学の観点で解説している資料「繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網」もあわせてご覧ください。
事例② 火花が燃料油に引火し火傷
アーク溶接中に火花が燃料油へ引火し、作業者3名が火傷を負った事例があります。発端は溶接コードが近くに置かれていたポリタンクに引っかかり、転倒した容器から混合油が流出しました。
さらに容器のふたが閉められておらず、飛散した油に火花が触れ炎上。原因は、引火性物質を作業現場に置いた管理不備と、作業員が特別教育を受けていなかったことです。
安全対策として、燃料容器は必ず作業場から離して保管し、ふたを確実に閉めることが求められます。
「火災リスクを軽視した配置ミス」が重大事故につながる事例です。溶接前の周囲環境確認を作業者は意識し、管理者は徹底させる、それだけでも事故は防げます。
なお、作業員の不注意や安全意識の低下による「ヒューマンエラー」は、単なる注意喚起や直接指導ではなかなかゼロにできません。ヒューマンエラーが根本的に生じない「仕組み作り」が重要ですが、その本質的な安全教育について解説された資料「ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育」もあわせて参考にすると、安全対策の具体的なヒントが得られると思います。あわせて参考にしてみてください。
事例③ 溶接棒の取替時にホルダー充電部に接触し感電
アーク溶接作業中、溶接棒の取替時にホルダーの充電部へ誤って接触し、作業者が感電死する事故が発生しました。
被災者は暑さの中で衣服が汗に濡れており、通電条件が整ったことで致命的な電撃となったと推定されています。さらに自動電撃防止装置が未設置であったことも被害を大きくしました。
事故原因は、濡れた衣服や保護具未使用による絶縁不良、そして安全装置の欠如です。安全対策としては、自動電撃防止装置や絶縁形ホルダーの導入、革手袋や乾いた作業服の徹底、安全教育の強化が挙げられるでしょう。
同様の事故が起こらないように事例からアーク溶接における安全対策を意識してください。
アーク溶接の安全対策7つ
ここまではアーク溶接の危険性や事故の事例を解説してきましたが、「では具体的にどういう安全対策をするべきなの?」と疑問を抱く方に向けて、以下の7つの方法を紹介します。
なお再発防止策は、口頭指導を何度実施してもなかなか浸透しないのが実状です。安全ルールが守られるための教育アプローチとして「動画マニュアル」が活用されるケースが増えていますが、詳しい改善効果や事例は以下の資料で紹介しています。
>>「再発防止策の「伝わらない」「守られない」を解消する動画マニュアルの活用事例」を見る
ベテラン社員の技術やカンコツの可視化
アーク溶接は熟練者の勘や経験、いわゆる「カンコツ(暗黙知)」に依存する部分が多くあります。例えば、溶接棒を母材に当てる角度やアーク長の保ち方は、数字や文章だけでは伝えにくいのが実情です。そのため、教育の属人化が進み、新人が安全な作業手順を理解するまでに時間がかかりがちです。
したがって、アーク溶接における重要な安全対策としては「カンコツ(暗黙知)を視覚的に理解できるマニュアルを整備する」ことが挙げられます。いわゆる、ベテラン社員の技術の見える化です。例えば「動画マニュアル」は文字による説明が不要な教育アプローチで、特に工場を中心に広く導入されています。
※動画マニュアルの例(出典:児玉化学工業株式会社)
※「tebiki」で約10分で作成
上記は、工場向け動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」で作成された動画マニュアルです(サービス資料はこちら)。
このように動画であれば、例えば微妙な姿勢や溶接トーチの動きを繰り返し確認でき、紙の手順書より理解が進みます。外国人にも視覚的にわかりやすく、製造業に特に多い言語の壁による事故を防げるでしょう。
属人化を排除し、教育内容を均一化することで、労災発生率を低下させる効果も期待できます。アーク溶接の安全対策では、動画マニュアルなどを利用して「カンコツの可視化」しましょう。
※動画マニュアルが工場の安全対策にもたらす効果や実際の事例は、以下の資料から詳細を確認できます。
>> 「動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例(pdf)」を見てみる
危険予知(KY)活動の実施
危険予知(KY)活動とは、事故リスクを事前に話し合って対策を決める取り組みのことです。具体的には4R法と呼ばれる手順を踏みます。第1Rでは作業現場に潜む危険を洗い出し、第2Rで本質的なリスクを絞り込みます。次に第3Rで防止策を立案し、第4Rで実行可能な行動目標を設定します。
※危険予知活動(KY活動)の進め方の詳細は「KY活動(危険予知活動)の進め方は?記入例文やネタ切れ対策を紹介」でも解説しています
アーク溶接なら、まずは第1R(現状把握)で「電源ケーブルが水に濡れて感電する恐れ」といった危険を特定しましょう。次に第2R(本質追究)で「濡れが感電リスクを高める」という原因に絞り込みます。
第3R(対策樹立)では「防水カバーを設置し、毎日点検を行う」という防止策を定め、第4R(目標設定)として「点検の実行徹底」「指差し呼称で確認漏れを防止」「ヒヤリハット体験の共有による再発防止」を具体的な行動目標にします。
KY活動は形式的に終わらせてはならず、作業者と管理者の全員で参加して、職場全体の安全意識を高めていきましょう。
関連資料:労災ゼロ!形骸化したKYTから脱却する動画KYTとは
作業手順の標準化
アーク溶接に限らず、安全対策の要は「標準化」です。読み手によって解釈が異なる文章マニュアルや、現場で読まれにくい紙のマニュアルでは十分活用できません。
そのため、誰が見ても同じ解釈となる資料を整備する必要があります。例えば映像や動画による手順書が挙げられます。溶接棒の角度やアーク長の調整など、文章だけでは伝わりにくい作業も、動画ならすぐに理解できます。
標準化がなかなかうまくいかない多くの場合、現場教育の体制に課題があるケースが多いです。しかし、これは個々人の問題というよりも、そもそも工場や製造業は現場教育を推進すること自体非常に難易度が高いという構造的な側面があります。
現場教育の本質的な進め方を含め、詳しくは以下の資料で解説していますのであわせて参考にしてみてください。
>>「新人教育に失敗する製造現場に潜む3つの構造的要因と新しい教育アプローチ」を見る
感電対策
アーク溶接は高電圧を扱うため感電リスクが常に伴います。ここでは感電対策として具体的に以下の3つを紹介します。
- 絶縁手袋・安全靴といった保護具や乾いた作業服
- 溶接機・ケーブルの点検と電源管理
- 感電事故につながる典型的な作業ミスと防止法
絶縁手袋・安全靴といった保護具や乾いた作業服
感電防止には、絶縁手袋や安全靴の着用は絶対です。アーク溶接では二次無負荷電圧が50V以上となり、汗や湿気で導電性が高まると100mAを超える電流が流れ、死亡事故につながる恐れがあります。
乾いた作業服を着用し、濡れた状態で作業しないことも絶対です。革製の前掛けや足カバーはスパッタの飛散防止と同時に絶縁効果があるので活用しましょう。保護具は月1回以上点検し、破損や劣化があれば即時交換しましょう。
安全靴はJIS規格適合品を選び、絶縁性能を確保し、作業員が安心して作業できる環境を整えることが大切です。
関連資料:ヒューマンエラー による労災を未然防止する安全教育
溶接機・ケーブルの点検と電源管理
感電事故を防ぐには、溶接機やケーブルの点検を欠かさず行いましょう。特にケーブルの被覆破損は感電の主要因であり、絶縁不良が確認された場合は直ちに交換が必要です。
溶接機には漏電遮断器を設置し、作業前に必ず動作確認を行いましょう。また、自動電撃防止装置を備えることで二次電圧を自動的に遮断でき、感電リスクを抑えられます。
電源スイッチは作業者が容易に操作できる位置に配置し、離席時には必ずオフにすることが基本です。さらに、ケーブル接続部は防水カバーで保護しましょう。
電源の管理は従業員の命を守るため、企業が一丸となり毎日の点検を習慣化しましょう。
※何度注意をしても不安全行動が繰り返される根本的な原因と対策について、行動科学の観点で解説している資料「繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網」もあわせてご覧ください。
感電事故につながる典型的な作業ミスと防止法
アーク溶接で多い感電事故は、溶接棒の取替時に通電部へ誤って触れるケースです。厚生労働省の事例でも、31℃を超える猛暑下で汗により衣服が濡れ、100mAを超える電流が体内を流れ死亡した事故が報告されています。感電防止のために、必ず電源を切ってから溶接棒の交換を行い、指差し呼称で確認漏れを防ぎましょう。
また、濡れた手袋や作業服を着用したまま溶接機を扱うことも感電による死亡事故につながります。
作業者の命を守るために何度でも言いますが、乾燥した装備に切り替える習慣を徹底させましょう。さらに、単独作業はリスクが高いため、相互確認を行う体制を整えて、災害発生率を抑える試みも有効です。
関連資料:「工場の労災ゼロを実現する、安全教育の新常識」を見てみる
火災対策
アーク溶接は火花や高熱を伴い火災の危険性が高い作業です。ここでは火災対策として以下の2点を解説します。
- 作業環境から可燃物を除去
- 消火器・消火設備の配置と使用
作業環境から可燃物を除去
火災を防ぐためには、作業環境から可燃物を徹底的に除去しましょう。アーク溶接では約1,500℃以上の高熱や1m以上飛散する火花が発生するため、わずかな紙くずや布切れでも着火源となります。
現場点検を実施し、作業開始前に半径5m以内の可燃物を完全に撤去することが推奨します。どうしても移動できない場合は耐火シートや防炎カーテンで覆い、火花が触れないように保護する必要があります。
また、床面の油分や木製パレットも着火リスクが高く、作業前に清掃と整理を徹底することが大切です。
消火器・消火設備の配置と使用
火花やスパッタが原因で火災が発生することを想定し、被害を小さくする仕組みと環境を整えましょう。
そのために、消火器や消火設備を現場に適切に配置し、誰でも即座に使用できる状態を保つことが重要です。特に溶接現場では粉末消火器を10m以内ごとに設置することが望ましく、消火栓やホースの使用訓練も定期的に行う必要があります。
さらに、消火器の有効期限や圧力ゲージの確認は月1回を目安に実施し、整備不良による不作動を絶対に防ぎましょう。一般的に初期消火が30秒以内に行えれば火災の延焼を70%以上防げるとされ、迅速に対応できる仕組みと環境を作れば、作業者のやけどや死亡事故を防げます。
関連資料:ヒューマンエラー による労災を未然防止する安全教育
有害物質対策
アーク溶接ではヒュームやガスが大量に発生します。そこで以下の2つの有害物質対策を行いましょう。
- 防塵マスクと呼吸保護具の活用
- 有害物質から身を守るための換気装置の活用
防塵マスクと呼吸保護具の活用
アーク溶接では、金属ヒュームやオゾンなどの有害物質が発生し、吸入すると健康被害を招きます。ヒューム濃度は作業環境により法定基準を超える場合もあり、呼吸器保護具の使用は必須です。特に防塵マスクや防毒マスクを選定する際は、国家検定合格品を使用することを徹底しましょう。
作業時間が1時間を超える場合や連続作業では、防塵マスクだけでなく、送気マスクや電動ファン付き呼吸用保護具を併用することが効果的です。また、フィルターの交換は目詰まりや劣化を確認して定期交換を徹底する必要があります。
保護具を正しく使用すれば、有害物質の吸入リスクを確実に低減できます。
関連資料:「工場の労災ゼロを実現する、安全教育の新常識」を見てみる
有害物質から身を守るための換気装置の活用
アーク溶接では、作業中に目に見えない細かい粉じん(ヒューム)が空気中に大量に舞い上がります。オーストラリアの研究機関AIOHの調査によると、呼吸すると肺まで入り込むレベルのヒュームが 1〜2 mg/m³ 前後、より大きな粒子も含めると数mg/m³に達することがあります。数mg/m³は、長時間浴び続けると 咳や呼吸器疾患、金属熱などの健康被害につながるレベルとされています。
さらに、オゾンや窒素酸化物、一酸化炭素といった有害ガスも発生し、条件次第では頭痛・めまい・中毒症状を引き起こす危険があります。
こうしたリスクを減らすためには、まず局所排気装置を溶接点のすぐ近くに設置することが効果的です。加えて、作業場全体の換気を行うと、空気中の濃度をかなり下げられます。
有害光線対策
アーク溶接では紫外線や赤外線が強く発生し、目や皮膚に深刻な障害を与えます。ここでは有害光線対策として以下の2点を解説します。
- 適切な遮光面・保護眼鏡を選ぶ
- 遮光カーテンで周囲作業者を守る工夫
適切な遮光面・保護眼鏡を選ぶ
アーク溶接では紫外線(波長200~380nm)や可視光線中の青光(400~570nm)が強く発生し、電気性眼炎や網膜障害を引き起こします(出典:日建連 Q&A, 鉄骨工事 溶接 アーク光障害)。
例えば、ガスシールドアーク溶接で100A〜300A程度の電流を使う場合、遮光度番号11〜12の遮光ガラスやレンズが推奨されています 。
遮光面や保護眼鏡を選ぶ際は、JIS規格に適合しているものを使い、作業電流に見合った遮光度番号か確認しましょう。
また、レンズやプレートがキズや汚れで視認性を失わないよう定期的に交換・清掃する必要があります。遮光面は正しく使えば、目や肌への光線被害を大幅に低減できます。
遮光カーテンで周囲作業者を守る工夫
アーク溶接の光線は点火作業者だけでなく、周囲の作業員にも影響を与えます。遮光カーテンを設置して、側方や後方への有害光線の漏れを防ぐことが重要です。
遮光カーテンは難燃性素材を使用し、透過率が低いものを必ず選びましょう。可能であれば、床から天井近くまでカーテンを伸ばし、光線の回り込みを抑える構造にします。
カーテンの設置位置は溶接作業者と他作業者の動線を考慮し、直線光が漏れやすい場所を重点的に覆うことが効果的です。
また、カーテン自体が破れたり劣化したりすると光線が透過するリスクが高まるため、定期点検・交換を行いましょう。
関連資料:「工場の労災ゼロを実現する、安全教育の新常識」を見てみる
危険な作業の安全対策に成功している企業事例
アーク溶接のような危険作業の安全対策を浸透・徹底している製造業の事例を紹介します。様々な危険作業が飛び交うなか、従業員の安全が守られている工場はどのような安全対策を導入しているのか、本セクションで参考にしてみてください。
- コスモ石油株式会社:安全な手順やヒヤリハットを動画で可視化
- トーヨーケム株式会社:危険な作業手順による事故を映像で再現・周知
コスモ石油株式会社:安全な手順やヒヤリハットを動画で可視化
コスモ石油株式会社は、国内有数の石油精製・販売企業であり、堺製油所は京阪神エリアに燃料を安定供給する重要拠点です。同社にとって「安全第一」は経営の最優先課題であり、火災や爆発のリスクを抱える石油プラントでは、生産効率よりも事故防止を優先する姿勢を徹底しています。
▼事例インタビュー動画▼
しかし、従来の教育は紙マニュアルやOJTに依存しており、専門用語が多く動きのある作業を正確に伝えきれないという課題を抱えていました。新人や中途採用者の増加により教育負担が膨大化し、労災事例の周知や設備管理の習熟に時間がかかる問題も顕在化していました。
そこで同社が導入したのが動画マニュアル(tebiki現場教育)です。
映像を通じて複雑な作業や労災事例を視覚的に共有できるようになり、安全教育の効率化と再現性が向上しました。さらに協力会社との安全会議でも災害事例を動画で周知し、現場レベルの安全意識を高める効果を実現。結果として教育コスト削減と安全対策の定着を同時に進められています。
>>工場向け動画マニュアル「tebiki現場教育」のサービス資料はこちら
トーヨーケム株式会社:危険な作業手順による事故を映像で再現・周知
トーヨーケム株式会社は、東洋インキグループの中核企業としてポリマーや塗加工事業を担い、接着剤や機能性フィルム、医療製品などをグローバルに展開しています。
同社の課題は、若手社員への技術伝承が進まず、属人的なOJTに依存して教育の質にムラが生じていたことです。特に、頻度の低いメンテナンス業務では「○○さんしかできない」という属人化が常態化し、業務効率や安全性に影響していました。
そこで同社が導入したのが動画マニュアル(tebiki現場教育)です。従来は紙マニュアルで半日以上かかっていた手順共有が、動画化によって1時間程度に短縮され、作成工数は約1/2に、OJT時間も約2/3に削減されました。
さらに、業務を映像で可視化することで習熟度の均一化が進み、教育のバラツキや不安全行動のリスクも低減。タブレットで現場から即座に動画を確認できる環境が整ったことで、安全意識の底上げにもつながりました。結果として、教育レベルを統一し、属人化を防ぎながら安全対策を行うグローバル企業として市場をけん引しています。
>>工場向け動画マニュアル「tebiki現場教育」のサービス資料はこちら
アーク溶接の安全対策まとめ:管理者が仕組みを作り、作業員が安全対策を徹底する
アーク溶接は感電や火災、有害光線・ヒュームによる健康被害など、多くのリスクを伴う危険作業です。
労災事例からも明らかなように、事故は「少しの油断」や「教育不足」から発生します。
安全を守るには、感電・火災・有害物質・光線ごとの具体的な安全対策や動画を活用した技術伝承など、仕組みで安全を定着させることが必要です。
管理者は教育と環境整備を徹底し、作業員は日常的に安全確認を実践することで、現場全体のリスクを減らし安心して作業できる職場を作れるでしょう。