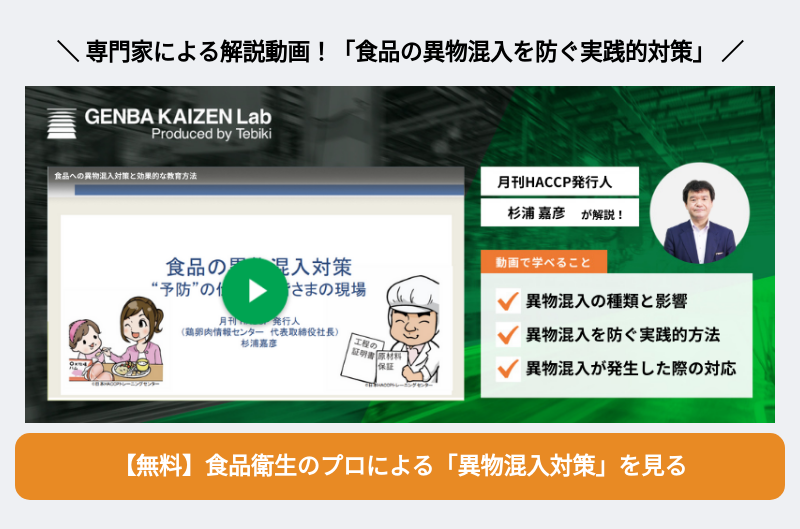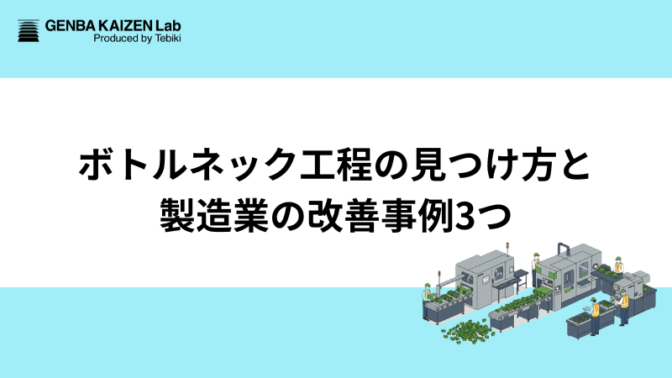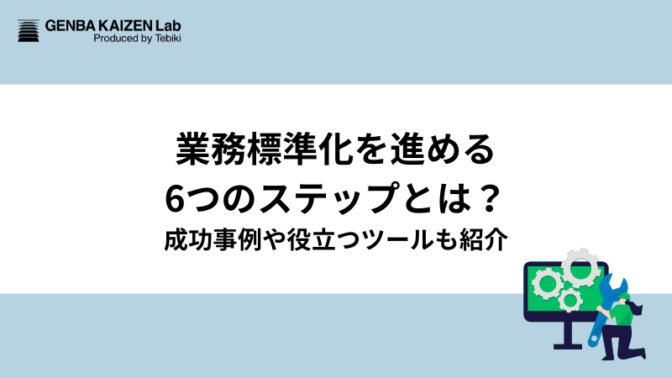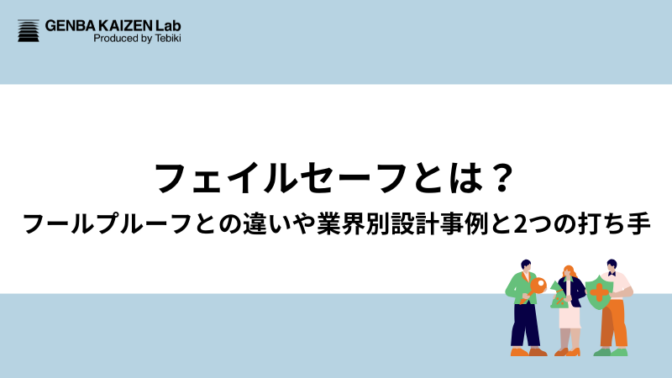かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」、かんたんデジタル現場帳票「tebiki現場分析」を展開する現場改善ラボ編集部です。
OPRPは、HACCPにおいてCCPの次に重要なポイントです。しかし「CCPやPRPとの違いがわかりにくい」と感じる方は少なくありません。
そこで本記事ではOPRPの概要から管理方法、実施手順まで詳しく解説します。CCPやPRPとの違いもわかりやすく説明しているので、ぜひ参考にしてください。
また、「そもそもHACCPとは?」という基礎から学びたい方は、無料のセミナー動画をご視聴ください。HACCPに基づいた衛生管理の基本をわかりやすく解説しています。
目次
OPRPとは?食品業界における意味と目的
OPRPは、HACCPの根幹となる衛生管理の要素の1つです。ここでは、OPRPの意味と目的について解説します。
oprpは「衛生管理のルールに基準を設けること」
OPRP(Operation Prerequisite Program)は、「オペレーション前提条件プログラム」と訳します。わかりやすく説明すると、「食品衛生を守るための基本的な取り組み(前提条件プログラム)」に対し「基準を設けて管理・運用(オペレーション)」することです。
例えば、工場自体が不衛生では、CCP(重要管理点)でどれだけ衛生管理を徹底していても、健康を害するおそれのある要因(ハザード)を防ぎきれません。そこで衛生管理のルールに基準を設け、チェックできる仕組みを作ることがOPRPです。
oprpの目的
OPRPの目的は、健康を害するおそれのある要因(ハザード)を減らし、食品の安全を守ることです。OPRPが適切に実施されることで、PRP(前提条件プログラム)の効果が最大限発揮され、CCP(重要管理点)の管理もスムーズに行えます。
なお、「CCP」と「PRP」は、OPRPと混同されやすい概念です。次項では、それぞれの違いについて詳しく解説します。
OPRPとCCP・PRPの違いをわかりやすく解説
OPRPと混同されがちなCCP・PRPの違いについて解説します。3つの違いをまとめた表もご用意しているので、ぜひご覧ください。
- CCPはOPRPより厳しい基準を設けている!
- PRPにチェックできる値を設けたのがOPRP!
- OPRPとPRP・CCPの違い|まとめ
CCPはOPRPより厳しい基準を設けている!
厚生労働省「HACCP入門のための手引書」によると、CCPとは以下のポイントを指します。
特に厳重に管理する必要があり、かつ、危害の発生を防止するために、食品中の危害要因(ハザード)を予防もしくは除去、または、それを許容できるレベルに低減するために必須な段階。
CCPとは「健康を害するおそれのある要因(ハザード)を含む製品が、消費者の手に届かないよう、確実かつ重点的に管理すべきポイント」です。CCPでハザードを確実に取り除くため、「とどめを刺す」工程とも呼ばれます。
一方で、OPRPはCCPほど厳格な管理を行いません。CCPのように「とどめを刺す」のではなく、ハザードが許容範囲を超えないようにコントロールする役割を果たします。
加熱殺菌におけるCCPとOPRPの違いを見ていきましょう。
| CCP | OPRP |
|---|---|
| 113℃以上、80分間以上の加熱殺菌 | 120℃以上、80分間以上の加熱殺菌 |
上記のCCPを設定した場合、113℃から1℃でも温度が下がってしまうと食品の安全性は損なわれてしまいます。
そこで重要になるのがOPRPです。「120℃以上、80分間以上の加熱殺菌」とCCPを遵守できる範囲でOPRPを設定しておくと、食品の安全性は損なわれることなく、120℃から下がった段階で対処できます。
つまり、CCPは「一歩間違えると大きな損失につながる可能性がある」のに対し、OPRPは「基準から外れても修正が可能」なのです。
なお、CCPとの違いとして、OPRPが「環境を清潔に保つ」ことを目的としているケースも見受けられます。詳しくは「CCPの状態を保つための管理」で解説します。
PRPにチェックできる値を設けたのがOPRP!
厚生労働省「HACCP入門のための手引書」によると、PRPとは以下のように示されています。
一般的衛生管理プログラム
(Prerequisite Programs:PRP)
HACCPシステムを効果的に機能させるための前提となる食品取扱施設の衛生管理プログラム。前提条件プログラムともいわれる。
PRP(前提条件プログラム)は、食品の製造環境を衛生的に保ち、ハザードを最小限に抑えるための基本的な取り組みのことです。具体的には、清掃や衛生管理、従業員の健康管理など食品衛生の土台となる対策が含まれます。
しかし、PRPは「管理する基準」を明確に設定できず、モニタリングが難しいという課題があります。そこで、PRPに「Operation(オペレーション)」の要素を加え、具体的な基準を設けて管理できるようにしたものがOPRP(オペレーション前提条件プログラム)です。
▼PRPとOPRPの例▼
| PRP | OPRP |
|---|---|
| 機械・器具は毎日清掃し、適切な衛生状態を維持する | ・洗浄後、次亜塩素酸ナトリウム溶液(濃度200ppm)で消毒する ・ATPふきとり検査で500RLU以下にする |
つまり、PRPが「基本となる衛生管理のルール」であるのに対し、OPRPは「その衛生管理のルールを数値や基準で管理し、チェックできる仕組みを整えること」なのです。
OPRPとPRP・CCPの違い|まとめ
OPRPとPRP、CCPの違いを表にまとめると、以下の通りです。
| PRP | OPRP | CCP | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 基本となる衛生環境のルール | PRPに基準を設けてチェックする | ハザードにとどめを刺す重要な工程 |
| (PRPを実施しても残ってしまったハザードのコントロール) | |||
| 対象 | 特定のハザードに特化しない | 特定のハザードに対して実施される | |
| チェック体制 | なし | あり | あり |
| 例 | 機械器具は清潔な状態を保つ | ATPふきとり検査で500RLU以下 | ― |
| ― | 120℃以上、80分間以上の加熱殺菌 | 113℃以上、80分間以上の加熱殺菌 | |
| 基準から外れた場合 | 柔軟に対応 | 厳しく対応 | |
OPRPとPRP・CCPの違いを理解できたところで、次章ではOPRPをさらに深掘りします。具体的な管理方法や実施手順について見ていきましょう。
OPRPでは何をする?OPRPの管理方法をポイント付きで解説
OPRPでは主に「7S活動」や「温度管理」を行います。それぞれの管理方法を実施のポイントと一緒に見ていきましょう。
なお、7S活動や温度管理のほかにも、虫やホコリなどの汚染物質を防ぐためのゾーニングや、器具・設備の衛生管理も重要な要素となります。
食品製造で特に警戒すべき「異物混入」を防ぐ対策については、以下の専門家による解説動画をご覧ください。
7S活動
7S活動とは、整理・整頓・清掃・洗浄・殺菌・しつけ・清潔の頭文字である、7つのSからなる活動のことです。
OPRPとして管理されるのは、主に「清潔」「洗浄」「殺菌」の項目です。基本となる衛生ルール(PRP)だけではハザードに対する管理が不十分である箇所に設定します。
▼OPRPの例▼
- 作業台の細菌量は(ATP検査)500以下
- 手指の細菌量を2,000RLU以下にする
7S活動の概要や具体例について知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。
関連記事:食品衛生7S「具体例」や「進め方」は?5Sとの違いも解説
温度管理
OPRPにおける温度管理は、大きく分けて2つのパターンがあります。
CCPをスムーズに運用するための管理
前項「CCPはOPRPより厳しい基準を設けている!」の通り、CCPは「一発アウト」な一方、OPRPは「アウトな場合は修正」できます。具体的な管理方法は以下の通りです。
- 他の計測器に切り替えて再測定
- 加熱・冷却システムの出力調整
- 加熱・冷却システムの異常がないか調べる
また、計測器の正確性も重要です。誤差がない状態を維持できるよう、定期的な校正と点検を実施しましょう。
CCPの状態を保つための管理
CCPでハザードを確実に除去・低減したうえで、その状態を維持するための基準を設定します。具体的には、CCPで「とどめ」を刺した食品がその後の工程で再び汚染されないよう、継続的にモニタリングします。
▼OPRPの例▼
- 10℃以下で保管~出荷する(低温管理が必要な食品の場合、細菌の増殖を防ぐ)
- 15℃~20℃で保温~出荷する(一定の温度を維持することで、品質を保持しつつ安全性を確保)
なお、温度管理における詳しい基準値や記録頻度について知りたい方は以下の記事をご覧ください。
関連記事:【テンプレートあり】HACCPに対応した温度管理の方法!冷蔵庫の温度や記録頻度は?
OPRPの具体的な実施手順
ここまでOPRPについて解説してきましたが、導入するには5つの段階を踏む必要があります。
- ①OPRPの導入準備
- ②管理基準の設定
- ③従業員への周知
- ④OPRPの運用
- ⑤評価と見直し
OPRPをはじめ、HACCPの要件を満たす業務の管理は煩雑になりがちです。「管理工数を減らして効率化したい…」「記録が精一杯で、分析まで手が回らない…」とお悩みの方は、以下のハンドブックもぜひご参照ください。
>>HACCP対応の課題を解決!管理業務を効率化する3つのステップと活用例を見てみる
①OPRPの導入準備
製造工程図(フローダイアグラム)にて、CCPほど厳しい管理は必要がないものの、継続的なモニタリングが必要なポイントを洗い出します。加えて、CCPを補完するために必要なOPRPがないかも検討します。
フローダイアグラムが作成できるテンプレートについては、以下のフォームから無料でダウンロード可能です。ぜひご活用ください。
▼フローダイアグラムのダウンロードフォーム▼
②管理基準の設定
OPRPを確認できる基準値を設定します。基準値は具体的かつ測定可能な数値であることが重要です。
▼OPRP数値例▼
- 120℃以上、80分間以上の加熱殺菌
- 2時間以内に10℃以下まで冷却する
また、基準値は科学的データや専門的な知見に基づいて設定する必要があります。大量調理衛生マニュアルやHACCPに基づく衛生管理のための手引書を参考にすると良いでしょう。具体的な数値は関連記事をご覧ください。
関連記事:【テンプレートあり】HACCPに対応した温度管理の方法!冷蔵庫の温度や記録頻度は?
③従業員への周知
現場で働く従業員がOPRPを運用できるよう教育を行います。
- どの工程にOPRPが適用されるのか
- 設定した基準をどのようにチェックするのか
- 基準を外れた際にどのような対応をすべきか など
上記を指導し、従業員が正しく実施できるようマニュアルを整備します。
このとき「マニュアルの動画化」がおすすめです。動画ならば、OPRPの細かな動作や判断基準を指導できます。食品製造業で動画マニュアルを活用するメリットや実際の事例・効果について知りたい方は、以下のリンクから資料をご覧ください。
>>食品製造業での動画マニュアル活用事例をみる
④OPRPの運用
実際にOPRPを運用し、設定した基準に従って管理を行います。OPRPの管理状況を記録に残すことで「⑤モニタリングと見直し」の際に継続的な評価・改善が行えます。
記録を残す際は「デジタル帳票の活用」がおすすめです。過去のデータをすぐに検索・活用できるため、OPRPの見直しに役立ちます。しかし「慣れ親しんだ紙帳票から変えるのは不安…」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
そこで、デジタル帳票導入に向けたハンドブックをご用意いたしました。導入の流れについても詳しくご案内しているため、デジタル帳票を検討されている方はぜひご覧ください。
>>デジタル帳票は本当に便利?メリットや導入の費用対効果をみる
⑤モニタリングと見直し
現場の状況に即した管理方法かどうかを定期的に見直します。
| 設定した管理基準は適切か? | 基準値が厳しすぎる・緩すぎるなど |
| 運用が実際の作業工程に適しているか? | 現場負担が大きすぎないかなど |
| 記録や管理の方法は効果的か? | 測定頻度やチェック項目の確認 |
上記の項目をチェックし、より効率的な運用を目指しましょう。
OPRPの実施には「従業員教育」と「モニタリングの見直し」が重要
動画マニュアル「tebiki現場教育」
OPRPを実施するうえで重要なのは、業務の標準化です。標準化されていない場合、以下のような問題が発生します。
- 従業員間で実施方法にばらつきが生じる
- OPRPやCCPが誤って運用される
業務標準化のためにおすすめなのが動画マニュアルです。理想的な手順を視覚的に伝えられ、現場全体で統一した教育が可能になります。
なかでも「tebiki現場教育」は、動画を使ったマニュアルをかんたんに作成できるツールです。
▼動画マニュアル作成ツール「tebiki」紹介動画▼
- 動画の素材はスマホで撮影するだけ→ 手軽に現場のノウハウをマニュアル化
- 必要な機能のみを厳選したシンプルな操作性→ だれでも気軽に使用できる
- 全プランでアップロード本数が無制限 → 何本でも動画を保存・活用可能
さらに、テスト機能を使って従業員の理解度を図ることも可能です。CCPやOPRPの管理方法がどれだけ定着しているかを確認しつつ、教育の進捗を可視化できる機能も備えています。
従業員教育の新たな手段としても活用できる「動画マニュアルtebiki」について、詳しく知りたい方は以下の資料をご覧ください。
デジタル現場帳票「tebiki現場分析」
OPRPの運用に欠かせない「見直し」。しかし、データが正確でなければせっかく集めた情報も意味を成しません。さらに帳簿を紙で管理していると、紛失や劣化、保管スペースの確保といった問題が発生することも。
そこでおすすめなのが「デジタル現場帳簿tebiki」です。

「デジタル現場帳簿tebiki」を利用することで、現場の帳票をかんたんに作成・管理できます。
- 正常値や異常値の設定がかんたん→ 管理基準を明確にし、ミスを防ぐ
- どこにいても現場の状況を瞬時に確認可能 → 遠隔からでもリアルタイムでデータを把握
- 検索機能で該当情報をすぐに発見 → 必要なデータを素早く呼び出せる
とくに注目すべきはデータの分析・可視化機能です。OPRPの見直しを行う際、必要なデータを一から収集する必要はありません。わずか数十秒で必要なデータを選別・分析できます。そんな「デジタル現場帳簿tebiki」を詳しく知りたい方は、以下の資料をご覧ください。
>>かんたんデジタル現場帳票「tebiki現場分析サービス資料」を見てみる
まとめ
OPRP(オペレーション前提条件プログラム)とは、衛生管理のルールに基準を設け、チェックできる仕組みを指します。OPRPとCCPの違いは、CCPは「一歩間違えると大きな損失につながる可能性がある」のに対し、OPRPは基準から外れても修正が可能である点です。
OPRPを実施するうえで重要なのは、「従業員教育」「モニタリングと見直し」です。これらをより効率的に行うツールの1つとして、「tebiki」が挙げられます。
- 動画マニュアル「tebiki現場教育」:かんたんに動画を使ったマニュアルを作成できる
- デジタル現場帳票「tebiki現場分析」:現場の帳票をかんたんに作成・管理・分析できる
これら2つのサービスについて詳しく知りたい方は、ぜひ以下の資料をご覧ください。
おまけ:OPRPに関するよくある質問
最後に、OPRPに関する疑問として頻繁に挙げられるものをまとめました。
- OPRPにおける「処置基準」とはなんですか?
- OPRPにおける「許容水準」とはなんですか?
- OPRPと「許容限界」に関係はありますか?
OPRPにおける「処置基準」とはなんですか?
処置基準とは、OPRPで設定される値のことです。たとえば、OPRPが「120℃以上の加熱殺菌」の場合、処置基準は「120℃」です。
OPRPにおける「許容水準」とはなんですか?
許容水準とは、食品の安全に問題を引き起こさない範囲で許される変動の限界のことです。上記の「処置基準」が守られていれば、許容水準も同様に守られるため、超えることはありません。
OPRPと「許容限界」に関係はありますか?
直接的な関係があるのはCCPです。許容限界とは可能と不可能を分ける値で、1℃でも管理を怠れば「安全ではない」と見なされます。CCPにおける「合格ライン」と言い換えてもよいでしょう。
▼参照/引用
・厚生労働省|HACCP入門のための手引書
・厚生労働省|大量調理施設衛生管理マニュアル
・厚生労働省|HACCPに基づく衛生管理のための手引書