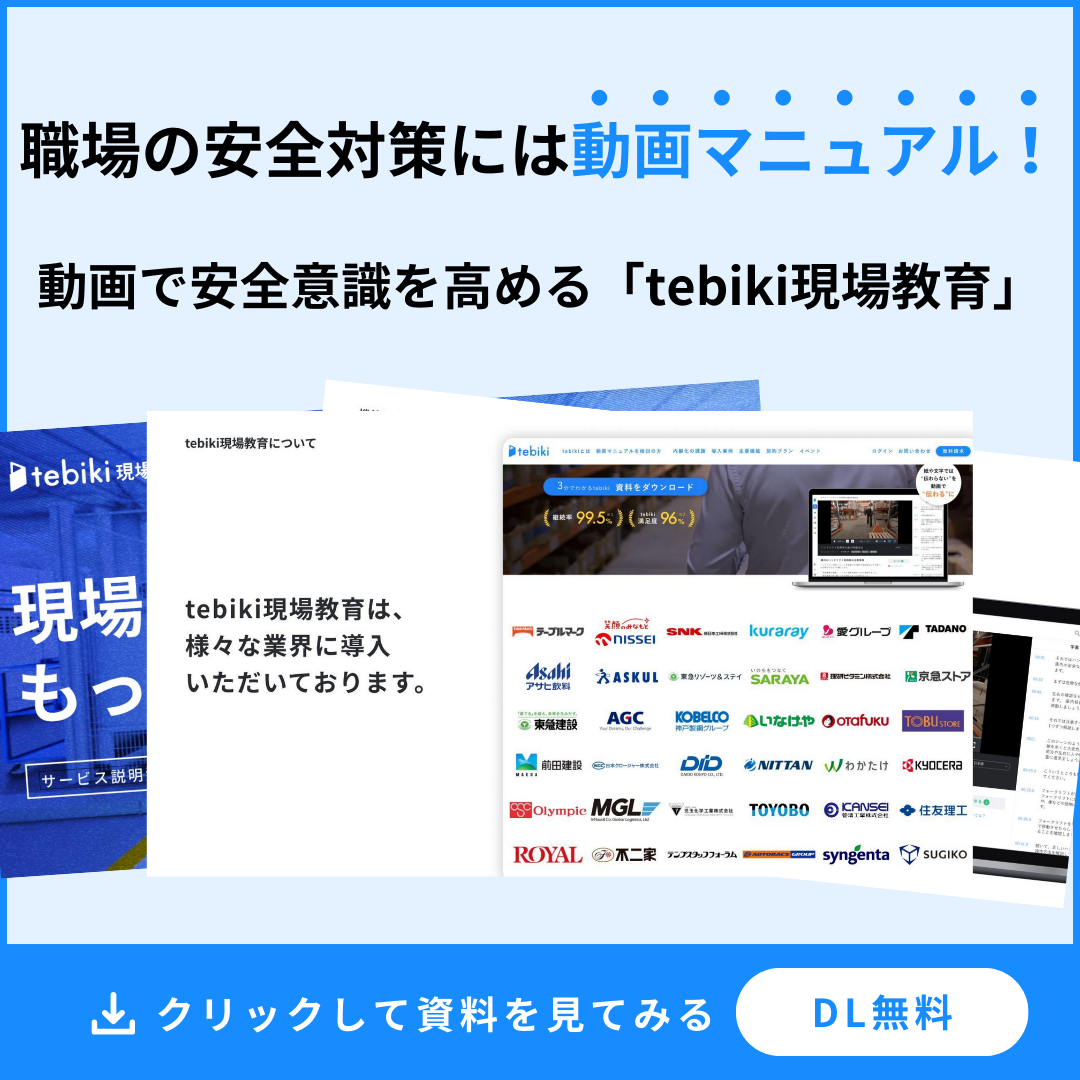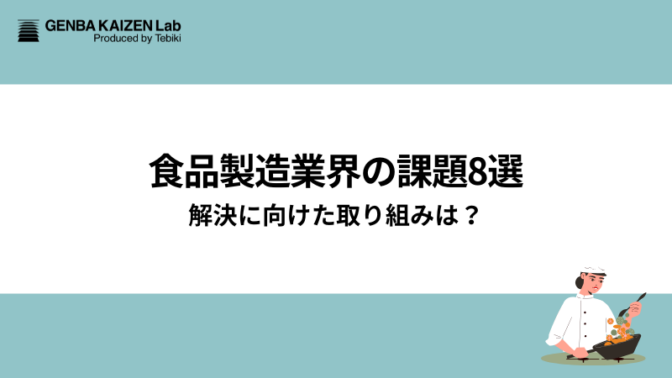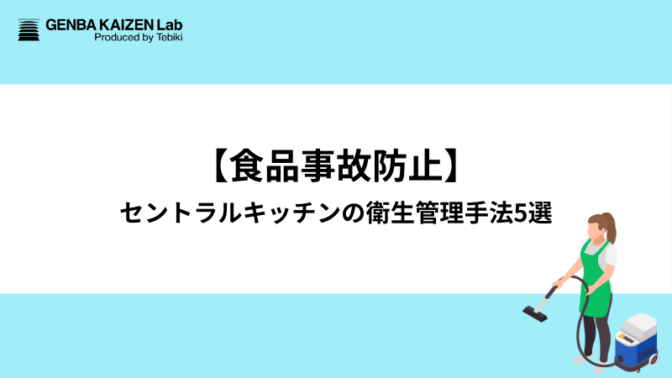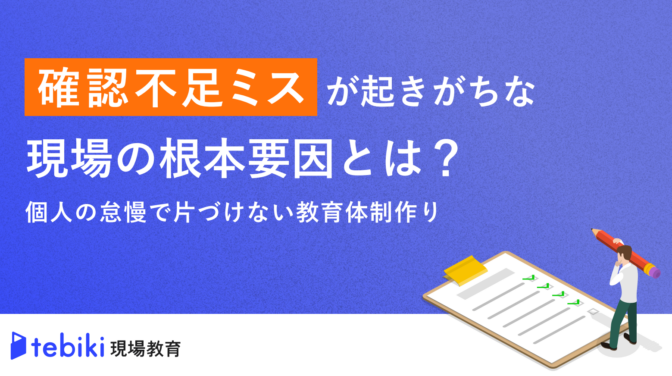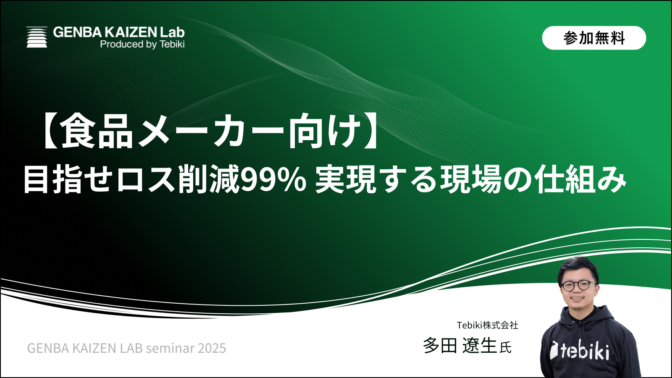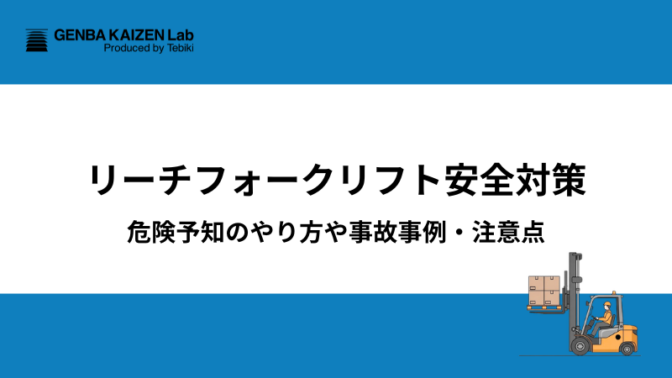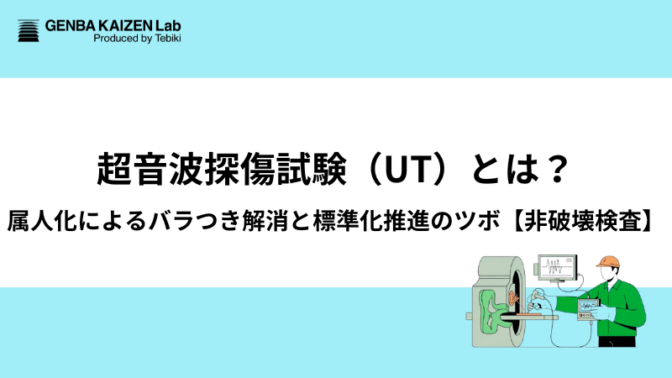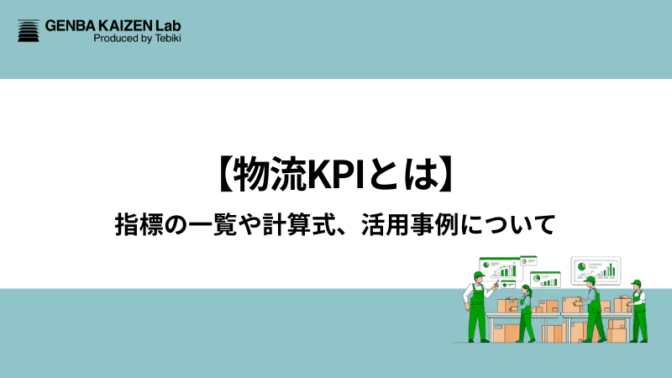安全衛生委員会とは、一定規模以上の事業場において設置しなければならないとされている組織です。しかし、安全衛生委員会は、注意しないと形骸化しやすい/会議が煮詰まってしまいやすいという問題があり、議論する際に工夫を凝らす必要があります。
そこで、2026年における安全衛生委員会のネタを月別にまとめた「安全衛生委員会ネタ年間スケジュール2026年版」を先に参考にしてみてください。
※元労働基準監督署署長「村木 宏吉」氏が監修
ここからは、安全衛生委員会のネタを選定する際のポイントや、安全意識を現場に定着させるための方法についても解説しています。労災や危険を未然防止するための現場・職場づくりを推進したい担当者様は、特に参考になると思います。
目次
安全衛生委員会とは
安全衛生委員会とは、労働者の安全と健康を確保するために、労働者の意見を汲み取り、安全で衛生的な職場環境を整える組織/会合です。安全衛生委員会は、労働安全衛生法で設置が義務付けられています。
安全衛生委員会で話し合うべき事柄は、厚生労働省ウェブサイトに詳しく掲載されています。わかりやすく噛み砕くと、以下の事項が代表的なものとなります。
- 安全に関して気にかかる、もしくは改善すべき事項
- 衛生に関して気にかかる、もしくは改善すべき事項
- 前回までの安全衛生委員会で挙がった事項の対策状況
- 産業医からのアドバイス
- 各部署等で行なっている安全・衛生対策の報告
- 他事業者/他社/他業界などで行われている安全衛生対策や事故事例の共有
- 各メンバーの気付き等の報告
- その他安全で衛生的な労働環境を整えるための取り組み等の提案
安全衛生委員会を「スムーズに進める方法」や「議題の選び方/ネタ例」などを知りたい方は、以下のリンクをクリックして『安全衛生委員会のガイドブック』をご覧ください。ネタ探しに使える2026年の年間スケジュールも掲載しています。
>>【無料で資料を見る】委員会のスムーズな運営のコツやネタの選び方とは?
【2026年2月】の安全衛生ネタ/テーマ一覧
2026年2月は、1ヶ月を通して「省エネルギー月間」および「サイバーセキュリティ月間(~3月18日)」が実施されており、また2月4日は「ワールドキャンサーデー(世界対がんデー)」となっています。それぞれ、効率的なエネルギー利用と職場環境の維持、情報セキュリティ意識の向上、そしてがんへの理解と予防・共生を深めることが意図されています。
※2026年における安全衛生委員会のネタを月別にまとめた「安全衛生委員会ネタ年間スケジュール2026年版」カレンダーはこちら
2月は暦の上では春(立春)を迎えますが、実際には一年で最も寒さが厳しく、乾燥もピークに達する時期です。インフルエンザなどの感染症対策はもちろん、乾燥による火災リスクや静電気による事故、また寒暖差によるヒートショックへの注意も引き続き欠かせません。
「省エネルギー月間」では、暖房器具の適切な使用やメンテナンスを呼びかけつつ、過度な節電によって作業環境の温度・湿度が損なわれ、健康被害や集中力低下を招かないようバランスを考える必要があります。
また、「ワールドキャンサーデー」をきっかけに、従業員のがん検診受診の推奨や、病気を抱えながら働く「仕事と治療の両立支援」について職場全体で理解を深めることも、現代の安全衛生における重要なテーマです。
そこでたとえばですが、以下のような議論を安全衛生のネタとしておすすめします。
| 省エネと快適な職場環境の両立 | 暖房器具の点検と安全な利用(火災・一酸化炭素中毒防止)、適切な湿度(40~60%)の維持によるウイルス対策、照明の効率化と作業照度の確保。 |
| 情報安全(サイバーセキュリティ)と労働安全 | テレワーク中のセキュリティルール再確認、偽メール(フィッシング)等への警戒、デジタル化に伴う作業負荷の管理。 |
| がんの予防と両立支援の周知 | 定期的ながん検診(職域検診・自治体検診)の受診推奨、がんに関する正しい知識の共有、病気になった際も安心して働ける相談体制や制度の確認。 |
| 冬の乾燥・静電気対策 | 静電気による引火事故防止(火気厳禁エリアの徹底)、乾燥による肌荒れや喉のトラブル対策、手指消毒による手荒れ防止。 |
「各月委員会を開催しているが、ネタが切れてしまった」という方は、安全衛生委員会ネタ年間スケジュールつきガイドブックを無料ダウンロードしてご活用ください。
▼2月に制定されている行事など▼
| 期間 | 行事内容 |
|---|---|
| 2/1~2/29 | 省エネルギー月間 |
| 2/1~3/18 | サイバーセキュリティ月間 |
| 2/4 | ワールドキャンサーデー |
2026年の安全衛生ネタ/テーマ例年間スケジュール
元労働基準監督署署長である村木氏に、安全衛生衛生委員会の各月のネタ/テーマ例をまとめていただいたものを編集部で2026年度版にブラッシュアップしました。各事業所で安全衛生委員会を行う際のヒントとしてご活用ください。
以下のフォームをご入力いただくと、本記事に掲載しているスケジュール一覧より詳細な年間スケジュールつきの安全衛生委員会ガイドブックを無料でダウンロードできます。「年間カレンダーを事業所に貼りたい」という方は、こちらをお使いください。
▼2026年間スケジュール▼
| 期間 | 行事内容 | |
|---|---|---|
| 1月 | 12月1日~1月15日 | 年末年始無災害運動 |
| 12月10日~1月10日 | 年末年始の輸送等に関する安全総点検 | |
| 1月15日~1月21日 | 防災とボランティア週間 | |
| 1月17日 | 防災とボランティアの日 | |
| 2月 | 2月1日~2月29日 | 省エネルギー月間 |
| 2月1日~3月18日 | サイバーセキュリティ月間 | |
| 2月4日 | ワールドキャンサーデー | |
| 3月 | 3月1日~3月31日 | 自殺対策強化月間 |
| 3月1日~3月7日 | 春季全国火災予防運動 | |
| 3月1日~3月8日 | 車両火災予防運動 | |
| 3月1日~3月8日 | 女性の健康週間 | |
| 3月1日~3月9日 | 子ども予防接種週間 | |
| 4月 | 4月1日~9月30日 | 熱中症予防強化キャンペーン |
| 4月6日~4月15日 | 春の全国交通安全運動 | |
| 4月7日 | 世界保健デー | |
| 5月 | 5月10日~5月16日 | 看護週間 |
| 5月14日~5月20日 | 看護の日 | |
| 5月14日~5月20日 | ギャンブル等依存症問題啓発週間 | |
| 5月31日 | 世界禁煙デー | |
| 5月31日~6月6日 | 禁煙週間 | |
| 6月 | 6月1日~6月30日 | 男女雇用機会均等月間 |
| 6月1日~6月30日 | 土砂災害防止月間 | |
| 6月1日~6月30日 | 環境月間 | |
| 6月4日 | 虫歯予防デー | |
| 6月4日~6月10日 | 歯と口の健康週間 | |
| 6月7日~6月13日 | 危険物安全週間 | |
| 6月10日~6月16日 | 火薬類危害予防週間 | |
| 6月23日~6月29日 | 男女共同参画週間 | |
| 7月 | 7月1日 | 国民安全の日 |
| 7月1日~7月7日 | フォークリフト安全週間 | |
| 7月1日~7月7日 | 全国安全週間 | |
| 7月1日~7月7日 | 全国鉱山保安週間 | |
| 8月 | 8月1日~8月31日 | 電気使用安全月間 |
| 8月1日~8月31日 | 食品衛生月間 | |
| 9月 | 9月1日 | 防災の日 |
| 9月1日~9月30日 | 心とからだの健康推進運動 | |
| 9月1日~9月30日 | 健康推進普及月間 | |
| 9月1日~9月30日 | 食生活改善普及運動 | |
| 9月9日 | 救急の日 | |
| 9月10日 | 世界自殺予防デー | |
| 9月21日~9月30日 | 秋の全国交通安全運動 | |
| 9月30日 | クレーンの日 | |
| 10月 | 10月1日~10月7日 | 全国労働衛生週間 |
| 10月1日~10月31日 | 体力つくり強調月間 | |
| 10月10日 | 目の愛護デー | |
| 10月12日 | スポーツの日 | |
| 10月17日~10月23日 | 薬と健康の週間 | |
| 10月23日~10月29日 | 高圧ガス保安活動促進週間 | |
| 11月 | 11月1日~11月30日 | 特定自主検査強調月間 |
| 11月1日~11月30日 | 過労死等防止啓発月間 | |
| 11月1日~11月30日 | ゆとり創造月間 | |
| 11月1日~11月30日 | 職業能力開発促進月間 | |
| 11月1日~11月30日 | 品質月間 | |
| 11月1日~11月30日 | 『しわ寄せ』防止キャンペーン月間 | |
| 11月5日 | 津波防災の日 | |
| 11月8日 | ボイラーデー | |
| 11月9日~11月15日 | 秋季全国火災予防運動 | |
| 11月24日~11月30日 | 医療安全推進週間 | |
| 12月 | 12月1日~12月31日 | 職場のハラスメント撲滅月間 |
| 12月1日~1月15日 | 年末年始無災害運動 | |
| 12月10日~1月10日 | 年末年始の輸送等に関する安全総点検 |
安全衛生のために必ず外せないネタ/テーマ
防災の日
毎年9月1日は、防災を啓発する日として「防災の日」が制定されています。防災の日は、甚大な被害をもたらした1923年9月1日の関東大震災の発生が由良となっています。
安全衛生委員会では、防災の日付近に、巨大地震が発生したらどのような行動をすればよいかをシミュレーションすると良いでしょう。職場で大きな地震に遭遇したら、まずは身を守る。そして、誰が、何をするか役割を決めておく。従業員はどこから逃げて、どこに集合するか。年1回は必ず防災に関する確認をするようにします。
熱中症
厚生労働省が発表した調査結果によると、仕事中に熱中症を発症した人は、2023年には1,000人を超えました。これは、2015年の2倍の数字です。ここ数年で急に異常気象が進みましたが、気温が38℃を超えるニュースに慣れてしまい、驚かなくなってきたのではないでしょうか? 危険にさらされているにも関わらず、当たり前になると鈍感になってしまうのが人間の性質です。
暑くなる前から、どのようなときに水分補給を忘れがちになるのか、体験談も交えて職場で話し合うと良いでしょう。ちなみに、政府が呼びかけを行っている「熱中症予防強化キャンペーン」は、4月1日から9月30日に行われています。
大雨・大雪
これも異常気象の1つですが、短時間にまとまった降雨降雪が頻繁に起きるようになりました。河川が氾濫して地下駐車場に水がたまり、車が水没するニュースをたびたび目にします。あるいは、冬になると一晩で、身長を超える積雪になることもあります。
多すぎる水は人を死に至らしめることを改めて認識し、警報が出たらどのタイミングで業務中断と帰宅指示をするか、ルールを確認しておくと良いでしょう。
感染症対策
冬場はインフルエンザやノロウイルス、風邪などの感染症が流行しやすい時期です。また、近年の新型コロナウイルスのように、新たな感染症が発生する可能性もあります。感染症が拡大すると、職場全体に影響を及ぼします。そのため、安全衛生委員会で、感染症対策の実施状況や感染症予防方法などを議題にあげて話し合うと良いでしょう。
感染症対策は毎年議題にあげて、「昨シーズンの対策で感染者数は減少したか?」「新しい対策案をどのように導入するか?」といった過去の感染症対策の成果を評価し、改善案を議論するのもおすすめです。
現場でウケる面白いネタ/テーマ
ヒヤリハット公募
危険予知トレーニング(KYT)を行っている企業は多いかと思います。安全衛生委員が職場を巡回して危険個所を見つけたり、絵を見せてみんなで危険な状況を想像してみたり、やり方は様々です。しかし、同じような危険個所の指摘になりがちで、徐々に飽きている従業員も少なくないでしょう。
そこで、従業員が経験したヒヤリハットや失敗談を公募して、職場に共有できそうなネタを集めるとよいでしょう。会社での体験だけでなく、休みの日に気づいたこと/買い物中に危ないと思ったことなど、日常生活に潜む危険も共有すると、従業員の興味を引きながら安全衛生について話し合えるでしょう。
現場で起きたヒヤリハットを労働災害防止などの安全対策に活かしたい方は、以下のリンクをクリックして「労災防止につながるヒヤリハット対策の心得」の解説動画をご覧ください。
>>【無料で動画を見る】労災を撲滅するヒヤリハット対策とは?
健康川柳
第一生命保険が企画しているサラリーマン川柳のように、社内でも自虐ネタ/時事ネタを川柳にして、身の回りで起きていることも面白く発表するのも良いでしょう。5-7-5という短い言葉にまとめるのは平安時代から続く日本独特の文化であり、若手社員からベテラン社員まで、職歴の長さに関係なく取り組める啓蒙活動になります。
「自分が目指す体型」や、「元気に遊びまわっていた若い頃に戻りたい想い」を短い句にまとめ、大賞として表彰するとより面白いかもしれませんね。
▼2024年のサラリーマン川柳ベスト10▼
改善提案の表彰(安全アイデア)
生産性の向上や作業を楽にするアイデアを出すことが多い改善活動ですが、安全衛生案を提案してもらうことも有効です。安全衛生委員会が審査してランク付けし、等級に応じた報奨を出せば、従業員は楽しみながらアイデアをたくさん出してくれるでしょう。安全で健全な職場から「良い製品」が生まれるので、品質の向上も期待できます。
最近注目されているネタ/テーマ
プチ筋トレ
コンビニ感覚で立ち寄れる「コンビニジム」の登場により、プチトレーニングをする人が増えています。少しでも健康でいたい、美しい体型を維持したいという意識の高まりを感じます。
「機器を使わなくても自席や自宅でできるトレーニング」を月1回紹介することで、腰痛のような労災を減らしたり、メタボ予備軍を減らす活動が推進できるでしょう。
快眠のコツ
睡眠の質を高める飲料やアイテムが話題になるほど、睡眠を意識している人が増えています。そのため、ゆったりと睡眠できるような方法についてアイデアを出し合うのもおすすめです。
ストレスや不安が積み重なると、寝つきが悪くなり、寝ても頻繁に目が覚めるなど睡眠の質が低下します。その結果、日中の仕事にミスが多くなり、場合によっては労災を発生させてしまうリスクも増えます。ただが睡眠と捉えずに、従業員の睡眠環境を向上させる取り組みを行いましょう。
働き方改革
政府が推進する働き方改革の中で特に注目されてるのは、「時間外労働の削減」と「年次有給休暇の取得義務化」です。いわゆる昭和の仕事の考え方である「残業も顧みず働けるだけ働く」とは異なり、健康のため/自分磨きのため/趣味のために労働時間をコントロールし、休みをしっかり取る人が増えてきました。
働き方改革は、過労や睡眠不足による労働災害の減少も期待されるムーブメントであるため、従業員の肉体的、あるいは精神的な負担を減らす方法について、安全衛生委員会で話し合うと良いでしょう。
リモートワーク時の健康管理
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が第5類に移行しても、リモートワークを維持する企業もあると聞きます。そして、周りに人がいないのでついつい間食に手が伸びてしまい、体重が増えたという話をよく聞きます。勤務時間内にずっと座りっぱなしのためエコノミー症候群のリスクもありますね。
そのため、以下のような内容を、安全衛生委員会で話し合ったり、産業医の先生の意見を聞いたりすることが、ステイホームが緩和された今でも注目されています。
- リモートワークならではの健康管理についての情報発信
- 定期的に体を動かす工夫
安全意識を現場に定着させるには?
ここでは、安全衛生委員会の目的である「安全意識の定着」を促す方法について解説します。
「安全な作業手順が一目でわかる」マニュアルの整備
誤った作業手順を踏むと危険やヒヤリハットの可能性がある場合、正しい作業手順を正確に教育しなければなりません。しかし、口頭や文書ベースでの教育の場合、伝えた内容を1度で完全に理解するのは難しいでしょう。外国人従業員が多い現場であればなおのこと、言語の差により理解できない可能性もあります。
そこで、安全な現場づくりに成功している多くの企業では「一目で作業手順が理解できるマニュアル」を整備しています。例えば「動画」によるマニュアルです。
以下の動画は、製造業の「児玉化学工業株式会社」が作成した「バリの取り方」を動画マニュアル化したものです。
▼ドリルで穴のバリをとる動画マニュアル▼
※「tebiki」で作成
このように、動画マニュアルなら安全な作業手順が一目でわかるので、標準化を図り現場の安全意識を高めたい現場責任者によく活用されています。他にも、動画マニュアルであれば以下のような効果が期待できます。
- 標準化された内容を、視覚的にわかりやすく伝えられる
- 復習したい箇所を、学習者のペースで何度でも見れる
- 動きを視覚的に伝えるため、言語の違いや文章読解能力の差が影響しない
- 動画を見せるだけなので、トレーナーの教育工数を削減できる
- 動画によって、画一的な教育が可能になる
動画であれば、現場のリアルな様子をいつでもどこでもありのままに視聴できます。そのため、「何が危険になりえるのか」というのが視覚的に理解でき、効率的かつ効果的な安全教育が可能になるのです。
安全対策に動画マニュアルを活用している事業者が増えています。動画マニュアルの効果や実際の対策事例については、以下のリンクをクリックして安全教育についてまとめた事例集をご覧ください。
>>【pdf】安全意識が高い現場がやっている、 動画マニュアルを活用した安全教育とは?
「周知」と「理解」が必要
安全意識について、一部の人だけが知っていても意味はありません。安全かつ衛生的な職場環境にするための方法を、現場にいる全員に確実に伝える必要があります。全員が同じ情報を共有し、一貫した安全意識を持つことで、統一された安全規則や手順に則り、安全な作業環境を維持できるでしょう。
周知と理解を促すためには、以下の考え方のもと安全教育を行ってください。
- 危険感受性を高める(危ないものを危ないと感じさせる)
- 現場を可視化する(何が危ないのかわかるようにする)
とはいえ、口頭や文書ベースで伝えるのは難しいとされています。そこで、「動画での教育」がおすすめです。
「危険感受性を高める」「現場を可視化する」ことを通じて、従業員の安全意識を向上させる。まさにそのための安全教育の進め方を、以下の資料で解説します。
従業員の安全意識向上や労災防止を実現している企業事例
危険が可視化できることから効果的な安全教育手法として導入している企業が増えている「動画」での教育。この章では、実際に動画を活用し、現場の安全意識を大きく向上させた企業の事例を紹介します。
ASKUL LOGIST株式会社:SAFEコンソーシアム「安全な職場づくり部門」受賞
物流業のASKUL LOGIST株式会社は、全国各地の各拠点にて「動画マニュアルによる標準化」を推進し、従業員の安全を守っています。
▼同社の取り組みのインタビュー動画▼
外国人スタッフなど多様な人材が増える中、従来のOJTや紙マニュアルでは安全教育が十分に伝わらない課題がありました。そこで、現場作業員がスマホで気軽に動画マニュアルが作成できるツール「tebiki現場教育」全社導入。危険な動作を視覚的に伝え、字幕の自動翻訳機能も活用することで、誰にでも分かりやすい安全教育を実現しました。
これにより新人教育時間は大幅に短縮され、業務も標準化。この「全国の拠点で動画マニュアルによる標準化」が高く評価され、SAFEコンソーシアムアワード2023の「安全な職場づくり部門」でダイヤモンド賞を受賞しています。
>>>標準化の要である動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」の詳細資料はこちら
コスモ石油株式会社
コスモ石油 堺製油所は、「安全第一」という最重要方針の実現に向け、動画マニュアルで教育改革を進めています。複雑な設備で危険物を扱うため、紙マニュアルでは作業内容が伝わりにくく、OJT頼りで教育者の負担が増大していました。
▼同社の取り組みのインタビュー動画▼
そこで動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を導入。過去の労働災害を再現動画にして協力会社とも共有し、危険を視覚的に伝えることで現場の安全意識向上に繋げています。教育担当者の負担も軽減され、若手が早期に知識を習得できることから、経営層からも事故リスク低減への貢献が期待されています。
>>>「危険」を視覚的に理解できる動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」の詳細資料はこちら
株式会社メトロール
株式会社メトロールは、工作機械や産業用ロボット向けのセンサの製造/販売を行う企業です。繁忙期は派遣社員を採用して稼働していますが、教育内容のバラついているという問題を抱えていました。
付き合いのある製造業の企業が「tebikiを導入して効果を出している」という話を聞いたことがきっかけで、導入したところ、従来の紙の手順書だけでは伝わりにくい作業動作のコツなどを伝えるうえで有効だと実感。管理のしさすさも導入するうえでの1つの理由だったとのことです。
導入後は、安全衛生に関するマニュアルを優先的に作成することに。その結果、導入前は1時間ほどかけて教えていた内容を、半分以下の時間で教えられるようになりました。また、tebikiの大きな効果として、「現場教育の精神的なストレスが軽減されて、現場で働く人が新しいことを習得していく流れができた」ことも挙げていただいています。
株式会社メトロールの事例を詳しく知りたい方は、以下のインタビュー記事をご覧ください。
インタビュー記事:世界で200社以上の装置メーカーに採用されているセンサの製造工程でtebikiを活用し、新人教育と多能工化を推進
なぜ?「議題/テーマがマンネリ化」の理由
「似たようなテーマの会議が多くなってしまうこと」は決して悪いことではありません。一朝一夕では解決できないような議題は、時間をかけて解決していく必要があります。また、時期ごとのイベントや気候にまつわるテーマは毎年必ず出てくる問題だからです。
しかし、以下のようなパターンでは議論が停滞する可能性があるため、テコ入れする必要があります。
開催することが目的になっている
開催すること自体が目的になってしまい、深い議論を展開することができなくなってしまう場合があります。その場合、定期的にテーマの棚卸しをしてあげると良いでしょう。
テーマを棚卸しする視点については、この後「安全衛生委員会のネタ選びのポイント」で解説していますので、ご覧ください。
時節ネタばかりになっている
前述の様に、時期ごとのイベントや気候に関わるテーマを毎年行うことは悪いことではありません。
ただし、昨年やそれ以前の年ではどういう問題が起こり、どういった対策を講じ、どういった結果になったかをしっかり洗い出し、PDCAサイクルを回していくことを心がける必要があります。
発言がいつも同じ人になっている
発言が同じ人ばかりになってしまうというのも、会議においてよく起こりがちな問題です。議長や安全管理者・衛生管理者・産業医などは毎回発言の機会が設けられますが、会議の構成によってはそれ以外の人が発言しにくい場合もあります。
そのため、経験の浅い人でも萎縮しにくい様な雰囲気づくりを心がけねばなりません。
安全衛生委員会のメンバーは、「参加しなければならない役職」以外の人は毎回入れ替えても問題ありません。「毎回同じメンバーばかりで多角的な意見が出てこない」場合には都度違ったメンバーに参加してもらうのも新たな視点を取り入れる良い方法となります。
安全衛生委員会のネタ選びのポイント
安全衛生委員会で良いテーマを設定する5つの方法をご紹介します。話すネタがマンネリ化している方は、ネタ選びもしっかりチェックしましょう。意外と身近なところに、面白いテーマが落ちているはずですよ。
時事ネタをヒントにする
近年話題になっている腸の調子を整える「腸活」や、リフレッシュ手段として人気のある「サウナ」などについて産業医の意見も仰ぎながら会議を進めると、話すネタが尽きにくいでしょう。また、その月にある「〇〇の日」に関連させて、理解を深めたり、話し合ったりすることも勉強になります。
例えば、3月24日「世界結核デー」に絡めて結核の歴史や予防法を話し合ったり、8月31日「野菜の日」に絡めて日常的に野菜を多く取り入れる方法について語り合ったりすることも、安全衛生意識向上に一役買ってくれます。
現場改善ラボでは、安全衛生委員会で議論するネタ/テーマの実践的な考え方を動画でも解説しています。以下のリンクをクリックして、ネタ切れしがちな委員会のテーマのヒントを得ていただけますと幸いです。
>>【無料で動画を見る】元労基署長が教える「委員会のネタ例」とは?
社内でアンケートをとる
いつも参加しているメンバーや議長・運営者だけで議題を決めてしまうのではなく、アンケートをとって各従業員が本当に悩んでいることを掬い上げていくのもオススメの方法です。
安全担当・衛生担当だけでは気付きにくい視点から意見を集められ、このアンケートで挙がった意見が労働者たちが本当に話し合ってほしいと考えているテーマとなります。
社内のニュースを取り上げる
社内で話題になっているニュースは、従業員がすでに関心を持っているトピックです。そのため、「関連する問題」や「課題」について議論することで、参加者の関心を引きやすくなる/より建設的な議論が生まれる可能性が高まります。
さらに、最新のニュースを取り上げれば、組織全体がリアルタイムの状況を把握でき、適切な対策やアクションを取ることが可能になるでしょう。
社内でリスクアセスメントを実施している場合には、その結果の報告を受けて、安全衛生委員会で審議するのも良いでしょう。
既存のネタを深堀する
安全衛生委員会のテーマの幅を広くしていくことはとても大事です。しかし、1つのテーマについて深掘りし、原因や対策を詳しく考えていくこともおろそかにしてはいけません。
時間との兼ね合いなどもあるでしょう。そのため、議長や運営者がうまく会議の舵をとり、バランスをみながら進めて行ってください。
他事業所/他社/他業界の事例を参考にする
例えば、航空業界の飛行機事故からは、システムのミスやコミュニケーションの行き違いが大きな問題を引き起こすことを学べます。また、飲食業界のワンオペ問題からは、人員を適切に配置する重要性などを知ることが可能です。
そのほかにも、自分たちの事業所だけで取り組みや解決策の良いアイデアが出ない場合には、他事業所などにもヒアリングをして意見を仰ぐのも良いでしょう。
安全衛生委員会で避けるべき内容や言動
安全衛生委員会で避けた方が良いテーマというのは、基本的にありません。ただし、安全衛生委員会で避けねばならない言動は、主に以下の3点です。
ミスや事故を起こした人を責める
原因の深掘りをすることは大事ですが、あくまで対策をすることが目的です。人を責めても良いことは何もありませんし、「次回から報告しない様にしよう」という思考に繋がるため、絶対に避けましょう。
会議では、特定の人を詰める様な物言いをしてしまう人や組織が時々存在します。そういった職場では、心理的安全性が保たれなくなり、安全衛生委員会を行なっているのに、安全性や精神衛生が損なわれるという本末転倒な結果に繋がります。
くれぐれも人を責めることはよくない行為だという認識を、しっかりと持つことが必要です。
ヒューマンエラーを精神論や意識だけで解決する
人間はミスをする生き物ですし、暑さ寒さ、疲れ、その時の状況などによっても判断を誤ることがあります。そのため、問題の原因を「注意が散漫になってしまった」、結果を「意識を高めて作業に集中する」という方向に持っていくのは賢明ではありません。システムや人員配置などを工夫し、精神論だけに頼らない対策を講じていく必要があります。
ヒューマンエラーは安全だけでなく、品質不良にも影響を及ぼす原因となります。現場改善ラボでは、専門家が解説するヒューマンエラーの再発防止策を無料で公開しています。本記事と併せてご活用ください。
デリケートなことを無理やり聞き出す
安全衛生委員会では、体のこと/心のこと/病気のこと/ハラスメントにまつわることなど、非常に繊細な事象を取り上げる場合があります。
ここで当事者を呼び出し、本人が話したくないことを話させる様なことは絶対にしてはいけません。また、健康診断やストレスチェックの結果などについて、個人が断定できてしまう様な発言も避けましょう。心に傷をつけてしまうことになりますし、これらの行為自体がハラスメントです。他者を慮る意識を忘れない様にしましょう。
また、ワクチンや予防接種、献血など個人の自由であることを強制することもNGです。無論「みんなはやるけど、お前もやるよな?」の様な半強制的な聞き方もご法度です。高いコンプライアンス意識を持って会議に臨んでください。
まとめ
安全衛生委員会では、1つのテーマを深く突き詰める、他社や他業界を参考にしてみるなど多くの切り口が存在しています。また、会議が煮詰まってしまった時にはメンバーを一部入れ替えてみたり、話しやすい雰囲気を作ってみたりと工夫を凝らすことで会議はより有意義なものとなります。ご自身の事業所で取り入れやすい工夫や方法を活用し、安全で快適な職場を作り上げていってください。
現場改善ラボでは、労働災害の観点で、元労働基準監督署長の村木氏をお招きし、実際の事故現場から見た安全管理について考えるウェビナーを開催しました。開催した内容は無料でご覧いただけますので、本記事と併せてご覧ください。
参照元