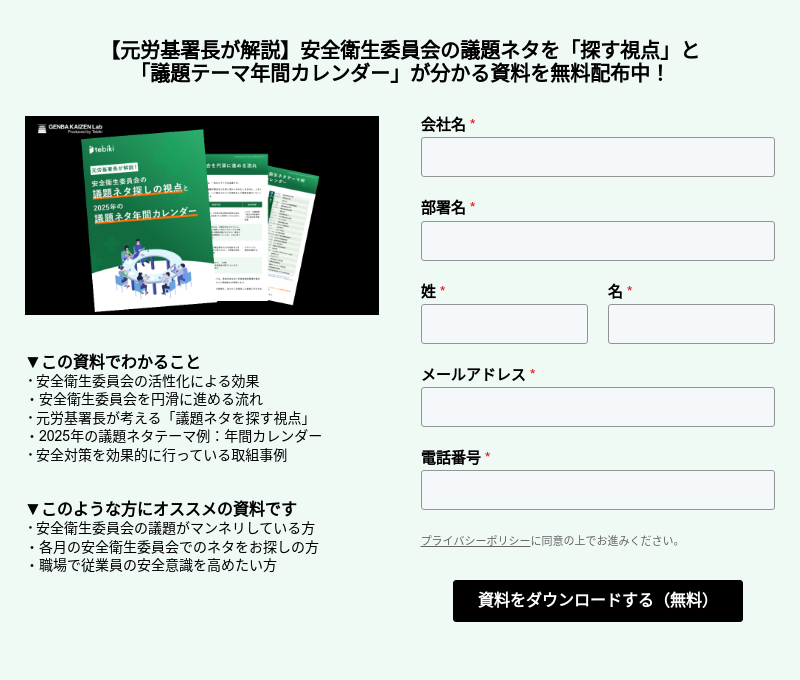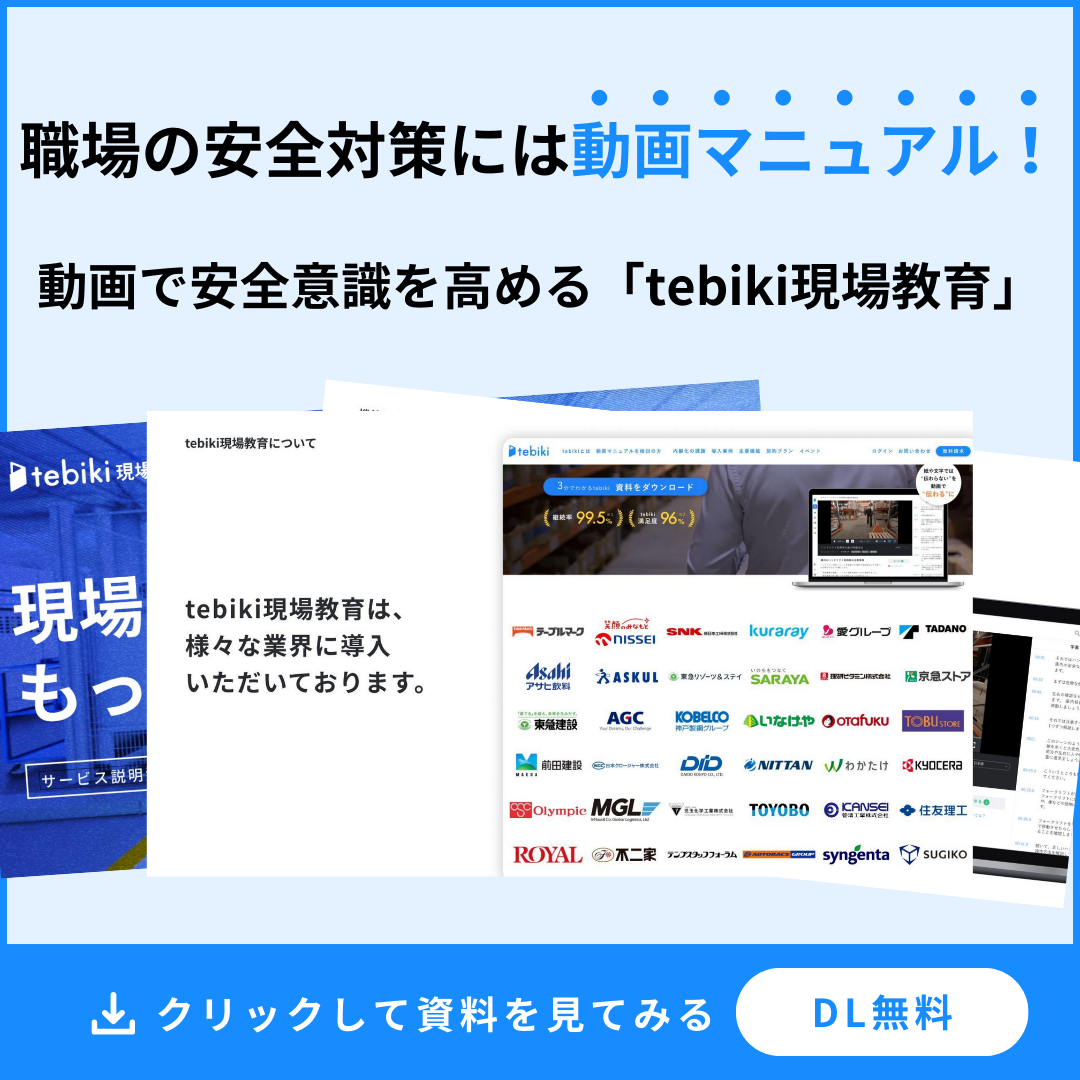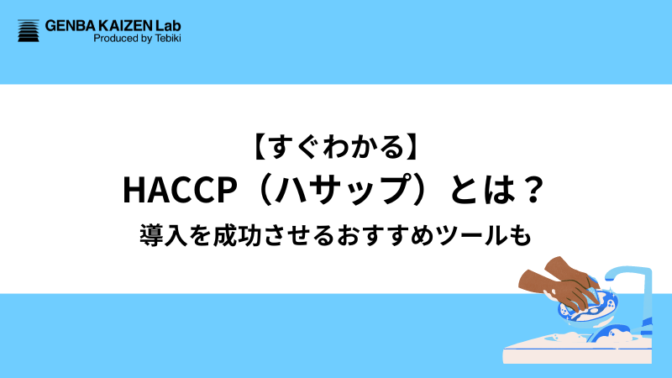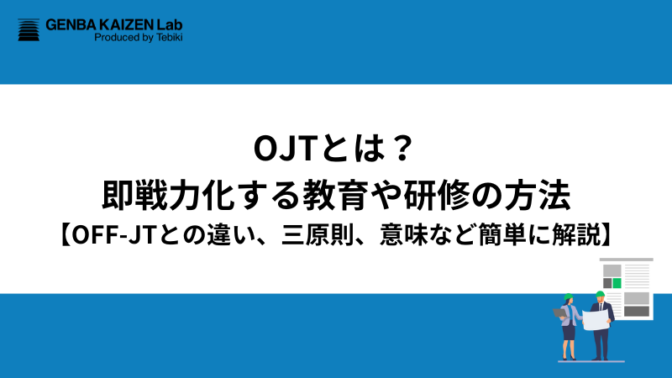かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
本記事では、安全衛生管理の概要や実践すべき具体策、必須体制について解説します。安全衛生活用の好事例もご紹介しますので、安全な職場の実現に向け是非お役立てください。
安全衛生管理の概要や体制を理解した上で、最も重要なのは現場での「実践」です。
ルールを形骸化させず、労災ゼロの職場を確実に実現するための、安全教育における「新常識」と具体的な実践策を以下の資料で解説します。
目次
安全衛生管理とは?目的や法律
安全衛生管理とは、企業や組織が労働者の安全と健康を保護する活動です。安全衛生管理は企業の社会的責任の一環であり、生産性の向上や労働者の健康の増進など、企業と労働者にメリットが生まれます。まずは目的や関連する法律などの基礎知識をおさえておきましょう。
取り組む3つの目的
安全衛生管理に取り組む目的は、主に以下の3つだといえます。
- 事故や健康被害の予防や対策の策定
- 労働者の安全意識の向上
- 労働者が働きやすい職場環境の維持
事故や健康被害の予防や対策の策定
安全衛生管理に取り組む目的の1つは、事故や健康被害の予防や対策を策定することです。
事故や健康被害が生じてからの対策は労働者の人命や健康を脅かすだけではなく、企業にとっても深刻な経済損失に繋がる恐れがあります。そのため、定期的に危険予知活動や評価(リスクアセスメント)を行い、事故や災害を未然に防ぐ必要があります。
例えば、過去の事故や災害のデータを分析し、類似の事象を未然に防ぐための対策を水平展開したり、定期的に現場や職場内を巡視して危険な箇所に適切な対策を実施したりすることが重要です。
万が一、事故や健康被害が発生した場合はすばやく処置をして、事故の対策や緊急対応のマニュアルを作成し再発防止に取り組みます。
労働者の安全意識の向上
労働者の安全意識を高めることは、安全衛生管理に取り組む目的の1つです。
企業側が安全衛生管理を一方的に推進するのではなく、労働者が自ら危険を予測し、事故を回避するための適切な知識や技術を身につければ、事故や災害を未然に防げる可能性が高くなります。
しかし、労働者の安全意識を高める教育は決して簡単ではありません。特に複雑かつ危険な作業手順を伴うことが多い製造業では、安全教育の重要度は極めて高い一方で、「有効な教育方法」が定まっていない現場が多いです。口頭指導やテキスト資料による教育で安全指導を行っているものの効率よく教育できず、教育工数ばかり膨らんでしまうというお声をよくうかがいます。
そこで、安全教育に注力している製造現場でよく取り入れられている教育手法が「動画マニュアルによる教育」です。例えば、ポリマー・塗加工関連事業を担う「トーヨーケム株式会社」では、動画上で作業中の事故を再現し、現場作業における安全教育を実施しています。
このように、安全教育がうまくいっている現場では動画による教育を手掛けていることが多いです。動画マニュアルによる安全教育の推進方法や製造業の事例もあわせて知りたい方は、PDF資料「安全意識が高い製造現場はやっている! 動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例」もご覧ください。下の画像をクリックして資料をダウンロードできます。
労働者が働きやすい職場環境の維持
安全衛生管理に取り組む目的の一つは、労働者が働きやすい職場環境を維持することです。健康維持の措置として、法律で定められた業務を行う現場では作業環境を測定し記録を残します。
また、常時使用する労働者を雇い入れるときの健康診断や、毎年1回以上行う定期健康診断で労働者の健康管理が必須です。労働者の健康を促進して労働者のストレスを軽減することで、職場内でコミュニケーションが良好になり労働者のやる気向上が期待できます。
風通しが良い職場では労働者の意見交換が盛んになるため作業や職場環境の改善活動が進みやすく、より積極的に業務に取り組む姿勢が生まれるでしょう。
関連記事:職場環境を改善する具体的な方法とは?7つの対策や注意点をご紹介
安全衛生に関する法律
安全衛生の管理体制を理解するうえで、おさえておきたい法律を2つ表形式でご紹介します。
| 目的 | 内容 | |
|---|---|---|
| 労働安全衛生法 | 労働者の安全と健康の確保 | ・危険作業に対する安全対策の実施 ・安全衛生に関する教育や訓練の義務化 ・健康管理の実施 ・安全衛生委員会の設置義務 |
| 労働基準法 | 労働者の権利保護と適正な労働環境の確保 | ・労働時間(1日8時間、週40時間) ・最低賃金の規定 ・有給休暇・育児休業・介護休業などの権利保障 ・時間外労働の上限規制などの改正も実施 |
次章では、実際に安全衛生活動を行う上でのポイントについてご紹介します。
安全衛生活動を管理・推進するポイント
全員が「自分ごと」として安全を考える体制の構築
安全衛生活動を現場全体のものとして根付かせるには、まずトップが率先して取り組む姿勢を示すことが重要です。例えば、社長や工場長が現場に出向き安全パトロールを実施したり、朝礼や面談を通じて安全の重要性を自ら語ることで、従業員に「本気で取り組んでいる」と伝わります。
特に非正規社員を含めた全員参加の研修やKYT(危険予知訓練)などを通じて、「安全は一部の人の責任ではなく、全員の責任である」という意識を醸成することが、自発的な行動を促す基盤になります。
作業者の気づきを安全対策に反映する
現場で実際に作業している人の「気づき」こそが、効果的な安全対策のヒントです。安全衛生委員会や朝礼(ツールボックスミーティング)、ヒヤリハット報告などを活用して作業者が感じたヒヤリハットや改善提案を吸い上げ、実際の対策に反映する仕組みを整えることで現場主導の改善が進みます。
さらに、改善提案を表彰する制度や成果の見える化(掲示・記録)によって、モチベーションの向上にもつながります。大切なのは、気づきを一時的なものにせず、継続的に拾い上げる風土づくりです。
守れる・使える・伝わるルールを設計する
安全衛生活動の基盤として不可欠なのが、実効性のあるルールの整備です。誰が・いつ・何を・何のために行うのかを明確にし、複雑すぎず現場で「使える」内容とすることがポイントです。ルールの策定は管理者が一方的に決めるのではなく、委員会等で現場の意見を反映させながら検討すべきです。
また、マニュアルや規程は文字ばかりにならないよう、図解やイラストを活用し、「読める・伝わる」工夫も必要です。実施後はPDCAのサイクルに則り実態に即した見直しを継続することで、現場に根付いたルールとなります。
ここで、現場の安全ルールや注意すべき危険ポイントをわかりやすく伝える手段として、「動画の活用」が注目されています。文字や口頭の説明だけでは伝わりにくい作業手順や危険箇所でも、動きを伴いながら見たままに示せる動画マニュアルのサンプルは、以下のリンクからご覧いただけます。
>>安全意識が高い現場はもう活用している!実際に使われている動画マニュアルのサンプルをみる(無料公開中)
安全衛生管理の好事例と効果的な手段
新人や外国人…多様な人材の安全意識を高めている企業事例
多様な人材が活躍する現代の職場では、安全衛生管理の手法も進化が求められています。特に、新人や外国人労働者に対しては、言語や文化の壁を越えた効果的な教育が不可欠です。
ここで、効果的な安全衛生管理を実践している好事例として、物流業である「ASKUL LOGIST株式会社」のケースをご紹介します。
同社では、安全衛生の教育手段として「動画によるマニュアル」を活用しています。従来の紙ベースのマニュアルでは作業手順の理解にばらつきが生じ、特に外国人従業員にとっては理解が難しいという課題がありました。また、新人教育にも時間がかかり、現場の負担となっていました。
これらの課題に対処するため動画マニュアルを導入したところ、視覚的に作業手順を示すことで言語の壁を越えて直感的に理解できるようになり、外国人従業員の習熟度が向上しました。また、新人教育の効率も大幅に改善され、現場の負担が軽減されました。
さらに動画マニュアルは、作業手順の標準化にも寄与しています。全従業員が同じ内容のマニュアルを視聴することで作業のばらつきが減少し、ヒューマンエラーのリスクが低減しました。これにより安全衛生管理のレベルが向上し、職場全体の安全意識が高まりました。
同社の取り組みは、厚生労働省による労働安全衛生の向上を目的とした「SAFEコンソーシアム」にて、「安全な職場づくり部門」の好事例として入賞しています。具体的な改善効果や対策の様子については、以下のインタビュー記事をご覧ください。
インタビュー記事:従業員数3,500名超・全国15拠点で動画マニュアルtebikiを活用!
安全衛生管理の推進に有効な手段
ASKUL LOGIST株式会社の取り組みから見えてくるのは、安全衛生管理において「誰にでも伝わる教育手段」を持つことの重要性です。具体的な手段としては、「動画マニュアル」が適しているでしょう。紙や口頭では伝えづらい作業手順や注意点も、動画であれば視覚的にわかりやすく伝えることができます。特に、多様なバックグラウンドを持つ従業員が混在する現場においては、共通理解を促進し教育の質を均一化するうえで非常に効果的です。
また、動画マニュアルは一度作成すれば何度でも繰り返し活用でき、教育コストの削減やOJTの効率化にもつながります。結果として現場の安全意識が底上げされ、事故やヒヤリハットの発生リスクを大幅に低減することが可能になります。
安全衛生の基本は「伝えること」と「理解してもらうこと」。その手段として、動画マニュアルの活用は今後ますます重要な選択肢になるでしょう。
ASKUL LOGIST株式会社が活用し、編集の簡単さや字幕の自動翻訳も行えることが評価された動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」については、以下のPDF資料内で詳しくご紹介しています。「多様な人材に対しても伝わる安全教育の方法を模索している方」や、「属人化せず、効率的に現場教育を進めたいとお考えの方」は、是非ご覧ください。現場での活用事例や導入のポイントを、わかりやすくご紹介しています。
安全衛生管理で実践すべき具体策10選
安全衛生管理で取り組むべき具体策には、以下のようなものがあります。
- 従業員への安全衛生教育の徹底
- 労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)の導入と運用
- リスクアセスメントの実施
- 標準作業の確立と職場への浸透
- 労働災害やヒヤリハット事例の共有
- 労働者の健康管理
- 作業環境の継続的な改善
- ヒューマンエラーの未然防止
- 内部安全衛生監査の実施と改善
- 緊急時対応計画の策定と訓練
従業員への安全衛生教育の徹底
従業員の安全意識を高め安全な行動を促すには、安全衛生教育が欠かせません。労働安全衛生法で定められた雇入れ時の教育、特別教育、職長教育などを確実に実施することはもちろん、職種や作業内容に応じた具体的な教育を実施することが重要です。
ここで、従業員の安全意識を高める教育方法として「動画」が活用されるケースが増えています。例として、物流企業である「株式会社近鉄コスモス」が作成した「フォークリフトの操作」に関連する動画マニュアルを以下に掲載します。「正しいハンドリフト操作」を動画化し、従業員に危険が及ばないように正しい操作手順を解説しています。
▼フォークリフトの操作を解説する動画マニュアル(音量にご注意ください)▼
※本動画は「tebiki」で作成されています
動画による安全衛生教育の事例や実際のサンプルを他にも確認したい方は、以下のPDF資料もご覧ください。
>>安全意識が高い製造現場が活用している「動画教育」の事例・サンプルをみてみる(無料公開中)
労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)の導入と運用
安全衛生管理を組織的かつ継続的に実施するには、労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)の導入と運用が効果的です。OSHMSは、PDCAサイクル(計画-実行-評価-改善)を基本として、安全衛生方針の策定、リスクアセスメント、安全衛生計画の作成、実施、評価、見直しを通じて、安全衛生水準の継続的な向上を目指す仕組みです。
このシステムを導入することで、安全衛生管理が組織に根付き、トップマネジメントから現場の従業員までが一丸となって取り組むことが可能となります。
リスクアセスメントの実施
職場に潜む危険を未然に防ぐには、リスクアセスメントが不可欠です。リスクアセスメントとは、作業内容や機械設備、化学物質などあらゆる危険源を特定したうえでそのリスクの大きさを評価し、リスクを低減する一連のプロセスを指します。
リスクの大きさは「重篤度」と「発生可能性」から評価し、その大きさに応じて対策の優先順位を決定します。そして適切なリスク低減措置を実施(例えば「保護具の着用」等)し、効果を定期的に確認しながら必要に応じて見直しを行います。
リスクアセスメントを実施する具体的な手段や例題について知りたい方は、労働基準監督署署長が直々に解説した以下の講演動画をご参照ください。
>>リスクアセスメントで現場の「キケン」を見極めるには?事故を発生させない「本質安全化」の実現策(無料公開中)
標準作業の確立と職場への浸透
安全で効率的な作業を実現するには、標準作業を確立し職場に浸透させる「業務標準化」が不可欠です。
業務標準化は安全性の確保だけでなく、労働衛生の向上やリスク低減を通じて従業員の健康を守り、ひいては職場全体の生産性と品質を底上げする不可欠な手段です。例として、標準手順書を基にした作業は個々の判断に頼るあいまいなやり方を排除し、危険源を事前に可視化・管理することでヒューマンエラーや事故発生率を抑制することが期待できます。
標準作業は定めるだけで終わりではなく、現場に浸透させることではじめて効果を発揮します。一方で、「作業手順書は整備しているものの形骸化している」という現場も多いのではないでしょうか?
「手順が守られる」作業手順書を整備するポイントについてまとめた資料もございますので、本記事と併せ是非ご覧ください。
>>標準作業を現場に根付かせるには「作業標準書のカイゼン」から!わかりやすい手順書整備の秘訣をみる(無料公開中)
労働災害やヒヤリハット事例の共有
労働災害やヒヤリハットの事例を職場全体で共有することは、安全衛生管理において欠かせない対策のひとつです。実際に発生した事故や、事故には至らなかったが一歩間違えれば大きな災害につながりかねなかった事例を共有することで、現場のリスクに対する感度を高め、同じ失敗を繰り返さないための学びを得ることができます。
また、共有の際には「なぜ起きたのか」「どうすれば防げたのか」といった背景や対策まで含めて伝えることが重要です。単なる事実の報告にとどまらず職場全体で原因と再発防止策を理解することで、現場の危険感受性が高まり、安全意識の定着につながります。
関連記事:【危険予知】工場のヒヤリハット事例21件!再発防止の考え方や安全意識を高める方法を紹介
労働者の健康管理
労働者の健康を守ることは安全衛生管理の基本であり、職場の安心・安全を支える重要な対策の一つです。まずは労働安全衛生法に基づき、定期健康診断を確実に実施することが求められます。健康診断の結果、異常が見つかった場合には、医師の意見を踏まえて必要に応じた就業制限や保健指導など、適切な対応を行うことが大切です。
また、長時間労働は心身に大きな負担をかけ、過労死や健康障害を招く原因となります。これを防ぐには勤務時間の適正な管理、業務量の見直し、人員体制の調整など、長時間労働を減らすための具体的な取り組みが必要です。
さらに、近年ではストレスによるメンタルヘルス不調も深刻な課題となっています。ストレスチェック制度を活用して従業員の状態を定期的に把握し必要に応じて面接指導を行うとともに、職場環境自体の改善にも取り組むことが重要です。
作業環境の継続的な改善
快適で安全な作業環境を維持することは、労働災害や健康障害の防止に効果的です。温湿度、照度、騒音、換気などの状況を作業環境測定などを通じて把握し、基準値を超えている場合は適切な対策を講じます。
特に有害物質を扱う現場では、局所排気装置の設置や保護具の使用、作業環境測定の実施といった具体的なばく露防止策が求められます。また、作業スペースの確保と整理整頓を徹底することで、転倒や接触といった日常的な事故の防止にもつながります。
こうした職場環境の改善を日常的に進めるうえで有効なのが「5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)」です。5Sの定着により危険の芽を早期に発見・除去できる職場風土が醸成され、安全衛生水準の維持・向上に大きく貢献します。
5S活動の具体的な進め方や実践のコツについては、以下の専門家による解説動画でも詳しくご紹介しています。
>>職場の安全は「環境整備」から!事故の芽を摘む5S活動の実践方法やポイントを学ぶ(無料公開中)
ヒューマンエラーの未然防止
多くの労働災害は、ヒューマンエラーによって引き起こされています。したがって、ヒューマンエラーの未然防止は安全衛生管理において極めて重要です。過去の事故事例やヒヤリハットを分析し、エラーの原因を明らかにすることが出発点となります。
例えば、作業手順が複雑すぎる、必要な情報が現場に届いていない、疲労やストレスが蓄積しているといった要因が、エラーを誘発する背景として挙げられます。こうした要因を洗い出し、的確な対策を講じることが重要です。
ここで重要なのが、「エラーの検知と抑制」です。単に個人の注意に頼った対策ではなく、組織全体でヒューマンエラーを発生させない仕組みを作ることが安全衛生管理の質を高める鍵となります。
ヒューマンエラーに適切な対策を講じるための重要な視点・対策例についてまとめた資料もご用意しておりますので、下記の画像をクリックし是非お役立てください。
内部安全衛生監査の実施と改善
安全衛生管理が適切に実施されているかを定期的に監査し、問題点を改善していくことが重要です。内部監査員が、安全衛生管理体制、リスクアセスメントの実施状況、各種対策の実施状況などを確認します。
そして、監査で指摘された問題点については速やかに改善措置を講じ、安全衛生管理の向上を図ります。
緊急時対応計画の策定と訓練
地震、火災、爆発などの緊急事態が発生した場合に備え、事前に対応計画を策定しておくことが重要です。避難経路、連絡体制、役割分担など、緊急時の対応手順を明確に定め、計画に基づき、定期的に避難訓練や救護訓練を実施します。
これにより、緊急時に迅速かつ適切に行動できるようになり、被害を最小限に抑えることができます。
安全衛生管理で必要な体制と役割
安全衛生管理体制の整備には、管理者等の選任や安全衛生委員会を設置する必要があります。それぞれ詳しく解説します。
安全衛生管理の基本は「安全衛生委員会」
安全衛生委員会は、職場の安全と健康を守るための中核的な役割を担う組織です。労働安全衛生法に基づき、一定規模以上の事業場では設置が義務付けられており、事業者と労働者の代表が協力し合いながら、安全衛生に関する重要事項を審議・推進します。
例として、リスクアセスメントや教育、健康管理、作業環境の改善など幅広い議題を扱い、現場の声を反映した実効性のある対策が実現できるのが大きな特長です。
また、委員会は月1回以上の開催と議事録作成が義務付けられており、その決定事項は実際の施策に反映されます。単なる形式的な会議に終わらせず継続的な改善を進めるには、経営トップの関与とPDCAサイクルの確立が鍵となります。
まさに、安全衛生委員会は職場の安全文化を根付かせるための「基本」であり、企業の持続的な発展に不可欠な仕組みといえるでしょう。
安全衛生委員会で議論すべき内容
安全衛生委員会で議論すべきトピックは多岐に渡りますが、いざ議論を進めようとすると「何を議論したらいいかわからない」となることは少なくありません。そこで、議論に行き詰まった際は『安全衛生管理で実践すべき具体策10選』を参考に、以下のカテゴリーから考えてみると良いでしょう。
- 「リスクアセスメント」関連
- 「安全衛生教育」関連
- 「健康管理」関連
- 「作業環境改善」関連
- 「労働災害・ヒヤリハット事例」関連
重要なのは、これらの例を参考に自社の事業内容、作業特性、過去の災害事例、労働者の意見などを踏まえ、具体的かつ実効性のある議題を設定することです。 また、議論するだけでなく決定事項を確実に実行し、その効果を評価して改善につなげるPDCAサイクルを回していくことが、安全衛生委員会の実効性を高める上で不可欠です。
もし、より具体的な議題ネタが知りたいという場合は、「安全衛生委員会を円滑に進める流れ」「議題ネタを探す視点」「2026年の安全衛生ネタテーマ例」などがまとめられたPDF資料『安全衛生委員会「議題ネタ探しの視点」と「2026年の議題ネタ年間カレンダー」』をご覧ください。下の画像をクリックするとダウンロードできます。
安全衛生管理に必要な体制と管理者
安全衛生管理を行う上で求められる体制や管理者について、表形式でわかりやすくまとめました。
| 概要 | 役割 | 選任基準 | |
|---|---|---|---|
| 総括安全衛生管理者 | 企業全体の安全衛生管理を統括する責任者 | -安全衛生方針・計画の策定・実施 -問題解決に向けた各部署との連携 -安全衛生情報の収集・分析 -法令遵守や教育の推進など | 常時300人以上の労働者を使用する事業場で選任義務あり。 工場長や事業所長などの責任者が就任。 |
| 安全衛生推進者 | 安全衛生活動を現場で推進する担当者 | -啓発活動や研修の実施 -安全衛生情報の提供 -相談対応 -取り組みの評価・改善提案など | 常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で選任義務あり。専属で必要な能力を有する者が就任。 |
| 安全管理者 | 安全管理の専門責任者 | -安全方針の策定・実施 -情報提供・教育訓練 -安全対策の計画立案 -相談対応、改善の推進など | 常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任義務あり。 所定の研修修了者または資格保有者が就任。 |
| 衛生管理者 | 衛生面から職場環境の安全と健康を守る専門責任者 | -衛生方針・計画の策定・実施 -環境測定 -健康管理 -災害対策 -相談対応など | 常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任義務あり。 免許または資格保有者から選任。※人数は規模に応じて異なる |
| 作業主任者 | 特定作業において作業者の安全を確保する監督者 | -安全手順書の作成 -作業方法の指導・監督 -危険物の管理 -災害発生時の対応など | 労安法第14条で定められた作業(高圧室内作業、ボイラー取扱作業など)に応じて選任義務あり。 |
| 産業医 | 労働者の健康管理を行う医師 | -作業環境の維持管理 -健康相談・面接指導 -衛生委員会への参加 -職場巡視 -健康障害防止措置の提案など | 常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任義務あり。 1,000人超で専属、3,000人超で2人以上必要。 |
衛生管理者の選任数については、以下の通りです。
| 常時使用する労働者の数 | 衛生管理者の数 |
|---|---|
| 50人以上200人以下 | 1人 |
| 200人を超え500人以下 | 2人 |
| 500人を超え1,000人以下 | 3人 |
| 1,000人を超え2,000人以下 | 4人(うち1人は選任) |
| 2,000人を超え3,000人以下 | 5人(うち1人は選任) |
| 3,000人を超える場合 | 6人(うち1人は選任) |
まとめ:安全衛生管理は「教育」から!
本記事では、安全衛生管理の基本的な体制から具体的な対策、管理・推進のポイントについて解説しました。
この中で特に重要なのが「従業員への安全衛生教育の徹底」です。どれだけ安全衛生委員会が活動的であっても、現場の従業員が安全かつ健康的に業務を推進できる環境が作られなければ、安全衛生管理は形骸化します。
したがって、安全衛生教育の体制整備が肝であるといえるでしょう。特に製造業では、「従業員の安全意識をいかに高められるか」が重要かつ長年の課題です。
そこで、安全教育を推進・浸透する有効手段として「動画」による教育が挙げられますが、その理由や動画教育の導入事例について詳しく知りたい方は、PDF資料「安全意識が高い製造現場はやっている! 動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例」も併せてご覧ください。下の画像をクリックすると、資料をダウンロードできます。