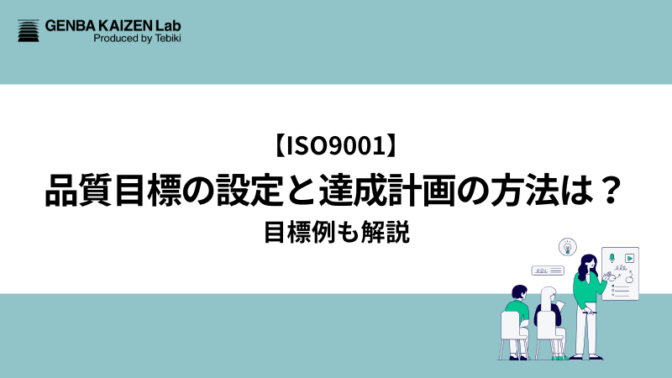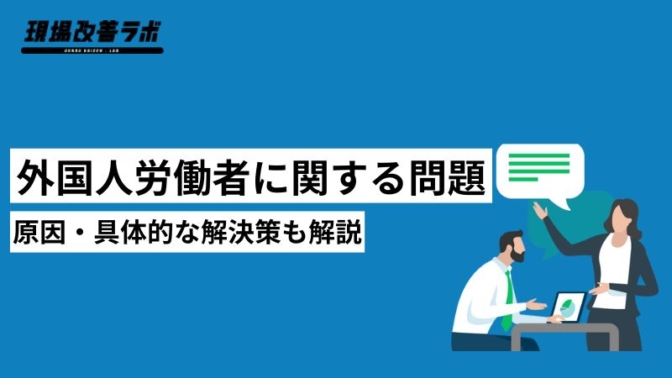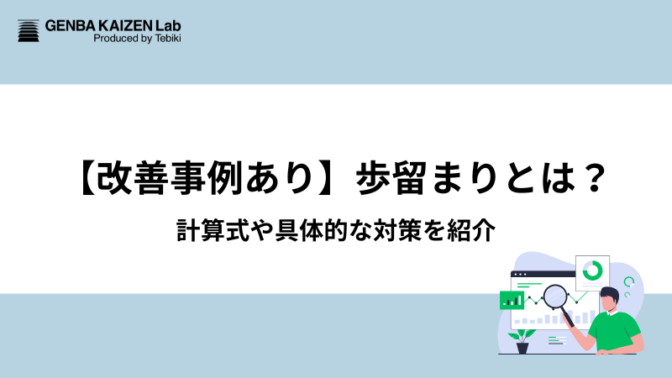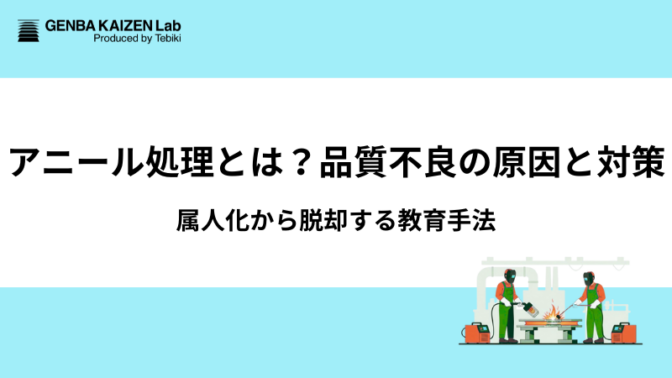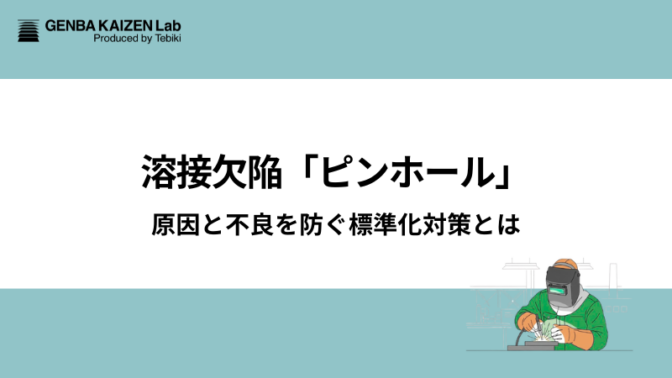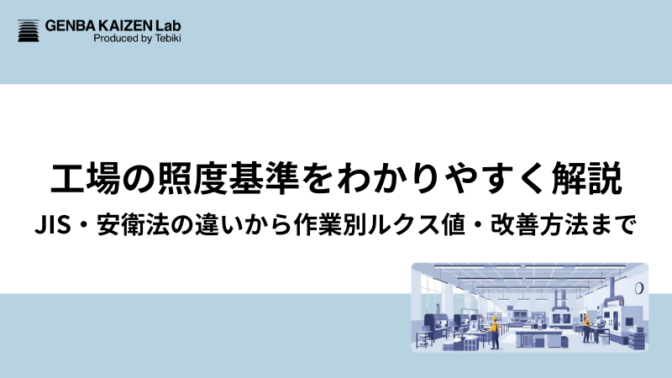私たちのまわりでは、さまざまな業務上のトラブルや事故が起こっています。そのたびに再発防止が叫ばれていますが、一向にその再発が止まりません。それは、トラブルの根本原因が追究されず、安易な再発防止策が講じられ、さらには未然防止ができていないからです。
このページでは、未然防止研究所が独自に構築した3ステップ対策を中心に、未然防止とは何か、再発防止との違いを解説します。さらに、未然防止を確実に実行するため効果的な手段をご紹介します。
ちなみに未然防止や再発防止策が現場に浸透しない多くの原因は、以下の3つに大別されます。
・場当たり的なOJT(その場しのぎや口頭指導)
・読まれないマニュアル(形骸化)
・進まない技術伝承(スキルのばらつき)
これらを解消する術として有効なのが「再発防止策を見える化する教育体制」であり、多くの現場で「動画による教育(マニュアル)」が導入されつつあります。動画マニュアルを通じた再発防止策の浸透や事例の詳細は、以下の資料「再発防止策の『伝わらない』『守られないを解消する動画マニュアルの活用事例』でまとめられているので、あわせて参考にしてみてください。
>>資料「再発防止策の『伝わらない』『守られないを解消する動画マニュアルの活用事例』を見てみる
※本記事は未然防止研究所の共同制作です。以下の目次より、気になるトピックスをぜひご覧ください。
目次
未然防止とは?
未然防止の定義
未然防止とは、将来のリスクを想定(発見)し、対策を実行して、将来起こるかもしれないトラブル・事故を未然に防ぐ活動のことです。事が起こってからどんな対策を実行しても遅すぎです。ここに未然防止の価値があります。
また、未然防止は単なる手法ではなく、経営理念や企業文化として定着させることがとても重要です。
未然防止の取り組みは、コスト削減や信頼向上など企業全体に大きなメリットをもたらします。
この取り組みを精神論で終わらせず、現場の「仕組み」として定着させ、品質不良の再発を確実に防ぐための「動画マニュアル活用法」を以下の資料で解説します。
>>製造業の品質不良を再発防止する動画マニュアル活用法を見てみる
再発防止との違い
未然防止と再発防止は似て非なるもので、まったく異なる概念です。再発防止は過去に発生したトラブルや事故の根本原因を追究し、同じ問題が繰り返されないよう対策を行うことを指します。
一方、未然防止は、過去のトラブルを参考にしながらも、将来発生し得る新たなリスクに対して予防策を講じる活動です。再発防止が「起きた問題の再発防止」にフォーカスするのに対し、未然防止は「まだ起きていない問題の予防」に主眼を置いています。
このため、再発防止を通じて得た知見やデータが、未然防止の出発点となります。
将来のリスクを防ぐ「未然防止」も、確実な「再発防止」による知見の蓄積があってこそ実現します。
表面的な対策で終わらせず、トヨタ式QCストーリーを用いて品質不良の「真因」を特定し、二度と同じ問題を繰り返さないための手順を以下の資料で解説します。
>>トヨタ式QCストーリーを通じた、品質不良の真因を断つ再発防止策を見てみる
未然防止に取り組むメリット
未然防止に取り組むことで、多くのメリットを享受することができます。
第一に、トラブルや事故による損失を未然に防ぐことで、時間やコストを大幅に削減できます。第二に、従業員の作業負荷を軽減し、創造的な業務に集中できる環境を整えることで、職場のモチベーションや生産性が向上します。第三に、顧客からの信頼を維持・向上させ、ブランド価値を高める効果があります。また、未然防止を企業文化として定着させることで、長期的な競争力を確保し、安定的な成長を実現できます。
このように、未然防止は企業活動全体にポジティブな影響をもたらします。
なぜ未然防止がうまくいかないのか?
一方で、未然防止を推進しようとしても、うまくいかないという声を伺うことが少なくありません。その背景には、いくつかの要因が存在します。
第一に、未然防止の認知度が低いことが挙げられます。多くの企業では、トラブルが発生してから対応することが当たり前とされ、未然防止の重要性が十分に理解されていません。第二に、未然防止を推進する指導者の不足も大きな課題です。未然防止には専門的な知識や経験が必要ですが、それを指導できる人材が育成されていない企業が多いのが現状です。
第三に、目先のコストに囚われ、先行投資として未然防止に取り組む意識が希薄な企業もあります。未然防止には初期費用や時間が必要ですが、それが長期的なコスト削減や利益向上につながるという視点が欠けていることが多いです。
さらに、将来のリスクを発見する方法を知らないことも障害の1つです。特に、現場レベルでリスクを予見する仕組みや教育が不足している場合、未然防止活動が形骸化する可能性があります。
最後に、抵抗勢力の存在も問題です。現状維持を好む文化や、変革に対する拒否感が強い職場では、未然防止の取り組みがスムーズに進まないことがあります。
このような要因を克服するためには、未然防止の価値を全社的に共有し、適切な指導者の育成や仕組みの整備を進めることが重要です。また、経営トップの強いリーダーシップは不可欠です。
未然防止3ステップ対策
ここまで、未然防止に関する基礎知識や効果、取り組みがうまく進まない背景を解説しました。本章では、未然防止の取り組みで効果を享受するために必要な、対策の3ステップをご紹介します。
- STEP① 緊急対応(火事に気付いて火を消す、延焼を止める)
- STEP② 再発防止(同じ場所・原因の火事を防ぐ)
- STEP③ 未然防止(異なる場所・原因の火事を防ぐ
ちなみに未然防止や再発防止策が現場に浸透しない多くの原因は、以下の3つに大別されます。
・場当たり的なOJT(その場しのぎや口頭指導)
・読まれないマニュアル(形骸化)
・進まない技術伝承(スキルのばらつき)
これらを解消する術として有効なのが「再発防止策を見える化する教育体制」であり、多くの現場で「動画による教育(マニュアル)」が導入されつつあります。動画マニュアルを通じた再発防止策の浸透や事例の詳細は、以下の資料「再発防止策の『伝わらない』『守られないを解消する動画マニュアルの活用事例』でまとめられているので、あわせて参考にしてみてください。
>>資料「再発防止策の『伝わらない』『守られないを解消する動画マニュアルの活用事例』を見てみる
STEP① 緊急対応(火事に気付いて火を消す、延焼を止める)
最初のステップは、発生した問題を迅速に収束させる「緊急対応」です。トラブルの事実を正しく把握します。推測や憶測に頼らず、確実な情報を基に初動対応を行います。
二次災害の防止や類似リスクの確認を行い、さらなる被害の拡大を防ぎます。
STEP② 再発防止(同じ場所・原因の火事を防ぐ)
次に取り組むのは、同じ問題が繰り返されないようにする「再発防止」です。問題の根本原因(真因)を追究します。表面的な対処ではなく、問題の本質に迫る分析が必要です。
根本原因から再発防止策を誘導し、対策実行の後、その効果を検証します。根本原因の追究方法は、未然防止研究所で公開している記事をクリックしてご覧ください。
STEP③ 未然防止(異なる場所・原因の火事を防ぐ)
最後のステップは、過去の教訓を活かし、将来起こるかもしれないトラブルを防ぐための「未然防止」です。再発防止で得た知見や経験を活用して、新たなリスクに気付きます。未然防止策を立案し、実行した後、その成果を振り返ります。
未然防止型QCストーリーの進め方
未然防止の対策3ステップを解説しましたが、この流れはQCストーリーに紐づく流れでもあります。ここからは、未然防止型QCストーリーの流れを、8つに分けてそれぞれ解説します。
問題の定義
問題の定義は、未然防止型QCストーリーの出発点であり、すべての活動の基盤となります。
このステップでは、現場で起こっているトラブルや課題を明確にし、具体的な事象として捉えることが重要です。例えば、「生産ラインで不良品が頻発している」という状況であれば、その不良品の種類、発生頻度、影響範囲などを定量的に記録します。
この段階で重要なのは、感覚や推測で問題を語るのではなく、客観的なデータや事実に基づいて問題を定義することです。さらに、問題が企業全体や顧客に与える影響を評価し、この問題を解決する価値について、チームで共有し、未然防止活動に取り組む必要性を明確にします。
目標設定
目標設定は、問題解決の方向性を定め、活動を進めるうえでの指針となる重要なステップです。
目標は、定量的で具体的な数値を設定し、現場にとって分かりやすいKPI(Key Performance Indicator)を使って、活動のモニタリングを実施します。例えば、「不良品率を現在の5%から2%に減らす」「顧客クレーム件数を月間10件から5件に半減する」といった明確な目標が挙げられます。
さらには、いつまでに目標を達成するかという期限も明確にします。この段階で目標が曖昧であると、このあとの活動に悪い影響が出る可能性があるため、関係者全員で共有・確認・納得することが大切です。
暫定対策
暫定対策とは、問題解決の初期段階で取る緊急的な措置を指します。この対策の目的は、問題が悪化するのを防ぎ、現状を安定化させることです。火事に例えれば、まずは火を消し、延焼を止めることです。
一例として、機械加工の現場で寸法不良が発生し、その不良品が顧客へ流出して、クレームが発生した場合、暫定対策(緊急処置)として、特別検査体制を整えかつ、不良品の隔離を徹底して、不良品の流出防止に努めます。
ただし、暫定対策は根本的に問題を解決するものではありません。一時しのぎに過ぎないことを関係者全員で認識する必要があります。このステップでは、対策の実施後に問題が沈静化していることを確認し、次の根本原因究明に進む準備を整えます。
根本原因(真因)究明
根本原因の究明は、未然防止型QCストーリーの中核を成すステップです。この段階では、表面的な原因ではなく、問題の発生を引き起こした真因を特定することに集中します。
代表的な手法として、なぜを繰り返す「なぜなぜ分析」がありますが、実は、この「なぜなぜ分析」には盲点があります。そこで、未然防止研究所では、なぜなぜ分析の改良版を推奨しています。詳細は、未然防止研究所で公開している記事をクリックしてご覧ください。
多くの企業では、根本原因が追究されず、表面的な対策しか打てていないため、トラブル・事故の再発が止まりません。ぜひ、正しい考え方と手法に基づいて、根本原因追究に取り組んでいただきたいと思います。
再発防止対策の立案、実施
根本原因が特定された後は、それを解決するための再発防止対策を立案し、実行に移します。
この段階では、問題が再び発生しないようにする具体的な行動計画を策定することが求められます。例えば、「工程設計手順を見直し、重要な寸法検査項目を明確化する」「作業者に対して新たな教育訓練を実施する」といった取り組みが考えられます。
対策の効果を最大化するためには、関連部門や従業員と緊密に連携し、計画的に進めることが重要です。再発防止対策を確実に実施するために、明確な期限と責任者の設定が欠かせません。
再発防止対策の効果検証、改善
再発防止対策を実施した後、その効果を検証することがこのステップの目的です。
設定した目標が達成されたかを測定し、必要に応じて対策の改善を行います。例えば、不良品率の削減を目標に掲げた場合、一定期間後にデータを分析し、改善が確認できなければ新たな対策を検討します。
この段階で重要なのは、検証結果を具体的な数値や事実に基づいて評価することです。また、効果検証が不十分な場合、再び同じ問題が発生する可能性があるため、慎重に進める必要があります。
標準化と水平展開
再発防止対策が効果を上げた場合、その対策を標準化し、他の業務や部門に水平展開することが必要です。
例えば、「新たに策定した工程設計手順」を全製品ラインに適用することで、同様の問題発生リスクを減らすことができます。標準化では、具体的な手順書やマニュアルを作成し、誰もが同じ基準で作業できる状態を確立します。
また、水平展開では、別の部門で類似の問題が発生しないように事例を共有し、組織全体で学びを活かします。
活動内容と成果の総括
最後に、未然防止型QCストーリー全体を振り返り、活動内容と成果を総括します。
これには、各ステップで得られた教訓や、今後の改善点を整理することが含まれます。また、活動によって達成された成果や組織全体への影響を具体的に示すことで、関係者の意識向上やさらなる改善意欲を引き出します。この段階では、取り組みの成功事例を社内外に発信することも効果的です。
成功の共有により、未然防止活動の重要性が認識され、組織文化として根付いていきます。
未然防止の成功事例
未然防止研究所では、これまでさまざまな現場でトラブルを未然防止するための取り組みを支援してきました。今回は、これまでの支援内容から未然防止の好事例を一部ご紹介します。
未然防止の意識を高めるタスクフォース活動(設備メーカー)
- 活動の目的:設計・製造ミスの撲滅
- 活動内容:過去の失敗事例を持ち寄り、正しい真因分析等、問題解決手法を学ぶ
- 活動メンバー:設計/製造/品質保証部門から、管理職と担当者を指名
- 活動期間:2か月限定。2週間に1回、1回2時間程度
- 活動の成果:活動の水平展開により、設計/製造にかかわる仕損費半減を達成
本活動のポイントは「真因追究の方法をマニュアル化し、いかに伝承していくか」です。経験が浅いメンバーのみで議論しても、有益な場にはなりにくく、かえって現場の生産性を落とす恐れもあります。
未然防止の取り組みでは、問題解決に精通したリーダーが活動を主導することで短期間でも成果を上げることができるため、普段からリーダーの育成をする視点が大切です。
活動に参加した設計部長からは、『真因を追究する過程で、多角的な目で事象を分析することができ、 不具合の真因が意外なところにあることを体感できた。』『契約から設計、製造、据え付けに至るまでの各ポイントでの不具合に対して具体的で 効果的な施策を立案できた。』『人はミスを犯すものという考えの元での改善の必要性を強く認識。 全社員の意識高揚への具体策が必須であることを痛感した。』という声を頂きました。
ヒヤリハット対策で品質改善(自動車部品メーカー、組み立て工程)
- 活動の目的:品質意識を製造現場に浸透させて品質トラブルを撲滅
- 活動内容:製造現場で体験したヒヤリハット事例を記録し、朝礼等で全員に共有。優先度の高いヒヤリハットは真因究明と再発防止策を実行
- 活動の成果:顧客クレームが200ppmから20ppm へ、1/10まで低減
本活動のポイントは「ヒヤリハットが品質対策としても効果的」という点です。通常、ヒヤリハットは安全対策の文脈で取り組まれることが多いですが、品質トラブルの未然防止策として取り入れたことで品質改善にも効果があることを立証できました。
一方で、真因追究で従来のなぜなぜ分析には盲点があるので、注意が必要です。前述の「根本原因(真因)究明」でご紹介した、なぜなぜ分析の改良版を使用しましょう。また、ヒヤリハットに関するデータ収集が目的化すると、未然防止の活動が形骸化しやすいため、活動の目的を浸透させることが大切です。
活動に参加した現場の方からは、『ヒヤリハットに着目することで、安全と品質の意識が高まり、現場で自ら改善することで、作業が楽になった。』『ヒヤリハット事例を文字で記録するよりは、動画の方が有効な場合がありそう。』という声を頂きました。
ダブルチェックの廃止でコスト削減(自動車部品メーカー、溶接工程)
- 活動の目的:検査コストの削減
- 活動内容:検査工程でのチェック漏れの真因追究と対策実施で、ダブルチェックを廃止
- 活動の成果:ダブルチェック廃止による検査コストの大幅削減に加え、品質意識の高揚で品質レベルが大きく向上
本活動のポイントは「検査漏れはダブルチェックでは解決できない」という点です。現場で起きたトラブルの対策例として、ダブルチェックを行うケースが少なくありませんが、単なる一時そのぎに過ぎないことが多いでしょう。
そのため、ダブルチェック自体を廃止する方向で推進しつつ、やむを得ずダブルチェックを実施する場合は期間限定とし、チェック漏れが改善されればダブルチェックを廃止しました。
活動に参加した現場の方からは、『ベテラン検査員の技能(とくに外観検査)をマニュアル化することに苦戦した。動画マニュアルが有効かもしれない。』という声があがってきました。
他の好事例の声でもあったように、未然防止の活動を推進する手段の1つとして「動画マニュアル」が対策の実効性を上げることに役立つと考えられます。
実際の製造現場を見て感じた「動画マニュアルのメリット」
製造現場で未然防止の取り組みを支援する中で、動画マニュアルを活用するメリットを感じる場面がさまざまありました。
通常、製造現場の作業者に作業手順を伝える場合、その手順を言語化します。しかし、熟練作業者が保有している技能(暗黙知)を言語(形式知)に落とし込むのは簡単ではありません。そこで、マニュアル作成でお困りの方々へ、動画マニュアルの活用をお勧めします。
次の2つの事例を参考にして、動画マニュアルをご検討ください。
「外観検査」で動画マニュアルを活用
カラー塗装された自動車のフロントバンパーを外観検査する場合、製品の表面を目視でキズ/色味/色ムラ/凹凸を限度見本に照らして判定します。
このような外観検査では、「決められた検査時間内で外観の欠陥を発見」することが求められ、広い製品表面をどういう順番で、どの角度から目視検査するかというカンコツが求められます。しかし、人の五感による官能検査作業を言語化されたマニュアルに表現するのは困難といえるでしょう。
そこで動画マニュアルを活用することで、熟練作業者が保有している技能(ワザ)を視覚的に伝え、言語化する難しさを解消しつつ、未熟練作業者にも理解されやすい状態にすることが可能です。
>>製造業の品質不良を未然防止する次世代の品質検査を見てみる
「熟練作業者の動き方」を動画マニュアルで伝える
すべての製造現場において、熟練作業者に依存する業務ノウハウがあるはずです。熟練者が持つノウハウは、指/手/腕/足が最短距離で、無駄なく動いていて、かつ体幹がぶれないので、正確に作業が行えてミスが起こりにくい特徴があります。
一方で未熟練作業者の場合、身体の動きが遠回り(ムリムダムラがある状態)しているので、1つの作業に多くの時間がかかってしまいます。さらに、体幹がぶれるので、作業ミスが起こりやすいでしょう。製造現場では、未熟練者を熟練者に近い水準に引き上げる教育が必要で、その場面で動画マニュアルがメリットを発揮します。
熟練作業者と未熟練作業者を比較する形で動画撮影すると、その違いは一目瞭然で、熟練作業者の技能(ワザ)を可視化できるので動画マニュアルが有効です。
未然防止の実現には「標準化」が重要
未然防止における「標準化」の重要性
未然防止とは、過去に起きた事故をもとに、将来的に発生が予想されるリスクへ対策を講じることです。つまり、対策内容や遵守の意識などが職場で浸透している必要があります。
これらは職場のルール、いわば「標準」として理解されていることが不可欠といえるでしょう。過去に起きた事象をふまえて、あらゆる側面から未然防止策を講じていたとしても、その内容が職場に浸透しておらず従業員が不遵守していたら事故が起こりかねません。
だからこそ、未然防止の実現には「標準化」が大切なのです。
標準化には動画マニュアルが有効
標準化を推進する手段として、以下のような取り組みがされるケースが多いものの、内容が伝わらないという課題に直面しやすいです。
- 座学研修:1度の受講で内容は完璧に理解されない。人により理解度も差が生じる。
- OJT:トレーナーによって教え方や内容が異なる。多忙の場合は質問しにくい。
- 文書マニュアル:作成や改訂が追い付かず、内容が実態と乖離している。
そのため、標準化を推進するためには「正しい内容を繰り返し見れる」状態が理想です。この状態を実現できる手段の1つとして、有効なのが動画マニュアルです。
読解力や言語の差に左右されない
文章や口頭で説明する場合、受け手の解釈に幅が出てしまい、上手く標準化の基準を伝えられない可能性があります。
一方、動画は内容を「目で見て」理解するため、解釈に幅が出ず、正しい内容を伝達できるでしょう。また、動画ならば外国人従業員の方へも、内容を伝えやすいというメリットがあります。
自分のペースで何度でも復習できる
対面での教育と違って、動画を活用すれば自分の都合の良い時間に学習を行えます。また、難しい部分を繰り返し動画を視聴し、理解を深めることもできるでしょう。
新人によくある『上司に質問しにくい…』という、心理的なハードルも取り除けます。
教育工数を大幅に削減できる
標準化する内容を伝えるには、何度も周知を促す必要があります。そのため、教育工数が膨大になり、本来の業務に注力できない時間が生じるケースも珍しくありません。
そこで標準のような業務・職場のルールを「動画を見て学ぶ」という方法を取れば、教育工数を大幅に削減できます。その中でもしもわからないことがあれば、トレーナーに聞くというフローにすれば、メリハリのある教育体制を実現でき、効率的に標準化を進められるでしょう。
標準化の推進に動画マニュアルが有効な理由は、以下のガイドブックでも詳しく解説しています。クリックして本記事と併せてご活用ください。
>>動画マニュアルを活用して「企業が業務標準化に着手すべき理由」を見てみる
標準化の推進に動画マニュアルを活用している事例
ここからは動画マニュアルを活用し、標準化を推進している事例として新日本工機株式会社をご紹介します。同社は、かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を活用して標準化に取り組んでいます。
▼動画マニュアル活用インタビュー:新日本工機株式会社▼
工作機械などの製造販売を行っている新日本工機株式会社では、作業の標準化ができておらず、基準が曖昧な状態で仕事を進めてしまっていた過去がありました。そこで、標準化プロジェクトを立ち上げて、tebiki現場教育による標準化の推進を決定。
文字ベースのマニュアルから動画に置き換えることで、作業手順を視覚的にわかりやすく伝えることに成功し、作業品質の安定を実現しました。さらに、tebiki現場教育の自動翻訳機能により、海外向けの手順書作成の工数がゼロに。プロジェクトメンバーへの負担軽減という点でも大きな効果を発揮できました。
同社が活用する、tebiki現場教育の特徴として以下のようなものが挙げられます。
- 100カ国語以上への自動翻訳
- 字幕の読み上げ(多言語にも対応)
- アクセス履歴等がわかるレポート機能
- オリジナルのテストを作成できるテスト機能
- 従業員のスキルを評価・可視化できる機能 など
tebiki現場教育のより具体的な機能やプラン、実際に動画マニュアルを活用した業務改善事例を知りたい方は、以下のリンクをクリックして概要資料をご覧ください。
>>かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」の概要資料を見てみる
まとめ
未然防止とは、過去の事故やトラブルを活かして将来起こり得るリスクを予測し、事前に対策を実行して被害を防ぐ活動です。一方、再発防止は、すでに発生した問題の根本原因を特定し、同じ問題を繰り返さないようにする取り組みを指します。
未然防止を着実に行うためには、3ステップ対策の流れや未然防止型QCストーリーの方法に沿って行うことが効果的です。そして、未然防止を確実に実行するためには「標準化の推進」がカギを握るといえます。動画マニュアルを活用して標準化を推進することで、正しい内容を繰り返し学習でき、教育工数を削減しながら従業員の理解度を高めることが可能になります。