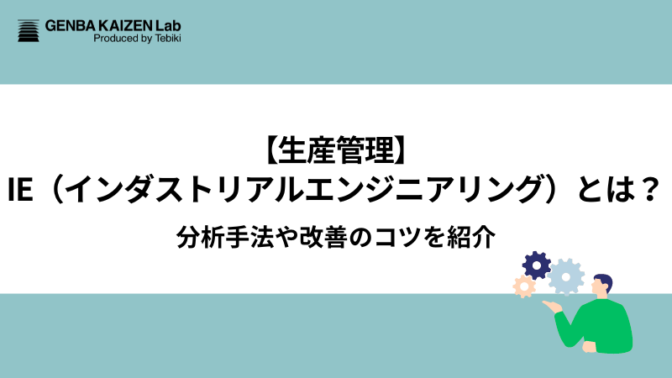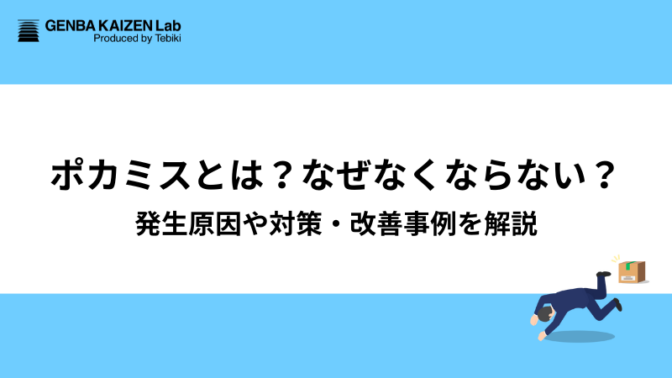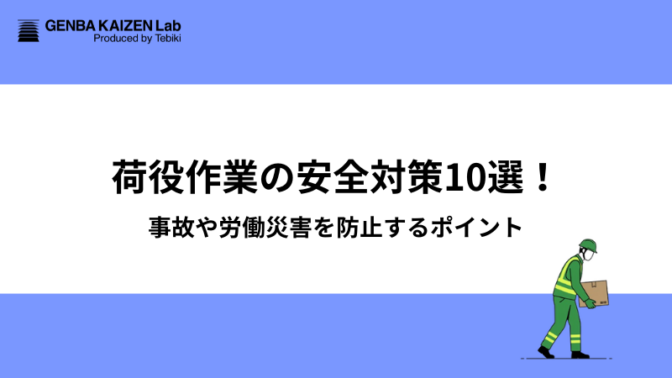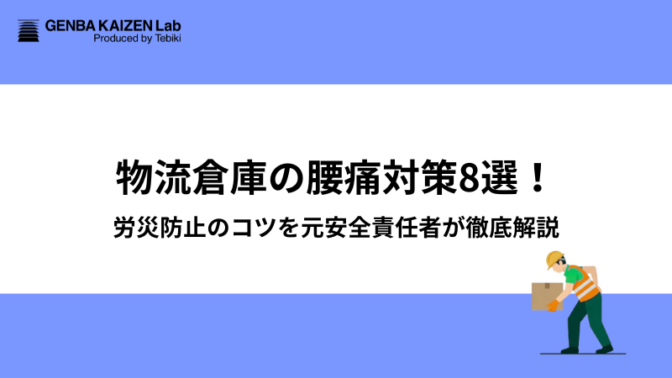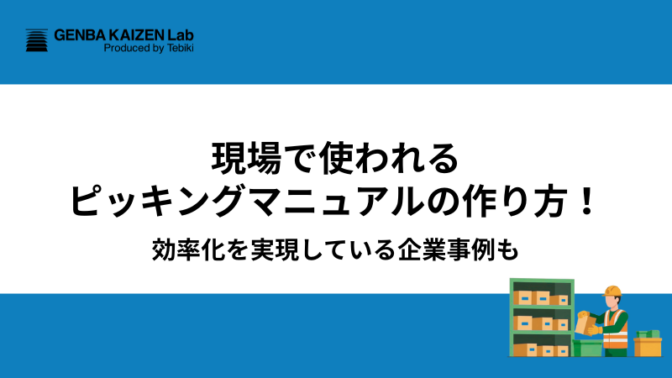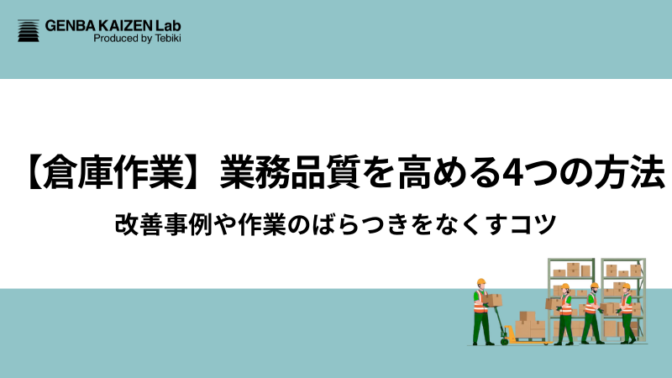工場向け安全対策の動画マニュアル「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
足場作業は建設現場やプラント工事などで必須の高所作業ですが、わずかな不注意が命に関わる重大災害につながりかねません。足場作業での事故を防ぐには、法令遵守だけでなく「誰が見ても同じ行動ができる」マニュアル整備や「誰が教えても同じ教育内容」を実現する仕組みが必要になります。
この記事では実際に工場の勤務経験がある筆者の観点も踏まえ、労働安全衛生法・安衛則の要点から実際のヒヤリハット・死亡事例、さらに教育と可視化で安全文化を築いた企業事例まで、足場作業の安全対策を解説します。
なお昨今、「安全な作業手順を動画マニュアルで見える化し、標準化を進める」現場が増えており、工場における主要な安全対策として広く浸透し始めています。詳しい改善効果や事例は「動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例(pdf)」をご覧ください。
労災が起きてからでは遅いので、ヒヤリハットで済んでいる現状のうちに安全対策を練ることが鍵を握ります。
>>「動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例(pdf)」を見てみる
目次
足場作業に潜む危険と安全対策が重要な理由
足場作業は建設現場など高所で不可欠ですが、墜落・転落といった労働災害に直結しやすい作業だといえます。
実際に厚生労働省が公表した「令和6年労働災害発生状況」*1によれば、墜落・転落は死亡事故のうち188人と最多要因として報告されています。高所で行われる足場作業ではこうした災害が発生し怪我や死亡につながるおそれが高いため、十分な安全対策が必要です。
事故を招きかねない物理的な要因としては、手すりの未設置や幅木の欠落、フルハーネス型安全帯の未使用、部材の腐食・損傷といった基本的な安全対策の欠如などが考えられます。しかし、このような「ハード面」での要因のみならず、現場によって手順や判断基準が異なる「標準化の欠如」や教育の属人化、そしてヒヤリハット情報が共有されない「可視化不足」といった人に起因する「ソフト面」での要因が影響していることも少なくありません。
そのため、足場作業の安全対策で重要なのは単なる設備の有無だけでなく、「正しい知識を・全員が・同じ手順で実践できる体制」をいかに構築するかにあります。マニュアルを整備して安全基準を明文化し、教育を標準化することで、経験や立場に関係なく誰もが同じ安全対策を実践できる現場をつくることが望ましいでしょう。
労災が起きてからでは遅いので、ヒヤリハットで済んでいる現状のうちに安全対策を練ることが必要です。
>> 「動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例(pdf)」を見てみる
足場の構造と安全装備の理解
足場作業を安全に行うには、構造と装備を正しく理解することが必要です。具体的には以下の4つの事項をおさえるとよいでしょう。
- 足場の種類と特徴
- 構成部材と役割
- 必須の安全装備
- 点検・整備が必要な箇所
足場の種類と特徴
足場には作業内容や現場環境に応じて、単管足場・枠組足場・くさび緊結式足場の3種が主に使われます。違いや注意点を以下の表にまとめました。
| 足場の種類 | 特徴 | 利点 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 単管足場 | 鋼管を組み合わせて 自由に構築 | 狭所や複雑形状の現場に対応可能 | 組立精度が安全性に直結 |
| 枠組足場 | 鋼製フレームを 連結して構築 | 強度が高く組立が早い | 重量があり 地盤確認が重要 |
| くさび緊結式足場 | ハンマーで連結できる モジュール型 | 組立・解体が簡単で効率的 | 緊結不良は崩落の危険 |
単管足場は自由度が高く、狭い場所や配管周りの作業などに適しています。枠組足場は建築現場で馴染みのある形式で強度が高く組立も早いのが特徴ですが、重量があるため地盤の安定確認が必須です。
くさび緊結式足場はハンマーで連結でき、作業効率が高く安全性にも優れています。ただし緊結部の確認を怠ると崩落の危険があるため、設置時に必ず点検が必要です。現場では作業の性質・高さ・荷重を総合的に考慮し、最も安全な足場を選定するようにしましょう。
現場の安全を守るには、まず足場の種類に応じたリスクを正しく理解することが不可欠ですが、そのリスクを「知っている」ことと「正しく行動できる」ことは別問題です。知識があっても、「うっかり」「面倒」といった不安全行動が起これば事故につながりかねません。
この不安全行動を「安全教育」によっていかに防止するか、具体的な方法をまとめた資料もご用意しています。是非併せてご一読ください。
>>繰り返される不安全行動はどう再発防止する?行動科学から編み出す決定的防止網を見る
構成部材と役割
足場を構成する代表的な5つの部材を以下の表にまとめました。
| 部材名 | 主な役割 | 点検の重要ポイント |
|---|---|---|
| 建地(たてじ) | 足場の柱として全体を支える | 垂直精度・腐食・接続状態 |
| 水平材 | 作業床の支持・強度確保 | 締結部の緩み・曲がり |
| 手すり・中さん | 墜落防止・体の支え | 固定の有無・高さ基準 |
| 幅木 | 工具・部材の落下防止 | 割れ・欠損の有無 |
| ジャッキベース | 地面との安定接地 | 地盤沈下・水平調整 |
建地は足場全体を支えるため、垂直でなくなると同時に全体が傾きます。水平材は作業床を安定させる骨格で、緩みがあると歩行時に揺れが生じます。手すりや中さんは墜落を防ぐため、高さ基準(地上1.1m以上)を満たしているか必ず確認しましょう。
幅木は工具の落下を防ぐため、足元10cm以上の高さで設置する必要があります。また、ジャッキベースは足場を支える部材で、地盤沈下が起きると全体が歪みます。部材は1つでも欠けると安全性が崩れるため、組立後の点検と緩み防止の確認を徹底することが重要です。
このように足場の安全は、作業員一人ひとりの知識によって支えられています。 だからこそ、その知識を伝える現場教育が形骸化してしまうと安全は確保できません。 現場の安全教育を形骸化させない実践的な取り組みについては、以下の資料で詳しく紹介しています。
>>ゼロ災を達成!形骸化させない安全教育の「新常識」について詳しく見る
必須の安全装備
足場作業で命を守るために活用される主な安全装備を以下の表にまとめました。
| 装備名 | 目的・役割 | 使用時の注意点 |
|---|---|---|
| フルハーネス型安全帯 | 墜落時の衝撃を全身で吸収 | 背中D環を正しく使用、 吊り下げ点検 |
| ヘルメット | 落下物から頭部を保護 | あごひもを必ず締める |
| 安全靴 | 滑り・踏み抜き・転倒防止 | ソールの摩耗確認 |
| 手袋 | 手の切創防止・グリップ確保 | サイズと素材選びが重要 |
| 反射ベスト | 夜間・屋外での視認性向上 | 光源方向の確認が必要 |
フルハーネス型安全帯は墜落時に衝撃を体全体で分散し、胴部への集中を防ぎます。装着時は背中のD環が中心にくるように調整することが重要です。ヘルメットは落下物や頭部の打撃から身を守りますが、あごひもを締めなければ意味をなさないので注意しましょう。
安全靴は滑り止めや踏み抜き防止機能を備え、雨天や油面でも安定した足場を確保します。さらに手袋は滑り防止と手の保護が可能で、反射ベストは暗所での視認性を高めます。
ここまで紹介した安全装備品も、使用方法が誤っていれば危険を防ぐことはできません。誤った知識は、現場の作業員を命の危険にさらすことになります。
安全装備を「持っているだけ」で終わらせないためにも、正しい「選び方」「使い方」「確認」の方法を深く理解し、現場で確実に活かすことが重要です。
このような正しい現場ルールや手順を手間なく伝える手段として、「動画」の活用が注目されています。動画が役立つ理由や実際のサンプル動画について、本文のほか以下の資料でも詳しく展開しているため是非ご覧ください。
>>安全意識が高い現場はもう採用している!現場の安全ルール・手順をわかりやすく伝える「動画マニュアル」の改善効果や事例を詳しく見る
点検・整備が必要な箇所
足場の安全性を維持するには、定期的な点検と整備が欠かせません。ここでは点検・整備が必要な箇所について以下の表にまとめました。
| 点検箇所 | 点検内容 | 対応策 |
|---|---|---|
| 建地・水平材 | 緩み・腐食・曲がり | 締付・交換 |
| 手すり・幅木 | 固定状態・欠損 | 再固定・補修 |
| ジャッキベース | 沈下・傾き・ズレ | 再設置・地盤補強 |
| 緊結金具 | ゆるみ・摩耗 | 増締・交換 |
| 全体点検 | 構造・揺れ・変形 | 責任者による確認記録 |
特に建地や水平材の緩み、腐食、曲がりは構造全体の強度を弱めます。手すりや幅木が外れている場合は墜落や落下物事故の危険があり、速やかに補修すべきです。ジャッキベースは足場を支えるため、地盤の沈下や傾きを見逃すと崩落につながります。緊結金具の摩耗やゆるみも見落とされがちな注意すべき項目です。
このような不備を防ぐため、可能であれば始業前・中間・解体前の3段階点検を実施し、結果を記録に残すとよいでしょう。点検は形式的に行うのではなく、現場全体の安全意識を高める行動として継続することが重要です。
一方で点検が「流れ作業」になってしまうと本来の目的を見失い、形骸化してしまいます。それを防ぐには、作業者一人ひとりが普段から「現場に潜んでいるかもしれない危険」に気づける力を養うことが大切です。
そして、その「危険に気づく力」を実践的に高める手法こそがKYT(危険予知訓練)です。従業員の危険感受性を高めるKYTの具体的な進め方や好事例については、下記資料で詳しく解説しています。
>>従業員の危険感受性を高める!形骸化しない「KYT」の手法や事例を見る
【法令知識】足場作業に関する労働安全衛生法と安衛則の要点
足場作業は労働災害が多発する高リスク業務です。労働安全衛生法*2および労働安全衛生規則*3では、事業者の責務や足場構造の基準、教育体制などを厳格に定めています。ここでは具体的に以下の3点について解説します。
事業者と作業主任者の責務(労働安全衛生法 第20条・第21条)
労働安全衛生法第20条は事業者に対し「機械・器具・電気・熱などによる危険を防止するため必要な措置を講じる義務」を定めており、要するに、足場作業における墜落・転落・感電・火災といったリスクを想定して設備や環境面で危険を除去することが求められています。さらに第21条では、掘削・荷役・伐木など作業方法から生ずる危険、特に「墜落の恐れがある場所」に対する安全措置を義務付けています。
足場作業では、労働安全衛生法 第20条・第21条に基づき「手すり・安全帯・作業床」の設置や「作業主任者の選任」が必須です。主任者は組立・解体・点検の手順を管理し、作業員へ危険箇所を明確に周知しなければなりません。条文は「措置義務」を明示していますが、実際には「教育・記録・点検の実行」が法の趣旨とも読み取れます。
現場の安全管理を徹底するには、法令の理解だけでなく実践的な仕組みづくりが欠かせません。事業者・管理者の責務や罰則、安全教育の進め方を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:【製造業向け】労働安全衛生法とは?義務一覧や罰則・安全対策の具体例
設置・手すり・幅木・点検の基準(労働安全衛生規則 第563〜567条)
労働安全衛生規則第563条は、足場の構造基準を明文化した条文です。高さ2m以上の作業場所では「幅40cm以上」「床材間の隙間3cm以下」「床材と建地の隙間12cm未満」の作業床を設けることを義務付けています。さらに、墜落防止のため「手すり・中桟・幅木」を設け、こうした設備は強度と損傷の有無を確認する必要があります。
続く第564条では、足場の組立て・解体・変更時の安全措置として、強風・豪雨・積雪時の作業中止や作業区域への関係者以外の立入り禁止などを講ずることが事業者の義務としています。また、墜落防止のために「要求性能を満たす墜落制止用器具(フルハーネス)」の使用を求め、取り付け設備を設けることも明記しています。
安全設備の基準は「知っている」だけでは不十分です。正しい教育と実践で、形骸化した安全活動を現場に根づかせる方法は以下の記事で紹介しているため併せてご覧ください。。
関連記事:高所作業における安全義務や具体的な対策!形骸化しない安全教育とは?
法改正の背景と「標準化・教育・記録整備」の重要性
足場に関する法改正は、過去に相次いだ墜落・転落事故を背景に進められてきました。特に2019年の改正で「手すり先行工法」と「フルハーネス型安全帯」の使用が義務化され、従来の胴ベルト型から大きく転換した結果、組立時の一時的な無防備状態を防ぐことが可能になりました。
また、安衛則第655条では、元請(注文者)にも足場の安全確保義務が課せられ、請負構造が複雑な現場でも統一的な安全管理が求められるようになっています。
こうした流れの中で重要となるのが「標準化」「教育」「記録」です。安全マニュアルの共有や教育による理解統一、点検・是正の記録保存を行えば、法令遵守が安全対策の文化として根付いていくと考えられます。
安全教育を強固にする「標準化」「教育」「記録」の具体的な実践策については、本文のほか以下の資料でも詳しく展開しています。
足場作業におけるヒヤリハット・事故事例
足場作業におけるヒヤリハット・事故事例として以下の4例を紹介します。
- 【ヒヤリハット】作業台清掃中、水のホースが飛び上がってバランスを崩した
- 【ヒヤリハット】雨天時の荷台作業で滑り転落しかけた
- 【死亡事故】緊結前の足場板に乗り墜落
- 【死亡事故】ボンジョイント使用による単管落下
このようなヒヤリハットは、労働災害を防ぐヒントとなる重要な情報です。
現場からヒヤリハットを吸い上げ、対策に落とし込むことはゼロ災達成に効果的ですが、「報告書の作成が手間」「報告フローが未整備」といった課題が原因でうまくいかないケースも見られます。
そのような現場に向け、現場ですぐに使える「ヒヤリハット報告書」が内包されたヒヤリハット事例・対策集をご用意しておりますので、是非お役立てください。
>>すぐに使えるヒヤリハット報告書付き!報告から教育まで行えるヒヤリハット事例・対策集を見る
【ヒヤリハット】作業台清掃中、水のホースが飛び上がってバランスを崩した
清掃時に起こりやすい「水圧の反動による転倒リスク」がわかる事例です。*4
| ヒヤリハットの詳細 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 踏み台(高さ70cm)で作業台を清掃中、水の反動でホースが暴れバランスを崩し転落しそうになった。 | ・ホースの水量が多すぎた ・水圧の変動によりホースが暴れバランスを崩した | ・ステップ面が広い脚立を使用する ・常に足元の安定を確認する ・滑り防止のため、軍手を装着する |
ホースの水量が急に変化すると制御が難しくなり、狭い足場では転倒や墜落の危険が高まります。安全のためには水圧を徐々に調整して安定を確認してから作業を始めること、またホースを片手で操作せず、両手で支えて姿勢を安定させることが重要です。
水圧の変化によるホースの飛び上がりは、わずかな油断でも転倒や墜落につながる危険があります。ヒヤリハット事例を他にも知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
関連記事:工場のヒヤリハット事例21選!原因と再発防止対策、安全意識を高める方法
【ヒヤリハット】雨天時の荷台作業で滑り転落しかけた
トラック荷台上での荷降ろし準備中に雨で濡れた鋼材の上で足を滑らせ、転倒しかけたヒヤリハットの事例です。*5
| ヒヤリハットの詳細 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 鋼材のシート外し中、濡れた鋼材で滑り転落しそうになる。安全帯着用で転落は免れた。 | ・濡れた鋼材の滑りやすさを軽視していた | ・荷台でも安全帯を必ず着用する ・天候や足場の状態を事前確認する ・雨天時は滑り止め靴を使用し足元のリスクを予測する |
このように雨天時の作業では、足元のリスクや危険を予測する力が欠かせません。従業員の危険感受性を高める手段である「KYT(危険予知活動)」の具体的な進め方や好事例については、下記資料で詳しく解説しています。
>>従業員の危険感受性を高める!形骸化しない「KYT」の手法や事例を見る
【死亡事故】緊結前の足場板に乗り墜落
足場の組立て工事中、鋼製足場板ごと約9メートル下へ墜落した死亡災害の事例です。*6
| ヒヤリハットの詳細 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 施工管理中、足場組立時に未緊結(未固定)の足場板に乗ったため、板ごとコンクリート床に墜落した。 | ・未固定の足場板に乗ったこと ・作業手順の不備、緊結作業の遅れ ・安全帯の未使用・施工計画の届出違反 | ・足場板は設置後すぐに緊結する ・作業手順を適正化し確認する ・安全帯を確実に使用する ・施工計画届を事前に提出する |
未緊結の足場板への立ち入りは、死亡事故を引き起こしかねない重大な要因です。このような事故を防ぐうえで重要な「従業員の不安全行動」を防ぐ秘訣については、以下の資料で詳しく展開しているため是非ご覧ください。
>>繰り返される不安全行動はどう再発防止する?行動科学から編み出す決定的防止網を見る
【死亡事故】ボンジョイント使用による単管落下
単管足場の組立て中に、ボンジョイントの脱落が原因で死亡災害が発生した事例です。*7
| ヒヤリハットの詳細 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 屋上から「ボンジョイント」で連結した単管を下ろす際、接合部が外れ単管(4m)が落下。真下の作業員に直撃し死亡。 | ・摩擦式ボンジョイントの構造的な不安定さ ・接合強度への過信 ・衝撃で外れやすいボンジョイントの使用 | ・ボンジョイントを使用しない(厚労省注意喚起) ・溶接式やクランプ式など確実な接合部材を使用する |
この事例は、わずかな「手間の省略」が命取りになる典型的な例です。本来は作業手順書などで現場ルールや正しい手順を周知しているものの、「わかりにくい」「読む暇がない」といった理由でルールの逸脱が見られることも。
現場ルールを浸透させ、守らせるコツや対策については以下の資料内で詳しく展開しています。是非ご参照ください。
>>“手順書通りにできない”から卒業!作業ルールを守らせる効果的な方法を見る
【教育面】足場作業の3つの安全対策
足場作業の安全対策を現場で根づかせるには、教育の仕組みづくりが必要です。ここでは、以下の3つの教育の方法を解説します。
- 標準化で安全作業の「基準」を作る
- 適切な技術伝承で安全作業の「教え方」を「統一」する
- 危険意識で危険やヒヤリハットを可視化して「自分事」にする
標準化で安全作業の「基準」を作る
足場作業では、誰が作業しても同じ動きができる「安全の基準づくり」が必要です。曖昧な手順書のままでは作業者ごとに判断が異なり、ヒューマンエラーによる労働災害を誘発します。
例えば「手すりを設置する」とだけ書かれていても高さ・順序・固定方法が不明確では事故を防げません。そのため安全作業の基準を作り、現場全体の標準化を推進することが重要です。
標準化を推進する有効手段として、動画マニュアルや図解付きの手順書など、視覚的に理解しやすい教材の整備が挙げられます。正しい立ち位置を図で示せば、全員が共通の基準で作業ができます。
実際に化学メーカーである児玉化学工業株式会社は、動画マニュアルによる標準化推進を実現しています。
※以下の動画は同社の現場従業員がスマホで作成した、実際のサンプル動画です。
▼動画マニュアルによる標準化の例▼
※「tebiki」で10分で作成
上のような複雑な業務作業も、動画で手順をおさめれば「誰が見ても同じ解釈」になり、安全作業の基準を作れます。
※本動画は、製造業の現場教育に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」で作成されています。tebikiのサービス詳細や導入事例についてはサービス資料をご覧ください。
>>かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育サービス資料」を見てみる
適切な技術伝承で安全作業の「教え方」を「統一」する
足場の組立や解体において、教育のばらつきは事故を生む要因です。特にOJTが中心の現場では指導者によって教え方が異なり「人によって手順が違う」状態が生じやすくなります。
足場作業における業務品質や認識のばらつきを防ぐには「誰が教えても同じ教育内容」を整備することが大切です。動画教材や標準化マニュアルを活用すれば、言語や経験の違いを超えて、共通理解が得られます。
具体例として、明和工業株式会社では作業場にディスプレイを設置し、QRコードで即座に動画マニュアル(を呼び出せる仕組みを設けており、誰でも迷わず標準作業を実行できる環境が整えています。

危険意識で危険やヒヤリハットを可視化して「自分事」にする
どんなにルールやマニュアルを整備しても、最終的に事故を防ぐのは作業者一人ひとりの「危険意識」です。しかし、経験を積んだベテランほど「自分は大丈夫」と慢心しやすく、油断が労働災害を招いてしまうことも。
作業者の慢心を防ぐには、危険の可視化が効果的です。実際のヒヤリハット事例や映像を共有し、危険行動がどんな結果を生むのかを目で見て理解させます。
さらに、KY(危険予知)活動やヒヤリハット掲示板を活用し、現場で起きた「ヒヤリとした瞬間」をチーム全体で共有することで、「一人で気をつける」から「全員で守る」職場文化が生まれます。
※危険予知活動(KY活動)の進め方の詳細は「KY活動(危険予知活動)の進め方は?記入例文やネタ切れ対策を紹介」でも解説しています
危険を可視化し、共有すれば足場作業の事故を未然に防ぎ、怪我や死亡という最悪の事態も防ぐことが可能です。
一方でKY活動は「形だけ」「マンネリ化」といった形骸化が起こることがしばしばあります。これは、作業員が危険を自分事化していない(そんな大事にはならないだろう、と思い込んでいる)ことが根本的な原因です。
安全意識を根付かせるための1つの指針として「動画KYT」が挙げられますが、詳しくは以下の資料で解説しているので、併せてご参照ください。
関連資料:労災ゼロ!形骸化したKYTから脱却する動画KYTとは
【作業面】足場作業の現場で実践すべき7つの安全対策と注意点
足場作業の現場では、危険を「予防」する具体的な行動が重要です。ここでは具体的に以下の7つの安全対策及び注意点について解説します。
- 組立・解体は手すり先行工法を徹底
- 高所作業はフルハーネス型安全帯の常時着用
- 作業床は幅40cm以上・隙間12cm未満・幅木10cm以上
- 昇降は手すり付き階段を使用、手ぶら昇降禁止
- 落下物対策は防網・メッシュシート・朝顔設置
- 点検は始業前・解体前点検の記録義務化
- 天候判断は強風・降雨・積雪時の中止ルールを明文化
組立・解体は手すり先行工法を徹底
足場の組立や解体作業で多く発生しがちな墜落事故の原因が、作業床や手すりが設置される前に高所に上がる「先行作業」にあることもよく見受けられます。
この「先行作業」を防ぐのが、手すり先行工法です。作業者が足場の上に上がる前に上段の手すりを地上または下段から設置できるため、常に墜落防止設備の中での作業が可能です。
法令上も労働安全衛生規則第564条において「足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、労働者の墜落を防止するための措置を講じなければならない」と義務付けられており、厚生労働省も手すり先行工法を推奨しています。
特に管理者は施工計画書に手すり先行工法の採用を明記し、教育・指導を徹底することが重要です。手すり先行工法を徹底することで、「高所での不安定な姿勢」そのものを無くせるため、現場の安全が守られるでしょう。
関連資料:繰り返される不安全行動はどう再発防止する?行動科学から編み出す決定的防止網
高所作業はフルハーネス型安全帯の常時着用
墜落事故の致命的なリスクを防ぐには、フルハーネス型安全帯の常時着用が必須です。腰ベルト型に比べて体全体で衝撃を分散できるため、転落時の致命傷を防げます。特に高さ2メートルを超える足場作業では、労働安全衛生規則第564条で「墜落制止用器具の使用」が義務付けられています。
装着時はD環やバックルの緩みを点検し、胴ベルト・肩ベルト・脚ベルトが正しい位置にあることを確認しましょう。管理者はサイズ不適合や破損した器具を放置せず、点検・更新を定期的に行う体制を作る必要があります。
作業床は幅40cm以上・隙間12cm未満・幅木10cm以上
足場の作業床は、労働安全衛生規則第563条で定められており、床幅は40cm以上、床材の隙間は3cm以下、建地との隙間は12cm未満が原則です。さらに、工具や資材の落下を防ぐため*高さ10cm以上の幅木(つま先板)を設ける必要があります。
基準から逸脱することで足の踏み外しや資材落下による重大事故につながりかねないため、厳守が求められます。現場では「一時的な仮設だから」といった油断が事故の引き金になるため安全基準は「例外なく守る」ことが鉄則です。
足場構造や高所作業の安全基準を詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:高所作業における安全義務や具体的な対策!形骸化しない安全教育とは?
昇降は手すり付き階段を使用、手ぶら昇降禁止
足場での昇降時に事故が多いのは、片手で資材を持ったまま昇り降りする行為です。こうした行為を防ぐために、手すり付き階段の使用と手ぶら昇降の徹底が必要です。はしごや単管を足場代わりに登る行為は極めて危険で、バランスを崩して墜落する事例が後を絶ちません。
資材の運搬にはロープ吊りやウインチを使用し、作業者は常に両手を自由にしておいてください。手すり付き階段を設けることで、昇降時の安定性が向上し、移動時の事故を大幅に減らせます。特に管理者は「安全装備を設けたのに使われない」という状況を防ぐため、使用ルールを明文化し、教育に組み込むことが重要です。
昇降時の転落は、日常の慣れが原因で起こります。安全な昇降行動を定着させるKYT(危険予知訓練)の実践方法は、以下の記事で詳しく紹介しています。
>>従業員の危険感受性を高める!形骸化しない「KYT」の手法や事例を見る
落下物対策は防網・メッシュシート・朝顔設置
足場作業では、上層からの落下物による二次災害が頻発することも。防止策として、防網・メッシュシート・朝顔(落下防止ひさし)の3点を組み合わせるのが効果的です。防網は工具や部材の落下を受け止め、メッシュシートは小さな破片や粉じんの飛散を防ぎます。朝顔は建物外周に設けることで、通行人や下層作業者を守る構造です。
特に強風時や解体作業中は、固定の緩みやシート破損の有無を確認しましょう。落下物事故は一瞬の油断から起こります。上から落とさない・下から守るといった二重の対策で抜け漏れのない内容にすることが求められます。
関連記事:【事例も紹介】転倒災害が発生しやすい環境とは?現場で実践できる改善策も
点検は始業前・解体前点検の記録義務化
足場の安全性は、一度設置して終わりではありません。始業前点検と解体前点検の実施・記録化が必須です。点検内容は、部材の緩み・変形・腐食・設置位置のずれ・安全装置の欠損など多岐にわたります。
労働安全衛生規則第567条では足場の点検を行う者を定め、結果を記録・保存することが義務付けられています。管理者はチェックリストやデジタル点検シートを活用し、誰がいつどの箇所を確認したかを可視化することが大切です。
記録を残すことで点検漏れの防止とともに、万一の事故時にも「安全確認を行った証拠」として機能します。
点検の「見える化」は、安全文化につながります。法令に基づく点検義務や罰則、安全確認の仕組み化を詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:【製造業向け】労働安全衛生法とは?義務一覧や罰則・安全対策の具体例
天候判断は強風・降雨・積雪時の中止ルールを明文化
足場作業は屋外で行われるため、天候リスクを軽視すると一瞬で事故が起こります。特に風速10m/s以上の強風、降雨、積雪時の作業中止は中止してください。湿った足場板や凍結した鋼材は滑りやすく、わずかな風でもバランスを崩す危険があります。
現場では「少しぐらいなら大丈夫」という判断が命取りになります。そこで有効なのが、作業中止基準を明文化したルールブックや手順書の整備です。誰が現場責任者として判断するのか、どの条件で作業を中断するのかを明確にし、全員に共有します。さらに気象アプリや風速計を活用し、感覚ではなく数値で判断する仕組みを導入することが効果的です。
関連資料:“手順書通りにできない”から卒業!作業ルールを守らせる効果的な方法
危険な作業現場の可視化に成功した事例
危険な作業現場の可視化に成功した事例として、以下の2社を紹介します。
- コスモ石油株式会社|KYTを動画で可視化し、安全文化を現場全体に定着
- トーヨーケム株式会社|危険作業を映像で再現し、教育を標準化・省力化
コスモ石油株式会社|KYTを動画で可視化し、安全文化を現場全体に定着
石油精製大手のコスモ石油株式会社 堺製油所は、ガソリンや灯油などの高危険物を扱うため、「安全第一」が絶対条件の職場です。同社では従来のテキスト中心の安全教育に限界を感じていました。文字情報だけでは理解度に個人差があり、協力会社を含めた全員に均一な指導を行うことが難しかったといいます。
そこで導入したのが、動画マニュアル作成ツールの「tebiki現場教育」でした。tebiki現場教育によって、紙では伝えにくい危険動作や作業手順を映像で「見える化」に成功しました。実際の災害事例を再現した動画を教材として活用し、月1回の「ゼロ災実行リーダー会議」では協力会社も交えてKYT(危険予知トレーニング)を実施しています。
動画を活用することで安全意識が全員で共有できるようになり、教育担当者の負担も軽減。紙のマニュアルを印刷・配布する手間も省け、教育効率が飛躍的に向上しました。現場からは「映像で危険を実感できる」「新入社員でもわかりやすい」と高く評価されています。
コスモ石油株式会社では動画によるKYTで危険を見える化し、安全文化を浸透させています。現場の理解度を高め、教育負担を軽減するデジタル手法については、以下の事例で詳しく紹介しているのでぜひご覧ください。
>>同社が扱う動画マニュアル「tebiki現場教育」の紹介ページはこちら
トーヨーケム株式会社|危険作業を映像で再現し、教育を標準化・省力化
トーヨーケム株式会社は、東洋インキグループの中核を担う化学メーカーで、粘着剤や機能性フィルムなどを世界に展開しています。多様な製品を扱う同社にとって「安全で高品質なモノづくり」を支える教育の標準化は重要な課題でした。
同社の課題は、OJT(現場教育)の属人化と教育のばらつきでした。紙マニュアルでは動きを伴う工程を伝えきれず、「人によって教え方が違う」「危険な手順が現場ごとに異なる」といった問題が発生していたと言います。
こうした課題を解決したのが「tebiki現場教育」です。危険をともなう作業を映像で再現し、「どの動作が危険で、どの行為が誤りなのか」を視覚的に伝えることで、誰でも同じ内容を理解できる教育を実現しました。さらに、クラウド機能により現場で撮影した動画をすぐに教材化できるようになり、動画マニュアルの作成工数を半減、教育時間を3分の2に短縮しました。
現場からは「紙では伝わらない動きが理解できる」「映像で危険を実感できた」と好評です。トーヨーケムは、映像による教育の標準化で安全意識を統一し、属人化しない安全文化づくりに成功した企業の好例といえます。
トーヨーケム株式会社では、危険な作業手順を映像で再現し、誰もが同じレベルで理解できる教育を実現しました。OJT負担を減らしつつ、安全文化を定着させた仕組みについては、以下の事例で詳しく紹介しています。
>>同社が扱う動画マニュアル「tebiki現場教育」の紹介ページはこちら
結論:足場作業の安全は「標準化」「技術伝承」「可視化」で守る
足場作業の安全対策は、設備だけでなく「仕組み」で守る時代に入っています。この記事で紹介したように、法令遵守の徹底に加え、「標準化」「技術伝承」「可視化」を通じて、誰もが同じ手順で安全に作業できる体制づくりが重要です。
コスモ石油やトーヨーケムのように、動画による教育や危険の見える化を実践すれば、現場の理解度と意識は大きく変わります。事故ゼロを実現するために必要なのは、全員が同じ知識と行動を共有する職場を築くことにあると考えます。
- *1:厚生労働省「令和6年労働災害発生状況」
- *2:e-gov法令検索「労働安全衛生法」
- *3:厚生労働省「労働安全衛生規則第563条と第564条の整理について」
- *4:厚生労働省 職場あんぜんサイト「作業台清掃中、水のホースが躍ってバランスを崩し、踏み台から落ちそうになった」
- *5:厚生労働省 職場あんぜんサイト「トラック荷台上で鋼材に掛けていたシートを剥がす作業中、雨で濡れた鋼材の上で足が滑り転倒しそうになった」
- *6:厚生労働省 職場あんぜんサイト「足場の組立て工事中、足場板もろとも墜落」
- *7:厚生労働省「単管ジョイントにボンジョイントを使用して発生した災害の事例」
- *8:コスモ石油 堺製油所が実現する“安全第一”の動画教育改革
- *9:新人からベテランまで700名を超える組織教育のグローバルスタンダードを目指す