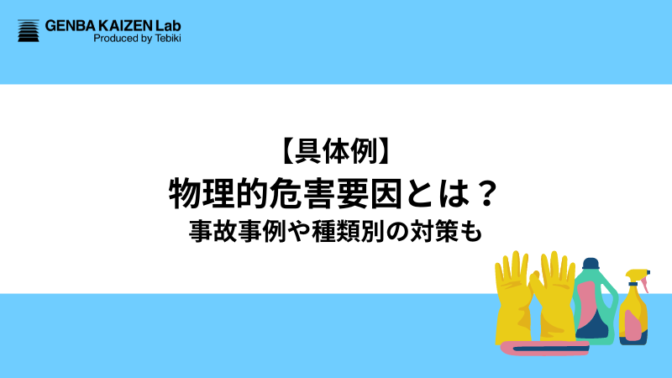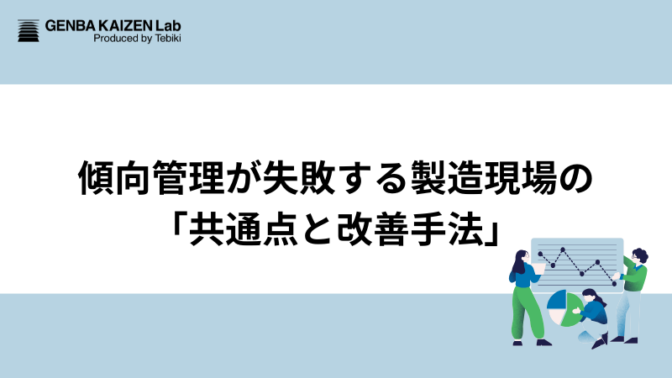かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を展開する現場改善ラボ編集部です。
「ゼロ災害」とは、単なる無事故状態を指すのではなく、職場に潜むあらゆる危険要因を根本から取り除き、全員参加で災害リスクを未然に防ぐ仕組みのことです。
この記事では、ゼロ災害の意味や企業が取り組むべき理由、現場での具体的な実践事例、そして形骸化を防ぐための対策までを体系的に解説します。安全性の高い現場改善を考えている現場責任者には、特に参考になると思います。
この「ゼロ災害」という高い目標を達成するためには、設備や環境といった物理的な危険要因だけでなく、人の行動に起因するリスクにも目を向けなければなりません。
多くの労働災害の背景には、作業者の「うっかり」や「思い込み」といった「ヒューマンエラー」が存在します。ゼロ災害を実現するには、このヒューマンエラー対策が避けては通れない、極めて重要なテーマとなります。
ゼロ災害に向けた取り組みの要となる、ヒューマンエラーを未然に防ぐための効果的な安全教育の進め方について、以下の資料で詳しく解説しています。
>>ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育を見てみる
目次
そもそもゼロ災害とは?基本を正しく理解する
ゼロ災害とは、災害を「出さない」ことを目指すのではなく、災害の原因となる危険を「なくす」プロセスを全員で実践し、安全文化を育てる取り組みのことです。ここでは具体的にゼロ災害について以下の2点を解説します。
- ゼロ災害の本質的な意味と目的
- ゼロ災害運動を支える「3つの柱(理念)」
この「全員参加」で危険を「なくす」プロセスを実践するための、代表的な手法の一つが「危険予知活動(KYT)」です。
作業前に危険を洗い出すKYTは、ゼロ災害の実現に不可欠ですが、毎日の活動がマンネリ化し、「形骸化」しやすいという大きな課題があります。
この形骸化したKYTから脱却し、参加者の危険感受性を本当に高めるための新しい手法として、近年「動画KYT」が注目されています。ゼロ災害を目指す活動の質を格段に向上させる、動画KYTの具体的な進め方について、以下の資料で詳しく解説しています。
>>労災ゼロ!形骸化したKYTから脱却する動画KYTとはを見てみる
ゼロ災害の本質的な意味と目的
ゼロ災害とは、「労働災害が一件も発生しない状態」を指すだけではありません。中災防(中央労働災害防止協会)が提唱する定義では「人間尊重の理念に基づき、全員参加で安全衛生を先取りし、一切の労働災害を許さない」ことを目指す運動とされています。
ここで重要なのは、結果としての「災害ゼロ」を求めるのではなく、その背景にある災害の原因、すなわち職場に潜む危険有害要因を根本から取り除く「プロセス」に主眼を置いている点です。
つまりゼロ災害とは、日々の業務の中で全員が危険に気づき、行動し、改善することの積み重ねによって築かれる、組織的・文化的な取り組みです。真の目的は、働く人一人ひとりが安全と健康を最優先に考え、自律的に行動する風土、いわば「安全文化」を社内に根付かせることにあります。
ゼロ災害運動を支える「3つの柱(理念)」
ゼロ災害の実現には、単なるスローガンではなく、明確な理念に基づいた行動が必要です。中核をなすのが以下の3つの理念です。
- ゼロの原則
- 先取りの原則
- 参加の原則
1. ゼロの原則
1つ目はゼロの原則です。ゼロの原則は「絶対に災害を起こさせない」という人間尊重の考えに立脚し、職場や作業に潜むすべての危険を徹底的に洗い出し、根絶しようという姿勢を意味します。
2.先取りの原則
2つ目は先取りの理念です。労災が起きてから対応するのではなく、危険の兆しを事前に察知し、未然に防ぐ行動を重視します。KYT(危険予知訓練)などの活動は、先取りの理念に基づく実践です。
3.参加の原則
3つ目が参加の理念です。経営者、管理監督者、現場作業員のすべてが、それぞれの持ち場で自主的に安全衛生活動に取り組むことで、安全を「誰かの仕事」にしない職場風土をつくり上げます。
なぜゼロ災害に取り組むのか?現場や企業にもたらされる3つの価値
ゼロ災害の推進は、単なる事故防止に留まりません。法的責任の遂行、企業価値の向上、そして人材の育成と、組織全体に大きな価値をもたらします。ここでは具体的に以下の3点について解説します。
- 企業が果たすべき「安全配慮義務」
- 生産性・品質・企業価値の向上
- 従業員の危険感受性と問題解決能力の向上
【法的側面】企業が果たすべき「安全配慮義務」
企業がゼロ災害に取り組む上で、基本となるのが「安全配慮義務」です。
労働契約法第5条では、使用者に対し「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするもの」と明記されています。安全配慮義務は単なる努力義務ではなく、労働契約に付随する法的責任です。
例えば、職場で災害が発生し、それが予見可能かつ防止可能だったにもかかわらず対策を怠った場合、損害賠償請求の対象となることがあります。
さらに、労災が報道されたり訴訟に発展すれば、企業の信頼や採用力、ブランドイメージにも深刻なダメージを与えます。ゼロ災害活動は、こうしたリスクを未然に防ぐ法的・社会的防波堤として、全企業にとって欠かせない取り組みと言えます。
関連記事:【事例あり】労働災害対策8選!職場で効果的な「安全意識向上の取り組み」とは
【経営的側面】生産性・品質・企業価値の向上
労働災害がもたらす損失は、単なるケガや休業に留まりません。生産ラインの停止や設備破損による修復コスト、業務の停滞による納期遅延、ひいては取引先からの信用失墜といった「見えない損失」が経営に影響します。
一方、安全な職場環境は、従業員の安心感を生み、定着率を高めます。さらに、士気の向上によって仕事への集中力が高まり、生産性や製品・サービスの品質向上にもつながります。
安全を重視する企業は、社内外から「信頼できる会社」として評価され、ブランド力の強化にもつながります。
【人材育成側面】従業員の危険感受性と問題解決能力の向上
ゼロ災害活動の価値のひとつは、人づくりにもあります。例えば、KYT(危険予知トレーニング)やヒヤリハット報告といった活動を通じて、従業員は自ら現場の危険を察知し、問題の本質を考え、改善行動を取る力を身につけていきます。
ゼロ災害活動は単なる安全対策に留まらず「自分で気づき、動く」人材を育てる良い機会になるでしょう。こうしたボトムアップの文化が根づけば、職場全体に自律的な改善の風土が広がり、業務効率やチーム力の向上にもつながります。
さらに、若手社員や外国籍スタッフも巻き込んだ全員参加型の安全活動は、組織の一体感を強め、より持続可能な現場づくりが実現できます。
このように「自分で気づき、動く」自律的な文化を育むことは、ゼロ災害活動の大きな目標です。
しかし、その文化づくりの前に立ちはだかるのが、「わかっているのに、ついやってしまう」という人間の「不安全行動」です。なぜ人は危険な行動を繰り返してしまうのか。その根本原因にアプローチし、対策を講じるためには、人間の行動原理を解き明かす「行動科学」の視点が非常に有効です。
自律的な安全文化を阻害する、繰り返される不安全行動を根本から防ぐための決定的な防止網を構築する方法について、以下の資料で詳しく解説しています。
>>繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網を見てみる
ゼロ災害を実現するための具体的な取り組み例
ゼロ災害を現実のものとするには、以下の2つの取り組み例が参考になります。
- 計画・体制づくりに関する取り組み
- 現場で実践する主な活動
計画・体制づくりに関する取り組み
ゼロ災害の実現には、現場任せの対応ではなく、組織としての明確な方針と体制づくりが大切です。まず重要なのが、経営トップによる強い決意表明です。「一人のケガ人も出さない」というトップの宣言は、全社的な意識改革につながります。
次に必要なのが、推進体制の構築です。安全衛生委員会とは別に、ゼロ災専門の推進チームを設けることで、継続的で具体的な活動が可能になります。そして、推進体制にもとづき、リスクアセスメントなどを活用して現場の実情を可視化し、年間の安全活動計画を策定します。
目標の明確化と進捗管理を行うことで「やりっぱなし」で終わらない安全活動が実現できます。
このように、経営トップのリーダーシップと、それを支える推進体制の構築は、ゼロ災害を実現するための「骨格」です。
そして、この骨格に血を通わせ、現場の従業員一人ひとりの行動を変える「血肉」となるのが、日々の安全教育です。トップの方針を現場の隅々まで浸透させ、本質的な安全文化を育むためには、これまでの形式的な教育を見直す「安全教育の新常識」を取り入れる必要があります。
組織として掲げたゼロ災害という高い目標を、現場の力で達成するための新しい安全教育のアプローチについて、以下の資料で詳しく解説しています。
現場で実践する主な活動
計画だけでは、安全は実現しません。例えば「指差し呼称」は基本動作ながら、意識を高め、確認ミスを防ぐ重要な行動です。また、KYT(危険予知訓練)は特にKYT4ラウンド法を使うことで、作業前に潜む危険を全員で洗い出し、予防意識を高められます。
「ヒヤリハット活動」は小さな異常や失敗を共有する文化が、大きな災害の防止につながります。報告しやすい雰囲気づくりが重要です。さらに、「安全パトロール」による定期的なチェックと、作業者との対話を通じた改善提案の吸い上げも欠かせません。作業前の短時間ミーティング「TBM-KY(ツールボックスミーティング)」も、手軽で効果的な習慣として取り入れたい取り組みです。
これらの活動はいずれも、現場の安全レベルを向上させるために非常に重要です。
中でも、作業前に危険を洗い出す「KYT(危険予知訓練)」は多くの現場で導入されていますが、マンネリ化し、「形骸化」しやすいという課題も抱えています。
この形骸化したKYTから脱却し、作業員の危険感受性を本当に高めるための新しい手法として、近年「動画KYT」が注目されています。形骸化を防ぎ、KYTを再び「生きた活動」にするための動画KYTとは何か、その具体的な進め方について以下の資料で詳しく解説しています。
>>労災ゼロ!形骸化したKYTから脱却する動画KYTとはを見てみる
▼関連記事▼
・危険予知訓練(KYT)の効果的な方法は?例題や解答、4ラウンド法の進め方を解説
・工場のヒヤリハット事例21件を解説!事故対策につなげる方法もご紹介
【活動事例】ゼロ災害の実現に向けたコスモ石油の挑戦
コスモ石油 堺製油所では、「安全第一」を企業の最優先事項と位置づけています。石油プラントという高リスク環境下において、ガソリンや灯油といった危険物を扱うため、一瞬の油断が大事故に直結する可能性があるからです。
しかし、近年の人材構成の変化によって教育体制に課題が生じていました。新卒や中途採用者の増加により、現場ではOJTが中心になっていたものの、紙ベースの手順書では複雑な作業や専門用語の理解が難しく、トレーナーの負担が増大していました。
動きのある工程や作業中の危険ポイントは、テキストでは伝わりづらく、知識の習得に時間がかかるうえ、ミスのリスクも高まっていたのです。
こうした状況を打破すべく、同社は動画マニュアル(tebiki現場教育)を導入。注目されたのは、tebikiが持つ簡単な動画編集機能と、現場スタッフでも扱える直感的な操作性です。なかでも労働災害の再現動画を用いた教育が高く評価されています。
月に一度、協力会社と合同で行う「ゼロ災実行リーダー会議」では、実際に発生した災害の状況を動画で再現し、その原因や再発防止策を視覚的に伝える取り組みを実施。結果として、現場スタッフが「自分の作業に置き換えて」危険を認識できるようになり、安全意識の向上につながっています。
また、動画によって若手社員でもベテラン並みの知識を早期に習得でき、従来必要だった紙マニュアルの印刷や持ち込みも不要となりました。教育担当者の業務負担が大幅に軽減されたことも、導入効果として見逃せません。経営陣からも「動画教育は事故リスクの低減と教育コストの削減に不可欠」と高く評価されており、今後はさらに多部署・多工程へと活用を広げていく方針です。
コスモ石油の詳細な事例は、以下のインタビュー記事で詳しくご覧いただけます。
インタビュー記事:コスモ石油 堺製油所が実現する “安全第一”の動画教育改革
【原因と対策】ゼロ災害活動が「形骸化」する3つの壁と解決策
ゼロ災害活動が「形骸化」する4つの壁と解決策として以下の順に解説します。
- 壁① 拠点やチームごとにルールが違い、安全レベルにバラつきがある
- 壁② マニュアルや手順書が「読まれない」「守られない」
- 壁③ 多様な人材への教育が追いつかず、安全意識に差が生まれる
壁① 拠点やチームごとにルールが違い、安全レベルにバラつきがある
安全ルールのばらつきが現場ごとにあり、結果的に均一な安全レベルが実現されない、という課題は多くの現場で見られています。これは、「安全作業を標準化するための仕組み作り(教育体制の整備)」が1つの解決策になります。
例えば株式会社ロジパルエクスプレスの物流現場では以前「あっちの工場ではOKだが、うちではNG。基準や安全ルールがバラバラで混乱する」といった声が現場から上がっており、さらに「ベテランのノウハウが共有されず、その人が辞めたら誰も分からなくなってしまった」という課題もありました。
混乱の原因は、拠点ごとに独自に作られたマニュアルとルールによって、全社としての基準が統一されていないことにありました。業務ノウハウが紙や口頭ベースで管理されていたため、属人化が進み、貴重な知見が形式知として蓄積されないまま失われていくリスクを抱えることに。
そこで同社は、動画マニュアル(tebiki現場教育)を導入し、全拠点で統一されたマニュアルの整備に乗り出しました。映像を活用することで、例えば「台車で運ぶ荷物は胸の高さまで」といった曖昧な基準も、実際の作業風景を見せながら明確に伝えることが可能になり、従業員の認識にズレが生じにくくなりました。
結果、マニュアルの活用が現場で定着し、教育の平準化と安全品質意識の向上を実現。パートナー社員や派遣社員を含む約300名の従業員が同一の基準で業務にあたれる体制が整い、属人化のリスクも大きく軽減されました。
以下のリンクから同社のインタビュー事例をご覧いただき、動画マニュアルによる安全性の向上を検討してみてはいかがでしょうか。
インタビュー記事:動画で全拠点の安全品質意識の向上と業務ノウハウの可視化を達成
壁② マニュアルや手順書が「読まれない」「守られない」
「せっかく作ったマニュアルや手順書が現場で読まれず、危険な作業手順を踏まれてしまう」「手順通りに作業してもらえず、ヒヤリハットが起きがち」という課題を抱える現場も少なくありません。
これは、「分厚いマニュアルなんて誰も読まない」「手順書通りにやっていたら仕事にならない」という現場の事情があることが多いです。
その背景には、紙のマニュアルが文字ばかりで分かりにくく、現場の実態と合っていないという問題があります。さらに、ベテラン作業者の手元の動きや目線、ちょっとした力加減といった“カンコツ”は文章では伝えきれず、結果として自己流が横行しやすくなります。
解決策としては、静的なテキストではなく、動的な映像で手順を示すことで、誰が見ても直感的に理解できる「生きたマニュアル」として機能します。
詳しくは、マニュアルや手順書が読まれるためのポイントについてまとめられた資料を参考にしてみてください。
>>カンコツが伝わる! 『現場で使われる』作業手順書のポイントを見てみる
壁③ 多様な人材への教育が追いつかず、安全意識に差が生まれる
人材の多様性も、安全意識のばらつきの原因の1つです。例えば「外国籍スタッフに安全ルールを説明しても、言語の壁があって本当に理解できているか不安」「障がいを持つ従業員に危険性を口頭や文字だけで伝えるのは限界がある」といった声はよく聞かれます。
こうした課題の背景には、短時間勤務者、外国籍スタッフ、障がいを持つ方など、働き手の多様化が進む一方で、従来型の画一的な教育手法では、安全のニュアンスが十分に伝わらないという実態があります。
言語や文化、理解の特性が異なる中で、教育内容の定着度にバラつきが生まれ、安全意識の格差が現場のリスクを高めているのです。
言い換えれば、言語による説明や伝達があまり介在しない教育手法が、安全性を高めるためのポイントと言えます。
例えば全国15拠点で物流業務を展開するASKUL LOGIST株式会社は、動画マニュアルの導入により、映像による視覚的な訴求に加え、自動翻訳字幕機能を活用し、外国籍スタッフが自国の言語で内容を学べる仕組みを整備しました。
結果として、導入時教育の時間は従来の2時間から30分に短縮され、現場での繰り返し教育も大幅に軽減。誰もが直感的に安全行動を理解できる環境が整い、個人の特性に左右されない「安全教育の平準化」を実現しています。
同社の詳しい事例は以下のインタビュー記事からご覧いただけます。
インタビュー記事:従業員数3,500名超・全国15拠点で 動画マニュアルtebikiを活用!
ご紹介したASKUL LOGIST社の例のように、言語の壁を越えて直感的に作業内容を伝えられる動画マニュアルは、外国人労働者への教育において絶大な効果を発揮します。
ASKUL LOGIST社以外にも、多くの企業が動画マニュアルを活用して外国人労働者への「伝わらない」という課題を解決しています。様々な企業の具体的な取り組みと成果をまとめた事例集を、以下の資料で詳しくご紹介します。
>>外国人労働者に「伝わらない」を解決した動画マニュアル活用事例集を見てみる
ゼロ災害を理解して現場改善をしよう【まとめ】
ゼロ災害とは精神論ではなく、全員参加による「仕組み」で実現する安全活動です。形だけの掛け声ではなく、現場の安全文化として根付かせるには、トップのリーダーシップのもと、形骸化しない作業標準と、行動変容を促す安全教育の整備が不可欠です。
「やらされる」活動ではなく、従業員一人ひとりが危険を自分ごととして捉える現場に変えていくことこそが、ゼロ災害を実現できます。その1つの手段として、本記事では動画マニュアルを推奨しました。
危険作業やヒヤリハットを実際の映像で可視化し、危険認識を高めることで、安全性の向上につながります。動画マニュアル導入を検討している方は、以下の画像をクリックして、本記事で紹介した動画マニュアル「tebiki現場教育」のサービス資料をご覧ください。