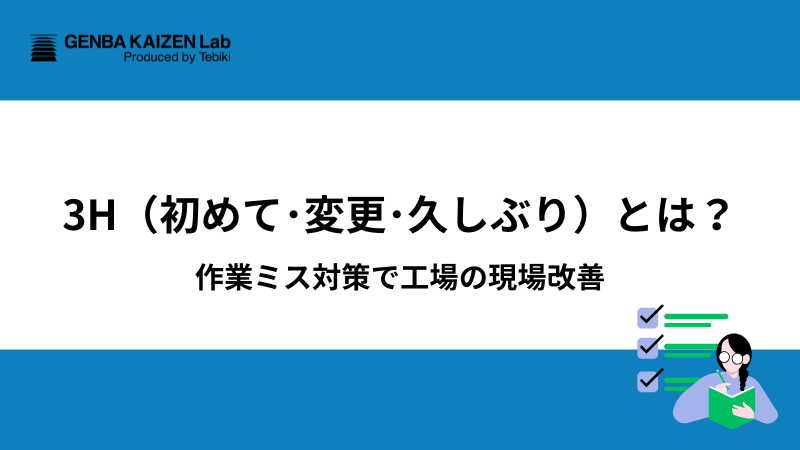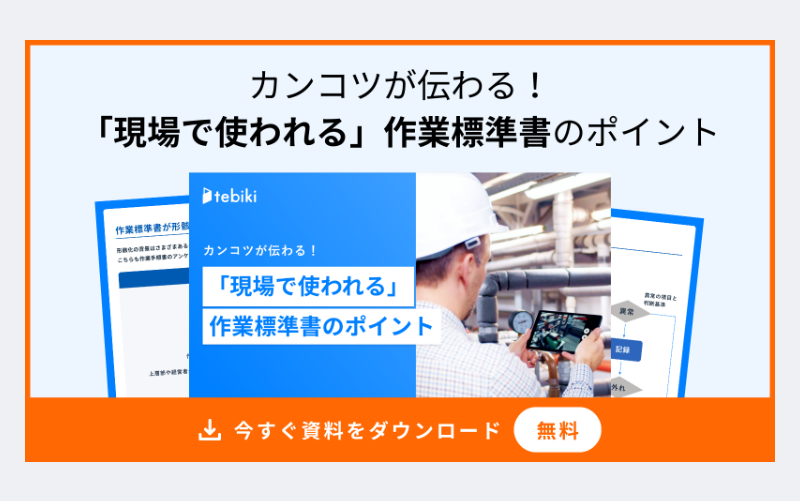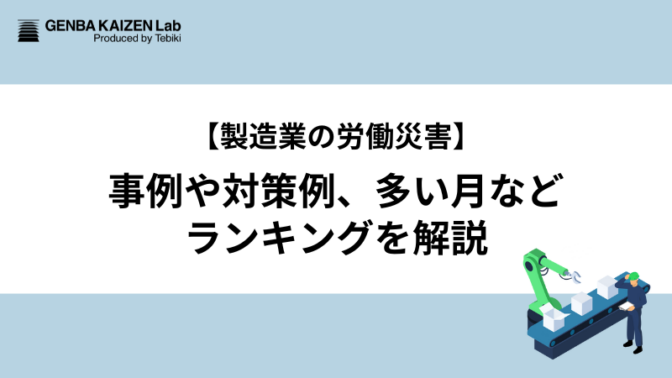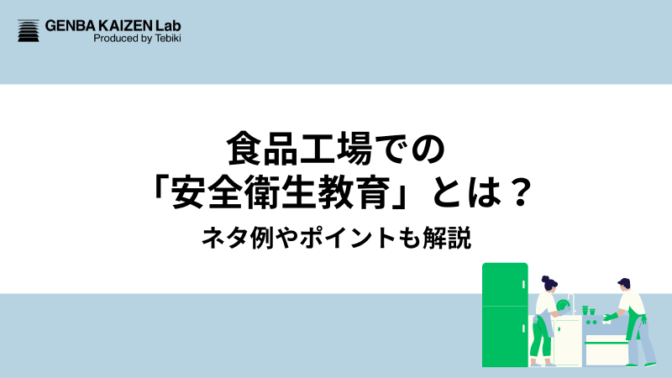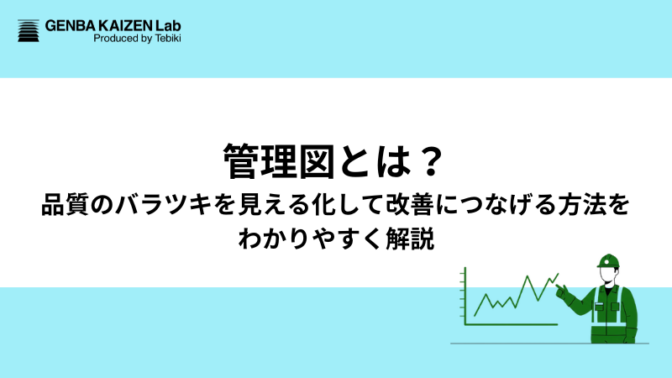かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を展開する現場改善ラボ編集部です。
「3H」とは「初めて・変更・久しぶり」を意味する言葉で、ミスを未然に防ぎ、業務の品質を向上させるための基本的な管理手法です。
本記事では、3H(初めて・変更・久しぶり)の基本的な概念や重要性、職場で実践するための具体的な方法をご紹介します。さらに、3Hの活用をサポートするツールや活用例もお伝えしますので、是非ご覧ください。
ちなみに3H派生でよくある問題が「ヒューマンエラー」ですが、ヒューマンエラーは、単なる注意喚起や口頭指導では改善されません。根本原因を解消するための「仕組み作り」が必要ですが、その仕組み作りは資料「製造業におけるヒューマンエラーの未然防止と具体的な対策方法」で解説しているので、あわせて参考にしてみてください。
>>「製造業におけるヒューマンエラーの未然防止と具体的な対策方法」を見てみる
目次
初めて・変更・久しぶり(3H)の管理とは?
製造現場でよく耳にする「初めて・変更・久しぶり」という言葉は、まとめて「3H」と呼ばれます。3Hは業務における変化点を管理し、ミスやトラブルを未然に防ぐための重要な考え方です。
ここでは、3Hの基本的な概念や重要性、管理方法について詳しく解説します。
初めて・変更・久しぶり(3H)とは
3Hはそれぞれ表のような状況を指します。
| 初めて | 新製品や新しい作業手順が導入される際に該当します。 この場合、作業手順書を新規に作成し、作業者に周知徹底することが求められます。 |
| 変更 | 製品や作業手順に変更が生じた場合がこれに該当します。既存の手順書を改訂し、変更点を明確にしたうえで関係者に共有することが大切です。 |
| 久しぶり | 長期間作業していなかった製品や手順に再び取り組む際を指します。 この場合、手順書の見直しや事前の作業シミュレーションが必要です。 |
これら3つの状況では、いずれもミスやトラブルが発生しやすいため、適切な管理が欠かせません。
3Hがミスを招きやすい理由
3Hに該当する状況では、以下のような理由からミスが発生しやすくなります。
| 初めて | 経験がない作業では手順や要点が不明確なため、見落としや誤解が起こりやすくなります。 |
| 変更 | 変更点の情報が十分に共有されない、あるいは作業者が誤解してしまうことで、ミスが生じるリスクがあります。 |
| 久しぶり | 長期間行っていない作業では、以前の手順を忘れていたり、感覚が鈍ったりすることが原因となりミスが発生します。 |
3Hは、それぞれが「未知」「変化」「忘却」というミスを引き起こしやすい要因を含んでいるため、注意深く管理する必要があります。これらは単なる個人の不注意ではなく、作業の標準化が不十分で、業務が個人のスキルや記憶に依存している「属人化」の状態であるために発生する構造的な問題です。
つまり、3Hに起因するヒューマンエラーは、個人の意識向上だけで防ぐことには限界があります。「人間はミスをする生き物である」という前提に立ち、ミスが起きにくい仕組みを構築することが、本質的な再発防止策となります。
もしヒューマンエラーの対策について悩んでいる場合は、資料「製造業におけるヒューマンエラーの未然防止と具体的な対策方法(pdf)」もあわせて参考にしてみてください。「人間はミスをする」という前提のうえでどう対策すべきか、いくつかの結論を述べています。
製造業で3H管理が重要とされる背景
製造業において、3H管理の不徹底が招くトラブルは、単なる生産性の低下に留まりません。具体的には、以下のような深刻な経営リスクに直結します。
労災・ヒヤリハット発生による労働環境の劣悪化
製造業の現場や作業にはあらゆる危険が潜んでいます。3H管理ができていなければ、例えば久しぶりに担当した作業で知らず知らずに危険な作業手順を踏んでしまい、労災の発生につながってしまいます。
3H管理を徹底している現場では必ず、3Hに該当する作業者には作業前のオリエンテーションや安全教育を実施する「仕組み」が作られているので、安全性を強化したい現場では必ず3H管理が求められます。
ヒヤリハットで済んでいるうちに、本質的な安全対策を施しましょう。 形骸化した安全教育から脱却し、従業員の安全意識を高める具体的な手法についてまとめられた資料「動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例(pdf)」も参考にしてみてください。
安全な現場作りができている企業では、「視覚的に理解しやすいマニュアル」を整備していることが多いです。動画マニュアルによる安全性や導入事例について知りたい方は、以下をクリックして資料をダウンロードしてみてください。
品質コストの増大と顧客信用の失墜
3Hに起因するヒューマンエラーは、製品の品質不良に直結します。不良品の発生は、材料費、再加工費、廃棄コストを増大させるだけでなく、最悪の場合、市場への流出によるリコールや顧客からのクレームに繋がり、取引先との関係値にも影響が出るリスクがあるのです。
ちなみに、品質不良の大きな要因には「手順不遵守」が含まれていることが往々にしてあります。 3H管理の不徹底が招く品質トラブルの根本原因と、その対策を徹底解説した資料「手順不遵守に起因する品質不良対策の考え方と対策(pdf)」も参考にすると、正しい作業手順が守られるための品質向上対策について理解を深められます。
技術伝承の停滞と組織競争力の低下
3H管理が形骸化し、作業が個人のカン・コツに依存した現場では、若手への技術伝承が円滑に進みません。結果として、ベテランの退職と共に現場の技術力が失われ、組織全体の競争力低下という長期的な問題を引き起こします。
技術伝承がいつもOJT頼りになり、なかなか本質的な技術伝承ができていない現場担当者向けに、「技術伝承を成功させるポイント(pdf)」についてまとめた資料があるので、あわせて参考にしてみてください。
サプライチェーン全体への甚大な影響
自社の生産ラインの停止は、後工程である顧客の生産計画に深刻な影響を及ぼす可能性があります。「変更」点の周知漏れで納入した部品に不具合があり、顧客の生産ラインを長時間停止させてしまった結果、多額の損害賠償を請求されるケースも少なくありません。
3H管理は、自社だけでなくサプライチェーン全体に対する責任でもあるのです。
3H管理を成功させるための原則と対策
ここまで3H(初めて・変更・久しぶり)がなぜ危険で、その管理が製造業にとっていかに重要かをお伝えしました。しかし、「重要性はわかったが、具体的に何から手をつければいいのか?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
そこでここからは、理論だけでなく、明日から現場で使える実践的なアプローチを「①原則 → ②具体的な対策 → ③目的別の改善アイデア」という流れで、網羅的に解説します。
3H管理の土台となる2大原則
まずは、3H管理をするうえでの土台となる2つの原則について解説します。
原則①:3Hは「4M」と組み合わせて変化点を管理する
品質管理の基本である「4M」(Man:人、Machine:機械、Material:材料、Method:方法)は、3H管理においても極めて有効な考え方です。なぜなら、3Hが発生するということは、必ずこの4Mのいずれかに「変化」が起きているからです。
- 初めての作業 → Man(人)のスキルが変化点
- 作業手順の変更 → Method(方法)が変化点
- 久しぶりに機械を稼働 → Machine(機械)の状態が変化点
- 新しい材料の使用 → Material(材料)が変化点
このように、3Hに直面したら「今回は4Mの何が変化したのか?」と自問する癖をつけることが重要です。変化点を具体的に特定することで、リスクの洗い出しと対策の精度が格段に上がります。
原則②:「変化点管理」でリスクを漏れなく洗い出す
4Mの視点で変化点を特定したら、次に行うのが「変化点管理」です。これは、「変更内容を事前に特定し、リスクを評価し、対策を講じてから実行する」という一連の管理プロセスを指します。
具体的には、変化点管理シートやチェックリストを用いて、以下の項目を明確にしていきます。
- 変化点は何か(例:部品Aの材質変更)
- 影響範囲はどこか(例:組立工程、検査基準)
- どのようなリスクがあるか(例:強度不足、既存の治具が使えない)
- どのような対策を講じるか(例:事前テストの実施、新しい治具の準備、作業手順書の改訂)
このプロセスを徹底することで、見込みや勘に頼った管理から脱却し、潜在的なトラブルを体系的に防止することが可能になります。
変化点管理の実践については、トヨタのやり方を参考に解説されているセミナー動画「トヨタ流品質管理に学ぶ!はじめての変化点管理」を視聴すると、より理解が深まると思います。あわせて参考にしてみてください。
>>>セミナー動画:トヨタ流品質管理に学ぶ!はじめての変化点管理
3Hによるトラブルを未然に防ぐ具体的な対策
原則を理解した上で、現場で実行すべき具体的な対策を3つご紹介します。これらは3H管理を成功させるための「車の両輪」とも言える重要なアクションです。
対策①:作業の「見える化」で手順と工程の課題を明確にする
「見えないものは管理できない」というのは、現場管理の鉄則です。作業手順や進捗、問題点などが特定の個人の頭の中にしかない「属人化」した状態では、ミスやトラブルの温床となります。
写真や動画といったツールを通じて、誰もが「正しい・安全な作業手順が一目でわかる」状態を作りましょう。作業工程が「見える化」されると、各工程の進捗や問題点が一目でわかり、3Hに潜むリスクの早期発見や、改善のヒントに繋がります。
例えば製造業の児玉化学工業株式会社は、属人化しがちな複雑な作業手順を「動画マニュアル化」し、一目で作業手順が分かるよう教育体制を整備しています。実際の動画を下に掲載します。
▼一目で分かる動画マニュアルの例▼
※「tebiki」で10分で作成
動画で手順をおさめれば「誰が見ても同じ解釈」になるので、円滑なコミュニケーションを促せます。ちなみに本動画は、製造業の現場教育に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」で作成されています。tebikiのサービス詳細や導入事例についてはサービス資料をご覧ください(下のリンクをクリック)。
>>>かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育サービス資料」を見てみる
対策②:「形骸化しない」マニュアルを整備し、状況に応じて活用する
マニュアルは、品質の標準化、安全確保、そして技術伝承の要です。しかし、ただ作るだけでは意味がありません。マニュアルがあるにもかかわらず、現場で活用されず放置されているケースは少なくありません。
現場で本当に「使われる」マニュアルを整備し、状況に応じて活用することが重要です。
「初めて」の作業では、マニュアルを渡すだけでなく、必ずOJTとセットで活用しましょう。実際にやって見せ、やらせてみることで、手順の理解度が飛躍的に向上します。
「久しぶり」の作業では、 作業前に必ずマニュアルを再確認することをルール化しましょう。KY(危険予知)活動と連動させ、「この作業の注意点は何だったか」を思い出すきっかけにするのも有効です。
文字だけでは伝わりにくいカン・コツは、写真や動画を活用することで、より効果的に伝えることができます。
カン・コツまで正しく伝わる、現場で本当に「使われる」手順書の作成ポイントは、資料「『現場で使われる』作業手順書のポイント」にまとめています。作業手順書の整備にお役立てください。
対策③:変更点を確実に周知し、教育を徹底する
「周知した=伝わった」ではない、という認識を強く持つことが重要です。「変更」があった際に、朝礼で口頭連絡したり、掲示板に貼り出したりするだけでは、情報は浸透しません。
したがって、周知と教育はセットで行いましょう。新しい手順書を配布するだけでなく、なぜ変更になったのかという背景から説明し、理解度を確認する小テストを行うなど、双方向のコミュニケーションを心がけます。
特に重要な変更の場合は、変更後の作業に管理者が立ち会い、正しく手順が守られているかを確認することも有効な手段です。
3H管理を行う際の注意点とよくある課題
ここでは、3H管理を行ううえで注意しておきたいポイントと課題について解説します。
初めて3H管理を導入する際の落とし穴
3H管理を初めて導入する現場では、従業員からの反発や新しい取り組みへの不慣れによる手間の増加がよく見られます。新しい管理手法を導入すると、従業員が「慣れたやり方を変えたくない」と感じ、反発することがあるからです。このような課題を適切に解決することで、スムーズな定着が可能になります。
導入初期には、管理手法の目的やメリットを従業員に丁寧に説明することが大切です。さらに、小さな成功体験を積み重ねることで、従業員のモチベーションを高めることができます。例えば、簡単な業務で3H管理を試し、その成果を共有することで、現場全体に良い影響を与えます。
3H管理の運用にありがちな落とし穴
3H管理が日常的な業務として定着する過程で、管理手法が形だけのものになりがちです。これを防ぐためには、継続的な改善活動が欠かせません。管理手法を導入しても、定期的な見直しやフィードバックがない場合、従業員が「形式的にこなすだけ」の状態に陥ります。その結果、実際の現場改善には繋がらなくなってしまいます。
月次レビューや定期的な現場ミーティングを通じて、3H管理の成果を確認し、課題があればその場で改善策を検討する仕組みを整えましょう。例えば、「初めて」の作業で発生した課題や、「変更」後に気づいた改善点を共有し、次回に活かす取り組みを継続することが効果的です。
現場スタッフへの教育と浸透方法
3H管理を現場に定着させるためには、適切な教育とツールの選定が必要です。教育が不十分な状態で3H管理を導入すると、スタッフが手順を理解できず、現場での混乱を招くためです。
現場に適した教育プログラムを作成し、段階的に進めることがポイントです。例えば、動画マニュアルやEラーニングを活用することで、従業員が自分のペースで学べる環境を提供できます。また、OJTを取り入れることで、現場での実践力を高めることも効果的です。
変更後の改善提案を継続する方法
3H管理の効果を最大化するためには、変更後の状況を継続的にモニタリングし、改善提案を現場で実行する仕組みを構築することが重要です。変更が行われた後、フィードバックを適切に収集しない場合、問題が見過ごされることがあるためです。
定期的なモニタリングを行い、成果や課題を可視化するツールを活用しましょう。例えば、改善提案の実施状況をスプレッドシートや専用の管理システムで記録し、進捗を全員で共有することで、改善活動の透明性を高められます。また、成功事例を現場全体で共有し、達成感を共有することも重要です。
「初めて・変更・久しぶり」対策を徹底し現場改善に努めている企業事例
ソニテック株式会社:初めての作業でもスムーズに取り掛かれる「QRコード」を整備
物流事業を展開するソニテック株式会社では、新人教育が大きな経営課題でした。特に、主要業務であるピッキング作業は荷主や配送便ごとに手順が細かく異なり、新人にとっては常に「初めて」の作業の連続。覚える負担が大きく、指示の誤解によるミスも発生していました。
従来は3ヶ月間のマンツーマン指導で対応していましたが、教育工数の膨大さが指導者の日常業務を圧迫していました。
この課題に対し、同社はマンツーマン指導を完全に撤廃し、動画マニュアル「tebiki現場教育」による教育へ移行。特に効果を上げたのが、便ごとに異なる作業手順を個別の動画マニュアルとして作成し、QRコードで管理する仕組みです。
これにより、作業に不慣れな方や、その日担当する便での作業が**「初めて」**という方でも、QRコードをスキャンするだけで迷わず正しい作業手順を動画で確認でき、安心して業務に取り掛かれる環境を構築しました。
結果として、かつて3ヶ月を要していた新人教育の時間は実質ゼロにまで削減され、業務の標準化も実現。3H、特に「初めて」の作業に対する不安やミスをテクノロジーで解消し、新人のスムーズな現場立ち上がりを成功させた好事例です。
※3H対策に適した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」のサービス資料はこちら
MSSステンレスセンター株式会社:形骸化したマニュアルを刷新し、3Hの作業を標準化
ステンレス鋼の加工を行うMSSステンレスセンター株式会社では、形骸化した作業手順書が3H(初めて・変更・久しぶり)に起因する様々な課題を生んでいました。
▼変更
作業手順に変更があっても、紙マニュアルの改訂に手間がかかるため、古い情報が放置されがちでした。
▼初めて
新人が作業を学ぶ際、指導者によって教え方が異なり、誰の指示が正しいのか分からず混乱していました。
▼久しぶり
一度見たきり手順書は確認されなくなり、記憶の曖昧さによるミスのリスクがありました。
この3Hにまつわる課題を解決するため、同社は現場主導で簡単に作成・編集できる動画マニュアルを導入。これにより、「変更」があっても、動画を差し替えるだけで常にマニュアルを最新の状態に保てるようになりました。
「初めて」作業を学ぶ新人も、標準化された動画を見ることで、指導者による内容の差異に悩むことなく、いつでも正しい手順を学べます。さらに、タブレットで手軽に確認できるため、「久しぶり」の作業でも手順を再確認することが習慣化しました。
動画マニュアルの活用によって、3Hの各場面で発生しがちな「情報の陳腐化」「教育のバラつき」「記憶の忘却」という課題をまとめて解決し、現場の安全性と品質向上に繋げている好事例です。
※3H対策に適した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」のサービス資料はこちら
3H対策は「すぐに正しい作業に取り掛かれる」マニュアル整備が重要
3H管理では、トラブルにつながりそうな要素を発見し、そのリスクを防ぐためのマニュアルや手順書に反映させることが大切です。
この際におすすめしたいのが、「動画マニュアル」です。動画マニュアルを活用することで、実際の状況が視覚的に理解しやすくなります。
以下の動画は、物流業の株式会社近鉄コスモスが作成した動画マニュアルですが、危険な作業手順(NG作業手順)を動画におさめることで、初めて・久しぶりに作業する方でも安全作業にキャッチアップできるようになっています。
▼3Hに対応した動画マニュアルの例▼
※tebikiで作成
このように、正しい(もしくは危険な)作業手順を動画を見ることで「どのようなポイントがミスにつながりやすいのか」を瞬時に把握できるため、内容が印象に残りやすく、効果的な学習が可能となります。
※3H対策に適した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」のサービス資料はこちら
せっかく管理している3Hを無駄にせず、適切な対策に結びつけることが、トラブルを未然に防ぐことに有効です。
さらに、外国人労働者が多い職場でも、動画は言語の壁を越える手段として有効です。言葉の理解が難しい場合でも、動画によって変更された場所を視覚的に確認することで「トラブルにつながりやすいポイント」を直感的に理解できます。これは3H管理を効果的に進めるための大きな助けとなります。
特に注目すべきは、100以上の言語に自動翻訳できる機能です。安全対策に関する重要な情報を母国語で伝えることができるため、理解度の向上が期待できます。
さらに、tebiki現場教育には以下の魅力的な機能も備わっています。
| テスト機能 | オリジナルテストを作成して、ユーザーの理解度を確認できる |
| レポート機能 | 従業員1人ひとりのアクセス履歴と習熟度進捗が可視化される |
| タスク機能 | 完了予定日を指定し、タスクを課すことができる |
| コース機能 | 作成したマニュアルをまとめて教科書を作成できる |
| スキル機能 | 従業員の教育状況とスキルを紐づけて管理できる |
tebikiは他にも多数の魅力的な機能を備えています。詳しく知りたい方は、ぜひ以下の資料をダウンロードしてご確認ください。
>>動画マニュアルがかんたんに作れる「tebiki」の概要を見る
まとめ|初めて・変更・久しぶりの作業を成功に導く改善提案の進め方
「初めて」「変更」「久しぶり」の状況は、製造現場においてトラブルが発生しやすい要因です。しかし、これらの状況を適切に管理することで、ミスのリスクを大幅に軽減し、効率的な現場運営を実現できます。
さらに、動画マニュアルやデジタルツールを活用して、作業者がより簡単に情報を理解できる環境を整備すれば、より効果的に管理可能です。3H管理を習慣化し、継続的な改善活動を行うことで、安全性・効率性の高い製造現場を実現しましょう。