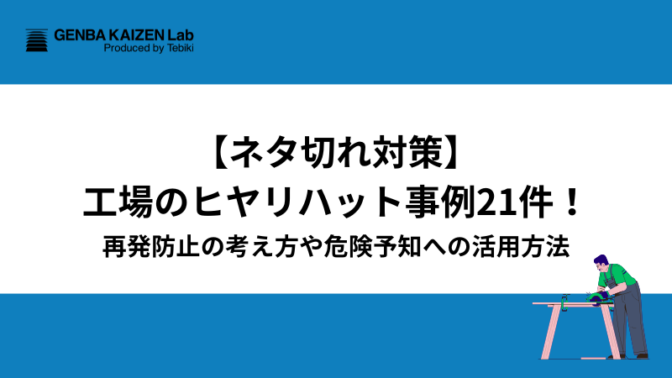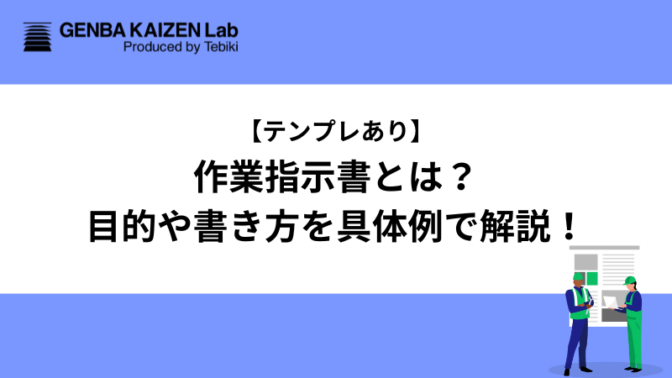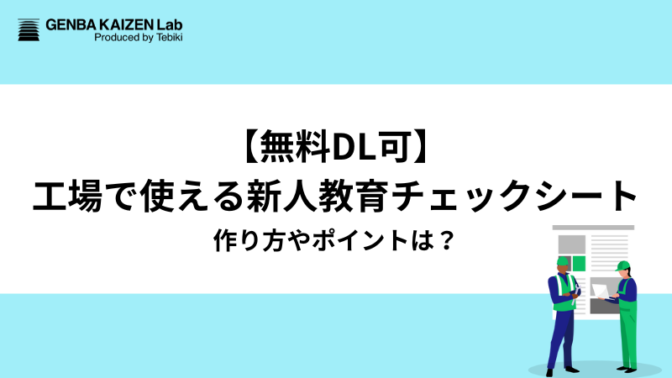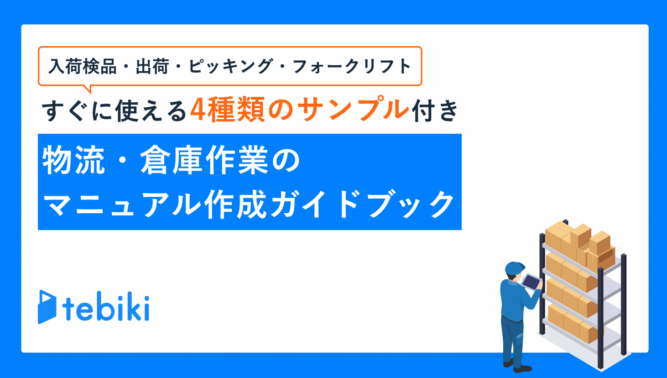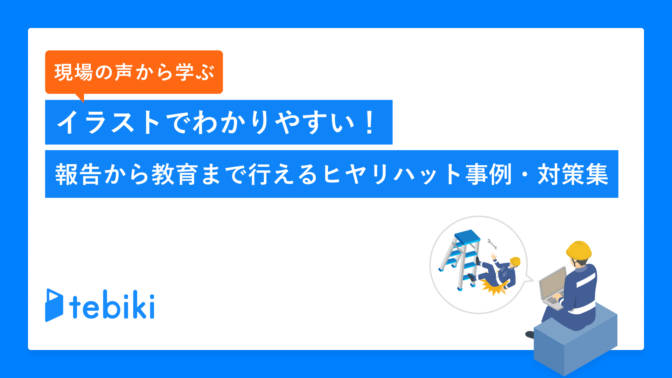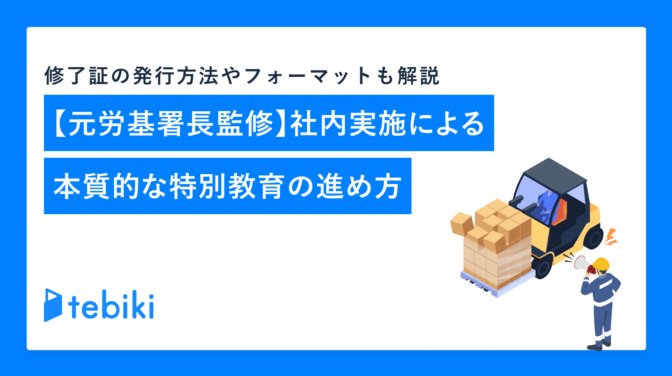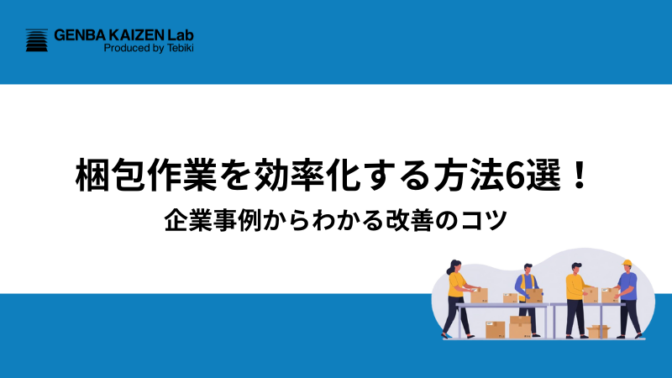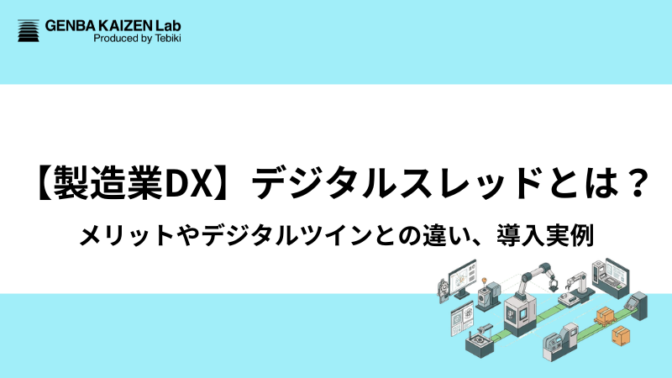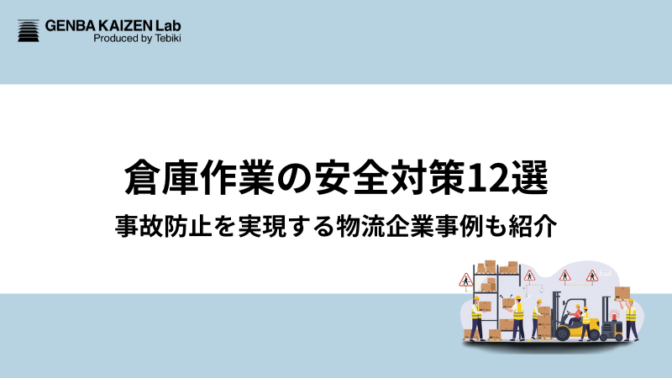品質や生産性の改善活動を行っていても「原因分析が甘いのではないか」「いい対策が思い浮かばない」といったお悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。
的確な原因分析や有効な対策を講じるには、「5M」を活用した原因分析が有効です。5Mは、複雑な事象を「Man(人)」「Machine(機械)」「Material(材料)」「Method(方法)」「Measurement(測定)」の5つの要素に分解し、原因を体系的に特定するフレームワークです。
この記事では「5M」を活用した原因分析のメリットや場面ごとの活用例、4Mや6M、5M+1Eとの違いについて紹介します。製造現場の品質や生産性の改善を目指す方は、ぜひご一読ください。
5Mをはじめとした様々な現場を適切に管理し、トラブルの未然防止に役立てるには「変化点管理」が欠かせません。変化点管理のコツや手法については以下の動画で詳しく解説しているため、本記事と併せてご覧ください。
目次
5Mとは、事象を5つの要素に分解して分析するフレームワーク
トラブルや不具合が生じた際は、さまざまな場面で発生した課題や事象の原因分析、改善を行います。しかし事象が複雑にからみあう場合も多く、原因がはっきりと分からないことも多いでしょう。
5M分析は、このような複雑な事象を「Man(人)」「Machine(機械)」「Material(材料)」「Method(方法)」「Measurement(測定)」の5つの要素に分解し、どこに原因があったのかを体系的に特定するフレームワークです。5つの要素のアルファベットの頭文字をとり、「5M」と呼んでいます。
問題が発生したときに、どの要素に原因があるのかを明確にすることで、的確な改善活動を実現できます。この分析手法により、勘や経験ではなく論理的なアプローチで問題の本質に迫ることが可能です。
5Mで分析するメリット
5M分析の最大の利点は、原因を論理的かつ明確に特定できることです。
真の原因が特定できれば、根本的な解決につながる有効な改善策を導き出せます。場当たり的な処置や勘・経験に頼った原因分析ではなくなりますので、データに基づいた客観的な改善策の立案が可能です。
課題に対し根本的な解決につながる有効な改善策が実行できれば、以下のようなメリットが期待できるでしょう。
- 品質不具合を改善し、安定した製品供給を実現できる
- 適切な管理方法を実践し、製品の品質を向上できる
- ムダな作業やコストを削減する方法を見つける
5M分析の具体例と改善策の立て方については、後述する『【ケース別】5Mの活用例』で詳しくご紹介します。
5Mを使う場面
5M分析は、製造業のさまざまな改善活動で活用されます。具体例として、下記が挙げられます。
- 顧客クレームなど品質不具合の原因分析
- 生産性の改善活動
- 工程変更時のリスク評価
- 新製品の開発
- 不安全箇所の洗い出し
何か解決したい問題や、改善したい課題がある多くの場面での活用が可能です。
5Mは何を指す?それぞれの要素
5Mの各要素についてさらに詳細にご紹介します。各要素を独立して考え、かつ相互の関連性を考慮することでより真因にせまった原因分析ができます。
Man(人)
「Man」は製造プロセスにおける人的要因を分析する要素です。具体的な要素として、従業員のスキル、知識、モチベーション、疲労度、作業習熟度などが対象となります。
新人や経験の浅い作業員、熟練工の技能継承、作業者の心身の状態、教育訓練の質、コミュニケーション能力などが、製品の品質や生産性に大きな影響を与えます。これらの要素を分析することで、製造プロセスにおける人的なミスや効率低下の要因を特定し、改善策を講じることが可能になります。
例えば、スキルや知識の不足が作業エラーを引き起こしている場合は、適切なトレーニングプログラムを導入することが考えられます。また、疲労度や作業習熟度の分析により、労働時間の調整や適切な作業配置を検討が期待できます。
Machine(設備)
「Machine」は生産設備や機械に関する要素です。設備の老朽化、メンテナンス状況、精度、稼働率、故障履歴、初期設定、保全方法などが対象となります。
機械の性能や状態は、製品の品質と生産効率に直接的な影響を与えます。定期的なメンテナンス、設備更新、予防保全、精度管理、適切な操作方法の確立などの対策を講じましょう。
Material(材料)
「Material」は原材料や部品に関する要素です。材料の品質、仕様、納入状況、保管条件、在庫管理、サプライヤーの信頼性などが対象です。材料の変動は、製品の一貫性や品質に直接的な影響を及ぼします。
原材料の受け入れ検査、仕入先の選定と評価、材料の保管方法、トレーサビリティの確保、材料変更時の影響評価など、材料に関する綿密な管理を行いましょう。
Method(方法)
「Method」は作業手順や生産方法に関する要素です。作業標準、工程設計、作業手順書、生産プロセス、作業効率、品質管理方法などが対象となります。
効率的で再現性の高い作業方法の確立は、生産性と品質向上において非常に重要です。作業標準書の整備、作業手順の可視化、作業改善活動、最適な作業方法の探求など、継続的な改善活動を行いましょう。勘や経験に頼らない、データに基づいた科学的なアプローチが求められます。
Measurement(測定)
「Measurement」は測定と検査に関する要素です。測定機器の精度、検査方法、測定のばらつき、モニタリングなどが対象となります。正確な測定と厳格な品質管理は、製品の信頼性を確保する上で不可欠です。
測定機器の校正、検査員のスキル、測定方法の標準化、計測システム分析(MSA)、データ管理、品質工学の活用など、原因に応じた改善アプローチを行いましょう。
4M、6M、5M+1Eとの違い
5Mと類似の目的で使用される、以下3つのフレームワークについて解説します。
- 4M
- 6M
- 5M+1E
特に製造業では4Mが歩留まりに多大な影響を与えることが多いため、各要素を体系的に分析し、改善策を講じることが重要です。
4Mの観点からみる歩留まり改善の手法については、以下の画像をクリックしてご覧いただける無料動画で詳しく解説しています。
4M
4Mは5Mの前身となるフレームワークで、「Man」「Machine」「Material」「Method」の4つの要素で構成されます。測定(Measurement)の要素が含まれていない点が5Mとの大きな違いです。
日本国内では変化点管理のことを「4M変更」と呼ぶことも一般的です。4M変更とは、品質や生産性に影響を与える可能性がある「Man」「Machine」「Material」「Method」の4つの要素に変化が生じた際に、変化点を明確に把握し慎重な管理を行うことです。具体的には生産設備や原材料、作業方法の変更などが挙げられます。
海外や自動車・半導体業界では、4M変更のような製造中の製品の仕様変更や製品の製造中止の際には顧客に対し一定期間前に通知するルールが定められており、PCN(Product Change Notification)と呼ばれます。
6M
6Mは、5Mに「Management(マネジメント)」の要素を加えたフレームワークです。
「そもそも組織的な管理に問題があったのではないか?」という視点を分析対象に含めることで、より広範囲な視点から問題をとらえます。担当者などが変わっても、同じ問題を二度と発生させないための仕組みづくりといった改善アプローチにつながります。
5M+1E
5M+1Eは、5Mに「Environment(環境)」の要素を加えたフレームワークです。
製造プロセスに影響を与える環境要因、たとえば温度、湿度、騒音、振動、汚染などを分析対象に含め、外部環境が製造プロセスや製品品質に与える影響をより詳細に分析することが可能です。5Mよりもさらに広い視点から問題を捉え、環境管理の重要性を強調するアプローチとなります。
【ケース別】5Mの活用例
5Mの具体的な活用例をご紹介します。品質不具合や生産性の低下は、何か1つの突発的な原因によってもたらされることもありますが、複数の要因がからみあって発生する場合も多いです。
からみあった原因を分解し、1つ1つの原因に適切な対策を講じましょう。
- 品質改善の事例
- 生産性改善の事例
品質改善の事例
たとえば、スマートフォンの基板実装において、はんだ付け不良が頻発するという問題が発生したとします。
5M分析を行わない場合、管理者は単に「作業者の熟練度不足」と決めつけ、その作業者への教育のみを行う可能性があります。しかし、根本的な原因追求を怠ったため不具合は継続し、製品の信頼性は大きく低下する‥といった事態になるかもしれません。
しかし、5M分析を実施すれば他の要因が判明するため、さまざまな対策を講じることができます。考えられる要因を以下の表にまとめました。
| 潜在的原因 | 分析結果 | リスク判定 | とるべき対策 | |
|---|---|---|---|---|
| 人(Man) | 作業熟練度 | 作業者の熟練度にばらつきがあった | 〇 | 標準作業教育 |
| 設備(Machine) | はんだ付け機の温度管理 | 温度管理は一定であった | × | |
| 材料(Material) | 材料の品質 | 品質変動はなかった | × | |
| 方法(Method) | 作業方法 | 作業方法にばらつきがあった | 〇 | 作業標準書の作成 |
| 測定(Measurement) | 品質の検査方法 | 検査方法にばらつきがあった | 〇 | 検査方法の標準書の作成 |
5M分析の考察
5M分析の結果として、設備(Machine)や材料(Material)にも温度管理や材料の品質変動というはんだ付け不良が起こりうる潜在的原因がありました。潜在的原因とは、「その要素が問題の原因となる可能性があるか?」を指します。設備(Machine)の場合、はんだ付け機の温度が不安定であれば不良の原因となりえます。
しかし調査の結果、今回のはんだ付け不良のロットでは設備(Machine)と材料(Material)にトラブルは発生していないことが分かりました。このためリスク判定(原因となっているかどうかの判定)は「なし」という結果です。
一方、人(Man)、方法(Method)、測定(Measurement)には、それぞれ作業熟練度のばらつき、作業方法のばらつき、検査方法のばらつきという、はんだ付け不良の潜在的な原因となる可能性がありました。
これらを調査した結果、今回のはんだ付け不良のロットに対しそれぞればらつきがあったため「リスクあり」と判定しました。分析によりそれぞれの原因に対し、標準作業教育や作業標準書の作成、検査方法の標準書の作成といったとるべき対策が明確になります。
このように、5M分析をする前は原因を「作業者の熟練度不足」だと決めつけていましたが、他にもさまざまな原因があったことが分かりました。それぞれの原因を改善するような対策を打てば、根本的な解決となり品質不具合の再発防止が見込めるでしょう。
生産性改善の事例
次に、部品工場における生産効率改善の例をご紹介します。
生産ラインの効率が低下している状況で、単に「もっと頑張れ」「残業で対応しろ」といった抽象的な指示や、部分的な改善のみを実施したとします。しかし、結果として作業者のモチベーション低下、過重労働、非効率な生産体制が継続し、根本的な生産性向上には至りません。
こちらの事例でも、5M分析により、人(Man)、材料(Material)、方法(Method)、測定(Measurement)にそれぞれ原因があることが明らかになりました。
| 潜在的原因 | 分析結果 | リスク判定 | とるべき対策 | |
|---|---|---|---|---|
| 人(Man) | 熟練度 | 作業者の熟練度にばらつきがあった | 〇 | 標準作業教育 |
| 作業動線 | 複雑だった | 〇 | 標準作業時の作業動線を分析し、導線の改善を行う | |
| 設備(Machine) | 生産設備の稼働率 | 設備の稼働率低下はなかった | × | |
| 材料(Material) | 部品供給の遅延 | 遅延は発生していなかった | × | |
| 在庫管理の効率 | 在庫管理がアナログで非効率だった | 〇 | 在庫管理システムの改善 | |
| 方法(Method) | 作業手順の標準化不足 | 標準作業が不明確だった | 〇 | 作業標準書の作成 |
| 無駄な動作 | 無駄な動作が多かった | 〇 | 動作分析に基づく作業標準書の再構築 | |
| 測定(Measurement) | リアルタイム分析の欠如 | リアルタイムで分析ができていなかった | 〇 | リアルタイムで生産性指標を確認できるシステムの開発 |
5M分析の考察
5M分析の結果として、トラブルの真因がいくつか明らかになりました。たとえば人(Man)であれば、生産性を低下させる潜在的な原因として、熟練度のばらつきや作業動線の複雑さが挙げられます。調査の結果、両方とも生産性低下の原因となっていることが分かったためリスクあり判定とし、標準作業教育、作業動線の改善という2つの対策が考えられます。
一方、材料(Material)では部品供給の遅延や、在庫管理システムの非効率さが課題として挙げられます。調査の結果、部品の供給遅延は起こっていなかったものの、在庫管理がアナログで非常に非効率だったことが判明しました。そのため、在庫管理システムの改善が解決策として有効でしょう。
このように生産性改善の取り組みとして複数の原因を突き止め、それぞれ対策をとっていき生産性の向上が図れます。
また、5Mの1つの要素の中に複数の潜在的原因がある場合には、特性要因図(フィッシュボーンチャート)を使って先に潜在的原因を洗い出す方法もあります。特性要因図の解説や書き方については、こちらの記事を参考にしてください。
関連記事:品質改善につなげる!QC7つ道具と新QC7つ道具の使い方【覚え方や事例、テンプレートをご紹介】
Man(人)やMethod(方法)の対策には「動画マニュアル」による標準作業教育が効果的
5M分析で判明したMan(人)やMethod(方法)への対策には、作業の品質や生産性が担保された「標準作業」を製造現場の標準として落とし込めるかがカギを握ります。
一方で、標準作業をOJTや座学のような口頭ベース、文書形式のマニュアルや手順書で共有しようとすると、以下のような課題が生じやすいです。
- トレーナーに教育工数がかかり、生産活動に割く時間が減ってしまう
- トレーナーによって言っている内容が異なり、作業者の混乱を招く
- マニュアルや手順書の作成/更新が追い付かず、標準作業の共有が進まない
- 文字や写真のような二次元的な情報では、三次元的な動きを伝えにくい
結果的に、教育不足/理解不足による標準作業の不遵守を招き、品質目標の達成を難しくしてしまいます。
ここで、これらの課題を解決できるツールとして注目されているのが「動画マニュアル」です。動画マニュアルは一度作成してしまえば、トレーナーに負担をかけずに「動きやノウハウ」を視覚的に分かりやすく伝えられます。
このように、動画マニュアルは「Man(人)」や「Method(方法)」の課題解決に大きく貢献し、製造現場の品質向上と生産性改善を効果的にサポートする重要なツールとなっています。
動画マニュアルの教育効果や現場で活用するイメージについては、以下のマンガ資料で分かりやすく解説しています。
次章からは、高品質な動画マニュアルが簡単に作成できる「tebiki」について解説します。
標準作業教育は「tebikiのかんたん動画マニュアル」で効率化!
動画と聞くと『編集が難しそう…』と感じるかもしれませんが、誰でもかんたんに動画マニュアルを作成/活用できるツールが「tebiki」です。
tebikiは以下のような機能を搭載し、5M分析で判明した課題解決に向けた業務標準化/人材育成を実行することが可能です。
- 映像編集未経験者でも「かんたん」に使える編集画面
- 音声読み取りによる字幕の自動生成機能
- 字幕を100ヶ国以上の言語へ瞬時に自動翻訳
- 一部言語は字幕の読み上げ機能に対応
- テスト機能やレポート機能による理解度・学習進捗の可視化
- スキルマップなどスキル管理機能による教育計画と実行
- 半永久的に続く専属サポート
各機能の詳細やプラン、具体的な活用事例などの情報は、以下のリンクをクリックしてサービス概要資料をご覧ください。
>>かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育サービス資料」を見てみる
tebikiの動画マニュアル活用によって問題解決した事例
tebikiの動画マニュアルを活用し、Man(人)やMethod(方法)における課題解決に成功した事例をご紹介します。
他にも様々な業界の事例についてまとめた資料もございますので、併せてご覧ください。
>>>動画マニュアルによる課題解決の事例をみてみる(無料)
新日本工機株式会社
工作機械の製造販売を手掛ける新日本工機株式会社は、現場教育に動画マニュアルを導入することで作業標準化を図り、品質ばらつきの改善を実現しています。
▼インタビュー動画:新日本工機株式会社▼
もともと紙マニュアルによる指導で運用してきていましたが、読み手によって文字情報の解釈に差が生じ、作業者間で認識が異なっていたことが課題でした。結果的に品質のばらつきが生まれ、作業の後戻りが頻発。
そこで動画マニュアルを主軸に置いた教育方針や情報伝達を整備したところ、複雑な作業手順もスムーズに教育できるうえに、海外拠点への情報共有も難なくできるようになり、品質向上やコミュニケーション工数削減を実現しました。
動画マニュアル導入効果を実感した同社は、1年間で1,500本もの動画マニュアルを作成しており、効果的かつ効率的なマニュアル整備を進めています。
同社の事例について詳細を知りたい方は、以下のリンクからご覧ください。
インタビュー記事:人が育つ環境づくりとして動画マニュアルtebikiを活用。技術の蓄積と作業品質の安定を実現。
株式会社アルバック
真空技術を駆使した製品やソリューションを展開する株式会社アルバックは、動画によるマニュアルの整備を通じて、作業品質の安定化や生産性向上を実現しています。
特に、専門的な製造プロセスや技術が求められる同社のマテリアル事業部では、生産拠点によって生産性に大きな差が生じており、その差を埋めることが急務でした。その対策として、技術伝承による作業品質の安定化を課題のひとつとして設定。
そこで動画によるマニュアルを整備し、拠点間の技術やノウハウ共有の促進を図ったところ、1日あたりの生産性が67%増を実現。従来のテキストや画像のマニュアルでは十分に伝えきれなかった暗黙知やカンコツが、動画を通じて言語化・可視化されたことが大きなインパクトを生み、全体的な生産効率の向上につながりました。
同社の事例について詳細を知りたい方は、以下のリンクからご覧ください。
インタビュー記事:人員・労働時間を変更せずに、ボンディング工程の生産性を167%に改善
5M分析で特定した課題には動画マニュアルで対策を
この記事では、製造業における5M分析の重要性とその効果的な活用方法について解説しました。
5M分析で特定した課題には、それぞれの要素に応じた適切な対策を講じる必要があります。特に「Ma(人)」や「Method(方法)」の課題には、動画マニュアル「tebiki」を活用した標準作業教育が有効です。
動画を活用することで、作業手順をわかりやすく伝えられるだけでなく、従業員全体のスキルや理解度の均一化を図ることができます。これにより、人為的ミスの削減や作業の効率化が期待できます。
本記事でご紹介したtebikiの機能詳細や費用対効果については、以下の資料で詳しく解説しています。「動画マニュアルの導入効果を具体的に知りたい」「自社の課題に適した活用事例を確認したい」とお考えの方は、是非ご参考ください。
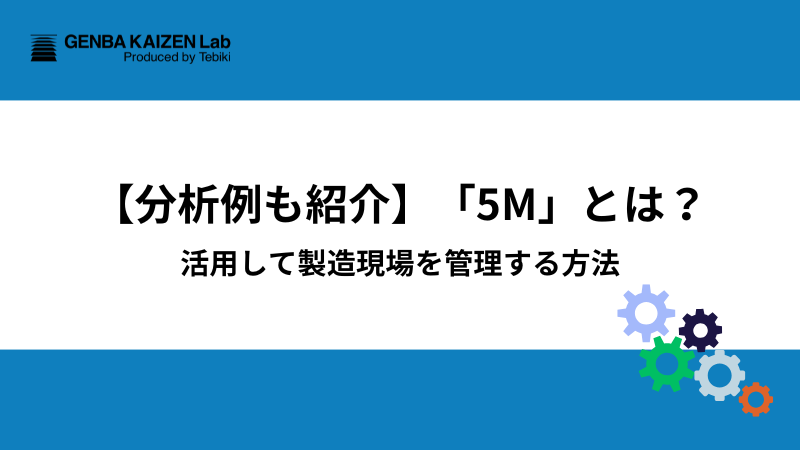




-2.png)