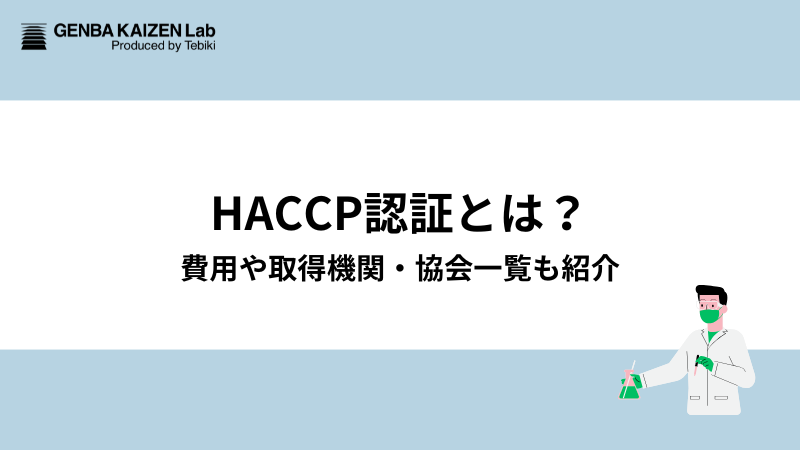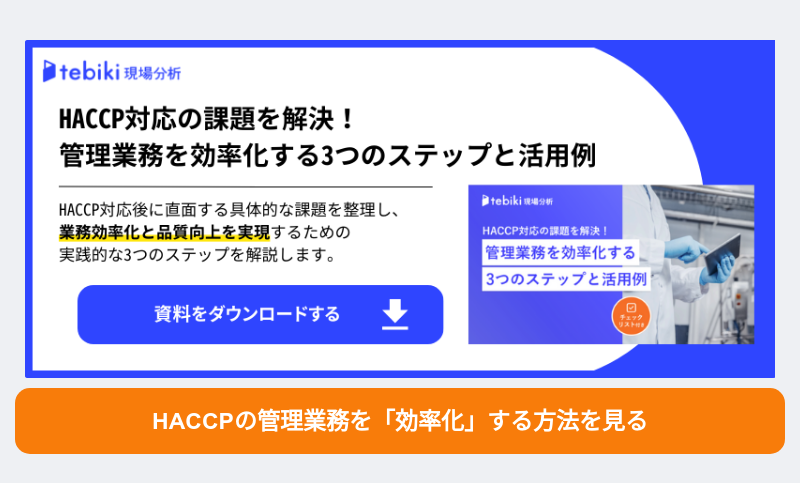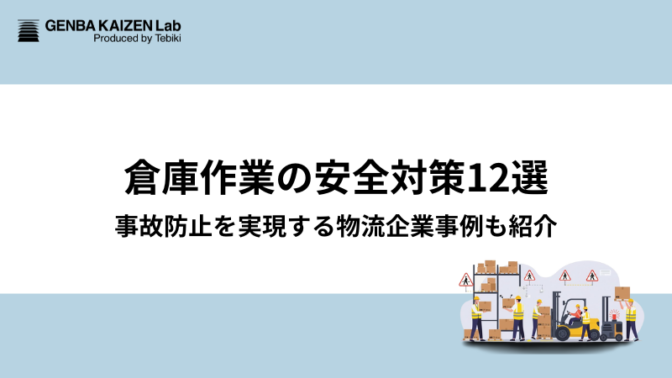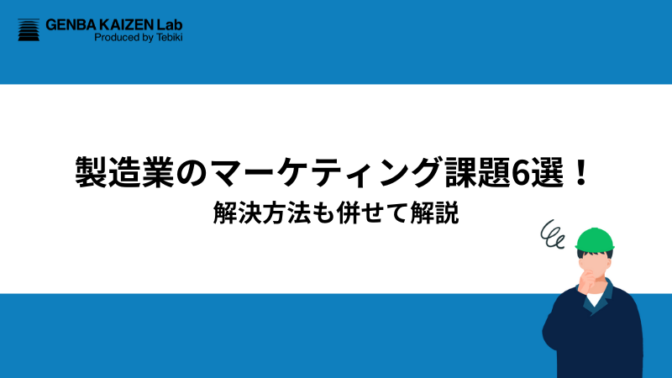かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を展開する現場改善ラボ編集部です。
HACCP認証は、安全性と品質管理を証明する仕組みとして、多くの事業者が取得を目指しています。本記事では、HACCP認証の基本情報やメリットに加え、認証機関や協会の特徴、費用、具体的な取得プロセスまで詳しく解説します。
HACCP対応は食品業界における品質管理や信頼性向上に不可欠ですが、HACCP管理業務が煩雑化し、現場での負担が増大するというケースが実態として多く見られています。PDF資料「HACCP管理業務を効率化する3ステップ」では、本来集中すべき業務を妨げずにHACCPを推進するハウツーがまとめられています。下のリンクからダウンロードしてみてください。
>>>PDF資料「HACCP対応の課題を解決!管理業務を効率化する3つのステップと活用例」を見てみる
目次
HACCP認証とは
HACCP認証とは、第三者機関により企業のHACCPシステムが審査され、HACCPの適合性を公式に認めてもらうことです。食品事業者が自社企業の品質や製造工程を対外的に証明するために取得します。
2021年6月以降、日本国内でHACCPが義務化されましたが、HACCP認証は義務ではありません。
HACCP「認証」と「導入」の違い
HACCP「認証」と「導入」は、内容が全く異なります。HACCP導入はすべての食品事業者の「義務」ですが、HACCP認証は任意です。主に目的や範囲、手続きの厳格さが異なります。
| 項目 | HACCP「認証」 | HACCP「導入」 |
|---|---|---|
| 目的 | HACCP体制を客観的に証明すること | HACCPを実施し、維持していくこと |
| 実施主体 | 第三者機関 | 企業自身 |
| 第三者の介入 | 必要 | 場合による |
| 義務 | 任意 | 義務 |
| コスト | 比較的高コスト | 比較的低コスト |
HACCP認証取得は、輸出を行う場合や大手取引先と契約を進める場合、または安全性と品質の高さをアピールしたい場合に取得します。
一方で「HACCP管理業務が煩雑化し、現場での負担が増大する」というケースが多いのも事実です。PDF資料「HACCP管理業務を効率化する3ステップ」では、本来集中すべき業務を妨げずにHACCPを推進するヒントが得られるので、気になる方は下の画像をクリックして資料ダウンロードしてみてください。
HACCP認証のメリットや効果
「HACCP認証が義務でないなら、取得しなくてもいいのでは?」とお考えの方に、HACCP認証取得のメリットや効果について解説します。
それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
取引先や消費者からの信頼獲得
HACCP認証は、食品の安全性と品質管理体制が国際基準に基づいていることを、第三者機関が公式に証明する制度です。認証取得により、取引先に対して自社の食品の優位性をアピールできます。
また、消費者にとってもHACCP認証は「安心して選べる食品」の象徴となります。特に食品の安全性を重視する市場においては、他社との差別化を図る重要なポイントとなるでしょう。
第三者機関からのチェックによる課題の明確化
HACCP認証の審査過程では、専門知識を持つ第三者機関から詳細なフィードバックを受けられます。内部では気づきにくい課題や改善点がわかり、衛生管理体制のさらなる向上につながるでしょう。
こうした客観的なチェックは、安全管理の精度を高めるだけでなく、組織全体の成長にもつながります。
衛生管理の「手法」について知りたい方は、無料セミナー動画『食品事故ゼロ!HACCPに基づく安心安全な「衛生管理」手法』をご覧ください。
>>>無料セミナー『食品事故ゼロ!HACCPに基づく安心安全な「衛生管理」手法』を見てみる
専用マークを使用して食の安全性をアピールできる
HACCP認証取得により、専用の認証マークを製品や広告に使用できます。ブランドイメージの向上や他社との差別化につながるでしょう。
さらに、認証マークは海外市場でもブランドの信頼性を高めます。競争力を強化し、新たな市場への参入や販路拡大にも役立てることが可能です。
HACCP認証機関・協会一覧!費用や特徴も解説
HACCP認証取得の際は、どの認証機関や協会を選ぶかが重要なポイントとなります。
それぞれの機関や協会の違いについて詳しく解説します。
地方自治体によるHACCP認証
地方自治体によるHACCP認証は「地域HACCP」とも呼ばれ、都道府県や市町村が独自の基準に基づいて審査を行います。
ただし、2021年6月のHACCP完全義務化以降、「地域HACCP」廃止が進んでいます。これは、地方自治体の認証制度がHACCPの普及を目的としているためです。今後も廃止の発表が増えていくことが予測されるため、もし長期的なHACCP認証を考えている場合は、別の認証機関・協会がおすすめです。
業界団体によるHACCP認証
業界団体によるHACCP認証は「業界団体HACCP」とも呼ばれ、企業が属する業界団体による審査を受けます。業界の特性に対応したHACCPで、以下のような特徴があります。
- 業界特化型の基準が設けられている
- 業界・業種ごと細かく分類されている
- 取得した業界にのみ適用される認証である
なお「業界団体HACCP」は、自身が所属する業界の認定のみ取得可能です。別の業界の認定は受けられないため注意しましょう。(例:菓子製造業者が食肉業界の団体の認定を受けることはできない)
| 業界団体HACCP | |
|---|---|
| 審査団体 | 各業界団体 |
| 難易度 | 中 |
| 費用 | 低(15万円~) ※業界ごとに異なる |
業界団体HACCP認証機関の例として、水産加工品の業界が該当する「大日本水産会」や冷凍食品業界が該当する「日本冷凍食品協会」が挙げられます。
他にもレトルト食品、総菜、食用加工油脂等、業界団体HACCPは様々存在します。どの業界に該当するのか確認のうえ、認証を進めましょう。
厚生労働省によるHACCP認証
厚生労働省によるHACCP認証は「総合衛生管理製造過程」と呼ばれ、厚生労働大臣が基準に適合することを個別に承認する制度です。この制度は令和2年6月1日をもって廃止されましたが、それ以前に承認または更新の手続きが完了していた場合、期間満了日まで適用されています。
民間審査機関によるHACCP認証
民間審査機関によるHACCP認証は「民間HACCP」と呼ばれ、最も一般的に知られる認証です。農林水産省によると、「業界団体HACCP」4.0%、「地域HACCP」6.8%の取得率に対して、民間HACCP(JFS-A~C、FSSC22000、ISO22000)計14.4%でした。
「民間HACCP」にはISO9001やFSSC22000などがあり、民間の専門機関が国際的な衛生基準に基づいて審査・認証を行います。特徴は以下の通りです。
- 国際的認知度が高い
- 選択肢が豊富
- 専門性の高い審査が行われる
「民間HACCP」取得のためには、HACCPだけでなく組織を管理する仕組みや環境基準の設定など包括的な取り組みを行う必要があります。
| 民間HACCP | |
|---|---|
| 審査団体 | 各民間団体 |
| 難易度 | 高 |
| 費用 | 高(100万円~) |
〈民間HACCP認証一覧〉
| 認証規格 | 求められるHACCPのレベル |
|---|---|
| JFS-A規格 | 一般衛生管理が中心 (HACCPの考え方を取り入れた衛生管理) |
| JFS-B規格 | HACCPに基づく衛生管理 |
| JFS-C規格 | |
| FSSC22000 | |
| ISO22000 | |
| ISO9001 |
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」と「HACCPに基づく衛生管理」の難易度の違いについては以下の記事で解説しています。おさらいしたい方はぜひご活用ください。
関連記事:HACCP「基準A」「基準B」の違いは?衛生管理の要求事項も解説
HACCP認証の取得方法とプロセス
HACCP認証を取得するためには、以下の3つの段階を順に進める必要があります。
それぞれのステップで必要な作業を解説します。
手順1.HACCPシステムの構築・運用
「7原則12手順」と呼ばれる、HACCP導入に推奨されている方法を用いてシステムを構築します。「7原則12手順」を以下のリストで一部のみ、簡潔に説明します。
- 原材料の受け入れから出荷までの各工程を書き出す
- 各工程で起こりうる危害要因を洗い出す
- 重点的に監視すべきポイントを特定する
- 監視する基準(温度、時間など)を設定する
- 運用開始
HACCP「7原則12手順」のすべての項目は以下の記事で解説しているので、気になる方は併せてご覧ください。
関連記事:【簡単解説】HACCP7原則12手順とは?覚え方や語呂合わせも
手順2.HACCPシステムの見直し・改善
HACCPシステムを一定期間運用した後、効果を評価し、必要に応じて見直しを行います。運用記録やモニタリングデータを分析し、設定した基準が適切に守られているかを確認します。
不備や改善点が見つかった場合は、HACCP計画を更新して新たな危害要因や工程変更に対応しましょう。
ここで重要となるのが「モニタリング」と「検証」です。モニタリングとは、CCP(重要管理点)が適切に管理されているかを継続的に確認することです。一方、検証とは、HACCPプラン全体が有効に機能しているかどうかを評価することです。
HACCPを効果的に運用するために重要な「モニタリング」や、効果の評価を実施するための「検証方法の設定」について理解を深めたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
▼関連記事▼
HACCPのモニタリングとは?検証との違いや設定方法も解説!
【HACCP導入】検証方法の設定とは?やり方や具体的な内容を解説
また、HACCP活動はすべて適切に記録し、保管することも重要です。記録は、HACCPシステムが適切に運用されていることを証明する証拠となるからです。以下の記事では、HACCP記録用の無料テンプレートをダウンロードできますので、あわせてご覧ください。
関連記事:【無料DL可】HACCP記録表のエクセルテンプレート2種!必要な文書や保管期間は?
手順3.HACCP認証審査を依頼する
HACCPシステムが十分に機能し、運用が安定してきたら、審査機関へ申請を行います。申請の際には、自社のコストやニーズ、目的に合った機関を選ぶことが重要です。例えば、海外展開を考えている場合は、国際的に認知度の高い認証機関が望ましいでしょう。
審査は、主に各機関から派遣された審査員が2回に分けて実施します。それぞれの審査で確認される点は以下の通りです。
| 第1審査 | HACCPの構築状況 第2審査のための情報収集 |
| 第2審査 | HACCPの実施状況を視察 規格適合性や運用の様子を審査 |
審査に合格すると登録証が発行され、その後も定期的に更新審査を受けることで、認証の有効性を維持できます。
HACCP認証に関するよくある質問
HACCP認証に関するよくある質問に回答します。参考までにぜひご覧ください。
HACCP認証は義務化されている?
HACCP認証そのものは義務ではありません。
ただし、HACCPの導入は2021年6月以降、日本国内のすべての食品事業者に義務化されています。HACCPの「認証」と「導入」の違いは、前項「HACCP認証とは」で解説しているのでご確認ください。
HACCP認証が必要な食品例は?
HACCP認証は、特定の食品に限定されるものではありません。
食品製造業者だけでなく、流通業者、飲食業者など、食品を取り扱う幅広い事業者が取得を目指せます。食品の種類や規模に関わらず、製品の安全性や品質管理体制を証明したい場合に取得します。
まとめ:HACCP認証の肝は「従業員の衛生管理教育」
HACCP認証とは、企業が第三者機関によりHACCPの適合性を公式に認めてもらうことです。海外進出を目指している場合や大手取引先との契約を進める場合、または安全性と品質の高さをアピールしたい場合に取得します。
HACCP認証を取得するには、計画を立てるだけでなく、実際に現場で運用を徹底し、継続的に改善していくことが必要です。そのためには、従業員1人ひとりが衛生管理に対する高い意識を持ったうえで、日々の業務を遂行することが求められます。
現場で活きる実践的な知識を教育する方法として、注目されているのが「動画マニュアル」です。動画は文字や画像だけでは伝わりにくい作業手順や衛生管理のポイントを、視覚的に分かりやすく伝えることができます。また、多言語対応の動画マニュアルであれば、食品工場や製造業で増え続けている「外国人従業員」への非言語教育もスムーズに行えます。
とくに、かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」には、100か国以上の自動翻訳機能に加え、認証をサポートするさまざまな機能が搭載されています。「動画マニュアル」の導入効果や「tebiki」の詳細な機能については、以下の資料で解説しているので、ご興味のある方はぜひご覧ください。