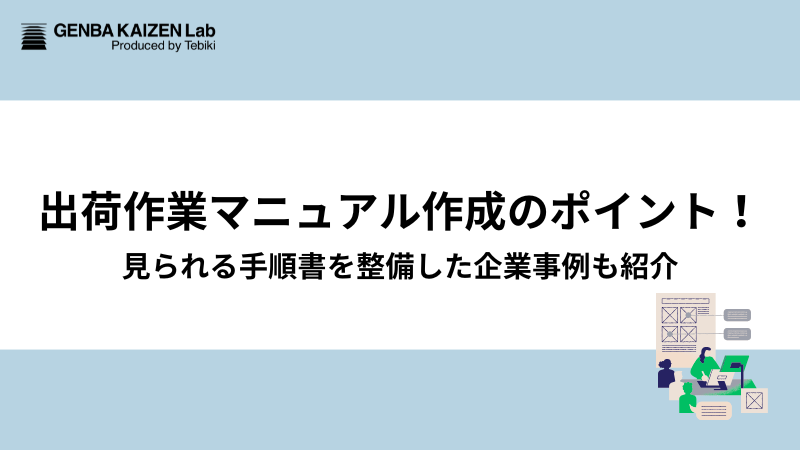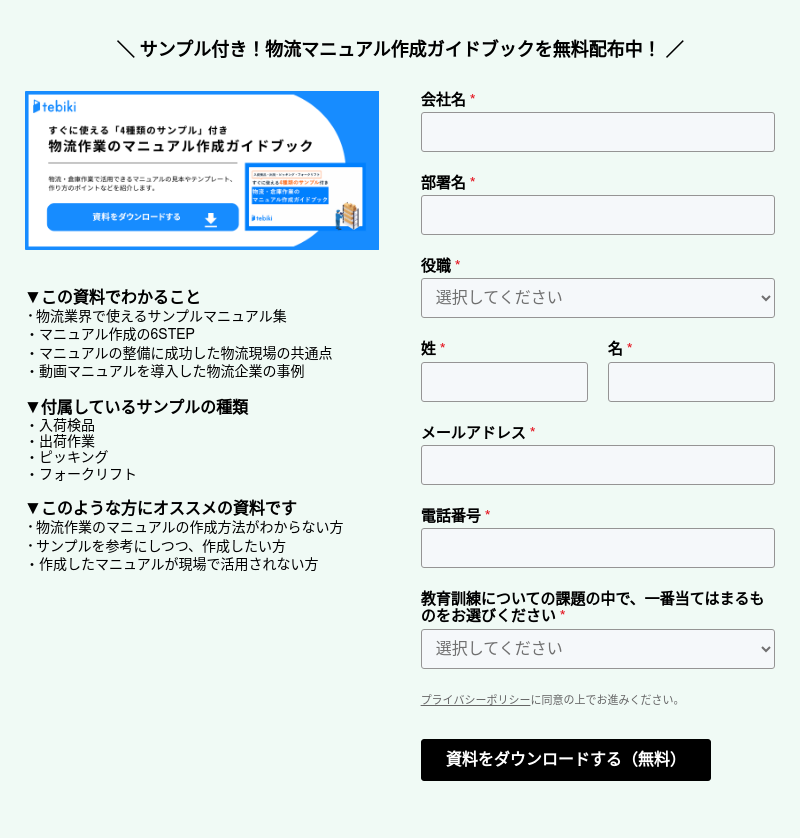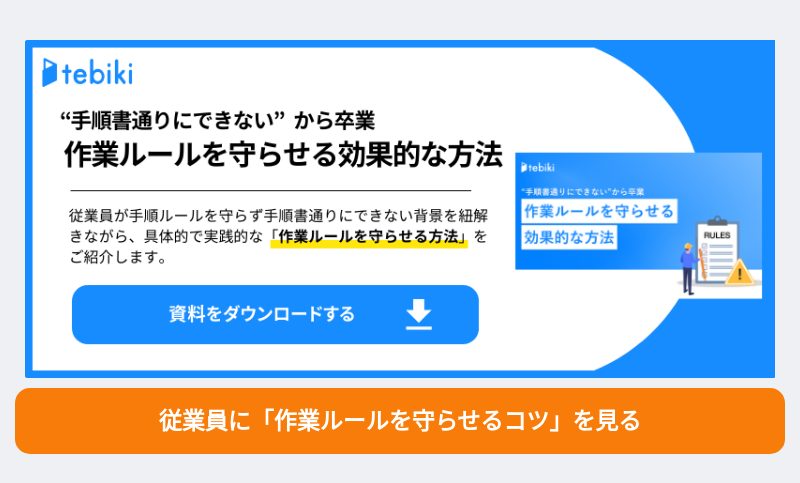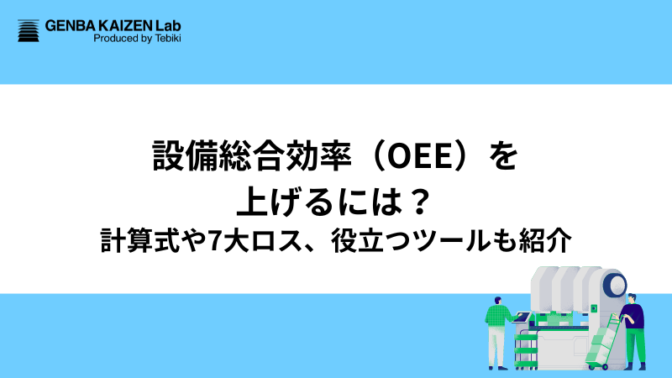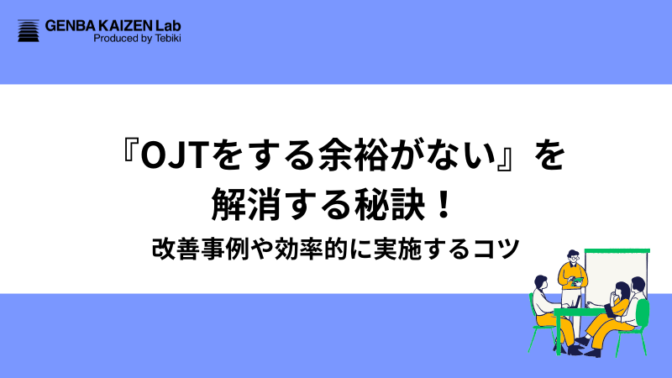かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
倉庫の現場改善に不可欠な「マニュアル整備」。特に出荷作業はミスが生じやすく、作業標準化がより重要な領域です。一方で、マニュアルが機能していない(形骸化している)倉庫現場は少なくありません。本記事では、「現場できちんと使われる」マニュアル作成のポイントや、見られる手順書を整備し、現場改善を実現した物流企業事例を紹介します。
なお、出荷作業マニュアルのサンプルが付属した物流現場のマニュアル作成ガイドブックもご用意しています。この記事で紹介しているポイントを踏まえつつ、ガイドブックをご覧頂くことで現場で活用されるマニュアル作成の近道になりますので、以下の項目を入力してガイドブックをご覧ください。
目次
出荷作業におけるマニュアル整備の重要性やメリット
マニュアルや作業手順書は、出荷作業の改善の基本にして重要な要素です。特に、以下の3つにおいて重要な役割を果たします。
- 作業スキルの標準化とミスの軽減
- 新入社員の教育工数を削減
- 外国人労働者やパートタイム作業員の即戦力化
※マニュアル整備以外で、出荷作業の改善ポイントについて知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。
作業スキルの標準化とミスの軽減
マニュアルや手順書の整備は、作業標準化につながります。つまり作業ミスが減るのです。出荷現場では、数量間違い、ラベルの貼り間違いなど、ちょっとした確認ミスが大きなトラブルにつながります。
このようなミスは、作業手順が人によって曖昧だったり、覚え間違いがあったりすることで発生します。言い換えれば、マニュアルが整備されていない現場は作業品質にバラつきが生じやすいです。
マニュアルを整備すれば、作業の手順や判断基準が統一され、「誰がやっても同じ結果になる」状態を作ることが可能です。結果として、ミスが減り、顧客からのクレームも減少します。また、手順が明確になっていると、作業者も安心して作業に取り組めます。
マニュアル通りに作業が進行される手順書整備のポイントは、資料「“手順書通りにできない”から卒業 作業ルールを守らせる効果的な方法(pdf)」で詳細に解説されています。下の画像をクリックするとダウンロードが可能です。
新人作業者の教育工数を削減
新入社員の受入教育はあらゆる物流現場で問題視されています。特に根強く残っている課題が「度重なる教育工数による通常業務の圧迫」です。
多くの物流現場では、先輩社員によるマンツーマン指導やOJT教育が実施されており、それらに費やされる教育工数は無視できません。教える側・教わる側双方にとって大きな負担になっています。ある程度の作業はマニュアルで理解し、必要最低限のOJT教育でそのほかをフォローできる教育体制が理想的です。
そのためには「正しい作業内容や手順が、一目である程度理解できるマニュアル整備」が重要ですが、その要件を満たすには紙マニュアルでは限界があるのも事実です。
ゆえに、物流現場では「動画によるマニュアル整備」が徐々に浸透し始めています。動画マニュアルの具体的な活用事例やユースケースについて少しでも興味があれば、以下の資料「物流業界の生産性向上を助ける動画マニュアルのチカラ(pdf)」も参考にしてみてください。
>>>物流業界の生産性向上を助ける動画マニュアルのチカラ(pdf)をダウンロードする
外国人労働者やパートタイム作業員の即戦力化
近年、多くの物流現場では外国人スタッフや短時間勤務のパートタイム作業員が増えています。こうしたスタッフが即活躍するには、言語や時間の壁を超える「伝わる」マニュアルが必要です。
マニュアルを一目見れば、正しい作業品質で出荷作業を行えるようになる状態が望ましいです。決して簡単なことではありませんが、出荷作業の品質を底上げするには、マニュアル整備は避けては通れない道と言えます。
「マニュアルが読まれない、整備できない」倉庫現場が抱える課題
出荷作業におけるマニュアルの重要性は理解しつつも、「そもそもマニュアルが読まれていない」「作っても現場で使われない」「時間がかかるし、継続できない」といった状態に直面する現場は少なくありません。
なぜ、これほどまでに重要なマニュアルが形骸化してしまうのでしょうか?
それは以下のような課題が、物流や倉庫現場で生じているからなのです。
- 手順書の内容が古く現場の実態と乖離している
- 紙によるマニュアルから抜け出せない
- 作成工数が膨らみ整備が追いつかない
- OJT教育やマンツーマン指導に過剰依存している
- 困ったときにマニュアルをすぐに取り出せない
手順書の内容が古く現場の実態と乖離している
マニュアルが読まれない要因のひとつが、「マニュアルに書かれている出荷作業の説明が、現場で運用されている作業方法とズレている」ことです。
例えば、出荷作業における工程変更が以前あったがマニュアルに反映されておらず、現場では新しいやり方になっていながら、マニュアルでは旧来の手順が残っている、というようなケースです。これでは現場で混乱が生まれるだけでなく、「マニュアルはあてにならない」という認識を持たれてしまい、ますます使われなくなってしまいます。
定期的にマニュアルが更新される仕組みづくりをするには、「カンコツが伝わる! 『現場で使われる』作業手順書のポイント」を参考にしてみてください。作業品質の向上につながる手順書整備の方法を知ることができます。
紙によるマニュアルから抜け出せない
多くの倉庫現場では、いまだに紙のマニュアルが中心です。しかし、紙媒体には以下のような課題があります。
| 検索性が悪く、必要な情報がすぐに見つからない | 実務の中で「あれってどうやるんだっけ?」と思っても、該当箇所を探すのに時間がかかってしまい、結局誰かに聞いてしまうといった状況が起きてしまう |
| 文章ばかりで理解しにくく、作業イメージがわかない | 作業の手順がすべて文字で書かれていると、読み手によって解釈に差が出やすく、実際の動きと結びつかないまま進めてしまう危険性がある |
| 日本語に不慣れな外国人スタッフにとっては、作業内容の理解が難しい | 特に外国人スタッフの場合、文字中心のマニュアルは読み進めるのが難しい言語の壁により、理解に時間がかかるだけでなく、ミスや事故につながる可能性もある |
このような課題を解決するために、注目されているのが動画マニュアルです。
例えば、総合物流企業である「株式会社フジトランス コーポレーション」は、外国人労働者に対する教育や指示内容の理解度向上が課題でした。
外国人労働者が増加している現場では、教育や指示内容の理解度向上が課題でした。言葉の壁があり、業務の指示を出しても「分かりました」とスムーズにニュアンスが伝わらず、教えるのに時間がかかり、教育者が本来の業務に取り掛かれないといった話もありました。
たとえば、海外拠点で新しいプロジェクトが発足した際、必ず日本人の熟練者が現地に赴いて数か月直接指導します。しかし指導を行うにあたり、マニュアルの翻訳工数なども発生しており、オンボーディング部分で熟練者の負担をもう少し軽減できればという課題がありました。
現在はマニュアル整備に成功し、外国人労働者の作業品質がバラつかないよう現場教育の体制を改善できています。同社の詳しい成功事例は、以下のインタビュー記事をご覧ください。
インタビュー記事:マニュアル整備事例~外国人労働者の教育改善に成功
作成工数が膨らみ整備が追いつかない
マニュアルを「きちんと作ろう」と思えば思うほど、膨大な工数がかかってしまうことは多くの現場担当者が悩むポイントです。
現場の人手不足や繁忙期が重なる中、更新作業が後回しになり、「古いまま」「未完成のまま」のマニュアルが現場に放置されるケースもあります。「整備に時間がかかる=現場で使えない」という悪循環を断ち切るためには、誰でも・短時間で更新できる仕組みが必要です。
例えば、事業所向けECサイト「ASKUL」サービスを展開する「アスクル株式会社」では、マニュアルの作成工数に課題を感じ、非効率な教育体制に苛まされていました。
紙の手順書については、個別で手順書が作成されており一元管理できていなかったので、内容が重複していたり似たような手順書がいくつかあったなどの問題が発生していました。このようにOJTや紙マニュアルによる教育だと、物量的にデータ量の過多や、無駄な工数が発生するなど非効率な状況でした。
現在では、新人社員が最短距離で一人前になるための教育体制が構築できています。同社の詳しい事例は以下のインタビュー記事よりご覧いただけます。
インタビュー記事:高度に自動化された倉庫の安定稼働を支えるために動画マニュアルtebikiを導入!
OJT教育やマンツーマン指導に過剰依存している
マニュアルが整備されていない現場ほど、OJT教育に頼りきりの教育体制になっています。
新人に付きっきりで教える時間がとれなかったり、人によって教え方が違ったりすることで、習得スピードや品質にバラつきが生じます。また、教育担当者の負担も大きく、教える側・教わる側ともにストレスがかかりやすい構造です。
例えば、建築副資材の提供等を手掛ける「ソニテック株式会社」では、教育にかかる時間とコストが大きな課題でした。新入社員には3ヵ月間のマンツーマン指導が必ず発生するようになっており、通常業務にリソースがなかなか費やせないという問題に直面していたのです。
物流倉庫における新人教育は、業務効率化と品質維持が必須ですが、教育にかかる時間とコストが大きな課題となっています。新入社員には3ヶ月間のマンツーマン指導が必須であり、指導者の日常業務に影響を及ぼすこともありました。
OJT教育やマンツーマン指導の依存から脱却できた同社は、具体的にどのように改善したのか、その成功事例について知りたい方は以下の記事もあわせてご覧ください。
インタビュー記事:3ヶ月間の直接指導を動画マニュアルで完全に置き換え、業務の効率化を実現
困ったときにマニュアルをすぐに取り出せない
マニュアルが事務所のファイル棚に置かれていたり、共有PCのフォルダに埋もれていたりすると、現場ではすぐにアクセスできません。
例えば、梱包作業中に「この商品の包装資材、どれを使うんだっけ?」という場面があっても、すぐに確認できないことで作業が止まったり、誤った資材を使ってしまう可能性もあります。
現場で使われるマニュアルは、すぐに確認できなければいけません。スマートフォンやタブレットから即座に確認できる仕組みがあれば、作業の流れを止めずにスムーズな対応が可能になります。
手順書通りに出荷作業されるための「マニュアル作成のポイント」
出荷作業を標準化するためには、作業手順を明確に記したマニュアルの整備が欠かせません。しかし、ただマニュアルを作ればよいというわけではなく、「読まれる」「使われる」状態を作るためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
手順書通りにマニュアルが作成されるための必要な要件は、資料「“手順書通りにできない”から卒業!作業ルールを守らせる効果的な方法」にすべてまとめられていますが、本記事では資料から一部抜粋し、実際に現場で運用されるマニュアルを作成するためのコツを5つご紹介します。
- マニュアル化(標準化)したい作業範囲を決める
- 「一目で見てわかる」マニュアル作りを意識する
- スマホやタブレットでのマニュアル閲覧を可能にする
- ヒヤリハット事例やNG作業例も記載する
- 数値目標(KPI)を設定する
>>>「“手順書通りにできない”から卒業!作業ルールを守らせる効果的な方法」を読んでみる
マニュアル化(標準化)したい作業範囲を決める
まずは、「どの作業をマニュアル化すべきか」を明確にすることが出発点です。現場ではさまざまな作業が同時並行で行われており、すべてを一度にマニュアル化するのは現実的ではありません。
出荷作業の一般的な流れは以下の通りです。
- ピッキング(商品の取り出し)
- 検品(商品内容の確認)
- 梱包(適切な資材を使用)
- 伝票作成(ラベル・納品書の出力)
- 出荷(配送業者への引き渡し)
この一連の流れを可視化し、その中から「ミスが起きやすい」「担当者によってやり方が異なる」「新人がつまずきやすい」などの課題が多い作業から優先的にマニュアル化すると、実務への効果を実感しやすくなります。
「一目で見てわかる」マニュアル作りを意識する
作ったマニュアルが現場で使われない原因の多くは、「見づらい」「わかりにくい」にあります。文章ばかりの手順書では、読むのに時間がかかり、作業中に確認することも難しいからです。だからこそ、「一目で理解できる」ことが、現場で使われるマニュアルの必須条件になります。
この点で注目されているのが、マニュアルの動画化です。
実際の作業手順をそのまま映像にすることで、初心者でも動きや流れを直感的に理解できます。「動画撮影」と聞くと一見大変のように感じるかもしれませんが、「現場作業でもかんたんに作成できる動画マニュアルツール」が近年では開発されており、物流現場においても動画によるマニュアル整備が徐々に増えてきています。
例えば、物流現場に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」は、現場作業員がスマホで作業手順を撮影し、そのままかんたんな編集ですぐにマニュアル化できる現場DXツールとなっています。
下の画像をクリックすると、tebikiの詳しい活用事例や詳細な機能が分かるサービス資料(pdf)がダウンロード可能です。参考にしてみてください。
スマホやタブレットでのマニュアル閲覧を可能にする
マニュアルがあっても、現場で気軽にアクセスできなければ意味がありません。作業中にすぐ確認できるよう、スマートフォンやタブレットなどモバイル端末での閲覧に対応した形式で整備するようにしましょう。
動画マニュアルであれば、QRコードを使って作業エリアに掲示したり、タブレットにショートカットを用意したりと、現場に合わせた運用が可能です。このようなアクセスの仕組みがあれば、「困ったときにすぐ確認する」という行動が習慣化され、作業品質の安定につながります。
ヒヤリハット事例やNG作業例も記載する
マニュアルには、「やるべきこと」だけでなく、「やってはいけないこと」も記載しておくと効果的です。
例えば、フォークリフトを扱う作業では、操作ミスが重大な労災につながる可能性があります。こうした危険を回避するには、実際に起きたヒヤリハット事例や、過去のNG行動を可視化して共有することが重要です。
物流企業「株式会社近鉄コスモス」では、フォークリフト作業におけるNG事例を動画で撮影し、従業員向けに周知する取り組みを実施しています。爪でパレットを押したり、荷物をフォークで持ち上げたまま離れたりなどのNG行為を、動画マニュアルで説明しています。
▼ヒヤリハット周知を動画でマニュアル化▼
※「tebiki」で作成
「見たことがある」状態を作ることで、リスク感度を高め、事故の未然防止に役立てることが可能です。
ちなみにフォークリフトは安全対策が特に求められる作業領域です。フォークリフトの安全性を高めるための現場改善については以下の記事も参考になるでしょう。
▼関連記事▼
・フォークリフトの安全対策8例!事故を防止した改善事例や安全意識を高める方法も解説
・フォークリフトのヒヤリハット事例集と対策まとめ!危険予知の事例もあわせて解説
数値目標(KPI)を設定する
マニュアル整備の成果を正しく評価するためには、KPI(重要業績評価指標)の設定が欠かせません。例えば、以下のような数値目標を設定することで、マニュアル化の効果を定量的に把握できます。
- 出荷作業時間を20%短縮
- ピッキングミスを月間5件→1件に削減
- 教育完了までの期間を2週間→5日に短縮
目標が明確になれば、現場のモチベーションも高まり、マニュアルの改善サイクルも回しやすくなります。
出荷作業のマニュアル整備がうまくいっている物流現場事例と現場の共通点
出荷作業のマニュアル整備がなかなか進まない要因は、紙マニュアルの更新のしにくさや読みにくさが温床となっていると解説しました。言い換えれば、紙マニュアルから脱却し、「一目で作業内容が理解できるマニュアル整備」が、出荷作業の改善要件だといえます。
マニュアル整備がうまくいっている多くの物流現場では、「動画」が教育体制に導入されています。例えば物流企業の「ソニテック株式会社」は動画マニュアルを新人教育に活用しており、OJT教育依存から脱却しています。それだけでなく、1本の動画マニュアルを5分~10分ほどで作成できており、マニュアル整備によって稼働時間が確保できないような問題も回避できています。
わずか数分程度で動画マニュアルを作成できているのは、現場作業の動画マニュアル作成に特化したツールを導入しているためです。その1つに「tebiki現場教育」があげられますが、同社もtebikiによってマニュアル整備に成功しており、現場改善を実現しています。
tebiki現場教育の主な活用事例や詳細機能がまとめられた資料は、以下の画像をクリックしてダウンロードできます。紙マニュアルからの脱却を検討中の方は参考にしてみてください。
まとめ:出荷作業の標準化は「一目で分かる」マニュアル整備が鍵を握る
出荷作業の標準化によるミス削減や教育効率化には、マニュアル整備が欠かせません。しかし、文字中心の紙マニュアルは「分かりにくい」「更新が手間」「探しにくい」といった課題から形骸化しがちです。
この問題を解決し「現場で使われる」手順書にする鍵が、「一目で見てわかる」マニュアル作りです。特に動画マニュアルは、作業の動きを直感的に伝え、新人や外国人スタッフの早期戦力化、教育工数削減に効果を発揮します。
スマホでかんたんに撮影できるツールを活用すれば、作成・更新も容易になり、作成工数をかけずに教育体制を改善できます。「一目でわかる」動画マニュアルの整備こそ、出荷作業の品質と効率を高める重要な鍵と言えるでしょう。
動画マニュアル作成ツールならどれでもいいわけではなく、あくまで現場作業員が気軽に扱えるツールを選べることが望ましいです。「tebiki現場教育」はまさに現場作業員が手軽に扱えることを念頭において設計されているので、こうしたツールを検討してみるとよいでしょう。