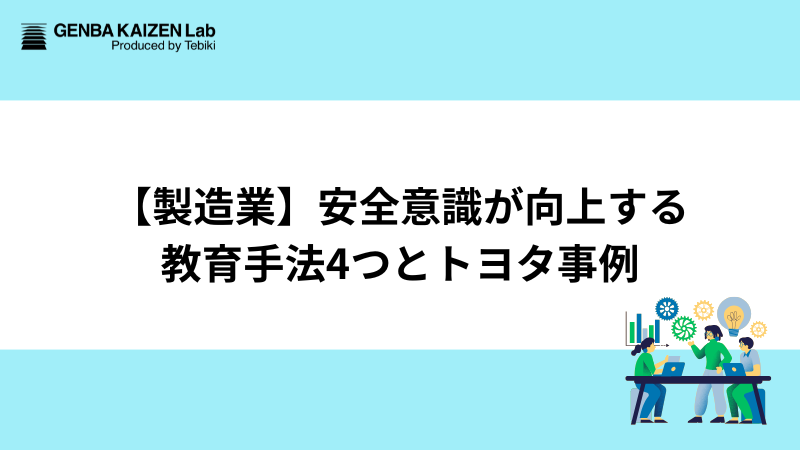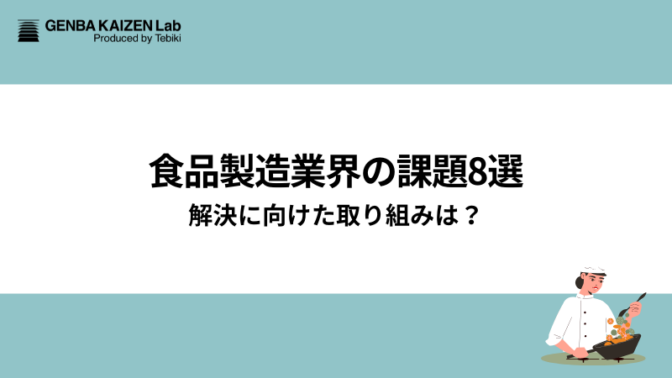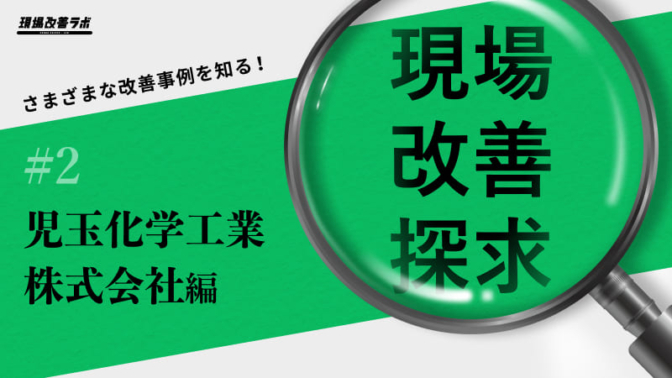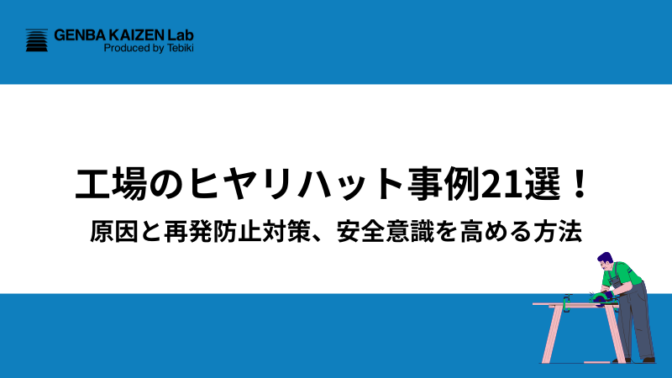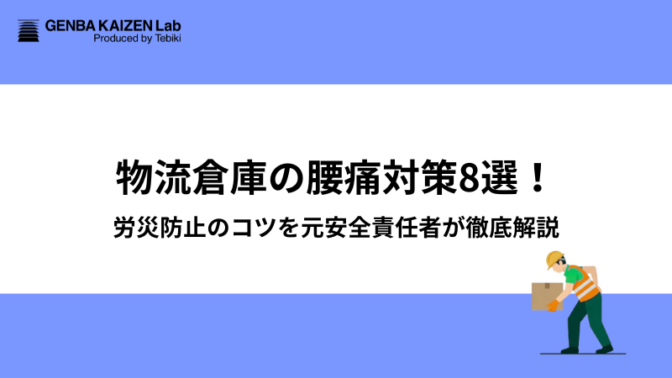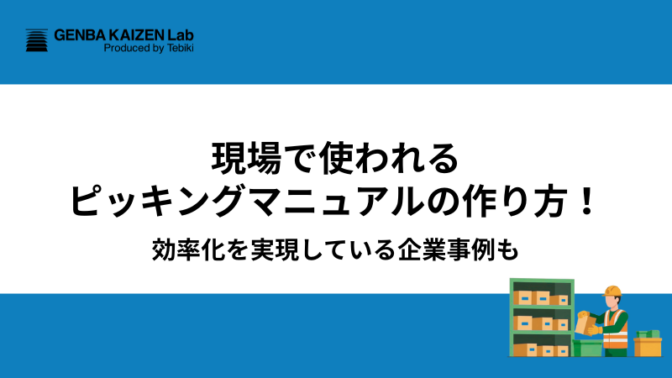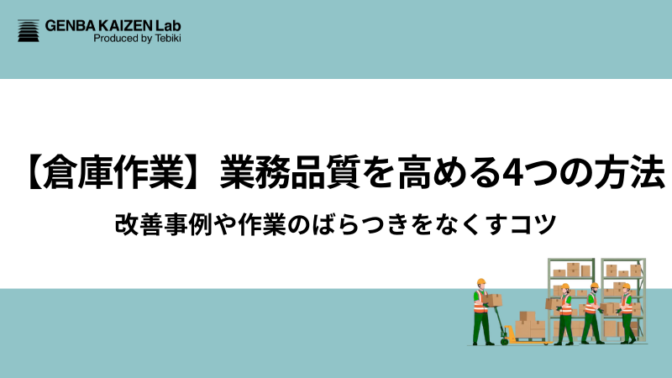かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
安全教育とは、労働者の安全と健康を守るための教育のことです。製造業は労働災害の発生頻度が多く、防ぐためにも、従業員の安全意識を高める安全教育の実施が大切です。
そこで本記事では、製造現場の安全意識を向上させ、労働災害や事故を未然防止するための教育方法を解説します。多くの現場で安全教育に採用されている「動画マニュアル」についていち早く知りたい方は、記事よりも情報が詳細にまとめられている資料「動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例(pdf)」をご覧ください。
目次
製造業の労災が減らないからこそ安全教育が大切
厚生労働省による「令和5年 労働災害発生状況」によると、令和5年度(2023年)の製造業における死亡者数と休業4日以上の死傷者数は以下の状況です。
- 死亡者数:138名(前年比1.4%減)
- 休業4日以上の死傷者数:27,194名(前年比1.9%)
労働災害による死亡者数は微減しているものの、全体の発生状況としては上昇傾向にあることが分かります。また、他の業界と比較しても少なくない頻度で死亡事故が発生し、休業4日以上のケガに至っては全産業で最も多い発生状況です。
労働災害が発生した場合、労働安全衛生法による処罰を事業者に課せられます。一方で、製造現場で労災が発生したとしても、処罰が課せられない場合もあります。ここで、元労働基準監督署署長の村木 宏吉氏による寄稿の一部をご紹介します。
労働安全衛生法には、「労働災害を発生させたら処罰する」という条文はありません。
なぜなら、労働災害をゼロにするためには、莫大な費用が必要だからです。そこで、事業者(会社)が行わなければならない事項を法令に定め、これらをすべて実行している場合には、労働災害が発生したとしても処罰はしない、という構成にしてあるのです。
(別記事「安全第一はだれのため?」より抜粋)
つまり、条文では処罰することは明記されていないものの、必要な安全教育や安全対策を行わずに労働災害が発生した場合、事業者が罰則を受けるということです。
労働災害の発生や罰則を受けた場合、第三者視点から厳しい目を向けられ会社の評判に悪影響を及ぼすだけでなく、労働災害にあった従業員の家族も精神的な苦痛を受けます。
このような負の連鎖を起こさないためにも、労働災害を防ぐための取り組みや安全教育を怠ってはいけません。
>>「安全意識を形骸化させない安全教育の進め方」を専門家が解説する動画を見る(無料)
労働安全衛生法で定められている製造業で必要な安全教育の種類
製造業では労働安全衛生法(労安法)に基づき、事業者に以下の安全教育が義務付けられています。
- 雇入れ時教育
- 作業内容変更時の教育
- 特別の危険有害業務従事者への教育(特別教育)
- 職長等教育
一方で、これらの教育だけを実施していればいいというわけではありません。この点についても本章で詳しく解説していきましょう。
製造現場で必須になる4つの安全教育
雇入れ時の教育
初めて製造現場に参加する労働者は、環境と機械に慣れておらず業務内容や使用する機械の操作方法を知らないことが多いため、雇入れ時にしっかりと教育を行う必要があります。
雇い入れ時に、特定の手順や機械の操作方法、作業時のリスク把握など業務の基礎知識を教育することで、事故のリスクを低減することや、新入社員が安心して業務に取り組むことができる環境を提供することが可能です。
雇い入れ時の教育は「新規入場者教育」や「入構者教育」と呼ばれるケースもあります。
関連記事:新規入場者教育とは?目的、送り出し教育との違い、実施内容、進め方などを解説
作業内容変更時の教育
製造現場では生産効率の向上や品質改善を目的とした、新しい機械の導入や作業手順の変更等が頻繁に行われます。このような変更は、製造現場を構成する要素、4M(Man/Machine/Material/Method)の変更にあたり、ミスやトラブルの原因となりやすく教育が欠かせません。
4Mのような作業内容変更を正確に伝えることで、従業員は新しい作業内容や機械の操作方法を正確に理解し、安全に業務を遂行することができます。
関連記事:4Mとは?分析方法や変更管理の目的とポイントを解説
特別の危険有害業務従事者への教育(特別教育)
製造業には危険有害業務と呼ばれる危険が伴う業務が存在します。例えば、高温の溶融金属を扱う鋳造作業や有毒な化学物質を使用する塗装作業には特別な注意が必要です。
危険な業務を行う労働者には通常の安全教育以上の特別教育が必要です。
特別教育を受けることで従業員は高リスクの業務における安全対策や緊急時の対応手順の習得が可能になり、労働者の安全を確保するだけでなく業務の効率や品質の向上も期待できます。
職長等への教育
製造現場において職長やリーダーはチームのメンバーを指導し、安全な作業環境を維持する責任があります。
職長等への教育は安全を確保するための基本的な知識や技術、さらにはリーダーシップやコミュニケーションスキルの向上を目的としています。職長等への教育を受けることで職長やリーダーはチームの安全を確保するための適切な指示や対応を行えるようになります。
また令和5年(2023年)4月1日より「食料品製造業」、「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」が新たに安全衛生教育の対象業種として追加されたため、教育の重要性がより一層高まることとなります。
関連記事:職長教育と安全衛生責任者教育の違いは?実施目的や再教育の期限を解説
労安法で義務の安全教育だけでは足りない
先ほどご紹介した4つの安全教育は労安法で義務化されていますが、これらだけ実施すればいいというわけではありません。たとえば、労安法第71条2項では以下の法令が記載されています。
<第七十一条の二>
事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
一.作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
二.労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
三.作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
四.前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
(「労働安全衛生法」より引用)
つまり、製造現場において、全従業員の安全意識向上を狙うような定期的な安全教育、危険な業務に従事する従業員を対象にした安全教育など、必要に応じて計画し実施することが求められています。
「努めなければならない」という努力義務にあたる表現ではあるものの、一定の法的な効力を持つ内容です。未実施で労災が発生した場合、総合的な評価で安全配慮義務違反の一要素として考慮される可能性はあります。
そのため、製造現場においては、定期的な従業員への安全教育も必要であるということです。
従業員への安全教育と聞くと座学研修やOJTをイメージするかもしれませんが、このような安全教育は管理者の教育負担が生じることに加え、不安全行動のような「動き」を口頭で正しく従業員へ伝える難しさがあります。
このような製造業における安全教育の難しさを解消する手段として、動画マニュアルを活用した安全教育を行う現場が増えています。動画で視覚的に伝えることで、従業員の危険感受性を高める効果が期待できます。また、管理者の教育工数を効率化することも可能です。
より具体的な動画マニュアルを安全教育に活用するメリット、実際に安全教育で動画を活用している企業事例やサンプル動画は、別紙のガイドブックで詳しく解説しています。以下のリンクをクリックするとガイドブックをご覧いただけますので、ぜひご活用ください。
>>>「動画マニュアル」を活用した安全教育の実践方法や事例を見てみる(pdf)
製造現場の意識を高める安全教育【4つの手法とポイント】
製造現場の安全レベルを高めるには、大前提として「なぜ安全行動が重要なのか?」を作業員一人ひとりが自分事として認識することが不可欠です。
しかし、「安全第一」というスローガンを唱えたり、「意識を高めろ」と精神論を説いたりするだけでは、現場はなかなか変わらないのが現実です。「健康のために毎日運動しましょう」が正論だと分かっていても、継続するのが難しいのと同じです。
安全活動が形骸化してしまうのは、決して現場の意識が低いからではありません。人間の「面倒くさい」「自分は大丈夫」といった心理を踏まえた、行動を後押しする「仕組み」や、やりたくなる「仕掛け」が欠けているからです。
そこでここでは、多くの現場で導入されている4つの安全教育手法について、よくある落とし穴と、それを乗り越えて成果に繋げるための具体策をご紹介します。
安全な作業手順が「一目でわかる」教育体制を整備する
安全トラブルに繋がるような不安全行動を起こさせないためには、製造現場のルール/標準が守られることが必要です。しかし、「手順書整備の重要性はわかるものの、取り組む時間がない」という現場は少なくありません。
というのも、従来の手順書(紙や文字のマニュアル)は、以下のような運用面の課題が負担となっていることが多いからです。
- 文字や写真だけでは「安全な動作」が伝わりにくい
- 多品種で手順書の新規作成や更新が追い付かず「形骸化」
- 保管場所や方法が統一されず「使いたい時にすぐ使えない」
上記のような背景から、「煩わしい説明を極限まで省いた、一目で理解できるマニュアル」が多くの製造現場で導入されつつあります。そのなかの1つの手段として「動画マニュアル」があります。
動画マニュアルの例として、製造業の「児玉化学工業株式会社」が作成した「バリの取り方」を動画マニュアル化したものを紹介します。
▼動画で安全な作業手順を示す例▼
※「tebiki」で作成
このように、「誰が見ても同じ解釈」「教える人によって教育内容がばらつかない」のが、動画マニュアルの強みであり、安全教育に広く採用されている理由でもあります。
「動画を作るのは大変」な印象はあるかもしれませんが、重要なのは「現場作業員でも手軽に作成できる」ツールを選定することです。例えば、製造業に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」は、片手間に動画マニュアルを作成できるのが特徴であり、導入事例が多く増えています。
tebiki現場教育の導入事例や安全現場への活用方法について、詳しく知りたい方は、下のリンクからサービス資料をダウンロードいただけます。あわせて参考にしてみてください。
>>>製造業の動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」のサービス資料を見る
労働災害を疑似体験してリスクを体感する
労働災害を疑似体験させる方法としては、VR技術を活用した仮想体験、実際の作業環境を模したシミュレーション訓練、動画マニュアルによる教材の整備などがあります。
例えば、某物流企業は「実際にあった事故」を動画にし、作業スタッフと視聴する時間を定期的に確保しています。以下は実際に同社で作成された、ヒヤリハット共有動画です。
▼事故の共有動画の例▼
労働災害を疑似体験することで、危険に対する意識や感度の向上や、日常業務に潜むリスクの理解が進みます。また、疑似体験というインパクトが強い体験であることからも、中長期的な安全意識の記憶定着が期待できます。
実際に体験する際は、画一的に用意されたコンテンツではなく、なるべく自社の現場や環境を再現したコンテンツが望ましいでしょう。
身近な環境を再現して体験することで、より自分事として捉えやすくなることから、安全意識を最大限引き出す効果が期待できます。最もハードルが低い疑似体験の手段として「動画の活用」がおすすめです。
また、動画マニュアルはヒヤリハットや事故事例の共有だけでなく、「正しい安全作業の周知・定着」や「ベテラン社員のみができる安全作業の可視化」にも寄与します。安全意識の高い製造業の多くの現場で、動画マニュアルがよく導入されているのは、上記のような背景があるからなのです。
製造業における動画マニュアルの取り組み事例や安全意識の定着のさせ方については、以下のPDF資料「安全意識が高い製造現場はやっている! 動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例」でまとめられているので、あわせてご覧ください。
>>安全意識が高い製造現場はやっている! 動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例
5S活動の徹底で安全な作業環境を維持する
5S(整理、整頓、清掃、清潔、躾)は、職場環境の改善や維持を目的とした活動です。
5Sが徹底されている現場は危険源も取り除かれており、安全な職場環境が整っているといえるでしょう。結果的に、ヒヤリハットや労働災害の未然防止につながります。
5Sの徹底は、危険源を取り除き、労災を未然に防ぐための基本です。
しかし、その重要性は理解していても「定着しない」「すぐに元通りになる」といった悩みは尽きません。5S・3定が浸透しない現場の共通点と、精神論ではなく「仕組み」として定着させるためのポイントを以下の資料で解説します。
>>【事例つき】5S3定が浸透しない現場の共通点3つと仕組み化の「核」を見てみる
KYT(危険予知訓練)の実施で危険予知能力を高める
KYT(危険予知訓練)とは、現場に潜む労働災害に繋がる危険を探し出し、対策を講じる能力を高めるためのトレーニングです。
写真や動画など、実際の作業現場を確認し『ここに○○な危険が潜んでいるかも?』という視点で洗い出し、危険源を予測する力を鍛え、ヒヤリハットや労働災害の発生を未然に防ぐ効果が期待できます。
よく行われている安全教育の1つですが、KYTがあいまいに進められている/内容がマンネリ化しているといった課題を抱え、うまく安全意識の向上につなげられていない製造現場のお話も度々伺います。このようなKYTの課題を解消する方法は、無料で公開している専門家による解説動画を以下のリンクよりご覧ください。
>>【セミナー動画】「生産性を高める5S活動 正しい運用に欠かせない「重要なS」とは」を視聴する
>>【お役立ち資料】労災ゼロ!形骸化したKYTから脱却する動画KYTを見てみる
安全意識を高めている製造業の安全教育事例
前章でご紹介したような安全教育の手法は、あくまでもよくある一例です。自社の安全意識向上や労働災害防止を実現するためには、実態に即した教育手法を取り入れることが必要でしょう。
その際に疑問を感じるのが『他の工場ではどのような安全教育を行っているのか?』です。ここからは、工場の安全教育の好事例を3社ご紹介します。
トヨタ自動車株式会社
トヨタ自動車株式会社では、「人づくり」「作業/仕事づくり」「場/環境づくり」を3本柱に安全衛生活動を推進しています。従業員が自然に安全な行動を取るために、トップダウンと1人ひとりに向き合うことをポイントに、以下のような活動を行っています。
- 全社安全現地現物活動
- 安全伝承館
- 安全コンテンツの動画化
- VRを活用した危険体験によるKY能力向上 など
過去に実際に発生した労働災害などを再現動画で可視化することで、視覚的に危険な動作を伝えて労災を未然防止している取り組みは、特に参考になります。動画を活用した安全教育は比較的着手しやすく、チームや部署内で小さくスタートし効果検証をすることも可能です。
トヨタも実践している「動画による安全教育」は、トヨタに限らずあらゆる製造現場で導入されています。動画マニュアル×安全教育の具体的な活用イメージや事例については、以下の資料で詳しく解説されているので、あわせて参考にしてみてください。
>>安全意識が高い製造現場はやっている! 動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例
<参照先>
・中央労働災害防止協会「製造業安全対策官民協議会」
・厚生労働省「安全衛生優良企業の取組事例 トヨタ自動車株式会社」
トーヨーケム株式会社
樹脂製品の製造を行い、アサヒビール(株)の「生ジョッキ缶」開発を手がけたトーヨーケム株式会社では、新人教育で生じる業務習熟度のバラツキが不安全行動につながると考え、人材育成に取り組む中で以下のような課題を抱えていました。
- OJTのトレーナーによって教え方や内容がバラバラ
- 教える人が業務ノウハウを言語化できず伝わらない
- 教え方の丁寧さにムラがあった
- 文字では表現が難しい業務のマニュアル作成が負担
このような教育課題の解消を目的に、動画マニュアルの活用を製造現場で取り組んでいます。結果的に、マニュアル作成工数が紙の1/2、OJT工数が2/3に削減といった効果につながりました。
新人からも『自立的な学習ができ、動画を見返すだけで業務の振り返りができる』という声が挙がり、不安全行動につながる業務習熟度の改善につながりました。
同社の具体的な取り組み内容は、以下のリンクをクリックしてインタビュー記事をご覧ください。
>>「トーヨーケム株式会社が取り組んだ安全対策事例」を詳しく見てみる
株式会社メトロール
マザーマシンの高精度タッチセンサの製造で、世界トップシェアを誇る株式会社メトロールでは、新人スタッフ向けの安全衛生教育に動画マニュアルを活用し、安全意識の定着と新人教育の効率化に取り組んでいます。
製造現場で使用するアルコールによって、労働災害が発生しないように薬品の扱い方を未経験のスタッフでも理解できるように、分かりやすい教育講座を整備しています。
このような動画マニュアルの整備によって、トレーナーが繰り返し教える時間の削減にもつながり、導入前に1時間近く割いていた教育工数が半分以下の時間まで減っています。
同社の具体的な取り組み内容は、こちらをクリックしてインタビュー記事をご覧ください。
本章でご紹介したように、製造業の安全教育に「動画」「動画マニュアル」が活用されているケースが増えています。次章では、なぜ工場の安全教育に動画マニュアルなのか?その有効性を詳しく解説します。
【補足】工場の安全教育ネタに使える資料や動画
政府や団体が設定している強化月間の情報
政府や業界団体によって、毎月何らかの強化月間を指定していることが多いです。以下はその一例です。
- 12月~1月:年末年始無災害運動
- 4月:春の全国交通安全運動
- 7月:フォークリフト安全週間
このような、安全に関する強化月間や強化週間の情報をもとに、取り組む安全教育のネタとすることができます。現場改善ラボでは、このような安全教育のネタに使える強化月間や運動の年間カレンダーをご用意しています。
以下のリンクをクリックすると、カレンダーの詳細をご覧いただけるのでぜひご活用ください。
厚生労働省が公開している製造業の安全に関する資料
安全教育のネタとして、厚生労働省が公開している資料を活用するのも手でしょう。
工場のことをまだ理解しきれていない、新人が労災に巻き込まれないようにするため、どのように教育すればよいのか?教育のノウハウも知ることができます。
参考資料の一部を以下に記載していますのでご活用ください。
現場改善ラボで公開している専門家による解説動画
私たち現場改善ラボでは、製造業の課題解決に役立つノウハウの一部として、安全教育に関する情報も多数発信しています。
サイト内では、専門家による解説動画も無料で公開しています。各動画で、専門家の方が紹介する内容を安全教育のネタとしてヒントにもなります。
無料でご覧いただける安全関連の解説動画の一覧は以下の通りです。ぜひこの機会に、安全教育のネタや改善に動画をご活用ください。
- 従業員の安全意識が継続する『効果的な安全教育の取組み』
- 【安衛法改正】元労基署長が解説!食品製造業界のための安全衛生教育
- 元労基署長が解説!事故を未然防止するKY活動と4ラウンド法の在り方とは?
- 労働災害を撲滅するヒヤリハット対策の心得
- 効果のあるKYTとは KYTの実情、3つの課題とその解決策
- 品質問題/労災を防ぐ 外国人受け入れ環境の作り方
動画を使って製造現場の安全教育を効果的に行おう【まとめ】
安全教育は、労働者が安全に作業を行うための知識や技術を身につけるための教育を指します。製造業における安全教育の実施は、労働災害を未然に防ぐという意味でも非常に重要です。
安全教育の具体的な内容としては雇入れ時の教育や作業内容変更時の教育、特別教育などが挙げられます。また、職長や危険有害業務従事者への教育も欠かせません。安全教育を通じて、安全衛生の水準を向上させることが期待できます。
製造現場の安全教育を実施する手段として、動画を活用する事例が増えています。動画を使用することで、正しい作業手順など「動き」を視覚的に理解しやすく、不安全行動の撲滅に効果が期待できます。
かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を利用することで、動画編集未経験者でもかんたんに安全教育用の動画が作成でき、従業員の理解度向上を助ける機能も多数あります。
この記事で紹介したtebikiの資料は無料でダウンロード可能です。tebkiを用いた、動画による製造現場の安全教育をご検討してみてはいかがでしょうか?