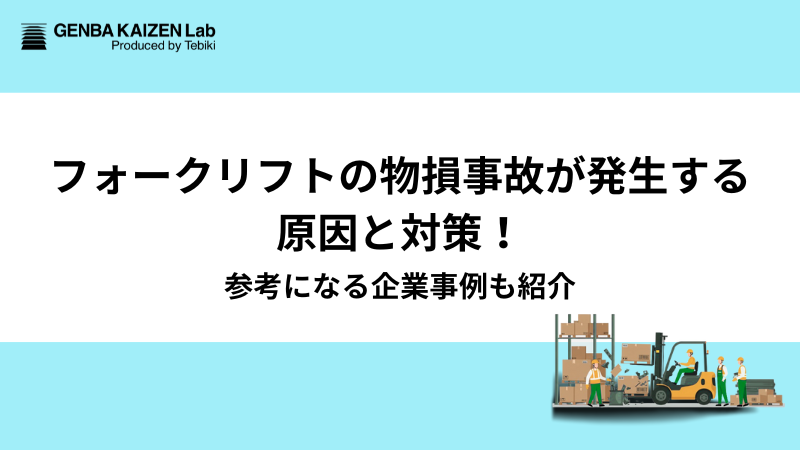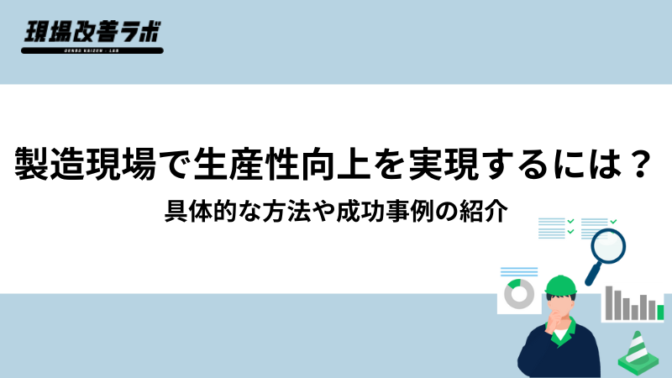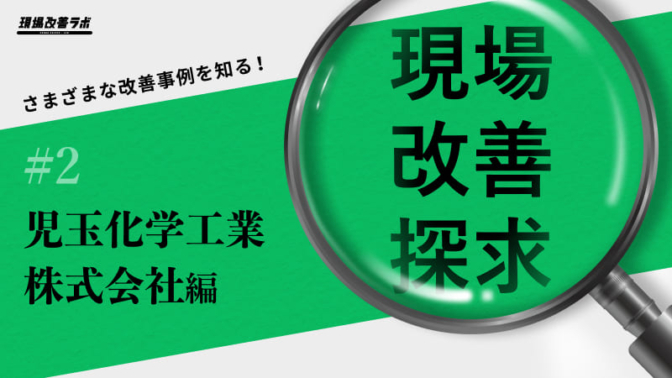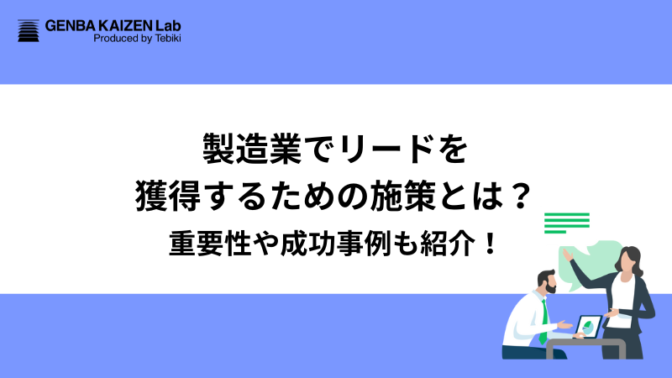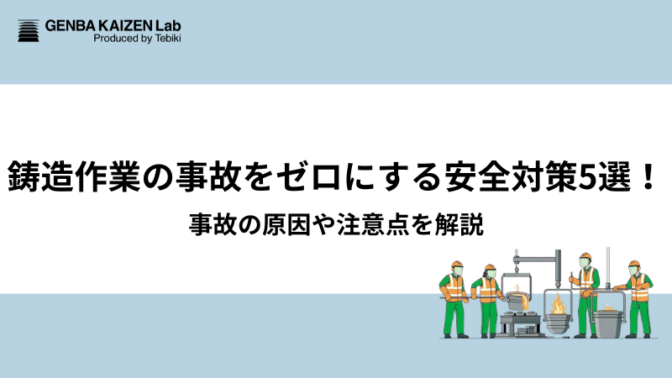かんたん動画マニュアル作成「tebiki現場教育」を展開する現場改善ラボ編集部です。
物流倉庫の現場責任者や安全衛生担当者の方で、このようにお悩みではありませんか?
- 「職場で物損事故が発生したが、どのような再発防止対策をとれば良いかわからない」
- 「物損事故ゼロを達成し、従業員が安心して働ける職場環境を実現したい」
フォークリフトを使う現場において、物損事故は残念ながら避けがたい問題です。とはいえ、小さな物損事故でも放置すれば、重大な人身事故につながる危険性があります。だからこそ、適切な対策を講じ、再発防止に本気で取り組むことが重要です。
そこで本記事では、フォークリフトを運用する物流現場に15年以上従事し、安全衛生管理を担当した経験を持つ筆者が、フォークリフトの物損事故について、発生原因から具体的な防止策までを解説します。
フォークリフトは一歩間違えると労災の温床になるため、安全教育や安全対策が必須ですが、そこで物流現場によく導入されているのが「動画マニュアル」です。「安全」や「危険」を視覚化し、安全を守るための作業/操作手順を見える化する動画マニュアルは、労災の未然防止に成功している多くの現場で導入されつつあります。
詳しくは、資料「動画マニュアルを活用したフォークリフトの安全教育・対策事例」をご覧ください。新人作業員からベテラン社員まで、標準的に安全を守るため打ち手がまとめられています。
>>目指せゼロ災!安全意識を高めるフォークリフトの安全教育・対策事例集を見てみる
目次
フォークリフトの物損事故が発生する原因
物損をはじめ、フォークリフトに起因する事故を未然に防ぐには、まずその原因を知ることが重要です。
ここでは、代表的な原因として以下の4つをご紹介します。
- 前後不注意による壁や荷物への接触
- 「急」がつく運転による荷崩れ
- 爪の角度の誤認による荷物の落下や破損
- 安全に作業できる環境が整っていない
前後不注意による壁や荷物への接触
よくある原因のひとつとして「前後の不注意」、いわゆる確認不足が挙げられます。
たとえば、前方のフォーク作業に集中するあまり後方の確認が不十分になり、後進(バック)した際に置いてあった荷物へ接触し、破損させてしまうといったケースです。
筆者の経験からも、前後の不注意などの確認不足は、ほとんどの事故において要因のひとつになると言えます。
これは「不安全行動」の典型的な例であり、問題なのは「なぜ、わかっているはずの確認を怠ってしまうのか?」という点です。この問いに根本から向き合うためには、人間の行動原理を解き明かす「行動科学」のアプローチが非常に有効です。
「気をつける」といった精神論に頼らず、繰り返される不安全行動を断ち切るための決定的な防止網を構築する方法について、以下の資料で詳しく解説しています。
>>繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網を見てみる
「急」がつく運転による荷崩れ
「急発進」「急ブレーキ」「急旋回」など、「急」がつく運転は事故につながりやすくなります。よくあるのが、荷物を載せたパレットを移動中に勢いよく旋回し、遠心力でパレット上の荷物が崩れてしまう事例です。
このケースは、ある程度フォークリフトの操作に慣れてきた頃に多く見られる傾向があります。多くの場合、スピードの出しすぎや荷物を高く積み過ぎているなど、複数の要因が重なって発生します。
フォークリフトを操作する際のコツを形式知として可視化するのは難しく、各従業員のカンコツに依存している傾向があります。操作のコツを体系的にまとめている以下の関連記事も参考にしてみてください。
関連記事:【経験者が解説】フォークリフト運転上達のコツ!上手い人の特徴とは?
爪の角度の誤認による荷物の落下や破損
フォークの角度が不適切なために荷物を落下・破損させてしまう事例は、特に経験の浅いオペレーターによく見られます。
例えば、商品が高く積まれたパレットをトラックへ積み込む際、マストを倒しすぎた状態でブレーキを踏み、荷崩れを起こしてしまうといったケースです。機種によってはフォークの角度を視認できる印などもありますが、ほとんどはオペレーターの「感覚」に依存しているのが実情です。
安全に作業できる環境が整っていない
オペレーターのヒューマンエラーだけでなく、作業環境そのものに問題が潜んでいることも少なくありません。具体的には、以下のような状況が挙げられます。
- 5S(整理、整頓、清潔、清掃、しつけ)活動が行われていない
- 通路にモノが置いてある
- 作業エリアが狭い
- 照明が暗い など
安全に作業できる環境を整備することも、事故防止において非常に重要です。
フォークリフトの物損事故は人身事故のきっかけになることも
物流現場で、フォークリフトと荷物や設備との接触による物損事故が発生した際、「もし、あれが人だったら重大事故になっていた」という言葉がよく聞かれます。そう言われるのは、物損事故と人身事故の原因が密接にリンクしているからです。
厚生労働省「労働災害統計」によると、フォークリフトに起因する「死傷災害」の原因として大多数を占めるのは、「はさまれ・巻き込まれ」と「激突され」です。
| 事故原因 | 割合(%) |
|---|---|
| はさまれ・巻き込まれ | 35.4 |
| 激突され | 27.3 |
| 墜落・転落 | 11.9 |
| 転倒 | 5.7 |
| 飛来・落下 | 6.0 |
| その他 | 13.7 |
この2つの事故類型で、死傷災害全体の6割以上を占めており、これらは物損事故においても非常によく見られる事故の型です。
つまり、同じような不注意によって接触する対象が「モノ」から「ヒト」に変わるだけで、重大な人身事故に発展する可能性は大いにあると言えます。
この事実は、物損事故の背景にある「不注意」がいかに危険であるかを示しています。
この「不注意」や「うっかり」こそが、労働災害の最大の原因である「ヒューマンエラー」です。物損事故と人身事故の両方を根本から防ぐためには、ヒューマンエラーがなぜ起きるのかを理解し、その発生を未然に防ぐための安全教育が不可欠です。
ヒューマンエラーによる労災を防止するための、効果的な安全教育の進め方について、以下の資料で詳しく解説しています。
>>ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育を見てみる
フォークリフトの物損事故を防ぐために講じるべき対策
フォークリフトの物損事故を防止し、その先にある重大な人身事故を発生させないためにも、多角的な対策を講じることが重要です。
ここでは、人材に対しての教育や管理などのソフト面、機械設備や職場環境などのハード面、それぞれで具体的な対策を紹介していきます。
ソフト(教育/管理)面で講じるべき対策
安全な作業手順を確立し、標準化を進める
「作業手順の標準化」は、実行しやすく効果も出やすい対策方法のひとつです。特に「安全」に焦点を当てて手順書を作成することで、高い事故防止効果が期待できます。
例えば、狭い場所でフォークリフトの作業をする際の安全な運転方法などをまとめた手順書を作成し、作業前に閲覧するなどの仕組みを構築することでフォークリフト作業が標準化され、物損事故が発生するリスク低減につながるでしょう。
実際に、物流企業「株式会社フジトランスコーポレーション」では、フォークリフト作業をはじめ、船舶での貨物の積み卸し作業などに関するマニュアルを整備し、作業の標準化を実現しています。なお、同社の取り組みで特徴的なのは、マニュアルを動画化しているのが特徴です。
同社の事例を詳しく読みたい方は、こちらのインタビュー記事か、標準化を進めるうえでの課題や効果的に進める方法をまとめた以下の資料をご覧ください。
KY活動(危険予知活動)を実施する
「KY活動(危険予知活動)」とは、作業に潜む危険を事前に予測し、予防措置を講じることで労働災害やトラブルを未然に防ぐ活動です。朝礼や作業開始前に、その日の作業における危険ポイントをチームで共有し、対策を確認することで事故防止につながります。
例えば、フォークリフト作業にあたって、どの程度の作業量なのか / 作業員が何人いるのか / 最近どのような事故が発生しているのかなどを周知するようにしましょう。
このように、KY活動は作業前に危険を共有し、安全意識を高めるための非常に有効な手法です。
しかし、毎日実施する中で「いつも同じような危険ばかり挙がる」「議論が盛り上がらない」といった理由から、活動がマンネリ化・形骸化してしまうという課題も多く聞かれます。
この形骸化したKYTから脱却し、作業員の危険感受性を効果的に刺激するための新しい手法として、近年「動画KYT」が注目されています。形骸化を防ぎ、KY活動を「自分ごと」として捉え直すきっかけとなる動画KYTとは何か、その具体的な進め方を以下の資料で詳しく解説しています。
>>労災ゼロ!形骸化したKYTから脱却する動画KYTとはを見てみる
物損事故事例を収集し、共有/再発防止策を考える
社内で発生した物損事故は、必ず事故報告書として作成・保管しておきましょう。
それらの事故事例データを収集・共有することで、従業員一人ひとりが危険箇所を再認識できます。また、その事例を元に全員で再発防止策を考え、意見交換する場を設けるのも効果的です。
また、フォークリフトの物損事故につながるリスクのある危険な操作をNG例として動画マニュアルに集約し、活用するのも良い共有方法の1つと言えるでしょう。
※「tebiki現場教育」で作成しています。
動画でNG例操作の事例を解説することにより、OJTや紙のマニュアルと比べて視覚的に情報を取得できるので、より学びが得られやすくなるでしょう。物流業界における安全教育に関するサンプル動画や他社の事例などをチェックしたい方は、以下のリンクをクリックして資料をご覧ください。
>>「物流業の事例から学ぶ|動画マニュアルを使った安全教育の取り組みと成果」を見てみる
指差呼称を徹底する
「指差呼称」とは、作業対象を指で差し、その名称と状態を声に出して確認することで、ヒューマンエラーを防ぎ安全性を高めるための安全確認行動です。
この指差呼称を徹底することで、確認作業が形骸化するのを防ぎ、オペレーターが落ち着いて作業に臨めるようになります。そのため、KY活動(危険予知活動)の一環として、幅広い企業で実施されています。指差呼称の正しいやり方や定着させる方法などについては、以下の関連記事もご覧ください。
関連記事:【事例あり】指差呼称とは?効果はある?正しいやり方や定着させる教育方法
ハード(設備/環境)面で講じるべき対策
障害物センサーを活用する
「障害物センサー」とは、車両の進行方向や後方にいる人や物を検知し、音や光で警告したり、走行を制御したりすることで衝突事故を未然に防ぐ安全装置です。
メーカーによっては最新機種に標準装備されているほか、後付けできる汎用品も販売され始めています。まだ広く普及はしていませんが、乗用車の先進安全機能のように「あって当たり前」になる時代も、そう遠くはないかもしれません。
5S活動を実施する
「5S活動」とは、整理・整頓・清掃・清潔・しつけの5つで構成される、トヨタ生産方式から生まれたとされる職場環境の改善手法です。この5S活動を徹底することは、効果的なフォークリフトの物損事故対策となります。
例として「整理」を見てみましょう。
「整理」には、不必要な物を処分し、スペースを確保するという意味が含まれます。例えば、倉庫内にある1年以上使用していないものを処分、または別の保管場所に移動させることで新たなスペースが生まれます。それによりフォークリフトの動線を広げることができ、壁や荷物への接触リスクを低減できます。
5S活動について詳しく知りたい方は、大手企業の生産現場を中心に5S活動の指導を実施してきた専門家による動画の視聴がおすすめです。5S活動の具体的な実践方法や5S活動を定着させて、生産性を上げる方法など、体系的に5S活動を学べる内容ですので、以下の画像をクリックして動画をご視聴ください。
>>【視聴無料】「生産性を高める5S活動 正しい運用に欠かせない「重要なS」とは」を見てみる
フォークリフトと作業者の導線を分ける
作業動線の見直しは、効果的な人身事故対策であると同時に、物損事故の防止にもつながります。
具体的な方法としては、まず白線などで作業者の歩行エリアを明確に区分し、フォークリフトの走行ルートがその歩行エリアに干渉しないよう、倉庫全体のレイアウトを見直します。
双方が物理的に近づくことのないレイアウトを設計することで、接触のリスクそのものを排除できるのです。
フォークリフトの具体的な安全対策の進め方や、現場の意識を高めるための取り組みを、以下の資料で解説しています。ぜひ、貴社の事故防止にお役立てください。
>>目指せゼロ災!安全意識を高めるフォークリフトの安全教育・対策事例集を見てみる
フォークリフトの物損事故防止に取り組む企業の事例
この章では、フォークリフトの物損事故対策における先進的な実例をご紹介します。
港湾運送事業や倉庫業など、多岐にわたる物流サービスを提供する総合物流企業「株式会社フジトランスコーポレーション」では、「動画」を活用した安全教育を実践しています。
同社では、人の入れ替わりが激しくOJTの質がばらつくという課題に対し、動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を導入。特に安全衛生推進部が中心となり、動画を用いて安全教育を標準化したことで、講師による指導内容の差を解消しました。
この取り組みにより、従業員間の認識のズレを防いで作業品質の均質化を実現したほか、外国人労働者への教育や問い合わせ対応も効率化するなど、全社的な働き方改革につながっています。同社の事例を詳しくチェックしてみたい方は、以下のインタビュー記事をご覧ください。
インタビュー記事:働き方改革の手段としてtebikiを活用。複数の部門で工数の効率化を実現!
安全意識の向上につながる物流現場の教育ツール
事例で紹介した株式会社フジトランスコーポレーションでは、フォークリフトをはじめ物流現場全般の安全教育に対して、動画マニュアルを活用した先進的な取り組みが実施されています。
動画を活用することで、紙マニュアルやOJTとは違い、実際のフォークリフトの作業風景を見て学べるのが大きな特徴。閲覧する人によっても作業認識に相違するリスクの低減が見込めます。
同社で活用されている物流業界に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」では、普段のOJTをスマートフォンで撮影するだけでかんたんに動画マニュアルを作成することが可能です。

【tebiki現場教育サービス説明資料】より抜粋
フォークリフトの物損事故の対策、現場全体の安全意識向上に向けて「tebiki現場教育」の導入を検討してみたい方は、以下のサービス資料もあわせてご覧ください。下のリンクをクリックすると資料をダウンロードできます。
【補足】フォークリフト物損事故の報告書テンプレート
フォークリフト事故報告書は、事故の客観的な事実を記録し、原因を正確に分析するための基礎資料です。
効果的な再発防止策を策定し、社内で共有することで全従業員の安全意識を向上させ、同種の災害を防ぐために不可欠なものです。しかし、いざという時にどのような項目を記載すればよいか迷うこともあるでしょう。その際は、以下の「報告書のテンプレート」をぜひご活用ください。
まとめ
フォークリフトを使用して作業するうえで、避けては通れない物損事故は、本記事で紹介したソフト面とハード面から多角的に対策を講じることで、そのリスクを最小限に抑えることができます。
そして、一つひとつの物損事故を防ぐことが、その先にある重大な人身事故の防止に直結するのです。
本記事で紹介した株式会社フジトランスコーポレーションのように「tebiki現場教育」を導入すれば、効率的に従業員に物損事故対策を講じることができます。動画マニュアルを簡単に作れる「tebiki現場教育」についてより詳しく知りたい方は、以下の画像をクリックしてぜひサービス資料をご覧ください。