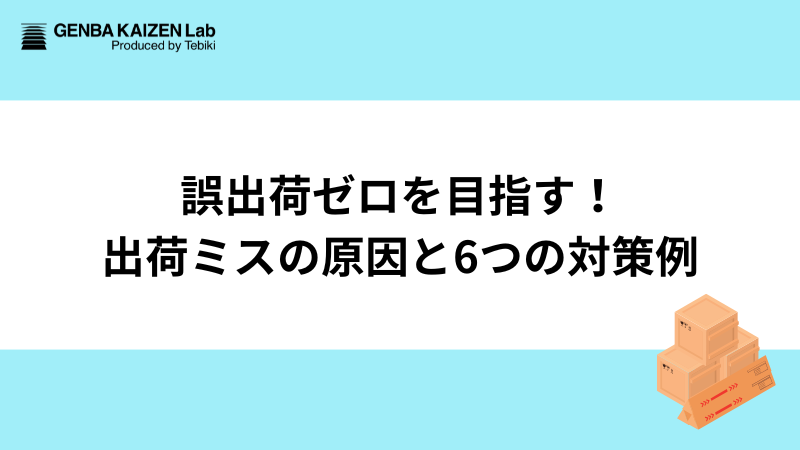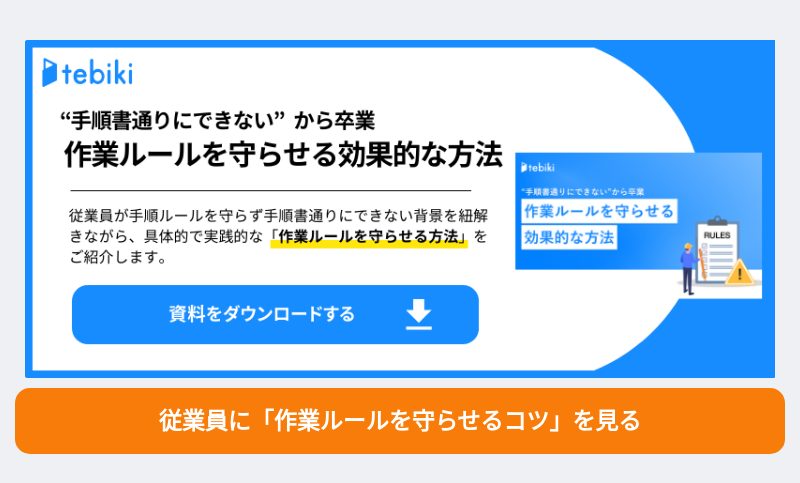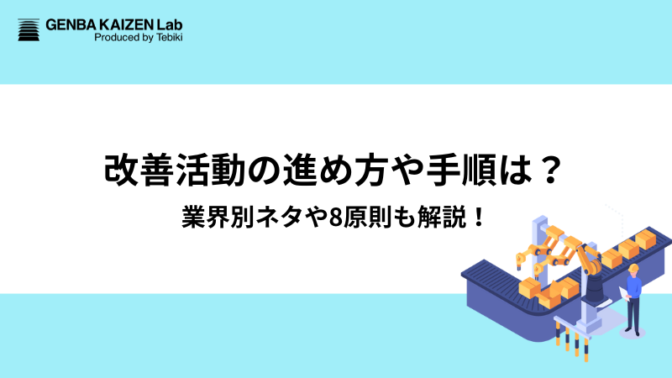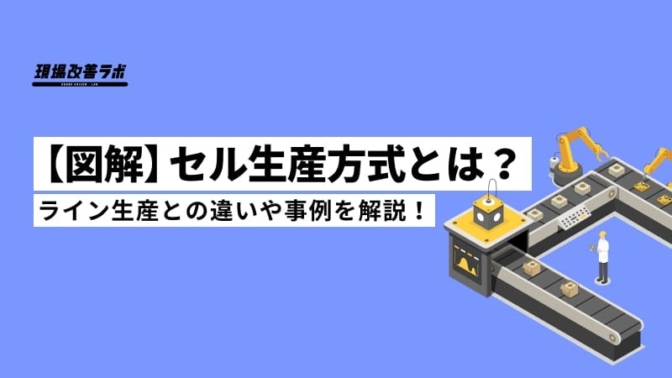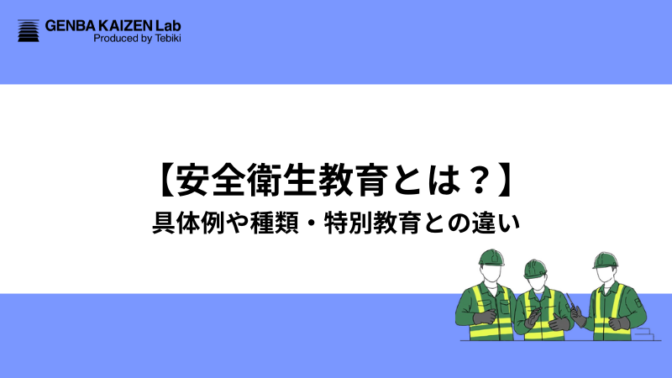物流現場のかんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
誤出荷は顧客からの信頼を失うだけでなく、返品や再出荷などの追加対応によって企業の利益を圧迫し、ブランドイメージの低下にもつながります。しかし多くの現場では「注意して作業すれば防げる」と考えがちで、根本的な原因が見過ごされがちです。
誤出荷を根本から減らすには発生のメカニズムを正しく把握し、作業手順やルールを誰でも守れる形に整えることが重要です。本記事では出荷ミスが起こる原因の解説に加え、現場で実際に成果が出た改善策も紹介しています。
より具体的な対策や事例を知りたい方は、下記「誤出荷ゼロへ!ヒューマンエラーによるピッキング作業ミスをなくす具体的な対策と改善事例」の資料も併せてご参照ください。
>>誤出荷ゼロへ!ヒューマンエラーによるピッキング作業ミスをなくす具体的な対策と改善事例を見る
目次
誤出荷はなぜ起きる?よくある原因
誤出荷とは、商品や数量、発送先などを間違えて出荷することをいいます。読み方は「ごしゅっか」で、大量の在庫を保管する物流倉庫や配送センターで起きる代表的なミスの1つです。
誤出荷の発生には必ず原因があります。なぜ出荷ミスが起きているのか、具体的な対策を考える前に誤出荷の原因を明らかにすることが大切です。
ここでは誤出荷のよくある原因を3つ紹介します。
倉庫内の動線や照度など作業環境の問題
動線が悪い倉庫では出荷する商品を集めるためにあちこち歩き回らなければならず、無駄な動きが増えることでピッキングミスや商品の取り違えが起こりやすくなります。出荷指示とは異なる商品や数量でピッキングし、出荷検品時のチェックでも気づけなかった場合は誤出荷となってしまいます。
また、適切な照度や温度が保たれていない、十分な作業スペースが確保されていないなど、倉庫内の環境整備が不十分な場合にはミスが発生しやすく、作業員の安全や健康、作業品質にも影響が及ぶことに注意が必要です。十分な作業スペースがない場合、商品の仮置きや仕分けが困難になり、誤って異なる商品を同梱してしまうなどのミスが発生しやすくなるからです。
ピッキングミスや数量間違いの未然防止は誤出荷対策において重要なので、以下の記事も参考にしてピッキングミスの改善案も検討すると良いでしょう。
関連記事:ピッキングミスや数量間違いが多い人の特徴と9つの対策!改善事例もあわせて紹介
在庫管理システムへの転記ミスなどツール側の不備
誤出荷はツール側の不備によって発生することもあります。例えば在庫管理システムへの転記ミスにより、システム上の在庫数と実際の在庫数が一致していない場合、誤った商品を出荷するリスクが高まります。
また、受注管理システムへの入力ミスもよくある誤出荷原因の1つです。通常、受注と出荷指示は紐付くため、受注入力の時点でミスがあると誤った出荷指示を行い、誤出荷につながってしまいます。経験年数の長い倉庫作業員がピッキングをするときはミスに気づくこともありますが、基本的には出荷指示に従ってピッキングや出荷検品を行うため、受注入力のミスはそのまま誤出荷に直結するケースが多くなります。
作業員の確認不足や思い込みなどのヒューマンエラー
作業員によるヒューマンエラー(人為的ミス)も誤出荷の主な原因の1つです。例えばピッキング時と出荷検品時のダブルチェックを怠ったり、商品は間違いなくても付属品やカタログなどの同梱物を入れ忘れていたりと、作業員の確認不足によって誤出荷が起きてしまうケースがあります。
送り状伝票の貼り間違いや住所・宛名の書き間違いによる誤出荷も多く、特に手書きで伝票を作成している場合にはミスが起こりやすくなります。
また、作業員の思い込みによって誤出荷が発生するケースも少なくありません。例えばほとんどの顧客から「1箱」の注文が入る商品があった場合、まれに「2箱」の注文が入っても作業員の思い込みで「1箱」で出荷してしまうことがあります。これは出荷業務に慣れてきた作業員に起こりがちなヒューマンエラーです。
こうしたヒューマンエラーの未然防止策は「ミスが起きないように注意する」というような意識レベルの対策では成り立たず、具体的かつ現実的な対策が必要です。つまり、ヒューマンエラーの発生メカニズムを知り、それを除去する打ち手を模索することが望ましいです。その打ち手について解説されているセミナー動画「人に起因する品質不良の未然防止と具体的な対策」もご覧いただくと、ヒューマンエラー未然防止策のアイディアがいくつか浮かんでくるはずです。
>>>「ヒューマンエラー未然防止策」を無料セミナー動画で学ぶ
外国人労働者やスポットワーカーが増えているから
物流現場に限らず、製造業や小売業などあらゆるデスクレス領域では、外国人労働者や派遣社員、短期アルバイトの従業員等、多様化した雇用形態の作業員が増えています。こういった多様化した現場で均一化した作業品質を確保するのは非常に難しく、結果的に作業ミスが増え、誤出荷の原因になるのです。
例えばEC専門の総合物流会社「ASKUL LOGIST株式会社」も、同様の課題を抱え、標準化や安全教育に悩まされていました。
これまで障がい者の方だけではなく、短時間勤務者や外国籍スタッフといった多様な方の採用を行ってきました。従来とは勤務時間や国籍も異なるなど、多様な作業者が増えてきたことで、物流プロセスがネック工程とならないように標準化を進めていましたが、同時にこのような方たちのケアやフォローをより必要とするという現場の負担面も悩んでいました。
最終的に同社は「教育体制」を改革し、多様化する現場の作業品質を向上させることに成功しています。詳しい事例は以下のリンクからご覧いただけます。
事例インタビュー:多様な人材を抱える現場で『標準化』と『安全教育』を実現したASKUL LOGIST株式会社
誤出荷が発生しやすいタイミング
誤出荷が起こりやすいタイミングは主に3つです。
- 入荷~保管
- ピッキング
- 目視による出荷検品
これらのタイミングでは作業者の注意力や経験に頼る部分が多く、ヒューマンエラーが発生しやすくなります。しかし、個人の頑張りだけに頼る改善には限界があります。作業手順やルールを明確化し、誰でも同じ品質で作業できる仕組みを整えることが、誤出荷ゼロへの近道です。
こうした根本的な対策や、実際に現場で成果を上げた改善事例をまとめた資料「誤出荷ゼロへ!ヒューマンエラーによるピッキング作業ミスをなくす具体的な対策と改善事例」もご用意しています。現場改善のヒントを探している方は、是非参考にしてください。
>>誤出荷ゼロへ!ヒューマンエラーによるピッキング作業ミスをなくす具体的な対策と改善事例を見る
入荷〜保管
入荷から保管にかけてのタイミングは、誤出荷が起きやすいタイミングの1つです。例えば、入荷した商品を本来のロケーション(棚番など)とは異なる場所に保管し、作業員が格納ミスに気づかないままピッキングしてしまうようなケース。
ピッキング時の確認が不足しているのは言うまでもありませんが、入荷の時点で正しいロケーションに保管していれば防げたミスといえます。特に経験の浅い作業員は商品ごとのロケーションを細かく把握できていないケースが多く、倉庫内のロケーション管理が不足している場合に起こりやすくなります。
ピッキング
誤出荷が最も発生しやすいタイミングが商品のピッキング作業時です。紙の出荷指示書をもとにピッキングする際、例えば一行読み飛ばして必要な商品を取り忘れたり、規格を読み間違えて誤った商品を取ってしまったりと、作業員の確認不足や思い込みによるピッキングミスが起こりやすくなります。
この後の出荷検品時にミスが見つかるケースが多いものの、ピッキング時のミスをいかに防げるかが重要です。
ピッキングミスに限らず現場作業員のヒューマンエラーを根本から防ぐには、作業手順やルールを誰でも守れる形に仕組み化することが重要です。こうした視点からピッキングミスの原因分析や具体的な改善策、さらに現場で成果を上げた事例までをまとめた資料も以下にご用意しています。
>>誤出荷ゼロへ!ヒューマンエラーによるピッキング作業ミスをなくす具体的な対策と改善事例を見る
目視による出荷検品
目視による出荷検品も、誤出荷が起きやすいシチュエーションです。小規模な倉庫では、目視による出荷検品を行っているところも少なくありません。
基本的には出荷指示書に載っている規格と、商品本体に記載された規格を見比べながら確認していきますが、出荷業務に慣れている作業員は商品の外観だけで判断して検品を終わらせてしまうことがあります。その結果、同じ外観でも色やサイズの異なる商品がある場合、細かい確認を怠ったことで誤出荷につながってしまいます。
目視による課題に対する解決策は、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
関連記事:目視検査の課題はどう解決する?原因や4つの対策を紹介
誤出荷が発生することで生じる影響
誤出荷は企業にさまざまな悪影響をもたらし、その数が増えれば増えるほど損失が膨らんでいきます。具体的に何が起きるのか、誤出荷によって生じる影響を紹介します。
誤出荷率の増加による物流コストの悪化
誤出荷が発生すると、顧客へのお詫びの連絡、返品受付、返品された商品の検品・再仕分け、正しい商品の再発送、場合によっては代替品の提案、そして在庫差異の確認といった、さまざまな対応が必要になります。
誤出荷が起きる度にこれらの対応を講じなければならないため、頻発すると、本来発生しないはずの人件費や配送料が増加し、物流コストを押し上げ、企業の利益を圧迫してしまいます。
返品率や顧客満足度への影響
商品の誤出荷は返品率の上昇や顧客満足度の低下を招きます。誤った商品が届いた場合、顧客は発送元への連絡や返品・交換の手続きを行う必要があり、その手間が企業への不満につながります。特に発送先の宛名や住所を間違えた場合は個人情報の漏洩リスクを伴い、顧客からの信頼を大きく失う事態にもなりかねません。
実在庫との差異が生じる
誤出荷は、システム上の在庫数と実在庫数の差異を生じさせる原因となります。例えば、システム上では在庫があることになっている商品が、誤出荷によって実際には不足している場合、顧客から注文を受けてもすぐに出荷することができず、販売機会の損失につながります。
反対に、実在庫が多い場合は過剰在庫の原因となり、過剰在庫は、商品価値の低下、保管スペースの圧迫、保管コストの増加、ひいては廃棄ロスにつながる可能性もあります。
誤出荷を防止する代表的な6つの出荷ミス対策
ここからは、誤出荷を防ぐための代表的な対策を6つ解説します。対策は以下のとおりです。
- 作業環境とレイアウトの改善
- システム導入による誤出荷防止
- ポカヨケなどヒューマンエラーを抑制する仕組み作り
- 従業員に対する品質教育の実施
- 標準作業の明確化と現場への徹底
- 経緯を説明する報告書の作成
ちなみに誤出荷の未然防止策を見出す場合、前提として、出荷ミスが起きる「原因」を明確にすることが重要です。根本的な原因が明確になって初めて、対策の立案が可能になるからです。
根本的な原因の究明に有効な分析フレームワークとして「なぜなぜ分析」があります。『なぜ』を繰り返し問いかけることで、問題の根本原因に迫り、再発防止につながる本質的な対策を立案できます。
なぜなぜ分析の実践的な方法をや活用事例について知りたい方は、資料「【事例で解説】トヨタ流「なぜなぜ分析」の実践方法とポイント(解説動画あり)」もあわせてご覧ください。以下の画像をクリックしてダウンロードできます。
では、誤出荷を防止する代表的な対策方法を6つ紹介します。
作業環境とレイアウトの改善
誤出荷を防ぐためには倉庫内の作業環境を整える必要があります。出荷頻度の高い商品のロケーション(保管場所)を倉庫の出荷口近くに設置する、台車やフォークリフト等の運搬機器を効率的に動かせるよう十分な通路幅を確保するなど、実際にピッキングを行う現場担当者の意見も聞きながら倉庫内の動線を工夫しましょう。倉庫内の照明や空調にも気を配り、作業員が快適に働ける環境を整えることが重要です。
また、倉庫内のレイアウトを見直して広い作業スペースを確保することで、「ピッキング済みの商品」と「出荷待ち状態の商品」が混ざる仕分けミスを防止できます。作業環境の改善は出荷ミスの予防とともに、仕事の効率化や作業員の負担軽減にもつながる対策です。
システム導入による誤出荷防止
誤出荷防止システムの導入は出荷業務のミスを防ぐ有効な対策となります。具体的には以下のようなシステムを活用できます。
| システム名 | 概要 |
|---|---|
| RFID(無線周波数識別) | タグに埋め込まれた情報を無線で読み取るシステム |
| ハンディターミナル バーコードリーダー | 商品と出荷指示書のバーコードを照合するシステム |
| デジタルピッキング | デジタル表示器でピッキングを効率化するシステム |
| オートソーター | 商品を自動で仕分けし、配送先ごとに振り分けるシステム |
| WMS(倉庫管理システム) | 在庫・入出荷・作業進捗をデータで管理するシステム |
目視による入荷処理やピッキング、出荷検品を行っている場合は、これらのシステムを導入することで効率的かつ精度の高い作業が可能となります。
ポカヨケなどヒューマンエラーを抑制する仕組み作り
ポカヨケとは、ヒューマンエラーによって生じるミス(ポカミス)を避けることです。倉庫業務においては商品の入荷から保管、ピッキング、検品、出荷までのどの工程においても、作業員の確認不足や思い込みによるミスが発生する可能性があります。
製造業寄りのお話にはなりますが、参考情報として、ポカヨケ対策が分かる記事「製造業のポカヨケ対策を解説!1番大切な対策や事例、語源も解説」もご覧いただくと理解が深まります。物流現場にも通じるヒントがまとめられているので、あわせてご覧ください。
また、ヒューマンエラーを抑制するには、先述したシステム導入によって目視や手入力などのアナログな作業を切り替えたり、ピッキングと出荷検品の担当者を分けてダブルチェックを行ったり、マニュアルを整備して標準作業を徹底するよう働きかけたりするのが効果的です。ミスが起こることを前提に、ヒューマンエラーを減らすための仕組みを前もって作っておきましょう。
ポカミス(ヒューマンエラー)再発防止の具体的な仕組みづくりについて知りたい方は、セミナー動画「各種事例に学ぶヒューマンエラーの原因分析と対策法」もあわせてご覧ください。物流領域の勤務経験がある専門家が詳しく解説しています。
従業員に対する品質教育の実施
誤出荷を防ぐには従業員に対する品質教育も欠かせません。出荷ミスが顧客と自社に与える影響や未然に防止する重要性を理解させたうえで、倉庫の作業員には以下のような教育を実施しましょう。
- 正しいピッキング手順(ピッキングリストの見方、商品の取り扱い等)
- 導入しているシステムの正しい使い方(ハンディターミナル、WMSなど)
- 適切な梱包材の選定方法と梱包手順
- 出荷検品時の確認ルールと手順
- イレギュラー発生時の対応(欠品、商品違い、破損など)
- 5S活動(整理、整頓、清掃、清潔、躾)の徹底
フルタイムで働く作業員だけでなく、パートやアルバイトなどの短期雇用者にも作業開始前に研修を実施し、一人ひとりの作業精度を向上させることが求められます。
作業品質を均一化するには、属人的な作業を見える化し、どの現場担当者でも適切な作業品質を保てるように現場を改善しなければなりません。属人化解消のための教育手法として参考になるセミナー動画「属人的な教育が引き起こす品質不良」もあわせてご覧いただくと、品質教育のヒントが得られるはずです。
下のリンクをクリックすると、動画視聴ページに遷移します。
>>>セミナー動画「属人的な教育が引き起こす品質不良」を見てみる
さらに、実際に発生した誤出荷事例をもとに振り返りを行い、今後の目標を標語にして倉庫内に掲げるなど、あらためて出荷ミス削減への意識を共有するのも有効な対策です。誤出荷の原因や反省点、今後の取り組みなどを共有することで、出荷業務に関わる全員が品質意識を高く持ち、再発防止や業務改善に主体的に取り組む姿勢が養われます。
標準作業の明確化と現場への徹底
現場の作業員が標準作業を守ることが出荷ミス防止に直結します。そのためには、倉庫業務の作業手順やルールを統一化したうえで、入荷から出荷までの各工程における標準作業をマニュアル化し、全員が同じ基準で業務を行える体制を整える必要があります。
しかし、マニュアルの整備は非常に工数が必要です。また、せっかくマニュアルを整備しても「文字が多すぎて見られない」という現場も多いです。標準作業手順書を整備するにはいくつかポイントがあるので、そのポイントがまとめられた資料「“手順書通りにできない”から卒業!作業ルールを守らせる効果的な方法」を参考にすることをおすすめします。
マニュアル運用後も指導者は定期的に現場確認を行い、標準作業が守られているかをチェックすることが重要です。
一般的に標準作業とは「無駄のない効率的な作業」を指し、これを守れば誰もが同程度の作業品質を確保できます。標準作業を徹底させれば業務効率と作業品質の両方が向上し、誤出荷のリスクを最小限に抑えられます。
経緯を説明する報告書の作成
誤出荷の経緯を説明する報告書は、出荷ミスの再発を防ぐ対策書として有効活用できます。誤出荷が発生した場合には報告書を作成・共有することで、出荷業務に関わる全員が問題点を把握し、再発防止に向けた品質意識の向上につなげられます。
報告書は問題の経緯や原因を明らかにするための書面であり、懲罰目的で作成するものではありません。インターネットを使って報告書の例文を検索することもできますが、あくまで参考程度とし、誤出荷発生の経緯や原因を事実に即して正確に記載させることが大切です。
誤出荷の発生をゼロに近づける考え方
誤出荷の発生をゼロに近づけるには、ヒューマンエラーによる出荷ミスをどれだけ減らせるかがカギとなります。誤出荷の多くは標準作業を守らなかった場合に発生することを念頭に置き、標準的な作業手順やルールをまとめたマニュアルを共有したり、出荷業務に関わるすべての従業員を対象に勉強会を実施したりする必要があります。誤出荷の防止はシステム導入だけでは不十分で、全員に標準作業を徹底させるための人材育成が不可欠です。
ただし、倉庫の作業員は短期雇用者や外国人労働者も多く、入場時の教育に手間がかかったり正確な情報共有が困難になったりするケースも少なくありません。このような場合は出荷業務の「動作」を動画で可視化し、実際の作業の様子を見てもらうのが効果的です。文字や言葉では説明しにくい業務も、動画マニュアルであれば正しい作業方法や手順を効率的に伝えることができます。
例えば物流企業の「ソニテック株式会社」は以前、作業手順の教育がOJT教育やマンツーマン指導に大きく依存していた結果、作業内容の正確な伝達の難しさや指導者の教え方のバラつきが原因で、たびたび作業ミスが発生していました。そこで「正確な作業を動画で見える化」し、現場全体の標準化を実現したのです。
動画マニュアルの例として、総合物流企業の「三井物産グローバルロジスティクス株式会社」で実際に作成・使用されている動画マニュアルが良い例です。同社では梱包作業の丁寧に動画マニュアル化し、正社員に限らず、パートタイムの従業員や外国人労働者でも作業手順が分かるよう、教育体制を整備しています。以下の動画は実際に同社で作成・編集された動画マニュアルです。
▼包装作業を動画マニュアル化した事例▼
現場従業員が「tebiki」で作成
このように動画マニュアルは「誰が見ても同じ解釈(誰が説明しても同じ教育内容)」になるので、標準作業が徹底される現場づくりに有効な手段です。動画マニュアルによって現場教育を推進する方法については、以下の資料「動画マニュアルで現場の教育をかんたんにする方法」で詳しくまとめられているので、あわせてご覧ください。
まとめ
誤出荷が起きる主な原因には、作業環境の問題やツール側の不備、ヒューマンエラーがあります。誤出荷が発生すると物流コストの悪化や顧客満足度の低下などのさまざまな悪影響が及ぶため、ミスが起こる原因を特定したうえで、倉庫内レイアウトの改善や品質教育の実施といった適切な対策を講じて未然防止に努めることが重要です。
特に作業員の確認不足や思い込みによるヒューマンエラーは、出荷業務の標準作業を正しく運用していないことが原因で発生します。出荷業務のような「動作」を効率的に伝えるためには、動画マニュアルによる現場教育を取り入れるのが効果的です。なかでも、物流現場に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」は、現場従業員がスマホ1つで撮影し、パソコンでのかんたんな編集で動画マニュアルが作成できます。
tebikiの詳しい機能や活用事例がまとめられた資料は、以下の画像をクリックしてダウンロードが可能です。
こうしたツールを活用しながら標準作業を徹底させ、ヒューマンエラーによる出荷ミスを減らしていきましょう。