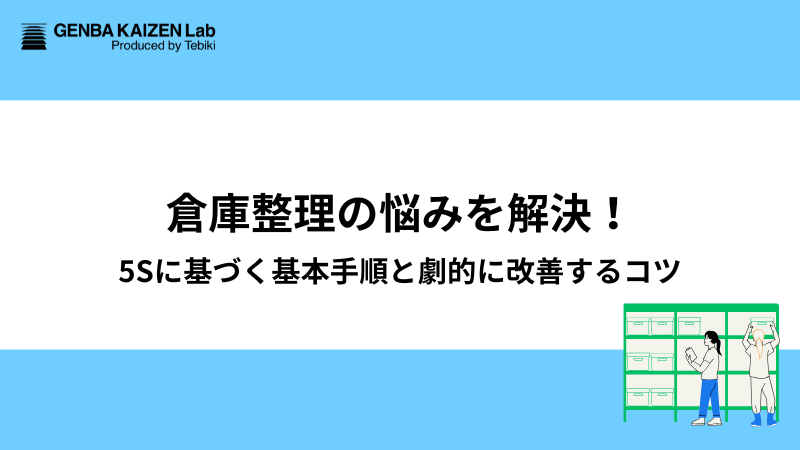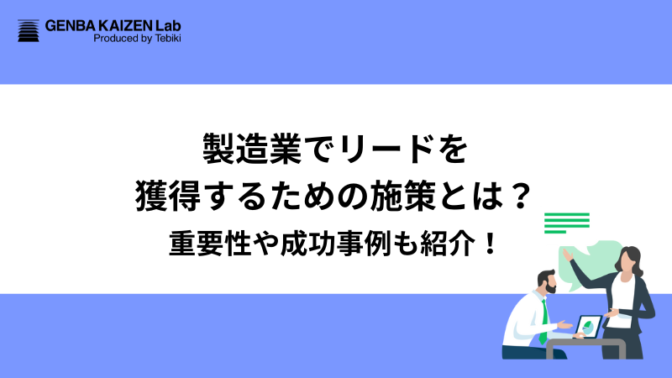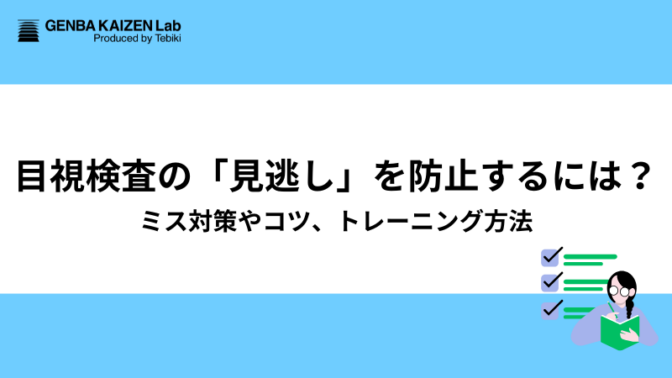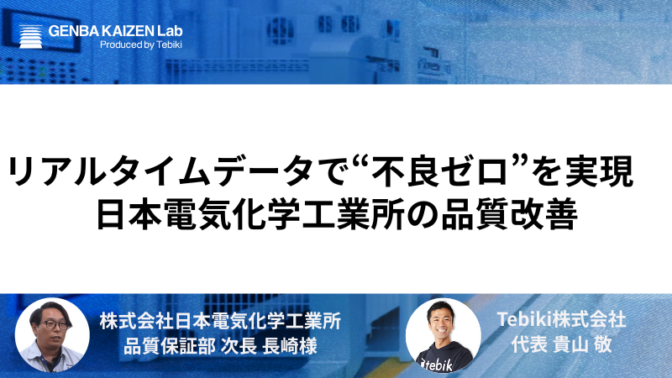かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
倉庫の乱雑さは、日々の業務効率を低下させるだけでなく、思わぬ事故や品質問題の原因にもなりかねません。
そこで本記事では、倉庫整理の重要性と具体的な手順を解説します。この記事を読めば、倉庫整理を実現するための具体的なアクションプランが見えてくるはずです。
本記事のほか、5S活動を「表面的な取り組み」ではなく「文化」として浸透させるためのコツや現場で実践できる具体的な取り組み例についてまとめた資料もご用意しておりますので、是非ご覧ください。
>>【事例つき】5S3定が浸透しない現場の共通点3つと仕組み化の「核」について見る
目次
なぜ倉庫整理は重要なのか?放置するリスクと5つのメリット
整理されていない倉庫には、見過ごせない多くのリスクが潜んでいます。
- 作業効率の低下
- 事故リスクの増加
- スペースの浪費
- 在庫管理精度の低下
- 品質問題の発生
これらのリスクは、具体的には探し物による時間のロス、床の障害物や不安定な荷積みによる転倒・荷崩れといった労働災害、不要な在庫による保管スペースの圧迫、在庫数の不一致、保管環境の悪化による製品劣化などを引き起こします。これらは結果的に、生産性の低下やコスト増加、さらには顧客満足度の低下にも繋がりかねません。
一方で、倉庫整理にしっかりと取り組むことで、これらの問題を解決し、多くのメリットを得ることができます。
- 生産性の向上
- 安全性の向上
- スペース効率の改善
- 在庫精度の向上
- 従業員のモチベーション向上
倉庫を整理整頓することで、探し物の時間がなくなり、作業動線が改善され、業務全体のスピードアップが期待できます。また、通路が確保され安全な状態が保たれることで事故リスクが低減し、不要品を処分し保管方法を見直すことで限られたスペースを有効活用できます。
さらに、在庫管理が容易になり精度が向上するだけでなく、清潔で働きやすい環境は従業員のストレス軽減やモチベーション向上にも貢献します。
倉庫整理を成功させるための基本「5S」とは?
倉庫整理を進める上で、非常に重要となる考え方が「5S」です。5Sとは、製造業や物流業などの現場改善活動で広く用いられているスローガンであり、「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「躾」の頭文字をとったものです。
単なる「片付け」とは異なり、効率的で安全な職場環境を維持・改善していくための活動全体を指します。
| 整理 (Seiri) | 「要るモノ」と「要らないモノ」を明確に区別し、不要なモノを処分すること。スペースを確保し、必要なモノを探しやすくする第一歩です。 |
| 整頓 (Seiton) | 必要なモノを、決められた場所に、誰でもすぐに取り出せるように置き、表示すること。探すムダを徹底的になくします。 |
| 清掃 (Seiso) | 職場や設備をきれいに掃除し、点検すること。ゴミや汚れがない状態を保つだけでなく、異常や不具合を早期に発見することにもつながります。 |
| 清潔 (Seiketsu) | 整理・整頓・清掃(3S)の状態を維持し、誰が見てもきれいで衛生的な状態を保つこと。3Sを徹底・維持する仕組みづくりも含まれます。 |
| 躾 (Shitsuke) | 決められたルールや手順を正しく守り、習慣化すること。従業員一人ひとりの意識改革と、改善活動の定着を目指します。 |
この5つのステップを順番に進めることで、場当たり的ではない、体系的で持続可能な倉庫環境の改善が実現します。
5S活動の具体的な理解や実践方法は、無料セミナー動画「生産性を高める5S活動 正しい運用に欠かせない「重要なS」とは」で詳しく解説されています。5Sを自社の現場にどう応用するのかイメージが湧くようになっているので、お時間がある際に視聴してみてください。
>>>無料セミナー動画「生産性を高める5S活動 正しい運用に欠かせない「重要なS」とは」を視聴してみる
【実践編】倉庫整理の具体的な手順4ステップと成功のコツ
それでは、5Sの考え方に基づき、倉庫整理を具体的にどのように進めていけばよいか、4つのステップに分けて解説します。それぞれのステップで成功のためのコツも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
ステップ1:【整理】不要なモノを徹底的に処分する
最初のステップは、倉庫内にあるすべてのアイテムの中から「要るモノ」と「要らないモノ」を仕分ける「整理」です。
具体的な進め方
- 判断基準の設定
- 「赤札作戦」の実施
- 不要な物の処分
まず、「要る・要らない」の判断基準を明確にすることが重要です。「過去1年間使用していないモノは不要」「〇ヶ月分の在庫があれば十分」「破損・劣化しているモノは不要」など、自社の状況に合わせた具体的な基準を設定し、部署やチームで共通認識を持つことが成功の鍵となります。
次に、判断に迷うモノや不要と思われるモノには「赤札」と呼ばれる札を貼る「赤札作戦」が効果的です。赤札に品名、発見場所、発見日、判断理由などを記入し、一定期間(例:1ヶ月)様子を見て、期間内に使用されなかったり必要性が証明されなかったりしたモノは処分対象と判断します。
最後に、処分対象となったモノは、ルールに従って速やかに処分します。単に廃棄するだけでなく、売却、リサイクル、他部署への譲渡など、環境やコストに配慮した方法も検討し、産業廃棄物処理法などの関連法規を遵守しながら進めましょう。
こうしたムダの削減はあらゆる業務改善において重要ですが、ムダの削減に基づいた業務効率フレームワーク「7つのムダ」もあわせて押さえておくと、本内容の理解度が一層深まると思います。
成功のコツ
仕分け作業中や赤札期間中のモノを一時的に置くスペースを確保しておくと、作業がスムーズに進みます。判断する際は「いつか使うかも」という考えは避け、設定した基準に基づいて迅速に行うことが大切です。
もし判断に迷う場合は、保留にせず上長に相談するなど、その場で解決するためのルールを決めておきましょう。
ステップ2:【整頓】モノの置き場所を決め、誰でも分かるように表示する
不要なモノがなくなったら、次は必要なモノを使いやすく配置する「整頓」のステップです。探す時間をゼロにすることを目指します。
具体的な進め方
- 保管場所の決定(ロケーション管理)
- 表示・ラベリング
- 安全な保管
まず、モノの使用頻度、作業動線、関連性などを考慮して、最適な保管場所を決定します。
この際、「どこに (Where)」「何を (What)」「どれだけ (How much)」置くかを明確にする「3定(定位・定品・定量)」の考え方を取り入れることが基本です。定位でモノの置き場所を区画線などで明確に決め、定品で決めた場所に置くモノの種類を特定し、定量でそこに置くモノの最大量や最小量を定めます。
次に、誰が見ても、どこに何がどれだけあるか一目で分かるように、表示やラベリングを行います。棚やエリアに番号や記号を割り振る「棚番表示」、保管されているモノの名前や品番を示す「品目表示」、最大保管数や現在の在庫数を示す「数量表示」、床にテープなどで置き場所の範囲を示す「区画線表示」などが有効です。
文字だけでなく、写真や図を活用すると、置き方や向きが重要な場合にも誤解なく伝わります。
さらに、安全な作業環境を確保することも整頓の重要な要素です。通路幅は、人やフォークリフトなどの運搬機器が安全に通行できる十分な幅(一般的に人が通るだけなら80cm以上、フォークリフトを使用する場合はその機種の最大幅に加えて左右に30cmずつの余裕を持たせるのが目安)を確保しましょう。
荷物は崩れないように安定した方法で積み上げ、重量物は下段に置くなど、常に安全を最優先に考えた職場環境を徹底します。
関連記事:職場環境を改善する具体的な方法とは?7つの対策や注意点をご紹介
成功のコツ
モノを配置する際は、使用頻度に応じて場所を決めるのが基本です。よく使うモノは取り出しやすい腰の高さや通路に近い場所に、あまり使わないモノは棚の奥や高い場所に配置しましょう。また、入荷から出荷までの一連の流れや、作業者・運搬機器の動きを考慮し、移動距離が最短になるような動線を意識したレイアウトにすることが重要です。
また、作業手順を明確にし、誰でも同じように作業できるようにするためには、分かりやすい手順書の整備が不可欠です。特に、写真やイラストだけでなく、実際の動きを見せるためのマニュアル整備にはコツが要ります。そうしたコツを以下の資料で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてみてください。
ステップ3:【清掃】常にきれいな状態を保つ
整理・整頓ができたら、次は倉庫全体をきれいに保つ「清掃」です。
具体的な進め方
- 清掃の目的共有
- 清掃の習慣化
- 清掃しやすい環境づくり
まず、清掃は単に美観を保つだけでなく、設備の維持管理や安全確保に直結する重要な目的があることを全員で共有します。ゴミや汚れを取り除く過程で、床のひび割れや機械の油漏れ、アイテムの破損といった異常を発見しやすくなることを理解してもらうことが大切です。
次に、清掃を一過性のものにせず、日常業務として定着させるための仕組みを作ります。例えば、始業前や終業後の数分間など毎日決まった時間に清掃タイムを設けたり、各部署やチーム、個人で清掃担当エリアを決めて責任を明確にしたりします。
ほうき、ちりとり、雑巾などの清掃道具をすぐに使えるように整備し、その置き場所も明確に決めておくこと(これも整頓の一部)が、習慣化を後押しします。
さらに、清掃の負担を減らすための環境づくりも重要です。床に直接モノを置かないルールを徹底する、配線や配管を整理してカバーで覆う、汚れにくい素材の棚や床材を選ぶ、床面を明るい色で塗装してゴミを見つけやすくするなど、物理的な環境を改善することも検討しましょう。
成功のコツ
清掃を行う際は、ただ掃いたり拭いたりするだけでなく、「何か異常はないか?」という保全活動の視点を持つことが重要です。これにより、設備の不具合や危険箇所を早期に発見し、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。
また、そもそも「汚さない工夫」を考えることも大切です。ゴミが発生しにくい作業方法を取り入れたり、汚れやすい箇所を特定して対策を講じたりするなど、発生源対策にも目を向けましょう。
関連記事:設備保全の目的とは?課題やあるべき姿、IoT化について解説
ステップ4:【清潔・躾】整理・整頓・清掃を維持し、習慣化する
最後のステップは、整理・整頓・清掃(3S)によって実現した良い状態を維持する「清潔」と、決められたルールや手順を全員が守ることを習慣化する「躾」です。
5S活動を一過性のイベントで終わらせず、組織文化として根付かせることが目的です。
具体的な進め方
- 「清潔」の維持
- 「躾」による習慣化
まず、「清潔」を維持するため、3S(整理・整頓・清掃)が保たれている状態を持続させる仕組みを作ります。具体的には、3Sの基準やルールを明文化し、朝礼での確認や掲示物などを通じて全員が理解できるように周知徹底します。
また、定期的に5Sパトロールなどを実施し、チェックリストを用いて客観的に維持状況を確認し、問題があれば改善策を講じるといった活動が有効です。汚れやすい場所にはあらかじめカバーを付ける、表示が剥がれたらすぐに貼り直すなど、維持しやすくするための工夫も継続的に行います。
次に、「躾」によって、決められたことを全員が当たり前に、正しく守れるように、従業員の意識向上と行動の習慣化を図ります。
これには、5Sの重要性や具体的なやり方についての継続的な教育・訓練が不可欠です。また、5S活動で成果が出た事例や優れた工夫を社内で共有し、全体のモチベーションを高めたり、従業員からの改善提案を奨励して活動への参加意識を高めたりすることも効果的です。
最も重要なのは、現場責任者や管理者が率先して5Sに取り組み、その重要性を行動で示すことです。
成功のコツ
5S活動の成果を具体的に示すことで、活動の意義を従業員全員が実感しやすくなります。例えば、探し物時間の削減効果、事故件数の減少、コスト削減額などを定期的に「見える化」して共有しましょう。
5Sの定着には時間がかかるため、すぐに結果が出なくても焦らず、根気強く継続することが最も重要です。活動がマンネリ化しないよう、時にはゲーム感覚を取り入れたり、チーム対抗で改善を競ったりするなど、従業員が前向きに、楽しみながら取り組めるような工夫を取り入れることも、継続の秘訣と言えるでしょう。
【応用編】倉庫の作業効率と安全性をさらに高める改善アイデア
基本的な5Sに加えて、さらに倉庫の機能性を高め、作業効率や安全性を向上させるための応用的な改善アイデアをご紹介します。
効率的な倉庫レイアウト設計の基本
倉庫全体のレイアウトは、モノの流れや作業動線に大きく影響します。効率的なレイアウトを実現するための基本的なポイントは以下の通りです。
- 動線の最適化
- 保管方法の選択
- ABC分析の活用
- 安全な通路幅の確保
効率的なレイアウト設計では、まず作業者の移動距離やモノの運搬距離が最短になるよう動線を最適化します。入荷から保管、ピッキング、出荷までの一連の流れを考慮し、入荷エリアと出荷エリアの分離、関連性の高いアイテムの近接配置、一方通行ルールの設定などを検討します。
代表的なレイアウトにはI字型(入荷から出荷まで一直線)やU字型(入荷と出荷の場所が近い)などがあります。
次に、保管するアイテムの特性や出荷頻度に応じて、最適な保管方法を選択します。各アイテムの場所を固定する「固定ロケーション」は場所を覚えやすい反面スペース効率が悪くなることがあり、空いている場所に保管する「フリーロケーション」はスペース効率が高いですがシステムによる管理がほぼ必須です。
また、ピッキングエリアとストックエリアを分け、ストックエリアから補充する「ダブルトランザクション」はピッキング効率を高める手法です。
さらに、出荷頻度や在庫金額などに基づいてアイテムを重要度別にランク付けするABC分析を活用し、重要度の高いAランクのアイテムを取り出しやすい場所(出荷エリアに近い、腰の高さなど)に配置することで、作業効率を大幅に改善できます。
最後に、フォークリフトや台車、人が安全にすれ違える通路幅を確保することも不可欠です。通路にはみ出してモノを置かないルールを徹底し、必要であれば床面にラインを引いて通路を明示しましょう。
フォークリフトを使用する倉庫では、レイアウト設計と合わせて安全対策が非常に重要です。フォークリフトのヒヤリハット事例や具体的な安全対策については、以下の記事も参考にしてください。
▼関連記事▼
フォークリフトのヒヤリハット事例集と対策まとめ!危険予知の事例もあわせて解説
フォークリフトの安全対策8例!事故を防止した改善事例や安全意識を高める方法も解説
探し物ゼロへ!「見える化」による在庫管理の最適化
どこに何がどれだけあるかを誰でもすぐに把握できる「見える化」は、整理整頓の効果を高め、在庫管理の精度向上に不可欠です。見える化を進めるための具体的な方法は以下の通りです。
- 在庫状況の見える化
- 保管方法の工夫
- ピッキング作業の改善
在庫状況の見える化には様々な手法があります。使用した分だけ補充する「カンバン方式」は在庫量を一定に保つのに役立ちます。ハンディターミナルなどを活用する「在庫管理システム (WMS) 」を導入すれば、リアルタイムで正確な在庫情報を把握でき、ロケーション管理や先入れ先出しの徹底にも有効です。
さらに、重量センサーやRFIDタグなどを利用する「IoTの活用」により、在庫量の自動把握や所在管理を行うことも可能です。
また、ピッキング作業の改善においても見える化は重要です。「ロケーション表示の最適化」により、ピッキングリストと棚の表示を連動させ、分かりやすくします。表示器の指示に従ってピッキングする「デジタルピッキングシステム」を導入すれば、ミスを削減し効率を向上させることができます。
在庫管理の見える化は、ピッキングミスや出荷ミスの削減にも直結します。関連する課題と対策については、以下の記事もご覧ください。
▼関連記事▼
ピッキングミスや数量間違いが多い人の特徴と9つの対策!改善事例もあわせて紹介
誤出荷ゼロを目指す!出荷ミスの原因と6つの対策例
5S活動を形骸化させないための推進ポイント
5S活動は、導入時だけでなく、継続していくことが最も重要であり、難しい点でもあります。活動を形骸化させず、組織文化として定着させるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 目的・目標の明確化と共有
- 推進体制の構築
- 従業員のモチベーション維持
- 定期的な効果測定とフィードバック
- 現場主導の改善
まず、なぜ5Sに取り組むのか(生産性向上、安全確保、コスト削減など)という目的と、具体的な目標(探し物時間〇分削減、事故件数ゼロなど)を設定し、全従業員で共有することがスタートラインです。
目的と目標が確立されれば、経営層の強いコミットメントのもと、5S推進リーダーや推進委員会などを設置し、役割分担を明確にした推進体制を構築して活動を進めます。
活動を継続するには、従業員のモチベーション維持も欠かせません。活動の成果を定期的に報告・共有したり、優れた改善事例を表彰したり、5Sに関する研修機会を提供したりすることで、従業員の参加意欲を高めます。
そしてより重要なのは、活動して終わりにするのではなく、定期的な効果測定とフィードバックに努めることです。5Sパトロールの結果や活動目標の達成度などを定期的に測定・評価し、結果をフィードバックします。うまくいっている点は称賛し、課題点は改善策を検討するPDCAサイクルを回し続けることが大切です。
最後に、トップダウンだけでなく、現場主導の改善を促す仕組みを取り入れることも効果的です。現場の作業者自身が主体的に問題点を見つけ、改善策を考え、実行できるようなボトムアップの活動が、真の定着につながります。
5S活動の具体的な理解や実践方法は、無料セミナー動画「生産性を高める5S活動 正しい運用に欠かせない「重要なS」とは」で詳しく解説されています。5Sを自社の現場にどう応用するのかイメージが湧くようになっているので、お時間がある際に視聴してみてください。
>>>無料セミナー動画「生産性を高める5S活動 正しい運用に欠かせない「重要なS」とは」を視聴してみる
倉庫整理のルール徹底と改善継続には「教育」が不可欠
倉庫を整理しルールを決めても、「いつの間にか元に戻る」「ルールが守られない」という問題が置き、以前の状態に戻る現場は少なくありません。その一因は「教育不足」にあります。
例えば物流企業の「ソニテック株式会社」では、「マニュアルをエクセルでひととおり整備したものの、結局現場には浸透せず、作って終わりという状態に。最終的にはOJTやマンツーマン指導に頼りきり」という状態が続いていました。結果的に教え方が人によってバラつき、現場従業員の作業品質もバラつき、標準ルールが徹底されていなかったのです。
倉庫整理も同様に、現場全体で標準化に努めなければなりません。しかし、従来のOJTや紙マニュアルでの教育には限界があります。
- OJTは教える人によって内容にばらつきが出やすい
- 紙のマニュアルは読まれにくい、更新が大変、コツが伝わりにくい
そこで有効なのが、視覚的に分かりやすく、繰り返し学べる「動画マニュアル」です。ソニテック株式会社のように、物流業や倉庫現場で動画マニュアルの導入は徐々に増えています。
▼動画マニュアル活用事例:ソニテック株式会社▼
実際の作業映像は理解度を高め、特に新人や外国人スタッフへの教育改善を通じた、倉庫整理ルールの徹底にも繋がるでしょう。
動画マニュアルの導入メリットや活用ステップ、事例について詳しく知りたい方は、資料「物流業界の生産性向上を助ける動画マニュアルのチカラ(pdf)」をご覧ください。下の画像をクリックするとダウンロードが可能です。
>>>「物流業界の生産性向上を助ける動画マニュアルのチカラ(pdf)」を見てみる
まとめ:倉庫整理は継続的な改善活動。教育を通じて定着させよう
倉庫整理は、一度きりの大掃除ではありません。5Sを基本とした、効率的で安全な職場環境を目指す継続的な改善活動です。その効果は、生産性向上、安全性向上、コスト削減、従業員のモチベーション向上など多岐にわたります。
整理整頓された状態を維持し、さらなる改善を進めるためには、ルール作りやツールの導入だけでなく、従業員一人ひとりへの「教育」を通じて、5Sの重要性を理解し、正しい作業方法を身につけ、改善意識を高めていくことが不可欠です。
現場教育の有効手段として「動画マニュアル」を推奨しましたが、なかでもおすすめは、物流や倉庫現場に特化した動画マニュアルツール「tebiki現場教育」です。現場従業員が気軽にスマホで撮影し、数分の編集で動画マニュアルが完成します。
tebiki現場教育の詳しい機能や活用事例がまとめられたpdf資料は、以下の画像をクリックするとダウンロードできます。教育手段の参考にしてみてください。