かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」、かんたんデジタル現場帳票「tebiki現場分析」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
品質とは「製品が持つべき特徴や性能が、要求された要件を満たしている状態」を指し、品質検査は「製品の外観や機能を確認する作業」のことです。
本記事では、製造業における品質検査の種類とその方法、品質検査における課題、品質検査の質を向上させるための改善策、検査員のスキル向上を実現する手段について網羅的に解説します。
- 製造業に勤めているけれど、品質検査についていまいち理解できていない
- 品質検査にはどのような種類があるのだろう?
- 具体的な品質検査の改善方法を知りたい
このようなお悩みをお持ちの方には、特にお役立ていただける内容です。
「品質不良を未然に防ぐための現代的な品質検査の手法」についていち早く知りたい方は、PDF資料「製造業の品質不良を未然防止する次世代の品質検査」をご覧ください。品質検査を改善するための重要なエッセンスのみを抽出し、まとめています。
>>製造業の品質不良を未然防止する次世代の品質検査を見てみる
目次
品質検査とは?
品質検査は、製品の外観に傷や汚れがないかの確認や、仕様通りの性能を満たしているかの確認など、多岐にわたる目的で行われます。ここでは品質検査の定義と目的を解説し、品質管理や品質保証といった類似語との違いを明確にします。
品質検査の定義と目的
品質検査とは、製品やサービスが、あらかじめ定められた規格、基準、仕様、顧客の要求事項などを満たしているかどうかを評価する体系的なプロセスです。具体的には、製品の寸法、外観、性能、機能などを測定、試験、観察し、合否を判定します。
また、品質検査は製品の合否を判定するだけでなく、その結果を設計や製造工程の改善に活かすための情報源としての役割も担います。品質検査から得られた情報を活用することで、長期的な品質向上とコスト削減を実現し、企業の競争力向上に寄与することが期待できます。
つまり品質検査は、品質管理活動の一部であり、品質を作り込む活動に対して、出来上がった製品やサービスが要求を満たしているかを確認する活動なのです。
類似用語との違い
ここでは、品質検査と類似する用語として、以下の2つとの違いを解説します。
- 品質管理との違い
- 品質保証との違い
品質管理との違い
品質管理(Quality Control)とは、製品が品質基準を満たすように生産工程全体を管理することです。品質管理は、品質に影響を与える工程や作業を管理することで、ミスや不良品の発生を最小限に抑えることを目的としています。一方、品質検査は品質管理の一部であり、主に最終製品の確認を行う工程を指します。
例えば、外観検査で不良品が発見された場合、その情報を分析し、不良の原因がプレス加工などの特定の工程にあると原因を発見します。この情報を製造部門にフィードバックし、製造工程を改善することで、同様の不良の再発を防ぐことが、品質管理の役割です。
品質保証との違い
品質保証(Quality Assurance)とは、製品やサービスが顧客の期待や規定された要件を満たしていることを保証するための「仕組み」を構築し、維持する活動です。品質保証は品質検査や品質管理とは異なり、企業全体の仕組みや企業文化に根ざした取り組みといえます。
例えば、品質保証では「なぜ不良が発生したのか?」という原因を追究し、工程の見直しや再発防止策を策定します。さらに、設計段階や製造工程の計画立案、従業員へのトレーニング、品質基準の策定なども品質保証の活動に含まれます。
つまり、「品質検査が製品そのものの評価を行い」、「品質管理が生産工程の監視や改善を行う」のに対し、「品質保証は企業全体で品質を維持・向上させるための仕組みづくり」を担っているのです。
関連記事:品質管理とは?品質保証との違いは?管理手法や品質改善のポイントを解説
品質検査の種類と方法
品質検査は多種多様な方法が存在しますが、大きく以下の4つに分類されます。
上記4つの分類はそれぞれが補完し合う関係にあり、単独で製品の品質を完全に保証できるわけではありません。それぞれの分類配下における具体的な品質検査の方法を順番に紹介します。
検査対象への影響による分類
品質検査は、製品や部品の品質を保証するための重要な工程であり、特に検査対象への影響によって以下の2つに分類できます。
- 破壊検査
- 非破壊検査
これら2つは製品の品質確認や安全性評価の根幹を成す検査方法です。それぞれの詳細について解説します。
破壊検査
破壊検査とは、文字通り対象物を破壊して、内部構造や材料特性を評価する検査方法です。切断試験、引張試験、圧縮試験、衝撃試験などが一般的で、強度、耐久性、硬度、成分分析などの詳細なデータを取得できます。
破壊検査のメリットは、製品や材料の物理的・化学的性質を直接的に評価できる点です。特に、安全性が重視される部品や構造物では、破壊検査によって強度や耐久性が要求基準を満たしているかを確認することが不可欠です。
一方で、破壊検査では検査対象が使用できなくなるため、検査後は製品として出荷・使用できません。そのため、量産品ではサンプルを抽出して行う抜取検査が一般的です。破壊検査はその性質上、検査コストやサンプル作成の手間がかかる場合もありますが、製品の信頼性を担保するための重要な検査方法として広く利用されています。
非破壊検査
非破壊検査とは、対象物を破壊することなく内部の欠陥や状態を検査する方法で、検査後も対象物をそのまま使用できる点が大きなメリットです。代表的な手法には、X線検査、超音波探傷検査、磁粉探傷検査、浸透探傷検査などが挙げられます。これらの検査技術は、内部構造や表面、表面直下の微細な欠陥を検出するのに非常に有効です。
非破壊検査のメリットは、完成品をそのままの状態で検査できることにあり、高価な部品や一品物の検査に特に適しています。また、検査を迅速に行えるため時間的コストの削減にも寄与します。ただし、破壊検査に比べて得られる情報が限定的になる場合もあり、検査の信頼性や精度は、使用する装置や技術者のスキル・カンコツに依存します。
カンコツを手順書で伝えられず、作業不遵守や属人化に悩む現場担当者は少なくありません。カンコツを正確に伝承するには「現場で常に使われる、形骸化していない作業手順書」の整備が鍵を握りますが、その作成ポイントについては以下のPDF資料「カンコツが伝わる! 『現場で使われる』作業手順書のポイント」にまとめています。あわせてご覧ください。
>>カンコツが伝わる! 『現場で使われる』作業手順書のポイントを見てみる
検査の目的・特性による分類
品質検査は、その目的や特性によって主に外観検査と機能検査に分類されます。ここでは、外観検査と機能検査について詳しく解説します。
外観検査
外観検査とは、製品の表面の傷や汚れ、形状、寸法などが、図面や仕様書で定められた基準に適合しているかを確認する検査です。製品の美観が消費者の購買意欲を左右したり、製品の安全基準に合致するかを判断したりするという意味で、外観検査はとても重要です。
顧客は多くの場合、製品の品質をまず見た目(外観)で判断するため、外観の不備は製品の評価に直接的な影響を及ぼします。例えば、自動車産業では、塗装のムラや部品の取り付け精度、隙間の均一性などが重要視されるため、厳格な外観検査が不可欠です。
機能検査
機能検査とは、製品が設計通りに機能し、所定の性能を発揮できるかを検証する検査です。機能検査は、製品が実際の使用環境で顧客の期待通りの性能発揮を保証するために不可欠です。
たとえ外観上は問題のない製品であっても、機能的に不備があれば顧客の安全性や製品への満足度に悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、電子機器製造業では、機能検査によって回路が仕様通り正確に動作することや、バッテリーが規定された時間持続することなどを確認します。
検査対象の範囲による分類
検査対象の範囲による分類として以下の2つが挙げられます。
- 全数検査
- 抜き取り検査
全数検査
全数検査とは、製造されたすべての製品を対象に、品質基準を満たしているか確認する検査方法です。全数検査は、製品1つ1つを個別に確認するため、不良品を見逃すリスクを最小限に抑えることが可能です。
不良品が発生した際のリスクが大きい医療機器や自動車部品、安全装備などでは、全数検査が特に重要視されます。また、高単価製品や小ロット生産品にも適しており、検査コストを差し引いても十分なメリットが得られるケースが多いです。
全数検査のメリットは、顧客満足度の向上と信頼性の確保です。全製品を確実に検査することで、リコールや不良品対応のリスクを軽減し、ブランドイメージを守る効果が期待できます。一方、全ての製品を検査するため、時間や人件費がかかる点がデメリットですが、近年ではAIや自動化技術を活用し、コストや工数を削減する取り組みが進んでいます。
抜き取り検査
抜き取り検査とは、製品の中から一定数をランダムに選び、品質基準を満たしているか確認する方法です。全数検査と異なり、すべての製品を検査するのではなく、サンプル品の品質をもとにロット全体の合否を判断します。抜き取り検査は、検査対象を限定することで時間とコストを削減できる点がメリットです。特に、生産量が多く、単価が低い製品には効果的で、短時間で効率的に品質管理を行えます。
ただし、良品が多いロットであっても、サンプルに不良品が含まれると全ロットを不合格と判断し、過剰な廃棄やコスト増加を招くこともあります。そのため、JIS規格やAQL(許容品質水準)などの基準に従い、適切なサンプルサイズを選定することが重要です。
特殊な品質評価による分類
特殊な品質評価による分類として以下の2つが挙げられます。
- 無試験検査
- 間接検査
無試験検査
無試験検査とは、過去の品質情報や技術情報をもとに、受入・工程間・最終・出荷といった全ての検査を省略する手法です。無試験検査は、供給元や製造工程の実績が十分に確立され、不適合品の発生リスクがほとんどない場合に採用されます。
具体的には、長期間にわたり不良品の発生が確認されていない製品や、信頼性の高い製造工程が確立されている場合に適用されます。例えば、実績のある部品メーカーからの納品品であれば、品質情報の記録や技術データにもとづき検査を省略するケースが一般的です。
無試験検査のメリットは、検査にかかる時間やコストを大幅に削減し、製造ラインの効率を向上できる点です。ただし、すべての検査を省略するため、その適用には十分な情報の裏付けが求められます。また、無試験検査は間接検査と補完し合う関係にあり、受入段階で供給元の検査成績を活用する間接検査と併用することで、より信頼性の高い品質管理を実現します。
間接検査
間接検査は、供給元が実施した検査結果や品質記録を活用して受入検査を省略する手法です。無試験検査とは異なり、全ての検査を省略するわけではなく、工程間検査や最終検査など他の工程での品質確認は引き続き行われます。例えば、部品を受け入れる際に供給元が発行した検査成績書を確認し、それをもとに合否を判断するケースが一般的です。
具体例として、受入検査では抜き取り検査を行い、非破壊検査である外観検査を採用する場合があります。その際、供給元からの検査成績書を参考にしつつ、重要なサンプル品だけを外観検査で確認することで効率的な検査が可能になります。間接検査と無試験検査は補完的な関係にあり、例えば高い信頼性の供給元からの部品については間接検査を行い、同時に無試験検査として全体の検査工程を省略する場合もあります。
品質不良を未然防止するための品質検査のやり方や手段については、以下のPDF資料「製造業の品質不良を未然防止する次世代の品質検査」もあわせてご覧ください。目視検査の限界を克服し、不良品流出を防ぐ次世代のアプローチについて解説しています。
>>製造業の品質不良を未然防止する次世代の品質検査を見てみる
製造工程における品質検査
ここからは、品質検査の「製造工程(段階)」を表す4つの概念について解説します。主に以下4つが挙げられます。
- 受入検査
- 工程検査
- 最終検査
- 出荷検査
これらは「検査が実施される工程」を表しており、具体的な手法ではないことに注意が必要です。例えば、食品工場における受入検査では、原材料の鮮度や異物混入の有無を目視や検査機器で確認する外観検査や、細菌検査などの成分分析が行われるようなイメージです。
詳しくみていきましょう。
受入検査
受入検査は、製品の製造に必要な原材料や部品が、規定された基準を満たしているか確認する工程です。受入検査では、原料や部品の品質や性能、安全性を評価し、不良品を製造工程に持ち込まないことを目的とします。具体的には、抜き取り検査や全数検査を行い、外観検査や性能検査によって不具合を早期に発見します。
例えば、プラスチック成形品を扱う場合、入荷時に外観検査でキズや汚れを確認し、性能試験で必要な強度が確保されているかを調べることが一般的です。受入検査を省略すると、後工程に不良品が混入し、全体の品質や生産効率に悪影響を及ぼします。また、受入時の検査を徹底することで、仕入れ先の信頼性向上や、トラブルの早期解決につながります。
工程検査
工程検査は、製造工程の途中で行われる検査で、不良品が次の工程へ進むのを防ぐ役割を担います。工程検査は、製品の完成前に不具合を発見し、早期に対処することで不良の連鎖や無駄を削減します。工程内で定期的に抜き取り検査を実施し、外観検査や寸法測定、機能試験を行うことが一般的です。
例えば、自動車部品の製造工程では、金属加工品の表面にキズがないか外観検査を実施し、寸法や形状の適合性を確認します。また、電気部品の製造では通電試験を行い、異常がないかを検査するケースも多いです。工程検査のメリットは、不良発生箇所の特定が可能になることです。不良が頻発している場合、原因を素早く究明し、工程を改善することで再発を防げます。
最終検査
最終検査は、完成した製品が取引先やエンドユーザーの基準を満たしているか確認する工程です。最終検査は、製品が市場に出る直前の品質の検査であり、不良品の流出を防ぐ最後の工程と言えます。最終検査では、主に外観検査、寸法検査、機能試験が実施され、製品の合否が判断されます。
例えば、家電製品の場合、最終検査では外観のキズや汚れをチェックし、動作確認を行い、取引先の仕様に適合しているかを確認します。一方で、食品業界では、パッケージの汚れやシールの不備、重量が基準を満たしているかを検査することが一般的です。最終検査の重要性は、不良品が市場に流出するリスクを防ぐ点にあります。
出荷検査
出荷検査は、製品を取引先に出荷する直前に行われる検査で、品質を最終的に保証する工程です。出荷検査では、製品の外観や機能、寸法などが出荷基準に適合しているかを確認します。
例えば、プラスチック部品を出荷する際には、製品の変色やキズ、寸法の誤差がないかを目視や計測器で確認します。また、食品や飲料では、パッケージの密封状態や印刷表示が正しいかを重点的に検査します。出荷検査を行うことで、製造工程中や在庫期間中に発生した劣化や人的ミスによる損傷を発見できるため、品質問題の市場流出を未然に防ぐことが可能です。
その他の品質検査
ここまで紹介した品質検査以外にも触れると、以下二つの品質検査手法が存在します。
- 官能検査
- 環境試験
官能検査
官能検査とは、人間の五感(視覚、触覚、嗅覚、味覚、聴覚)を使って製品の品質を評価する検査方法のことです。食品、化粧品、医薬品など、消費者が使用時に「感じる品質」を評価する際に特に重要な役割を果たします。
例えば、食品では目視検査で色合いの異常を確認したり、嗅覚で香り、味覚で実際にテイスティングする等、様々な角度から基準との適合性を判断します化粧品では、肌への触り心地や香りが基準に沿っているかを検証します。
官能検査は、機械やセンサーでは測定が難しい主観的な要素を評価できる点がメリットです。ただし、検査結果にばらつきが出る可能性があるため、訓練を受けた専門の官能検査員が実施することが求められます。
環境試験
環境試験とは、製品が実際の使用環境に耐えられるかを確認するための検査方法のことです。製品が温度、湿度、圧力、振動、紫外線などにさらされる過酷な条件を想定し、そうした影響に耐えられるかを検証します。
例えば、自動車部品では、高温多湿や低温条件下での動作試験が行われます。また、電子機器では振動試験を実施し、輸送中や使用時の振動に耐えられるかを確認します。
環境試験によって、製品の耐久性や寿命を予測できるため、信頼性の高い製品開発につながります。環境試験は特に、医療機器や航空機部品など、高い信頼性が求められる製品で活用されています。
製造現場でよくある品質検査の課題
製造現場における品質検査は、数多くの課題に直面しています。ここでは、品質検査に関する代表的な以下の5つの課題とその背景について詳しく解説します。
- 「検査員スキルの属人化」による品質のばらつき
- 「紙ベースの記録管理」による非効率性
- 検査工程における「ヒューマンエラー」の発生
- 「多品種少量生産」への対応の難しさ
- 「グローバル化」に伴う品質管理の複雑化
それぞれの課題に対して一部、改善案や対策もPDF資料等で随時紹介しているので、あわせてご覧ください。
「検査員スキルの属人化」による品質のばらつき
製造現場では「検査員のスキルや経験」が品質検査の精度に大きく影響を与えています。熟練の検査員が担当する場合は高精度な検査が可能ですが、経験の浅い検査員では不良品を見逃すリスクが高まります。さらに、検査基準が明確でない場合、検査員ごとに判断基準が異なり、品質のばらつきが生じやすくなります。
例えば、外観検査では「どの程度のキズを許容範囲とするか」という基準が曖昧な場合、検査員ごとに合否判定が異なることがあります。
こうした属人化が進行すると、検査員間での手順にバラつきが生まれ「作業手順の不遵守」が生じ、品質不良につながります。PDF資料「手順不遵守に起因する品質不良への考え方と対策」では、手順不遵守の対策方法についてまとめられているので、別途ご覧いただくことで属人化解消のヒントが得られるはずです。
下のリンクから、PDF資料をご覧いただけます。
>>>「手順不遵守に起因する品質不良への考え方と対策」を見てみる
「紙ベースの記録管理」による非効率性
品質検査の記録を紙ベースで管理している製造現場は、まだまだ少なくありません。紙ベースでは記録漏れや記入ミスのリスクが高くなり、後日データを確認する際の手間も増大します。また、紙ベースでは過去の記録を分析するのが困難で、トラブル発生時の原因追及や改善策の立案が遅れる可能性があります。
例えば、検査データをもとに不良品の発生傾向を分析したい場合、紙の記録では膨大な時間がかかり、必要な情報がすぐに取り出せないことがあります。こうした課題に対しては、検査結果をデジタルデータとして記録・管理する仕組みの導入が有効です。
クラウドベースのシステムや専用のデータ管理ツールを活用することで、データの一元化が可能となり、記録の正確性や効率性が向上します。また、データの分析・共有が容易になるため、品質改善サイクルを迅速に回すことが可能です。
そこでオススメできる手段の1つが「現場帳票のデジタル化」です。検査項目の記録を紙から電子に乗り換えることで、「現場におけるデータのリアルタイム分析」が可能となり、異常も自動で知らせてくれるようになるので、迅速な異常検知や品質不良の防止に寄与します。
現場帳票デジタル化導入による詳しいメリットや推進方法、活用事例については、以下のPDF資料「資料はじめての現場帳票デジタル化ガイド」をご覧ください。下の画像をクリックすると、ダウンロードページに遷移します。
検査工程における「ヒューマンエラー」の発生
品質検査は多くの場合、人の手に依存しているため、ヒューマンエラーの発生が避けられません。例えば、検査作業中の見落としや測定値の記録ミス、不適切な判定基準の適用が挙げられます。特に作業が単調であるほど、検査員が注意力を失い、不良品を見逃すリスクが高まります。
もうひとつの例として、外観検査では同じパターンのキズや汚れを繰り返し確認する作業が多く、作業員が疲労すると合否判定の精度が低下することがあります。
ヒューマンエラーに対する解決策として、AIや画像認識技術を活用した自働化システムの導入が挙げられます。自働化によって検査員の負担が軽減され、本来集中すべき作業に集中できる環境整備が可能です。ヒューマンエラーは負担や疲労から発生することが多いので、いかに検査員の負担を軽減できるかが重要だと言えるでしょう。
製造業におけるヒューマンエラーの未然防止と具体的な対策方法は、PDF資料「製造業におけるヒューマンエラーの未然防止と具体的な対策方法」にて詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
>>>PDF資料「製造業におけるヒューマンエラーの未然防止と具体的な対策方法」を見てみる
一方で、自働化できない官能検査のような「ヒトのスキルに依存する作業プロセス」は、人材育成/技能伝承による、属人化解消や業務標準化と平準化を推進することでバラつきを改善できます。作業手順のバラつきが発生する一番の理由のひとつは「教育体制が整備されていない」であり、この背景には「作業プロセスを教える難易度が非常に高い」ことが挙げられます。
そこで製造現場で導入されている教育体制が「動画による教育」であり、ベテラン社員のカンコツや技術をすべて「見える化」し、新人教育がスムーズに進んでいる事例が増えています。
動画による教育は「誰が教えても同じ指導内容になる」「ベテラン社員がいなくとも一定の技術継承がなされる」ことが大きなメリットであり、製造業の作業プロセスや品質検査で有効な教育アプローチとされています。
製造業の動画マニュアル活用事例について知りたい方は、以下のPDF資料「製造業における動画マニュアル活用事例集」もあわせてご覧ください。
「多品種少量生産」への対応の難しさ
近年、多品種少量生産の需要が高まり、製造現場では豊富な種類の製品を柔軟に生産する必要が求められています。しかし、検査方法や基準を製品ごとに変更する必要があるため、品質検査の工程が複雑化し、対応が難しくなっています。また、製品ごとの検査基準を正確に把握できない場合、品質にばらつきが生じる可能性があります。
例えば、自動車部品を製造する工場では、異なる車種や仕様に応じた部品の検査基準を設定する必要があります。その場合、検査員に多くの基準を覚えさせるのは非効率であり、ミスを誘発する原因となります。
こうした課題に対処するためには、柔軟に設定を切り替えられる自動検査システムの導入や、デジタルツールを活用した検査基準の共有が有効です。また、検査プロセスを標準化し、どの製品にも適用できるフレームワークを構築することで、多品種少量生産にも対応しやすくなります。
ちなみに、多品種少量生産の品質改善には「人的要因のデータを可視化」し、PDCAサイクルに落とし込むことが重要です。では、具体的に人的要因のデータをどのように取得するか、PDCAサイクルをどう落とし込んでいけばよいのでしょうか。
その方法は、高崎ものづくり技術研究所代表の濱田金男氏が講演したセミナー「多品種少量生産における製造品質向上の攻めどころ」で詳しく解説されています。 以下の画像をクリックすると動画視聴ページに遷移するので、あわせて参考にしてみてください。
「グローバル化」に伴う品質管理の複雑化
製造業のグローバル化が進む中、各国の規格や顧客要件に対応するため、品質管理が複雑化しています。特に、拠点が複数の国にまたがる場合、各国の基準に適合させた品質検査を行う必要があり、検査基準の統一が難しくなります。また、言語や文化の違いが影響し、各拠点間での情報共有や品質データの一元管理に課題が生じることも少なくありません。
例えば、欧州向けに輸出する製品ではCEマーキング規格、北米向けにはUL規格の基準を満たす必要があり、要件を製造現場で正確に反映させなければなりません。
加えて、製造現場では「従業員」におけるグローバル化も進んでおり、数多くの外国人労働者が所属しています。製造業の業務プロセス自体がそもそもとして複雑かつ高度なスキルが求められるなかで、外国人労働者の教育難易度は非常に高いと言えるでしょう。
製造現場での外国人労働者を教育する手段には「非言語による教育」が推奨されており、その手段のひとつに「動画マニュアル」が多く採用されています。動画マニュアルによって外国人労働者を教育する有効性や活用事例については、以下のPDF資料で詳しくまとめられています。
>>外国人社員の教育課題は、動画マニュアルで解決できる!を見てみる
品質検査の質向上に必要な改善案・対策
品質検査の質を改善する打ち手は、主に以下の二つです。
- 検査員のスキル向上・教育体制の整備
- データ分析に基づく課題の明確化
上記が品質検査の鍵を握ります。それぞれ詳しく解説するので、今後の打ち手を検討するうえで参考にしてみてください。
検査員のスキル向上・教育体制の整備
検査員のスキルは品質検査の精度に直結します。すなわち「検査員の教育」は極めて重要です。特に、検査基準や作業手順の標準化が進んでいない場合、検査員ごとに判断基準が異なり、品質にばらつきが生じるリスクがあります。
また、技術伝承が不十分だと、熟練者が退職した際にノウハウが失われ、検査品質が低下する可能性があります。さらに、教育の質にばらつきがあると、スキルの均一化が難しくなります。
以上の課題が生まれる原因は多くの場合、「教育体制が整備されていない」ことに起因しています。
では、作業手順の標準化や円滑な技術伝承を実現しうる有効な教育手段は何か?その答えのひとつに「動画マニュアル」の活用が挙げられます。動画は視覚的かつ直感的に情報を伝えられるため、新人からベテランまで一貫した教育を提供できます。
例えば、検査の具体的な手順や判断基準を動画で示すことで、分かりやすさが向上し、教育内容の標準化が可能です。また、動画は繰り返し確認できるため、検査員が自主的にスキルを高める際にも役立ちます。
以上の背景から多くの製造現場が動画マニュアルを導入していますが、製造業における動画マニュアルの活用事例集をご覧になりたい方は、以下のリンクからPDF資料「製造業における動画マニュアル活用事例集」をダウンロードしてみてください。
また、動画マニュアルで現場教育を具体的にどのように推進するのか、よりイメージを膨らませたい方は、以下をクリックして「動画マニュアルで現場の教育をかんたんにする方法」もあわせてご覧ください。
>>動画マニュアルで現場の教育をかんたんにする方法を見てみる
データ分析に基づく課題の明確化
品質検査を改善するには、「現場で何が問題になっているのか」を正確にかつ迅速に把握する必要があります。課題が明確でなければ、改善のための具体的な打ち手を見いだすことは困難です。課題の明確化には、客観的なデータ分析が欠かせません。データから仮説を立て、そこから現場で検証するという一連の流れが必須です。
課題の明確化と改善活動を実現するために有効なのが「現場帳票のデジタル化」です。紙ベースの記録では、情報の収集や分析に多くの時間がかかり、課題の把握が遅れることがあります。一方、デジタル化された帳票では、現場で発生する不良品や検査結果をリアルタイムで収集・分析できます。
例えば、不良品が発生しやすい工程や検査基準とのズレを迅速に特定し、改善策を講じることが可能です。また、デジタルデータを活用することで、全体的な品質管理体制を見直し、より効果的な品質検査体制を構築できます。
当メディア「現場改善ラボ」では、現場帳票デジタル化を実現する方法を解説した資料を配布中です。以下の画像をクリックして、ダウンロードしてみてください。
品質検査の質が向上するツール・システムとは?
品質検査の質を向上させるには、効果的な教育体制と効率的なデータ管理が必要です。具体的には「動画による現場教育」と「現場帳票のデジタル化」がおすすめです。それぞれのメリットやおすすめのツールについて詳しく解説します。
動画による教育が品質検査の質向上につながる理由
検査員のスキルや技術伝承は、品質検査の精度を左右します。しかし、多くの現場では紙マニュアルを用いた教育が主流であり、課題が残ります。紙マニュアルは「読まれない」「読んでも理解されにくい」ことが多く、現場ではOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)に依存するケースがほとんどです。その結果、教育担当者やベテランの力量に左右される属人的な教育体制が生まれ、スキルのばらつきや技術の伝承不足が問題となっています。
このような課題を解決する手段として注目されているのが、動画マニュアルの活用です。動画は視覚と聴覚を使った情報伝達が可能なため、教育担当者が不在でも、ベテランの技術を一目で理解できるのが大きなメリットです。その中でも特におすすめなのが 「tebiki」 です。tebikiはシンプルな操作性で動画を作成・共有でき、現場で実際に行う作業手順を分かりやすく伝えることが可能です。また、スマートフォンやタブレットで手軽に閲覧できるため、検査員が自分のペースで復習でき、スキル向上を促進します。
tebikiは教育の質を標準化し、現場全体で均一な検査品質を実現するツールとして多くの現場で採用されています。具体的なtebikiの資料は以下のリンクからダウンロード可能ですので、ぜひチェックしてみてください。
現場帳票のデジタル化が品質検査の質向上につながる理由
品質検査の改善を阻むもう一つの課題が「紙ベースの帳票管理」です。紙での記録は、記録作業自体が目的化するケースが多く、収集したデータが分析や改善活動に活用されないことがしばしばあります。さらに、紙ではリアルタイムでのデータ取得が難しく、異常値の検出や対応に時間がかかるという重大な問題があります。過去データの参照や傾向分析にも多大な手間がかかり、品質改善のスピードが著しく低下することも問題でしょう。
こうした課題を解決するおすすめのツールは「現場帳票のデジタル化」です。デジタル化によって、どこからでも簡単に記録を入力できるようになり、記録と同時にデータが自動的に収集・整理されます。また、異常値が記録された際にはリアルタイムでアラートが発生する仕組みを備えており、迅速な対応が可能になります。さらに、データはクラウド上で管理されるため、過去データの検索や傾向分析が容易に行えます。
その中でもおすすめなのが 「tebik現場分析」 です。tebik現場分析は、現場帳票のデジタル化を簡単に実現できるだけでなく、責任者の承認や押印作業もデジタル上で完結できます。多くの現場で採用されている理由は、現場のニーズに合わせた柔軟な運用が可能で、操作しやすさも魅力です。
品質検査を改善した製造現場の企業事例
アルミニウム表面処理を専門とする「株式会社日本電気化学工業所」は、紙帳票による品質管理の課題を抱えていました。異常値の検出遅れ、データ活用の困難さ、非効率な承認プロセスが、品質不良や工程停止のリスクを高めていました。特に、製品の品質を左右する各種検査データの管理は、重要な課題だったのです。
▼同社の品質改善事例インタビュー動画▼
この課題を解決するため、同社は「tebiki現場分析」を導入。「点検票」「温度記録」「計測機器日常点検記録」など、重要な帳票をデジタル化しました。特に、アルマイト皮膜の品質保証に不可欠な完成品検査に使用される計測機器の精度維持は、「計測機器日常点検記録」のデジタル化で大きく改善。膜厚計等の機器調整記録をデジタル管理することで、測定器の精度を常に最適化できるようになりました。
結果、検査の精度と効率が向上し、不良品流出のリスクを低減。さらに、製造工程のリアルタイム監視と異常値の即時検出を実現しました。例えば、温度異常から配管の微細な穴を早期発見し、大規模トラブルを未然に防ぐことができました。
また、デジタル化によるデータ蓄積・分析の効率化も大きな効果を生みました。ダッシュボードでデータを即時確認、異常値を強調表示することで、承認作業を大幅に短縮。傾向分析や改善活動も容易になり、継続的な品質向上が可能となりました。
さらに、現場従業員の意識改革にも繋がり、記録精度が向上。業務効率改善に加え、ISO9001等の審査対応にも役立っています。
同社の詳しい事例は、以下のインタビュー記事からご覧いただけます。
インタビュー記事:品質不良の未然防止をリアルタイムデータで実現。異常値検知を迅速にできた理由。
【まとめ】品質検査に潜む課題と改善方法
品質検査は、製造業における製品の信頼性を確保し、顧客満足度を向上させるための工程です。しかし、多くの現場では「検査員のスキル属人化」「紙ベース記録による非効率性」「ヒューマンエラー」「多品種少量生産への対応」「グローバル化による品質管理の複雑化」などの課題が存在します。
課題を解決するためには、検査員教育の標準化や、リアルタイムデータを活用した品質管理の仕組みが必要です。特に「動画による教育」と「現場帳票のデジタル化」は、検査精度の向上と業務効率化を実現する効果的な手段としておすすめです。
株式会社日本電気化学工業所の事例では、「tebiki現場分析」を活用することで、リアルタイムの異常値検知、データ蓄積・分析の効率化、承認プロセスの簡素化に成功しました。同時に、現場の意識改革を促し、正確な記録や改善活動が進む基盤を構築。品質の安定化と顧客満足度の向上を達成しました。
「tebiki現場教育」と「tebiki現場分析」サービス資料は以下のリンクからチェック可能ですので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。
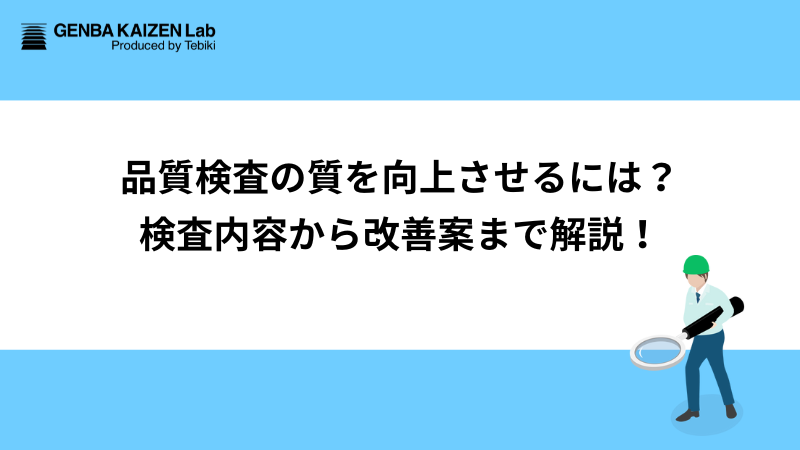






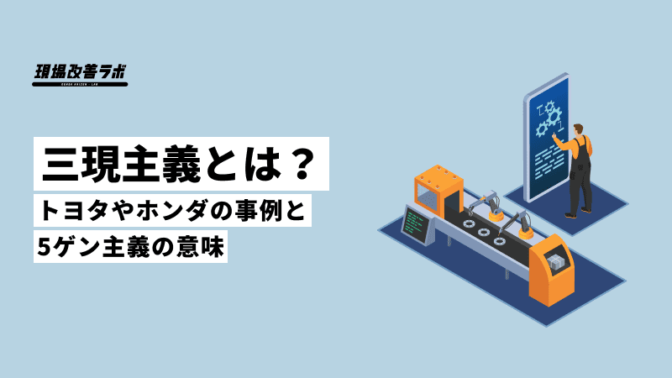
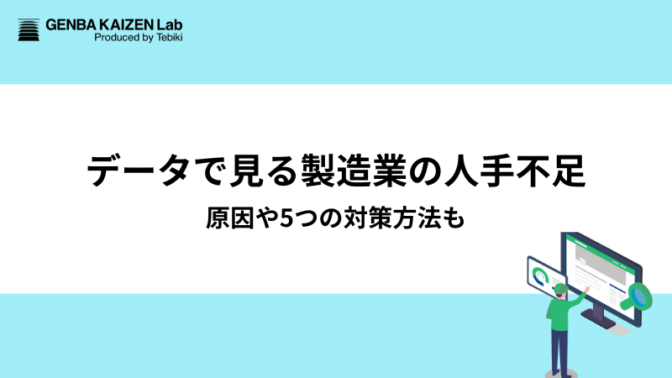
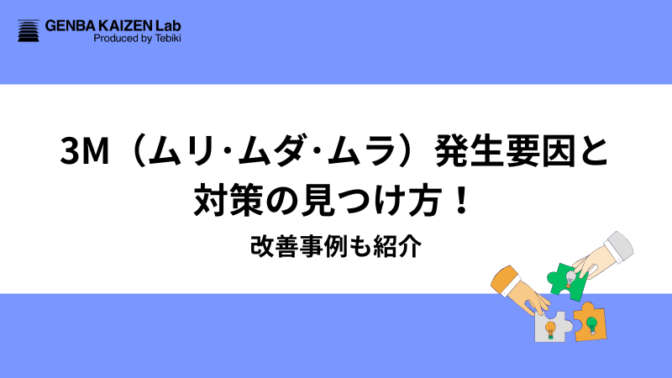










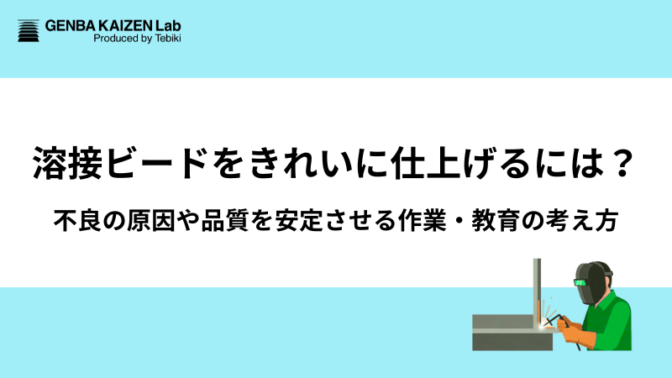
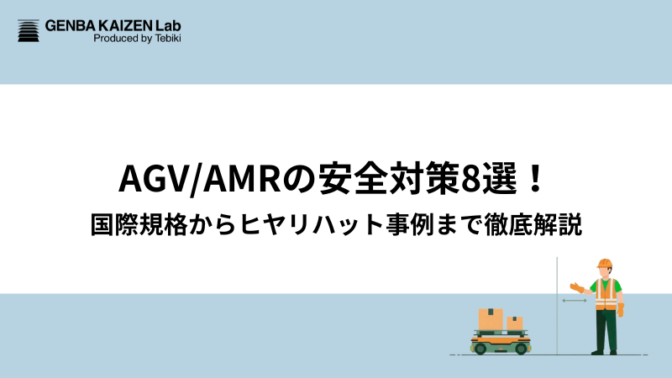
-672x378.png)