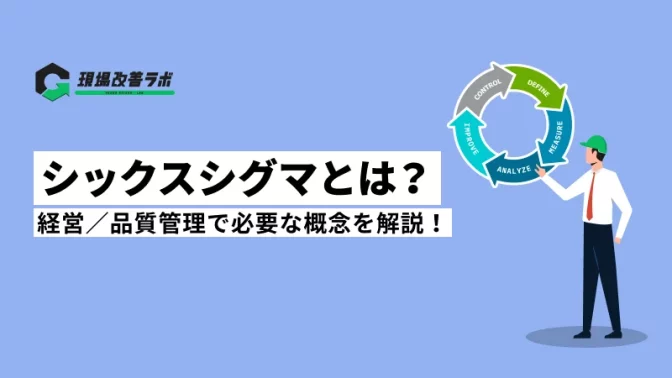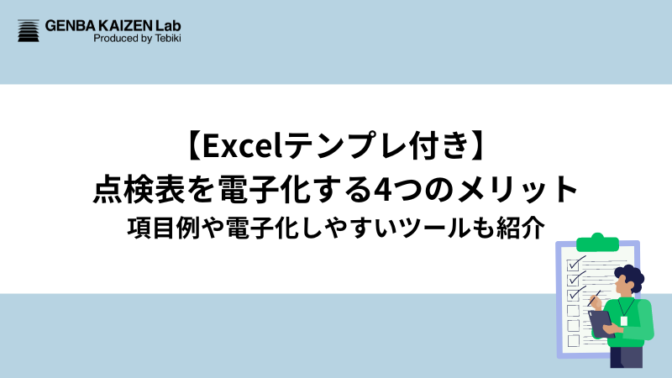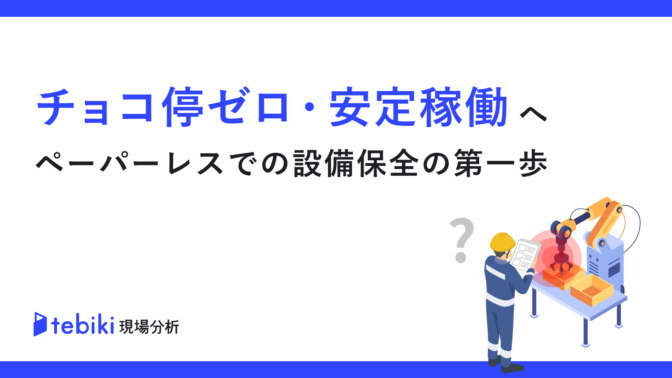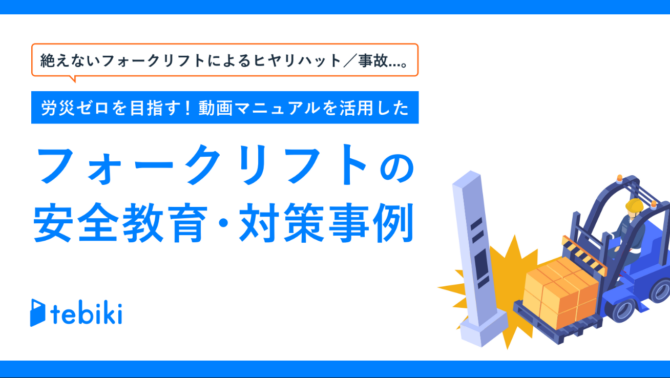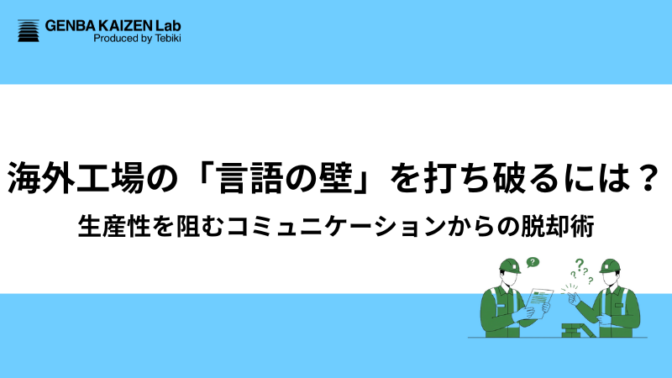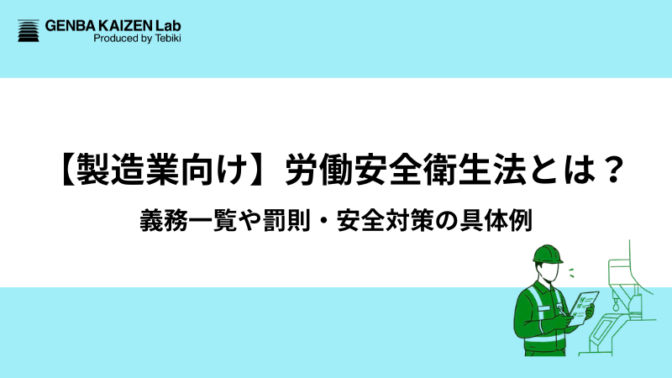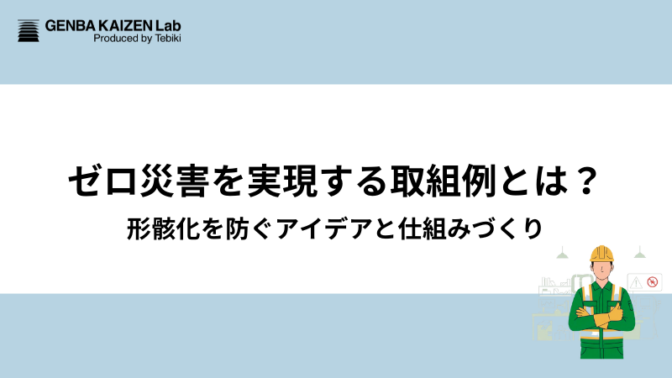かんたん動画マニュアル作成「tebiki現場教育」や、かんたんデジタル現場帳票「tebiki現場分析」を展開する現場改善ラボ編集部です。
製造現場で不良品が頻発し、頭を抱えていませんか?品質のばらつきは、不良品の増加によるコスト増、顧客からのクレーム、生産効率の低下など企業に深刻な影響を与える温床であり、製造業における長年の課題です。
そこでこの記事では、品質のばらつきが発生する根本的な要因と具体的な3つの改善策もご紹介しています。下の目次から、気になるトピックをご覧ください。
目次
品質のばらつきとは?
品質のばらつきとは、製品の製造過程で発生する品質の不規則性のことです。製品の品質特性(寸法、重量、性能、色、外観など)を一定に保てないことで顧客の期待を満たせず、市場での信頼性が損なわれる可能性があります。
例えば、製造業界では部品の寸法や性能のばらつきが製品の性能に直接影響を及ぼし、顧客の満足度に大きく影響します。
そのため、製造プロセスの各段階で品質管理を徹底することが、製品の一貫性と信頼性を保証する上で重要です。
品質のばらつきは、以下の種類に分類できます。
▼「品質のばらつき」の種類▼
| 寸法ばらつき | 製品の長さが規格値100mmに対し、実際には98mmや102mmといった個体差が生じる場合。これは許容範囲±1mmを超えているため、不良品となります。例えば、ねじの長さが規格よりも長かったり短かったりする場合。 |
| 重量ばらつき | 製品の重量が規定値100gに対し、実際には95gや105gといった個体差が生じる場合。例えば、食品のパック詰めにおいて、内容量が規定量と異なっている場合。 |
| 性能ばらつき | 製品の出力が規格値100Wに対し、実際には90Wや110Wといった個体差が生じる場合。例えば、機械の出力が個体によって異なったり、電子機器の動作速度に差があったりする場合。 |
| 外観ばらつき | 製品の色が規格値の色見本と異なって見える場合や、表面に微細な傷がある場合。例えば、塗装の色ムラや、製品表面の傷など。 |
品質のばらつきが企業に及ぼす影響
品質ばらつきが企業にもたらす影響は深刻です。特に、以下のような影響は企業の収益やブランドイメージに大きな打撃を与えます。
▼「品質のばらつき」が企業に及ぼす影響▼
| 不良品増加 | 規格外の製品が増加し、廃棄コストや再加工コストが発生します。これは直接的なコスト増につながり、企業の収益を圧迫する要因となります。 |
| クレーム増加 | 顧客からのクレームが増加し、顧客満足度や信頼が低下します。これはブランドイメージの低下に直結し、長期的な顧客離れを引き起こす可能性があります。 |
| 生産効率低下 | 不良品対応、クレーム対応、再加工などに伴うコストが増加します。これらのコストは企業の利益を直接的に減少させます。 |
| ブランドイメージ低下 | 品質の不安定さが顧客に伝わり、ブランドイメージが低下します。これは長期的な売上減少に繋がり、最悪の場合、企業の存続に関わる事態にもなりかねません。 |
品質のばらつきの原因を特定する3つの方法
品質のばらつきの原因を特定することは、製造業において非常に重要です。原因を正確に把握することで、効果的な改善策を講じられます。
ここでは品質のばらつきの原因を特定する方法として、以下の3つを解説します。
- 4M(人/機械/材料/作業手順)の各要素をチェックリスト化し、ばらつきの要因を徹底的に洗い出す
- QC7つの道具を用いて、ばらつきの要因を定量的に分析する
- 特定した要因に対して5回以上のなぜなぜ分析を行い、真因を深堀りする
4M(人/機械/材料/作業手順)の各要素をチェックリスト化し、ばらつきの要因を徹底的に洗い出す
4M分析は、品質ばらつきの原因を「Man(人)、Machine(機械)、Material(材料)、Method(方法)」の4つの要素に分類し、体系的に分析する手法です。それぞれの要素は以下のとおりです。
▼「4M」の各要素▼
| Man(人) | 作業員のスキル、経験、教育、意識、健康状態など。例えば、熟練作業員と新人作業員の間で作業スピードや品質に差が出る場合。 |
| Machine(機械) | 設備の性能、精度、メンテナンス状況、老朽化など。例えば、機械の老朽化によって精度が低下し、製品の寸法にばらつきが生じる場合。 |
| Material(材料) | 原材料の品質、ロット差、保管状態など。例えば、原材料のロットによって成分にばらつきがあり、製品の品質に影響する場合。 |
| Method(方法) | 作業手順、作業環境、検査方法など。例えば、作業手順が曖昧で作業員によって解釈が異なり、品質にばらつきが生じる場合。 |
例えば、製品の寸法にばらつきが発生している場合、以下の手順で4M分析を活用できます。
▼4M分析の実践例▼
| 手順1.問題の明確化 | 「製品Aの長さが規格値±1mmを超えている」という問題を明確にします。 |
| 手順2.「4M」における要素の洗い出し | Man(人): 作業員の測定スキル不足、測定時の姿勢のばらつき、教育不足などが考えられます。 Machine(機械): 測定器の精度不良、校正不足、老朽化などが考えられます。 Material(材料): 材料自体の寸法ばらつき、熱膨張などが考えられます。 Method(方法): 測定方法の曖昧さ、測定環境の温度変化などが考えられます。 |
| 手順3.要因を特定し、対策を検討 | 4Mで洗い出した要因から、データや現場の状況に基づいて最も可能性の高い要因を特定します。例えば、過去のデータから測定器の校正が長期間行われていないことが分かれば、「Machine(機械)」の「測定器の校正不足」が最も可能性の高い要因となります。 |
| 手順4.対策の実施と効果測定 | 特定した要因に対して対策を実施します。上記の例であれば、測定器の校正を行います。その後、再度測定を行い、ばらつきが改善されたかを確認します。 |
このように、4M分析は単に要因を分類するだけでなく、問題解決のための具体的な手順として活用できます。
▼関連記事▼
4Mとは?分析方法や変更管理の目的とポイントを解説
4M変更とは?通知義務の有無や管理しやすくする方法も解説!
【図解あり】4M分析とは?問題整理や変更管理での分析方法を解説!
QC7つの道具を用いて、ばらつきの要因を定量的に分析する
品質のばらつきの原因を特定する方法として有効なのがQC7つ道具です。
ここではQC7つ道具の定義と、品質のばらつきを特定するのに有効なツールについて解説します。
QC7つ道具とは?
QC7つ道具は、品質管理の分野で広く用いられる7つの基本的な分析ツールです。
QC7つ道具は、品質の問題を特定、分析、解決するために設計されており、製造業をはじめとする多くの業界で効果的に活用されています。
具体的には、以下のツールが含まれます。
チェックシート
目的: データ収集と整理。
作成手順: 調査項目を明確にし、チェックする形式(例:正の字、○×)を決めてシートを作成。
解釈方法: 集計結果からデータの傾向や分布を把握。
活用例: 不良の種類別発生回数、作業工程ごとの作業時間などを記録。
パレート図
目的: 問題の優先順位付け。「80/20の法則」を活用し、重要な要因を特定。
作成手順: データを集計し、棒グラフで表示。累積構成比を折れ線グラフで表示。
解釈方法: 棒グラフの高い順に要因を並べ、累積構成比が高い要因に注目。
活用例: 不良原因別の発生件数を集計し、最も多く発生している原因を特定。
特性要因図(フィッシュボーン図)
目的: 問題の原因を体系的に整理し、根本原因を特定。
作成手順: 問題を「結果」として右側に記述。主要因(例:4M)を大骨として左側に記述。各要因に関連する原因を中骨、小骨として追加。
解釈方法: 骨の繋がりを辿ることで、問題と原因の因果関係を把握。
活用例: 製品の不良発生原因を4Mの視点から分析。
ヒストグラム
目的: データの分布状況を把握。
作成手順: データを適切な階級に分け、各階級の度数を棒グラフで表示。
解釈方法: データの中心、ばらつき、偏りなどを確認。
活用例: 製品の寸法データをヒストグラムで表し、寸法ばらつきの程度を確認。
散布図
目的: 2つのデータの相関関係を分析。
作成手順: 2つのデータをそれぞれX軸、Y軸にプロット。
解釈方法: 点の分布から相関の有無や強さを判断。
活用例: 作業時間と不良品発生数の相関を分析。
管理図
目的: 工程の状態を監視し、異常を発見。
作成手順: データを時系列順にプロットし、管理限界線(上限値と下限値)を設定。
解釈方法: プロットされた点が管理限界線を逸脱した場合、工程に異常が発生していると判断。
活用例: 製品の寸法を定期的に測定し、管理図で監視。
グラフ
目的: データの変化や比較を視覚的に表現。
作成手順: データの種類や目的に合わせて適切なグラフ(折れ線グラフ、棒グラフ、円グラフなど)を選択し作成。
解釈方法: グラフの形状からデータの傾向や変化を把握。
活用例: 月ごとの不良品発生数の推移を折れ線グラフで表示。
品質管理の実施に必要不可欠なQC7つ道具は、目的や状況によって使い分ける必要があります。品質問題を解決するにはQC7つ道具を正しく用いて問題を見える化することが求められますが、「改善を行う際にQC7つ道具を使いたくても使い方が分からない」や、「実務でどう活かせばいいか分からない」とお悩みの方も多くいるでしょう。
そこで、QC7つ道具の実践的な活用法をさらに知りたいという方は、以下の動画を参考にすると良いでしょう。株式会社エイシン・エスティー・ラボの代表取締役である山本 諭氏に品質問題が起きる原因やQC7つ道具と新QC7つ道具の違い、実務で実践できる品質問題を見える化させるQC7つ道具の使い方、QCストーリーの重要なステップである標準化について解説しています。
特定した要因に対して5回以上のなぜなぜ分析を行い、真因を深堀りする
なぜなぜ分析は、品質の問題の根本原因を深堀りするのに有効な手法です。特定された要因に対して、「なぜ?」を5回程度繰り返して問いかけることで、根本原因にたどり着きます。
例えば、「製品に傷がある」→「なぜ?」→「作業員が工具を落とした」→「なぜ?」→「工具の置き場所が不安定だった」→「なぜ?」→「工具置き場が整理整頓されていなかった」といった具合に深掘りしていきます。
より実践的ななぜなぜ分析の具体的手法が知りたい方は、動画『ヒューマンエラーに対する「トヨタの考え方」ートヨタで学んだなぜなぜ分析ー』もあわせてご覧ください。本動画では、トヨタ社内にてトヨタの正社員に対して「なぜなぜ分析」を教えていた訓練指導者「伊藤 正光氏」をお招きし、トヨタ社内にて実際に教えられていた「なぜなぜ分析」のエッセンスをお届けしています。
なぜなぜ分析の演習から標準作業を確立させる教育アプローチの解説まで、多岐にわたるコンテンツが収録された無料動画になります。以下の画像をクリックしてご視聴ください。
品質のばらつきを改善する3つの実践アプローチ
品質ばらつきを改善するためには、場当たり的な対応ではなく、根本的な原因に目を向け、現場レベルでの実践可能な具体的アプローチが重要です。ここでは、以下の3つのアプローチを紹介します。
作業手順の標準化と徹底
作業手順の標準化は、品質のばらつきを抑制する基盤です。手順が曖昧な状態では、作業が個々人の解釈に左右され、品質にばらつきが生じやすくなります。標準化によって、誰が行っても一定の品質を保てるようにすることで、品質管理の土台を築きます。これは品質安定に加え、作業効率や安全性向上にもつながります。
多くの現場では、標準化が形骸化し、効果を発揮できていないケースが見られます。手順書作成で満足し、現場の実情に合っていなかったり、浸透していなかったりする状況です。定期的な見直しが形骸化し、過去のSOPがそのままになっていたり、現場と乖離しているのに更新されない場合、実質的な改善には繋がりません。
そこで、標準化を効果的に実施するためのポイントをまとめました。
▼標準化を効果的に実施するためのポイント▼
| 目的の明確化 | 何のための標準化なのか、具体的な目的(例:不良率低減、作業時間短縮、安全性向上)を明確に定義します。目的を共有することで、関係者全員が同じ方向を向いて取り組めます。 |
| 現場主導のプロセス | 現場の作業者が主体的に参加し、意見を反映させることで、実効性の高い標準化が実現します。現場が納得し、使いやすい標準を作ることが、定着の鍵です。 |
| 継続的な改善 | 標準は作成して終わりではなく、環境変化や新たな課題に合わせて、定期的に見直し、改善していくことが不可欠です。PDCAサイクルを回し、継続的改善を文化として根付かせる意識が重要です。 |
| 徹底的な周知と教育 | 作成したSOPは、現場作業者全員に周知徹底し、必要に応じて教育訓練を実施することで、SOPの理解と定着を促進します。単に配布するだけでなく、研修やOJTなどを通じて、実際に使えるレベルまで落とし込むことが大切です。 |
作業品質向上や技術継承を目的とした現場教育の実施
製造現場における教育は、技術や暗黙知(カンコツ)を次世代へ継承する重要な役割を担っています。しかし、従来の教育方法は複雑な作業手順や微妙なニュアンスを伝えきれず、多くの現場で効果を発揮できていません。
従来の教育方法、特に紙のマニュアルは、動きのある作業や複雑な手順を詳細に伝えるには限界があります。製造現場のように複雑な動きや力加減が求められる環境では、紙媒体だけでは作業の要点を十分に伝えられず、作業品質のばらつきや教育効率の低下を招いていました。また、マニュアルが現場の状況と合わなくなったり、更新が滞ったりして形骸化し、適切に運用されていないケースも少なくありません。これでは、技術継承はおろか、基本的な作業手順の遵守すら困難です。
そこで、製造業の教育現場では、教育方法そのものの変革が求められ、解決策として「動画」を活用した教育指導が注目を集めています。動画マニュアルを多くの製造企業が取り入れ始めているのは、こうした切実な課題を解決するためです。
動画マニュアルは、従来の教育方法の課題を克服する可能性を秘めており、主なメリットは以下のとおりです。
▼動画マニュアルのメリット▼
| 視覚的な情報伝達力 | 動画は、文字や図では伝えにくい複雑な動きやニュアンスを、映像と音声で分かりやすく伝えます。ベテラン社員の熟練した技術やカンコツも、見て学べるため、技術継承がスムーズに進みます。 |
| 作業手順の遵守徹底 | 正しい作業手順が映像で明確に示されるため、作業員は迷うことなく作業を行い、作業遵守が徹底されます。手順のばらつきが抑えられることで、品質の安定と向上に貢献します。 |
| 教育効率の向上 | 動画マニュアルは繰り返し再生可能なため、教育担当者の負担を軽減し、教育にかかる時間やコストを削減できます。時間や場所を選ばずに学習できるため、作業員の自主学習も促進し、学習効果を高めます。 |
| 多言語対応の容易性 | 字幕や音声の変更によって多言語対応が容易になるため、グローバル展開している企業や外国人労働者を雇用している企業にとっても大きなメリットとなります。 |
これらのメリットから、動画マニュアルは、従来の教育方法の課題を克服し、技術継承を円滑に進め、品質向上に貢献する有効な手段と言えます。
動画マニュアルを実際に取り入れ、現場教育や品質のばらつきを改善した製造現場の企業事例を見てみたい方は、以下の画像をクリックしてご覧ください。
データに基づいた改善活動
データに基づいた改善活動とは、原因特定で明らかになったデータを分析し、効果的な改善策を発見し、実行、そして効果測定を通じてさらなる改善につなげる、まさにPDCAサイクルを回す活動です。感覚や経験に頼るのではなく、客観的なデータに基づいて問題点を把握することで、真の原因を特定し、より的確な改善策を講じることが可能となります。
この活動を効果的に行うためには、まずデータが収集できる基盤構築が不可欠です。適切なデータを収集・蓄積する仕組みがなければ、分析を行うことすらできません。
例えば、製造ラインの各工程における稼働状況、不良品の発生状況、作業時間などのデータを継続的に収集することで、問題の発生傾向やボトルネックとなっている工程を客観的に把握することができます。
データ収集基盤を構築する有効な手段の一つとして、「現場帳票のデジタル化」が挙げられます。これまで紙ベースで管理されていた現場帳票をデジタル化することで、製造現場の数値をリアルタイムで正確に把握できるようになります。これにより、以下のようなメリットが得られます。
▼「現場帳票デジタル化」のメリット▼
| リアルタイムな状況把握 | 作業現場で入力されたデータが即座にシステムに反映されるため、管理者は常に最新の状況を把握できます。 |
| 異常の早期発見 | リアルタイムデータに基づいて異常検知を行うことで、問題が深刻化する前に早期に対応できます。 |
| 迅速な品質改善 | データ分析を通じて品質問題の原因を特定し、迅速に改善策を実行できます。 |
| データ分析の効率化 | デジタル化されたデータは容易に集計・分析できるため、改善活動の効率が大幅に向上します。 |
このように、現場帳票のデジタル化は、データ基盤構築の第一歩と言えるでしょう。
製造現場DXやペーパーレス化の第一歩でもある「現場帳票デジタル化」に興味がある方は、「はじめての現場帳票デジタル化ガイド」を一読すると、デジタル化を推進するヒントが得られます。以下のリンクをクリックして、資料をダウンロードしてみてください。
>>>「はじめての現場帳票デジタル化ガイド」を読んでみる
品質のばらつきを改善した企業事例
ここからは、品質のばらつきを改善した企業の取り組み事例について紹介します。品質のばらつきに対して他社がどのようなアプローチを取っているのか、参考にしてみてください。
新日本工機株式会社:現場教育を改善し、品質のばらつきを根本から解消
工作機械の製造販売を手掛ける新日本工機株式会社は、現場教育に動画マニュアルを導入することで作業標準化を図り、品質ばらつきの改善を実現しています。
▼インタビュー動画:新日本工機株式会社▼
もともと紙マニュアルによる指導で運用してきていましたが、読み手によって文字情報の解釈に差が生じ、作業者間で認識が異なっていたことが課題でした。結果的に品質のばらつきが生まれ、作業の後戻りが頻発。
そこで動画マニュアルを主軸に置いた教育方針や情報伝達を整備したところ、複雑な作業手順もスムーズに教育できるうえに、海外拠点への情報共有も難なくできるようになり、品質向上やコミュニケーション工数削減を実現しました。
動画マニュアル導入効果を実感した同社は、1年間で1,500本もの動画マニュアルを作成しており、効果的かつ効率的なマニュアル整備を進めています。
同社の事例について詳細を知りたい方は、以下のリンクからご覧ください。
関連記事:人が育つ環境づくりとして動画マニュアルtebikiを活用。技術の蓄積と作業品質の安定を実現。
株式会社アルバック
真空技術を駆使した製品やソリューションを展開する株式会社アルバックは、動画によるマニュアルの整備を通じて、作業品質の安定化や生産性向上を実現しています。
特に、専門的な製造プロセスや技術が求められる同社のマテリアル事業部では、生産拠点によって生産性に大きな差が生じており、その差を埋めることが急務でした。その対策として、技術伝承による作業品質の安定化を課題のひとつとして設定。
そこで動画によるマニュアルを整備し、拠点間の技術やノウハウ共有の促進を図ったところ、1日あたりの生産性が67%増を実現。従来のテキストや画像のマニュアルでは十分に伝えきれなかった暗黙知やカンコツが、動画を通じて言語化・可視化されたことが大きなインパクトを生み、全体的な生産効率の向上につながりました。
同社の事例について詳細を知りたい方は、以下のリンクからご覧ください。
関連記事:人員・労働時間を変更せずに、ボンディング工程の生産性を167%に改善
株式会社日本電気化学工業所
アルミニウムの表面処理を専門に行う株式会社日本電気化学工業所では、現場帳票のデジタル化によって現場の変化/異常を迅速に捉え、品質不良の発生を未然防止することを実現しています。
▼インタビュー動画:株式会社 日本電気化学工業所▼
現場帳票のデジタル化によって、製造現場の品質管理にまつわるデータをリアルタイムで計測できるようになりました。結果的に、現場の異常発生を早期に検知し、品質問題が顕在化する前に迅速な対応を講じられています。
例えば、温度データのわずかな変化から配管の穴を早期発見し、大規模な故障を未然に防ぎました。また、タブレット端末による入力で手書き時代に比べて入力ミスが減少し、作業時間も短縮。数値入力時の異常値判定機能によりデータの信頼性も向上しました。
管理面では、異常値判定メール機能により、異常を即座に検知し管理者に通知することで、問題の拡大を防ぎ、アラートの履歴分析で異常の傾向把握も容易になりました。承認プロセスも大幅に改善され、全記録を一覧表示し異常値を強調表示することで、確認作業時間が大幅に短縮。過去データの参照も容易になり、傾向分析や改善活動への活用が進んでいます。
同社の具体的な品質改善事例は、以下のインタビュー記事をクリックしてご覧ください。
インタビュー記事:品質不良の未然防止をリアルタイムデータで実現。異常値検知を迅速にできた理由。
「tebiki」は、数多くの製造現場における「品質のばらつき」を解消しています
品質のばらつきを根本的に解消する「現場帳票のデジタル化」と「動画マニュアルによる現場教育」は、製造現場DXを支援する「tebiki」がいずれも提供しています。もし、品質のばらつきに影響する以下のような課題があれば、tebikiが解決の糸口になるはずです。
- 作業者によって製品の品質にばらつきがある
- OJT教育に時間がかかり、教育担当者の負担が大きい
- 紙帳票の管理に手間がかかり、データ分析に時間を割けない
- 異常発生時の対応が遅れ、損失につながることがある
「tebiki」はこうした現場の課題を解決し、品質向上と業務効率化を同時に実現するための2つのソリューションを提供しています。
1. 現場の「見える化」で不良要因を特定:「tebiki現場分析」
「tebiki現場分析」は、紙やExcelで行っていた現場帳票の記録・管理をデジタル化し、リアルタイムなデータ分析を可能にします。
▼現場帳票デジタル化サービス「tebiki」の特徴▼
| 異常値を自動検知 | 設定した正常値から外れた数値をアラートで通知し、迅速な対応を支援。 |
| データ集計・分析を自動化 | 手作業での集計・グラフ作成の手間を削減し、データに基づいた改善活動を促進。 |
| 記録・承認フローを効率化 | 申請から承認までのプロセスをスムーズにし、管理業務の負担を軽減。 |
これにより、不良傾向の早期発見、根本原因の特定、そして品質改善活動のPDCAサイクル高速化に貢献します。
tebiki現場分析に少しでも興味がある方は、以下のリンクからPDF資料をご覧ください。
>>かんたんデジタル現場帳票「tebiki現場分析」の概要資料を見てみる
2. 現場主導で教育を標準化:「tebiki現場教育」
「tebiki現場教育」は、製造業に特化した動画マニュアル作成ツールです。現場の作業員でもスマホやタブレットで簡単に撮影・編集できるため、熟練者の暗黙知を確実に伝え、教育の質と効率を飛躍的に向上させます。
▼動画マニュアル作成ツール「tebiki」の特徴▼
| 現場でかんたん撮影・編集 | 設定した正常値から外れた数値をアラートで通知し、迅速な対応を支援。 |
| 視覚的に分かりやすいマニュアル | 手作業での集計・グラフ作成の手間を削減し、データに基づいた改善活動を促進。 |
| 多言語対応 | 申請から承認までのプロセスをスムーズにし、管理業務の負担を軽減。 |
| 教育効果の可視化 | テスト機能やレポート機能で、従業員の理解度やスキルを客観的に評価。 |
これにより、教育のムラをなくし、誰でも高品質な作業を実現できる体制を構築します。技術伝承の課題解決にも大きく貢献します。
tebiki現場教育に少しでも興味がある方は、以下のリンクからPDF資料をご覧ください。
>>かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」の概要資料を見てみる
まとめ|品質ばらつき改善への継続的な取り組み
本稿では、製造現場における品質のばらつきを改善するための3つの重要なアプローチ、すなわち「作業手順の標準化と徹底」「現場教育の徹底」「データに基づいた改善活動」について解説しました。
品質のばらつきは、単一の原因によって引き起こされるものではなく、作業手順の不明確さ、教育不足、データ活用の不足など、複数の要因が複雑に絡み合って発生します。そのため、これらのアプローチを包括的に、そして継続的に実施していくことが、品質安定への近道となります。
▼「品質ばらつき」の改善策▼
| 作業手順の標準化と徹底 | 作業手順を明確に定義し、誰が行っても同じ品質を保てるようにすることで、品質のばらつきを根本から抑制します。標準化は作成して終わりではなく、現場の意見を取り入れながら継続的に改善していくことが重要です。 |
| 現場教育の徹底 | 従来の教育方法の課題を克服し、動画マニュアルなどを活用することで、技術や暗黙知を効果的に伝承します。作業者一人ひとりのスキルアップは、品質の安定に直結します。 |
| データに基づいた改善活動 | 収集したデータを分析し、客観的な根拠に基づいて改善策を立案・実行することで、より効果的な品質改善を実現します。現場帳票のデジタル化は、データ活用を推進する上で重要な第一歩となります。 |
品質ばらつきの改善は、一度きりの取り組みで完了するものではありません。変化する状況に合わせて、常に改善を続ける姿勢が重要です。PDCAサイクルを回し、継続的に改善に取り組むことで、品質の安定と向上を実現し、企業の競争力強化に繋げることができるでしょう。