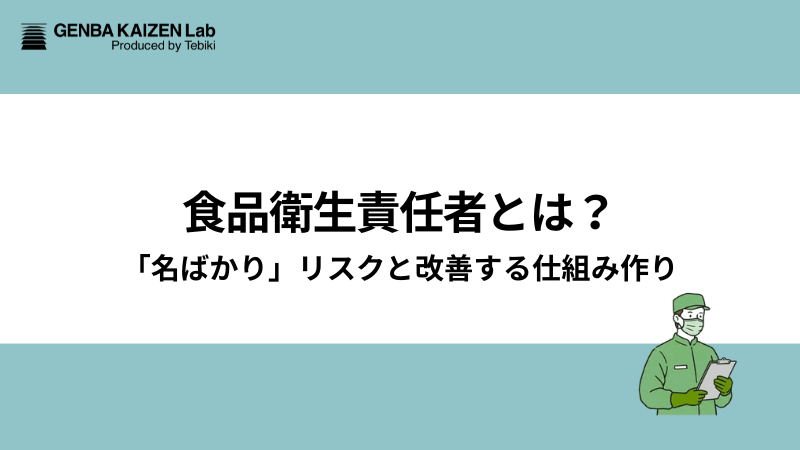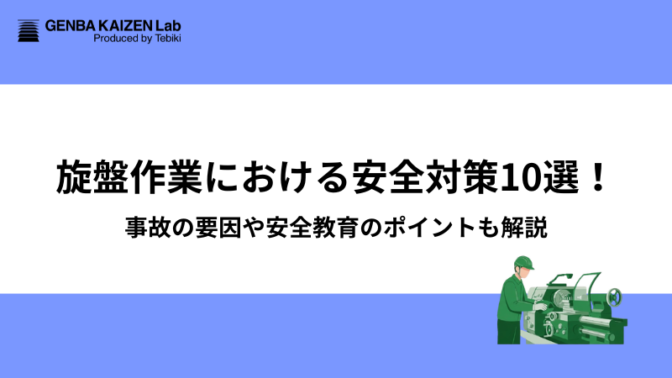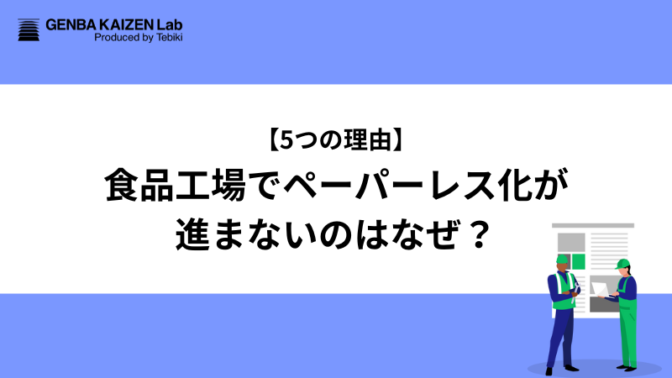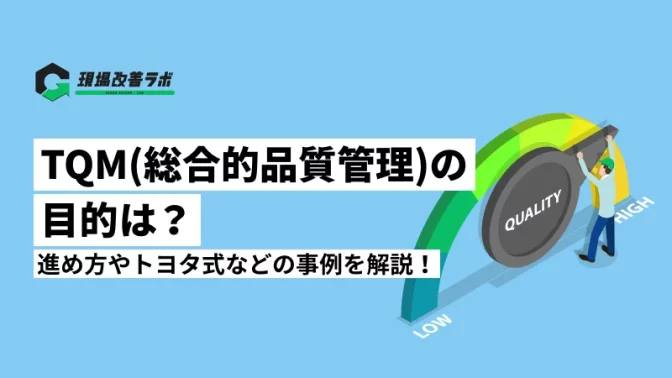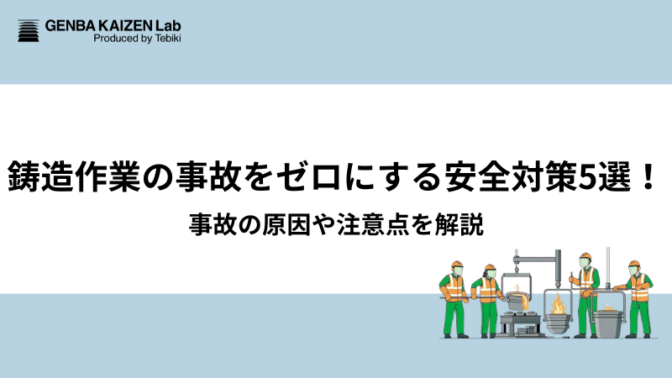かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する現場改善ラボ編集部です。
食品を扱う施設において、必ず1人以上の設置が必要な食品衛生責任者。
- 資格取得が目的で、実務に活かせていない…
- 衛生管理は形だけ。リスクと向き合えていない…
上記の悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、食品衛生責任者の概要から現場で陥りやすい“名ばかり”な実態、企業全体に振りかかる法的・経済的リスク、構築すべき体制まで詳しく解説します。
なお、現場改善ラボでは専門家による「食品衛生管理の教育方法」の解説動画を無料で公開しています。実践的なポイントを知りたい方は、以下のリンクから是非ご視聴ください。
>>HACCPに基づく衛生管理レベルを維持・改善するために行うべき「現場教育」を視聴する
目次
食品衛生責任者とは?概要や「食品衛生管理者」との違い
食品衛生責任者の基礎情報のおさらいと、混同されやすい「管理者」との違いについて解説します。
- 食品衛生責任者の基本情報
- 食品衛生責任者が働く場所とは
- 食品衛生責任者と「食品衛生管理者」の違い
なお、食品衛生責任者の現状について先に知りたい方は『現場で陥りやすい“名ばかり”食品衛生責任者の実態』をご覧ください。
食品衛生責任者の基本情報
食品衛生責任者とは、食品衛生法第51条に基づき、食品を衛生的に取り扱うために配置が義務付けられている資格者のことです。
第五十一条 厚生労働大臣は、(中略)施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。
一 施設の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。
二 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(中略)に関すること。引用元:食品衛生法 「e-Gov 法令検索」
令和3年6月より、食品を扱う全ての施設に食品衛生責任者の設置が義務付けられました。
食品衛生責任者が働く場所とは
食品衛生法に基づく営業許可が必要な施設は、基本的に配置が必要です。
- 飲食店
- 食品販売店
- 食品製造業 など
ただし、一部の業種では、より上位資格である「食品衛生管理者」の配置が求められる場合もあります。
食品衛生責任者と「食品衛生管理者」の違い
食品衛生責任者と「食品衛生管理者」はいずれも食品の衛生管理を行う資格ですが、以下の違いがあります。
| 資格名 | 食品衛生責任者 | 食品衛生管理者 |
|---|---|---|
| 配置場所 | 食品を扱う全ての施設 | 特に衛生上の考慮が必要な食品を扱う施設 |
| 取得難易度 | 易 | 難 |
| 管轄官公庁 | 各都道府県の保健所 | 厚生労働省 |
| 公的資格 | 国家資格 |
基礎情報を理解できたところで、次項では食品衛生責任者の実施できること・役割を整理します。あいまいな方は、この機会に確認しておきましょう。
食品衛生責任者のできることや役割とは?
食品衛生責任者が施設内で実施できることや役割について、「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」に基づいて解説します。
| 役割 | 概要 | 例 |
|---|---|---|
| 衛生管理 | 施設や食品の取り扱いが常に衛生的な状態で行われるよう管理する | ・施設内の清掃 ・定期的な害虫駆除 ・原材料の適切な温度での保管 |
| 従事者の健康管理 | 従業員の健康状態を把握し、 必要に応じて適切な措置を取る | ・毎日の健康チェック ・発熱、下痢、嘔吐など体調不良時の報告 ・定期的な検便検査 |
| 衛生教育 | 食品が衛生的に取り扱われるよう、 従事者に対して衛生教育を行う | ・正しい手洗い方法について ・衛生的な身だしなみについて ・施設・設備・器具の衛生管理について |
なお、従業員への食品衛生教育の進め方は以下の記事で解説しています。教育に使える無料動画もご用意しておりますので、併せてご覧ください。
関連記事:【動画で学べる】食品衛生教育の進め方!使える教材や教育事例も
食品衛生責任者資格の取り方!申し込み・参加の流れ
食品衛生責任者の資格を取得する方法について解説します。自分の状況に合った方法を選びましょう。
- 食品衛生責任者資格の取り方は2通り
- 養成講習会に申し込む
- 養成講習会の時間割
- 資格の更新は、基本的に必要なし
食品衛生責任者資格の取り方は2通り
食品衛生責任者資格の取り方は、以下の方法があります。
| 1 | 食品衛生責任者養成講習会の受講が修了した者 |
| 2 | ①食品衛生監視員・食品衛生管理者の資格要件を満たす者 ②栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士など 衛生関係法規に基づく資格を取得している者 |
1の方法については以下で詳しく解説します。2の場合、資格免許証自体が食品衛生責任者の資格を証明する書類となります。
食品衛生責任者養成講習会に申し込む
食品衛生責任者養成講習会は各都道府県で実施しています。対面での講習会以外にeラーニングを行う都道府県もあり、費用はおよそ1万円〜1万2千円です。
講習を修了すると受講修了証が交付されます。原則として全国で有効ですが、一部の地方自治体(講習時間が6時間に満たない場合など)では認められない場合があります。受講前に各自治体の条件を確認しておきましょう。
食品衛生責任者養成講習会の時間割
標準的な食品衛生責任者養成講習会の時間割は以下の通りです。
| 科目 | 時間 | 内容例 |
|---|---|---|
| 食品衛生学 | 約2.5時間 | 食中毒の原因、設備衛生、 食品の衛生的な取り扱い方など |
| 食品衛生法 (衛生法規) | 約3時間 | 法令の全体像、営業者の責務、 リコール制度など |
| 公衆衛生学 | 約0.5時間 | 環境衛生、感染症対策など |
| 確認試験 | 約0.5時間 | 理解度チェック用のテスト |
食品衛生責任者資格の更新は、基本的に必要なし
食品衛生責任者の資格は更新の必要がありません。
ただし、一部の地域では「実務講習会」が定期的に開催されており、参加が義務付けられている場合や、推奨されている場合があります。自治体例は以下の通りです。
さて、食品衛生責任者に関する基本を理解できたところで、現場に根付く課題について掘り下げて解説します。根本的な原因から具体的な解決策に至るまで詳しく見ていきましょう。
現場で陥りやすい“名ばかり”食品衛生責任者の実態
食品衛生責任者が配置されていても、営業許可を得るためだけに名義上置かれている、いわゆる“名ばかり”の状態になっているケースは少なくありません。
“名ばかり”の状態が続くと衛生上の重大なリスクを見逃すリスクを高めます。ひとたび問題が起これば、企業全体の信頼や評価に大きな影響を及ぼしかねません。
そこで、“名ばかり”食品衛生責任者が生まれる背景と構造的な課題、具体的な改善策をご紹介します。
講習会だけで終わってしまい、実務に活かせない
食品衛生責任者の講習はおおむね6時間で修了するため、習得できる知識には限りがあります。その結果以下のような課題が生じやすく、学んだ内容が実務に十分活かされないまま日々の業務に追われてしまうケースもしばしば見られます。
| 業種・規模による違い | 講習の内容が画一的な内容であるため、 自分の職場に何が必要で何が不要か判断できない |
| 理想とのギャップ | 講習で学んだ衛生管理と、実際の職場の古い設備や 狭いスペースとのギャップに直面する |
| リソースの制約 | 現場の人手不足や予算制約に縛られ、 現実的な衛生管理方法がわからない |
上記の問題を解決するための方法は主に2つです。
- 最寄りの保健所窓口への相談
- 実務講習会に参加する
特に保健所の食品衛生監視員は現場経験が豊富で、施設の状況に応じた具体的なアドバイスが可能です。また、各地方自治体では食品衛生責任者を対象とした実務講習会が定期的に開催されています。eラーニングによる受講が可能な場合もあり、継続的な学習の機会として活用できるでしょう。
パート・アルバイトに指導する時間がない
食品衛生責任者には「従事者への衛生教育」を担う役割がありますが、実際の現場では十分に行えないケースが多く見受けられます。主な理由に、以下の点が挙げられます。
- 責任者自身が現場業務で手一杯
- 人手不足により業務が常にひっ迫している
- 指導のための資料や仕組みが整っていない
上記により、パート・アルバイトが衛生管理の重要性を理解しないまま業務にあたると、食中毒や異物混入といったリスクが高まります。
衛生教育は売上への直接的な効果が見えづらいため、どうしても優先順位が下がりがちです。しかし、教育不足が原因で起きたトラブルは、企業全体の信頼や評価に大きな影響を与えます。
根本的な改善には、食品衛生責任者任せにしない教育の仕組み作りと、現場全体で取り組む衛生管理体制の構築が不可欠です。具体的な方法については『食品衛生責任者に依存しない!企業が構築すべき「衛生管理体制」とは?』で詳しく解説します。
衛生管理の形骸化
現場での衛生管理が単なる作業の一環として行われているケースも少なくありません。例えば、以下の意識が現場で見られがちです。
- 衛生管理が「チェックリストに✓をつける作業」として認識され、なぜそのチェックが必要なのかという理解が不十分
- 実際の作業や設備状況ではなく、やりやすい方法に依存する
- 「問題が起きていないから、今のままで問題ない」と捉えてしまう
- 「マニュアルは見なくても何となくわかる」と、内容を確認する習慣がない
上記の意識が積み重なると、衛生管理の形骸化を招き、食中毒や異物混入のリスク見落としにつながります。
教育では「何をするか」だけでなく「なぜするのか」を伝えることが重要です。そのうえで、誰でも見やすく実践しやすいマニュアルを整備し、現場で日常的に活用できる仕組みを作る必要があります。『現場で使われる』作業手順書のポイントについては、以下のPDF資料で詳しく解説しています。気になる方は併せてご覧ください。
>>「カンコツが伝わる!『現場で使われる』作業手順書のポイント」をチェックする
現場任せに潜む危機…企業全体に降りかかる法的・経済的リスク
衛生管理の不備による問題が発覚した場合、責任を問われるのは企業自身です。一度の違反が企業に与える影響は大きく、経営リスクにも直結します。
ここでは、違反時に生じうる具体的なリスクについて詳しく解説します。
食品衛生法違反
食品衛生法に違反した場合、営業の全部または一部を禁止・停止され、最悪の場合は営業許可が取り消されます(第60条・第61条より)。
また、行政指導に従わなかった場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)が発生する場合があります(第81条・第88条より)。
食品衛生法や違反について詳しく知りたい方は、要点が整理されている以下の関連記事をご覧ください。
関連記事:食品衛生法の要点をわかりやすく解説!改正点や違反時のリスクも
製造物責任法(PL法)違反
製造物責任法(PL法)では、故意や過失でなくても、製品に欠陥があれば損害賠償責任を負います。
例えば、食中毒や異物混入で消費者に健康被害が出た場合は、意図的でなくても損害賠償の対象です。被害が拡大すれば賠償額も大きくなり、企業の経営に深刻な影響を及ぼします。
上記の法的リスクに対応するために、企業はどのような行動を取るべきでしょうか。次項では、具体的な体制構築について解説します。
食品衛生責任者に依存しない!企業が構築すべき「衛生管理体制」とは?
食品衛生責任者を配置しているだけでは、現場の衛生管理レベルは高まりません。ここでは、食品衛生責任者に依存しすぎない、実効性ある衛生管理体制を築く方法について解説します。
- 衛生管理の属人化を防ぐ
- 根拠が説明できる仕組み作り
- 教育体制の標準化
衛生管理の属人化を防ぐ
衛生管理を特定の担当者や「できる人」に頼りきりにしないためには、従業員全員の衛生意識の底上げが欠かせません。まず重要なのは、「衛生管理は一部の人の仕事ではなく、全員で取り組むべきもの」という意識を共有することです。
意識を共有するために効果的な取り組みは、以下の通りです。
- 経営者自らが現場を巡回し、衛生管理の実践状況を確認する姿勢を見せる
- 衛生管理を売上や利益と同等の重要指標として扱う
- ある部署で成功した衛生管理の取り組みを、他部署でも活用する
- 毎日の朝礼で、その日の衛生管理重点ポイントを確認する
- 衛生管理に関わる業務を特定の担当者に固定せず、定期的にローテーションで全員が実施する
上記のような取り組みによって、衛生管理は「やらされるもの」から「みんなで取り組むもの」へと意識が変わり、企業文化として定着していきます。
一度に全て実施するのではなく、できることから少しずつ始めることがポイントです。継続的な取り組みを通じて、意識は徐々に変化します。
根拠が説明できる仕組み作り
日頃から実施していても「なぜそれを行っているのか」を説明できなければ、保健所の立入検査や監査で不十分と判断される可能性があります。
そこで、次のような仕組みづくりが必要です。
| 根拠の明確化 | なぜその衛生管理を行うのかを 手順と一緒に教育する |
| 理解度チェック | 従業員の衛生管理知識を確認するテストを 定期的に実施する |
| 評価制度 | 客観的に評価し、一定の基準をクリアした者に 認定を与える制度を設ける |
教育体制の標準化
衛生教育をOJTだけに頼っていると、指導者によって教え方に差が出てしまい、重要な内容が抜け落ちるリスクがあります。
そこで有効なのが、誰に対しても同じ内容を同じ順序で伝えられる「動画マニュアル」です。動画であれば、一度作成すれば何度でも繰り返し使用でき、教育のたびに人手や時間を割く必要がありません。
以下は、実際に飲食店で使用されている衛生管理の動画マニュアルです。
▼実際に使用されている動画マニュアル▼
※「tebiki現場教育」で作成
映像で実際の手順や注意点を確認できるため、文章や口頭説明よりも細かいニュアンスを理解しやすいのが特徴です。責任者が常に立ち会わなくても、動画を流すだけで教育が可能です。休憩室などで繰り返し再生するだけでも理解が深まり、教育の標準化が一層進みます。
他にも、教育内容が動画として“記録”されていることは、万が一衛生事故が発生した際の証明(エビデンス)としても機能します。「適切な教育を行っていたか」を示せることは、社内だけでなく保健所など外部からの信頼にもつながります。
動画による教育効果や導入のメリットについてより詳しく知りたい方は、以下のリンクをクリックしハンドブックをご覧ください。マンガ形式でわかりやすく解説しています。
>>3分で分かる!動画マニュアルは何に役立つの?活用ケースを詳しくみてみる(無料配布中)
動画で教育を「見える化」!現場の衛生レベルを高める管理体制とは
教育を動画で記録することで「教育の見える化」が実現でき、形式的な責任者任せの体制から脱却して、理想的な衛生管理体制の構築につながります。
とはいえ「動画の作成は難しそう」「導入に手間がかかるのでは?」と感じる方も多いのではないでしょうか。
そこでおすすめしたいのが、操作がシンプルで誰でも使いやすい動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」です。
tebiki現場教育で衛生教育をもっとかんたんに!
「tebiki現場教育」は「かんたんさ」を追求した動画マニュアル作成ツールです。
スマホやタブレットを普段から使っている方であれば、直感的に操作できるほど動画編集がスムーズ。現場で本当に必要とされる機能だけを厳選しているため、誰でも迷わず使いこなせます。
さらに、以下のような豊富な機能まで搭載されています。
| 自動文字起こし機能 | 動画内の音声は自動で文字起こし!誤字や言い回しを少し修正するだけで、手間なく字幕付きマニュアルが完成します |
| レポート機能 | 誰が・いつ・何を見たかがわかり、教育の抜け漏れを防げます |
| テスト機能 | テストで理解度を可視化!自己採点で学びを定着させます |
| 自動翻訳機能 | ボタンをタップするだけで、100か国語以上の言語に翻訳可能 |
「tebiki現場教育」の機能やサポート体制についてさらに詳しく知りたい方は、下の画像をクリックして資料をご覧ください。
tebiki現場教育で従業員教育を実施している事例
実際に「tebiki現場教育」を使って、従業員教育を成功させた事例をご紹介します。
- 飲料製造業:アサヒ飲料株式会社
- 食肉業:株式会社大商金山牧場
- 飲食業:株式会社ハングリータイガー
食品に関わる業界における動画マニュアル活用事例をもっと参照したい方は、以下のリンクからハンドブックをダウンロードしてご覧ください。
>>食品製造業での動画マニュアル活用事例をもっとみる(無料ダウンロード)
飲料製造業:アサヒ飲料株式会社
まず紹介するのは、飲料の製造販売を手がける「アサヒ飲料株式会社」の事例です。
| 課題 | tebiki導入後 |
|---|---|
| ・教育担当者の教え方にバラつきがあった ・手順書作成に時間がかかるため、後回しに… | ・バラつきのない標準化された教育が可能に! ・手順書作成工数が3分の1に減少 |
同社では、OJTを中心に人材育成を行っていましたが、「教育担当者によって教え方にバラつきがあるのではないか」という課題を感じていました。
そこで複数のツールを比較検討した結果「操作のかんたんさ」が決め手となり、tebikiの導入を決定。
導入後は、細かなニュアンスや複雑な動きまでバラつきなく共有でき、教育の標準化が実現!さらに、手順書の作成にかかる工数が約3分の1に削減され、マニュアル整備もスムーズに進んでいます。
アサヒ飲料株式会社の活用事例について、詳しくは以下のインタビュー記事をご覧ください。
インタビュー記事:OJTや手順書作成工数を大幅に削減!熟練者の暗黙知も動画で形式知化
食肉業:株式会社大商金山牧場
次に、総合食肉会社である「株式会社大商金山牧場」の事例をご紹介します。
| 課題 | tebiki導入後 |
|---|---|
| 拠点間で衛生管理の質に差がある | ・拠点ごとに異なる衛生教育が統一された ・質の高いマニュアルを水平展開し、衛生管理レベルの底上げにつながった |
同社では、FSSC22000を取得している拠点とそうでない拠点で、衛生管理教育の質にバラつきがあることが課題でした。
全拠点で教育内容を統一しようと動画マニュアルの導入を検討したものの、制作や運用のハードルが高く、一度は断念。しかし「tebiki」と出会い、その手軽さから導入を決定しました。
結果、教育担当者が付きっきりで指導する必要がなくなり、教育工数は約5割も削減!拠点ごとのマニュアルもtebiki上で一元管理できるため、質の高い拠点の内容を会社の標準として展開し、全社的な衛生教育レベルの底上げにもつながっています。
「tebikiはサポート面も手厚く、本当におすすめです!」と語る株式会社大商金山牧場の導入事例について、詳しくは以下のインタビュー記事をご覧ください。
インタビュー記事:衛生管理教育を徹底し、食肉の安全性を確実なものとするために動画マニュアルを活用!
飲食業:株式会社ハングリータイガー
最後に紹介するのは、チェーンレストラン「株式会社ハングリータイガー」の事例です。
| 課題 | tebiki導入後 |
|---|---|
| ・新しく人が入る度に同じOJTを繰り返して実施… ・従業員教育の管理ができていない | ・OJTの時間・回数の削減に成功! ・業務習熟度など教育の管理ができるようになった |
同社では、文字情報だけでは伝えきれない業務をOJTで対応していたものの、新人が入るたびに同じ内容を繰り返し指導することに非効率さを感じていました。
そんな中「現場でも動画編集が簡単にできる」という点に魅力を感じ、tebikiを導入。
導入後は、OJTの多くが「tebikiを見ておいて」の一言で完結!教育にかかる時間や回数を削減しながら、業務習熟度の向上に成功しました。
また、従業員の教育状況が可視化され、個別フォローや全体の進捗管理にも役立てています。
株式会社ハングリータイガーの活用事例について、詳しくは以下のインタビュー記事をご覧ください。
インタビュー記事:飲食業の動画マニュアル│接客の所作や動きを伝えるには動画がベスト
まとめ
食品衛生責任者とは、食品を衛生的に取り扱うために各施設への配置が義務付けられている資格者です。
おおよそ6時間の講習で取得でき、更新も不要。そのため、営業許可を得るためだけに名義上だけで、実務に関わっていない“名ばかり”の状態になっているケースも少なくありません。
こうした背景から企業に求められるのは、衛生管理を食品衛生責任者任せにせず、現場全体の衛生意識と実践スキルを底上げする仕組みづくりです。
そこで効果的なのが、誰に対しても同じ内容を同じ順序で伝えられる「動画マニュアル」。一度作成すれば何度でも繰り返し使用でき、教育のたびに人手や時間を割く必要がありません。
中でもおすすめなのが、「かんたんさ」に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」です。スマホやタブレットで直感的に操作でき、現場で本当に必要な機能だけが厳選して搭載されています。
「tebiki現場教育」について詳しく知りたい方は、以下の画像をクリックして資料をご覧ください。
出典
・食品衛生法 「e-Gov 法令検索」
・厚生労働省「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」