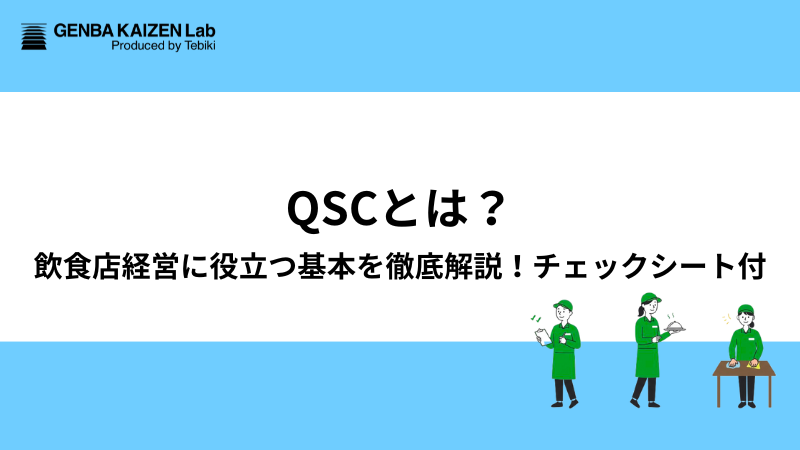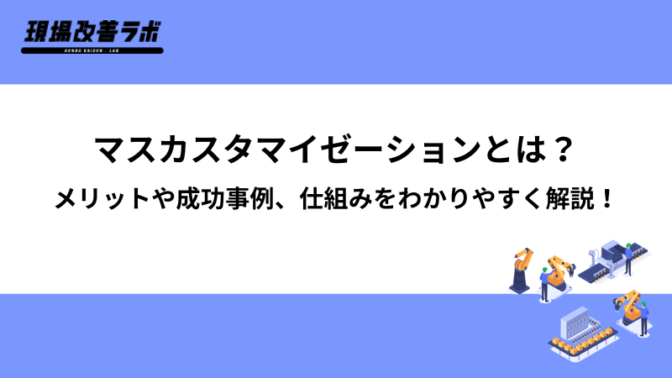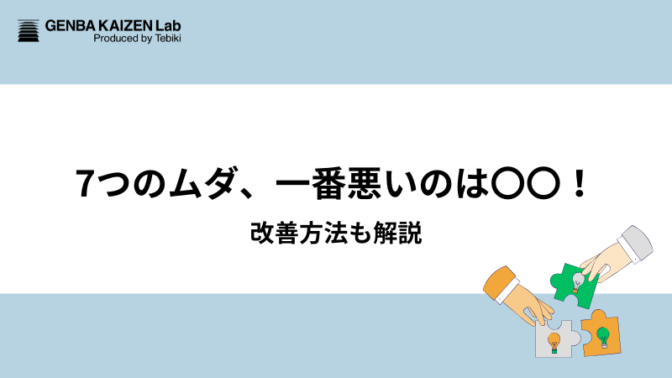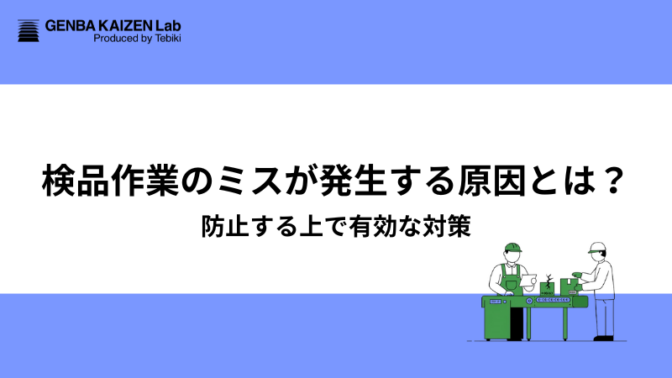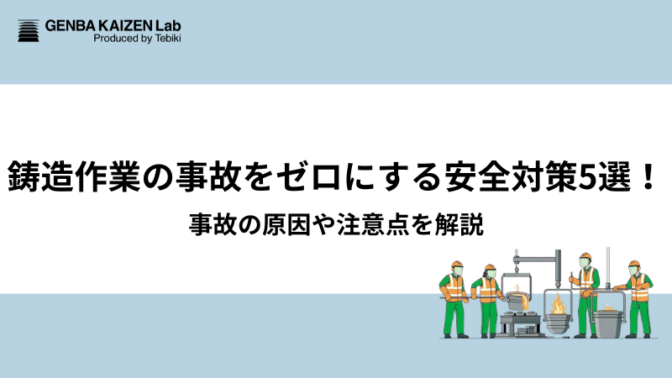飲食店の現場で使える、かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する現場改善ラボ編集部です。
QSCは、Quality(料理の品質)Service(接客サービス)Cleanliness(清潔さ)の頭文字をとった略語で、飲食店の評価やリピート率に直結する指標です。「自店のQSCレベルを高めたい」「取り組んでいるのに思うような成果が出ない」といった課題を抱える経営者やエリアマネージャーの方も多いのではないでしょうか。
本記事ではQSCの基本的な概念から、効果的な取り組み例、具体的なチェックシート、QSC向上を妨げる問題点まで、実務に役立つ情報を詳しく解説します。QSCの質を底上げするためのヒントを、是非最後までご覧ください。
目次
飲食店におけるQSCの意味とは?
QSCは、Quality(クオリティ)Service(サービス)Cleanliness(クレンリネス)の頭文字をとった略語で、飲食店が最も丁寧に取り組むべき指標です。
マクドナルドの創設者が発案したことをきっかけに、QSCは全世界へと広がりました。マクドナルドは、どの国の店舗でも同じ価値を提供するためにQSCを指標としたマニュアルを作成・徹底して成功を収めたのです。
ここからは、QSCの各要素の意味を詳しく解説します。
- Qualityとは「料理の品質」
- Serviceとは「接客サービス」
- Cleanlinessとは「店舗・従業員の清潔さ」
- QSCの発展形
Qualityとは「料理の品質」
Quality(クオリティ)とは「料理の品質」です。美味しさだけでなく、料理に関するあらゆる要素が含まれます。Qualityが不十分な場合、たとえ店舗が清潔で接客が丁寧でもリピートを促すのは難しくなります。
▼Quality(料理の品質)の具体例
- 美味しさ
- ボリューム
- 提供時の温度
- 盛り付け、見た目
- 注文から提供までのスピード
- 価格と品質のバランス
Serviceとは「接客サービス」
Service(サービス)とは「従業員の接客サービス」です。笑顔やあいさつといった基本的な対応から、気配りや臨機応変な対応力まで、顧客対応全般が含まれます。Serviceが欠けていると、従業員の態度によって来店者に悪い印象を与える可能性があります。
▼Service(接客サービス)の具体例
- あいさつや笑顔
- 言葉遣い
- コミュニケーション能力
- 臨機応変な対応力
- 行動に応じた声かけ・気配り
Cleanlinessとは「店舗・従業員の清潔さ」
Cleanliness(クレンリネス)とは「店舗・従業員の清潔さ」です。店内の清掃状況やスタッフの身だしなみなど、衛生面に関わるすべての要素が含まれます。Cleanlinessが行き届いていないと、衛生面に不安を感じさせ、料理やサービスの質が高くてもリピートには結びつきにくくなります。
▼Cleanliness(清潔さ)の具体例
- 床やテーブルなどの清掃状況
- トイレの清潔さ
- 調理器具や食器の衛生管理
- 従業員の服装・身だしなみ
- ゴミの管理や臭い対策
関連記事:一般衛生管理とは?PRPやHACCPとの違いも解説
QSCの発展形
QSCの考え方をベースに、+αの視点を加えた3つの発展形を紹介します。
| 名称 | 意味 | 具体例 |
|---|---|---|
| QSC+A | QSCに「Atmosphere(雰囲気)」を加えた考え方。居心地の良さや店舗全体の雰囲気を指す。 | ・内装やインテリアの統一感 ・業態・客層に合った照明やBGM ・店舗の雰囲気と調和した従業員の接客 |
| QSC+V | QSCに「Value(価値)」を加えた考え方。競合他社と比較した際の「選ばれる理由」を作ることを指す。 | ・独自のサービスや強みがある ・季節限定メニューなど来店のきっかけがある ・店内でコンセントやWi-Fiが使える |
| QSC+H | QSCに「Hospitality(おもてなしの心)」を加えた考え方。顧客に対する思いやりのある言葉や行動を指す。 | ・夏は冷たい水、冬は温かいお茶を提供する ・大きな荷物がある場合、「荷物をお預かりしましょうか?」と声をかける ・待ち時間が長くなりそうな場合、「お待たせして申し訳ありません」と一言添える |
ここまでQSCについて理解を深めてきましたが、「なぜ重要なのか」を知ることで取り組みの意義や定着の必要性がより詳細に見えてきます。さらに詳しく見ていきましょう。
QSCはなぜ重要?向上が必要な5つの理由
飲食店経営においてQSCがなぜ重要視されているのか、わかりやすく解説します。QSCが「最も丁寧に取り組むべき指標」と言われる理由がわかるため、是非ご覧ください。
ブランド評価に直結する
QSCは、顧客が抱くブランドへの評価に直結します。QSCが優れている店舗は「また来たい」「次も変わらず満足できそうだ」といった信頼を顧客から得やすく、ブランド価値が向上します。
さらに求職者にとっても魅力的な職場に映り、「あの店で働きたい」という意欲を引き出す要因にもなります。
顧客満足度の向上につながる
高品質なQSCを提供する飲食店は、顧客の期待を上回る体験ができ、顧客満足度が向上します。さらに店舗への信頼と愛着が深まり、定期的な再来店を促進するでしょう。加えて、良い体験をした顧客は自然に店舗を推薦するため、口コミによる新規顧客の獲得も期待できます。
従業員教育の軸になる
QSCを従業員教育の中心に置くことで、全員が共通の目標を持って業務に取り組めるようになります。指導の重点が明確になり、新人研修から継続的なスキルアップまで一貫した教育が可能です。教育の標準化が進み、人材育成もより効果的に行えるでしょう。
多店舗展開時の品質基準となる
多店舗を展開する際にQSCを共通の指標とすることで、各店の状態を可視化・比較できます。例えば、料理の質、接客レベル、清潔度を同じ基準で評価できるため、どの店が優秀でどの店に問題があるかが一目でわかります。
売上アップが見込める
QSCの向上は売上増加に直結する重要な要素です。質の高い料理、丁寧な接客、清潔な環境が整うことで顧客満足度が向上し、リピート利用や口コミによる新規来店が期待できます。
QSCの重要性を理解できたところで、次に「具体的にどのように向上させるか」を解説します。
QSCレベルを向上させる取り組み5選
QSCの向上を目指して、各要素を改善させる施策・取り組みを紹介します。現場で実践しやすく、効果が見込める取り組みを5つ厳選しました。
①料理・提供の安定化
料理・提供の安定化は、QSCのうち「Quality(料理の品質)」向上に欠かせない取り組みです。
どれほど優れたメニューを考案しても、日々ぶれなく再現されないと、顧客の満足や信頼は得られません。誰が調理・提供を担当しても、一定の基準を満たした料理を安定して提供できる体制の整備が必要です。
- 完成時の盛り付け写真を共有する
- 提供までの目標とする時間を設定する
- 定期的なスキルチェック・トレーニング
- 動画による調理工程のマニュアル化
動画のマニュアルは、文章や写真だけでは伝わりにくい細かい動作や火加減などをより正確に伝えられます。
効果・コスト・リスクの観点から、紙マニュアルとの比較や導入メリットを解説した資料を以下でわかりやすく紹介しています。ご興味のある方は併せてご覧ください。
>>「はじめての動画マニュアル作成ガイド」(PDF資料)を見てみる
②接客スキルの底上げ
接客スキルの底上げは、QSCのうち「Service(接客サービス)」向上に欠かせない取り組みです。
一部の従業員の接客が優れていても、他の従業員の対応に問題があると、店舗全体の評価は下がってしまいます。顧客は店舗単位でサービスの質を判断するため、従業員全員が一定水準以上の接客スキルを持つ必要があります。
- 基本的な接客マナーや言葉遣いを教育する
- 理想とする接客を朝礼で共有・音読する
- ミニロールプレイを従業員間で実施
言葉では伝えきれない接客はOJT頼りになりがちです。しかし動画を活用すれば、接客の表情や声のトーン、立ち居振る舞いまで共有できるため、OJTの負担を軽減できます。詳しくは『動画マニュアルは手順がそのまま伝わる』で解説しているので、併せてご覧ください。
③清掃ルールの仕組み化
清掃ルールの仕組み化は、QSCのうち「Cleanliness(清潔さ)」向上に欠かせない取り組みです。従業員1人ひとりの「清潔さ」の感覚に任せていては、清掃の質や頻度にばらつきが生じます。そこで、誰が見ても誰が担当しても同じレベルで実施できるよう、清掃ルールを仕組みとして整えましょう。
- チェックシートを利用する
- 「きれいな状態」の見本を清掃用具の近くに掲示する
- 清掃箇所ごとの方法や頻度を明確にする
以下の記事では、安全な食品を提供するために、意識改革や行動変容を促す方法を詳しく解説しています。気になる方は是非ご覧ください。
関連記事:【動画で学べる】食品衛生教育の進め方!使える教材や教育事例も
④QSCを「見える化」する
QSCを「見える化」するとは、日々のQSC状況を客観的に評価できる仕組みを作ることです。課題を把握しやすくなり、具体的な改善行動が生まれます。
- QSCチェックリストを作成し自己点検
- 従業員間での相互チェック
- アンケートを通じて顧客の声を収集
- 覆面調査でリアルな接客態度を調査
- 店舗ごとのQSC評価スコアを共有
QSCのチェックリストとは、最初は3〜5項目からでも十分に効果が期待できます。項目数が多すぎると現場の負担が増え、形骸化してしまう恐れがあるため、無理のない範囲から始めましょう。
⑤従業員満足度(ES)の向上
従業員満足度(ES)が低い状態が続くと、業務へのモチベーションが低下し、QSC向上への取り組みが形骸化する恐れがあります。さらに、企業への愛着も薄れて離職率が高まる傾向があり、十分な注意が必要です。
一方で、働きやすい環境が整うと、従業員は自発的に店舗の品質向上に取り組むようになり、結果としてQSC全体のレベルアップが実現します。
- 適正な労働時間の管理
- シフト調整の柔軟性確保
- 福利厚生の充実
- 社内資格制度の導入
- 従業員や優秀スタッフに表彰する
ここまでQSCレベルを向上させる取り組みをご紹介しましたが、向上を妨げる問題も存在します。次項では、それぞれの問題点について詳しく解説します。
QSCの向上を妨げる3つの問題点
QSCの向上を目指していても、以下の項目が不十分・適切に実施されていないと、十分に機能しません。ここからは主な要因と、どのように改善を図るべきか解説します。
- 継続的な振り返り・改善が不十分
- 明確なルールが共有・徹底されていない
- 教育しても現場で活かされない
継続的な振り返り・改善が不十分
多くの現場では、振り返り・改善が問題発生時のみ行われる場当たり的なものになりがちです。従業員が「注意されたからやる」という受け身の姿勢になると、改善行動は定着しません。また、定期的な振り返りや改善がないと、誤ったやり方や自己流の対応がそのまま習慣化してしまう恐れがあります。
重要なのは、振り返りと改善の時間をあらかじめ確保し、継続できる仕組みを持つことです。忙しい飲食店の現場でも「小さく始めて、確実に続ける」を意識することが成功の鍵となります。
明確なルールが共有・徹底されていない
QSCのレベルに店舗や従業員ごとのばらつきが見られる場合、ルールの共有・徹底が不十分であることが原因として考えられます。
マニュアルなどで明確なルールが可視化されていないと、現場任せの属人的な教育に偏り、ルールが徹底されにくくなります。その結果、サービスや品質に個人差が生じ、顧客満足度の低下を招くのです。
また、マニュアルが存在していても、内容が古い場合や現場の実情に即した更新が行われていない場合も問題の一因となります。
ポイントになるのは、繰り返し視聴しやすく、更新・改善しやすいマニュアルを作成することです。おすすめのツールを『tebiki現場教育でQSC向上を効率化!』で紹介しているので、気になる方は併せてご覧ください。
教育しても現場で活かされない
「教えているつもり」でも実際には定着していないケースには、教育の形骸化が見られます。背景として考えられる事柄は以下の通りです。
- チェックリストが単なる作業になっている
- 忙しさから従業員教育に十分な時間が割けない
- 教育の効果を具体的に評価・可視化できていない
上記の課題を解消するには、実践に即した教育と、定期的なスキルチェックを組み合わせることが効果的です。さらに教育には「誰が教えても同じ成果が得られる教育体制」、すなわち教育の標準化が必要不可欠です。
次項では、教育の標準化がなぜ重要なのか、またどのように実現すべきかについて解説します。
飲食店におけるQSCの向上には教育の標準化が重要
飲食店におけるQSC向上には「誰が教えても同じ成果が得られる教育体制」、すなわち教育の標準化が欠かせません。なぜ教育の標準化が重要なのか、またどのように実現すべきか詳しく解説します。
QSC向上に教育の標準化が重要な理由
QSCの向上において、根幹となるのは人材育成です。どれほど完璧なQSCの基準を設定しても、現場で実行できる従業員が育たなければ、基準は十分に機能しません。
飲食店におけるQSCは、従業員1人ひとりの行動によって支えられ、多くは従業員の技術や意識に依存しています。
そのため、安定したQSCを実現するには、従業員教育が欠かせません。さらに教育の標準化により、従業員全員が一定の知識とスキルを習得でき、QSCの基準が現場で機能するようになるのです。
動画マニュアルは手順がそのまま伝わる
動画マニュアルは、一度作成すれば教育の標準化を図れるだけでなく、文字だけでは伝わりにくい調理手順や接客の所作を、実際の動きとして視覚的に確認できます。
例として、実際に現場で使用されている動画マニュアルを紹介します。
▼ビールサーバーの洗浄手順|動画マニュアル▼
ビールサーバーのビールサーバー洗浄の際、ホースをはずす手順を誤ると大事故につながりかねません。
動画マニュアルなら作業手順だけでなく、ホースの脱着方法などの手の動きを含めて伝えられます。加えて、以下のようなメリットもあります。
| 繰り返し学習の促進 | 忙しい飲食店の現場では、指導者が手を離せない場合や、シフトの都合でベテランスタッフの動きを確認できないこともありますが、動画であれば何度でも繰り返し視聴して学習できます。 |
| OJTの負担軽減 | 動画を活用することで実践に近い教育が可能となり、OJTの負担を軽減できます。 |
| ルールの可視化 | 写真やイラストでは表現しきれない「動き」を動画でルール化できます。 |
しかし、動画マニュアルを作るとなると、ツールの準備や編集作業が現場の負担になってしまうケースも少なくありません。そこでおすすめなのがtebiki現場教育です。
tebiki現場教育でQSC向上を効率化!
tebiki現場教育は、動画マニュアルを誰でもかんたんに作成できるツールです。動画作成に必要な機能だけを厳選しているので、操作はシンプル。「機能が多すぎて使いこなせない…」といった迷いが生じることもありません。

実際に、従来は1時間以上かかっていたマニュアル作成が、わずか5分で完了したケースや、3ヶ月で約200本の動画を作成した事例もあり、忙しい現場でもスムーズに導入・活用できます。
さらに、現場での教育を効率化するために、以下の便利な機能も備えています。
| 自動字幕機能 | 動画の音声が自動で文字起こしされるため、音声をあとから入力する手間なし |
| 自動翻訳機能 | 100を超える国や地域の言語へボタンタップで瞬時に翻訳 |
| レポート機能 | いつ・誰が・何のマニュアルを閲覧したかなど学習のアクセス状況が見える化 |
| タスク指示機能 | 従業員ごとに特定のマニュアルの閲覧指示を出すことが可能 |
| テスト機能 | オリジナルテストが作成でき、業務内容の理解度を確認できる |
tebiki現場教育には飲食店における従業員教育に役立つ機能がまだまだ搭載されています。詳しくは以下の画像のサービスご紹介資料をご覧ください。
飲食店で教育の標準化を実現した事例
飲食店において業務マニュアルを動画化した結果、より高い成果を上げた事例をご紹介します。
OJTの工数削減|株式会社ハングリータイガー
株式会社ハングリータイガーは、オリジナルハンバーグとステーキの専門店を12店舗展開しているチェーンレストランです。
同社では従来、文字だけでは伝わりにくい業務をOJTで補っていたものの、指導するスタッフによって教え方にばらつきがあり、教育の質に差が出ることが課題となっていました。
そこで同社が導入したのがtebiki現場教育です。動画マニュアルによって実践的な業務を視覚的にわかりやすく伝えられるようになり、現場に出る前から必要なスキルを習得できるようになりました。さらに現場での対応力が向上・業務の習熟度にムラがなくなり、OJTの工数も大幅に削減しました。
| tebiki導入前の課題 | tebiki導入の効果 |
|---|---|
| 指導方法に個人差があり、教わる側の習熟度に偏りが生じていた | ・現場に出る前に必要な知識やスキルを身につけられた ・OJTの時間や回数が大幅削減 |
「tebikiは単なる動画作成ソフトではなく、社員教育ツール」と語る同社の導入事例について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
国籍を超えた教育が可能に|株式会社タイソンズアンドカンパニー
株式会社タイソンズアンドカンパニーは、飲食を軸とした幅広い事業を展開する会社です。
同社では外国人スタッフの採用を積極的に進めていましたが、現場教育において言語の壁が大きな課題となっていました。業務内容の伝達に時間がかかり、習得スピードにも差が出ていたのです。
そこで導入したのが、100ヶ国語以上に対応可能なtebiki現場教育。動画によって業務の流れや動作を視覚的に共有できるだけでなく、スタッフ自身が自国の言語で内容を理解できるため、教育の効率化が実現。
また、動画の作成・共有も直感的に操作できるため、ITに不慣れなスタッフでも扱いやすく、現場からは「簡単」「使いやすい」との声が上がっています。
| tebiki導入前の課題 | tebiki導入の効果 |
|---|---|
| 外国人スタッフに対して、教育内容がうまく伝わらない・スムーズに指導できない | ・視覚的な内容+母国語で、国籍を問わずスムーズな教育が可能に ・動画の作成からアップロードまで直感的に操作できるため、「簡単」との声 |
株式会社タイソンズアンドカンパニーの事例を知りたい方は以下の記事もご覧ください。
インタビュー記事:ワイン、ビバレッジ、コーヒー・紅茶の製造工程や、ビールサーバーの洗浄方法などの飲食店の業務を動画で伝達し、教育レベルを底上げ。
まとめ
QSCは以下の頭文字を取った略語であり、飲食店が最も重点的に取り組むべき指標です。
- Quality(クオリティ):料理の品質
- Service(サービス):接客サービス
- Cleanliness(クレンリネス):店舗・従業員の清潔さ
QSCの向上には人材育成が不可欠です。いくら優れた基準を設定しても、現場で実行できる従業員が育っていなければ、基準は十分に機能しません。
そこで効果的なのが動画マニュアルの活用です。動画マニュアルなら、「誰が教えても同じ教育が可能」になり、教育の標準化が図れます。また、文字だけでは伝わりにくい調理手順や接客の動作を、実際の動きとして視覚的に確認できるため、理解度が格段に向上します。
なかでもtebiki現場教育は操作がかんたんな動画マニュアル作成ツールです。必要な機能に絞られているため使いやすく、学習成果を確認できるテスト機能や、100ヶ国語以上に対応する自動翻訳機能も搭載。多様な現場で活用されています。
さらに詳しい機能やサポート体制については、以下の画像をクリックして資料をご覧ください。
おまけ:飲食店におけるQSCのチェックリスト
飲食店におけるQSCの基本的なチェックリストは以下の通りです。自店の業態や運営方針に応じて、必要に応じた調整やカスタマイズを行いましょう。
Quality(クオリティー:品質)チェック項目
・適正な食材管理ができている
・季節メニューやバリューメニューの提案など工夫がされている
・料理を正確に適切な時間で提供している
Quality(料理の品質)のなかでも特に重要なのは食材管理です。どれだけ調理やメニューに工夫を凝らしていても、食材が劣化していては意味がありません。衛生面・鮮度の両面において、徹底した管理体制の構築が不可欠です。
Service(サービス:接客)チェック項目
・水を出したり、注文をお伺いするタイミングが適切である
・わかりやすく説明するコミュニケーション能力がある
・好感を与える注文の復唱・確認をしている
・行動に応じた声かけをしている
・メニュー・料理の提供の仕方が丁寧である
・商品や店舗に対する知識がある
Service(接客サービス)は、来店から退店までの一連の流れに沿ってチェック項目を設定するのが効果的です。接客対応を段階ごとに可視化することで、スムーズで一貫性のあるサービスが実現し、顧客満足度の向上につながります。
Cleanliness(クレンリネス:清潔)チェック項目
・目にふれる場所にゴミなどを集めていない
・机上や椅子、床、壁などに汚れがなく清潔感がある
・雑誌やインテリアなどの整理整頓が行き届いている
・食器や調味料入れなど、清潔感がある
・厨房は整理整頓され、清潔に保たれている
Cleanliness(清潔さ)は厨房を含めた店舗全体の衛生管理を指します。顧客はもちろん、従業員にとっても快適で清潔な環境を保つことが重要です。日常的な清掃と衛生意識の徹底を心がけましょう。