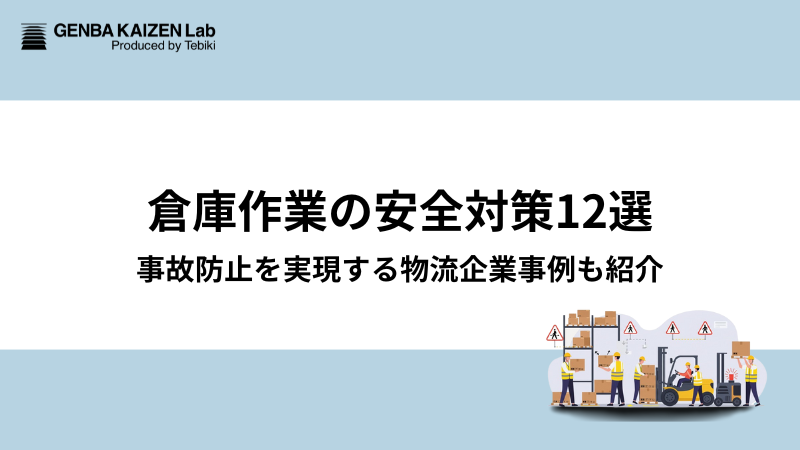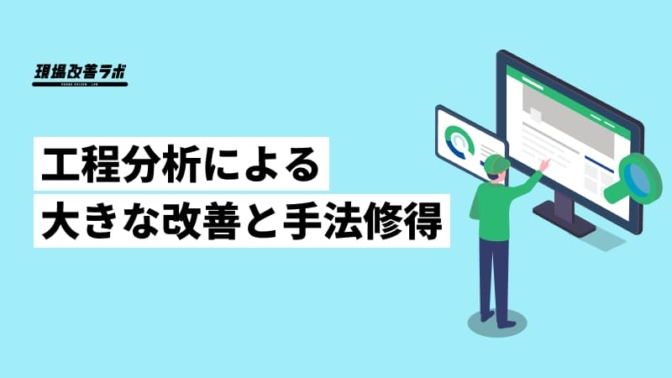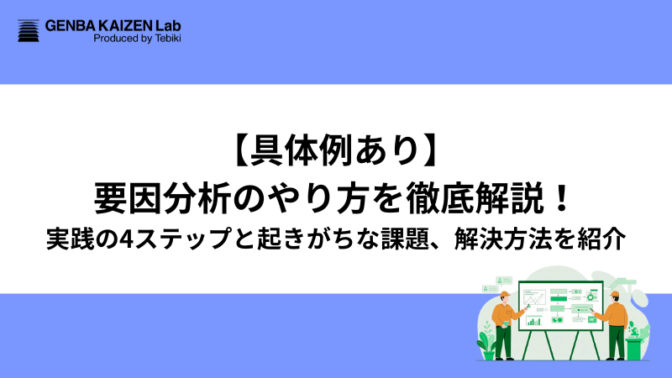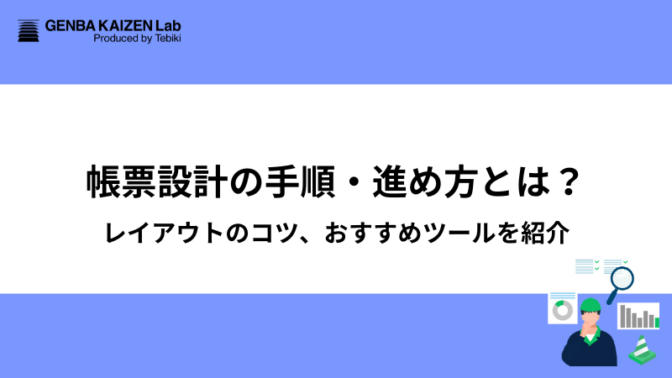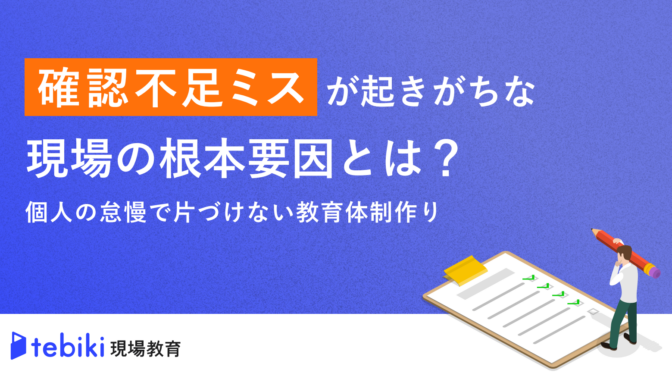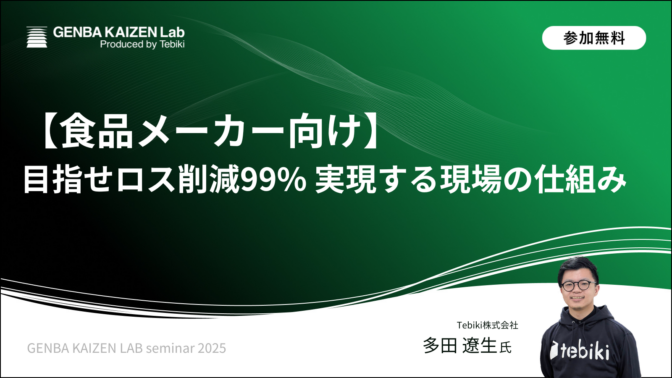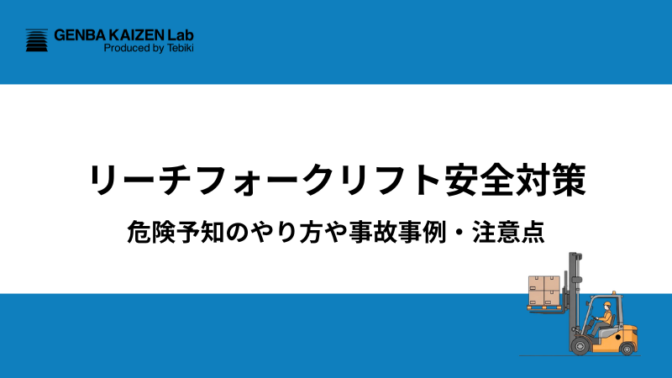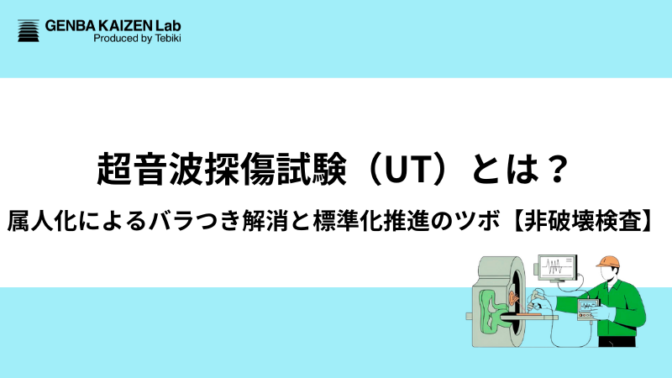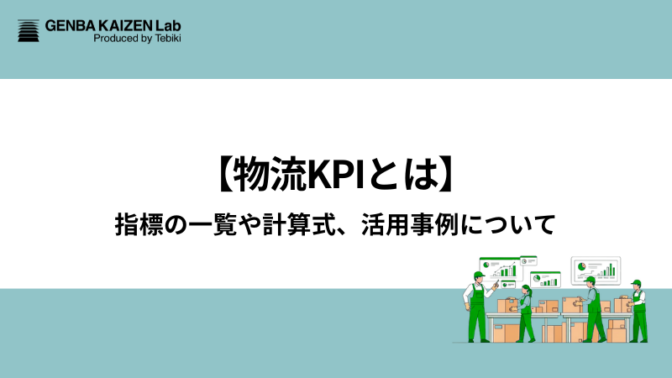物流倉庫の安全教育・対策に役立つかんたん動画マニュアル「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
倉庫や物流の現場には、日常の作業の中にさまざまな危険が潜んでいます。重大な事故の裏には数多くの「ヒヤリハット」が存在し、見逃せばいずれ大きな事故や労働災害につながりかねません。事故を未然に防ぐためには小さな問題や違和感を放置せず、「教育」と「設備・ルール」の両面で安全対策を講じることが重要です。
本記事では倉庫作業に潜む危険とともに、事故や災害の未然防止につながる安全対策を紹介します。
なお、近年では安全教育の手段に「動画マニュアル」を採用する企業が増えています。動画を用いた安全教育は現場における危険な行為や状況を視覚的に伝えられるため、従業員の安全意識を効果的に高めることができます。
動画を活用した安全教育の事例や活用の効果については、本記事のほか以下の資料でも詳しく解説しています。ゼロ災達成に向け、是非お役立てください。
>>物流業の事例から学ぶ!動画マニュアルを使った安全教育の取り組みと成果についてみる
目次
倉庫作業に潜む危険や事故の一覧と事例
1件の重大事故には29件の軽傷事故と300件の無傷事故があるという「ハインリッヒの法則」が示すように、事故や災害は日常に潜む小さな危険の積み重ねから生まれます。
倉庫・物流の現場でも同様に、些細なミスや不注意、環境の変化が思わぬ事故につながることがあります。具体的にどのような危険が潜んでいるのか、ここでは倉庫作業で起こり得る事故の事例を紹介します。
具体的な安全教育や安全対策の事例を参照し、自社での対策に取り入れたい方は以下の資料をご覧ください。
>>具体的な安全教育/安全対策の取り組みや成果を確認されたい方はこちらをクリック!
転倒・転落
倉庫内外では、雨で濡れた床やトラックヤードで作業を行うときに、足を滑らせて転倒するリスクがあります。また作業環境が十分に整備されていない場合、床にある段差や電源コード、緩衝材などの障害物につまずいて転倒しそうになるケースも少なくありません。
さらに荷台に乗って荷物の積み降ろしをする際には、バランスを崩してトラックから転落する恐れもあります。高所での作業では「もしも」を想定した安全対策が不可欠です。
このような「もしも」を想定するには、日頃から現場に潜む危険を意識させ、「危険への感受性」を高めることが有効です。そこでKYT(危険予知訓練)を行っている現場も多い一方、文章や写真での説明ではイマイチ伝わらずに形骸化しやすいという声もよく耳にします。
現場の危険をわかりやすく伝え、従業員の危険感受性を高める「次世代型KYT」について以下の資料で詳しく説明しているため、現場での効果的な安全対策をお探しの方は是非ご覧ください。
>>労災ゼロ!形骸化したKYTから脱却する「〇〇」を使った次世代のKYTをみてみる
挟まれ・巻き込まれ
倉庫内ではフォークリフトの走行中、車両と壁との間に作業員の体が挟まれたり腕や足が巻き込まれたりする危険性があります。発進の際に指差呼称を怠り、他の作業員の位置や周囲の安全を十分に確認しないまま走行したことが主な原因として挙げられます。
特に荷物の積み込みや検品作業員との会話など、他の作業に気を取られたときに安全確認が不十分となり、挟まれ・巻き込まれ事故が起きやすくなることに注意が必要です。
このような「気のゆるみ=不安全行動」は慣れや疲労だけが原因ではありません。不安全行動が繰り返されてしまう背景や安全ルールを現場に浸透させる対策については、以下の資料で詳しく展開しています。本記事と併せてご覧ください。
>>繰り返される不安全行動に終止符を!行動科学から編み出す「決定的な防止網」をみてみる
落下物
商品のピッキング作業ではフォークリフトや台車を使って倉庫内を動き回るため、振動や衝突によって高い位置にある棚から商品が落ちてくるリスクが高まります。背景には商品を保管する際に適切な固定措置を取らなかったり、走行ルートが狭くて車両が通りづらかったりと、ルールの不徹底や倉庫内の導線に問題があります。
また、フォークリフト走行中の急ブレーキによって積載していたパレットが落下し、近くで作業をしていた従業員に衝突した事故も発生しています。
関連記事:フォークリフトの安全対策8例!事故を防止した改善事例や安全意識を高める方法も解説
フォークリフトによる接触や負傷
他にも倉庫内では、走行中のフォークリストが他の作業員に衝突し怪我を負う事故が発生しています。死角の多い走行ルートや作業員同士の合図不足により、後退してきた車両に接触したり、車輪に足を踏まれるケースがあります。
加えて作業エリアの区分けが不十分で車両と歩行者の動線が重なることや、現場でのコミュニケーションが足りていないことも事故の要因です。
※フォークリフト安全対策の詳細は以下の記事でも紹介しています。
▼関連記事
・フォークリフトのヒヤリハット事例集と対策まとめ!危険予知の事例もあわせて解説
・フォークリフトの安全対策8例!事故を防止した改善事例や安全意識を高める方法も解説
フォークリフトは倉庫内作業に欠かせないツールである一方、ひとたび事故が発生してしまうと怪我だけでなく生命を脅かすような大惨事に発展しかねません。そのため、フォークリフト運転で避けるべき行動や事故防止対策をわかりやすく伝える「安全教育」が現場の安全を左右するといえます。
従業員の安全意識に働きかける「安全教育・対策事例」を以下にご用意しておりますので、事故防止に向け是非お役立てください。
>>ゼロ災を目指す!安全意識を高めるフォークリフトの安全教育・対策事例集をみてみる
熱中症
夏場の倉庫は高温多湿の環境になりやすいうえ、荷物の積み込み・積み降ろしなど屋外での作業も多いため、熱中症のリスクが高まります。
倉庫内の空調設備が十分に整っておらず、作業員も休憩や水分補給を後回しにした場合には、めまいや立ちくらみ、吐き気といった熱中症の初期症状が現れることがあります。しかし、作業に集中しているときは自分の不調を認識しにくく、気づいたときには重症化しているケースも少なくありません。
加えて暑さによる体調不良は判断力や集中力の低下を招き、ヒューマンエラーの発生リスクも高まります。例えばフォークリフトの操作ミスや荷物の取り違え、足元の不注意による転倒など、普段なら起こらないようなミスが増える傾向にあります。
熱中症対策は体調管理だけでなく、こうしたヒューマンエラーを防ぐためにも重要です。作業中のこまめな休憩や水分補給、異常を感じた際の早めの報告を徹底し、体調の変化を軽視しない意識づくりが求められます。
>>ヒューマンエラーによる労災を未然防止する対策について知りたい方はこちらをクリック!
感電
倉庫で使用する電動工具のコードが劣化していたり、水気のある場所で機械を操作した場合には感電のリスクがあります。特に手や足が濡れていると人体に電気が通りやすくなるため、電気器具を使用する際は水や汗をよく拭き取ることが重要です。
また、コードやプラグの損傷、定格電力を超えた使用(タコ足配線)により、漏電の危険性も高まります。漏電は感電や火災の原因となり、重大な事故につながる恐れがあります。
こうした労災は設備や機器そのものの不具合だけでなく、従業員の不安全行動によって発生するケースも多く見られます。例えば、「少しぐらいなら大丈夫」と濡れた手のまま電源を入れたり、劣化したコードをそのまま使い続けたりする行為は典型的な例です。
安全ルールが形だけになり日常の中で慣れや油断が生じると、わずかな行動の誤りが大きな事故につながります。現場では正しい取り扱い手順を繰り返し教育し、不安全行動を放置しない風土づくりが不可欠です。
従業員の不安全行動を再発防止する仕組み作りの進め方や事例については、以下の資料をご参照ください。
>>繰り返される不安全行動に終止符を!現場ルールを浸透させる方法や好事例をみてみる
有害物質
有害物質による健康被害は、化学品や危険物を扱う特殊な倉庫だけの事例ではありません。一般的な倉庫でも、内燃機関を持つエンジン式フォークリフトを長時間使用したことにより、作業員が一酸化炭素中毒となった事例があります。
原因は換気の不備であり、倉庫の出入り口を完全に閉め切った状態で長時間の作業を行っていたことで空気中の一酸化炭素濃度が徐々に上昇し、作業者が気付かないうちに危険なレベルに達していたことが考えられます。また、一酸化炭素中毒に対する理解が不足していたことも災害につながった要素でしょう。
このような労災は設備や環境の問題だけでなく、ヒューマンエラーが原因となることもあります。例えば、「少しぐらいなら大丈夫」と換気を怠ったり、体調の異変を軽視して作業を続けるといった判断ミスが事故を引き起こすことがあります。正しい知識と危険予知の意識を持ち、ヒューマンエラーを防ぐ行動を徹底することが求められます。
>>ヒューマンエラーによる労災を未然防止する対策について知りたい方はこちらをクリック!
火災
倉庫内には大量の可燃物を保管しているケースが多く、ひとたび火災が発生すれば甚大な被害に発展する恐れがあります。火災の原因としては、電気機器の故障や過熱、たばこの火の不始末、さらには荷物の自然発火などが挙げられます。
加えて、消火設備の未整備や通報体制の不備が被害拡大の一因となるケースもあり、日頃の点検や火元管理、作業員の火災予防意識が重要です。
さらに火災の多くは設備の不具合だけでなく、従業員の不安全行動によって引き起こされることも少なくありません。例として決められた喫煙所以外での喫煙、使用後の電気機器の電源切り忘れ、可燃物の近くでの溶接作業など、ちょっとした気の緩みや慣れが重大な火災につながります。
安全対策は設備面の整備だけでなく、従業員一人ひとりが「自分の行動が火災を防ぐ」という意識を持ち、日常の作業の中で不安全行動をなくすことが何より重要です。
>>従業員の不安全行動を再発防止する具体的な対策や好事例について知りたい方はこちらをクリック!
倉庫作業の安全対策は「教育」と「設備・ツール」の2本柱
ここまで紹介してきたように、倉庫作業には転倒や落下、機械との接触、有害物質による健康被害といったさまざまな危険が潜んでいます。これらの事故の多くは、安全意識の不足や作業環境の不備が原因となって発生しています。
事故や災害を未然に防ぐためには、倉庫作業の安全対策を「教育」と「設備・ツール」の両面から進めることが重要です。具体的には、安全教育を通じて標準作業の徹底や危険に対する知識の習得を行うと同時に、現場の設備やツールを見直し、危険を最小限に抑える環境を整える必要があります。
また、安全対策は一度で終わるものではありません。対策を講じたあとは一定期間ごとに効果を測定し、継続的な見直し・改善を行うことが大切です。これにより現場の変化や新たなリスクに対する柔軟な対応が可能となり、安全な作業環境の維持につなげられます。
倉庫作業の安全対策【教育面】
ここからは倉庫作業における具体的な安全対策を紹介していきます。
教育面では、倉庫作業の正しい手順やルールを伝えるとともに、危険な行為や禁止事項を認識させる安全教育が不可欠です。具体的には以下のような対策が考えられます。
- 作業標準化がなされる仕組み作り
- 安全教育のためのマニュアルや手順書整備
- 危険予知(KY)活動の実施
- ヒヤリハット事例や報告書の共有
- 外国人労働者やパートタイム作業員の教育体制整備
- 5S活動の実施
- 指差呼称や声かけのルール化
作業標準化がなされる仕組み作り
労災や事故は、「正しい手順とは異なる手順で、作業がなされる」場合に発生します。つまり作業標準化がなされる仕組みを、現場に作れるかどうかが、安全対策の鍵を握ることは重々承知かと思います。
大事なのは、あくまで「仕組み」を根付かせる点です。例として、テーブルマーク株式会社では「操作する機械の近くにQRコードを設置し、QRコードをタブレットで読み込むと、機械の操作方法が動画でその場で確認できる」ような仕組みを整備しています。
▼機械に貼られたQRコードを読み込み、動画マニュアルを確認する様子▼
QRコードを読み込み、動画マニュアルを確認する様子-1024x576.png)
こうした取り組みによって、「誰が担当しても正しい手順で作業を遂行できる」体制が構築されています。ゆえに、新人作業員や経験の浅いパートタイムの方も標準手順で業務を進められるのです。
また、読み込むマニュアルも映像化されているので、文字の読み込みは最低限で済んでいるのも、動画マニュアルの強みです。
物流業界における動画マニュアルの活用事例や活用イメージについて、より理解を深めたい方は以下の資料も併せてご覧ください。
>>>「~製造業・物流業の事例から学ぶ~動画マニュアルを使った安全教育の取り組みと成果」を見てみる
安全教育のためのマニュアルや手順書整備
倉庫作業の安全を守るには、各工程の標準作業をまとめたマニュアルや手順書が欠かせません。作業ごとのリスクを明確にし、安全に作業を進めるための標準化された手順・ルールを徹底させることが重要です。
とはいえマニュアル整備の重要性はわかりつつも、なかなか整備する時間が取れず取り組めずにいる、という物流企業は多いです。特に紙マニュアルは作成も更新も労力がかかりやすく、加えて内容が見にくいことから「現場で活用されない」問題に悩まされる企業は少なくありません。
そこで昨今では、紙マニュアルよりも手軽に整備しやすい「動画による安全教育」も導入されつつあります。
例えば、近鉄コスモスではフォークリフト操作の禁止事項を解説する動画マニュアルを作成し、誤った操作や危険な行為に対する注意喚起を行っています。
▼動画によるフォークリフト安全教育の例▼
※「tebiki」で作成
上記で作成している動画は、物流業界に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を活用して作成されています。スマホ1つで気軽に撮影が可能で、マニュアルの内容によっては撮影から編集まで10分程度で完結し、多くの物流企業で導入されています。
動画マニュアルを安全教育に活用している事例をより詳しく知りたい方は、物流業界における安全教育の事例をまとめている資料もご覧ください。以下のリンクをクリックすると資料をダウンロードできます。
>>「~製造業・物流業の事例から学ぶ~動画マニュアルを使った安全教育の取り組みと成果」を見てみる
危険予知(KY)活動の実施
危険予知(KY)活動とは、業務前に「どのような危険が潜んでいるか」を作業者同士で話し合い、危険要因への対策を一人ひとりが実践していく取り組みです。
事故や災害の多くはヒューマンエラー(人為的ミス)に起因し、特に「業務に慣れてきた頃」に起こりやすくなります。業務に関わる全員が毎日の作業にKY活動を組み込むことで、作業員一人ひとりの危険に対する意識が高まり、現場全体で安全を先取りする姿勢が養われます。
特にKY活動のなかで用いられる具体的な手法であるKYT(危険予知訓練)は、安全を守るうえで重要な取り組みです。一方で、「文字情報だと何が危険なのかイマイチ伝わらない…」「また同じテーマになり、マンネリ化してしまった…」と、形骸化しているという声もよく耳にします。
この形骸化したKYTから脱却し、作業員の危険感受性を本当に高めるための新しい手法として、近年「動画KYT」が注目されています。形骸化を防ぎ、KYTを再び「生きた活動」にするための動画KYTとは何か、その具体的な進め方について以下の資料で詳しく解説しています。
>>労災ゼロ!形骸化したKYTから脱却する「動画」KYTのメリットや実際のサンプル動画をみる
ヒヤリハット事例や報告書の共有
倉庫作業の各工程には、重大な事故に直結する一歩手前の危険(ヒヤリハット)が隠れています。作業員が経験したヒヤリハットは事故の予兆となる重要な情報であり、こうした事例を記録・共有することで、現場全体での再発防止につなげられます。
ただし、作業員によっては「些細なことだからわざわざ報告する必要はない」と考える人もいます。こうした意識があると、小さな問題や違和感が見逃され、結果として大きな事故や災害を引き起こす恐れがあります。これを防ぐには「気づいたら共有する」文化を根付かせ、現場全体で報告しやすい雰囲気をつくることが大切です。
外国人労働者やパートタイム作業員の教育体制整備
安全教育は倉庫作業に関わる全員を対象に実施するべきです。自社の正社員やベテラン作業員だけでなく、外国人労働者やパートタイム作業員も含め、全員が安全教育を受けられる体制をつくる必要があります。
このような教育体制を整備するには、倉庫作業の「動作」を動画で可視化し、標準的な作業手順や禁止事項を実際に見てもらうのが効果的です。文字や言葉だけでは伝えづらい情報も、動画マニュアルを活用すれば正しい動作や危険な行為をわかりやすく、効率的に伝えることができます。
5S活動の実施
安全な職場づくりの基本となるのが、5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)活動の実施です。業務に不要なものを片付けずに放置していると、転倒や挟まれなどの事故につながる恐れがあります。倉庫内の事故を予防するためには、5S活動によって作業環境を改善し、危険の芽を早期に取り除くことが大切です。
5S活動の具体的な実践方法を知りたい方は、以下のリンクをクリックし専門家による「5Sの正しい進め方」の解説動画をご覧ください。
>>ただの片付けで終わらせない!安全な現場の基礎を作る「5S活動」の進め方や具体例をみてみる
指差呼称や声かけのルール化
倉庫作業で発生する事故は、作業員の確認不足やコミュニケーション不足に起因するものが多く、指差呼称や声かけのルール化・習慣化が有効な対策となります。
例えば、フォークリフトを操作する前に「前方ヨシ!」と指を差しながら確認したり、荷物を積み降ろすときに「降ろします!」と声をかけたりと、作業の要所要所で指差呼称や声かけを行うことで事故のリスクを減らせます。
倉庫作業の安全対策【設備・ツール面】
設備・ツール面の安全対策では、危険を未然に回避できる仕組みを整えることが重要です。倉庫内の構造や環境を整備し、根本的に「事故が起こりにくい」状態をつくることが作業員の安全確保につながります。
具体的には以下のような対策が考えられます。
- 作業動線の見直し
- 安全設備の導入
- 保護具の導入
- 倉庫内の環境改善
- システム導入による作業負担の軽減
作業動線の見直し
倉庫内では「歩行者とフォークリフトの通路が交差する」「無駄な移動が多くてあちこち歩き回っている」といった作業導線の問題が起こりがちです。事故を防ぐには走行ルートやレイアウトを見直し、危険を回避する適切な動線を設定する必要があります。
作業導線の改善には、以下のような見直しが有効です。
| 改善策 | 内容 |
|---|---|
| 動線の分離 | 歩行者とフォークリフトの通行ルートを明確に分ける |
| 通路幅・スペースの確保 | 通路幅や作業スペースは十分な広さを確保する |
| レイアウトの最適化 | 出荷頻度の高い商品を出荷口付近に配置する |
| ロケーションの最適化 | 重い商品は下段、軽い商品は上段に配置する |
安全設備の導入
倉庫内では高い位置にある棚から商品が落下したり、台車に積載した荷物が荷崩れしたりするリスクがあります。こうした事故を防ぐためには、棚や商品をしっかりと固定する器具や、台車の荷崩れを防ぐ落下防止装置の導入が有効です。また、作業エリアの区切りとして安全柵を設置することで、作業員とフォークリフトの動線を分離し、接触事故のリスクを減らせます。
安全設備の導入は形式的に行われがちですが、正しい使い方を説明する資料や動画を用いて、その重要性を現場でしっかりと共有することが重要です。
保護具の導入
安全設備と同様に、保護具の導入も安全対策の基本となります。どれだけ対策を講じても突発的な事故をゼロにするのは難しく、そのときに作業員の体を守る「最後の砦」となるのが保護具です。安全靴やヘルメット、手袋、安全帯といった保護具の着用を徹底させることで、倉庫内の危険から身を守ることができます。
保護具を正しく機能させるためには、作業員の体に合った適切なサイズの保護具を支給し、定期的に破損や劣化をチェックする点検を行う必要があります。形だけの対策にならないよう、現場での確実な着用が徹底されているかも含めて管理することが大切です。
倉庫内の環境改善
倉庫内の作業環境は、現場で働く作業員の安全と健康に大きく影響します。照度や温度が適切でない倉庫では、作業員の判断ミスや体調不良が起こりやすくなり、思わぬ事故にもつながりかねません。照明や空調の調整、換気の確保など、倉庫内の環境を整えることで作業員の集中力が保たれ、作業の安全性も高まります。こうした環境改善は事故の予防だけでなく、現場のモチベーションや作業品質の向上にも寄与する施策です。
システム導入による作業負担の軽減
目視でのピッキングや検品作業は、長時間にわたる立ち作業や繰り返し動作によって体力的な負担が大きく、集中力の低下や判断ミスを招きやすくなります。こうした疲労やストレスが原因で、事故や災害の危険が高まるケースも少なくありません。
こうしたリスクへの対策として有効なのが「作業のシステム化」です。ハンディターミナルやデジタルピッキング、WMS(倉庫管理システム)などの導入は、作業の効率と正確性を高めるだけでなく、作業員の負担を軽減する安全対策としても大きな役割を果たしています。
【事例】倉庫作業の安全対策で労災を未然防止している物流企業
ASKUL LOGIST株式会社
ASKUL LOGIST株式会社は、「安全」をすべてに優先させることを行動指針とし、全国15拠点の物流センターで安全対策に取り組んでいます。同社では、短時間勤務者、外国籍スタッフ、障がいを持つスタッフなど多様な人材が活躍しており、誰にでも確実に安全ルールを伝え、理解してもらうことが課題でした。
従来のOJTや紙マニュアルによる教育では、内容のバラつきや理解度の差が生じやすく、特に危険な動作や注意すべきポイント、言語の壁などが安全教育の障壁となっていました。そこで同社は、動画マニュアル「tebiki現場教育」を全拠点で導入。労働安全衛生法に基づくリスクアセスメントを重視し、安全な作業標準を動画で整備しました。
▼実際に作られた動画マニュアルの画面▼
実際に使われる動画マニュアル.jpg)
tebikiを活用し、腰に負担のかかる作業姿勢など、紙では伝わりにくい危険な動作を視覚的に分かりやすく解説。図形の挿入や字幕、自動翻訳機能により、国籍や言語、個人の特性に関わらず、全ての従業員が安全に関する情報を正確に理解できるよう工夫しています。さらに、ヒヤリハット事例の共有やKYT(危険予知トレーニング)にも動画を活用し、現場の状況に近い臨場感で危険への感受性を高め、安全意識の向上を図っています。
これにより、導入教育や繰り返し教育の工数を大幅に削減しつつ、安全で標準化された作業を実現しています。
同社の詳しい事例は、以下のインタビュー記事でご覧いただけます。
インタビュー記事:従業員数3,500名超・全国15拠点で動画マニュアルtebikiを活用!
※tebikiの詳しい機能や活用イメージがまとめられた資料はこちら
株式会社ロジパルエクスプレス
株式会社ロジパルエクスプレスでは、物流現場における安全品質の向上と事故・ヒヤリハットの削減を重要な課題と捉えていました。従来は拠点ごとに紙のマニュアルが作成されており、ルールや作業手順にバラつきが生じていました。
また、紙媒体では「荷物の積み上げは胸の高さまで」といった安全基準の微妙なニュアンスが正確に伝わりにくく、認識の違いから事故につながるリスクがありました。
これらの課題を解決するため、同社は動画マニュアル「tebiki現場教育」を全拠点の従業員約300名を対象に導入しました。tebikiを活用することで、安全に関するルールや正しい作業手順を、動画を通して全拠点で統一し、明確に伝えることが可能になりました。特に、危険な箇所や注意すべきポイントを視覚的に示すことで、従業員一人ひとりの安全意識と理解度を高めています。
具体的な取り組みとして、社内の事故防止強化月間に合わせ、フォークリフトの危険予知トレーニング(KYT)や商品の取り扱いルールに関する安全教育動画を作成し、tebiki上で全拠点に配信しています。
現場ではこれらの動画教材を活用し、忙しい業務の合間でも効果的な安全教育を実施。動画によって業務上の危険性が具体的に伝わりやすくなり、安全品質意識の向上につながっています。また、マニュアルへのアクセス性が向上したことで、必要な時にすぐに安全手順を確認できる環境も整備されました。
同社の詳しい事例は、以下のインタビュー記事でご覧いただけます。
インタビュー記事:動画で全拠点の安全品質意識の向上と業務ノウハウの可視化を達成
※tebikiの詳しい機能や活用イメージがまとめられた資料はこちら
株式会社フジトランス コーポレーション
株式会社フジトランスコーポレーションは、港湾運送や倉庫業など多岐にわたる物流サービスを提供する中で、働き方改革の一環として安全教育の質の向上と標準化に取り組んでいます。
同社では、特にフォークリフト作業など「動き」を伴う業務において、講師による指導のニュアンスの違いや受講者の受け取り方の差が課題でした。また、安全教育用の動画を内製しようとしても、従来の編集ソフトでは作成負担が大きいという問題も抱えていました。
これらの課題に対し、同社は動画マニュアル「tebiki現場教育」を導入。安全衛生推進部が中心となり、安全衛生教育会で使用する関連法令の解説やリスクアセスメント教育、具体的な作業手順などの教材をtebikiで作成・活用しています。
動画を用いることで、正しい作業の「動き」や危険なポイントを視覚的かつ具体的に示すことが可能となり、教える側と教わる側の認識のズレを大幅に減らすことができました。
tebikiはパソコン操作に不慣れな熟練講師でも直感的に扱えるため、現場の知見が詰まった質の高い安全教育コンテンツを効率的に作成できます。作成された動画は、全従業員が繰り返し視聴でき、教育内容の標準化に貢献しています。
また、作業者が標準作業から逸脱していないかを確認するための振り返りツールとしても活用されています。さらに、多言語自動翻訳機能により、増加する外国人労働者に対しても、言語の壁を越えて安全ルールを正確に伝えることが可能になりました。これにより、教育工数を削減しつつ、より効果的で均質化された安全教育を実現しています。
同社の詳しい事例は、以下のインタビュー記事でご覧いただけます。
インタビュー記事:働き方改革の手段としてtebikiを活用。複数の部門で工数の効率化を実現!
※tebikiの詳しい機能や活用イメージがまとめられた資料はこちら
まとめ
本記事では倉庫の事故につながる様々な危険と、それらを防ぐための具体的な安全対策を解説しました。安全な職場環境の実現には、「教育」と「設備・ツール」という2つの柱を立て、継続的に改善することが不可欠です。
形骸化したルールやマニュアルを見直し、動画の活用などで「伝わる」安全教育を実践することが、従業員一人ひとりの危険感受性を高めます。この記事を参考に明日からできる安全対策に取り組み、労働災害ゼロの現場づくりに是非お役立てください。
本記事でご紹介した動画マニュアル作成ツール「tebiki」については、以下の画像から詳細な機能や導入事例をご覧いただけます。倉庫作業の安全対策をお探しの方は是非ご参照ください。