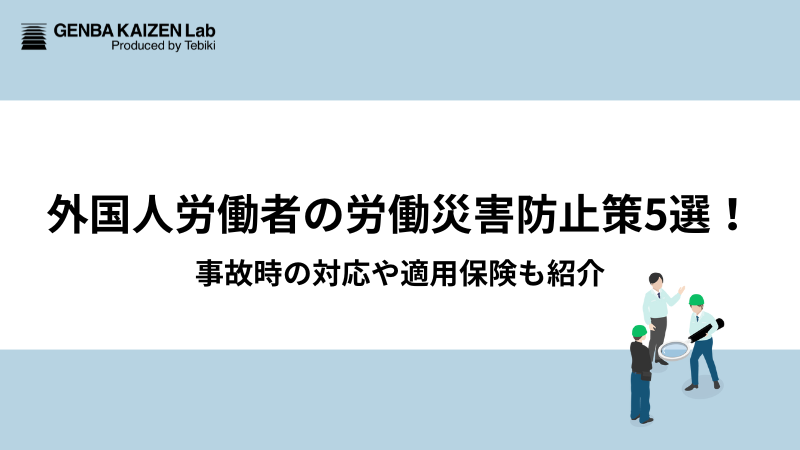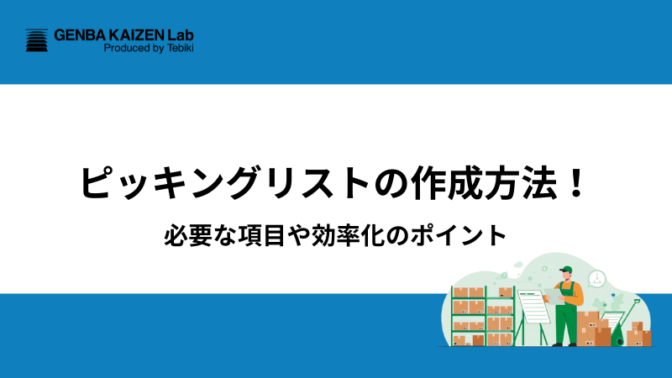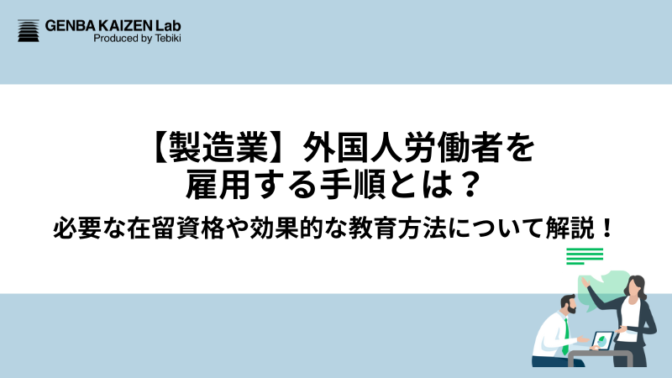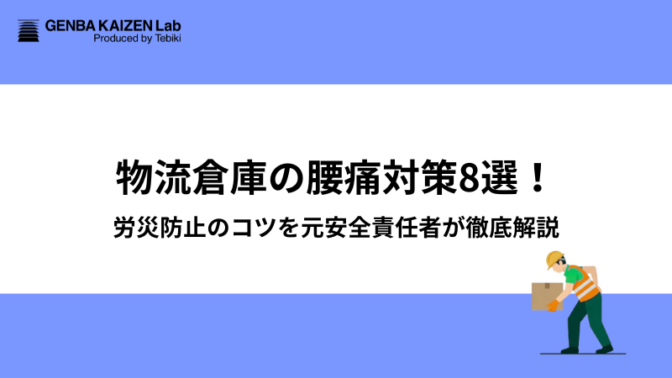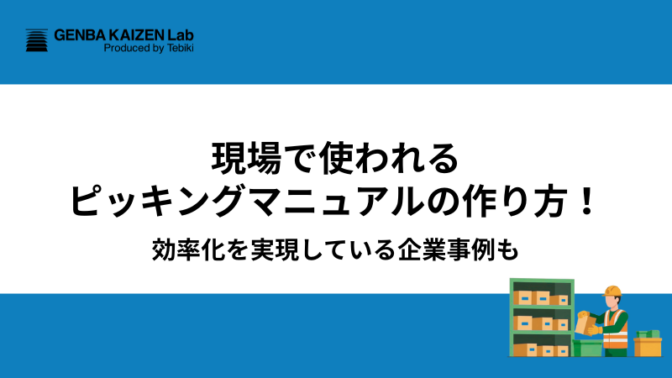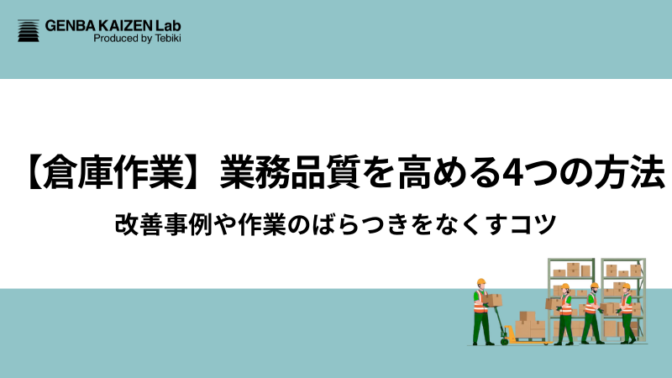近年、外国人労働者の増加とともに労働災害の危険性が指摘されています。この記事を読んでいる方は、以下のような悩みを抱えているのではないでしょうか。
- 「外国人労働者の労災リスクと事例について知りたい!」
- 「労働災害の予防策や安全対策について知りたい!」
- 「労災保険制度の変更や改正に対応し、法的問題を回避したい!」
そこでこの記事では、外国人労働者が直面する労働災害の現状や労働災害が発生しやすい理由、事故発生時の適切な対応方法や保険の種類も紹介します。また、労災防止に向けた対策についても紹介します。
外国人教育は、文字に依存しない「非言語マニュアル」整備が鍵を握ります。その手段として広く導入されているのが「動画マニュアル」です。
特に多国籍人材が所属する製造業や物流業では動画マニュアル×外国人教育の導入が進んでいますが、詳しい導入事例や改善効果は「外国人労働者に「伝わらない」を解決した動画マニュアル活用事例集」を参考にしてみてください。
>>「外国人労働者に「伝わらない」を解決した動画マニュアル活用事例集」を見てみる
目次
外国人労働者の労働災害発生状況
厚生労働省の「令和5年 外国人労働者の労働災害発生状況(※1)」によると、2023年の労働災害による外国人労働者の死傷者数は5,672人で、前年と比べ864人増加しています。
また、日本人を含む全労働者の死傷年千人率は2.36であるのに対し、外国人労働者のみの場合は2.77と高い傾向があります。とくに技能実習では4.10、特定技能では4.31と倍近い数値であることからも、外国人労働者は日本人の従業員以上に労働災害の被害に遭うリスクがあるといえるでしょう。
また、業界別の死傷者数で見ると製造業が48.3%、建設業が17.6%と、現場産業のような業種で外国人労働者による労災が多く発生している様子が伺えます。
製造業の場合、日本人の従業員を含んでも労働災害の発生が多い傾向にあるため、安全第一を担保するための安全対策が不可欠といえます。
関連記事:工場の安全対策10選と好事例を解説!製造業の安全宣言例も紹介
外国人労働者が労働災害に遭いやすい3つの理由
前章で外国人労働者が労災の被害に遭いやすいことが分かりましたが、その理由として大きく以下の3つが考えられます。
- 業務経験が浅い
- 日本語能力のバラツキで言語の壁がある
- 職場の危険をうまく伝達できない
※外国人教育は、文字に依存しない「非言語マニュアル」整備が鍵を握ります。その手段として広く導入されているのが「動画マニュアル」です。
特に多国籍人材が所属する製造業や物流業では動画マニュアル×外国人教育の導入が進んでいますが、詳しい導入事例や改善効果は「外国人労働者に「伝わらない」を解決した動画マニュアル活用事例集」を参考にしてみてください。
>>「外国人労働者に「伝わらない」を解決した動画マニュアル活用事例集」を見てみる
業務経験が浅い
外国人労働者が労災に遭いやすい理由の1つは「業務経験の短さ」にあります。
とくに技能実習生など経験が浅い従業員は、業務手順の理解度が進んでいないことで、業務に潜む危険やリスクへの対応能力が身についておらず、労働災害に遭ってしまう可能性が高いです。
実際、群馬労働局健康安全課による経験期間別の労働災害発生状況(※2)では、2019年から2023年に労働災害に遭った外国人労働者928人のうち、経験期間が1年以内の事故が543人と半数以上にものぼります。
日本語能力のバラツキで言語の壁がある
外国人の日本語能力を示す指標として日本語能力試験がありますが、業務の場合「N2レベル(日常場面、幅広い場面で使われる日本語をある程度理解できる)」が求められるでしょう。しかし外国人にとって、N2レベルの日本語習得は難易度が高く、人によって日本語力のバラツキがあります。
このような言語の壁は、業務指示の内容や安全衛生に関わるコミュニケーションを阻害します。
安全性が担保されている業務手順だとしても、正しく理解されていないことで、手順不遵守による労働災害のような安全トラブルが生じやすくなってしまいます。
関連記事:外国人労働者の言語問題はどう解決する?具体的な対処法や事例、おすすめのツールを紹介!
職場の危険について伝達できない
前述の言語の壁にも通じますが、このようなコミュニケーションの課題は業務指示以外にも、安全衛生教育の理解が進まないといった弊害もあります。
職場には目に見える顕在的な危険だけでなく、「見えないけれども、実際にはあるかもしれない」「トラブルが発生しやすいから、いつもより注意が必要」という潜在的な危険もあります。
このような潜在的な危険は、安全衛生教育の内容を理解していなければ事故を未然に防ぐことが難しく、外国人労働者の労働災害を引き起こす理由の1つです。
これら3つの理由をまとめると「言語の壁によって業務理解が進まず、経験の浅さも相まって労働災害が起きやすい実態」があるといえるでしょう。このような実態に対し、言葉の壁を解消しつつ業務理解を進める教育手段として、動画マニュアルを活用する事例が増えています。
以下の資料では、外国人労働者に「言葉や意図が伝わらない」を動画マニュアルで解決した事例をまとめて紹介しています。労働災害の防止事例もあるので、ぜひご覧ください。
>>「外国人労働者に「伝わらない」を解決した動画マニュアル活用事例集」の資料を見てみる
外国人労働者の労働災害対策5選
外国人労働者の労働災害を防ぐためには、以下のような対策を検討しましょう。
- 母国語で安全教育を学べる体制を整備する
- 業務マニュアルの多言語対応
- 動画で視覚的に不安全行動を伝える
- 安全標識を多言語対応する
- 通訳を一時的に依頼する
※外国人教育は、文字に依存しない「非言語マニュアル」整備が鍵を握ります。その手段として広く導入されているのが「動画マニュアル」です。特に多国籍人材が所属する製造業や物流業では動画マニュアル×外国人教育の導入が進んでいますが、詳しい導入事例や改善効果は「外国人労働者に「伝わらない」を解決した動画マニュアル活用事例集」を参考にしてみてください。
>>「外国人労働者に「伝わらない」を解決した動画マニュアル活用事例集」を見てみる
母国語で安全教育を学べる体制を整備する
外国人労働者が労働災害に遭ってしまう背景に「言葉の壁」があるため、一番の理想は従業員の母国語で安全教育を学べる体制を整備することでしょう。
母国語で安全教育を学ぶことで、正しい知識と意識が定着し、従業員自身が危険を認識できるようになることが期待できます。このような体制を整備する手段として、動画マニュアルを用いるケースが多いです。
多国籍の従業員を抱えるASKUL LOGISTICS株式会社では、安全教育の標準化を目的に動画マニュアルを活用しています。同社が動画マニュアル活用で使用しているツール、tebiki現場教育は動画マニュアルの字幕を100ヶ国以上の言語に自動翻訳することが可能です。
ASKUL LOGISTICS株式会社のより詳細な取り組み事例は、こちらのインタビュー記事をご覧ください。
なお、同社以外でも外国人の安全教育、安全意識向上にむけて動画マニュアルを活用する企業は多くあります。以下の資料では、外国人教育に動画を活用している企業の事例をまとめているので、あわせてご覧ください。
業務マニュアルの多言語対応
前述のような「母国語で学べる体制」の手段として、現状使われている業務マニュアルを翻訳して多言語対応するという手もあるでしょう。複雑な動作や危険な動作が少ない業務、特定の国籍に偏っている職場であれば有効な手段です。
一方で、多国籍の外国人労働者を抱える職場の場合、多言語対応の工数が業務を圧迫する恐れがあります。マニュアルの新規作成や改訂が多い職場の場合、多言語対応は向いていない場合があるため注意が必要です。
製造業の新日本工機株式会社では、業務マニュアルそのものを「動画化」し、従来発生していた多言語対応の工数をゼロにしているようなケースもあります。
インタビュー記事:人が育つ環境づくりとして動画マニュアルtebikiを活用。技術の蓄積と作業品質の安定を実現。
動画で視覚的に不安全行動を伝える
複雑な動作や危険な動作は、文字や口頭でイメージすることが難しいです。
外国人の労働者による労災が多い製造業を例とすると、製造現場はヒト・モノ・機械など、あらゆる「モノ」の動きが業務ノウハウです。このような動きを文字や写真など、二次元的な情報で理解するのは日本人でも限界があります。
そこで不安全行動を「動画マニュアル」で見せることで、具体的に何が危険なのか?イメージを補完することができます。

安全対策に動画マニュアルを活用する方法や効果、具体的な事例は以下のガイドブックで詳しく解説しているので併せてご活用ください。
>>「安全意識が高い製造現場はやっている! 動画マニュアルを活用した安全対策事例」を見てみる
安全標識を多言語対応する
外国人労働者の安全を確保するためには、安全標識の多言語対応が効果的です。
職場の安全標識は危険を知らせたり、安全な作業手順を指示したりするための重要な手段です。言語の壁で情報が伝わらないと、本来の効果を発揮できずに労働災害のリスクが高まる恐れがあります。
このような事態を回避するには、英語や中国語、ベトナム語など労働者の母国語を含む多言語の標識を導入することが有効です。結果として、労働者は標識の意味を正確に理解し、事故の発生率が低下すると考えられます。
通訳を一時的に依頼する
新たに配属された外国人労働者が多い場合、一時的に通訳者を依頼することも効果的です。通訳を交えることで、労働者に対して伝えたい内容を母国語で伝えることが可能です。
通常のOJTや座学は通訳を交えて、実際の業務では前述のような動画マニュアルを活用するといった運用方法であれば、外国人労働者の業務理解を助け、結果的に新人の事故を減らすことにもつながるでしょう。
通訳を依頼する場合、該当業務もしくは業界に対して一定の知見を持つ人にお願いする方がよいでしょう。知見がない場合、こちらが伝えたいポイントを正確に伝えられるか分からず、誤った内容で理解されてしまう危険があります。
本章では外国人労働者の労働災害対策として、主要な5つをご紹介しました。ご紹介した中でも、特にオススメしたい手段が「動画マニュアルの活用」です。次章以降では、労災防止に動画マニュアルが有効な理由や、実際の活用事例などを詳しく解説します。
外国人労働者の労災防止には「動画マニュアル」が有効
前章でも記載しましたが、外国人労働者の労働災害対策として「動画マニュアル」は有効的な手法の1つです。実際に、製造業や物流業など、外国人を多く受け入れている事業所で動画マニュアルの活用事例が増えています。
ここからは、動画マニュアルの有効性や実際の活用事例、主要ツールなどを解説します。
外国人の労災防止に動画マニュアルが有効な理由
外国人を受け入れる際、最も壁となるのが「言語の違い」です。
普段の業務で使用する日本語によるコミュニケーションでは、外国人の日本語能力によって内容の理解度が大きく変わります。また、分かりやすい日本語表現を心がけても、優しい日本語で業務内容を正確に伝えられるかはトレーナーの言語化力に依存するといえるでしょう。
言葉を使用する座学やOJT、文書マニュアルは安全な動作を正確に伝えられるとは限りません。動画マニュアルであれば、正しい動作を視覚的に伝えつつ、〇や✕といった言語の違いが影響しない記号も用いることで、外国人労働者の理解を助けることができます。
▼動画マニュアルのサンプル▼
tebiki現場教育で動画マニュアルを活用すれば、日本語字幕を100ヶ国以上の言語へ自動翻訳できます。また、一部言語は自動音声による読み上げ機能にも対応しているため、外国人労働者は安全にまつわる内容を母国語で学ぶことができます。
実際に動画マニュアルを活用している企業事例
実際に、動画マニュアルを活用している事例としてASKUL LOGIST株式会社をご紹介します。同社は、事業所向け通販サイト「ASKUL」および個人向け通販サイト「LOHACO」の物流・配送機能を担う物流会社です。
物流センターでは、多様な人材受け入れの一環で外国籍スタッフを採用しているため、外国人労働者に対する導入時教育・安全教育に課題を抱えていました。
▼動画マニュアル活用インタビュー:ASKUL LOGIST株式会社▼
導入時教育として、OJTやパワーポイントによるマニュアル/手順書整備を行っていたものの、以下のような状況に陥っていました。
- OJTトレーナーによって、内容の濃さや教える内容のバラつきがあった
- 辞書のような分厚いマニュアルが大量に作られてしまい、新人が1日で理解するには限界
- 導入時教育が上手くいかないことで、作業中に何度も説明する教える側の負担が発生
言語の問題や文化の違いも相まって、導入時教育や安全教育の内容が伝わらない実態を解決する手段として「動画マニュアル」を活用しています。動画マニュアルの活用を各センターで推進したことで、以下のような改善効果を実感されています。
- 外国人スタッフの業務理解度が向上
- 導入時教育、倉庫内の繰り返し教育の工数が大幅に削減
- 均質化された同じ教育を受けるので業務の標準化に繋がった
同社の動画マニュアルを活用した安全衛生の取り組みは、厚生労働省が運営するSAFEコンソーシアム(※3)による「2023年度アワード:安全な職場づくり部門」で表彰されています。具体的な取り組み内容は、以下のインタビュー記事をクリックしてご覧ください。
インタビュー記事:従業員数3,500名超・全国15拠点で動画マニュアルtebikiを活用!
「外国人教育」を目的に活用されている動画マニュアルツール
ASKUL LOGIST株式会社のように、外国人従業員に対する人材育成・安全衛生教育の推進を目的に活用されているツールが、かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」です。
tebiki現場教育は、主に以下の特長や機能を搭載しているため、外国人労働者の業務理解度・安全意識向上によって、労働災害対策を効果的に行えます。
- シンプルな画面で直感的に操作が可能
- 動画をわかりやすくする図形テンプレートあり
- 音声認識による自動字幕生成機能
- 100ヵ国語への自動翻訳機能
- 習熟度を確認できるテスト機能
- 閲覧指示ができるタスク機能 など
業務やOJTの様子、従来の座学を撮影するだけで、動画マニュアルがほとんど完成。編集作業もかんたんで、紙マニュアルと比べて作成時間が1/3まで削減できたという声もいただいています。
さらに一部のご利用プランでは、スキルマップ作成機能も搭載しています。安全というトピックスにおいて、自社の現場で必要な項目の理解度がどれほど進んでいるか?個人ごとに進捗状況を把握する使い方も可能です。
tebiki現場教育のより詳細な機能やプラン、導入効果は、以下の画像をクリックして概要資料をご覧ください。
外国人労働者に労働災害が起きた場合の対応
外国人労働者に労働災害が起きた場合の対応としては、以下の3つが考えられます。
- 病院で適切な治療を受けさせる
- 労災手続きを行う
- 再発防止対策を行う
病院で適切な治療を受けさせる
外国人労働者に労働災害が発生した場合、まずは迅速に病院での治療を受けさせることが重要です。労災保険は国籍や雇用形態を問わず利用することができるため、被災者は費用の心配をせずに必要な治療を受けられます。
このとき、企業は外国人労働者が言葉の壁に阻まれず、正確な症状を伝えられるよう通訳の手配や同行支援を行うべきです。
例えば、工場で働く外国人労働者が機械に手を挟んでしまった場合はただちに病院へ搬送するほか、日本人スタッフが同行して症状の説明や手続きの支援を行うことがおすすめです。結果、コミュニケーションによる齟齬を回避して正確な治療を受けさせることができ、早期の職場復帰を目指せます。
労災手続きを行う
製造業において外国人労働者が労災に遭遇した場合、適切な手続きを迅速に行うことが不可欠です。ここでは2つの手続きを解説します。
- 労働者死傷病報告をする
- 労災保険の給付申請を行う
労働者死傷病報告をする
労働者が労災により休業する日数が4日以上、または死亡した場合、企業は速やかに労働基準監督署宛てに労働者死傷病報告を行う必要があります。また、休業4日未満の場合は、3ヵ月ごとに発生した労働災害をまとめて報告する必要があります。(※4)
労働者死傷病報告は労災保険給付に必要な情報であり、外国人労働者が適切な補償を受けるために企業が行う法的義務です。製造現場では外国人労働者が多く、言葉の壁や文化の違いにより労災のリスクが高まることがあります。そのため、報告書の正確な提出は労働者の権利を守り、企業の社会的責任を果たすために不可欠です。
労災保険の給付申請を行う
労災による怪我や病気で治療を受けた場合、外国人労働者は療養補償給付や休業補償給付などの保険給付を申請することが可能です。労災保険の給付は外国人労働者が早く回復し、生計について支援するために設けられています。
製造業では労働者が機械や設備による怪我を負うリスクがあります。そのため、労災保険の給付申請は労働者の経済的負担を軽減し、安心して治療に専念できるようにするために重要です。
とくに外国人労働者は労災保険の存在を知らなかったり、書類が複雑かつ難しい日本語で記載されていることで苦労してしまうケースも多く見受けられます。労災保険の給付申請を行う際は、事業者も間に入りサポートしながら行うとよいでしょう。
再発防止対策を行う
再発防止対策は事故を発生させないために欠かせない取り組みである他、1度の事故が企業の財務状況、従業員の士気、そして企業イメージに長期的な悪影響を及ぼす可能性があるため早急な対策が求められます。
再発防止に向けた具体的な施策については、本記事内の「外国人労働者の労働災害対策5選」をご覧ください。
外国人労働者に適用される保険や注意点
ここでは、外国人労働者に適用される2つの保険について紹介します。
- 労災保険
- 健康保険
適用される2つの保険
労災保険
労災保険とは、業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・障害または死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。労災保険は外国人労働者にも日本人労働者と同様に適用されます。
労災保険の休業補償や補償申請後に事業主が行う対応については、以下の記事内で詳しく解説しています。
関連記事:労災保険とは?事業者に必要な対応や補償の種類、手続きの流れを解説
健康保険
健康保険は、突然の病気やケガによって生じる経済的な負担を加入者同士で支え合うことを目的としている公的な医療保険制度で、外国人労働者に適用されます。健康保険法はすべての労働者に対して平等に適用されるため、外国人労働者も例外ではありません。
しかし、健康保険は業務外での傷病や休業、出産や死亡時の補償を目的としているため、労災保険とは異なり労働災害が発生した際は使えないということを押さえておきましょう。
保険の対象には注意が必要
労災保険と健康保険には様々な違いがあるため、注意が必要です。まず、労災保険が労働災害発生時に使用する制度であるのに対し、健康保険は労働災害の発生時には使えないということが大きな違いです。
次に、保険適応の対象が異なるという点も大きな違いです。労災保険はアルバイトや正社員といった違いに関わらず適用され、極端な例では不法就労者も含めた労働者全員が対象となる制度です。
一方で、健康保険は在留資格や労働条件によって適用となる対象者が異なります。日本に住民登録があり(在留資格が3ヵ月以上)他の健康保険に加入していない外国人は健康保険の加入ができます。
しかし、以下の条件にあてはまる方は加入できないので注意してください。
- 学生(休学中、夜間学生をのぞく)
- 1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、同一事業所/同一業務を行う一般社員の3/4未満
- 週の所定労働時間が20時間未満
- 2ケ月を超える雇用の見込みがない
- 月額賃金が8.8万円未満
【まとめ】外国人労働者の安全意識を高めて労災防止
外国人労働者は、言語の壁や経験不足から労災の発生率が高いという事実があります。
短い業務経験、日本語の理解不足、コミュニケーションのギャップ、企業の隠蔽傾向などが労働災害を引き起こす要因となります。
労災が起きた際には、適切な治療と労災手続きが不可欠です。労働者死傷病報告の提出や労災保険の給付申請は、被害を受けた労働者にとって重要であり、何よりも重要なのは再発防止対策を講じることであり、物的または人的の両方に対する措置が含まれます。
外国人労働者の労働災害を未然に防ぐためには、複数言語の標識の使用や包括的な安全衛生教育の実施が効果的です。しかし、紙マニュアルやOJTによる教育だと危険度が十分に伝わらないという課題があります。こうした課題を解決するには動画マニュアルが効果的です。
tebiki現場教育であれば、動画マニュアルを軸として外国人労働者が母国語で業務内容や安全衛生教育を学べる体制を整備できます。ASKUL LOGISTICS株式会社では、tebiki現場教育を活用した安全教育を推進し、厚生労働省が運営するSAFEコンソーシアムでアワードを受賞しています。
外国人労働者の労働災害対策の手段として、tebiki現場教育の活用をご検討ください。
※1:参照元「厚生労働省 令和5年外国人労働者の労働災害発生状況」
※2:参照元「群馬労働局健康安全課 経験期間別の労働災害発生状況」
※3:参照元「厚生労働省 SAFEコンソーシアム 2023年度アワード」
※4:参照元「厚生労働省 労働者死傷病報告の提出の仕方を教えて下さい。」