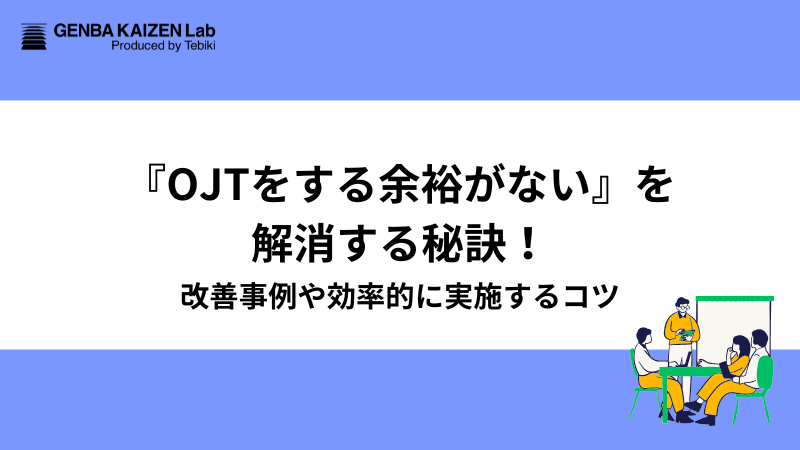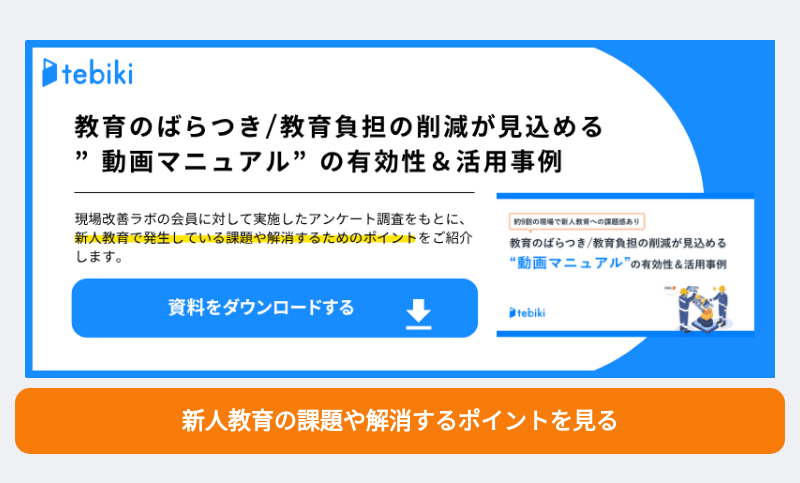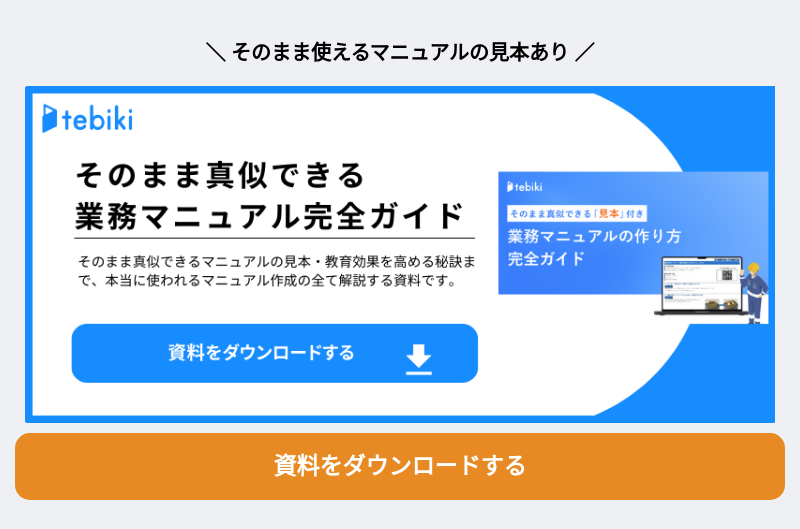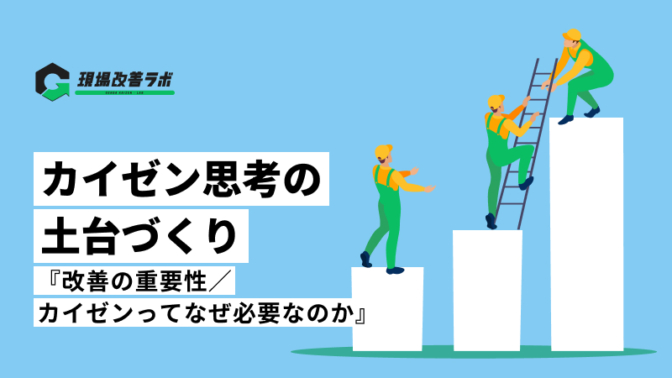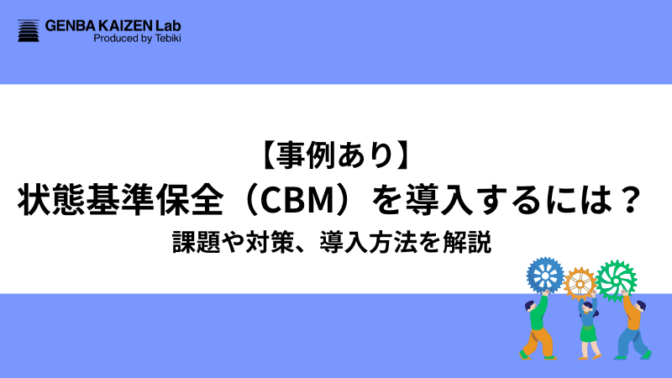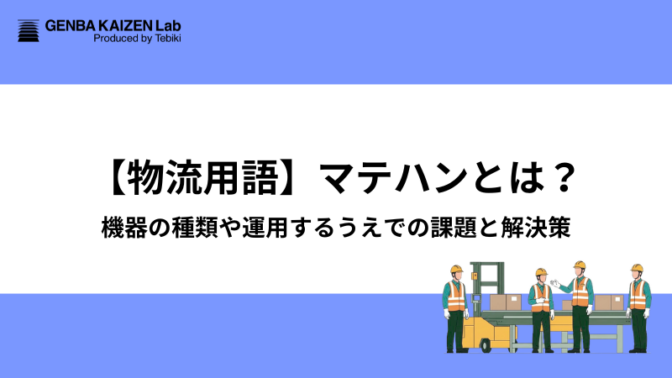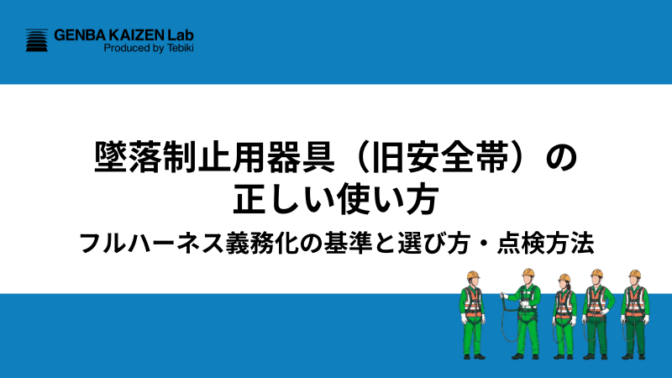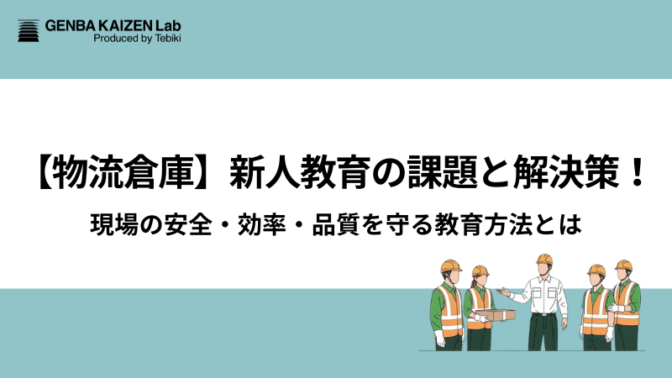かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
新人や若手社員を対象に実施するOJT。本来であればしっかりと時間を確保して充実した教育体制を構築する必要がありますが、中々実施する余裕がない方も多いのではないでしょうか?
この記事では、OJTをする余裕がないと感じている職場が取り組んでいる改善事例や、OJTを効率化できる教育手法について解説します。
OJT教育は正しい手順や技術が伝わりやすい一方、教育担当者の負担が大きく、現場全体の生産性に影響を及ぼしているケースは少なくありません。「OJT担当者の負担が激減する、OJT教育の新常識とは?」では、OJT教育担当者の負担を解消する教育手法について紹介するとともに、現場任せの教育から一歩進めて再現性ある育成体制を構築するための改善指針にも触れています。
OJTの教育負担や非効率性に課題を感じている方は、以下の資料もあわせて参考にしてみてください。
>>「OJT担当者の負担が激減する、OJT教育の新常識とは?」を見てみる
目次
OJTをする余裕がない理由
企業ごとに社内の状況や従業員数などが違うため、事情は異なるもののOJTをする余裕がない理由はおおよそ同じです。ここでは、なぜOJTをする余裕がないのかその理由について紹介していきます。
※OJTの教育負担や非効率性に課題を感じている方は、以下の資料もあわせて参考にしてみてください。>>「OJT担当者の負担が激減する、OJT教育の新常識とは?」を見てみる
OJTを担当する人材が不足している
少子高齢化を抱えている昨今では、業界や業種を問わずに慢性的な労働力不足に陥っています。また、OJTを担当するのは社歴が長かったり、業務に対して豊富な経験があったりする従業員が担当します。
そのため、そもそもOJTを担当できる人材自体が不足しているのが現状です。OJT担当者が不足しているにも関わらず、新人・若手の従業員が増えてしまうと、OJTの制度自体が円滑に進まなくなり余裕がなくなってしまうのです。
OJT担当者の業務量が多い
OJT担当者に業務比率が偏ってしまい、業務量自体が多くなっているのも余裕がなくなる理由の1つです。業務の高度化・複雑化によって、業務負荷が年々増加してしまい、目先の業務をこなすだけでリソースが逼迫してしまうのです。
OJTに時間を割いて、通常業務の時間を削減してしまうと、売上や全社的な生産性などに直結します。担当者の評価にも影響する可能性があるので、重要度の高い通常業務に時間を割いてしまうのは必然と言えるでしょう。
※OJTの教育負担や非効率性に課題を感じている方は、以下の資料もあわせて参考にしてみてください。>>「OJT担当者の負担が激減する、OJT教育の新常識とは?」を見てみる
OJTで利用するマニュアルが整備されていない
OJTをするうえでは、業務の全体像や社内のルールなどをまとめたマニュアルを活用します。しかし、マニュアルが整備されていないことも多く、全て言葉で伝える必要が生じてしまい、OJTが非効率になってしまうことも。
非効率なOJTは、時間・期間が長引いてしまうことはもちろん、担当者への負担も増加します。その結果、OJTに負担がかかってしまい、余裕がなくなってしまうのです。
OJTに活用するマニュアルを整備する際、「どのように進めればよいのかわからない…」「参考となる見本が欲しい」という方も多いはずです。そんな方に向けて、「そのまま真似できる「見本」付き 業務マニュアルの作り方完全ガイド」を用意しています。こちらもあわせてご覧ください。
教育のノウハウ・ナレッジが不足している
新人・若手の教育に対してのノウハウやナレッジなどの不足も余裕がなくなる理由の1つです。
新人に対してどのような教育をするのか、どの程度の期間をかけるのか、OJTの最終目標は何なのかなどが曖昧になってしまい、効果的なOJTのオペレーションが組めなくなります。
また、全社的なノウハウ・ナレッジの不足だけではなく、担当者個人に対しても業務理解やスキルが不十分な場合もあります。理解できていたとしても、指導スキルや指導手法を持ち合わせていないことも考えられるでしょう。
OJTを非効率に進めている方は、うまくいかない理由や改善策、成功事例などを詳しく紹介している以下の記事もご覧ください。
関連記事:『OJTがうまくいかない…』失敗する理由は?改善策も解説!
担当者がOJTに消極的
OJTの成功は、担当者の積極的な取り組みに関係します。担当者がOJTに消極的であると、ネガティブな姿勢がOJTを受ける側に伝わり、OJTの効果が薄れてしまいます。
消極的になるのは様々な理由が考えられますが、具体的な例としては以下が考えられます。
- OJT担当者の指導スキル向上の取り組みが不足している
- 現場まかせなOJTを実施している
- OJT担当者を評価する仕組みがない
全社的に効果的なOJTを実施するためも、担当者の意欲が向上するような働きかけが重要と言えるでしょう。
OJTを教える側の担当者に必要なスキルや負担を解消する方法などについて詳しく知りたい方は、以下の記事もクリックしてあわせてご覧ください。次章からはOJTを効率的に実施している企業事例をご紹介します。
関連記事:【OJT】教える側に必要なスキルとは?負担を減らす方法や、メリット/デメリットも解説
負担のかかるOJTを効率的に実施している企業事例
負担がかかり、OJTをする余裕がないと感じる職場が少なくありませんが、負担を解消して効率的にOJTを行っている会社もあります。
ここでは、効率的に実施している企業の好事例を3社ご紹介していきます。
OJTや手順書作成工数を大幅に削減!|アサヒ飲料株式会社
アサヒグループに所属する飲料の製造販売を担っているアサヒ飲料株式会社。同社では、人材育成をOJTで行っていたものの、教育担当者ごとに教え方に違いがあったり、1日の勤務時間のうち、半分以上がOJTに時間を取られるなどの課題を抱えていました。
その課題に対し、OJTで利用していた紙の手順書を動画化することで解消を目指しました。動画マニュアル(tebiki現場教育)の導入後、OJTにかける時間が長くても2時間ほどに短縮することに成功。定常業務をこなしつつ、OJTを実施する余裕も生まれています。
また、従来の手順書や紙のマニュアルでは伝わらなかったカンコツを要する作業も、動画で視覚的な学びをすることで、早期に習熟者と同程度の作業ができるようになったと話します。同社の詳しい取り組み内容は、以下のインタビュー記事をクリックしてご覧ください。
インタビュー記事:OJTや手順書作成工数を大幅に削減!熟練者の暗黙知も動画で形式知化
新人教育時間を3700時間削減|株式会社GEEKLY
IT・WEB・ゲーム業界に特化した人材紹介事業に取り組んでいる株式会社GEEKLY。同社では、トレーナーごとの教え方にバラつきがある・トレーナーの負担が大きいという2つの課題を抱えていました。1ヶ月で50時間程度教育に時間をかけていたこともあるそうです。
そこで同社では、文章よりも伝えやすく、何度でも反復して学べる動画マニュアルを導入しました。紙マニュアル+OJTで行っていた新人教育の7割近くを動画マニュアルに置き換えてトレーナーの負担軽減に成功し、年間にすると約3,700時間もの時間削減に成功しています。
同社の詳細な取り組み内容については、以下のインタビュー記事をクリックしてご覧ください。
インタビュー記事:年間の新人教育時間を3,700時間削減。トレーナーの教育時間が大幅に減り営業成績も向上!
新人OJTの7割を動画に置き換え|日本クロージャー株式会社
各種金属キャップ、樹脂キャップ及び樹脂製品の製造販売を行っている日本クロージャー株式会社。同社では、新人の質問に対して30分ほど時間がかかる、先輩に対して質問ができないなど、新人教育を効率化できない課題を抱えていました。
そこで、作業工程を視覚的に学べる動画マニュアルを導入。今までOJTをしていた作業の7割程度を動画で学ぶことができ、従来と比べて教える側・教わる側それぞれに時間的な余裕が生まれています。同社の詳しい取り組み事例については、以下のインタビュー記事をクリックしてご覧ください。
インタビュー記事:新人OJTの7割を動画に置き換え。教育の手間を大幅に削減しました。
なお、他にも成功事例を見たい方は、教育のバラつきや教育負担を動画マニュアルによって解消した企業事例を紹介している「教育のばらつき/教育負担の削減が見込める”動画マニュアル”の有効性&活用事例」の資料をご覧ください。企業事例を基にして、具体的な教育方法も詳細に解説しているので、「OJTの余裕がない…」課題を解決するヒントが得られるはずです。資料は、下の画像をクリックすると資料をダウンロード頂けます。
OJTをする余裕がないまま新人を放置するリスク
OJTをする余裕がない状態では、せっかく入社した新人を放置することになります。一見、しょうがないことと思う方もいるかも知れませんが、新人を放置すると大きなリスクに発展する可能性も。ここでは、その理由について紹介していきます。
※OJTの教育負担や非効率性に課題を感じている方は、以下の資料もあわせて参考にしてみてください。>>「OJT担当者の負担が激減する、OJT教育の新常識とは?」を見てみる
新人が育たずに現場への負担が軽減されない
OJTの対象となる新人社員は、近い将来の戦力となる貴重な存在です。OJTを適切に実施しないで放置すると新人が育たずに戦力としては見込めなくなるでしょう。
その結果、基本的な作業や業務のみできるようになるものの、専門的で独自性のある業務ができないため、特定の従業員への負担は軽減されることはありません。また、業務の標準化もできなくなり、ベテラン社員と社歴が浅い社員とで、業務の習熟度に差が生じてしまうリスクも考えられるでしょう。
新人教育で抑えるポイントや失敗しないコツなど、以下の記事で詳しく解説しているのであわせてご覧ください。
関連記事:【新人教育】OJTを効率的に行うポイントとは?事前準備から役立つツールまで解説
モチベーションが低下して早期離職者が増加する
OJTを含めた教育が不足している状況は、新人からすると不安や焦りなどの感情につながってしまい、モチベーションの低下してしまいます。モチベーションが低下する状況が続いてしまうと、成長やキャリア形成に対する不安から、早期離職につながる可能性も考えられます。
早期離職は新人社員のキャリア形成や負担につながるのはもちろん、企業にとっては教育にかけたコストの損失や再び採用活動を行うコストや手間が増加することにもつながるでしょう。
ノウハウやナレッジの蓄積ができない
はじめから最適なOJTをできるのではなく、取り組む中で失敗や成功を繰り返し、より良くなるように改善する必要があります。OJTを受けた社員が数年後OJTを担当する側になることも十分にあり、自身の経験を踏まえた上でOJTに望むこともあるでしょう。
しかし、不十分なOJTで新人にかける時間が少ないと、OJTに対してのノウハウやナレッジがいつまでも蓄積されず、質の高いOJTをすることはできなくなるリスクも考えられます。
従業員のスキルが低下し、会社の生産性にも影響する
不十分なOJTによって、業務方法や決まりなどをしっかりと教育できなくなり、社員ごとに業務への理解度や習熟度に乖離が発生します。
年々従業員のスキルが低下してしまうので、全社的な生産性にも影響する可能性があるので注意が必要です。入社当初に覚えた作業方法に慣れた状態では、本来の正しい作業を途中で教え直しても矯正するのにかなり時間がかかる可能性もあります。
OJTをできる余裕を持つ秘訣
OJTができる余裕を持つには、以下2つの対策が有効です。
- 定常業務を効率化させる
- 現場における教育の優先度を高める
それぞれの対策ごとにより細分化して具体的な対策を紹介していきます。
※OJTの教育負担や非効率性に課題を感じている方は、以下の資料もあわせて参考にしてみてください。>>「OJT担当者の負担が激減する、OJT教育の新常識とは?」を見てみる
定常業務を効率化させる
業務マニュアルを整備するしてノウハウを蓄積する
現在活用している業務マニュアルを見直して、整備や改訂を進めるのも有効な手段の1つです。業務マニュアルを作成したのが数年前で、現在まで更新されていない場合などは早急に対応を進めましょう。
数年前と現在とでは、作業手順が変わっていることもありますし、OJTの目的や目標なども変化していることが十分に考えられます。マニュアルと業務の実態に乖離があると、新人社員にとってはギャップに感じてしまい、負担につながるので注意が必要です。
なお、マニュアルを整備するうえでは、見本となるマニュアルがあると不備なく高品質なものを作成できます。以下の資料では、見本の他に作成の流れなども詳しく紹介しているのでぜひ参考にしてみてください。
ムダな業務を洗い出す
当たり前のように行っている日常業務の中には、意外にも必要がないムダな業務が潜んでいる傾向も十分にあります。長年の慣習や伝統的な方法に固執して、新しい技術や方法を取り入れて来なかったなどが原因です。
そのため、「不必要な業務がないか」の視点を持った上で現在の業務の洗い出しを進めていきましょう。洗い出しをする際には、業務をより詳しく理解している現場の社員にヒアリングするのも有効です。
また、トヨタ生産計画(TPS)における重要な基本思想である3M(ムリ・ムダ・ムラ)の考え方も改善のヒントになります。以下の動画では、3Mの重要性や気づくための視点などを専門家の視点で分かりやすく説明しています。無料で視聴できますので、画像をクリックしてご覧ください。
採用を強化する
近年、人手不足が大きな問題となり、高度な技術や専門知識を持った人材が求められる一方で、新たな採用が難しくなっています。人手不足を解消するためには、採用活動を強化することが必要です。具体的には、新卒採用の枠を増やす、中途採用を活発に行う、外国人労働者の受け入れを検討するなどの方法が考えられます。
特に外国人労働者の受け入れは多くの企業で行われているものの、これから受け入れを検討している場合にはどのように雇用すればよいのか、疑問点も多いかと思います。そんな方は、在留資格や雇用する流れなどをまとめたこちらの記事をご覧ください。
また、外国人労働者を雇用した後に発生しやすい教育課題については、動画マニュアルの活用が最適です。紙の手順書やマニュアルでは伝わりにくい動きや絶妙なニュアンスを動画で分かりやすく伝えることができます。以下の資料では、外国人従業員の教育における動画マニュアルの有効性を紹介しています。以下のリンクをクリックしてご覧ください。
>>「外国人労働者の教育に動画マニュアルが有効な理由」を読んでみる
現場における教育の優先度を高める
教育の優先度を高めるためには、以下の2つの対策を実行しましょう。
- OJT担当者に対しても教育を行う
- OJTを評価の対象にする
OJT担当者に対しても教育を行う
OJT担当者に対しても教育を実施しましょう。現場にOJTを丸投げするのではなく、なぜ実施するのか、最終的なゴールはなにかなど、できるだけ具体的にした上で指導するのが重要です。
担当者に対しての教育が行われないと、OJTの内容や質がそれぞれに依存してしまい、OJTにバラつきが発生してしまいます。例えば、OJTの前にOFF-JTを実施する、OJTで活用するマニュアルを整備するなどの対応が必要と言えるでしょう。
なお、OJTの経験が浅い担当者の場合には、「どのように進めるべきか」「新人へどのようにアプローチすべきか」などの疑問や課題を抱えている方もいるかと思います。以下の動画では、令和の時代にフィットしたOJTのポイントや進め方、注意点などを解説しています。視聴は無料でできますので、以下の画像をクリックして動画をご覧ください。
OJTを評価の対象にする
OJTの効果を最大限に引き出すためには、OJT担当者に対する評価を適切に行うことが重要です。評価を通じてOJTの内容や方法の改善点を見つけ出し、さらなる質の向上を図ることができます。
OJTを評価の対象にすることで、具体的な成果をもとにOJTの内容を見直し、さらなる生産性の向上を目指せることも。また、OJT担当者や受講者の意見やフィードバックも評価の一部として取り入れることで、より実践的な教育ができるようになります。
OJTを効率的に行うには動画マニュアルの活用がおすすめ
「負担のかかるOJTを効率的に実施している企業事例」の見出しでも紹介したように、動画マニュアルはOJTを効率的に行うツールとしておすすめです。ここでは動画マニュアルでOJTを行うメリットを解説します。
なお、以下の資料でははじめて動画マニュアルを作成する方に向けて、導入するステップやメリットをより詳しく紹介しています。比較検討している方は、資料もあわせてご覧ください。
わからないことを繰り返し学べる
動画マニュアルは閲覧できるデバイスがあればいつでもマニュアルの視聴が可能です。OJTで不明点があったとしても、業務のスキマ時間や就業後などに自主的に繰り返し学べるのがメリットといえます。
テキストや画像などの紙ベースのマニュアルとは違い、視覚的に学ぶことができるので、学習するハードルも低くなるでしょう。
大人数に効率よく教育ができる
動画マニュアルの場合には、PC上に保存ができ、ネットワークを通じて社内に素早く展開できます。OJTの対象者が多く、多拠点で実施する場合などに動画マニュアルを活用することで効率よく教育を進められるでしょう。
また、紙のマニュアルを個別に見るのと比べて、大画面でマニュアルを閲覧したほうが意見が活発に飛び交い、効果的なOJTの実現につながるのもポイントです。
教育の差が生じにくい
従来のOJTでは、指導者の技量や経験によって、指導内容にバラつきが発生することもあり、教育の質に差が生じることもあります。また、文面だと微妙なニュアンスなどに対して、認識に齟齬が生まれてしまうリスクも。
しかし、動画マニュアルであればテキストと比べて認識の齟齬や指導内容のバラつきを防げて、教育の差が生じにくくなるのがメリットです。
「OJTの余裕がない…」を解決できるtebiki現場教育
▼動画マニュアル作成ツール「tebiki」紹介動画▼
tebiki現場教育は、動画マニュアルの作成から従業員の習熟度管理まで行えるクラウド型ツールです。
動画内の音声を認識し自動で字幕を生成する機能を始め、直感的な操作性やシンプルなデザイン性を兼ね備えているため、OJTで利用するマニュアルをスピーディーに作成できます。また、作成したマニュアルのアクセス履歴や習熟度などの学習度合いが一目でわかるのもポイント。
対象者ごとの習熟度が分かるので、OJTの回数や時間を削減する効果も見込めます。「tebiki現場分析」の詳しい機能や特徴などを知りたい方は、以下の資料もご覧ください。
tebiki現場教育でOJTを効率化しよう【まとめ】
多くの企業でOJTの実施に関する課題が浮き彫りになっており、課題の背景には、業務の多忙さや人手不足、業務マニュアルの不備、教育のノウハウ不足などがあります。
OJTに余裕がない状態が続くと、新人が十分に育たず、早期離職のリスクが高まるだけでなく、技術伝承が進まず、現場でのミスが増えるという深刻な結果を招きかねません。
これらの課題を解決するためにも、「tebiki現場教育」の活用がおすすめです。OJTに余裕がないと思っている方やOJTが思うようにいかないと悩んでいる方はぜひこの機会にサービス資料をダウンロードしてみてください。