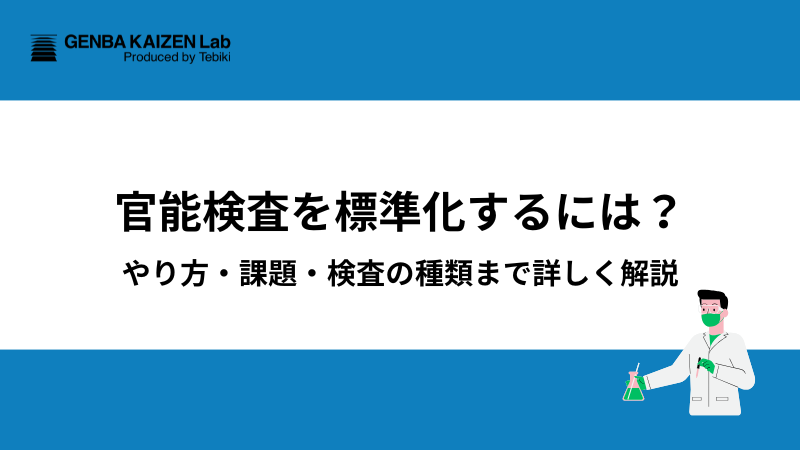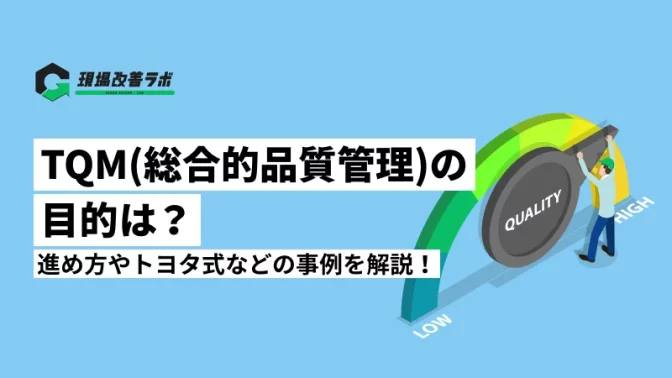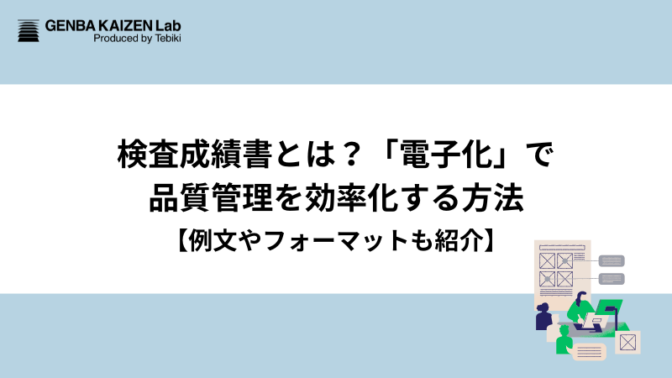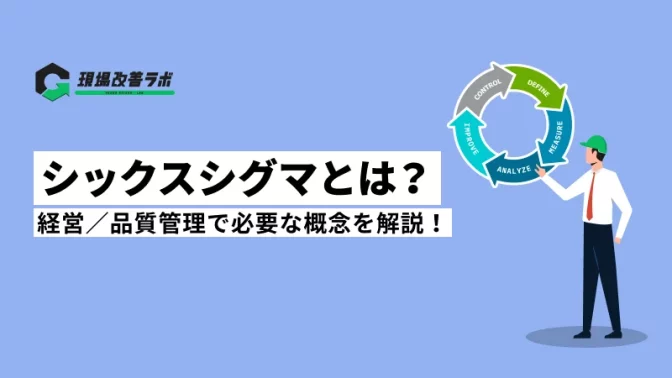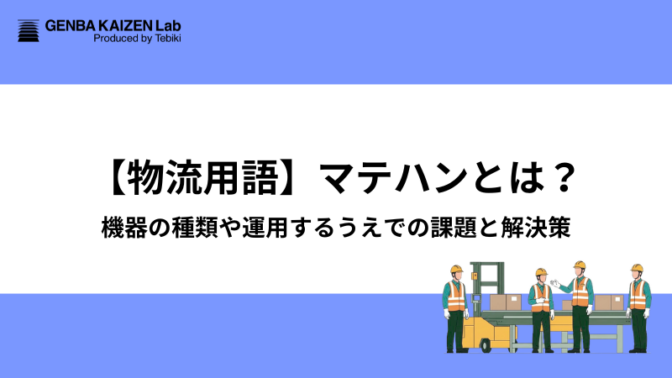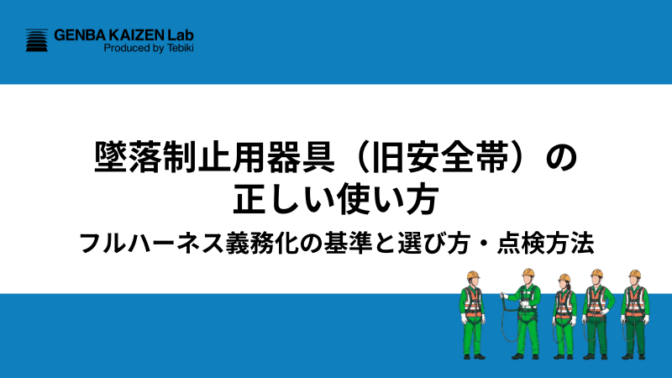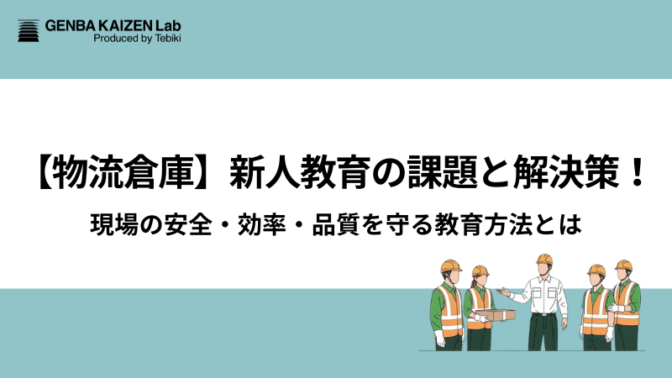かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
官能検査とは、人の五感(視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚)で製品の品質を評価する検査方法です。しかし「人の感覚」という不確定な要素に頼るため、検査結果にばらつきが生じやすいという課題もあります。
そこで本記事では、官能検査の種類や実践方法だけでなく、官能検査に関する現場の課題と改善策についても解説しています。官能検査の属人化や精度のばらつきに課題を感じている方は、是非ご覧ください。
目次
官能検査とは?検査の目的や重要性
官能検査とは、人間の五感(視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚)を用いた品質検査です。数値化できない感覚的な特性を評価できる点が大きな特徴で、微妙な色合いや手触り、異音など、機械では検出しにくい不具合を人の感覚で見抜き、不良品の流出を防ぎます。試作品の評価にも活用され、消費者の嗜好に合った製品づくりに役立ちます。
顧客目線で検査できる官能検査は、人にしかできない重要な工程といえます。ここからは、その目的やメリット、主な検査手法について解説します。
官能検査の対象
官能検査では、人間の五感を使って製品のさまざまな感覚的特性を評価します。具体的には、色や香り、味、音、手触りなど、機械では測定しにくい要素が対象となります。製品の最終的な使用感や消費者の満足度に直結する重要なポイントであるため、対象となる感覚や評価項目を明確にしておくことが欠かせません。
以下に、五感ごとの主な検査対象と活用例をまとめました。官能検査を導入・見直す際の参考にしてください。
| 五感 | 検査対象の例 | 活用される製品・場面例 |
|---|---|---|
| 視覚 | 色・ツヤ・濁り・形状・気泡・傷など | 飲料の透明度、塗装品の色ムラ、樹脂成形品の外観検査など |
| 聴覚 | 音の有無、異音、音質など | モーターや搬送装置の異音検知、部品の打音検査など |
| 味覚 | 甘味、苦味、酸味、うま味、後味など | 食品・調味料の製品検査、試作品の官能評価など |
| 嗅覚 | 香り、においの強弱・質など | 洗剤や塗料のにおい確認、食品の腐敗臭チェックなど |
| 触覚 | ザラつき、滑らかさ、硬さ、湿り気など | ゴム部品の硬さ確認、包装資材の手触りチェックなど |
官能検査の目的やメリット
官能検査の最大の目的は、製品の品質を人間の感覚を通じて多角的に評価・保証することです。数値では捉えきれない感覚的な特性を見極めることで、品質の安定や製品開発の精度向上につながります。主な目的と、それによって得られるメリットは以下の通りです。
- 品質保証・品質管理
- 製品開発・改良
- 官能特性の把握
品質保証・品質管理
官能検査は、製造された製品が定められた品質基準を満たしているかを最終的に確認する手段です。
機械検査では見逃されがちな微細な欠陥や数値化できない感覚的な品質不良(異味、異臭など)を検出し、不良品の市場流出を未然に防ぎます。官能検査により、顧客満足度の向上、クレームの削減、ブランドイメージの維持が期待できます。
製品開発・改良
新製品の開発や既存製品の改良においても官能検査は有効です。
試作品の官能評価を通じて、消費者の嗜好やニーズを把握し、製品の改良点や方向性を明確にします。例えば、食品であれば味や食感、工業製品であれば使い心地や外観など、数値だけでは測れない項目を評価し、より魅力的な製品開発につなげます。
官能特性の把握
官能検査は、製品の持つ様々な感覚的特性(官能特性)を詳細に把握するために用いられます。
例えば、食品の甘味、苦味、酸味のバランス、香りの強さ、衣類の肌触り、音響機器の音質など、製品の特性を多角的に評価します。官能検査により、製品の品質特性を明確化し、品質管理の基準設定や競合製品との比較分析に役立てることが可能です。
他の品質検査との違い
官能検査は人間の五感を使い製品の感覚的品質を評価する方法であり、機器分析や物理的検査など他の品質検査と組み合わせて用いられることが多いです。各検査手法は異なる視点で品質を評価するため、それぞれの特長を活かすことでより信頼性の高い品質保証体制を築けます。
以下に、他の代表的な品質検査との違いを記載します。
| 検査手法 | 評価対象・特徴 | メリット・活用例 |
|---|---|---|
| 官能検査 | 人の五感で色・におい・味・手触り・音などを評価 | 数値化困難な感覚的特性を直接評価。最終消費者視点の品質保証に有効 |
| 機器分析 | 成分分析や物理的特性の数値化(例:GC/MSなど) | 揮発性化合物の特定や濃度測定が可能。客観的データで品質管理を補完 |
| 破壊検査 | 製品を破壊し強度や耐久性、内部構造を評価 | 製品の性能評価に必須。ただし検査対象は使用不可となる |
| 非破壊検査 | X線や超音波で内部の欠陥・構造を検査 | 製品を傷つけずに内部検査が可能。生産ラインでの検査に適している |
他の品質検査との組み合わせ例として、機器分析で特定したにおいの原因物質をもとに官能検査で実際のにおいの強さや印象を確認するなどが挙げられます。こうした複数の検査手法を組み合わせることで製品品質を多面的に評価でき、より精度の高い品質管理が実現します。
その他の品質検査手法や検査員のスキル向上については、以下の記事で詳しく解説しています。是非併せてご覧ください。
関連記事:製造業の品質検査に潜む課題と改善策!検査員スキル向上事例も解説
官能検査の種類
官能検査は、人間の五感を用いて製品の品質を評価する検査方法ですが、その目的や手法によって以下のように分類されます。
- 分析型と嗜好型による分類
- その他の官能検査
分析型と嗜好型による分類
官能検査は、その目的によって大きく以下の2つに分けられます。
- 分析型官能検査
- 嗜好型官能検査
分析型官能検査
製品の特性や品質の差を、客観的に評価することが目的です。例えば、新しい食品の甘味の強さを、既存の製品と比較して評価する場合などが該当します。
検査員には、微妙な味の違いを識別する能力や客観的な判断力が求められ、専門的な訓練が必要となることもあります。製品の出荷検査、製造工程の管理、品質改善などで活用されます。
嗜好型官能検査
製品に対する検査員の好みや嗜好を調査することが目的です。例えば、新しい化粧品の香りが、ターゲットとする年齢層に好まれるか、というような調査です。
特別な識別能力は必要ありませんが、製品のターゲット層(年齢、性別、ライフスタイルなど)を代表するような検査員を選ぶことが重要です。新製品開発や、マーケティング調査などに有効です。
その他の官能検査
記述試験
検査員が製品の特性や特徴を、自身の言葉で詳細に記述する検査です。例えば、新しい椅子の座り心地について、「包み込まれるような柔らかさ」「背もたれのカーブが体にフィットする」といった具体的な言葉で表現します。検査員の感性や表現力に依存する部分が大きいですが、製品の主観的な項目を幅広く確認する際に有効です。
等級試験
あらかじめ設定された等級、例えば1級品、2級品、3級品など、検査対象の製品がどれに該当するかを判断する検査です。例えば、木材の等級分け(節の数や大きさ、木目の美しさなど)や、果物の等級分け(大きさ、色、形など)が挙げられます。検査結果は数値データとして整理できるため、客観的な評価が可能です。
差別検査
製品間の差異や相違点を検出するための検査です。例えば、製造ラインを変更した際に、変更前と変更後の製品に、外観や味などに違いがあるかどうかを評価する場合などに用いられます。検査条件(照明の明るさ、温度、湿度など)を明確に設定し、統計的に分析することで、製品間の優位性を確認します。
官能検査のやり方は?実践手法
官能検査にはさまざまな手法があり、それぞれ目的や検査対象によって使い分けられます。本章では、以下5つの検査の進め方について具体的に解説します。
- 二点識別法
- 三点識別法
- 一対比較試験法
- 順位法
- 採点法
官能検査を進めるうえで重要なのは「誰が行っても同じ水準で検査ができるかどうか」という点ですが、感覚に頼る検査は属人化しやすく、検査員によって評価にばらつきが生じるリスクがあります。
この課題に対して有効なのが、「動画マニュアルの活用」です。検査の手順や評価基準を動画で共有することで、言語だけでは伝わりにくい感覚的なポイントも明確になり、誰が見ても同じように理解・再現しやすくなります。
官能検査をはじめとする品質検査に動画が有効な理由や、実際の動画サンプルについて詳しく知りたい方は以下の画像をクリックし、無料のハンドブックをご覧ください。
二点識別法
差異のある2つのサンプルを比較し、指定された特性についてどちらが強いか(該当するか)を判断する方法です。簡単に実施でき、識別力の有無や製品間の差の有無を確認するのに適しています。。
例えば異なるメーカーのコーヒーを比較し、苦味が強いのはどちらかなどを評価する際に使用します。
▼二点識別法の進め方▼
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | 比較対象のサンプルA・Bを用意。特性に差が出やすい順番(ランダム化)で提供。 |
| 2 | 評価対象の特性を事前に設定(例:苦味、触感、光沢など) |
| 3 | 検査員に「どちらがより〇〇か」を問い、直感的に選ばせる |
| 4 | 結果を記録し、複数人・複数回で傾向や一致率を分析 |
二点識別法は非常にシンプルな設計で官能検査の入門としても適していますが、サンプル間に微妙な差しかない場合は検査員の感覚に依存しやすくなります。そのため、繰り返し評価を行う、検査員の訓練を積むなどして、再現性を高めることが重要です。また、サンプルの提示順を毎回変えることで検査結果への先入観を防ぐ工夫も求められます。
三点識別法
3つのサンプルを用意し、そのうち2つは同じもの、1つは異なるものを検査する方法です。微妙な差を判別する能力の確認や、新旧製品の変更後比較に有効です。
例えば、同じ銘柄のコーヒー2つと異なる銘柄のコーヒー1つを使用して識別します。
▼三点識別法の進め方▼
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | 同一サンプル×2、異なるサンプル×1を無作為な順番で配置(例:B-A-B) |
| 2 | サンプルをランダムな記号(例:X, Y, Z)で表記 |
| 3 | 検査員に「異なるサンプルはどれか」を選ばせる |
| 4 | 結果を記録。複数検査員でデータを集計し、正答率を統計処理 |
この手法は官能的な違いを「特定できるかどうか」という視点から検査できるため、製品変更時の味や香りの変化を確認したい場面で有効で、検査員の識別力の有無も同時に評価できます。ただし、見た目や温度、容器の違いで無意識に判断されないよう、できる限り条件を統一する必要があります。
一対比較試験法
複数のサンプルの中から2つずつを選び出し、1対1で比較を繰り返すことで、最終的に各サンプルの優劣や順位を整理する検査手法です。例として、異なる種類のチョコレートの中から「甘さ」「苦さ」「香り」などの項目についてそれぞれのサンプルを比較し、最終的に総合的な評価を実施します。
▼一対比較試験法の進め方▼
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | 全サンプル(例:A〜D)を用意する |
| 2 | 全ての組み合わせ(ペア)を作成し、比較順を決定する |
| 3 | 評価項目ごとに「どちらが優れているか」を検査員が判定 |
| 4 | 判定結果を集計し、順位やスコアを算出する |
この手法は各サンプルを1対1で判断するため検査員の迷いや混乱が起きにくく、感覚的な負荷が比較的少ないといえます。対象サンプルが多くなっても比較単位が2つで済むため、整然と進められます。食品の分野では、「シェフェの一対比較法」という、好みの程度を尺度で評価する手法もよく用いられます。
順位法
複数のサンプルを特定の官能特性に従って、相対的な順番で並べる手法です。評価結果は「どれが一番強いか」などの比較には有効ですが、順位の間隔が等しいとは限らない点に注意が必要です。
▼順位法の進め方▼
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | 複数サンプルを識別記号(例:X〜Z)で用意する |
| 2 | 評価特性(例:香りの強さ)を1つに絞って検査員に伝える |
| 3 | 各サンプルを比較し、1位〜最下位までの順位をつける |
| 4 | 順位データを複数の検査員から集めて平均順位や頻度で整理・分析する |
順位法は、対象サンプルの官能特性の“強弱”を明確に把握したいときに使われます。シンプルで直感的に評価できる点がメリットですが、1位と2位の差と、3位と4位の差が同じとは限らない点から、分析結果を読む際には注意が必要です。
例として、異なる4種類のクッキーを「甘味の強さ」で評価する場合、検査員は実際にすべてのクッキーを試食し、もっとも甘いと感じたものを1位、最も甘味が弱いと感じたものを4位として順位付けを行います。このとき、1位と2位の甘味の差が大きく、2位と3位はほとんど差がない場合でも、評価上は単純に1→2→3→4と並べられるだけで、差の大きさまでは表現されません。。
採点法
特定の官能特性について、各サンプルを数値で評価する方法です。5段階、7段階、9段階などのスケールを用い、「強度」や「好ましさ」などを点数化します。
例として、異なる3種類のヨーグルトを「酸味の強さ」で評価する場合、検査員はそれぞれのサンプルを試食し、あらかじめ設定された9段階評価(1=非常に弱い、9=非常に強い)などのスケールに従って数値をつけます。例えば、Aは7、Bは5、Cは3というように評価されれば、単に順位だけでなく酸味の強さの差異も定量的に把握できます。
▼採点法の進め方▼
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | 検査対象サンプルと官能特性(例:甘味の強さ)を明確に設定する |
| 2 | 評価スケール(例:1=非常に弱い〜9=非常に強い)をあらかじめ定義する |
| 3 | 検査員は各サンプルを評価し、数値で記録する |
| 4 | データを平均・標準偏差などで集計し、統計的に分析する |
採点法は各サンプルの絶対的な強さや嗜好の程度を数値として取得できるため、統計処理やグラフ化などによる分析がしやすく、製品間の定量的な比較や、製品改良の進捗確認に非常に適しています。一方で検査員の感じ方の違いがスコアに影響するため、評価スケールの解釈を統一しないとばらつきが生じやすくなります。実施前にトレーニングや基準サンプルを使い、評価の方向性を揃えておくことが望ましいでしょう。
ここまで官能検査における実際の検査手法を解説しましたが、これらの検査を行い、正しい検査結果を導き出すにはいくつかの留意点があります。
次章では、官能検査で直面しがちな課題や留意点について整理します。
官能検査における主な課題と留意点
官能検査は、人間の感覚に頼る検査方法であるため、いくつかの課題を抱えています。主な課題としては以下の4つが挙げられます。
これらの課題は総じて「教育体制の整備が行き届いていない」ことが根本的原因となっていることが多いです。というのも、検査業務は言語化しにくいカンコツや複雑かつ高度な技術が求められることが多く、検査員ごとにスキルの差が生じやすいからです。
検査品質が人によってばらつきやすい
官能検査は人の五感に基づく評価手法であるがゆえに、「誰が行うか」によって結果が大きく変わってしまうという本質的な課題を抱えています。同じ製品を検査していても、ある検査員は「特に問題なし」と判断する一方で、別の検査員は「異臭を感じる」「わずかに味が変わっている」と指摘するといったケースは、現場では決して珍しくありません。
このようなばらつきは、検査員の体調(鼻づまり、疲労など)、経験値の差、さらには個人の感受性の違いなど、さまざまな要素が複雑に絡み合って生じるものです。結果として検査の精度や判断の一貫性を確保することが難しくなり、本来なら弾くべき不良品を見逃したり、逆に問題のない製品を過剰に廃棄したりするリスクにつながります。
加えて、検査品質のばらつきが顕著な現場では、「この人に検査を任せれば安心」という認識が暗黙のうちに広まり、特定の検査員への依存が強まることで、検査体制そのものが属人化してしまう傾向があります。このような状況が続くと検査精度の平準化や標準化が進まず、品質保証の仕組み自体が不安定になるという、根深い悪循環に陥ってしまいます。
パネラー(検査員)のスキルや水準が見えにくい
官能検査における大きな課題は、検査員(パネラー)のスキルや水準が可視化されにくいという点です。機械検査のように明確な数値や合否基準がない官能検査では、検査員の「感覚の正確さ」や「判断の一貫性」を客観的に評価することが難しくなります。
例として新人検査員がベテランと同じ項目を評価していたとしても、その評価にどれほどの精度や妥当性があるのかは、表面的には見えません。「この人の判断は信頼できるのか」「本当に感覚が鋭いのか」といった点は、現場の肌感や上司の経験則でなんとなく評価されてしまっているのが実情です。
このような状況では検査の信頼性に疑念が生じるだけでなく、検査員の育成も属人的になりがちで、組織としての検査力の底上げが難しくなります。万一、品質トラブルが発生した際に「誰の判断だったのか」「なぜ見逃したのか」といった振り返りも曖昧になり、再発防止の取り組みにも支障をきたす要因となります。
カンコツに依存する属人的な業務になりやすい
官能検査の現場では、「あの人の鼻は利く」「あの人は経験があるからわかる」といった、経験や勘、個人の『カンコツ』に依存した運用が暗黙のうちに常態化しているケースが少なくありません。特に、ベテラン検査員が長年の経験で身につけた判断基準や微妙な感覚は言語化やマニュアル化が難しく、他者に継承されにくいという特徴があります。
このような属人的な運用が続くと、ベテランがいないと検査が成り立たない、「あの人がいない日は検査の精度が落ちる」といった状況に陥りやすくなります。さらに検査員ごとの判断基準が微妙に異なることで、同じ製品でも結果が変わる、つまり「品質保証の一貫性」が損なわれるという重大なリスクも発生します。
また、暗黙知で回っている業務ほど新人育成に時間がかかり、引き継ぎも曖昧になりやすいため、人が抜けたタイミングで現場の品質が一気に不安定になるという、組織としての脆さも浮き彫りになります。
評価環境の影響を受けやすい
官能検査は評価の対象だけでなく、「どこで」「どんな条件で」行うかによって結果が大きく左右されるという特性があります。例えば室温、照明、騒音、臭気、時間帯など、わずかな環境の違いが検査員の感覚に影響を与え、同じサンプルでも感じ方が変わることがあります。
特に、においや音、手触りなどを評価する場合、他の製品の臭気や騒音が混じることで、判断が鈍るといった問題が発生しがちです。また、日中と夕方、体調や疲労度によっても検査結果に微妙な差が出ることがあり、検査の再現性を担保するうえで大きなハードルとなります。
こうした環境要因が管理されていないと、同じ製品を異なるタイミングで検査した際に異なる評価が出る、という矛盾が生じやすく、品質の信頼性を損なう結果につながります。加えて、こうした環境影響の多くは現場では「気付きにくいが結果に効いてくる」ため、対処が後手に回りがちです。
このような課題を解決し、品質を担保するにはどのような対策が必要なのでしょうか?次章では、官能検査の品質向上に欠かせない要素について解説します。
官能検査の質向上には「検査員の現場教育」が肝
官能検査において品質の安定と再現性を確保するには、検査手法や設備の整備だけでなく「検査員の育成と教育」が極めて重要なポイントになります。官能検査は人の感覚に強く依存する検査手法であるため、検査員ごとのスキルや感受性の差が検査品質に直結するという構造的な弱点を抱えています。属人的な判断に任せきったままでは、製品の品質評価に一貫性を持たせることは困難です。
このような課題を乗り越えるには、「官能検査員の教育・トレーニング」を軸とした取り組みが必要です。ここでは特に、「属人化の防止」と「再現性の向上」という2つの観点から、その重要性を解説します。
属人化を防ぐ:ベテラン依存から組織全体のスキル共有へ
官能検査の現場では、ベテラン検査員の経験や感覚に業務が依存しているケースが多く見られます。特に検査基準が言語化されていない職場では、「あの人なら間違いない」「この人の判断だけは信頼できる」といった暗黙の信頼に頼る構造になりやすく、属人化の温床になりがちです。
このような属人化を防ぐために求められるのは、感覚や経験に頼った“勘とコツ”を、できる限り形式知として可視化・共有する仕組みです。例として、以下のような対策が挙げられます。
- 官能評価に関する基準やガイドラインの整備(感度基準、用語の統一など)
- ベテラン検査員の評価プロセスや判断理由を動画や音声で記録・共有する
- 検査実施時に使用する評価シートや記録方法の統一
- ロールプレイや模擬検査によるOJTの定期実施
これにより、属人化しがちな「判断基準」や「観察ポイント」を共通言語化し、経験の浅い検査員もスムーズに実務に馴染めるようになります。個人の能力差を埋めるのではなく、組織全体の知見を下支えする構造を作ることが本質的な属人化対策だといえるでしょう。
こうした取り組みに加え、属人化対策として真っ先に挙げられるのが「作業手順書の整備」です。しかし、単に手順書を作成するだけでは不十分であり、現場の従業員がきちんと読んで理解できる環境を整えること、運用とともに内容を継続的にアップデートできる体制を作ることが極めて重要です。SOPが実態とかけ離れたまま放置されている状況では、むしろ属人化を助長するリスクすらあります。
そこで、現場で形骸化せず、「使われる」作業手順書を整備するポイントについてまとめたガイドブックをご用意いたしました。本記事と併せご活用ください。
>>>「カンコツが伝わる! 『現場で使われる』作業手順書のポイント」を読んでみる
再現性を高める
官能検査における再現性の確保とは、「誰が、いつ、どこでやっても、同じような評価結果が得られる」状態を目指すことです。しかし実際には検査員の状態や環境要因によって判断にばらつきが生じやすく、現場では再現性の低さに悩まされるケースが後を絶ちません。
ここで重要なのは、再現性を個人のスキル向上に任せきりにしないことです。再現性を担保するには、「環境」「プロセス」「評価基準」の3要素を仕組みとして整備・管理する必要があります。具体的には以下のような取り組みが挙げられます。
- 検査室の照度・温湿度・臭気など、環境条件の標準化と記録管理
- 検査実施時間・検査前の体調確認・嗅覚のリセット時間など、運用ルールの明確化
- 標準品や基準サンプルを用いた官能トレーニングの定期実施
- 個人の評価傾向を可視化・記録する評価ログシステムの活用
また、定期的に官能検査員の能力検定やスキルの可視化(洗い出し)を実施することで、感度や識別力の変化を客観的に把握し、必要な補強を行うことも重要です。
このように、再現性を高めることは個人の能力に依存せず、組織として「制度設計」していくべき領域です。検査のやり方だけでなく「再現性のある仕組み」そのものをつくることが、品質保証の信頼性を大きく左右します。
再現性を高めるには、まず従業員が持つ能力(スキル)を把握し、適切に管理することが欠かせません。しかし、現場では「誰が・何を・どこまでできるのか」が可視化されていないケースが多く、スキルの偏りや不足に気づかないまま日々の検査が進んでいることも珍しくありません。
そこで、「スキルの可視化・標準化」の進め方を解説したハンドブックをご用意いたしました。検査員ごとのスキルの棚卸し方法、教育・トレーニング計画の立て方まで網羅しているため、是非ご覧ください。
>>「効果の出ない」スキル管理の原因は?現場力を高めるスキル管理のコツを学ぶ(無料配布中)
次章では、属人化の防止と再現性の向上に役立つ新たな教育手段である、「動画」についてご紹介します。
【サンプル有】官能検査の教育体制を整備する有効手段は「動画」
前述した属人化の防止と再現性の向上を従業員教育で改善する手段として、「動画マニュアル」の導入が徐々に進んでいます。ここでは動画の活用による3つのメリットと、実際のサンプル動画をご紹介します。
- 複雑な作業プロセスやカンコツが「目で見て分かる」
- 「誰が教えても同じ教育内容」になる
- 「力量評価」の代替ツールになる
他にも動画マニュアルのサンプルと導入効果について知りたい方は、以下のリンクをクリックし別紙のハンドブックをご覧ください。
>>実際に業務で使われている動画マニュアルのサンプル集!教育による標準化はどう叶える?(無料配布中)
複雑な作業プロセスやカンコツが「目で見て分かる」
官能検査は、微妙な味や香りの違い、製品の触感など、言葉だけでは伝えにくい感覚的な要素を多く含みます。動画マニュアルなら、熟練者の動き、製品の状態変化を視覚的に捉えられ、理解を深められます。
例えば、目視検査の「確認所作」や、検査道具の「組み立て方」など、文章や口頭説明では伝わりにくいカンコツも、動画なら一目で理解可能です。
動画マニュアルの例として、工作機械や遠心力鋳造管・産業機械の製造/販売を手掛ける「新日本工機株式会社」の現場従業員が作成した動画マニュアルを以下に掲載します。こちらはスマートフォンで撮影しています。
▼動画マニュアルによる標準化の例(音量にご注意ください)▼
※「tebiki現場教育」で作成
このように、現場従業員でもスマホで手軽に撮影・編集ができる動画マニュアル作成ツールであれば、業務プロセスの標準化や可視化が可能になります。
「誰が教えても同じ教育内容」になる
教育担当者によって教え方に差が生じたり、伝え漏れがあったりすると、検査員のスキルにバラつきが生じ、検査品質の低下につながります。動画マニュアルは、常に一定の品質で、均質な教育を提供するので、新人検査員でもベテラン検査員と同じレベルの知識・技術を習得可能です。
例えば、自動車部品や住宅設備等のプラスチック成形品を手掛ける製造企業である「児玉化学工業株式会社」では、現場従業員が以下の動画マニュアル「ヤスリでバリを取る業務プロセスの解説」を作成し、技術をスムーズに共有しています。
▼動画マニュアルによる教育の例(音量にご注意ください)▼
※「tebiki現場教育」で作成
こうした複雑な業務は教え方にばらつきが生じやすいですが、動画であればこのように一目で「何をどうすればいいか」が把握でき、文字では伝えにくい動きもすべて理解できるようになっています。
「力量評価」の支援ツールになる
動画マニュアルを主軸に置いた教育体制が整備できれば、力量評価も適切に実施できるようになります。官能検査に求められる業務を動画化できれば、それらは単なる現場マニュアルになるだけでなく、官能検査に求められるスキルセットの一覧化にもつながります。従業員ごとに動画の視聴状況が分かれば、すなわちそれは従業員ごとのスキルセットの可視化につながり、力量評価が可能になります。
力量評価の代替ツールでもある動画マニュアルサービス「tebiki現場教育」であれば、下図のように「従業員ごとのスキル習得状況」を可視化できます。

【「動画マニュアルが紐づくクラウド型スキルマップ – tebiki現場教育」より抜粋】
tebiki現場教育の詳細機能や活用事例について詳しく知りたい方は、以下のPDF資料もあわせてご覧いただくと、tebikiを現場でどのように活用できるのか・どのように稼働率向上に貢献するのかが具体的にイメージできます。
>>>PDF資料「動画マニュアルが紐づくクラウド型スキルマップ『tebiki現場教育』」を見てみる
品質検査の現場教育に有効な「tebiki現場教育」
動画の有効性は分かったものの、「動画の作成は難しそう」「導入に手間がかかるのでは?」と感じる方も多いのではないでしょうか。
そこでおすすめしたいのが、操作がシンプルで誰でも使いやすい動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」です。

「tebiki現場教育」は、現場での作業手順や官能検査のポイントをスマートフォンで撮影し、簡単に編集・共有できるクラウド型の動画教育システムです。視覚と聴覚を使った動画による学習は紙やテキストのマニュアルよりも直感的に理解しやすく、未経験者でも短期間で習得できます。
また、実際の作業手順をそのまま動画にすることで言葉や表現のばらつきを防ぎ、手順や検査基準を正確に共有・再現できるため、標準化と検査品質の均一化にもつながります。
さらに、自動字幕機能や多言語対応により、多国籍なスタッフが在籍する現場でもスムーズな教育が可能です。教育の進捗をデータとして可視化できるため、個々のスキル向上の管理も容易になります。
実際にtebiki現場教育を導入した自動車部品メーカーである「上松電子株式会社」では、教育不足や言語の壁による品質不良の課題が大きく改善されました。
外国人作業者の多い現場でも、紙マニュアルでは伝わりにくい細かな作業のニュアンスや手順が動画によって視覚的・聴覚的に正確に伝えられるようになり、教育の均一化が実現。特に塗装工程では、不良見逃し率を500ppmから0ppmに削減する成果を上げました。
さらに動画を通じてコミュニケーションが活性化し、現場の雰囲気が明るくなったという副次的効果も報告されています。今後はスキルマップ機能を使って、個々のスキルに合わせた教育を行う仕組み作りを進めていく予定です。
上松電子の事例は、動画マニュアルが再現性の高い教育と品質向上に直結する手段であることを示しています。
tebiki現場教育の具体的な機能やプラン、活用事例は以下のリンクをクリックして概要資料をご覧ください。
>>>「tebiki現場教育」の機能や導入効果を詳しく見てみる
まとめ:教育による標準化で官能検査の質を高めよう
官能検査は、人間の五感を活用して製品の品質を評価する検査手法であり、機械では検出できない微細な違いや感覚的な特性を把握できます。品質保証、製品開発、官能特性の把握などが主な目的で、分析型と嗜好型に分類されます。また、検査方法として二点識別法や三点識別法などが用いられます。
官能検査には検査品質のバラつきや属人化といった課題があり、課題解決のためには教育の標準化が重要です。
そこで、製造業に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を活用した動画教育が有効です。スマートフォンで簡単に撮影・編集でき、多言語対応・自動字幕機能も備えているため、検査手順の統一と技術継承を効率的に実現します。
検査員のスキル向上や教育体制の改善を図りたい現場担当者の方は以下の画像をクリックし、是非詳細をご覧ください。