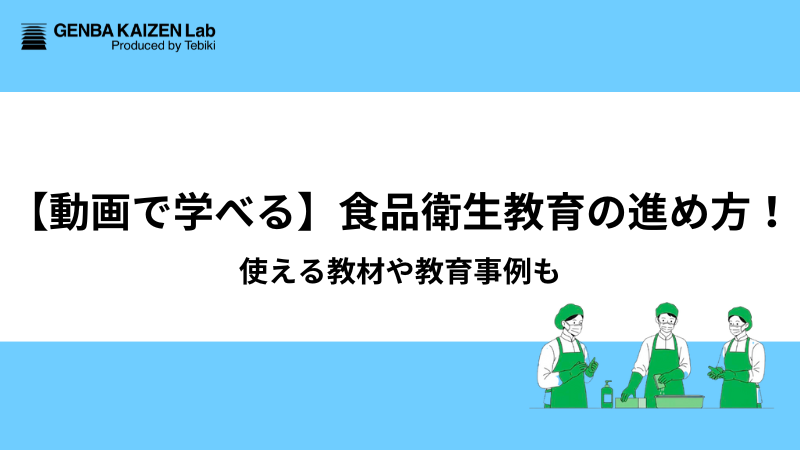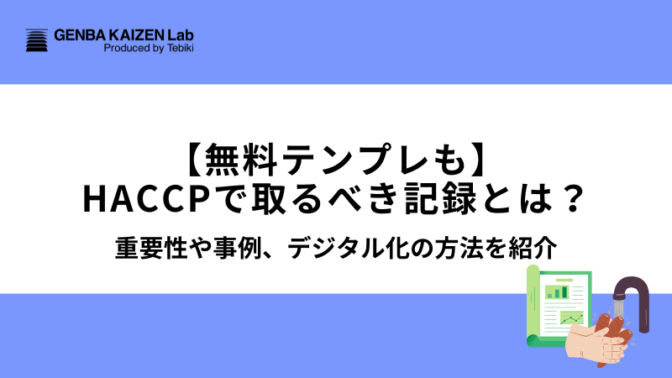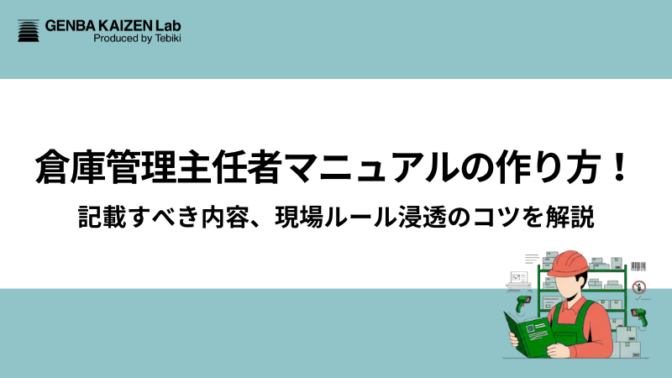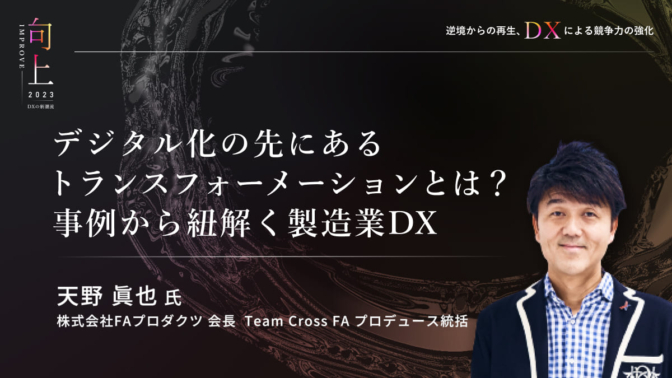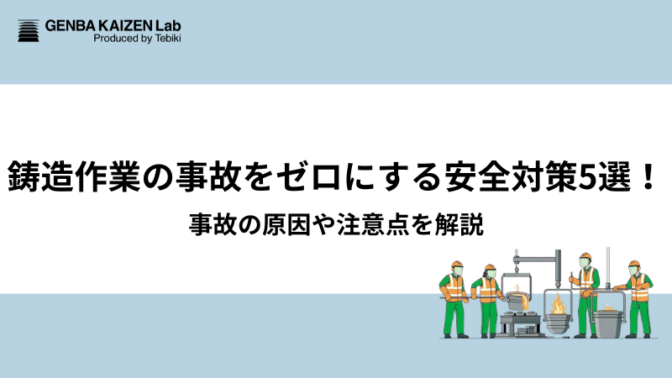かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を展開する現場改善ラボ編集部です。
食品の製造現場では、一般的な衛生管理に加えて、より高度で徹底した管理が求められます。特に新人や経験の浅い従業員への教育が不十分であると、思わぬ事故やトラブルを招くおそれがあります。
本記事では、食品衛生教育に役立つ具体的な資料やネタをわかりやすくご紹介。教育内容や効果的な指導テクニックまで詳しく解説します。食品衛生教育の質を高めたい方は、是非参考にしてください。
なお、より実践的な衛生管理・衛生教育の仕組みづくりを知りたい方には、別紙の資料『食品トラブルを防ぐ!衛生管理を「守られる仕組み」に変える教育法』もおすすめです。現場でルールが“定着する”教育の考え方と実践ステップをわかりやすくまとめています。
>>食品トラブルを防ぐ!衛生管理を「守られる仕組み」に変える教育法を見る
目次
食品衛生教育とは:基本と重要性
はじめに、食品衛生教育の基本事項を整理しておきましょう。基礎を押さえることで、効果的な教育の土台が築けます。
- 食品衛生教育とは何か
- 食品衛生の基礎は「食品衛生法」の遵守から
- 食品衛生教育の役割と効果
食品衛生教育とは何か
食品衛生教育とは、食品を衛生的に取り扱うために必要な知識を身につけさせることです。製造・加工・販売・提供など、食品に関わるすべての人を対象に実施します。
単なる知識の定着ではなく、安全な食品を提供するための意識改革や行動変容を促す必要があります。
食品衛生の基礎は「食品衛生法」の遵守から
食品衛生法第3条では、以下のように規定されています。
販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
引用元:e-Gov 法令検索|食品衛生法
食品衛生教育は、上記の「販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得」に該当し、実施に努める必要があります。食品衛生法に加え、「大量調理施設衛生管理マニュアル」や「食品等事業者が実施すべき管理運営に関する指針(ガイドライン)」においても、食品衛生教育の重要性は示されています。
食品衛生教育の役割と効果
食品衛生教育によって得られる役割と効果は、以下の通り整理できます。
| 食品衛生教育の役割・効果 |
|---|
| ・「なぜこの業務が必要なのか」を理解でき、日々の業務への責任感が増す ・ミスを早期に発見・対応できる能力が養われ、トラブルを未然防止できる ・食品衛生管理が強化されることで顧客からのクレームが減る ・教育体制の整備により、外部に対する信頼性をアピールでき、社会的信用の向上につながる |
基本と重要性を理解できたところで、実際の教育に取り入れるべき具体的な内容について解説します。
食品衛生教育に含めるべき内容とは?
食品衛生教育で実際に指導すべき内容をまとめました。教育資料の作成や指導の際にご活用ください。
食品衛生に関する基礎知識
食品衛生に関する基礎知識とは、食品の安全を確保するために現場で守るべき基本ルールのことです。例えば以下の内容が該当します。
| 正しい手洗い | ・衛生的手洗い ・手洗いのタイミング (作業開始前、トイレの後など) |
| 衛生的な身だしなみ | ・作業着・帽子・マスクの正しい着用 ・アクセサリー禁止 ・ポケットに物を入れない ・爪・髪・服装の管理 |
| 衛生的な環境づくり | ・5S活動 ・7S活動 |
関連記事:【食品工場】衛生管理の基本を解説!マニュアルを守らせるコツも
食品ハザードへの注意・基礎知識
食品ハザードの教育は、食品事故を防ぐために理解しておく必要があります。特に新人教育において、食品を扱うことの責任の重さを理解させるうえで重要です。
| 生物的ハザード | 化学的ハザード | 物理的ハザード | |
|---|---|---|---|
| 例 | ・細菌 ・ウイルス ・寄生虫 | ・洗剤 ・殺虫剤 ・アレルゲン | ・金属片 ・昆虫 ・髪の毛 |
| リスク | ・食中毒 ・感染症 | ・内部機能障害 ・アナフィラキシーショック | ・ケガ ・内臓損傷 |
| 原因 | ・加熱不足 ・食材の取り扱い不備 ・手洗い不足 | ・保管方法が不十分 ・意図せず混入 ・クロスコンタミネーション | ・器具の破損 ・点検のモレ ・身だしなみの不備 |
| 防止策 | ・適切な温度管理 ・正しい手洗いの徹底 | ・保管方法の見直し ・ゾーニングの徹底 | ・異物混入対策 ・衛生的な身だしなみの徹底 |
従業員の衛生管理
従業員が特に注意すべき衛生管理の項目をリスト化してご紹介します。
- 毎日の健康チェック
- 発熱、下痢、嘔吐など体調不良時の報告
- 粘着ローラーのかけ方
- エアシャワーの浴び方
- 持ち込み禁止リストについて
- 傷・手荒れがある場合の手袋や絆創膏の使用ルール
上記の内容は「入室マニュアル」に記載される事項です。入室マニュアルの具体例やわかりやすく作成するための方法は以下の記事で解説しています。
関連記事:【テンプレあり】食品工場の入室マニュアル見本例!効果的に衛生管理を行うには?
施設・設備・器具の衛生管理
施設や設備、器具の衛生管理において重要なポイントをまとめました。以下の内容を従業員に徹底させることで、ハザードを発生させない環境を維持できます。
- 清掃・洗浄・消毒の手順
- 使用前・使用後の設備や器具の洗浄・消毒
- 点検・メンテナンス
- 壁・床・排水溝などの定期清掃
- 清掃用具の清潔な保管
- ゴミの分別・保管方法と廃棄処理
- ねずみや昆虫の発生防止と駆除
関連記事:一般衛生管理とは?PRPやHACCPとの違いも解説
製造工程ごとの注意点
製造工程における具体的な教育内容をまとめました。
| 製造工程 | 教育内容 |
|---|---|
| 受入 | ・納品物の温度・状態・表示の確認 ・異物・破損・期限切れの有無のチェック |
| 保管 | ・冷蔵・冷凍・常温での適切な温度管理 ・食品ごとの保管場所・区分の管理 |
| 洗浄 | ・専用器具(包丁・まな板など)の使い分け |
| 加熱 | ・加熱温度・時間の測定 ・加熱前後の器具・作業スペースの区分け |
| 冷却 | ・調理後の迅速な冷却 ・冷却機器の温度管理 |
ヒヤリハット・事故事例の共有
ヒヤリハットや食品事故事例は他の従業員と情報共有することで、危険な行動を具体的に認識できます。実際の現場で発生した事例をもとに学ぶことで、理解が深まり、注意喚起や衛生意識の向上にもつながります。
実際に発生したヒヤリハット事例について、現場改善ラボの会員213名のアンケート回答をもとにまとめた資料もございます。「現場ではどうすべきだったのか・次はどうすべきか」といったKY活動や再発防止策に是非お役立てください。
HACCPに沿った食品衛生管理
HACCPとは、製造工程のなかで起こりうる危害(ハザード)を見つけ出して管理することです。従業員がその考え方や管理方法を理解し、日々の業務に活かすことが求められます。
具体的な衛生管理の手法や教育内容については、以下の記事内で詳しく解説しています。本記事と併せ是非ご覧ください。
関連記事:【HACCP教育】従業員には何を教える?効果的な教育方法も!
ここまで、食品衛生教育について基本的な内容を解説しました。ですが、これらの内容をわかりやすく伝えるにはわかりやすい教材や教育時間が必要…。そこで、次章では従業員に理解されやすい「動画形式」の教材についてご紹介します。
食品衛生教育のネタに使える!セミナー動画集
食品衛生の専門家が解説するセミナー動画をご用意しました。現場での教育や研修に活用でき、すべて無料で視聴可能です。
HACCPに関するセミナー動画
HACCPの基礎から実践のポイントまで網羅したセミナーです。1,000名以上のHACCP責任者や米国FDA予防管理適格者の育成に携わる今城敏氏が解説しています。
▼動画概要▼
- HACCPに沿った衛生管理が求める基本事項
- 食品衛生管理における「3つのポイント」
- 衛生管理を標準化し、衛生レベルを保つ効果的な方法
>>「食品事故ゼロ!HACCPに基づく安心安全な『衛生管理』手法」を視聴する(無料公開中)
入場教育の徹底に関するセミナー動画
食品事故を未然に防ぐため、具体的にどのような異物混入対策を立てるべきか解説しています。『月刊HACCP』の発行人である杉浦 嘉彦氏による講演のもと、実践につなげるための方法をわかりやすく紹介しているので、対策強化を目指す企業の方は必見です。
▼動画概要▼
- 食品の異物混入の種類と影響
- 食品安全ハザードとしての異物混入対策
- 異物混入が発生した際の対応
>>「食品工場の労災から新人を守る入場教育の新標準」を視聴する(無料公開中)
アレルゲン対策に関するセミナー動画
アレルゲン混入を防止するための仕組みづくりや管理手法を解説しているセミナーです。「ルールや手順を定めているのに、現場からアレルゲン交差接触のリスクがなくならない…」という事態を防ぐうえで役立つポイントや、従業員の意識を高める方法についてとことんご紹介します。
▼動画概要▼
- 食物アレルゲンに関する法的要求事項
- 現場のアレルゲン管理への自覚をうながす方法
- アレルゲンの交差接触を防ぐ2つのツール
>>「食品製造のアレルゲン対策最前線」を視聴する(無料公開中)
異物混入対策に関するセミナー動画
一般的な衛生教育の内容に加え、労働災害やヒヤリハット防止に向けた安全衛生教育も行うと良いでしょう。新人教育を担う方に向け、食品工場における労災防止につながる効果的な入場教育の方法を解説しています。
▼動画概要▼
- 新人が現場の「キケン」に気づかない理由
- 労災をゼロにするための入場教育の秘訣
- 「失敗の情報伝達」から見るルールを徹底させる方法
>>「食品への異物混入対策と効果的な教育方法」を視聴する(無料公開中)
食品衛生教育を効果的に進めるコツ
食品衛生教育を実施する際に、従業員の理解を深めるためのポイントをご紹介します。現場教育に是非お役立てください。
不適切な食品の取り扱いで起こる危険性を伝える
従業員に食品衛生教育を浸透させるためには「なぜそれが必要なのか」=危険性を理解させることが重要です。
例えば、単に「手を洗いましょう」「加熱しましょう」と言っても、背景がわからなければ習慣化されません。「怠った場合、どんな被害が及ぶのか」を具体的かつストレートに伝えることがポイントです。
関連記事:食品事故一覧!日本の有名事例をもとに対策・傾向を分析
教育のネタは現場で集める
効果的な教育内容とは現場の実態を反映していることが前提です。日々の現場で起きている小さなミスやヒヤリハットを教育ネタとして取り上げると良いでしょう。
例えば「冷蔵庫の扉が半開きだった」「手袋の交換を忘れていた」など、よくある事例を用いることで当事者意識を持つことができ、スムーズな理解につながります。
カリキュラムを作成する
行き当たりばったりの指導では、知識が断片的になり、教育内容は定着しにくくなります。カリキュラム化することで学ぶべき内容が整理され、段階的に理解を深められます。
例えば「動画マニュアルtebiki」では、動画マニュアルを作成する以外にも、「基礎編」「応用編」など内容を教科書のように整理できる機能があります。これにより、必要な知識を順序立てて習得でき、知識の定着を促します。
-1024x584.png)
ロールプレイを実施
学んだ知識を活かすための手法としてロールプレイは効果的です。例えば、手洗いの手順をただ説明するのではなく、実際に手を動かして行うことで、動作を体に染み込ませられます。
また、異物混入が発生した場合の対応など、緊急時を想定したシミュレーションも有効です。現場の状況に即した場面を再現することで従業員の理解が深まり、実践力と衛生意識の両方を高められるでしょう。
定期的なフォローアップ
学んだ知識を現場で活かすためには、継続的な振り返りが欠かせません。食品衛生のように日々の業務に直結する知識は、一度学んで終わりではなく繰り返し確認する必要があります。
効果的な方法が定期的なテストの実施です。例えば「動画マニュアルtebiki」に搭載されているテスト機能は、動画マニュアルで学んだ内容の理解度を確認できます。
.jpg)
しかし、上記の方法を行っても、現場に教育内容が浸透しないケースがみられます。次項では、現場の教育が浸透しない原因を深掘りします。
食品衛生教育が現場に浸透しない?よくある課題
学習意欲の高い従業員は教育の定着率が高い一方、学習意欲が低い従業員は以下のような課題により、教育が進まない場合があります。
| 課題 | 詳細 |
|---|---|
| 専門用語に拒否反応 | HACCP、ハザード、クロスコンタミネーションなど普段使用しない用語 |
| 実践の機会が少ない | メンテナンス業務、年間1度しか行わない作業など |
| 理解しているという思い込み | 理解度が可視化されていない場合に生じることが多い |
また、従来の紙のマニュアルは文字が多く、頭で動きを想像して読む必要があるため、学習する意識がないと頭に入りにくいことも。文章だけでは従業員間で作業方法にズレが発生してしまうリスクもあります。
食品衛生教育の資料は「動画化」がおすすめ
食品衛生教育では正しい手洗いの方法や器具の洗浄手順など、動作を伴う作業が多くあります。動画であれば、文章やイラストでは伝えにくい細かな動きも視覚的に指導できるでしょう。
動画マニュアルは現場のリアルがわかる!

実際の作業現場で撮影された動画マニュアルを活用することで、手洗いの方法だけでなく、手洗い洗剤や爪磨きが置かれている場所など1回の視聴で得られる情報が文字よりも多くなります。現場の雰囲気や作業の流れも把握しやすくなるでしょう。
食品衛生教育には「動画マニュアルtebiki」がおすすめ
「動画マニュアルtebiki」は、誰でもスマホで撮影するだけで動画マニュアルが作成できるツールです。映像編集の知識がなくても直感的に使えるため、多くの現場で高く評価されています。実際にマニュアル作成にかかる時間を約75%削減した事例もあるほどです。
さらに、以下の豊富な機能も備えており、現場全体の教育体制を強化できます。
- 理解度をチェックできるテスト機能
- 従業員の習熟度を見える化するレポート機能
- 教科書のように内容をまとめられるコース機能
- キーワード入力だけで見たい動画が見つかる検索機能
- 特定のマニュアルを見てほしい時にはタスク指示機能
「動画マニュアルtebiki」には他にも自動翻訳機能など魅力的な機能が搭載されています。詳しく知りたい方は、以下の画像をクリックして資料をご覧ください。
「動画マニュアルtebiki」で食品衛生教育/新人教育を効率化させた事例
「動画マニュアルtebiki」を導入して食品衛生教育や新人教育を効率化させた事例をご紹介します。動画マニュアル導入の参考資料として是非ご覧ください。
株式会社大商金山牧場
食肉の生産・加工・販売を行う株式会社大商金山牧場。同社では、拠点ごと食品衛生教育のレベルにバラつきがあることを問題視していました。さらに、教育の簡略化や時間経過により会社基準とのズレが発生しているという課題も。そこで教育内容を統一するために「動画マニュアルtebiki」を導入しました。
結果、直感的な操作で簡単に動画を作成できたことで、マニュアル作成にかかる時間は従来の半分以下まで短縮しました。また、質の良いマニュアルは会社基準として全拠点に共有され、企業全体の衛生教育レベル向上に貢献。
新人教育も動画で対応できるようになり、教育担当者の負担が軽減され、教育にかかる工数を約50%削減できました。
| tebiki導入前の課題 | tebiki導入の効果 |
|---|---|
| ・拠点ごと食品衛生教育の質にバラツキがある ・担当者が付きっきりで新人教育 | ・マニュアル作成時間が半分以下に ・会社全体の食品衛生教育レベルの底上げに! ・OJTの教育工数を約50%削減 |
株式会社大商金山牧場の導入事例を詳細に知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
インタビュー記事:衛生管理教育を徹底し、食肉の安全性を確実なものとするために動画マニュアルを活用!
タマムラデリカ株式会社
▼動画マニュアルtebiki活用事例動画▼
大手コンビニエンスストア向けのそば、うどん、中華麺や軽食惣菜などの開発製造を手掛けるタマムラデリカ株式会社。同社では、従来の紙のマニュアルでは外国籍の従業員に細かいニュアンスが伝わりにくく、活用されないという課題がありました。さらに、OJTではベテラン従業員の作業を「見て覚える」雰囲気が強く、従業員の理解度確認が不十分だったことも課題視していました。
そこで紙マニュアルとOJTの課題を克服し、簡単に作成できる動画マニュアルとして「tebiki」を導入。導入後は、外国籍スタッフにも紙マニュアルでは伝わりきらなかった細かいニュアンスが伝わるようになり、新人社員の自学自習も進みました。
今後はOJTの効率化や作業の標準化を推進し、工場間の業務標準化と全体的なレベルアップを図っていくことを目指しています。
| tebiki導入前の課題 | tebiki導入の効果 |
|---|---|
| ・紙マニュアルでは細かいニュアンスが伝わらず、活用されない ・外国籍従業員向け多言語マニュアル作成に手間がかかる ・動画マニュアルを作れる人員が限られ、マニュアル化が追いつかない | ・細かいニュアンスが伝わり、自学自習が進んだ ・動画マニュアル作成時間が大幅に削減(1時間→15分) ・動画マニュアル作成できるメンバーが倍増(3名→20名近く) |
「導入・編集が簡単で、学習コストが低い点がメリット」と語るタマムラデリカ株式会社の導入事例を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
インタビュー記事:動画マニュアル作成時間が75%削減!教育体制を強化し、お客様に喜ばれる商品を提供したい
まとめ
食品衛生教育とは、食品を衛生的に取り扱うために必要な知識を身につけさせることです。単なる知識の定着にとどまらず、意識改革や行動変容を促す必要があります。
しかし、従来のマニュアルは文字情報が多く、動作を頭の中で想像しながら読み進める必要があり、学習意欲が低いと理解しづらいという課題があります。
そこでおすすめなのが「動画マニュアルtebiki」です。伝わりにくい動きをそのまま可視化できるだけでなく、理解度を確認するテスト機能や、従業員の習熟度を見える化するレポート機能も備えています。
「動画マニュアルtebiki」の詳細や豊富な機能にご興味のある方は、下の画像をクリックして詳しい資料をチェックしてください。
▼引用/参照/出典
・e-Gov 法令検索|食品衛生法
・厚生労働省|大量調理衛生マニュアル
・厚生労働省|食品等事業者が実施すべき管理運営に関する指針(ガイドライン)