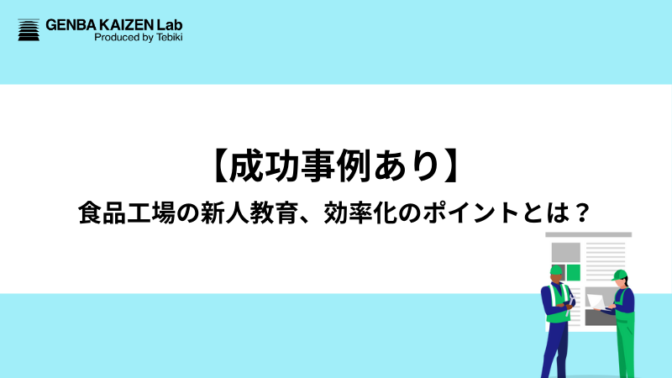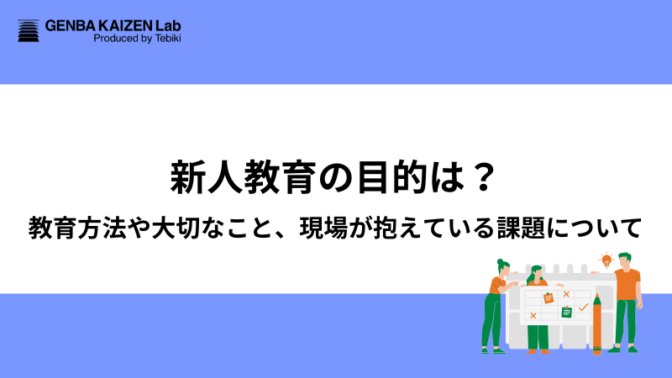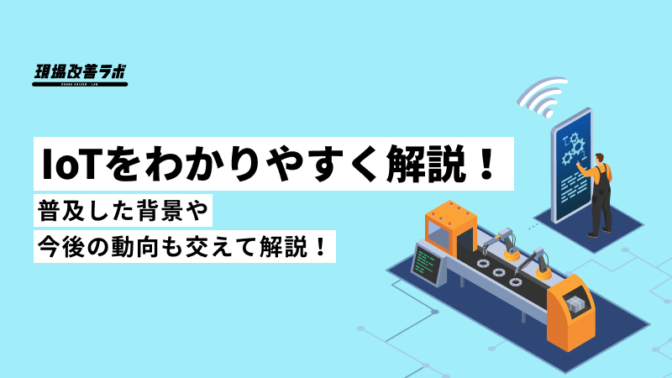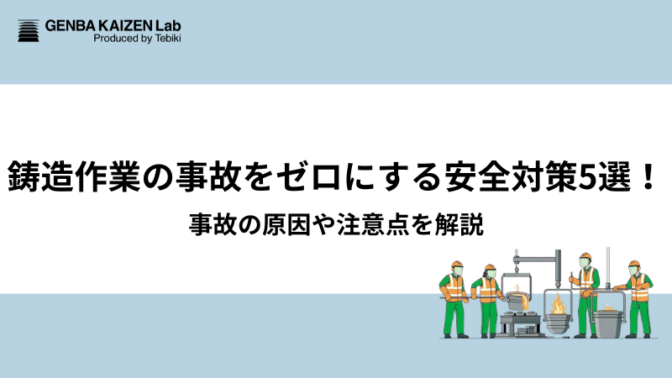工場向け安全対策の動画マニュアル「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
ディスクグラインダーは、金属やコンクリートの研削・切断を行う現場では欠かせない電動工具です。しかし、火花・砥石の破損・キックバックによる労災が後を絶ちません。
そこで本記事では、実際に工場の勤務経験がある筆者の観点も踏まえ、グラインダー作業における安全対策と注意点を整理し、教育の標準化・安全習慣の定着方法まで解説します。
なお昨今、「安全な作業手順を動画マニュアルで見える化し、標準化を進める」現場が増えており、工場における主要な安全対策として広く浸透し始めています。詳しい改善効果や事例は『 動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例(pdf)』をご覧ください。
労災が起きてからでは遅いので、ヒヤリハットで済んでいる現状のうちに安全対策を練ることが鍵を握ります。
>>「動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例(pdf)」を見てみる
目次
グラインダーとは?安全対策が重要な理由
グラインダーとは、砥石(といし)を高速回転させて金属やコンクリートなどの表面を削ったり、切断したりする電動工具です。
特に工場現場で汎用的に使われる携帯型のディスクグラインダー(アングルグラインダー)は、コンパクトながら強力な回転力を持ち、鉄骨のバリ取りや溶接部分の仕上げ、塗装はがしなどで使用されています。
一方で、高速回転による火花や粉じんの飛散、砥石の破損・キックバック(跳ね返り)といった危険が常に伴う作業でもあります。厚生労働省が公開している資料でも、グラインダーによる死亡事故が報告されており、特に顔面や手の負傷、視覚障害を伴う事故が後を絶ちません。
>>『工場の労災ゼロを実現する、安全教育の新常識』を見てみる
グラインダーの事故の多くは「慣れ」や「自己流」が原因です。例えば、安全カバーを外したまま作業したり、砥石の点検を怠ったり、火花の方向を気にせず切断するなど、日常化した小さな油断が重大事故につながります。現場では「ベテランの感覚に頼る教育」や「指導者ごとのばらつき」も多く、安全対策の知識が正しく伝承されないケースが少なくありません。
だからこそ今、求められているのは「安全対策を一時的に守る」ことではなく「誰が作業しても安全が維持される仕組みを作る」ことです。管理者が作業者に安全カバーや保護具の着用、砥石の点検といった基本を習慣化させれば、事故は必ず減ります。そのために本記事の安全対策を参考に、仕組みづくりに役立ててください。
なお昨今、「安全な作業手順を動画マニュアルで見える化し、標準化を進める」現場が増えており、工場における主要な安全対策として広く浸透し始めています。詳しい改善効果や事例は『動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例(pdf)』をご覧ください。
労災が起きてからでは遅いので、ヒヤリハットで済んでいる現状のうちに安全対策を練ることが鍵を握ります。
>>『動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例(pdf)』を見てみる
【教育面】グラインダー作業の安全対策4つ
グラインダー作業はまずは安全対策の教育を徹底させる必要があります。ここでは具体的に教育面での安全対策について以下の4点を解説します。
- 技術伝承の仕組みを整備する
- 「教育担当者によって教え方が違う」を解消する
- ヒヤリハットの可視化と共有
- 危険予知(KY)活動の実施
技術伝承の仕組みを整備する
グラインダー作業では、熟練者が長年の経験で身につけた動作や判断が多く、文字だけでは伝えきれない技術が多くあります。
特に、砥石の角度の取り方や回転時の感覚、火花の飛ばし方などはカンやコツの場合があり、OJTだけでは正確に再現しづらいのが現実です。そのため、技術伝承を個人の記憶や感覚に頼るのではなく、仕組みとして可視化・共有することが重要です。
>>『技術・技能伝承の進め方~伝承を阻害する5つの誤解とその解決策~』を見てみる
技術伝承の仕組みを整備する方法としては、まず作業標準書の整備が基本です。手順ごとに写真や図を入れ、使用する工具、作業姿勢、危険箇所などを明確に示すことで、教育担当者が変わっても同じ品質で指導できます。
ただしここで課題となるのが、以下の観点です。
- マニュアルを整備しても読まれない
- ベテランが我流にこだわり標準化がなされない
- 外国人労働者は日本語マニュアルが読めない
したがって、安全対策のマニュアル整備では「非言語マニュアル」が推奨されています。例えば写真や画像、映像や動画を用いたマニュアルです。
非言語マニュアルの例として、化学メーカーである児玉化学工業株式会社の取り組みが挙げられます。同社は現場で働く外国人の多言語化が進んでおり、動画マニュアルによる作業手順書を展開しています。
※以下の動画は同社の現場従業員がスマホで作成した、実際のサンプル動画です。
▼動画マニュアルによる技術伝承の例▼
※「tebiki」で10分で作成
上のような複雑な業務作業も、動画で手順をおさめれば「誰が見ても同じ解釈」になるので、円滑な技術伝承を促せます。
※本動画は、製造業の現場教育に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」で作成されています。tebikiのサービス詳細や導入事例についてはサービス資料をご覧ください。
>>かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育サービス資料」を見てみる
「教育担当者によって教え方が違う」を解消する
グラインダーの安全教育では、教える人によって内容や強調点が異なることが大きな課題です。担当者の経験や表現の違いにより、同じ作業でも危険認識にばらつきが生じます。
製造業のような、高度な技術が求められる複雑な作業の教育は、マニュアルだけではなかなか教育し切れず、必ずOJT教育(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)が必要になります。とはいえOJTに過剰に依存すると、「人によって教え方が異なる」ことが多発し、属人化のリスクも生じることになります。
また、教育担当者がシフトで不在の場合や新人教育の時間が確保できない現場では、学びの機会が失われがちです。
※OJT教育の負担軽減を実現する教育アプローチについては、以下の資料で詳しく解説しています。
>>『OJT担当者の負担が激減する、OJT教育の新常識とは?』を見てみる
したがって、教育品質のバラつき解消には、グラインダー作業の正しい安全手順をまとめた資料を整備し、それを1つの正しい基準として周知する機会を設けましょう。
例えば、砥石点検・保護具着用・カバー装着といった基本行動を、共通の手順書や動画マニュアルにまとめておくことで、誰が教えても同じ品質の教育が行えます。
明和工業株式会社では作業場にディスプレイを設置し、QRコードで即座に動画マニュアル(を呼び出せる仕組みを設けており、誰でも迷わず標準作業を実行できる環境が整えています。

ヒヤリハットの可視化と共有
ヒヤリハット(危険予知)を組織的に可視化・共有することで、教育面での安全対策が可能です。グラインダー事故の多くは、実際のヒヤリハットや危険の経験が共有されず、同じミスが繰り返される点にあるからです。
例えば、ヒヤリハット事例を動画マニュアルで教材化して「火花が可燃物に引火しかけた」「安全カバーを外したまま使用してしまった」などの実例を映像で見ることで、抽象的な危険意識が個別具体的な意識へと切り替わります。
>>『イラストでわかりやすい!報告から教育まで行えるヒヤリハット事例・対策集』を見てみる
さらに、定期的な安全教育ミーティングや動画による事例共有を行い、危険を全員で再確認する仕組みを整えましょう。チェックリストと結びつけて「ヒヤリ→改善→再発防止」の流れを循環させることで、安全対策が単なるルールではなく、現場改善の文化として根づいていきます。
ヒヤリハットのような不安全行動は、単なる注意喚起や直接指導ではゼロにできません。不安全行動が根本的に起きない「仕組み作り」が重要ですが、行動科学の観点から具体的な対策が解説されている『繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網』を参考にすると、本質的な安全対策のヒントが得られるはずです。あわせて参考にしてみてください。
>>『繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網』を見てみる
危険予知(KY)活動の実施
グラインダー作業の安全を確保するには、危険予知(KY)活動が必要です。KYとは、作業前に「どんな危険が潜んでいるか」を現場全員で話し合い、事故を防ぐための行動を決める取り組みです。
※危険予知活動(KY活動)の進め方の詳細は「KY活動(危険予知活動)の進め方は?記入例文やネタ切れ対策を紹介」でも解説しています
厚生労働省による「労働災害原因要素の分析(平成22年)」によれば、労働災害の96.4%が労働者の不安全な行動に起因して発生しています。そのことから、現場での危険予知活動による安全対策の重要性がわかります。
例えば、保護具の着用忘れ、火花の飛散方向、姿勢の不安定さなどをテーマに危険予知活動を行い、対策を整理すれば、ヒューマンエラーを未然に防ぐことが可能です。さらに、先述のチェックリストやヒヤリハット報告と連携させることで「危険を見つける→改善策を立てる→再発を防ぐ」という循環が生まれます。そうすれば自然と安全対策が根付いた現場へと改善できます。
KY活動は「形だけ」「マンネリ化」といった形骸化が起こることがしばしばあります。これは、作業員が危険を自分事化していない(そんな大事にはならないだろう、と思い込んでいる)ことが根本的な原因です。
安全意識を根付かせるための1つの指針として「動画KYT」が挙げられますが、詳しくは以下の資料で解説しているので、あわせて参考にしてみてください。
>>『労災ゼロ!形骸化したKYTから脱却する動画KYTとは』を見てみる
【実務面】グラインダー作業の安全対策7つ
前節では教育面での安全対策を解説しました。ここからは実務面での安全対策として以下の7つを紹介します。
- 保護具の正しい着用
- 安全カバーの装着
- 砥石の点検と交換
- 試運転の実施
- キックバック防止と正しい姿勢
- 正しい砥石の選択と保管
- 使用後の点検・保管
保護具の正しい着用
グラインダー作業では、飛散する火花や粉じん、金属片から身を守るために保護具の着用が必須です。特に保護メガネやフェイスシールド、防じんマスク、イヤーマフ、耐切創手袋は基本の装備です。
粉じんの多い環境では防じんマスクを、長時間作業では耳栓よりも遮音性の高いイヤーマフを推奨します。また、回転部に巻き込まれる危険がある作業では、手袋を着用しないほうが安全な場合もあります。そのため、手袋の使用可否は作業内容と工具の種類に応じて判断して、教育で明確に伝えることが必要です。
>>『工場の労災ゼロを実現する、安全教育の新常識』を見てみる
安全カバーの装着
安全カバーは、砥石が破損した際に破片の飛散を防ぐ重要な保護装置です。カバーを外して作業すると、破片や火花が直接作業者に向かい、重傷につながる恐れがあります。そのため、どんなに作業しづらくても外してはいけません。
また、カバーは必ずメーカー純正部品を使用しましょう。社外品や流用部品では、取り付け精度が低く破損のリスクが高まります。角度調整や締め付けが甘いと、作業中にズレて防護機能を果たさない場合もあります。安全カバーは「付けるだけでなく正しく付ける」ことが大切です。定期点検を行い、変形や緩み、腐食が見られた場合はすぐに交換しましょう。
>>『ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育』を見てみる
砥石の点検と交換
砥石は高速回転するため、ひびや欠けがある状態で使用すると破裂の危険があります。使用前には必ず外観検査と打音検査を行いましょう。打音検査は、砥石を軽くたたいて澄んだ音がするか確認する方法です。鈍い音がする場合は内部にひびがある可能性があります。
また、取り扱いの基本は「転がすな・落とすな・ぶつけるな」の三原則です。砥石は意外と脆く、軽い衝撃でも内部損傷を起こすことがあります。保管時は乾燥した平面に置き、湿気や温度変化を避けることも重要です。交換時は電源プラグを抜き、付属の専用工具でしっかり固定して行います。点検と手順を徹底することで、砥石破損による労災を未然に防げます。
>>『工場の労災ゼロを実現する、安全教育の新常識』を見てみる
試運転の実施
新しい砥石を取り付けた後は、必ず試運転を行うことが義務づけられています。厚生労働省の外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業(建設業)では、取り替え時には3分以上の試運転が推奨されています。試運転を行うのは、取り付けのズレや内部欠陥による破損を事前に確認するためです。
試運転中は作業者が安全距離を取り、砥石の回転状態を目視で確認します。異音や振動がある場合は、すぐに停止して原因を確認してください。試運転を省略すると、実作業中に砥石が破裂して重傷事故に発展する恐れがあります。また、定期的に機械側の回転速度も確認し、砥石に表示された最高使用周速度を超えないよう管理しましょう。
キックバック防止と正しい姿勢
グラインダー作業の事故で多いのがキックバックです。キックバックは、砥石が材料に食い込み反動で跳ね返る現象で、顔や腕に大けがを負う危険があります。防止するには、常に両手で工具を保持し、補助ハンドルを活用することです。片手作業や不安定な姿勢での使用は絶対に避けましょう。
また、切り込みを深くしすぎると反発力が増し、キックバックが起きやすくなります。10mm以上深く切り込む場合は注意して保持し、一定の角度でゆっくり進めることが大切です。さらに、姿勢は重心を低くし、足元を安定させることでリスクを減らせます。焦らず、安定した操作を徹底することが、労災防止につながります。
>>『ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育』を見てみる
正しい砥石の選択と保管
砥石は用途によって「切断用」と「研削用」に分かれています。切断用は薄く外周で切る構造、研削用は厚みがあり面を削る構造です。用途を誤ると砥石が破損し、飛散事故を引き起こします。必ず目的に合った砥石を選びましょう。
さらに、使用するグラインダーの最高回転数と砥石に表示された「最高使用周速度」が一致しているか確認することが重要です。保管時は湿気や温度変化を避け、平らな面に水平に置きましょう。立てかけたり重ね置きすると変形や破損の原因になります。定期的に在庫を点検し、古くなった砥石は早めに交換する習慣をつけてください。
使用後の点検・保管
作業後の点検を怠ると、次回の使用時に思わぬトラブルを招きます。使用後は電源を切り、プラグを抜いてから砥石・カバー・電源コードの状態を確認します。変形やひび割れ、焦げ跡がある場合はすぐに交換しましょう。
コードの断線やプラグのゆるみも感電の原因となるため注意が必要です。保管時はグラインダーを定位置に戻し、砥石部分を上に向けた状態で安定して置きます。金属粉や粉じんを除去してから収納することで、機器寿命を延ばせます。また、作業記録や点検結果を共有する仕組みをつくると、次の作業者が安心して使用できます。
>>『工場の労災ゼロを実現する、安全教育の新常識』を見てみる
グラインダーの作業中の4つの注意点
グラインダーは正しい扱いを怠ると一瞬で重大事故につながります。ここでは作業中の以下の4つの注意点を解説します。
- 丸ノコ用チップソーを装着しない
- 空中でスイッチを入れない
- 強く押し当てすぎない・無理な姿勢で削らない
- 周囲の火花飛散・可燃物への注意
丸ノコ用チップソーを装着しない
ディスクグラインダーに丸ノコ用チップソーを取り付けるのは絶対に避けてください。丸ノコは本来、回転数がグラインダーよりも低い機械に合わせて設計されています。そのため、グラインダーに装着すると回転速度が合わず、刃のチップが飛散して深刻なけがや死亡事故を引き起こす危険があります。
また、丸ノコ用刃は保護カバーの取り付けができないため、破片や火花が直接作業者に向かう可能性が高くなります。見た目が似ていても構造や設計目的がまったく異なるため、互換性はありません。
厚生労働省の外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業(建設業)でも「丸ノコ刃の装着は禁止」と明記されています。用途に合った砥石を使用し、製品ラベルの回転数・材質・使用面を必ず確認してください。
>>『ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育』を見てみる
空中でスイッチを入れない
グラインダーのスイッチを入れる際は、必ず砥石を空中でなく安全な位置に固定してから行ってください。空中でスイッチを入れると、モーターのトルクにより本体が急に反動し、作業者の手から飛び出すおそれがあります。その勢いで他人や自分の体を傷つけるケースが多く、実際の労災でも多発しています。
また、スイッチを切る際も同様に、砥石の回転が止まるのを待たずに置くと、跳ね返りや接触事故の原因になります。実際に厚生労働省の外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業(建設業)で「砥石が完全停止するまで置かない」ことが求められています。使用後は電源プラグを抜いてから保管する習慣をつけましょう。
強く押し当てすぎない・無理な姿勢で削らない
作業中に砥石を材料へ強く押し当てすぎると、摩擦熱や過負荷によって砥石が破損する危険があります。特に深く削ろうとするほど反発力が強くなり、キックバック(跳ね返り)を引き起こしやすくなります。グラインダーは軽い力で当てても十分な研削力を発揮するため、無理な力を加える必要はありません。
また、無理な姿勢で作業を続けると、バランスを崩して転倒したり、工具を支えきれなくなったりするリスクも高まります。両手でしっかり保持し、重心を低くして安定した姿勢を保ちましょう。体の真横ではなく、火花が自分に向かない角度で操作することも重要です。
>>『工場の労災ゼロを実現する、安全教育の新常識』を見てみる
周囲の火花飛散・可燃物への注意
グラインダーの火花は、金属粉を高温で飛散させるため危険です。作業時には周囲の可燃物に火花が当たらないよう、環境を整えてください。木材や紙、油類、ウエスなどは着火しやすく、数メートル離れていても引火することがあります。
特に狭い工場や倉庫では、消火器の設置位置も事前に確認しておきましょう。また、近くで他の作業者がいる場合は、火花の方向を変えるか防炎シートを使用します。屋外作業では風向きにも注意しましょう。
さらに、防じんマスクを着用しないと金属粉を吸い込む危険があります。火花や粉じんを「見える危険」として常に意識し、安全対策を徹底してください。
【事例】標準作業の遵守や安全ルールの浸透に成功している製造業
標準作業の遵守や安全ルールの浸透に成功している事例として以下の3つの事例を紹介します。
- 労災事例を動画にし、周知させて現場の安全意識が向上させた事例
- 動画を使って日本人、外国人問わずルールが浸透した事例
- 多能工に向けたベテランから若手への教育がスムーズになった事例
労災事例を動画にし、周知させて現場の安全意識が向上させた事例:コスモ石油
コスモ石油株式会社は、国内有数の石油精製・販売企業です。特に堺製油所は、京阪神エリアに向けてガソリンや灯油、軽油などを安定供給する重要拠点であり「安全第一」が企業理念です。ガソリンなどの危険物を扱う現場では、わずかな油断が重大災害につながるリスクがあるため、生産よりも安全を優先する体制を全社で徹底してきました。
しかし、同社では長年「教育の属人化」という課題を抱えていました。プラント設備が大規模で専門用語も多く、紙の手順書では作業の「動き」を伝えきれず、結果としてOJTに依存せざるを得ませんでした。新人や中途採用者が増える中で、教育担当者の負担が増し、理解度にもばらつきが生じていたと言います。
そこで堺製油所では、現場教育の効率化と安全意識の定着を目的に、動画マニュアル「tebiki現場教育」を導入しました。特に効果を発揮したのが、労働災害の再現動画による教育です。過去の災害事例を実写映像で再現し、原因と再発防止策をセットで周知することで、従業員一人ひとりが「危険を自分ごと」として理解できるようになりました。
こうした取り組みは、協力会社を含めた「ゼロ災実行リーダー会議」でも活用され、映像を使った啓発活動として高い評価を受けています。従来のテキスト中心の教育では伝わりにくかった臨場感と具体性が加わり、安全意識が大きく向上しました。結果として、教育時間の削減と理解度の均一化が進み、現場におけるヒューマンエラー防止につながっています。
>>同社が扱う動画マニュアル「tebiki現場教育」の紹介ページはこちら
インタビュー記事:コスモ石油 堺製油所が実現する“安全第一”の動画教育改革
動画を使って日本人、外国人問わずルールが浸透した事例:児玉化学工業株式会社
児玉化学工業株式会社は、1946年創業の老舗化学メーカーです。住宅設備や自動車部品、産業機器などで合成樹脂製品を製造しており、高い成形技術と品質管理力を強みとしています。主力となる自動車部品や住宅設備関連の生産現場では、多国籍な人材が協働しており、スペイン語・ポルトガル語・中国語・ベトナム語など、さまざまな言語が飛び交う環境です。
しかし、そうした国際的な職場環境こそが大きな課題となっていました。紙のマニュアルでは専門用語や細かな動作が伝わりづらく、作業者によって手順の理解が異なる状態になりました。教育はベテランのOJT頼みで、人によって教え方や解釈が違い「暗黙の了解」が横行。結果として、作業ミスや製品不良が増加し、現場全体の品質と安全が不安定化していました。
こうした課題を解決するために導入されたのが動画マニュアル「tebiki現場教育」です。児玉化学工業では、既存の紙マニュアルを動画化するとともに、これまで言語や経験の壁で伝えきれなかった手順・ルールを視覚的に共有できるようにしました。スマートフォンで撮影し、簡単に編集できる点が現場に受け入れられ、マニュアル作成の工数は従来の約1/3に削減されました。
動画は外国語字幕にも対応し、日本人・外国人問わず統一的な教育が可能になりました。作業の「正しい動き」と「やってはいけない理由」を同時に見せることで、従業員の理解度と安全意識が向上。さらに、「tebikiマイスター」を中心とした社内展開が進み、工場間での教育格差も解消されつつあります。
>>同社が扱う動画マニュアル「tebiki現場教育」の紹介ページはこちら
インタビュー記事:手順書作成の工数は紙の1/3になったと思います。動画で作るのはかんたんだし、学ぶ側にもわかりやすいですよね。
多能工に向けたベテランから若手への教育がスムーズになった事例:株式会社メトロール
株式会社メトロールは、世界200社以上の装置メーカーに採用されている高精度センサメーカーです。工作機械や産業用ロボットに組み込まれる位置検出センサを製造しており、製造現場での不良品防止や精密加工の品質向上を担っています。従業員は約120名で、その半数が製造部門に所属。多品種少量生産を行うため、現場では高いスキルと柔軟な対応力が求められます。
しかし、同社では新人教育がベテランの経験に大きく依存しており、教える人によって手順や内容が異なる属人化が進んでいました。特に、未経験者や派遣社員が多い時期には、文書や口頭だけの教育では理解に時間がかかり、具体的な作業イメージを持ちにくいという問題も発生。結果として教育コストが増大し、現場の生産効率にも影響を及ぼしていました。
こうした状況を打破するため、株式会社メトロールが導入したのが動画マニュアル「tebiki現場教育」です。導入後は、現場で働くスタッフの安全衛生に関するマニュアルを優先的に作成しました。例えば、アルコールが誤って目に入ってしまうことのないように正しく蓋を閉めましょうという内容や素手でアルコールを扱ったあとにその手で目に触れてしまうと危険なので素手で扱わないようにしましょうといった内容の動画など、主に未経験で入社してくる新人向けの動画マニュアルです。
また新人向けという点では、1回動画を見れば覚えられるような操作が簡単な装置の動画マニュアルも作成していきました。そういった動画は、一度作成してしまえば自分が繰り返し教える時間の削減になります。導入前は1時間ぐらいかけて教えていた内容が、その動画マニュアルを見ながら、その中でも大事なところを停止して説明することで、半分以下の時間で教えられるようになっています。
>>同社が扱う動画マニュアル「tebiki現場教育」の紹介ページはこちら
インタビュー記事:世界で200社以上の装置メーカーに採用されているセンサの製造工程でtebikiを活用し、新人教育と多能工化を推進
グラインダー安全対策の結論は「作業員が注意を払い、管理者は徹底させる」
本記事では、グラインダーの安全対策を教育・実務の両面から整理し、厚生労働省の資料などをもとに解説しました。安全は個人の注意だけでなく、組織としての仕組み化と習慣化が欠かせません。
動画マニュアルの導入やヒヤリハットの共有、チェックリストの活用などにより、「守るべきこと」を理解して実践できる状態へと変えることが重要です。現場の安全は一人の努力ではなく、チーム全体の取り組みで守るものです。
教育・仕組み・文化の3つを意識し「ゼロ災害」実現に向けた継続的な改善サイクルを回していきましょう。
< 出典情報 >
・ 職場のあんぜんサイト 労働災害事例(厚生労働省)