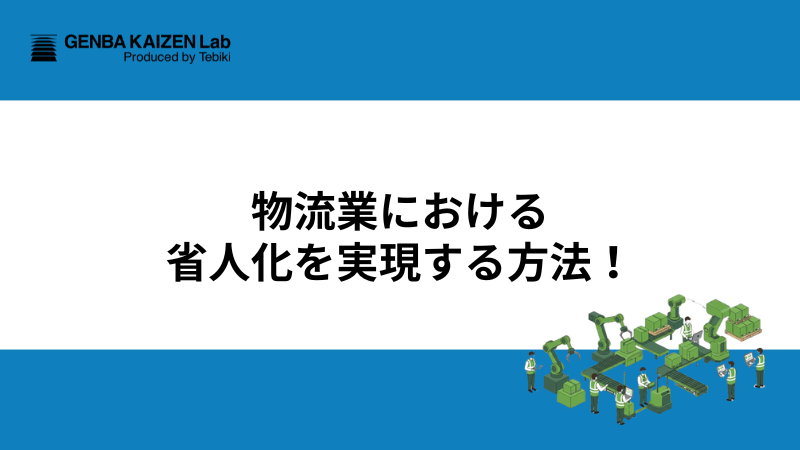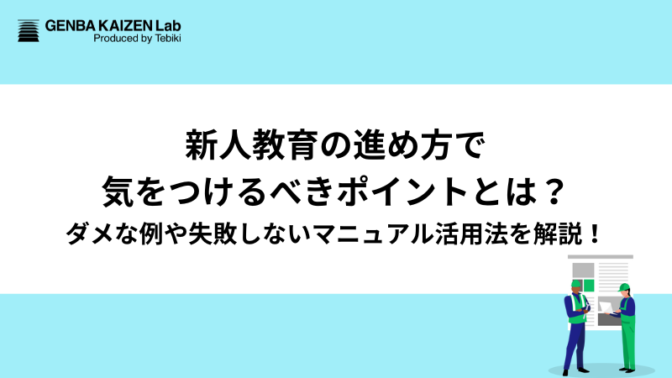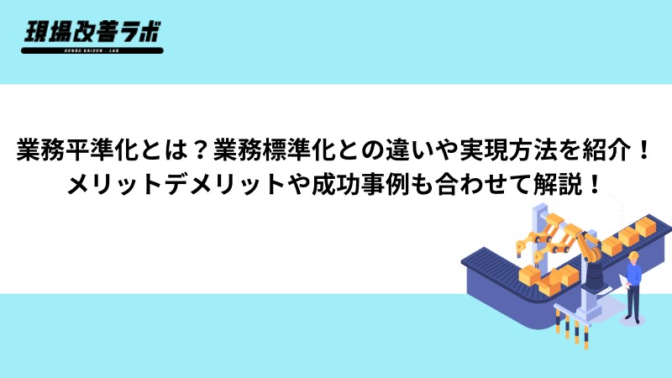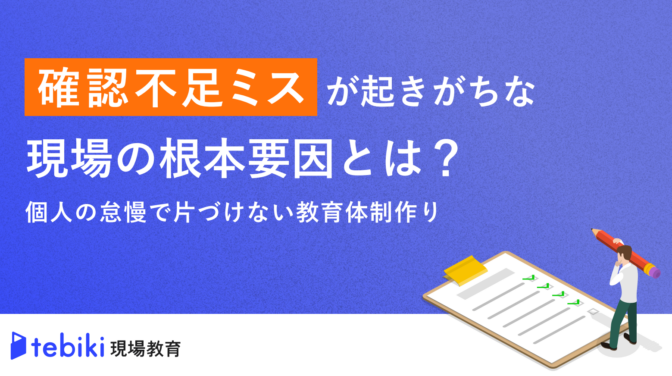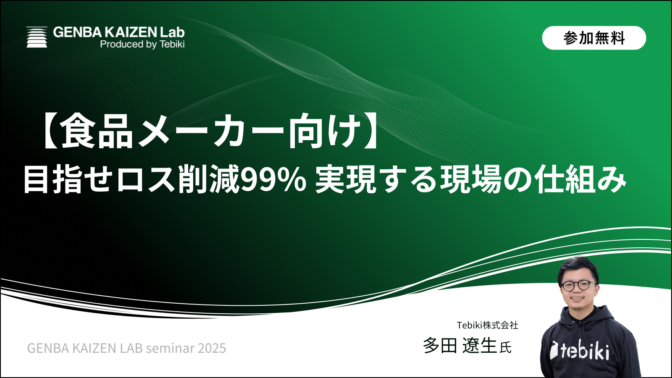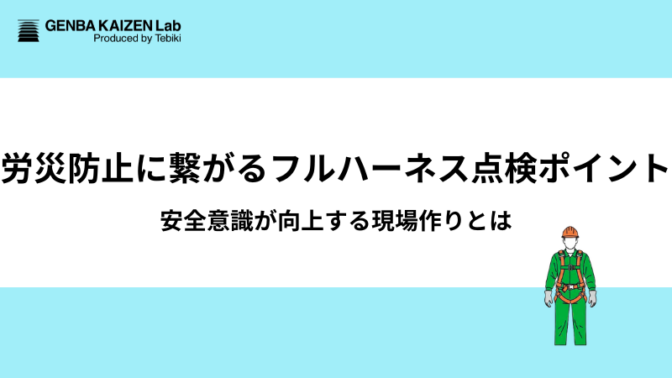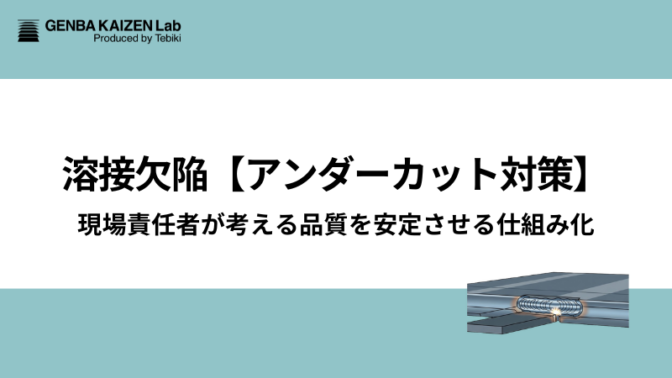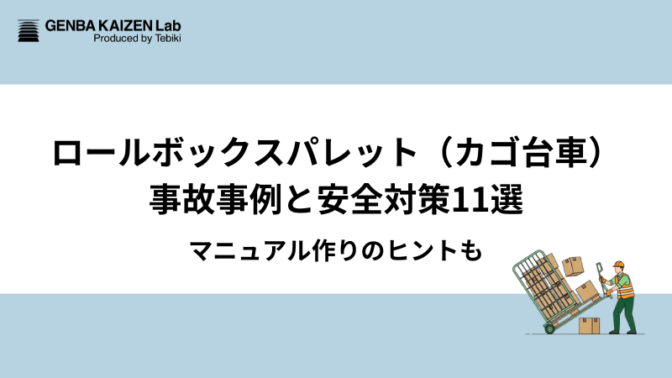かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
昨今の物流業界は、EC市場の拡大による物量増加や、深刻な人手不足といった多くの課題に直面しています。これらの課題への有効な対策として、「省人化」への関心が高まっています。
この記事では、物流現場における省人化の定義や必要性から、具体的な方法、導入のメリット・デメリット、そして成功の鍵となる教育の重要性までを紹介していきます。
目次
物流業界における省人化とは?
物流業界における「省人化」とは、単に人員を削減することではありません。ロボットやシステムなどを活用して、従来は人が行っていた作業を機械やシステムに置き換え、業務プロセス全体を効率化することを指します。
これにより、少ない人数でも物流業務を円滑に遂行できる体制を構築し、生産性向上やコスト削減を目指します。省人化は、人手不足が深刻化する物流業界において、持続可能な事業運営を実現するための重要な取り組みです。
物流業界で省人化が求められている理由
現在、物流業界で省人化が強く求められている背景には、複数の要因が絡み合っています。まず、オンラインでの購買活動が活発化していることによって、小口配送の数は年々増加傾向にあり、物流現場の負担が増大しています。加えて、Eコマースの普及は多品種少量・短納期といったニーズの多様化も招き、オペレーションの複雑性を増しています。
一方で、物流業界は他産業と比較して賃金面での待遇などに課題があり、慢性的な人手不足に悩まされています。特にトラックドライバー不足は深刻で、「物流の2024年問題」として、時間外労働の上限規制が適用されることで、輸送能力の低下が懸念されています。
こうした状況下で、限られた人員で増大・複雑化する業務に対応し、安定した物流サービスを提供し続けるために、省人化による効率化が不可欠となっているのです。
省人化と省力化の違い
「省人化」とよく似た言葉に「省力化」があります。この二つは目的やアプローチが異なります。「省力化」は、人の作業負担を軽減することが主な目的です。
例えば、重い荷物を運ぶ際に台車やカゴ車を導入するのが省力化の一例です。これにより作業者の負担は減りますが、作業者の人数自体はあまり変わりません。
一方、「省人化」は、機械やシステムが人に代わって作業を行って、業務の人員数を減らすことを目指します。マテハンシステムや搬送ロボットの導入などがこれにあたります。
省力化は、より少ない労力で作業できるようにする改善であり、省人化は人が行う作業そのものを減らす改善といえます。目的や現場の状況に応じて、どちらのアプローチを取るか、あるいは段階的に進めるかを検討することが重要です。
なお、省力化・省人化・小人化の進め方やコツを通し、多能工化を推進するための仕組みやポイントを具体的に学びたい方は、専門家によるセミナー動画が役立つと思います。ただいま無料公開中なので、お時間がある際に視聴してみてください。
>>【専門家が解説】省力化・省人化・小人化への具体的な対応策を視聴する(無料)
物流現場で省人化を進めるメリット
物流現場で省人化を進めることで、単に人員を減らすだけでなく、事業運営の様々な側面で良い効果をもたらします。ここでは主なメリットを4つご紹介します。
人的なコストの削減が見込める
省人化の直接的なメリットとして、人件費の抑制が挙げられます。これまで複数の人員で行っていた作業をロボットやシステムが代替することで、必要な人員数を最適化できます。これにより、長期的に見て人件費を削減することが可能です。
また、人員削減だけでなく、採用活動にかかるコストや、新人教育に費やす時間と労力といった教育コストも削減できます。浮いたコストやリソースを、他の戦略的な分野へ投資することも可能になります。
生産性・作業効率の向上につながる
ロボットや自動化システムは、人間のように休憩を取る必要がなく、24時間365日の稼働も可能です。また、一定のスピードと精度で作業を継続できるため、生産性の大幅な向上が期待できます。
リードタイムの短縮や、より多くの物量を処理できる体制の構築、誤出荷の防止が可能になります。結果として、長時間労働の是正や、単純作業から解放された従業員がより付加価値の高い業務に取り組む機会が生まれ、労働環境の改善にも繋がります。従業員のモチベーション向上も期待できるでしょう。
人手不足の解消が見込める
深刻化する物流業界の人手不足に対して、省人化は直接的な解決策となり得ます。募集をかけてもなかなか人が集まらない、採用してもすぐに辞めてしまうといった課題を抱える現場にとって、少ない人数でも業務を円滑に遂行できる体制を構築することは喫緊の課題です。
自動搬送ロボットやピッキングロボットなどを導入し、人の手で行っていた作業を自動化することで、限られた人員をより重要な業務に集中させることが可能です。これにより、現場の負担軽減と同時に人手不足の中でも安定した事業運営を継続するための基盤を築くことができます。
技術伝承を効率的に行える
物流現場では、特定の熟練作業者の経験や勘に頼っている業務も少なくありません。こうした属人化した技能は、その担当者が退職してしまうと失われてしまうリスクがあります。
一方、省人化の過程で標準化やロボットの活用が推進されることによって、技術伝承やノウハウの継承が効率的に進みます。例えば、複雑なピッキングルートや効率的な積み付け方法などをシステム化したり、ロボットに作業を覚えさせたりすることで、暗黙知であったノウハウを形式知として残すことができます。
これにより、担当者の異動や退職に左右されずに業務品質を維持でき、効率的な技術伝承が可能となります。
しかし、「伝承する人材を確保できない」「教育に時間を割けない」などの様々な理由から、思うように技術伝承が進まない企業がほとんどです。以下の資料「技術伝承を成功させるポイント(pdf)」では、技術伝承を阻む課題に対する対策を述べたうえで、実際にその課題に対してどう対策すべきか具体例を交えて解説しています。一部製造業向けの話題もありますが、全体を通して物流業界にも取り入れられる内容となっておりますので、下のリンクをクリックしてご覧ください。
物流現場における省人化のデメリット
多くのメリットがある一方で、物流現場の省人化にはデメリットもあります。導入を検討する際には、これらの点を十分に理解し、対策を講じることが重要です。
システムの導入や維持にコストが発生する
省人化を実現するためのロボットや自動倉庫、ソフトウェアといったシステムの導入には、多額の初期投資が必要となるケースが多くあります。
また、導入後もシステムの維持管理にはコストがかかります。定期的なメンテナンス費用や、ソフトウェアのアップデート費用、故障時の修理費用など、ランニングコストも考慮に入れなければなりません。補助金の活用なども視野に入れつつ、長期的な視点での投資計画を立てることが求められます。
全ての作業を代替できるわけではない
現在の技術では、物流現場の全ての作業を完全に自動化・省人化することは困難です。特に、イレギュラーな事態への対応、複雑な状況判断が求められる作業、破損しやすい商品や不定形な荷物の取り扱いなどは、依然として人の手が必要となる場面が多くあります。
また、導入したシステムやロボットの操作、メンテナンス、トラブル対応なども、人が行う必要があります。「省人化=完全無人化」ではないことを理解し、どの作業を自動化し、どの作業を人が担うのか、人と機械・システムがどのように連携するのが最も効率的か、最適な役割分担を検討することが重要です。
従来の作業手順から変更があるため、従業員の理解を得る必要がある
省人化のために新しいシステムや機器を導入すると、従来の作業手順や業務フローが大きく変更されます。従業員にとっては、慣れ親しんだやり方を変えることへの抵抗感や、新しいことを覚えることへの不安が生じる可能性があります。
導入をスムーズに進めるためには、なぜ省人化が必要なのか、導入によってどのようなメリットが期待できるのか、そして具体的な変更内容や従業員への影響(配置転換や必要なスキルなど)について、事前に丁寧な説明を行い、従業員の理解と協力を得ることが不可欠です。一方的な導入は現場の混乱を招き、かえって生産性を低下させるリスクがあります。
システムトラブルへの対応が必要
機械やシステムは、どれだけ高性能であっても故障や不具合のリスクをゼロにすることはできません。省人化を進め、システムへの依存度が高まると、システムトラブルが発生した場合の業務への影響は甚大になります。物流業務が完全にストップしてしまう可能性も考慮しなければなりません。
そのため、システムダウンや機器の故障が発生した場合に備えて、対応を事前に策定するのが重要です。具体的には、トラブル発生時の連絡体制、復旧までの手順、代替手段による業務継続方法などを明確にし、関係者間で共有しておく必要があります。
物流業界の省人化を実現する具体的な方法
物流現場の省人化を実現するためには、様々なアプローチがあります。ここでは、その具体的な方法をいくつかご紹介します。
多能工化の促進
省人化を目指すうえでは、従事する従業員が複数の業務に対応できる「多能工化の促進」が重要なポイントです。一連の物流業務に対して幅広く対応できる多能工な人材を育成することによって、属人化の解消が進み、人材を適切に配置できます。1人の従業員が複数の業務や工程を担当できるようになるため、人員配置の柔軟性が高まり、少人数でも効率的な業務をこなせる=省人化にも寄与します。
なお、多能工化を進めるうえでの人材教育に、業務の標準化は欠かせない要素であり、標準化に向けて参考になるのが、「ASKUL LOGIST株式会社」の事例です。同社では、OJT・紙で行っていた従業員教育に動画を活用することで、従来の教育手法で課題であった教育のばらつきを解消し、標準化を進めることができています。
標準化に取り組むうえでは、「業務標準化がなかなか進まない理由」をベースに最適な取り組み方をわかりやすく解説した「企業が業務標準化に着手するべき理由(pdf)」が参考になります。下の画像をクリックして、ダウンロードしてみてください。
マテハン(マテリアルハンドリング)機器の活用
マテハン(マテリアルハンドリング)とは、生産拠点や物流拠点内で、原材料や仕掛品、完成品などを効率的に移動・保管・管理するための技術や機器の総称です。マテハン機器の活用は、物流現場の省人化・省力化に大きく貢献します。
代表的なマテハン機器としては、荷物を載せて自動で目的地まで搬送するAGV(無人搬送車)やAMR(自律走行搬送ロボット)、棚の出し入れを自動で行う自動倉庫システム、コンベヤ上を流れる商品を自動で行き先別に仕分けるソーター(自動仕分け機)、工程間を自動で繋ぐコンベヤシステムなどがあります。これらの機器を導入することで、搬送、保管、仕分けといった作業の自動化・効率化が図れます。
ロボット技術の導入
近年、ロボット技術の進化は目覚ましく、物流現場でも様々な種類のロボットが活躍しています。特に、これまで人手に頼ることが多かった複雑な作業の自動化に貢献しています。
代表的な例としては、棚から商品を取り出すピッキング作業を自動化するピッキングロボットや、パレットへの荷物の積み付けや荷降ろを行うロボットが挙げられます。これらのロボットは、作業の高速化・高精度化だけでなく、重量物作業からの解放による労働環境改善にも繋がります。
物流システムの導入・活用
省人化を効率的に進め、その効果を最大化するためには、物流システムの導入・活用が不可欠です。これらのシステムは、倉庫内や輸送におけるモノと情報の流れを一元管理し、最適化する役割を担います。
代表的なシステムとしては、倉庫内の在庫や入出荷、作業進捗などを管理するWMS(倉庫管理システム)、ロボットやマテハン機器の動きを最適に制御するWES(倉庫実行システム)、トラックの配車計画や運行状況を管理するTMS(輸配送管理システム)などがあります。これらのシステムを連携させて活用することで、業務全体の可視化と効率化、そして省人化が促進されます。
AI・IoT技術の活用
AIやIoTといった先端技術も、物流現場の省人化・効率化するうえで重要な手段です。これまで人の経験や勘に頼っていた部分をデータに基づいて最適化したり、新たな価値を創出したりする可能性を秘めています。
AIを活用した例としては、過去のデータから物量を高精度に予測する需要予測システム、最適な在庫配置や輸送ルートを算出するシステムなどがあります。IoTの活用例としては、倉庫内に設置したセンサーで温湿度などの環境データを収集・管理したり、マテハン機器に取り付けたセンサーで稼働状況を監視し故障を予知したりする予兆保全などが挙げられます。また、カメラと画像認識技術を用いた自動検品なども実用化が進んでいます。
省人化を実現している物流企業の好事例
実際に省人化に取り組み、成果を上げている企業は数多くあります。ここでは、特に省人化と合わせて、それを支える教育体制の整備にも注力した企業の事例を2つご紹介します。
ASKUL LOGIST株式会社
EC専門の総合物流企業として、事業所向け通販サイト「ASKUL」、及び個人向け通販サイト「LOHACO」の物流・配送機能を担っているASKUL LOGIST株式会社。同社の現場では短時間勤務者や外国籍スタッフなどの様々な形が作業に従事していることもあり、何度も繰り返し教育が発生したり、教育担当者の負担が増加したりするなどの課題を抱えていました。
また、従来の紙マニュアルやOJT中心の教育では、指導者の負担が大きい上に教育品質にバラつきが生じ、新人が即戦力になるまでに時間がかかるという課題を抱えていたそうです。
そこで同社は、省人化に向けて動画での教育を実施。従来の教育で発生していた理解度のばらつきを軽減でき、作業の標準化が実現しています。教育負担の削減につながった結果、現場作業の効率化につながっています。
従来の教育と比べて4分の1まで工数削減を実現している同社の事例は以下のインタビュー記事をご覧ください。
インタビュー記事:従業員数3,500名超・全国14拠点で動画マニュアルtebikiを活用!
株式会社ロジパルエクスプレス
物流改革の企画・提案や国際一貫物流とアミューズメント関連事業を担当している株式会社ロジパルエクスプレス。同社では、同一の業務を行っていても業務品質や作業手順にバラツキが発生していたり、業務の属人化が発生したりなどの課題を抱えていました。
作業手順のばらつきや属人化の解消に向けて、”動画”での業務標準化を実施。現場教育の平準化が図れ、省人化にもつながっています。従来のOJTを動画におきかえることで、教育担当者の実業務を圧迫せずに現場教育に取り組めていると語ります。同社の事例を詳しく読んでみたい方は、以下のインタビュー記事をご覧ください。
インタビュー記事:動画で全拠点の安全品質意識の向上と業務ノウハウの可視化を達成
物流業界の省人化に「教育」が不可欠な理由・推奨される教育方法
省人化に向けて、従業員ごとの生産性向上・稼働率の底上げは欠かせない重要な要素であり、これらの要素を向上させるためには、従業員の教育が不可欠です。
教育に取り組むことによって、ベテラン社員に業務が属人化してしまうリスクの軽減、特定の業務だけではなく一人の従業員が幅広い業務をこなせる多能工化などを実現できます。しかし、このように教育の重要性は理解できているものの、通常業務に追われて教育のリソースを確保できない・教育の体制が整っていないなど、実際に動けていない場合も多いでしょう。
これら物流現場の教育課題を解消する手段として注目されているのが、動画マニュアルの活用です。物流企業のソニテック株式会社のように、物流業や倉庫現場で、動画マニュアルの導入・活用が進んでいます。
同社では、新人教育に動画マニュアルを取り入れた結果、3ヶ月かかっていた新人のマンツーマン教育の工数を実質ゼロにしています。
なお、『省人化を実現している物流企業の好事例』でも紹介した物流企業で紹介した企業でも動画マニュアルが活用されていることからも、物流企業の省人化を実現するための教育方法として有効な手段と言えるでしょう。動画マニュアルの有効性や事例などをより詳しく知りたい方は、以下の資料をご覧ください。
>>「物流業界の生産性向上を助ける動画マニュアルのチカラ(pdf)」を見てみる
まとめ:物流業界の省人化は計画的な推進と「人」への投資が鍵
人手不足や物流の2024年問題といった厳しい環境下で、省人化は避けて通れない重要な経営課題です。ロボットや自動化技術の導入は、生産性向上やコスト削減に大きく貢献する可能性を秘めていますが、その効果を最大限に引き出すためには、技術導入と並行して、それを使いこなす「人」への投資、すなわち教育体制の整備が不可欠です。
特に、変化に対応し、新しい技術やプロセスを現場に浸透させるためには、従来のOJTや紙マニュアルの限界を克服する、分かりやすく効率的な教育手段が求められます。動画マニュアルは、その有力な解決策の一つとなり得ます。
自社の現場教育の課題解決や、動画マニュアル導入による効果について、より具体的に知りたい方は、「はじめての動画マニュアル作成ガイド(pdf)」をご覧ください。下の画像をクリックすると、資料をダウンロードできます。