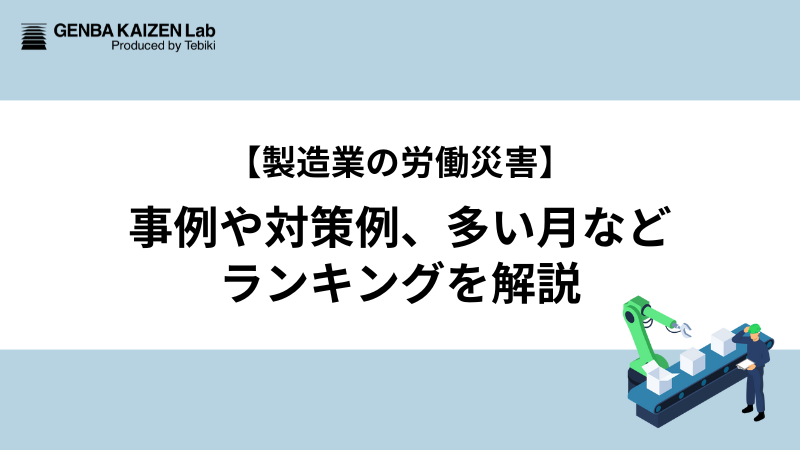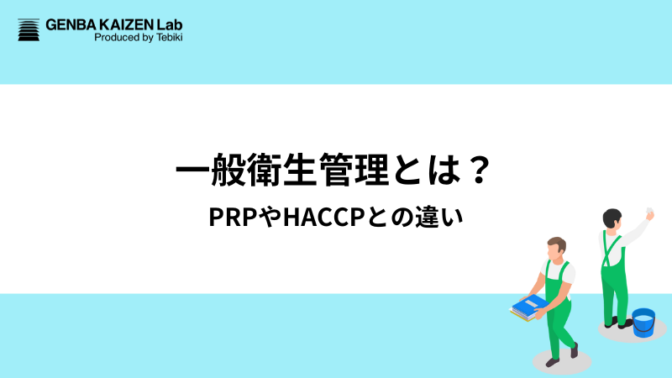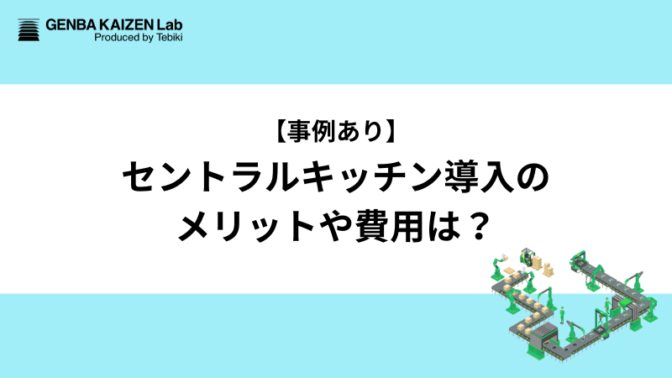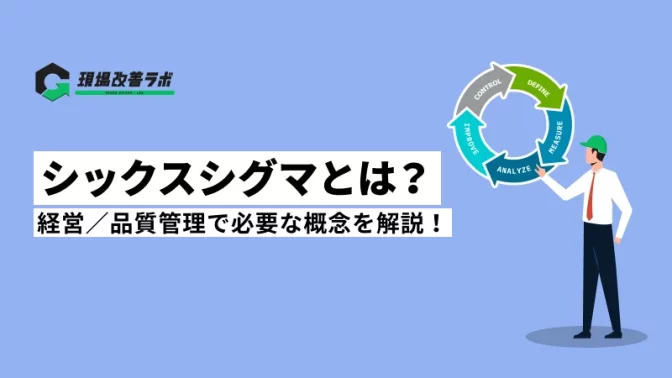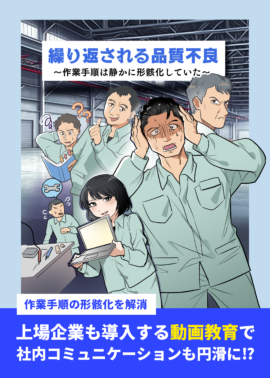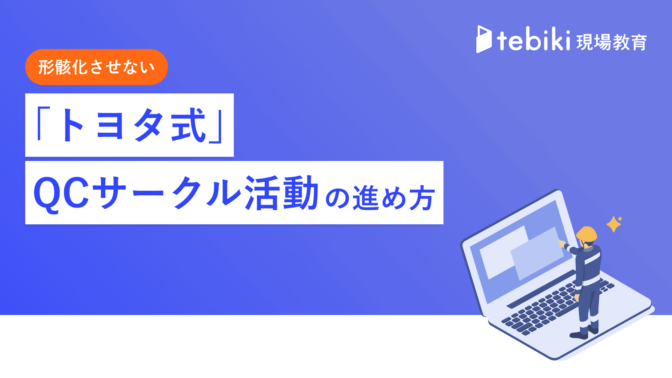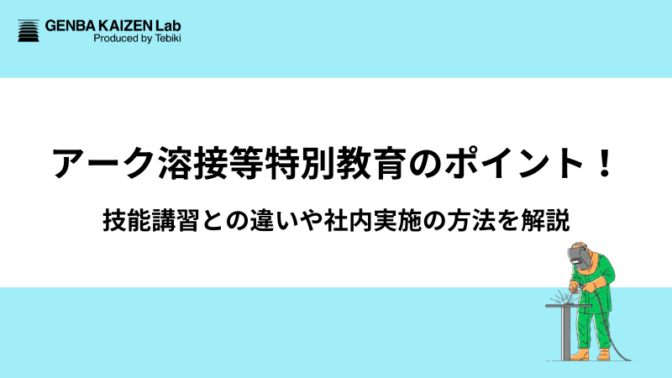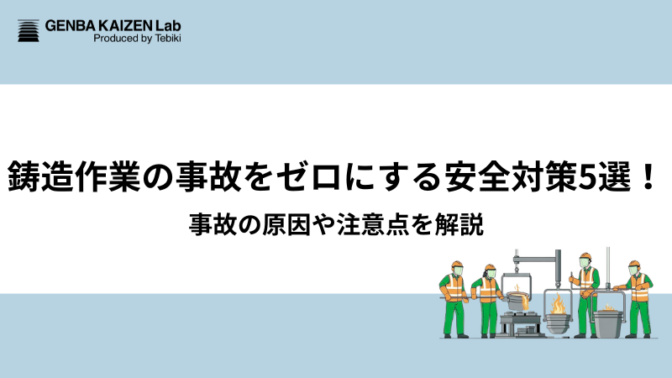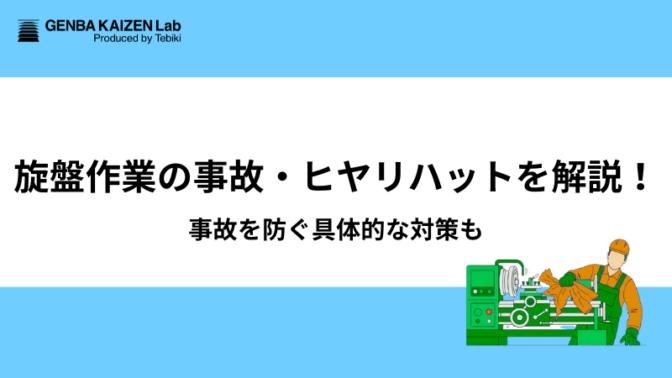かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
厚生労働省によると、令和4年から令和5年にかけて労働災害による死傷者数は+3,016人(2.3%増)。製造業に絞ってみても+500人(1.9%増)と、労働災害の発生件数は増加傾向にあります。では、具体的にどのような労働災害が発生しているのでしょうか?
この記事では、製造業における労働災害の発生件数をランキング形式でご紹介します。実際の事故事例やそれらを踏まえた対策方法も解説しますので、安全な現場づくりにお役立てください。
▼製造業の労災対策を網羅的に知りたい方▼
製造業での労災ゼロを達成する従業員の安全意識を向上させる安全教育
▼ヒューマンエラーや作業ミスの対策を重点的に知りたい方▼
・繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網
・ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育
目次
製造業で多い労働災害ランキングと原因
厚生労働省が発表する令和5年の労働災害発生状況による死傷者数を確認すると、製造業で多い労働災害ランキングは以下の通りになりました。
- 1位:はさまれ・巻き込まれ(6,377件)
- 2位:転倒(5,823件)
- 3位:動作の反動・無理な動作(3,191件)
- 4位:墜落・転落(2,870件)
- 5位:切れ・こすれ(2,327件)
この5件の労働災害が起こる原因として、主な原因としては以下のようなものが考えられます。
| 労働災害種別 | 考えられる主な原因 |
|---|---|
| はさまれ・巻き込まれ | 機械の操作ミス / 作業手順の不遵守 / 安全装置の誤作動 |
| 転倒 | 床面の滑り・凹凸 / 足元の障害物 / 作業場所の照明不足 |
| 動作の反動・無理な動作 | 不適切な作業姿勢 / 作業台・工具の不適合 |
| 墜落・転落 | 高所作業の教育不足 / 足場の不備 / 不注意 |
| 切れ・こすれ | 刃物・工具の不適切な使用 / 保護具の不使用 |
これらの労働災害は、死亡災害になるほど重大な事故に発展する可能性があります。このような不安全行動を撲滅するためにも、製造現場で適切な安全教育や安全対策が大切です。
その手段の1つとして、製造現場で活用されるケースが増えているのが「動画マニュアル」です。現場改善ラボでは、製造現場の安全意識向上を目的に動画マニュアルを活用する事例や効果、サンプル動画を解説する資料を無料で公開しています。
以下のリンクをクリックすると、資料をご覧いただけますので、参考資料としてご覧ください。
>>「安全意識が高い製造現場はやっている! 動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例」を見てみ
製造業で労働災害が多い月
厚生労働省が発表している令和5年の「製造業における月別の死亡災害件数」のデータによると、令和5年では9月の死亡災害が17件と最も多くなっています。
| 1月 | 14 |
| 2月 | 12 |
| 3月 | 12 |
| 4月 | 14 |
| 5月 | 9 |
| 6月 | 12 |
| 7月 | 10 |
| 8月 | 11 |
| 9月 | 17 |
| 10月 | 4 |
| 11月 | 9 |
| 12月 | 14 |
| 合計 | 138 |
夏季休暇明けである場合が多い9月は、休暇明けによって体のリズムが整っていないことで安全意識が低下し、労働災害を起こしてしまっていることが考えられます。
また、夏の暑さから少しずつ涼しくなる9月ですが、近年はまだまだ暑さが残っており、体調を崩しやすい時期です。集中力の低下 / 体力の消耗などが起きて、労働災害が多発してしまっているのでしょう。
このように、季節柄から労災が起こりやすいタイミングがあるため、安全衛生委員会で事前に話し合い、未然防止策を講じることが取り組みとして大切です。
▼製造業の労災対策を網羅的に知りたい方▼
製造業での労災ゼロを達成する従業員の安全意識を向上させる安全教育
▼ヒューマンエラーや作業ミスの対策を重点的に知りたい方▼
・繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網
・ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育
製造業における労働災害対策
労働災害を減らすことは、従業員の安全を守るだけでなく、企業の生産性や企業イメージの向上にもつながります。本章では、労働災害の発生件数が多い製造業の労働災害対策として以下をご紹介します。
- リスクアセスメントで危険を可視化
- KY活動で危険感受性を向上
- 5Sで作業環境の整備・危険要因の排除を行う
- フェイルセーフ/フールプルーフでヒューマンエラーによる危険を防止
- 安全教育で従業員の安全意識を向上させる
▼製造業の労災対策を網羅的に知りたい方▼
製造業での労災ゼロを達成する従業員の安全意識を向上させる安全教育
▼ヒューマンエラーや作業ミスの対策を重点的に知りたい方▼
・繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網
・ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育
リスクアセスメントで危険を可視化
リスクアセスメントとは、事前に潜在的な危険やリスクを特定し対策を講じることで、事故の発生確率を大幅に低減できる手法です。リスクアセスメントで労働災害の要因を特定することで、危険源に対して適切な対策を講じることができるため、労働災害の未然防止につながります。
リスクアセスメントの具体的な方法については、元労基署長による解説動画を公開していますので、以下の画像をクリックしてご覧ください。
KY活動で危険感受性を向上
KY活動とは、「危険(Kiken)予知(Yochi)活動」の略称で、従業員自身が日常の業務中に潜在的な危険を予知 / 共有することで、チーム全体の安全意識が高まる活動です。
例えば、製造ラインで作業中に発見された小さな異常や不具合をKY活動を通じて共有することで、大きな事故に発展する前に対処することが可能になります。従業員の危険源に対する察知能力を高めるためには、KYT(危険予知訓練)を事前に行うことも効果的です。
KY活動やKYTの実践的な方法を知りたい方は、専門家による無料の解説動画をご覧いただくことがオススメです。危険要因の回避行動を習慣化する方法などを解説していますので、以下のリンクよりご活用ください。
▼専門家による無料の解説動画(クリックしてご覧ください)
・元労基署長が解説!事故を未然防止するKY活動と4ラウンド法の在り方とは?
・効果のあるKYTとは?KYTの実情、3つの課題とその解決策
5Sで作業環境の整備・危険要因の排除を行う
5Sとは、「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「躾」の5つの頭文字をとった言葉で、職場環境を良くするための活動のことです。5Sをしっかり行うことで、安全でスムーズに作業できる環境が作られ、労働災害を未然に防げるでしょう。
5Sは安全と効率の要ですが、その重要性は理解していても「現場に定着しない」「形骸化してしまう」という悩みは尽きません。
精神論ではなく、5Sを組織の「仕組み」として定着させるための具体的なポイントを、以下の資料で解説します。
>>【事例つき】5S3定が浸透しない現場の共通点3つと仕組み化の「核」を見てみる
フェイルセーフ/フールプルーフでヒューマンエラーによる危険を防止
フェイルセーフとは、システムに異常が生じても、安全に停止できるように設計する機能や仕組みのことを指します。たとえば、フェイルセーフとして緊急停止ボタンを設置すれば、異常時に即座に運転を停止でき、作業者を危険から守れます。
フールプルーフとは、作業者の誤った使用方法を防止するための設計思想を指します。これにより、ヒューマンエラーによる労働災害を防ぐことが可能です。たとえば、刃がついている機械を操作する際、保護カバーが閉じられていないと作動しないように設計することで、切れ・こすれといった怪我を防げます。
▼フェイルセーフ/フールプルーフの例▼
| フェイルセーフ | ・なんらかの異常が生じた際に緊急停止する ・異常により停止した機械を、急に再起動させないようにする ・重量オーバーの際にブザーが鳴る |
| フールプルーフ | ・開口部から、加工物や工具等は入るが、手は危険領域に届かない ・機械のスイッチを切った後の惰性運動を検知して、危険がある間はガードが開かない ・鍵の利用により一方を施錠しないと、他方が解放されない |
安全教育で従業員の安全意識を向上させる
安全教育は、労働者の安全と健康を確保し、災害を防ぐとともに生産性の向上や業績の安定を図ることを目的としています。
特に製造現場では、機械や設備の取り扱いや作業手順など、安全性が担保された作業ルールを守る安全教育が重要です。安全な手順である標準作業を遵守することが、結果的に事故のリスクを低減につながります。
このように、定められた標準作業を全従業員が遵守することが、労働災害を防ぐ上での基本です。
しかし、ルールを教えるだけの一方的な教育では、「なぜその作業が必要なのか」という本質が伝わらず、形骸化してしまう恐れがあります。従業員一人ひとりが自律的に安全な行動をとるためには、ルールの遵守から一歩進んで、個々の「安全意識」そのものを高めるアプローチが不可欠です。
労災ゼロを達成するために、従業員の安全意識を効果的に向上させる教育の進め方について、以下の資料で詳しく解説しています。
>>製造業での労災ゼロを達成する従業員の安全意識を向上させる安全教育を見てみる
【安全意識を形骸化させない】製造業の労災対策事例と手段
ここまで製造現場の労働災害を防ぐ対策などをご紹介しました。フェイルセーフなどハード面で実行できる対策もありますが、即効果が出るような特効薬的な労災対策はありません。
従業員の安全意識を高めつつ、形骸化しないように取り組むことが将来的な労災発生リスクの未然防止につながります。
本章からは、従業員の安全意識向上や形骸化を防ぐために取り組んでいる、製造業の好事例2社と手段をご紹介しましょう。
▼製造業の労災対策を網羅的に知りたい方▼
製造業での労災ゼロを達成する従業員の安全意識を向上させる安全教育
▼ヒューマンエラーや作業ミスの対策を重点的に知りたい方▼
・繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網
・ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育
製造業における労災対策の好事例
株式会社メトロール
株式会社メトロールは、マザーマシンの高精度タッチセンサの製造で、世界トップシェアを誇るメーカーです。
製造現場において、業務理解がまだ浅く労災リスクが高い新人スタッフ向けに、安全衛生教育に関するカリキュラムを動画マニュアル化し、安全意識の定着と新人教育の効率化に取り組んでいます。
たとえば、製造現場で使用するアルコールによる労働災害を防ぐため、薬品の扱い方が未経験のスタッフでも理解できるように、動画マニュアルを整備しています。このような取り組みを通じ、トレーナーが繰り返し指導する時間を半分以下まで短縮しつつ、新人スタッフへの安全意識定着を実現しています。
同社の具体的な取り組み内容を詳しく知りたい方は、以下のインタビュー記事をクリックしてご覧ください。
インタビュー記事:世界で200社以上の装置メーカーに採用されているセンサの製造工程でtebikiを活用し、新人教育と多能工化を推進
トーヨーケム株式会社
樹脂製品の製造を行い、「生ジョッキ缶(アサヒビール)」の開発を手がけたトーヨーケム株式会社では、新人教育で生じる業務習熟度のバラツキが不安全行動につながると考えていました。
そこで、質の高い教育の提供や教育内容の標準化を目的に、動画マニュアルの活用に取り組むことに。結果的に、マニュアル作成工数が紙の1/2、OJT工数が2/3に削減といった効果につながりました。
新人からは「自立的な学習ができ、動画を見返すだけで業務の振り返りができる」という声が挙がり、不安全行動につながる業務習熟度の改善につながりました。同社の具体的な取り組み内容は、こちらのインタビュー記事をクリックしてご覧ください。
今回ご紹介した取り組み事例のように、何が危険か?不安全行動を動画で視覚的に伝え、正しい業務手順を遵守するように効率的に取り組んでいる製造現場が増えています。
「動画マニュアルを活用した製造現場の安全教育・安全対策事例集」では、動画マニュアルを利用し労災対策を行っているケース、サンプル動画をご覧いただけます。以下の画像をクリックすると資料をご覧いただけますので、ぜひご活用ください。次章では、多くの製造現場で活用されている動画マニュアルツールをご紹介します。
多くの製造現場で活用される労災対策の手段
製造現場の労働災害を防止する安全教育・安全対策の手段として、動画マニュアルを活用する現場が増えています。
従来の紙のマニュアルやOJTと比較し、以下のようなメリットがあります。
- 危険を視覚的に捉えられるため、安全意識が向上する
- リアルな状況を把握できるため、危険予知能力が向上する
- 教育効率の大幅な向上とコスト削減が可能になる
- 言語の壁を越えた情報伝達が可能なため、外国人労働者教育にも使える
動画であれば、「正しい手順」を「正しい内容」で、繰り返し何度でも伝えることが可能です。そのため、教育の効率化と同時に、安全教育の質の向上も実現でき、効果的な安全対策として活用できます。
動画作成と聞くと『編集が難しそう…』と感じるかもしれませんが、編集未経験者でも簡単に動画マニュアルを作成できるツールとして、多くの現場で活用されているのが「かんたん動画マニュアル:tebiki現場教育」です。
実際に活用している製造現場の中には、半年間で400動画近く作成を行っている事例があることからも、その簡単さがイメージいただけると思います。とくに、安全教育・安全対策で活用する上で効果的な「tebiki現場教育」の機能は以下の通りです。
- 閲覧状況が分かるレポート機能や、テスト機能で習熟度の可視化ができる
⇒ 安全教育の進捗状況を把握・理解度を定量的に計測可能 - 100カ国語以上の字幕翻訳に対応し、一部言語は自動読み上げも可能
⇒ 従業員の母国語で安全作業について学べる - 教育記録機能によって、安全教育の履歴を従業員ごとに残せる
⇒ 万が一の事故発生時に備え、安全教育の履歴を追える状態に
一部のプランでは、スキルマップ作成機能や教育計画機能といった、人材スキル管理の機能も搭載されています。この機能により、安全に関するトピックにおいて、自社の現場で必要な項目の理解度がどれほど進んでいるか、業務に必要な危険業務の資格保有状況などを従業員ごとに把握できます。
今回は、製造業の安全対策で有効な機能をメインにご紹介しました。「他の機能やプランの詳細を知りたい」という方は、以下の画像をクリックしてサービス紹介資料をご覧ください。
【補足】死亡事故を含む労働災害の有名な事例
「製造業で多い労働災害ランキングと原因」でご紹介した通り、製造業では、挟まれ・巻き込まれや転落などの労働災害が多発しています。
最後に補足情報として、死亡事故を含む、転落や安全装置の未設置による挟まれ・巻き込まれの有名な事故事例をご紹介します。
転落による死亡事故
埼玉県の飲食チェーン店の工場で発生したこの事故では、清掃作業中の従業員が貯水槽に転落し死亡しました。
労働基準監督署によれば、同工場では転落を防止するための措置が取られていなかったそうです。そのため、会社と現場責任者が、労働安全衛生法違反の疑いで書類送検されました。
本事例から、製造業における転落防止対策の重要性が浮き彫りになります。特に高所作業や開放されたエリアで作業を行う際は、柵の設置や安全ハーネスを使用するなどの安全対策を講じる必要があります。転落事故を未然に防ぐためには、従業員に対する適切な安全教育の実施と、作業環境の安全確保が不可欠です。
参考元:男性死亡…松屋フーズ工場で窒息、廃油入れた槽に落ちて 責任者を書類送検 男性はふた開けて清掃中だった
機械挟まれによる重傷事故
平成30年11月に静岡県の紙加工品製造業者で発生したこの事故では、労働者が型打ち機でプラスチックシートを打ち抜いている際に、右腕を機械に挟まれてしまい、肘から下を切断する重傷を負いました。
機械には、物の検出機能を持つ光電センサーが装備されていました。しかし、作業効率を重視して安全機能を意図的に無効にしていたため、労働災害発生時には安全機能が無効化されていたそうです。
安全装置の設置は、労働者の身体的安全を確保するための必須措置です。特に、機械操作に伴う危険性が高い作業では、適切な安全装置の設置と正常な作動が必須になります。事例のような事故を防ぐためには、安全装置の設置だけでなく、常に機能を確認して必要に応じてメンテナンスを行うことが必要です。
参考元:労働者が右肘から下を切断 安全装置無効にした製造業者を送検 島田労基署
まとめ
製造業で多い労災ランキングや、死亡事故を含む工場での有名な事故事例などをご紹介しました。労働災害の発生は、経済的損失 / 企業イメージの悪化などのデメリットが発生します。何より従業員の大切な命を守るために、徹底した安全教育を行いましょう。
安全教育の効果を高めるための手段として、tebiki現場教育の活用がおすすめです。tebikiでは、動画マニュアルの作成による業務標準化が行えるだけではなく、自動翻訳による外国人教育 / 習熟度把握ができるテストの作成など幅広いシーンで活用できます。
tebikiについて「もっと知りたい!」と思っていただけたら、以下のサービス説明資料をご覧ください。tebikiの便利な機能やずっと無料で続くサポート体制をご紹介しています。