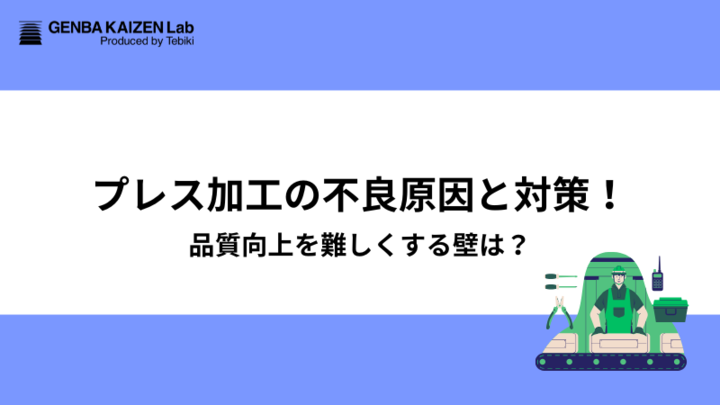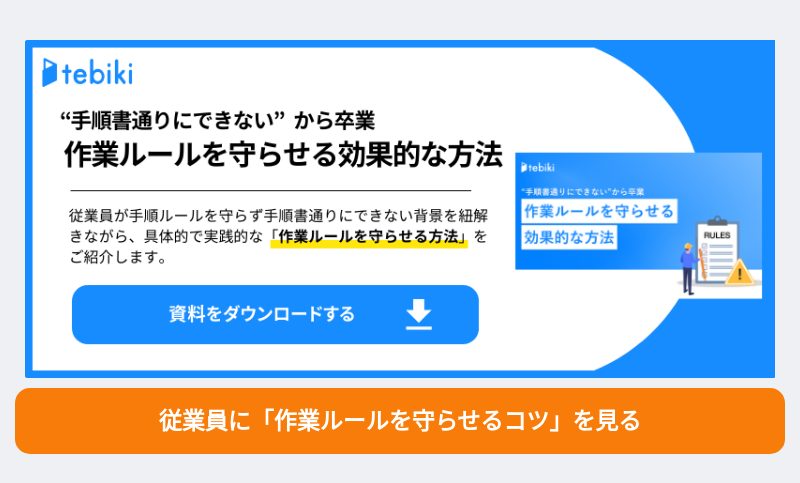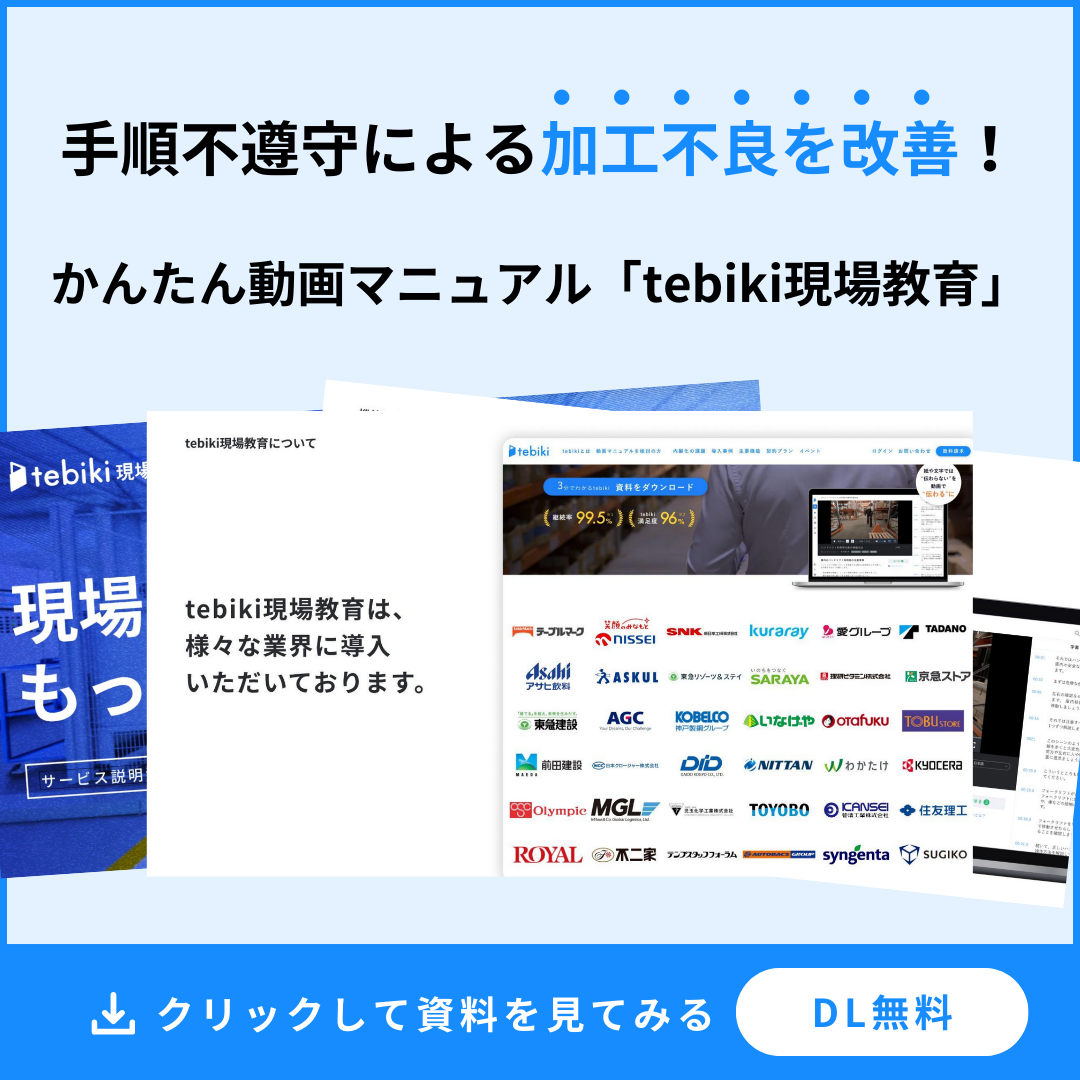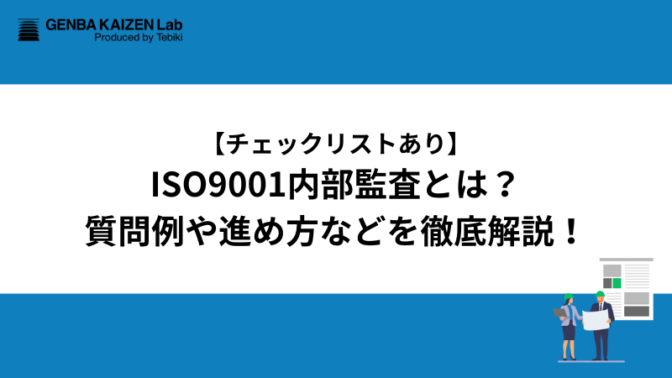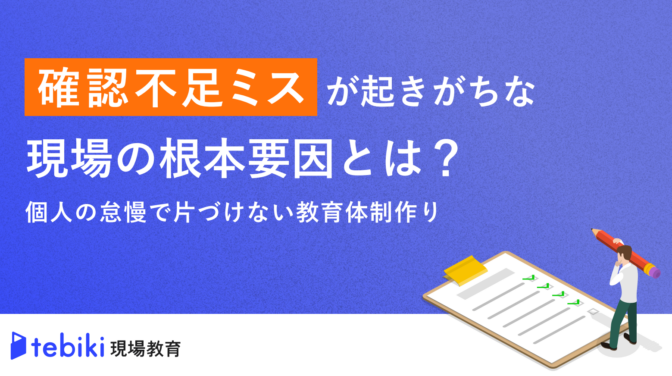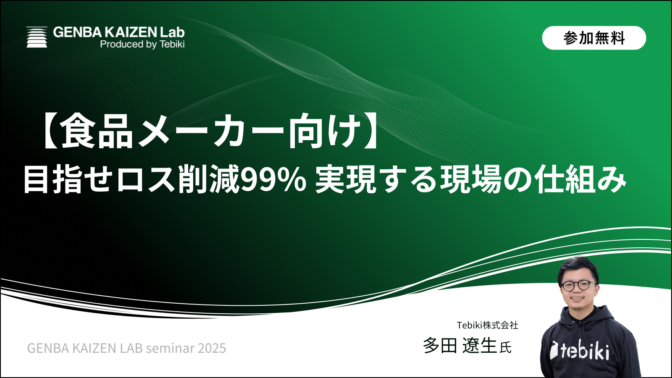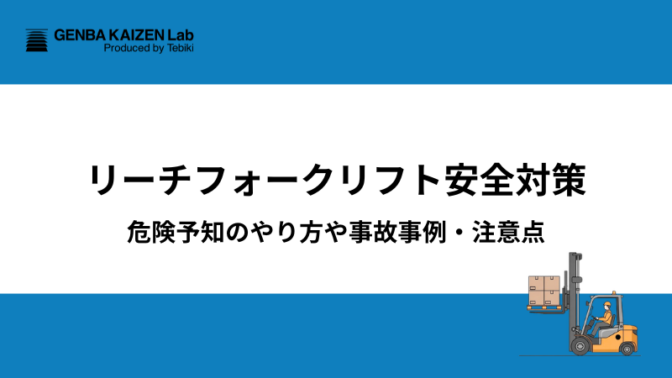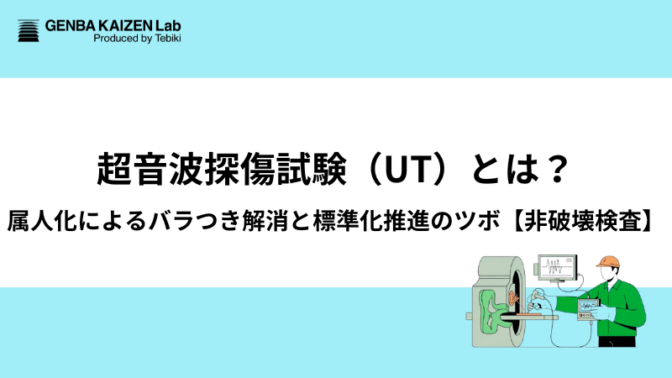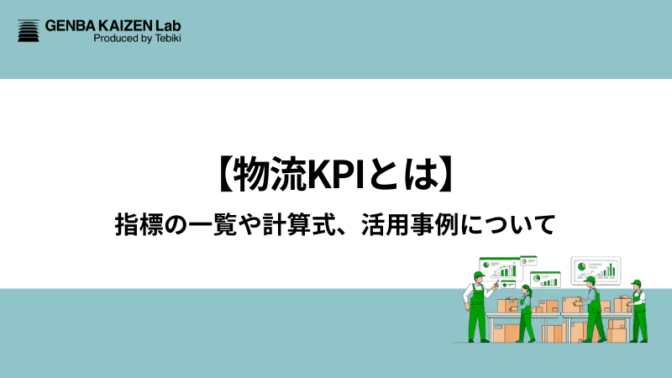かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
プレス加工とは、金属などの材料に圧力を加えて目的の形状に成形する加工方法であり、自動車や家電、電子機器部品など、日々の生活に欠かせない製品の生産に広く用いられています。
この記事では、プレス加工の基礎から、現場で実際に発生する不良の種類と原因や具体的な対策方法に加え、教育改善による品質向上の取り組み事例まで解説します。
目次
プレス加工の主な種類
プレス加工とは、金属の塑性変形を利用し、金型を用いて圧力を加えることで目的の形状を得る加工方法のことです。ここでは、生産現場で特に多用される代表的な以下の4種類の加工法をご紹介します。
せん断(打抜き)加工
せん断加工は、金属をはさみで切るような原理で加工物を分離する方法です。プレス加工のなかで最も広く用いられており、大量生産における効率の良さが特徴です。
具体的には「打ち抜き(ブランキング)」「穴あけ(ピアッシング)」「切断(シャーリング)」「切り欠き(ノッチング)」などの種類があります。適正なクリアランスが確保されていないと、バリやダレの原因となるため、加工精度に直結する重要な工程です。
また、近年はタレットパンチプレスを用いた高精度な打抜きも普及しており、加工力とスピードの両立が可能です。加工時の荷重やパンチ状態をモニタリングすることで、不良の早期検出や金型損傷の防止が実現されるようになっています。
曲げ加工
曲げ加工は、金属に引張力と圧縮力を加えて目的の角度に成形する加工方法です。代表的な方法として、V形やU形に曲げる「ベンディング」があります。
曲げ加工は、せん断加工と異なり材料を分離しないため、材料に残る「スプリングバック(弾性変形)」を考慮する必要があります。「スプリングバック」を無視すると寸法精度の低下や不良品発生の原因となります。
絞り加工(深絞り)
絞り加工は、パンチとダイで金属板を挟み込み、引張応力を利用して立体形状に成形する加工方法です。「深絞り」は、コップ状や筒状の製品を一体成形する際に用いられ、接合の必要がないため強度・美観に優れる反面、加工難易度が高いことが特徴です。
底部には圧縮応力がかかるため「シワ」が、側面には引張応力が集中し「割れ」や「クラック」が生じやすくなります。こうした品質不良を防ぐには、材料の選定や金型のR形状調整、しわ押さえの圧力管理が重要です。
フランジ加工
フランジ加工は、主に円筒形状や孔の周囲を外側または内側に拡げて立ち上げる加工です。絞り加工やせん断加工の後工程として行われることが多く、強度の確保や部品の結合性向上に関係します。
フランジ加工では、材料に局所的な引張や圧縮が加わるため、条件が不適切だと「シワ」や「割れ」が発生しやすくなります。特に均一な材料厚さや金型の摩耗状態が品質につながるため、定期的な金型のメンテナンスが欠かせません。
また、加工条件(圧力・速度)の最適化により、不良率の低下が期待でき、製造現場の生産性向上にもつながります。
プレス加工の主な種類と概要をご紹介しましたが、加工条件によって発生する不良の種類や原因が変わってきます。ここからは、プレス加工で発生する不良の種類や原因など、メカニズムを詳しく解説します。
プレス加工で発生する不良の種類と原因/メカニズム
プレス加工は高効率な大量生産を実現する反面、工程中でさまざまな不良が発生しやすい加工方法です。ここでは、現場で特に頻発する以下の6つの代表的な不良とその原因・発生メカニズムを詳しく解説します。
今回はプレス加工に焦点を当てていますが、製造現場ではさまざまなシーンで品質不良が発生します。以下の記事では、製造現場における品質改善策を事例を交えて網羅的に解説しているので、参考記事としてクリックしてご覧ください。
関連記事:【品質改善】製造業の品質向上策9選!改善事例も解説
割れ(クラック)
割れは、絞り加工や曲げ加工などで被加工材に過剰な引張応力がかかり、材料が破壊限界を超えた際に発生する不良です。
特に深絞りでは、底面に圧縮、側面に引張応力が生じるため、引張に弱い材料や過度な成形条件下ではクラックが発生しやすくなります。また、曲げ加工でも材料の圧延方向や曲げ半径が不適切だと、曲げ部に微細なひび割れや裂け目が発生します。
対策としては、金型のR形状を滑らかにし、成形抵抗を低減することや、材料の方向性に配慮した配置、板厚の8倍以上にする曲げ幅の適正化などが効果的です。
シワ
シワは、主に絞り加工中にフランジ部分に過剰な圧縮力がかかることで、材料が波打って発生する不良です。シワが発生すると、美観を損ねるだけでなく、製品の寸法精度や強度にも悪影響を与えます。特に材料の厚さが薄い場合や、しわ押さえの圧力が不均一な場合に発生しやすくなります。
対策としては、「しわ押さえ装置(ブランクホルダー)」を利用し、材料の流れを均一化することが有効です。固定式だけでなく、スプリングやダイクッションを使った可動式のしわ押さえも、柔軟な圧力制御が可能で効果的です。
バリ
バリは、せん断加工時にパンチとダイの隙間(クリアランス)が適正でないと、材料の一部が切断時に飛び出し、鋭利な突起となって残る不良です。
クリアランスが大きすぎるとバリは大きくなり、はめあい精度の低下や、安全性リスクを引き起こします。一方、過小クリアランスでも「ヒゲ状のバリ」が発生します。バリは製品の品質だけでなく、作業者の安全にも影響を及ぼすため、特に注意が必要です。
対策としては、板厚に対し1/2〜1/3がせん断面になるよう、クリアランスを適正化することが重要です。さらに、4Kマイクロスコープによる観察により、微細なバリの発生状況を詳細に評価し、加工条件を最適化することが可能です。
スプリングバック
スプリングバックは、曲げ加工後に被加工材の内部に残留した応力により、加工部が元の形に戻ろうとする現象です。スプリングバックによって、意図した曲げ角度からズレが生じ、寸法精度が確保できなくなる不良が発生します。特に高強度材料や薄板では顕著に表れるため、精密部品の製造においては深刻な問題です。
対策としては、あらかじめ深めの角度で曲げる「オーバーベント」や、パンチにストライキングを設けて応力を分散させる方法、さらにはノッチを付けて変形しやすくする手法などが有効です。
穴ズレ
穴ズレは、パンチとダイの位置ズレや材料の送りズレなどにより、意図した位置に穴が開かない不良です。特に順送プレスや多工程プレスでは、材料の搬送や金型の精度がズレを生じさせる要因となります。穴ズレが発生すると、組立時の不具合や機能不全を招き、再加工や廃棄のコストが発生します。
対策としては、金型の位置精度を定期的に確認・補正することに加え、材料の送り装置(フィーダー)の精度管理、ピッチずれの検出センサーの導入が効果的です。
表面キズ
表面キズは、材料搬送中の摩擦や、スクラップ・異物の混入、金型のかじりなどにより発生する不良です。特にスクラップがパンチに吸着する「カス上がり」が原因となり、製品に打痕や傷が残るケースが多く、生産性・品質を大きく損ねます。
対策には、「キックピン」を活用しスクラップを物理的に除去するほか、パンチ先端からエアを噴出する、油の粘度を下げるなどの方法が効果的です。また、4Kデジタルマイクロスコープによる高コントラスト観察により、微細な傷や打痕も詳細に可視化でき、原因究明と対策立案のスピードが向上します。
ご紹介したように、プレス加工における不良は作業内容や手順のミス、原材料の特性を起因にしたものなど、さまざまな原因によって生じてしまいます。次章からは、このような不良や不具合に対して、少なくとも製造現場で実施しておきたい対策を詳しく解説していきます。
プレス加工における不良/不具合に対する対策
プレス加工における不良や不具合の発生を防ぐためには、日常の管理・運用において具体的な対策が必要です。ここでは、不良を未然に防ぎ、品質を安定させるための以下の4つの実践的対策について解説します。
金型の検査などメンテナンスを定期的に実施する
金型の摩耗や損傷は、プレス加工の品質につながるため、定期的なメンテナンスや検査といった保守点検は必須です。特に、バリの発生は刃先の摩耗によるクリアランス拡大が原因となるケースが多く、精密な点検により不良リスクを最小限に抑えることが可能です。
また、製品や材料の特性に応じて、加工方法や金型の仕様、プレス機の設定(圧力・速度)を品質管理部門や生産技術部門と連携しながら最適化することが重要です。
さらに、現場の作業者が実際にその加工条件にもとづいて正確に作業を行うことも品質維持につながるでしょう。標準作業/作業標準を現場の作業ルールとして明確にし、現場と管理部門が一体となって改善を進めることが、安定した生産と歩留まり向上につながります。
作業者が加工条件をルールとして遵守するための仕組みづくりについては、以下のガイドブックで詳しく解説していますので、画像をクリックして資料をご活用ください。
ヒューマンエラーによる不良を防ぐポカヨケの実施
プレス加工では、ヒューマンエラーのような作業者の小さなミスが重大な不良につながる可能性があります。このような事故を防止するために、ポカヨケ(Poka-Yoke)と呼ばれる誤操作防止策の導入が効果的です。
例えば、金型セット時の位置ズレを防ぐガイド設置や、裁断機に手が近づいた際に自動停止する安全装置などがその一例です。特に、異物混入や部品の取り違いなどは、現場でよくあるポカミスですが、ポカヨケにより作業者の意図せぬミスを未然に防ぐことが可能です。
製造現場ではこのようなヒューマンエラーがよく発生します。現場改善ラボでは、製造業におけるヒューマンエラー(ポカミス)の未然を防ぐための具体的な対策方法について、別紙のガイドブックで詳しく解説しています。以下のリンクをクリックして、ガイドブックもご活用ください。
>>「製造業におけるヒューマンエラーの未然防止と具体的な対策方法」を見てみる
原材料の品質確保を目的とした不純物/異物混入の確認
高品質な製品を安定して生産するには、原材料の品質確保が必須です。不純物や異物が混入した材料を使用すると、せん断面でバリやクラックが発生しやすくなるだけでなく、金型の損傷リスクも高まります。
入荷時の受入検査で異物の有無や材質の均一性を確認することで、加工トラブルの発生を未然に防げます。また、トレース可能な材料管理体制(トレーサビリティ)を構築することで、不具合が生じた際も迅速な原因追跡が可能になります。
関連記事:トレーサビリティとは?目的やブロックチェーンとの関係、メリットや企業事例についても解説!
圧力や速度、温度などの加工条件の最適化
プレス加工における「圧力」「速度」「温度」といった加工条件は、製品の品質に大きな影響を与えます。
加工条件が適切でないと、材料が正確に切断・成形されず、バリ・シワ・割れといった品質不良が発生しやすくなります。製品ごとの仕様や材料の特性にもとづき、最適な加工条件を設定することは、生産安定化の基本です。
加工条件の設定においては、生技や品質管理部門と連携し、実データや過去の実績をもとに科学的な根拠をもって最適化を図ることが重要です。また、現場の作業者がその条件を正確に理解し、常に遵守できるように現場教育の推進や標準作業の確立も不可欠です。加えて、条件の変化をリアルタイムで把握できるシステムを導入すれば、不具合の早期発見と再発防止に大きな効果を発揮します。
ここまで、プレス加工における基本的な品質不良対策をご紹介しました。原材料や設備などハード側で行う対策もありますが、人の手を必要とする加工工程であるため、人材育成といったソフト面の対策も大切です。
しかし製造現場の場合、このソフト面の対策を進める難しさが、プレス加工の品質向上の壁となる恐れがあります。次章からは、プレス加工の品質向上における「教育改善」の重要性や難しさを詳しく解説します。
プレス加工の品質向上を難しくする壁【教育改善も大切】
標準作業の未整備による品質のバラつき
作業手順が標準化されていない現場では、作業者ごとにやり方が異なり、結果として製品に品質のばらつきが生じます。特に段取りや設備調整など、精度が求められる作業ほど、「いつも通り」が人によって異なることが不良の原因となります。
標準作業を整備することは、誰が作業しても一定の品質を担保するために必要です。一方で製造現場の場合、標準作業の中にカンコツが要求されるような作業があるケースもあります。このようなケースに対し、カンコツ作業の標準化を進める最適解について、詳しく解説するガイドブックをご用意しているので、以下のリンクをクリックしてご覧ください。
>>「“伝わらない”“属人化している”カンコツ作業を標準化する最適解」を見てみる
金型メンテナンスなど、作業者にカンコツが要求される
プレス加工においては、金型のメンテナンスやトラブル対応といった日々の作業において熟練者の技能(カンコツ)が要求される場面が多くあります。特に、微妙な摩耗の見極めや異音の違和感を察知して対応するような判断は、経験にもとづく技術であり、マニュアルやOJTだけでは伝えきれません。
技術伝承が進まない現場では、メンテナンス不足からバリの増加や寸法不良などが発生し、結果的に品質の安定性が損なわれます。属人的な対応を脱し、技能の見える化・標準化を図ることで、技術の底上げと不良品の抑制が可能になります。教育改善は、品質安定のための土台作りです。
現場改善ラボでは、技術・技能伝承が進まないことで生じる品質不良の改善策について、元トヨタのトップ技能者が解説する動画を無料で公開中です。以下の画像をクリックすると、解説動画をご覧いただけますのでぜひご活用ください。
段取り替えが多く、作業手順の共有がOJTなどに依存してしまう
プレス加工では、加工品目や材料の変更により、頻繁な段取り替えや金型交換が必要です。その結果、作業手順の種類が膨大になり、手順書の作成や更新が後回しになりがちです。
その結果、プレス加工に関する作業手順についてはOJT(現場教育)で対応することが多くなり、管理者の負担増加や指導内容のバラつきにより、作業ミスや品質不良が発生しやすくなります。
業務内容が正しく伝わらなければ、意図しない操作や判断ミスが積み重なり、不具合を生む原因となります。手順の標準化、教育ツールの整備、そして誰でも再現できる仕組み作りが求められており、その一環として動画マニュアルの活用が有効です。
樹脂製品の製造・販売を行う日本クロージャー株式会社では、現場で大きな負担が生じていたOJTの7割を動画マニュアルに置き換え、現場教育の大幅な効率化を実現しています。同社のような動画マニュアルによる改善事例は、以下の資料で詳しくご紹介しているので、リンクをクリックしてご覧ください。
>>「製造業の現場課題に動画マニュアルは効果的?活用事例集」を見てみる
外国人籍の従業員へ、うまく作業内容を伝えられない
プレス加工が盛んな金属製品、自動車部品、電気機械器具などの製造分野では、外国人従業員が一定数在籍しています。
しかし、言語の壁によって基本的な作業手順がうまく伝えられず、手順不遵守による品質不良や作業ミスが起きやすいのが現場の実情です。特に紙のマニュアルや口頭指示だけでは理解が難しく、指導内容が伝わらないまま作業を進めてしまうケースもあります。
こうした課題に対して、視覚的に理解できる動画マニュアルの導入が効果を発揮します。動作を直接見て学べる仕組みを作ることで、言葉に頼らずとも理解度を向上させ、品質の安定化と安全な作業環境づくりを両立させることが可能です。
多くの製造現場で活用されている、かんたん動画マニュアル「tebiki現場教育」であれば、以下のような機能によって、外国籍の従業員が母国語で業務を学べる環境が整えられます。
- 動画の字幕は100ヶ国以上の言語に自動翻訳が可能
- 自動音声による字幕の読み上げ機能(一部言語)
- 管理ページ全体の翻訳も可能で、文書マニュアルも多言語化(一部言語)
tebiki現場教育に関する具体的な機能紹介やプラン、活用事例は以下の画像をクリックすると概要資料をご覧いただけます。
「人材育成」で品質向上に取り組む製造業の事例
ここまでご紹介したように、プレス加工における品質不良の改善には、ハード面の対策だけでなく、人材育成のようなソフト面の対策も大切です。
最後に、人材育成を通じて品質向上を実現した製造業の事例や活用した手段をご紹介します。
手順不遵守を9割削減し、品質改善を実現した事例
自動車の樹脂製品を製造・販売する児玉化学工業株式会社は、多国籍の従業員が在籍する製造現場で、手順書が理解されず作業ミスや品質不良が発生する課題を抱えていました。
紙のマニュアルでは専門用語や作業のコツが伝わらず、「暗黙の了解」に頼る教育が常態化していました。結果的にOJTベースの指導はばらつきが大きく、製品不良の原因となっていました。
▼インタビュー動画:児玉化学工業株式会社▼
そこで同社は動画マニュアルを活用し、人材育成を通じた品質向上の取り組みを推進しました。映像編集未経験者でもかんたんに編集できる「tebiki現場教育」を活用し、視覚的に作業手順を伝えることで、日本人・外国人問わずルールが浸透しました。
この取り組みによって、手順不遵守による不良は9割削減され、マニュアル作成工数も紙より1/3に低減しています。教育の負担が軽減されたことに加え、社内ルールの「見える化」も実現し、品質と業務効率の両面で大きな成果を上げています。
児玉化学工業株式会社のより詳しい品質改善事例は、以下のリンクをクリックしてインタビュ-記事をご覧ください。
インタビュー記事:手順書作成の工数は紙の1/3になったと思います。動画で作るのはかんたんだし、学ぶ側にもわかりやすいですよね。
多くの製造現場で活用されている教育改善を目的としたツール
製造現場において、品質不良や安全トラブルの多くは「作業手順の誤り」から発生しています。特に複雑な作業や細かな動作が求められる工程では、紙の手順書や口頭指導だけでは正確に伝わらず、ミスの温床となっていました。
そこで注目されているのが、動画マニュアルによる教育改善です。作業の流れや重要なポイントを視覚的に伝えることで、経験や言語の違いを超えて、誰でも正確に理解しやすくなります。
こうした動画教育ツールでおすすめなのが「tebiki現場教育」です。スマホで簡単に撮影・編集ができ、100カ国語以上に対応した自動翻訳、テスト機能やスキルマップ、教育履歴の可視化なども搭載。教育の効率化と質の向上を両立でき、多くの製造現場で導入が進んでいます。
実際に先述の児玉化学工業株式会社では、tebikiを活用し、手順不遵守による不良を9割削減する成果を実現しています。「tebiki現場教育」の具体的な機能やプラン、活用事例は以下のリンクをクリックして概要資料をご覧ください。
>>かんたん動画マニュアル「tebiki現場教育」の概要や改善事例を詳しく見る
プレス加工で発生する不良を改善しよう【まとめ】
製造現場の品質向上には、正確な作業手順の伝達と標準化が欠かせません。紙の手順書や口頭指導だけでは伝わりづらい作業も多く、ミスや不良の原因となります。
そこで注目されるのが、視覚的にわかりやすく作業を伝えられる動画マニュアルの活用です。中でも「tebiki現場教育」は、簡単操作で動画作成ができ、多言語対応や教育進捗の見える化機能も搭載。実際に多くの現場で導入され、品質改善や教育効率化を実現しています。
「tebiki現場教育」の資料はこちらからからダウンロード可能ですので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。