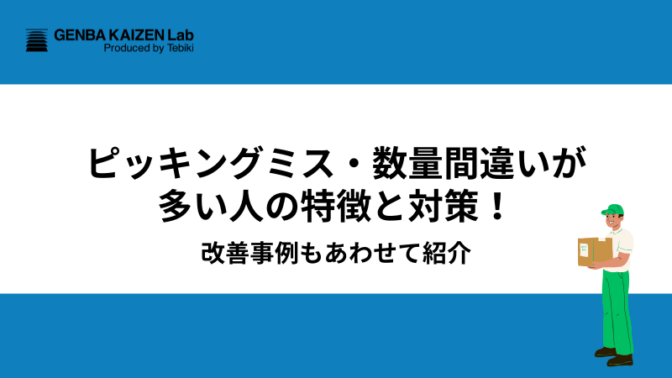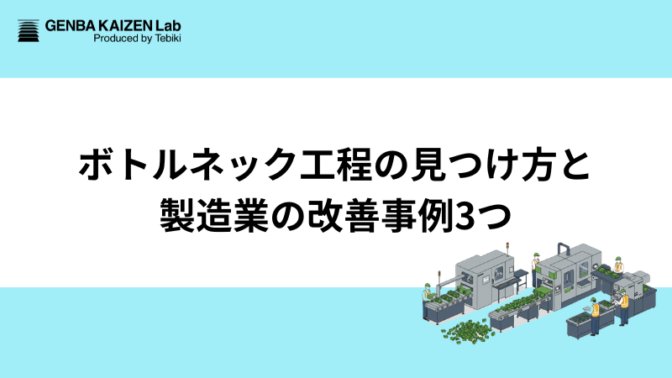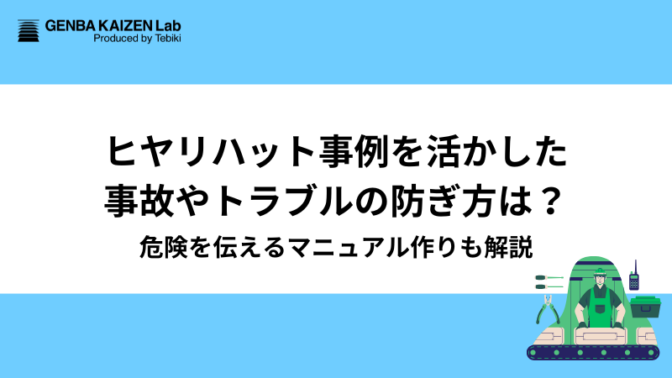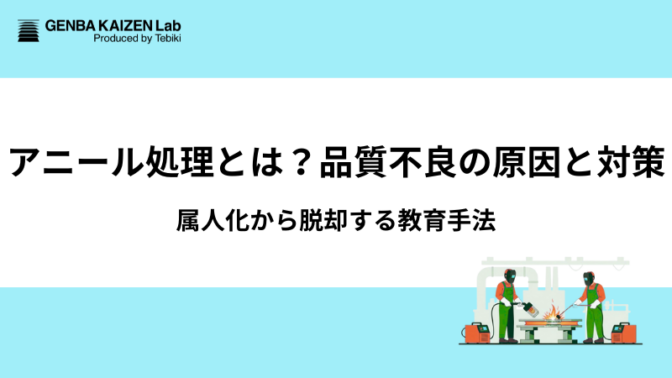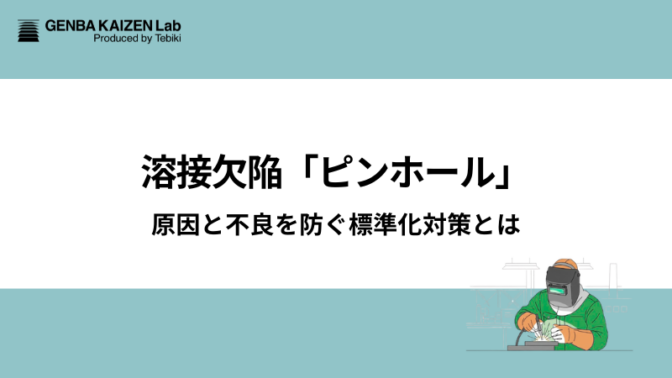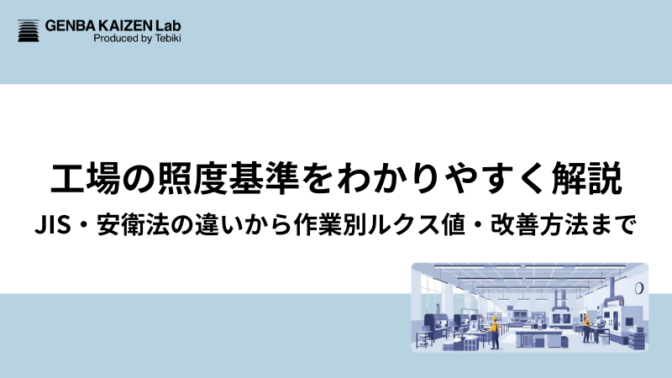かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を展開する現場改善ラボ編集部です。
製造業ではQCDという言葉はとても重要な意味を持ちます。この記事では、このQCDにSを追加した「QCDS」とは何か?解説するほか、QCDSの改善手法などを紹介します。QCDSを改善させたい方はぜひ参考にしてください。
QCDSの4つの要素は相互に関連していますが、その中でも全ての基本となるのが「Q(品質)」です。品質が安定してこそ、コストの削減(C)、納期の遵守(D)、安全な職場(S)が実現しやすくなります。
この品質(Q)を科学的に管理し、改善していくために必須となるのが、データ分析の基本的な手法である「QC7つ道具」です。
QCDS改善の第一歩として、品質問題の原因を的確に捉え、見逃しを防ぐためのQC7つ道具の具体的な使い方を、以下の資料で詳しく解説しています。
QCDSとは?
QCDSとは、品質(Quality)・コスト(Cost)・納期(Delivery)・サービス(Servise)/安全性 (Safety)の頭文字を取ったものです。
製造業はモノを作り、販売することで利益を生み出します。何も考えずただモノを作っていただけでは、利益を確保することは難しく、顧客にも満足してもらえない可能性があります。そのため、生産活動や製品を評価する指標が必要であり、そこで登場するのがQCDです。
QCDSの中でも、全ての土台となるのが「Q(品質)」です。品質が安定してこそ、コスト(C)や納期(D)の改善にも繋がります。この品質(Q)を科学的に管理し、改善していくために必須となるのが、データ分析の基本的な手法である「QC7つ道具」です。
QCDS改善の第一歩として、品質問題の原因を的確に捉え、見逃しを防ぐためのQC7つ道具の具体的な使い方を、以下の資料で詳しく解説しています。
品質(Quality)
品質(Quality)は、顧客が求める製品の基準のことです。
企業は顧客が求める基準をつねにクリアすることを求められます。開発や設計段階で要求を満たした製品の仕様を決定し、生産現場では良品と不良品の基準を明確にして、品質不良の発生を最大限抑え込みます。
これらの手法の中でも、特に製造現場の数値データを客観的に分析し、問題点を明確に「見える化」するために広く用いられているのが「QC7つ道具」です。
品質改善の第一歩である「現状理解」を正しく行うために、まず押さえておきたいQC7つ道具の各手法と、その具体的な使い方について、以下の資料で詳しく解説しています。
コスト(Cost)
コスト(Cost)は、製品の原価のことです。
具体的には仕入れにかかる原材料費や人件費、資材費、光熱費、外注費などが原価に相当します。売上から原価を引いたものが利益に当たり、企業としては利益を最大化するために原価をできるだけ抑えたいところです。
納期(Delivery)
納期(Delivery)は、顧客が求める納品期日のことです。
基本的に納期に遅れることは許されません。顧客が指定する期日までに納品できなければ、失注につながる恐れもあります。したがって、納期を守るように緻密な生産計画が求められます。
サービス(Servise)/ 安全性(Safety)
サービス(Servise)は、顧客へのサービスやサポートのことです。
製造業では製品価値だけでなく、顧客の体験価値という点も大切な要素になっているため、製品を販売したあとのアフターサービスやソリューションを提供することが重要です。
なお、製造業においては、Sをサービス(Servise)ではなく、安全性(Safety)と解釈している場合もあります。
製造現場では、機械への挟まれや巻き込まれ、転倒などの労働災害が発生する危険性があります。このような事故が起きないように、安全第一の考え方があります。
製造業における優先順位は「SQCD」?
QCDSの優先順位は一般的に、Q>C>D>Sの順番ですが、業務に危険が伴い、安全第一の考え方がある製造業では安全性(Safety)の優先度が非常に高くなります。
厚生労働省の調査では、令和4年から令和5年にかけて労働災害による死傷者数は+3,016人(2.3%増)。製造業に絞ってみても+500人(1.9%増)と、労働災害の発生件数は増加している傾向です。製造業は常に危険と隣り合わせの環境で日常的に業務に従事しています。
労働災害は大切な従業員の日常生活ひいては、将来にも影響を及ぼす重大な事故です。労働災害を防ぐためにも、製造業では安全性(Safety)の優先度を上げ、S>Q>C>Dの順番で捉えることが重要と言えるでしょう。安全性を高めるためにも、さまざまな安全教育や安全対策が行われています。
▼関連記事
・【製造業の安全教育】安全意識を高める教育手法やネタ例を解説!
・工場の安全対策10選と好事例を解説!製造業の安全宣言例も紹介
製造業におけるQCDSの改善手法
ここでは製造業に絞ってQCDSを改善するための手法について紹介していきます。
品質(Quality)の改善手法
製造業における品質改善のはじめの一歩として、現状を正しく理解することが重要です。現状理解の方法は、トヨタ自動車が発案した分析手法の一つである「なぜ」を繰り返して課題を深堀りする「なぜなぜ分析」や、製造品質の現状分析や不良発生時の原因分析に役立つ「QC7つ道具」「新QC7つ道具」などが製造現場で用いられています。
これらの手法の中でも、特に製造現場の数値データを客観的に分析し、問題点を明確に「見える化」するために広く用いられているのが「QC7つ道具」です。
品質改善の第一歩である「現状理解」を正しく行うために、まず押さえておきたいQC7つ道具の各手法と、その具体的な使い方について、以下の資料で詳しく解説しています。
コスト(Cost)の改善手法
製品原価の大部分は、設計や開発の段階で決まるとされています。生産現場でコスト管理をすることも大切ですが、それよりも上流の設計の段階でコスト削減をすることが先決です。
設計でのコスト削減としては、部品や材料の見直しがあります。たとえば、他の製品でも使っている共通部品を増やすことで、管理する部品点数が少なくなり、在庫にかかるコストが削減できます。
また、新人受け入れなどの場面では、OJTや作業手順書の整備などで人的なコストも発生します。製造業の新人教育では、紙ベースの作業手順書が使われますが、より効率化するためにも動画の活用がおすすめです。以下の資料では、「動画マニュアルのメリット」「期待できる効果」などを説明しているので、ぜひご覧ください。
>>>動画マニュアルで現場の教育をかんたんにする方法を見てみる
納期(Delivery)の改善手法
顧客の納期に応える方法として、在庫を持っておくことがあげられます。しかし、いつ来るか分からない注文のために在庫を大量に持つとコストの増大につながるため、在庫を適正に保つことも大切です。
手法としては、在庫を繰り返し生産する見込み生産品と受注生産品を分けることがあげられます。注文が来てから作り始める受注生産品は、在庫を極力持たないようにします。一方、頻繫に注文が来るような見込み生産品は、ある程度在庫を抱えていてもいずれ無くなる可能性が大きいため、あらかじめ在庫として用意しておくのです。
また、納期短縮には、リードタイム短縮という手法もあります。製造リードタイムとは、生産に着手してから出荷までにかかる時間で、製品リードタイムを短くすることは納期短縮のカギです。リードタイムの計算方法や改善方法を知りたい方は以下の記事も参考にしてください。
関連記事:タクトタイム・サイクルタイム・リードタイムの計算と改善方法【意味や違いも解説!】
安全性(Safety)の改善手法
安全性の改善は従業員に対しての安全な労働環境の提供、社会的な信用・信頼の確保などに寄与する重要な要素です。
具体的な改善方法として、現場に潜む危険性や有害性を調査し、低減/除去するまでの一連の手法であるリスクアセスメントへの取り組みが挙げられます。リスクアセスメントに取り組むことで、現場に潜むリスクが明確になり、必要な安全対策の優先順位を合理的に決めることが可能です。
なお、リスクアセスメントを実施して製造現場の安全性を向上させるためにも、動画を活用したマニュアルや教育機会の整備が大切です。動画の活用によって、注意点や作業手順などを口頭や紙での教育と比べて伝わりやすくなります。
以下の資料では、「製造現場にいて安全教育がうまくいかない理由」「安全意識が高い製造現場で実施してる安全教育」などを紹介しています。以下より資料をご覧ください。
QCDSの改善に役立つフレームワーク
QCDSの改善を進めていく上では様々な取り組みが必要になります。その中で役立つフレームワークを3つ紹介します。
QC7つ道具
製造現場では製品の品質や工程などの様々なデータがあり、適切に収集して管理し、収集したデータを分析する必要があります。これらの製造現場における定量的な数値データの解析に使用するものをQC7つ道具と呼びます。
- パレート図
- 特性要因図
- グラフ(層別)
- ヒストグラム
- 散布図
- 管理図
- チェックシート
上記のグラフや図を活用してデータを表現し、品質を客観視することによって、課題解決の優先順位をつけたり改善の効果を確認したりします。「QC(Quality Control)=品質管理」なので、品質(Quality)の改善に役立てることができます。
このように、新QC7つ道具は複雑な問題の構造を言語データで整理し、本質的な原因を探るのに非常に有効です。
一方で、こうした言語データで表現される問題(例:「バリが発生する」)を分析する前段階として、まず「いつ、どこで、どのくらい」その問題が起きているのかを数値データで正確に把握することが不可欠です。
そのための最も基本的で強力なツールが、定量分析の王道である「QC7つ道具」です。
複雑な問題の解決に取り組む前に、まずはその土台となる現状把握とデータ分析を行うためのQC7つ道具の使い方を、以下の資料でしっかり確認しておきましょう。
新QC7つ道具
QC7つ道具が数値データを扱うものであることに対し、新QC7つ道具は言語データを扱います。
- 親和図法
- 連関図法
- 系統図法
- アローダイアグラム
- マトリックス図法
- マトリックスデータ図法
- マトリックスデータ解析法
- PDPC法
言語データの具体例としては、「製品にバリが発生してしまう」「食品に異物が混入してしまう」などです。これらのデータは発生する原因が複雑に絡み合っており根本の原因を見つけるのは非常に難しい傾向があります。この原因となる課題を見つけて改善するために「新QC7つ道具」を活用するのです。
このように、新QC7つ道具は複雑な問題の構造を言語データで整理し、本質的な原因を探るのに非常に有効です。
一方で、こうした言語データで表現される問題(例:「バリが発生する」)を分析する前段階として、まず「いつ、どこで、どのくらい」その問題が起きているのかを数値データで正確に把握することが不可欠です。
そのための最も基本的で強力なツールが、定量分析の王道である「QC7つ道具」です。
複雑な問題の解決に取り組む前に、まずはその土台となる現状把握とデータ分析を行うためのQC7つ道具の使い方を、以下の資料でしっかり確認しておきましょう。
4M
4Mとは、「Man(人)・Machine(機械)・Material(材料)・Method(方法)」のことを指し、それぞれの頭文字を取って名付けられたフレームワークです。製造業の「ものづくり」を支える重要な要素であり、理解を深めて効果的に管理することで製品品質の向上に寄与します。
4M分析をすることによって、発生している問題の原因を漏れや偏りなく突き止めることができ、一見些細な作業者のミスであっても作業手順や設備の不具合が根本的な原因であることが判明する場合もあります。
なお、QCDSの改善にはフレームワークだけではなく、動画や電子帳票の活用も効果的です。次章では、動画・電子帳票が効果的な理由や企業の改善事例を紹介します。
QCDSはtebikiで改善!
QCDSの改善は、動画マニュアルを作成できて従業員の教育ができる「tebiki現場教育」、現場帳票の作成、記録、管理、分析がかんたんにできる「tebiki現場分析」の活用がおすすめです。
QCDSの改善には「tebiki現場教育」
QCDSの改善には、動画マニュアルを作成でき、従業員への教育に役立てられる「tebiki現場教育」がおすすめです。紙の手順書の場合、更新が一切行われない/作業の細かい指示が曖昧などの課題があり、従業員のスキルにバラつきが生じるリスクがあります。
一方、動画を活用することで、文章では伝えにくい「動き」を伝えられ、カンコツを要する作業を視覚的に学べて作業の要領をいち早く掴むことができます。また、動画はタブレットがあれば場所や時間にとらわれず、繰り返し学習できるためOJTなどの教育コスト削減、作業の標準化にもつながるでしょう。危険が伴う作業については、動画内で危険を知らせる「図形」、動画を一時停止させて注視率を上げるなどの安全教育にもつながります。
tebiki現場教育についてより詳しく知りたい方は、機能や導入メリットを分かりやすくまとめた「かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育サービス資料」」をご覧ください。
次の見出しでは、QCDSの改善につながった動画マニュアル活用事例として、テーブルマーク株式会社の例を解説します。
「tebiki現場教育」を活用したQCDSの改善事例
「tebiki現場教育」を活用したQCDSの改善事例として、テーブルマーク株式会社の事例をご紹介します。
▼インタビュー動画:テーブルマーク株式会社▼
うどんやチャーハンなどの冷凍製品や業務用商品など、幅広い食品を製造販売している同社では、指導者ごとに指導する内容にばらつきがあったり、外国人労働者に対しての教育コストが発生するなどの課題がありました。
そこで、カンタンに動画マニュアルを作成できる「tebiki現場」を導入。OJTを動画に置き換えることで、教育工数を6時間から1時間まで教育コストを削減でき、動画で繰り返し学習することで製品の配合不良を防ぎ、品質向上にもつながっています。
現場の従業員からは「動きをわかりやすく動画で伝えた方が安全に作業ができる」など、安全性(Safety)の改善も実感しています。同社の具体的な取り組み内容や抱えていた課題を詳しく知りたい方は、こちらのインタビュー記事をクリックしてご覧ください。
より多くの動画マニュアルの活用事例を見てみたい方は、製造現場で動画マニュアルを活用したことによる改善事例集もご用意していますので、以下のリンクをクリックして参考資料もご覧ください。
QCDSの管理には「tebiki現場分析」
QCDSは改善するだけではなく、日々異常がないかを適切にモニタリングして管理することが大切です。その管理に活用できるのが、製造現場の帳票を作成〜分析までできる「tebiki現場分析」です。
「tebiki現場分析」では、作業日報や設備点検表、製品入庫伝票などの現場帳票をデジタル化して管理でき、タブレット上で記録を管理し分析できます。異常が発生した際にはリアルタイムで状況を把握できて、現場の改善に繋げられます。
デジタル現場帳票の有効性をより詳しく知りたい方はこちらの記事か、以下のリンクをクリックして参考資料をご覧ください。
「tebiki現場分析」を活用したQCDSの管理事例
▼インタビュー動画:株式会社日本電気化学工業所▼
「tebiki現場分析」を活用したQCDSの管理事例として、株式会社日本電気化学工業所の事例をご紹介します。
同社ではアルマイト加工を中心に、建材や車両などの表面処理を手がけており、帳票の記録そのものが目的とされ、収集したデータを活用して現場の改善につなげることができない課題を抱えていました。
この課題を解決すべく、帳票の作成・管理をデジタル化できる「tebiki現場分析」を導入し、ダッシュボード上でデータのリアルタイム監視が可能になり、品質管理のプロセスが大きく改善したと語ります。具体的には、温度データの些細な変化に気づき、調査したところ設備の不良を見つけられ、大きな故障や生産ラインの停止といった深刻な事態を防ぐことができました。
「デジタル化の取り組みを通じて、より高品質な製品を効率的に提供し、お客様満足度の向上につなげていきたい」と語る、同社のインタビュー記事は以下よりご覧ください。
インタビュー記事:品質不良の未然防止をリアルタイムデータで実現。異常値検知を迅速にできた理由。
現場帳票のデジタル化に興味がある方は、「はじめての現場帳票デジタル化ガイド」の資料もご覧ください。
【補足】QCDSの派生語について
ここではQCDSから派生した用語について紹介していきます。
QCDSM
QCDSMとは、Quality(品質)、Cost(費用)、Delivery(納期)、Safety(安全)、Moral(モラル)の頭文字を取った言葉のことです。
モラル(Moral)は従業員・経営者の倫理感のことであり、健全でハラスメントのない職場のことを指します。5つの要素をバランスよく管理することで企業成長につながるという考え方です。Moral(モラル)は、従業員アンケートや360度フィードバックなどで評価されます。
QCDSE
QCDSEとは、Quality(品質)、Cost(費用)、Delivery(納期)、Safety(安全)に環境(Environment)を追加して頭文字を取った言葉のことです。主に建設業界で用いられることが多く、重要な指標となっています。
建設業界はその時々で現場の環境が異なり様々な影響が及びます。そのため、環境に適した施工方法や素材の選定や運搬など、環境への影響を最小限に抑える努力が必要になるでしょう。
PQCDSME
PQCDSMEとは、生産性(Productivity)、Quality(品質)、Cost(費用)、Delivery(納期)、Safety(安全)、安全(Safety)、やる気(Morale/Moral)、環境(Environment)の頭文字を取った言葉のことです。
QCDSM、QCDSEは主に製品やサービスの品質向上の意味合いが強いのに対し、PQCDSMEは組織全体の効率、働きやすさなどにも寄与します。
まとめ
QCDSは生産活動や製品を評価する指標であり、品質(Quality)・コスト(Cost)・納期(Delivery)に、安全性(Safety)もしくはサービス(Servise)のいずれかを加えた4つの要素で構成されています。
様々な業界で取り入れられているフレームワークですが、安全第一を追求する製造業においてはSを安全性(Safety)と解釈されることが多く、優先順位はS<Q<C<Dの順であることが多いです。QCDSの改善には様々な手法があるので、自社に適した方法で取り組んでみてください。
なお、QCDSの改善には、動画マニュアルを作成できて従業員の教育ができる「tebiki現場教育」、現場帳票の作成、記録、管理、分析がかんたんにできる「tebiki現場分析」の活用がおすすめです。以下の画像から無料でダウンロード可能ですので、ぜひ詳細をチェックしてみてください。
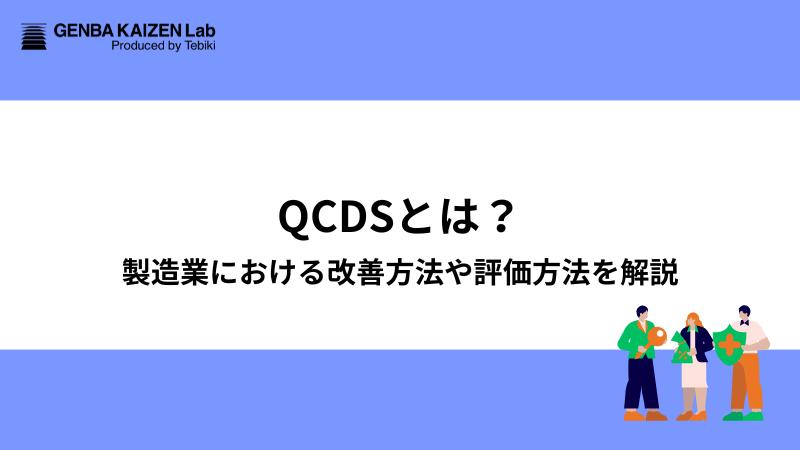



-2.png)