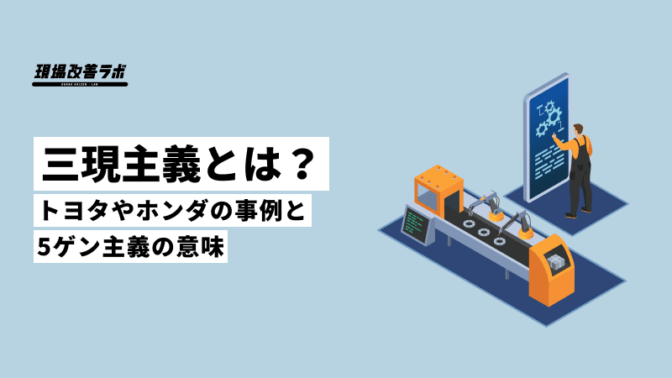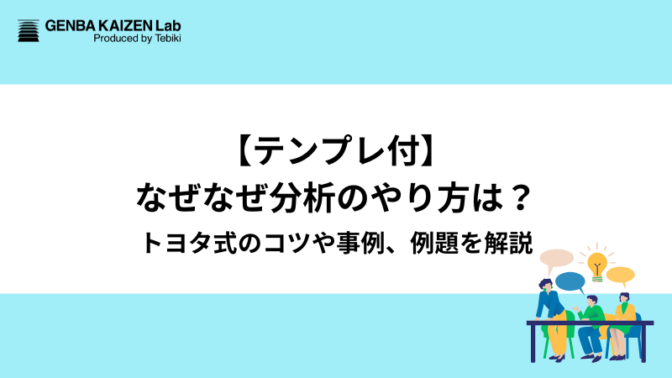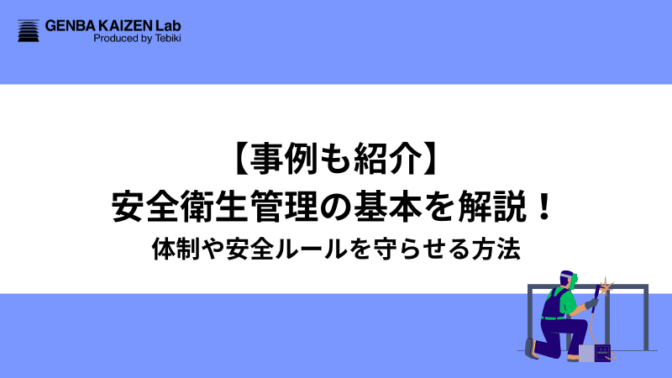かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」とかんたんデジタル現場帳票「tebiki現場分析」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
QMSとは「Quality Management System」の頭文字を表し、日本語では品質マネジメントシステムと呼びます。QMSはその本質を理解していないと、意外と難しい言葉ではないでしょうか。
本記事では、ISO9001の審査員補で株式会社エイシン・エスティー・ラボ代表取締役の山本 諭氏の監修で、QMSの基本的な役割や構築手順、内部監査のポイントをわかりやすく解説します。
QMS(品質マネジメントシステム)を構築しても、そのルールが現場で無視されては意味がありません。
この「ルール無視」の根本原因である「品質意識」の低下について、その考え方と対策を以下の資料で解説します。
>>品質意識の低下が招く「ルール無視」に対する考え方と対策を見てみる
▼監修者:株式会社エイシン・エスティー・ラボ 代表取締役 山本 諭

2004年化粧品容器の製造企業に入社。生産管理、品質管理の経験を経て、製造部門長に就く。100人の従業員をマネジメントする傍ら、独自の自動化で生産性を10倍に向上。生産管理システムの導入やISO9001の認証取得などにも積極的に取り組む。2020年(株)エイシン・エスティー・ラボを設立。ISOの認証取得支援や、財務改善、業務改善に加え、1on1による従業員のモチベーション向上支援に従事。
目次
QMS(品質マネジメントシステム)とは?わかりやすく解説
QMSとはQuality Management Systemの略称で、日本語に訳すと「品質マネジメントシステム」「品質管理システム」です。QMSは、企業が製品やサービスの品質を継続的に維持・改善するための仕組みです。方針や目標を定め、その目標を達成するために必要な管理業務のまとまりを指します。
ただ、英語を日本語に訳しただけでは、イメージが湧きにくいかもしれません。そこで、同じ“システム”が付くシステムキッチンを例に考えてみましょう。
QMSとは「製品やサービスの品質維持/改善を継続する仕組み」
『QMSの概要を掴みにくい…』という方に向けて、分かりやすくお伝えするためにシステムキッチンを例にご紹介します。
システムキッチンは、流し台・コンロ・調理台・収納などが、1枚の天板で繋がり、全てが一体となるように組み合わせたキッチンのことです。食洗機や浄水器なども組み込まれていて、「料理を作る」という目的に対して全体の動線や使いやすさを考慮して設計されています。
同じように、マネジメントシステムも「目的」を達成するために様々な業務や作業をひとつのまとまりとして考えられたものです。QMSの場合、その目的は「顧客満足を向上させる」ことで、個々の業務や作業が、全体として効果的に機能するように設計された仕組みなのです。
▼QMS(品質マネジメントシステム)のイメージ図▼

コンロと換気扇が別々の場所にあったら意味をなさないように、業務の流れがバラバラでは顧客満足を向上させることは難しいです。
製造業であれば、原材料の調達、製造工程、品質検査、出荷までの一連の流れを標準化して管理します。サービス業であれば、顧客とのコミュニケーション、サービス提供のプロセス、顧客フィードバックへの対応などが含まれます。
QMSは、顧客満足(品質)の向上を目的とした、製品やサービスの品質を維持/改善(マネジメント)していくための仕組みと言えます。
関連記事:【7原則】品質マネジメントとは?目的やポイント、効率化方法を徹底解説
QMSにおける「品質」の定義
一般的に「品質」と聞くと、製品の寸法や性能が規格に合っているかどうかを思い浮かべるかもしれません。
しかし、QMSにおける「品質」の定義は、顧客のニーズや期待を満たす程度を指します。単に品質不良を減らすことだけではなく、顧客満足に繋がるすべてのことを「品質」と呼んでいるのです。
「顧客満足」という広義の「品質」も、それを実現するための「ルール」が現場で無視されていては達成できません。
この「ルール無視」の根本原因である「品質意識」の低下について、その考え方と対策を以下の資料で解説します。
>>品質意識の低下が招く「ルール無視」に対する考え方と対策を見てみる
QMSは意味ない?構築の目的やメリット
『QMSは意味がないのでは?』という声が聞かれることもありますが、それはQMS本来の目的を理解していない場合や、形式的に導入されている場合があります。
QMSは以下のような目的で正しく構築すれば、メリットとして効果を教授できます。
顧客満足の向上
QMSの目的は、顧客満足を継続的に向上させることです。顧客の声を取り入れ、プロセスを改善することで、信頼性の高い製品やサービスを提供できます。
業務効率の向上
プロセスを標準化し、誰もが同じ方法で同じ作業ができる仕組みを整えることで、ムリ・ムラ・ムダが減り、効率的な業務運営が可能になります。
リスクの低減
リスクを特定し、管理する仕組みを持つことで、トラブルやクレームの発生を未然に防ぎます。
競争力の強化
高品質な製品やサービスを安定的に提供できる企業は、顧客からの信頼を得やすく、競争優位性を確立できます。
法令遵守の確保
法規制に適合するための仕組みを構築することで、法令違反のリスクを最小限に抑えることができます。
どのような企業でも、顧客満足を向上するために何らかの取組みを行っているはずです。それがすなわちQMSです。意味があるかないかということではなく、どの企業にもすでに存在するものというのがQMSの本質ではないでしょうか。
QMSとISOの違い、どのような関係性か?
QMSは、組織が製品やサービスの品質を維持・向上させるための仕組みやプロセスの集合体です。
一方、ISOとは「International Organization for Standardization」の略称で、国際標準化機構という組織の名称です。ISOは『世界中で同じ品質、同じレベルのものを提供できるようにしましょう』という考えのもと、世界共通の規格を制定しています。それがISO規格です。
ISO規格には、大きく分けて2つの規格があります。
- モノ規格:非常口のマークやクレジットカードのサイズ、ネジの規格など「モノそのもの」が対象
- マネジメントシステム規格:モノではなく「組織のマネジメント」が対象
つまり、QMSはISOのマネジメントシステム規格の1つであるということです。そしてQMSの構築にあたり、組織が目的(品質向上)を実現し、効率的に業務を実施するためのルールや手順を定めたものとして、有名なものがISO9001です。
QMSとISOの関係性を分かりやすく表現すると、QMSがシステムキッチン全体のことを指すのに対して、ISOは「流し台はこのサイズでこの場所に設置し、コンロはIHで、食洗機はこの容量」といった具合で、それぞれのパーツに対する性能基準のようなイメージです。
QMS(品質マネジメントシステム)に関する主な規格
QMSに関連する規格は、最も有名なISO9001など様々な規格が存在します。本章では以下の規格について、概要をご紹介します。
- ISO9001
- IATF16949(自動車業界向けのQMS)
- ISO13485/QMS省令(医療機器向けのQMS)
- FSSC22000(食品業界特向けのQMS)
ISO9001
ISO9001は、組織が製品やサービスの品質を向上し、顧客満足を向上するための国際規格です。多くの企業が品質保証や信頼性向上のために採用しています。
関連記事:【意味がない?】ISO9001とは?メリットや費用、やめた企業の理由
IATF16949(自動車業界向けのQMS)
IATF16949は、自動車産業に特化した国際規格です。ISO9001をベースとし、サプライチェーン全体で不具合の予防、ばらつき・ムダの低減、継続的改善を目的としています。世界の多くの自動車メーカーがこの規格を採用しています。
ISO13485/QMS省令(医療機器向けのQMS)
ISO13485は、医療機器産業に特化した国際規格です。医療機器の安全性と品質維持を目的とし、医療機器の設計、製造、流通、サービスなど、すべてのプロセスを対象とした規格です。
また、QMS省令は、ISO13485と日本の薬機法をもとに作られていて、医療機器の承認・認証における製造管理、品質管理の審査の基準となる省令です。
FSSC22000(食品業界向けのQMS)
FSSC22000とは、Food(食品)Safety(安全)System(システム)Certification(認証) の略称で、ISO 22000食品安全マネジメントシステムを追加要求事項で補強した食品業界向けの国際規格です。消費者に安全な食品を提供することを目的としています。
関連記事:【簡単解説】FSSC22000とは?取得企業一覧や要求事項、認証の流れを解説
QMS(品質マネジメントシステム)規格:ISO9001の要求事項や原則は?
前章では、QMSの代表的な規格を一覧でご紹介しましたが、とくに多くの現場で運用されているのがISO9001ではないでしょうか。
ISO9001の要求事項は、顧客満足を向上するためにQMSを構築し、実施し、より有効に活用するための要件となっています。QMSの構築にあたり、ISO9001で求められている概要を確認しましょう。
ISO9001が定める「要件(=ルール)」も、現場の「品質意識」が低ければ無視されます。
QMS構築の土台となる「ルール無視」の問題について、その考え方と対策を以下の資料で解説します。
>>品質意識の低下が招く「ルール無視」に対する考え方と対策を見てみる
ISO9001の要求事項
ISO9001の要求事項は10項目あります。それぞれの項目にのっとりルールを作成し、運用することで、効果的なQMSを確立することができます。
- 適用範囲
- 引用規格
- 用語及び定義
- 組織の状況
- リーダーシップ
- 計画
- 支援
- 運用
- パフォーマンス評価
- 改善
この10項の中でも、構築/運用時に求められるものが4項から10項の内容です。具体的な要求事項の内容は、以下の記事で詳しく解説しているので併せてご覧ください。
関連記事:【ISO9001】要求事項をわかりやすく解説!現場では何が必要?運用のコツとは
ISO9001:2015版で品質マネジメントの原則が変更
ISO9001の規格は、以下の品質マネジメントの7原則を踏まえて作られています。
- 原則1.顧客重視
- 原則2.リーダーシップ
- 原則3.人々の積極的参加
- 原則4.プロセスアプローチ
- 原則5.改善
- 原則6.客観的事実に基づく意思決定
- 原則7.関係性管理
この品質マネジメントの原則は2015年の改訂に伴い、「プロセスアプローチ」と「マネジメントへのシステムアプローチ」が統合され8原則から7原則になりました。
より構築しやすく、そして効果の出やすいISOになった半面、組織の自主性に任される部分が増えたので、組織ごとのQMSのレベル差が大きくなったとも言えます。
関連記事:【7原則】品質マネジメントとは?目的やポイント、効率化方法を徹底解説
ISO9001の改訂でQMSの最新情報はどうなる?
ISO9001の改訂は6年〜8年のスパンで行われてきました。2024年12月現在、2015年の改訂から大きな改訂はありませんが、次の改訂は2026年頃と予想されています。
具体的な改訂内容は現時点では公表されていませんが、日本規格協会の情報によると以下の項目が改訂作業のインプットに含まれると言われています。
- 「附属書SL‐MSSのための調和させる構造」の改訂
- グローバルに関連するビジネスと社会の変化
- リスク及び機会の要求事項に関する改善
- 文書化した情報に関する要求事項の見直し
- サプライチェーンに関する課題
- 可監査性(auditability)を考慮した改善
「ビジネスと社会の変化」という文言からも、デジタル化を含め、より今の時代に即した規格に変更されることが期待されます。
品質改善のPDCAを推進するQMS(品質マネジメントシステム)構築の手順やポイント
QMSの構築に必要なのは、ISO9001の要求事項だけではありません。その他に、顧客要求事項、法規制、社内の独自ルールも含まれることを踏まえ、構築手順やポイントを解説します。
QMS構築の手順
目的の明確化と現状の把握
QMSを構築する第一歩は、「なぜQMSを構築するのか」を明確にすることです。
目的が明確になることで、従業員や利害関係者に共通の理解が生まれ、プロジェクトのスムーズな推進が可能になります。この段階では、経営層が主導的な役割を果たし、全社的な方針として方向性を示すことが求められます。
また、組織の現状を正確に理解することも重要です。SWOT分析シートなどを使って、利害関係者のニーズや期待、組織の内部や外部の課題、ビジネスチャンスやリスクを洗い出します。
品質方針と品質目標の設定
組織の品質に対する基本的な考え方を示す「品質方針」を定めます。
そして、品質方針を実現するための具体的な「品質目標」を設定します。定性的な品質方針に対して、品質目標は「不良率を年間1%以下に抑える」といった定量的な形で、達成状況を測定できる内容が好ましいです。
プロセスの設計と文書化
QMSの構築において最も重要なステップの1つです。QMS体系図やQC工程表などを使って、組織の業務フローを明確にすることで、組織全体で一貫した運用が可能になります。また、定めたルールを守るために、責任の所在や権限を組織図などを使って明確にしておくことも重要です。
代表的な業務プロセスには、以下のようなものがあります。
- 営業プロセス:見積、受注、問い合わせ対応など。
- 設計・開発プロセス:新製品の開発、試作品の製作など。
- 製造プロセス:製品の組立て、検査、梱包など。
- 品質管理プロセス:原材料の検査、製造工程の確認、完成品の検査・測定など。
- 購買プロセス:発注、仕入れ先の評価・選定など。
また、プロセスごとのルールを視覚的に分かりやすくするために、基準書や手順書、帳票を作成します。
- マニュアルや要領:各作業の具体的な手順。
- 検査基準書:品質を確認するための基準。
- 各種帳票類:決まったフォーマットで記録を残すための書類。
ここで求められている手順書や帳票は『紙や文書形式でないといけない』というイメージがあるかもしれませんが、動画マニュアルやデジタル現場帳票などの形式でも問題はありません。
>>ISO9001の文書管理に動画マニュアルが有効な理由を見てみる
リソースの整備
QMSを効果的に運用するためには、必要なリソースを準備することが不可欠です。リソースには、以下のようなものがあります。
- 人材:必要なスキルを持つスタッフを配置し、教育・訓練を実施する。
- 設備:効率的な生産を支える機械やシステムを導入する。
- 情報:デジタルツールや記録システムを導入して情報管理を効率化する。
このようなリソースを可視化する手段については、後ほど「効率的なQMS(品質マネジメントシステム)の構築/運用を実現するデジタルツール」で詳しくご紹介します。
運用開始
設計されたプロセスや準備したリソースをもとに、QMSを実際に運用します。
初期段階では、現場からのフィードバックを積極的に収集し、問題があれば迅速に対応することが大切です。また、定期的なミーティングを通じて、従業員の理解を深め、ルールの遵守を徹底させます。
パフォーマンス評価
QMSが正しく運用されているかを確認するために、定期的な評価を行います。
- KPI(重要業績評価指標):設定した品質目標の達成状況を測定する。
- 内部監査:QMSに適合しているか、また有効に機能しているかを確認する。
- 顧客からのフィードバック:苦情やアンケート結果を分析する。
- マネジメントレビュー:経営トップがQMS全体の状況を確認し、改善の方向性を決定する。
パフォーマンス評価で課題になりやすいのが、KPIである品質目標の状況測定です。定量的に測ろうとすると、製造現場にまつわるあらゆるデータを集計/分析する工数が発生します。管理者にとって、この工数は大きな負担となります。
このようなデータ集計/分析を効率化できる手段が「現場帳票のデジタル化」です。
実際、ISO9001を認証取得している製造現場でデジタル現場帳票を活用したことで、管理者のデータ集計工数が1日2時間から1分に短縮し、分析~改善の動きが効率化された事例もあります。
継続的改善
発見された問題や課題を解決し、システム全体を改善する仕組みを構築します。中でも「是正処置」は、発生した不適合の再発を防ぐための具体的な対応であり、継続的改善の一部として位置づけられています。
継続的な品質改善を促進するQMS構築/運用のポイント
PDCAサイクルを徹底する
QMSは構築の流れからも分かるように、PDCAサイクルで作られています。各ステップごとに取るべきアクションを明確にすることで、継続的改善が進む流れを整えましょう。
- 計画(Plan):目標を設定し、実行可能な計画を立てる。
- 実行(Do):責任と権限を明確にし、全従業員が計画にもとづいて行動できるようにする。
- 評価(Check):定量データをもとに進捗状況や達成度を評価する。
- 改善(Act):課題や新たな機会にもとづいてシステムを改善する。
従業員の巻き込み
現場の従業員がQMSの意義を理解し、主体的に取り組むことが成功の鍵です。
そのためには、目的の共有、教育、意見収集、成功事例の可視化が重要です。従業員が主体的に参加できる環境を作り、改善活動の価値を実感してもらうことで、QMSの効果は最大化されます。
デジタルツールの活用
QMSにおけるデジタルツールの導入は、標準化・効率化・継続的改善を強化する最適な手段です。
例えば、動画マニュアルを「支援」として利用することで、作業者全員が同じ基準で作業を行えるようになったり、新人教育や技能伝達の時間短縮が可能となります。また、デジタル現場帳票で「監視・測定」を強化することで、リアルタイムで記録の確認・分析ができるようになります。
デジタルツールの活用は、QMS構築による従業員の負担を軽減するためにも必要不可欠なものとなりつつあるのです。次章では、QMS構築と運用で有効的なデジタルツールをご紹介します。
効率的なQMS(品質マネジメントシステム)の構築/運用を実現するデジタルツール
「動画マニュアル」で業務標準化を推進
QMSの運用における動画マニュアルの有効性
QMS構築時に定めた品質目標を達成するためには、作業の品質や生産性が担保された「標準作業」を、如何にして製造現場の標準として落とし込めるかがカギを握ります。
一方で、標準作業をOJTや座学のような口頭ベース、文書形式のマニュアルや手順書で共有しようとすると、以下のような課題が生じやすいです。
- トレーナーに教育工数がかかり、生産活動に割く時間が減ってしまう
- トレーナーによって言っている内容が異なり、作業者の混乱を招く
- マニュアルや手順書の作成/更新が追い付かず、標準作業の共有が進まない
- 文字や写真のような二次元的な情報では、三次元的な動きを伝えにくい
結果的に、教育不足/理解不足による標準作業の不遵守を招き、品質目標の達成を難しくしてしまいます。動画マニュアルであれば正しい内容で一度作成してしまえば、トレーナーに負担をかけずに「動き」を視覚的に分かりやすく伝えられます。
動画と聞くと『編集が難しそう…』と感じるかもしれませんが、誰でもかんたんに動画マニュアルを作成/活用できるツールがtebiki現場教育です。
動画マニュアルをかんたんに活用できるのは「tebiki現場教育」
かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」は、製造現場で使われる作業手順書や作業指示書などの、いわゆる「マニュアル」を動画で分かりやすく伝えることを目的としたツールです。
▼「tebiki現場教育」サービス紹介動画▼
動画マニュアルは、QMSの規格の1つであるISO9001で要求されている「プロセスの運用を支援するための文書化した情報」に該当します。そのため、効率的に文書の作成や更新できる効果が期待できます。実際、tebiki現場教育を活用したことで、作業手順書の作成工数が紙ベースの1/3まで削減された事例もあります。
また、ISO9001の要求事項として「力量管理」もありますが、tebiki現場教育ではスキル管理(スキルマップ)機能を搭載し、管理者が従業員のスキル保有状況をかんたんに可視化することが可能です。
具体的なtebiki現場教育の搭載機能やプラン、導入効果については以下のリンクをクリックして概要資料をご覧ください。
「デジタル現場帳票」で品質目標の状況を可視化
QMSの運用におけるデジタル現場帳票の有効性
QMS構築時に定めた品質目標は、基本的には定量的な情報です。そのため、データとして状況を可視化し達成状況を計測することが必要です。
製造現場の生産状況や不良数を確認する手段として、製造日報のような現場帳票を用いられることがある一方で、以下のような課題が生じやすいでしょう。
- 現場帳票が日々膨大に発生し、管理者が1枚1枚目視で確認と承認をする手間がある
- 記入ミスを発見したら作業者に直接確認する手間が生じる
- 紙の現場帳票からExcelに集計/転記する手間がある
- Excelやマクロでデータ分析できる人が属人化する
このように品質目標の進捗状況のような、製造現場のデータを可視化するだけで管理者に大きな負担を生じます。QMSの本質は「品質向上を通じた顧客満足度向上」であるものの、分析までの手間からその先の改善活動につなげられないといった状況に陥るでしょう。
現場帳票をデジタル化することで、このような集計/転記作業を大幅に効率化することが可能です。また、記録されたデータが管理図のような形で自動で可視化されるツールが「tebiki現場分析」です。
現場帳票をかんたんにデジタル化できるのは「tebiki現場分析」
かんたんデジタル現場帳票「tebiki現場分析」は、製造現場の帳票を手間なくペーパーレス化し、紙の現場帳票で起きていた課題を解消できるツールです。
紙ベースの場合、配布/記録/承認/集計/分析と多くの工数を必要としますが、tebiki現場分析であればスマートフォンやタブレットのような端末上で記録されたデータを、リアルタイムで管理者が確認/承認できます。記録された定量的なデータは自動計算できるだけでなく、管理図やパレート図などグラフ機能があるため、確認段階で現場データを瞬時に可視化して分析を行うことが可能です。
tebiki現場分析を活用したことで、「現場帳票の集計時間が1日2時間から1分に削減された」「設備の異常傾向を即時に検知して不良品発生を未然防止できた」という事例もあります。
tebiki現場分析の具体的な機能やプランなど、サービスの詳細は以下をクリックして概要資料をご覧ください。
>>かんたんデジタル現場帳票「tebiki現場分析サービス資料」を見てみる
【補足】QMS(品質マネジメントシステム)の内部監査を行う場合
QMSでは内部監査を行うことが要件となっています。ここでは、内部監査の方法と内部監査員の認定について解説します。
内部監査で見るべき点は?主なチェックリスト項目と方法
QMSの内部監査は、適合性と有効性の2つの側面から評価します。適合性とは、ルールや手順が守られているかを確認することで、以下のようなチェック項目が含まれます。
▼適合性のチェック項目一覧
- 文書と記録:品質マニュアルや規定が規格要求事項を満たすか。記録が正しく作成・保管されているか。
- 目標の設定:具体的な品質目標が設定され、達成に向けた計画が策定されているか。
- 業務プロセスの準拠:各部門が、決められたルールや手順に従って業務を行っているか。
- 機械や設備の管理:作業に使う工具や機械が決められた間隔で点検・校正されているか。
- 教育・訓練:担当者が必要な教育や訓練を受け、業務を行う能力を備えているか。
- 変更管理:製品設計、手順、プロセスに関する変更が記録され、適切に管理されているか。
- 法規制や顧客要求:製品やサービスが関連する法規制や顧客要求を満たしているか。
一方、有効性とは、ルールを守ることで成果や効果が出ているかに焦点を当て、以下のようなチェック項目が含まれます。
▼有効性のチェック項目一覧
- 品質目標の達成状況:各部門が目標に向けたKPIをどの程度達成しているか。
- 不適合と是正処置:不適合に対して是正処置が適切に実施され、その効果が確認されているか。
- 顧客満足度:顧客満足の向上が見られ、クレームが減少しているか。
- 改善活動の成果:生産性向上やコスト削減など、改善活動が具体的な効果を上げているか。
上記のようなチェックを行うためには、以下の方法で確認を行います。
- サンプリング:製品や記録を抜き取り、規格や基準を満たしているかを確認する。
- ヒアリング:従業員が手順や方針を理解し、実行しているかを確認する。
- 現場観察:作業現場を直接観察し、手順書や規定どおりに実行されているか確認する。
内部監査員の資格基準や研修の方法
内部監査員に必要な資格は不要であるため、実施が必要な試験や資格維持に必要な取り組みはありません。一方で、内部監査員になる従業員には以下のようなスキルがあると望ましいです。
- ISO規格の理解:ISOの規格要求事項を理解していること。
- 業務内容の理解:監査対象となる部門の業務を理解していること。
- 監査手法の知識:内部監査の計画、実施、報告、フォローアップの基本的な流れを理解していること。
- コミュニケーション能力:現場担当者や管理者とのインタビューをスムーズに行い、適切な情報を引き出せること。
第三者機関の外部審査では、内部監査員の力量をどのように判断しているかをよく聞かれます。
外部講習を受講することで「内部監査員認定証明書」や「内部監査員養成講座修了証明書」などの証明書が発行されるので、その証明書を持って「内部監査をするスキルがある」とみなしたり、知識を習得した従業員が講師となり、社内で講座を開催し、テストを実施するなどして社内資格認定とすることも可能です。
いずれにしろ、実務経験を継続し、監査回数を重ねることでスキルを向上させていくことが重要です。
まとめ
QMS(品質マネジメントシステム)は、組織全体で顧客満足を向上させる仕組みであり、書類だけ作れば良いというものではありません。QMSを効果的に運用するためには、PDCAサイクルを軸にした継続的な改善が重要であり、その成功には従業員全員の協力と参加が欠かせません。
構築の際には、業務に即した柔軟な設計が必要であり、ISO規格や組織特有のルールに準拠することで、顧客の信頼を獲得するだけでなく、組織全体の成長や利益拡大にも寄与する強力な手段となり得ます。
QMSを効率的に運用する手段として、デジタルツールを活用することもおすすめです。「動画マニュアル」であれば業務標準化を、「デジタル現場帳票」であれば品質目標の状況可視化を少ない負担で行えます。
かんたんに動画マニュアルやデジタル現場帳票を活用できる、tebiki現場教育とtebiki現場分析のサービス概要は以下の画像をクリックしてご覧ください。