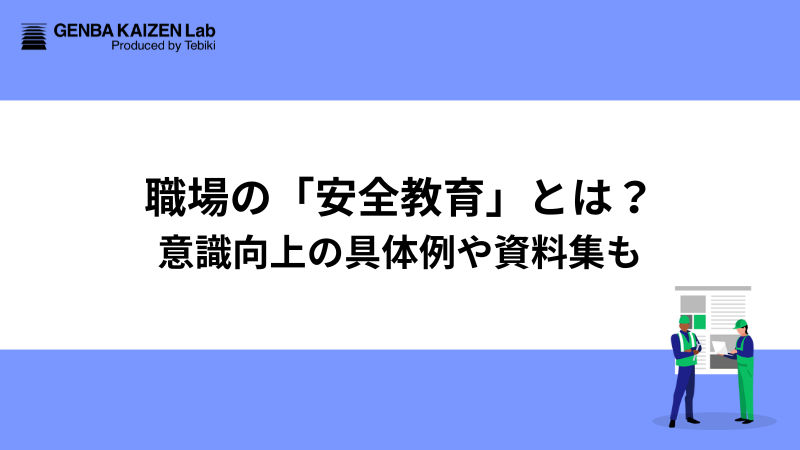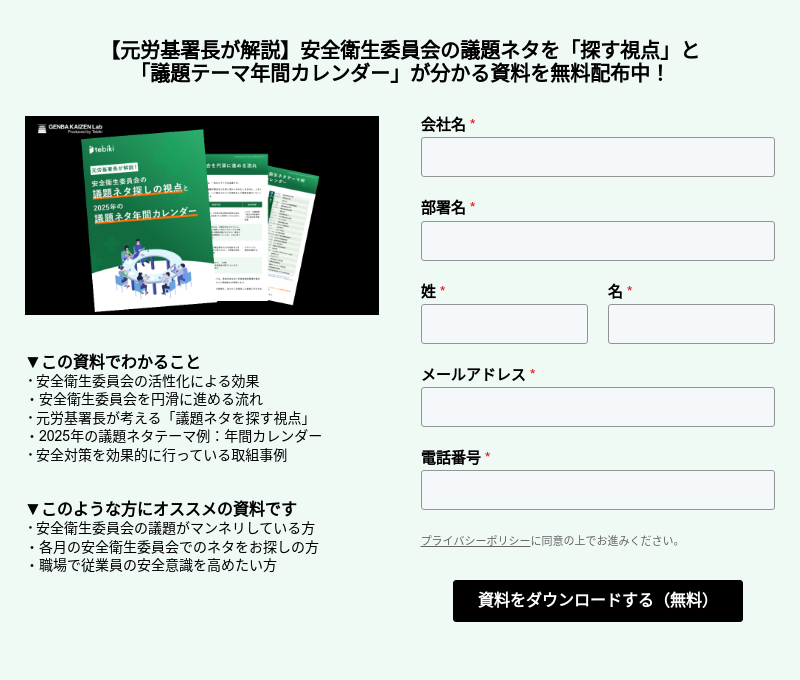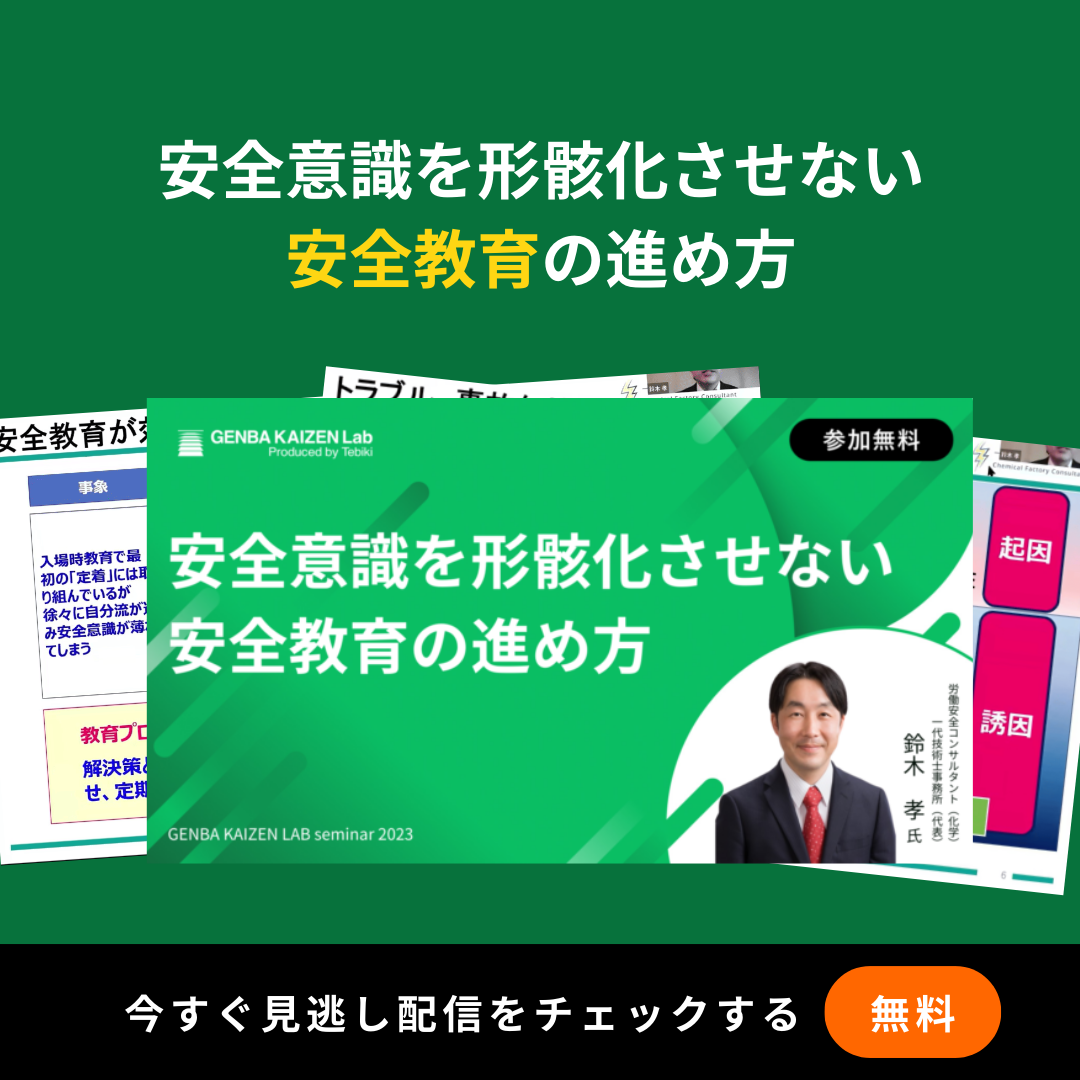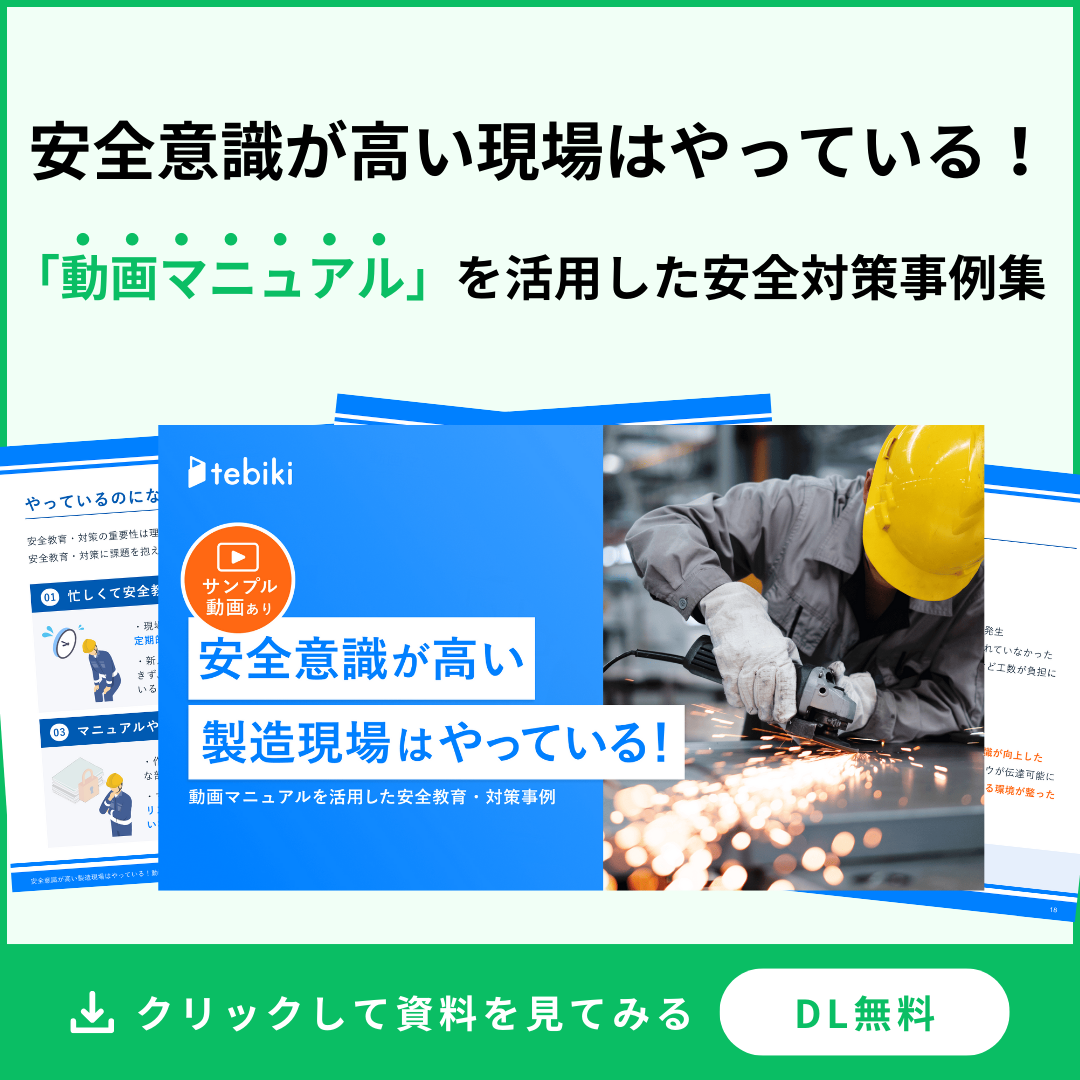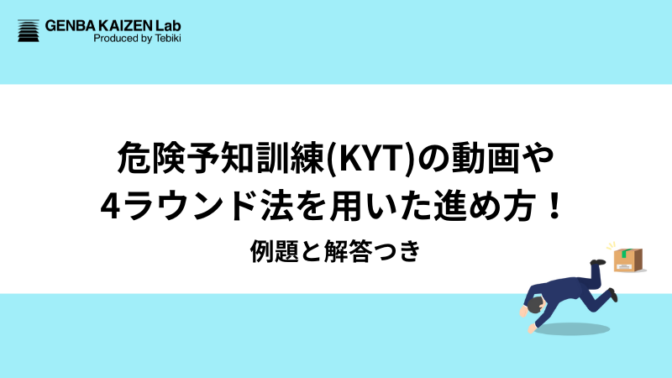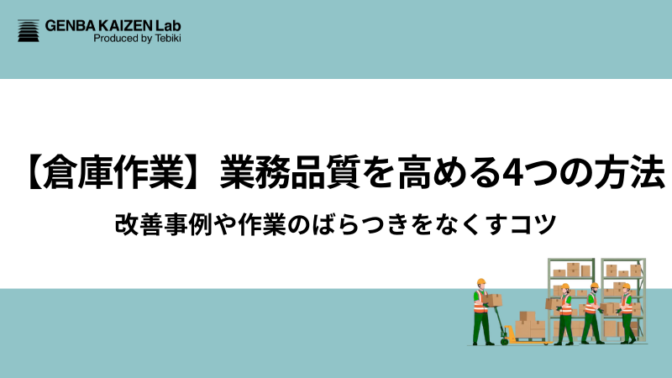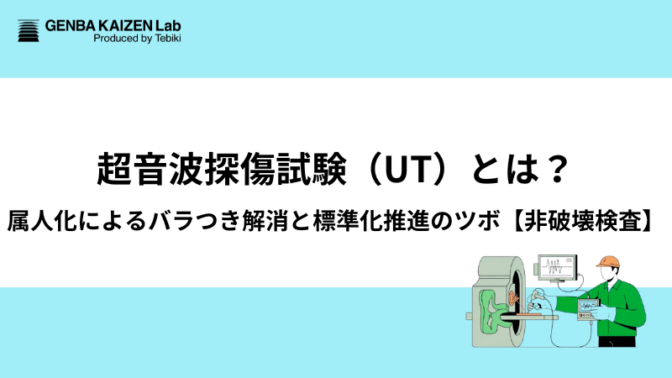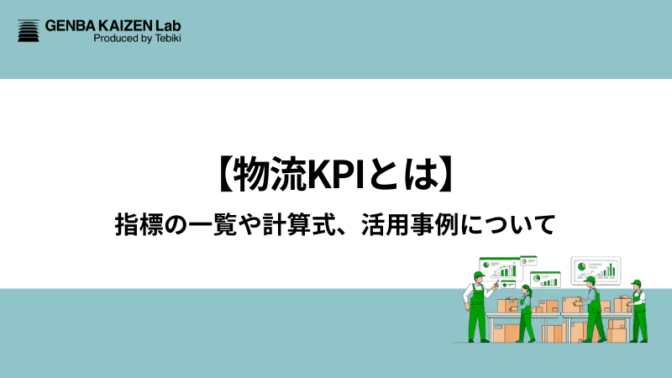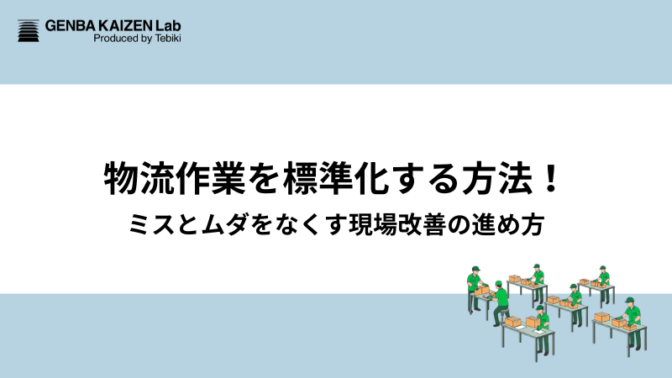かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を展開する現場改善ラボ編集部です。
安全教育とは、「安全衛生に関する知識や技術を労働者に伝えるための取り組み」です。
本記事では、職場での安全教育とはどのような取り組みを指すのか、具体例を挙げながら解説します。安全教育に使える資料集もご紹介しますので、従業員の安全を守るために参考にしていただけますと幸いです。
目次
安全教育とは
職場における安全教育とは、労働者に対して、安全衛生に関する知識や技術を伝え、実践するための教育を指します。
厚生労働省によると、「事業者は、労働者(常時、臨時、日雇等雇用形態を問いません)を雇い入れたとき、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行う必要があります」と定められています。つまり、安全教育は、企業が負うべき義務なのです。
安全教育の具体的な教育例は、『具体例つき!安全教育の種類5選』で後述しています。
現場改善ラボでは、「安全教育の進め方」と「取り組み事例」の解説動画も無料で公開しています。工場長として働いていた専門家による実践的な内容は、以下のリンクをクリックしてご覧ください。
>>専門家による解説動画「安全意識を形骸化させない安全教育の進め方」 を見る
安全教育の必要性と目的
職場における安全教育の目的は、労働者に「安全に関する知識や技能を付与し、事業所での安全活動を活発化させる」ことです。安全教育は、労働災害を防止するための重要な取り組みとして位置づけられ、事業所の安全文化をつくり、労働者の安全意識を向上させるための不可欠な取り組みと言えます。
安全に関する知識や技能を持たずに危険な業務を行う場合、重大な労働災害につながる可能性があります。そのため、実務を行う者/労働者を指揮監督する者が、安全に関する知識や技能を十分に持ち、安全対策を行う必要があるのです。
具体例つき!安全教育の種類5選
安全教育の教育例として、以下の5種類を紹介します。それぞれ具体例も記載していますので、安全教育時の参考にしてください。
- 雇入れ時
- 作業内容変更時
- 危険有害業務従事者への特特別教育
- 職長や監督者への教育
- 安全衛生意識向上のための教育
厚生労働省が発表する労働災害統計では「労働災害の原因の8割はヒューマンエラー」というデータもあるほど(※1)、ヒューマンエラー対策は労災を防ぐ上で重要です。現場改善ラボでは、ヒューマンエラーによる労災を防止する安全教育の解説動画を無料公開中。繰り返し発生するヒヤリハットをなくしたい方は、以下のリンクより動画をご覧ください。
>>専門家解説動画「ヒューマンエラーによる労災を防ぐ安全教育」を見る
雇入れ時
新しい職場環境で業務を開始する際、労働者には新しい職場特有のリスクや安全対策に関する知識を教える必要があります。雇い入れ時に安全教育のプログラムを実施することで、迅速に職場に適応し、労働災害を未然に防げるでしょう。
雇い入れ時の安全教育は、基本的な内容が多いため、「新人が入るたびに同じことを何回も教えている」と考える方も少なくないでしょう。そこで、教育負担を軽減するための手段として動画マニュアルがおすすめです。
日本一のセントラルキッチンを目指す株式会社ロイヤルでは、短期スタッフの教育負担を問題視していましたが、雇入れ時の説明を動画マニュアルに置き換えたことで、教育工数をほぼゼロにすることに成功しています。 さらに、教育のムラをなくせたという効果も得られました。
「安全教育で使われている動画を見たい」「より詳しい効果を知りたい」という方は、以下のリンクをクリックして安全教育の事例集もご覧ください。安全教育のネタの参考にもなります。
具体例
- 会社の安全に関する方針や基準
- 使用する機械や設備の基本操作
- 特定の化学物質の取り扱い方法 など
作業内容変更時
作業内容の変更により、新たな危険要因が生じる可能性があります。新しい作業内容には、未経験の部分が含まれるため、リスクを理解し適切に対応するための教育が必要です。
具体例
- 変更内容の明確な説明
- 新たなリスクの特定と対処法
- 個人用保護具の見直しと使用方法
- 緊急時の対応手順 など
製造業の場合、ヒト/設備/手順/材料といった「4M」の要素が変わるときに労働災害リスクが生じやすいのはもちろん、品質不良といった問題も発生しやすいので何かしら変更があった際には、丁寧に教育を行いましょう。
危険有害業務従事者への特別教育
特定の危険有害業務に従事する労働者には、業務特有のリスクや対策に関する深い知識と技能が求められます。高いリスクを伴う業務の場合、事故防止のため一般的な安全教育に加え、専門的な教育が必要となるからです。これを特別教育と言います。
具体例
- 特定の化学物質の取り扱い方法
- 高圧機械の操作方法 など
社内で特別教育を行う方法や具体的な教育内容を知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
関連記事:【特別教育】社内での実施方法!修了証の自社発行のやり方も紹介!
職長や監督者への教育
職長や監督者への安全教育は、現場で安全を管理し、従業員の安全意識を高めるために不可欠です。安全教育を通じて、職長や監督者が効果的な安全リーダーシップを発揮し、職場の安全文化の強化を目指しましょう。
具体例
- 労働安全衛生法と関連規則の説明
- 安全面におけるリーダーシップの重要性の説明
- 現場の潜在的な危険を特定し、適切な対策を講じる方法 など
安全衛生意識向上のための教育
技術の進化/新たなリスクの発見/業務の変更など、常に状況は変動するものです。そのため、変動する状況に対応し、最新の安全知識を共有しましょう。上記で紹介した4つの安全教育と異なり、全ての労働者に対して継続的に行われるべきと言えます。
具体例
- 最新のリスクアセスメント手法
- 新技術や新設備の活用方法
- さまざまな緊急事態における対応方法(火災/地震/化学物質漏洩など)
- 法令やガイドラインの変更時の対応方法 など
現場に潜む危険性を除去する「リスクアセスメント」の進め方は、以下のリンクから元労基署長による解説で学べます。潜在的なリスクを発見できる手法でもあるため、安全教育としてもおすすめです。
安全教育の実施方法
安全教育を自社で行う場合、以下の進め方で行うのがおすすめです。
- 目的 / 教育内容 / スケジュールなどを決める
- 安全教育資料を準備する
- 実践的なトレーニングを含めた教育を実施する
- 受講者の理解度をテストする
- テスト結果などをもとに次回の改善点を見つけ出す
単に理論を教えるのではなく、実際の作業環境を想定した実践的なトレーニングやシュミレーションも行いましょう。また、常に最新の安全基準と手法を理解させるために、学習を継続させることも重要です。より詳しく安全教育の進め方を知りたい方は、以下のリンクをクリックして「安全教育の進め方」の解説動画をご覧ください。工場長の経験がある労働安全コンサルタントだからこそお伝えできる、取り組みの具体例や実践的な内容は必見です。
安全意識を向上させる教育方法
前述した通り、座学だけではどうしても知識が一方通行になりがちで、従業員の行動変容を促すには不十分な場合があります。そのため、安全意識向上には模擬訓練や危険予知トレーニングなどの体験できる実践的な安全教育が有効です。
▼実践的な安全教育例▼
- 危険な状況を模擬体験させる
- 実際の作業環境で、保護具の装着や機械操作などを教える
- 応急処置や避難誘導などの緊急時の対応手順を教える
- イラストや写真などを使い、作業現場に潜む危険要因を特定する(KYT)
しかし、現実の現場で起こりうる危険な状況をその場で完全に再現することは困難です。そこで効果を発揮するのが、「動画」を活用した安全教育です。
安全教育に「動画」を使う職場が増えている
安全教育を行うたびに、危険な作業や事故現場を再現するのは難しいでしょう。しかし動画を活用すれば、場所や時間に捉われず危険な状況を安全に体験でき、対策も動的に理解できることから、安全意識を効果的に向上させられます。
安全教育に動画を活用している職場も増えており、「安全ルールが守られるようになった」「教育の工数を削減できた」などの効果が出ています。活用されている動画の例としては、以下をご覧ください。
▼安全教育に活用されている動画マニュアル例▼
(音量にご注意ください)
より多くの動画例や活用事例を見たい方は、以下のリンクをクリックして安全教育の事例集もご覧ください。
動画マニュアルを作成するなら「tebiki現場教育」の活用がおすすめです。tebikiは、簡単に動画マニュアルが作れるツールとして人気を集めており、教育管理もできる「現場教育ツール」として開発されました。
特に、安全教育で活用する上で効果的な「tebiki現場教育」の機能は以下の通りです。
- 動画字幕自動生成機能により、作成工数を大幅削減
⇒ 作業音が大きい現場でも活用しやすい - 100カ国語以上の字幕自動翻訳機能がある
⇒ 従業員の母国語で安全について学べる - 閲覧状況やテスト機能で習熟度の可視化ができる
⇒ 安全教育の進捗状況を把握・理解度を定量的に計測可能
一部のプランでは、スキルマップ作成機能も搭載されています。この機能により、安全に関するトピックにおいて、自社の現場で必要な項目の理解度がどれほど進んでいるかを、従業員ごとに把握できます。
今回は、製造業の安全対策で有効な機能をメインにご紹介しました。「他の機能やプランの詳細を知りたい」という方は、以下の画像をクリックしてサービス紹介資料をご覧ください。
動画を使った安全教育の成功事例
tebiki現場教育の導入によって動画マニュアルで安全教育を行い、効果を出している企業事例を3選ご紹介します。より多くの事例やサンプル動画を見たい方は、以下のリンクから事例集をご覧ください。
ASKUL LOGIST株式会社
▼動画マニュアルtebiki活用事例動画:ASKUL LOGIST株式会社▼
ASKUL LOGIST株式会社は、EC専門の総合物流企業として全国15拠点展開しています。長期的な労働人口問題対策として外国籍スタッフを雇用していますが、言語や文化の違いにより、安全教育を行っても伝わらないという問題を抱えていました。
外国籍スタッフのほかにも、障がい者の方の採用も推進している同社。多様な人材を抱える現場において、誰もが理解しやすい教育の方法を模索する中、「動画化した方がわかりやすい」と考え、tebikiを導入いただくことになりました。
安全教育の徹底のために、直近起こった事故事例を動画マニュアルで共有。動画により、現場のリアルな臨場感をつくれて「何が原因」で「どこに注意が必要」かが伝わりやすくなりました。実際に「動画の方が画像で説明するよりも解りやすい」という声も挙がっているそうです。
安全をすべてに優先させることを行動指針としているASKUL LOGISTの事例を詳しく読みたい方は、以下のインタビュー記事をご覧ください。
インタビュー記事:従業員数3,500名超・全国14拠点で動画マニュアルtebikiを活用!
株式会社ロジパルエクスプレス
物流サービスを提供している株式会社ロジパルエクスプレスは、正確な情報が伝わりにくい紙マニュアルによって、安全や品質に影響を与えてしまっていることを問題視していました。実際に、台車から荷物が落ちるといった事故が起きてしまっていたそうです。
そこで、さまざまな動画マニュアル作成ツールを検討したうえで、圧倒的に操作性がよかったtebikiを導入。
導入後、動画を見ておいてもらうだけでも安全品質意識を担保できていると実感いただきました。さらに、感じていただけた効果としては、品質の向上。実際にロジパルエクスプレスのお客様からも「品質が上がっている」と評価をいただいたそうです。また、紙マニュアルと比べて、作成工数と承認までの期間が大幅に削減できたという効果も実感いただいています。
「現場の安全だけでなく、会社全体の安全、品質を高める」ことをミッションに置いている株式会社ロジパルエクスプレスの事例をもっと読みたい方は、以下のインタビュー記事をご覧ください。
インタビュー記事:動画で全拠点の安全品質意識の向上と業務ノウハウの可視化を達成
株式会社メトロール
株式会社メトロールは、工作機械や産業用ロボット向けのセンサという装置の製造販売をしている企業です。
未経験で入社する方が多く、文書や口頭で教育をしても具体的なイメージが伝わらない/トレーナーにより教育内容がバラついているといった教育課題を抱えていました。そこで、作業動作などを伝えるうえで動画が有効だと考え、tebikiを導入。
導入後は、新人向けの安全衛生に関するマニュアルを優先的に作成することに。ほかにも新人向けの操作マニュアルなども作成した結果、教育時間を半分以下にまで抑えることに成功したそうです。
株式会社メトロールの導入経緯や効果をもっと詳しく読みたい方は、以下のインタビュー記事をご覧ください。
インタビュー記事:世界200社以上のメーカーで採用のセンサ製造工程でtebikiを活用し、新人教育と多能工化を推進
安全教育ネタの具体例
実際に起きたヒヤリハット事例の共有
従業員から過去に経験したヒヤリハットを集めて、「なぜ生じたのか?」「再発防止するにはどうすればいいのか?」という原因と対策を話し合うと良いでしょう。実際に社内で起きた身近なヒヤリハット事例を取り上げることで、自分事に置き換えながら安全意識を高められます。
行事を参考にした教育の実施
「9月1日の防災の日」「7月1日から7月7日はフォークリフト安全週間」など、政府や協会が制定している行事に合わせて安全教育を行うことも有効です。行事を活用することで、安全教育をより楽しく、記憶に残りやすいものにすることができるでしょう。
月ごとに安全教育のネタを探してみたい場合は、安全衛生委員会のネタやトピックを月別で見つけられる記事「【2026年版】安全衛生委員会ネタ一覧!工場や建設業で使える“面白い”テーマは?」もあわせてご覧ください。
安全教育に使える行事を一覧でチェックしたい方は、以下のフォームを入力してネタカレンダーをご覧ください。こちらももともとは安全衛生委員会のネタ案用に作成されたものですが、安全教育を行う際にも活用できるため、ネタ案を考える際の参考にしてください。
緊急事態のシミュレーション訓練
火災/地震/化学物質漏洩など、職場で起こり得る緊急事態のシナリオを作成し、シナリオをもとにシミュレーション訓練を行うのも良いでしょう。
訓練では、具体的に以下のような内容を教えるのが有効です。
- 避難経路の確認
- 緊急時の集合場所の確認
- 緊急連絡網の確認
- 消火器の使用方法
- 応急手当
- 心肺蘇生法の訓練 など
シミュレーションを行うことで、従業員の対応力を高められます。訓練後は、振り返りと改善点の共有を行い、従業員の安全意識を高め、緊急事態に対する準備をより強化できるようにしましょう。
安全装備の正しい着用方法
普段習慣として着用している安全装備ですが、従業員全員が正しく着用できているでしょうか? 安全装備は命を守るために重要なので、安全教育の一環として正しい着用方法をレクチャーするのもおすすめです。安全装備の重要性を理解させ、正しい使用方法を習慣付けさせることができるでしょう。
職場の安全教育に使える資料一覧
現場改善ラボでは、職場の安全教育に使える多数の資料を無料でダウンロードできます。以下から現場で使えそうな資料や動画をクリックしてご覧いただき、ご活用ください。
▼安全教育に使えるおすすめ「資料」はこちら
- 安全衛生委員会「議題ネタ探しの視点」と「2026年の議題ネタ年間カレンダー」
- 安全意識が高い製造現場はやっている!安全教育・対策事例
- 食品工場での労災ゼロを達成する従業員の安全意識を向上させる安全教育
▼安全教育に使えるおすすめ「解説動画」はこちら
安全教育と安全衛生の違い
「安全教育」と「安全衛生」は、どちらも職場での安全を確保するために重要な要素です。しかし、それぞれ目的や重視している点に違いがあります。
安全教育は、従業員に対して安全の知識や技術を教えることに重点を置いています。一方で、安全衛生は、従業員の安全と健康を確保するための一連の活動と管理体制で、従業員が安全に働ける環境を整える目的があります。
安全教育と安全衛生の取り組みを徹底することで、労働者の安全と健康を確保し、生産性の向上や業績の安定を望めます。
関連記事:安全衛生とは?法律や資格、必要な体制や教育など基礎知識を解説!
まとめ
安全教育とは、従業員に安全な作業方法やリスクを理解させるための教育のことで、事故やトラブルを防ぐだけでなく、従業員の安全意識を高める目的があります。そして、安全教育にはさまざまな種類があり、雇入れ時の教育から作業内容変更時の教育、特別な業務に従事する者への教育など、状況や目的に応じて適切な教育を行うことが求められます。
社内で安全教育を行う場合は、tebiki現場教育の活用がおすすめです。職場に潜む危険や熟練したトレーナーの技術を広く共有でき、専門的な安全教育にも役立つでしょう。tebikiは、動画を活用した教育ツールとして多くの企業で利用されている便利なツールです。
この記事で紹介したtebiki現場教育の資料は、無料でダウンロード可能です。安全教育に力をいれるためにも、ぜひこの機会にtebikiの資料を無料でダウンロードしてみませんか?