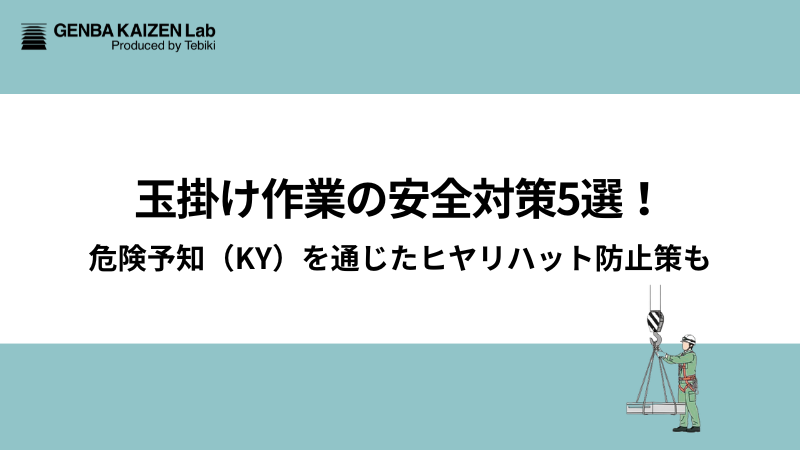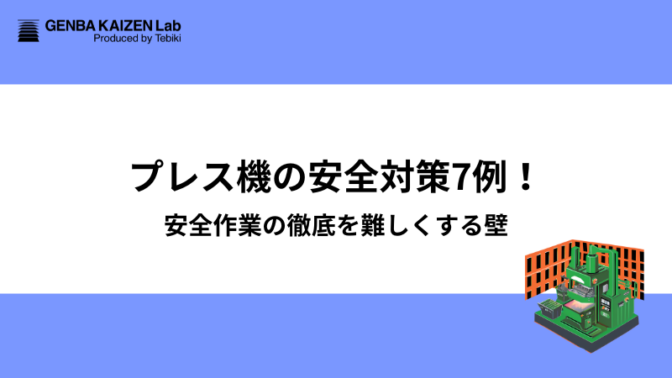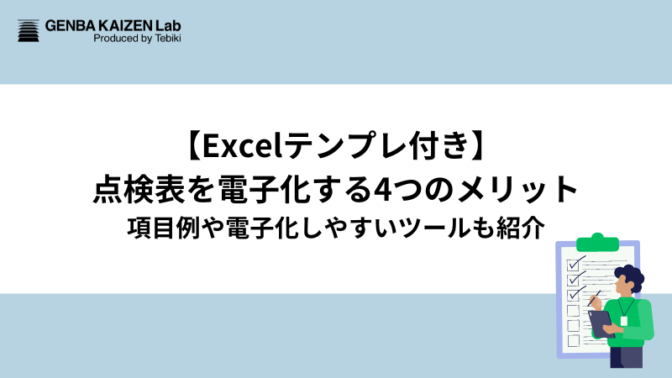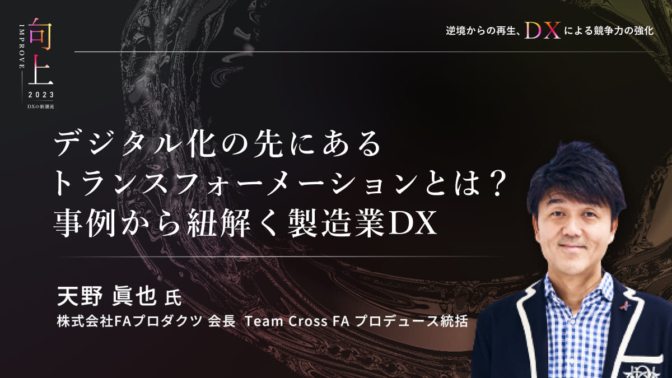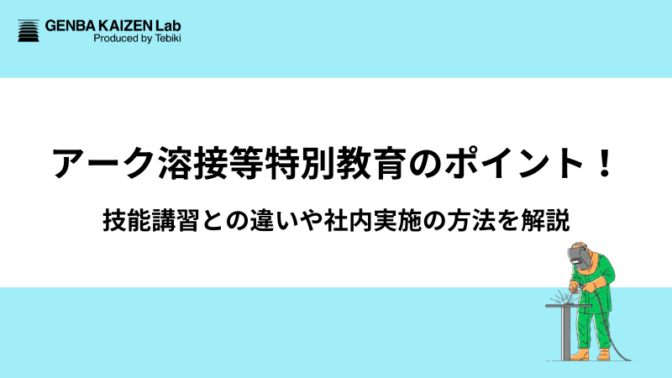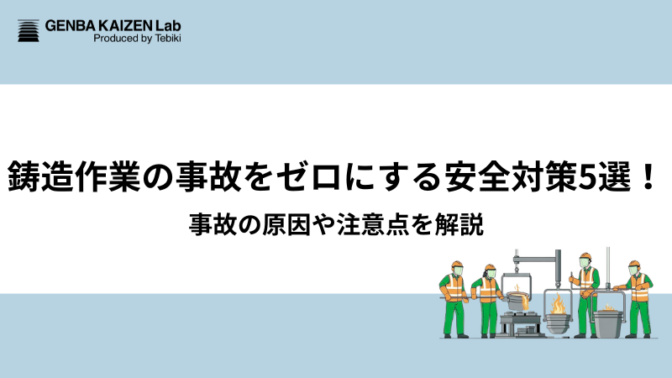工場向け安全対策の動画マニュアル「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
玉掛け作業は、一瞬の油断が命に関わる危険な作業です。事故原因の多くが「確認不足」「退避距離の未確保」「誤った玉掛け方法」といった要素が取り上げられます。
しかし大事なのは、ルールを知りながらも守れなかった「個人の意識」ではなく、事故を未然に防ぐ「仕組みの欠如」にこそ根本的な原因がある点です。
そこで本記事では、実際に工場の勤務経験を持つ筆者が、玉掛け作業の安全対策に加え、作業員一人ひとりが危険を「自分事」として捉えるための方針、つまり安全文化を現場に根付かせる改善指針についても解説します。
なお、安全対策が浸透している現場では「動画マニュアル」による、安全な作業手順の見える化が推進されています。詳しい改善効果や事例は「動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例」をご覧ください。
労災が起きてからでは遅いので、ヒヤリハットで済んでいる現状のうちに安全対策を練ることが鍵を握ります。
>>「動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例」を見てみる
目次
玉掛け作業に潜む危険と安全対策の重要性
玉掛け作業とは、クレーンを用いて重量物を吊り上げ・運搬する危険性の高い作業のことです。吊り荷のバランスが崩れれば、数百kg単位の荷が一瞬で落下し、命に関わる災害につながることもあります。
厚生労働省の統計によると、令和5年の労働災害における死亡者数は墜落・転落が204人、はさまれ・巻き込まれが108人に上ります。これらの災害の多くに、クレーンや玉掛け作業が関与しています。例えば「玉掛けワイヤロープの切断による吊り荷の落下」といった死亡事故は後を絶ちません。
安全対策の重要なところは、技術ではなく意識を徹底させる点にあります。後述しますが、「吊り荷下への立ち入り禁止、333運動(3m退避・30cm停止・3秒確認)の励行、用具の損傷点検といった行動を、全員が「習慣化」できるかどうかが鍵を握ります。
※以下の資料では、危険作業における安全対策の新しい教育アプローチについて解説しています。
補足:厚生労働省が定める安全管理基準と資格区分
玉掛け作業は、労働安全衛生法第61条およびクレーン等安全規則によって「就業制限業務」に指定されています。つまり、厚生労働省が定めた資格を持つ者以外は、玉掛け作業に従事できません。具体的には「玉掛け技能講習」を修了した者、または職業訓練で玉掛け科を修了した者のみが、正式に現場で作業できるとされています(安衛則第221条)。
制度の目的は、重量物を扱う際のリスクを作業者に十分に理解してもらい、安全手順を遵守できる人材を確保することにあります。厚生労働省は、玉掛けに関わる器具や作業方法にも厳しい安全基準を設けており、ワイヤロープは「安全係数6以上」、つりチェーンは「安全係数4〜5以上」、フックやシャックルは「安全係数5以上」でなければ使用してはならないと規定(安衛則第213〜214条)しています。
さらに、使用前点検の実施(第220条)や、不適格なワイヤロープ・チェーンの使用禁止(第215〜218条)など、日常点検を通じた「予防安全」の考え方も法令に組み込まれています。こうした規定は、厚生労働省が定めた労働安全衛生規則に基づき、ヒューマンエラーの防止と危険源の除去を徹底するために設けられた安全基準です。
もっとも、玉掛けは資格を持つだけでは安全は確保できません。法令に沿った点検・確認を習慣化し、現場全体で安全を意識することが重要です。厚生労働省の安全基準は、現場で働く人の命を守るための「最低限の共通ルール」として理解しましょう。
玉掛け作業時に多いヒヤリハット・災害事例
玉掛け作業時に多いヒヤリハット・災害事例を2つ紹介します。いずれも、安全対策の重要性を改めて認識するための重要な事例です。
- 【ヒヤリハット事例】指の挟まれ
- 【死亡事例】玉掛ワイヤロープが切断
【ヒヤリハット事例】指の挟まれ*1
厚生労働省の公式サイトで紹介されているヒヤリ・ハット事例として、クレーンを使用した玉掛け作業中の「指挟み寸前」の事故があります。
資材置き場で2人1組でケーシングを吊り上げていた際、クレーン操作担当者が吊り上げを開始するタイミングを誤り、玉掛け担当者の手がまだ資材に触れている状態で荷が動き出したため、ワイヤーとケーシングの間に指をはさまれそうになりました。
原因は、作業員同士の声掛けや合図が不十分だったこと。特に2人作業では、わずかな認識のズレが重大事故につながります。
対策として、吊り上げ開始時は声だけでなく身振り手振りでも合図を行うこと、そして常に相互確認を怠らないことが重要です。
なお、作業員の不注意や安全意識の低下による「ヒューマンエラー」は、単なる注意喚起や直接指導ではなかなかゼロにできません。ヒューマンエラーが根本的に生じない「仕組み作り」が重要ですが、その本質的な安全教育について解説された資料「ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育」もあわせて参考にすると、安全対策の具体的なヒントが得られると思います。
【死亡事例】玉掛ワイヤロープが切断*2
鋼材(約2.5トン)をクレーンで吊り上げ中、玉掛ワイヤロープが切断し、荷が落下して作業者が死亡する事故が発生しました。原因は、使用していたワイヤロープの強度不足(安全係数6を大きく下回る)と、廃棄基準が明確に定められていなかったこと。
また、玉掛け者とクレーン運転者に必要な技能講習・特別教育が未実施であった点も問題とされました。
対策として、法令で定められた資格保有者による作業の徹底、ワイヤロープの安全係数を満たす製品の使用、長尺物を一本づりしない玉掛け方法の遵守、そして点検・教育を管理する責任者の配置が求められています。
こうした事例は「たった一本のロープの過信」が命を奪うことを意味します。法令遵守と日常点検の徹底こそが必須の安全対策であることがわかります。
※作業員の不安全行動に終止符を打つには、単なる口頭指導や注意喚起だけでは問題の根本を断つことはできません。ヒューマンエラーが起きない仕組みを行動科学の観点で解説している資料「繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網」もあわせてご覧ください。
【死亡事例】下敷きになり死亡*3
玉掛けワイヤロープが切断し、吊り荷の下敷きとなって作業員が死亡する事故が発生しました。クレーンで鋼製収納庫(約4.2トン)を荷下ろし中、安全係数を満たさない細いワイヤロープ(径10mm)を使用していたことが原因で、吊り荷が落下。荷を安定させるために手を添えていた3人のうち、進行方向にいた作業者が逃げきれずに下敷きとなり死亡しました。
労災の背景には、無資格者による玉掛けとクレーン操作、定格荷重を超える吊り上げ、作業指揮者の不在、および関係会社間の連絡不足があり、いずれも基本的な安全対策の欠如が重なった結果です。
再発防止のためには、安全係数6以上のワイヤロープ使用、資格者の配置、作業マニュアルの整備、連絡調整の徹底が必要と言えます。
【死亡事例】玉掛け後につり荷がハッカーから外れて落下*4
角形鋼管をハッカーで玉掛け中につり荷が外れ、作業員が下敷きとなり死亡事故が発生しました。
工場内で2基のホイスト式天井クレーンを使い、長さの異なる角形鋼管2本をハッカーで玉掛けして共吊りしていた場面です。荷を仮置き場へ移動した後、つり荷を吊ったままの状態で被災者が荷の下に入り、下に敷く角材を拾おうとした際、短い鋼管がハッカーから外れて落下。下敷きになり死亡事故となりました。
原因は、ハッカーのつめの引っ掛かりが浅く、短い鋼管が固定されていなかったこと、2基のクレーンを同時に操作する「共吊り」によって荷のバランスが不安定だったこと、さらに作業基準や安全教育が整備されていなかったことにあります。
防止策として、共吊りの禁止、1本ずつの運搬徹底、つり荷下への立ち入り禁止、ハッカー使用基準の明確化、安全教育の強化が挙げられます。
この事例は、「つり荷の下に入らない」「定格荷重を守る」「適正な玉掛け具を選定する」という基本原則から外れた行為をし、労災に至った事例です。
玉掛け作業の安全対策①安全意識を現場に根付かせる現場教育
安全基準や正しい作業手順を定めるのは重要ですが、それよりも重要なのが「浸透」です。玉掛け作業の安全対策が現場に浸透する根幹には「現場教育」があり、安全対策と現場教育は切っても切り離せない関係にあります。
そこでまずは、玉掛け作業の安全対策が形骸化せずに現場で徹底されるための「仕組み作り」の部分について紹介します。
- 誰が見ても同じ解釈ができるマニュアル整備(標準化)
- 誰が教えても同じ教育内容になる体制整備(技術伝承)
- 危険・ヒヤリハットの可視化
※安全対策を浸透させる教育の進め方や、多くの工場で導入されている教育アプローチについて知りたい方は、以下の資料が参考になると思います。
>>「工場の労災ゼロを実現する、安全教育の新常識」を見てみる
誰が見ても同じ解釈ができるマニュアル整備(標準化)
玉掛け作業の安全を確保するうえで「誰が見ても同じ行動を取れる手順書」を整備しているかどうかで、現場の事故発生率は大きく変わります。
視覚的に分かりやすいマニュアルを整備している現場では、安全行動の再現性が高く、危険の芽を日頃から摘み取れる文化が形成されるのに対し、文字中心のあいまいな手順書しかない現場では、作業者ごとに「我流のやり方」が生まれ、ヒューマンエラーやミスに繋がりかねないからです。
例えば、文字で「ハッカーを確実に掛ける」と書かれている手順書があるとします。この場合、以下のような疑問が生まれます。
- どの角度で掛けるのが正しいのか
- 吊り荷の重心はどこにあるのか
- 安全確認のタイミングはいつか
こうした具体像に対して読み手の解釈が異なり、我流のやり方が定着していきます。
一方、視覚的な理解がしやすい手順書(例:動画マニュアルや図)であれば、「読み手によって解釈が異ならない」教育が可能です。
- 正しいハッカー角度(例:60°以内)を図で示す
- 危険な姿勢と安全な姿勢を対比させる
- 実際の吊り作業を動画で見せる
こうした「見るだけで分かる状態」によって、現場全体の判断基準を統一させられ、経験差・言語差・感覚差によるミスを根本的に防ぐことが可能です。
さらに副次的な効果ですが、動画マニュアルや図のマニュアルは、「指摘・是正がしやすい」メリットも存在します。文字マニュアルでは「どこが間違いか」が共有されにくいのに対し、動画マニュアルや図の手順書は、ズレが一目で分かるため教育者も指導が容易になります。
動画マニュアルによる安全教育の詳しい進め方や改善事例は、「 動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例」で詳しく解説しています。以下のリンクをクリックして、堅実な安全対策の一環として参考にしてみてください。
>>「動画マニュアルを活用した安全教育・対策事例」を見てみる
誰が教えても同じ教育内容になる体制整備(技術伝承)
玉掛け作業におけるヒューマンエラーは、教育内容のばらつきが主な原因の1つです。特にOJT教育が中心になる製造業や工場では、指導者によって教え方が異なることが多く、結果的に「人によって作業の進め方が異なる」状況が度々生じます。
こうした状況では、同じ作業をしても安全レベルが統一されず、結果として事故が多発する現場となりかねません。
例えば、玉掛けの安全作業の1つである「吊り荷の重心確認」にて、「作業者Aは目視で済ませ、作業者Bは実際に揺らして確認している」というような作業のばらつきは、教育品質のばらつきが原因の1つです。このようなばらつきがヒューマンエラーを生み、労災や死亡事故につながってしまうのです。
こうした「人によって安全教育の指導方法が異なる」原因を解消するには、「誰が教えても同じ教育体制」の整備が必要です。例えば動画マニュアルや図解は、読み手によって解釈が異なりにくく、安全意識のバラつきも生じにくくなります。
例えば化学メーカーである児玉化学工業株式会社では、現場で働く外国人の多言語化が進んでおり、以前は作業品質のばらつきが生じていました。最終的に同社は「言葉による説明がなくとも、安全な作業手順が解できる動画マニュアル」を整備し、安全教育を推進しています。
▼同社が活用している動画マニュアル▼
※「tebiki」で作成
上のような複雑な業務作業も、動画で手順をおさめれば「誰が見ても同じ解釈」になり、作業品質のばらつき解消→現場全体の安全が守られる仕組みの整備につながります。
※本動画は、製造業の現場教育に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」で作成されています。tebikiのサービス詳細や導入事例についてはサービス資料をご覧ください。
>>製造業向け動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育サービス資料」を見てみる
危険・ヒヤリハットの可視化
安全教育の目的は「危険を自分事として認識させること」です。ところが、現場では経験を積んだベテランほど、「自分は大丈夫」と慢心しやすくなります。こうした慣れが、労働災害の温床になります。
実際に多くの労災調査で、「危険を認識していたが軽視した」「過去も同じやり方で問題なかった」という証言が繰り返されています。こうした思い込みを打破するには「危険を見せる教育=可視化」が効果的です。ヒヤリハット事例や再現映像を映像・写真で共有することで、「なぜその行動が危険なのか」を視覚的・感覚的に理解できます。頭で理解するのではなく、映像として危険を目で見ることで、作業員の安全意識を高められます。
さらに、KY活動(危険予知活動)やヒヤリハット共有掲示板と連携し、現場で起きた生の危険を全員が見える形で共有することも有効です。
つまり、危険・ヒヤリハットの可視化とは「一人で気をつけるのではなく、全員で安全を守る職場をつくること」です。ヒヤリハットを共有し、互いに注意を促し合うことで「安全は個人の意識ではなく、みんなで築くもの」という考えが自然と根づいていきます。
関連資料:イラストでわかりやすい!報告から教育まで行えるヒヤリハット事例・対策集
玉掛けの安全対策②危険予知活動(KY活動)
KY活動(危険予知活動)とは、事前に危険を予測し、予防措置を講じて、労働災害やトラブルを未然に防ぐ活動です。玉掛け作業の安全確保のために、事前の危険予知活動を行いましょう。ここでは具体的に以下の2点について解説します。
- 作業前打合せで確認すべき事項
- KY活動で使える「危険ポイント洗い出し表」
作業前打合せで確認すべき事項
玉掛け作業でのKY活動として、作業前打合せを行い、全員で危険要因を共有するのが良いでしょう。まず確認すべきは「吊り荷の重量・形状・重心・吊り角度」です。こうした危険な情報が正しく把握されていないと、荷のバランス崩壊や落下の危険が高まります。
次に「使用する玉掛け用具の点検結果」と「吊り位置・経路の安全性」を確認しましょう。ワイヤロープの摩耗、フックの変形、シャックルの緩みなどがあれば即交換が原則です。また「合図の統一」も重要です。クレーン操作員と玉掛け者が異なる場合、手信号や無線での合図方法を事前に明確化しておく必要があります。さらに、退避場所・避難経路をチーム全員で確認し、吊り荷の下には絶対に立ち入らないことを徹底します。
別記事の「KY活動(危険予知活動)の進め方は?記入例文やネタ切れ対策を紹介」にある通り、全員で集まり意見を交わす「KYミーティング」は作業前の5〜10分ほどの短時間で構いません。それだけでも安全意識を高め、現場全体のヒューマンエラーを防ぐ効果があります。
KY活動で使える「危険ポイント洗い出し表」
KY活動では、危険ポイントを洗い出す「危険ポイント表」を使うと効果的です。まずは「人」「設備」「環境」「手順」の4要素で整理します。例えば「人」では、慣れや思い込みによる不安全行動、「設備」ではワイヤの劣化や吊り具の不具合、「環境」では風・雨・照明不足など、「手順」では合図漏れや吊り順序の誤りが該当します。
それぞれの要因ごとに「どんな危険があるか」「どう防ぐか」をチームで話し合い、リスト化しましょう。記録はKYシートに残し、次回の作業でも活用できるようにします。危険を「見える化」し、安全意識を定着させましょう。
特に、吊り荷下での作業・声掛け不足・角度超過などのリスクは頻出項目です。KY活動を継続し、チェック表を改善し続けることで、常に改善しようという心構えが作業員に付き、玉掛け作業の安全対策に前向きな作業員が増えていく効果もあるでしょう。
ただし危険予知訓練(KYT)は形骸化しやすく、表面的に実施しても安全意識の向上にはつながりません。現場の安全に直結する本質的なKYTは「動画」が有効で、多くの現場で導入が進んでいます。詳しくは「労災ゼロ!形骸化したKYTから脱却する動画KYTとは」をご覧ください。
>>「労災ゼロ!形骸化したKYTから脱却する動画KYTとは」を見てみる
玉掛けの安全対策③3大原則「333運動」
玉掛け作業では、「3m退避・30cm停止・3秒確認」を徹底させる「333運動」での安全確保が必要です。ここでは具体的に以下の3つの項目を解説します。
- 3m退避・30cm停止・3秒確認の意味と実施手順
- 333運動を徹底するための合図・配置ルール
- 退避距離を確保できない現場での代替策
3m退避・30cm停止・3秒確認の意味と実施手順
333運動とは、玉掛け作業における「距離」「停止」「確認」を数値化した安全ルールのことです。まず「3m退避」とは、吊り荷が動く範囲から作業員が3メートル以上離れることを指します。吊り荷下やクレーンの旋回範囲に立ち入らないことで、落下・激突などの重大事故を防ぎます。
次に「30cm停止」は、吊り上げ時に荷を地面から約30cm上げて一度止め、バランスや傾きを確認する動作です。30cmの段階で不安定な荷重やワイヤの偏りを早期に発見できます。
最後に「3秒確認」は、荷を動かす前に合図者・クレーン運転者・作業員全員が3秒間静止し、安全を確認してから動作を再開することを意味します。333運動を毎回確実に実施することで、ヒューマンエラーを減らすことが可能です。
※作業員の不安全行動に終止符を打つには、単なる口頭指導や注意喚起だけでは問題の根本を断つことはできません。ヒューマンエラーが起きない仕組みを行動科学の観点で解説している資料「繰り返される不安全行動 行動科学から編み出す決定的防止網」もあわせてご覧ください。
333運動を徹底するための合図・配置ルール
333運動を現場で定着させるには、合図と作業者の配置の統一が必須です。まず、クレーン運転者と玉掛け作業者の間で指示を行う「合図者」を明確に決め、他の作業員は原則として合図を出さないようにします。
合図は声だけでなく、手や旗、無線などの視覚・聴覚的手段を併用し、誤認を防ぎます。特に騒音の多い現場では、手信号やライトシグナルの併用が効果的です。
また、合図者は吊り荷の進行方向を見渡せる安全位置に立ち、玉掛け者は吊り荷下を避けて作業しましょう。さらに、退避距離が確保できない現場では、バリケードや床面ラインによる安全区画の設定も有効です。
合図と配置のルールを「現場標準」として共有・訓練することで、333運動の効果を十分に引き出せ、安全対策の意識が現場に馴染むでしょう。
※以下の資料では、危険作業における安全対策の新しい教育アプローチについて解説しています。
退避距離を確保できない現場での代替策
「なかなか退避距離を確保できない…」という現場の方々に向けて以下の5つの大替作を紹介します。
- 吊り荷と作業員の間に仮設バリケード・防護柵・鉄板などの遮へい物を設置
- リモコン操作・無線式クレーン・吊具の遠隔開放装置などを使用
- 床面や柱に退避ラインを設け、限界距離を見える化
- 合図者を吊り荷から離れた安全位置に配置
- 荷の通過経路に人が入る場合は「一時停止・全員退避→再開」の手順を徹底
吊り荷と作業員の間に仮設バリケード・防護柵・鉄板などの遮へい物を設置
狭い現場で3mの退避距離を確保できない場合は、物理的な遮へい物を設置し、万一の落下や揺れに備えることが重要です。例えば、吊り荷と作業員の間に仮設バリケード・防護柵・鉄板パネルなどを設置すれば、直撃や巻き込みを防げます。
遮へい物は、現場ごとに荷の重量・形状・動線に応じて配置し、重りを置いて動かない対策を講じて倒壊防止の固定を徹底しましょう。加えて、作業前に全員で設置状況を確認し、撤去や移動の際も責任者の指示を必ず仰ぐ体制を整えましょう。
リモコン操作・無線式クレーン・吊具の遠隔開放装置などを使用
退避距離を十分に取れない現場では、作業員が吊り荷に近づかずに操作できるリモコン式・無線式クレーンの導入を推奨します。リモコン式・無線式クレーンを使用すれば、作業者は安全圏から荷の移動や旋回を制御でき、落下・衝突のリスクを大幅に減らせます。
また、吊具の遠隔開放装置を併用すれば、荷の開放時に作業員が直接近づく必要がなくなるので、安全です。特に狭所や高所作業では、従来の手動開放よりも安全性と効率が上がります。導入時は、無線通信が途切れないかといった通信の安定性やバッテリー残量の管理など機器の定期点検を徹底しましょう。
床面や柱に退避ラインを設け、限界距離を見える化
退避距離を確保できない現場では、作業エリアの視覚的な区分が有効です。床面や柱に明確な退避ラインを設け、「これ以上近づかない」距離を誰でも一目で分かるようにします。例えば、黄色や赤の反射テープを使い、吊り荷の通過範囲をマーキングする方法が有効です。
さらに、吊り荷下禁止区域や退避位置をピクトサインや注意表示で明示すると、初めて現場に入る作業者でも直感的に理解できます。こうした見える化は、ヒューマンエラーを防ぎ、安全行動を習慣化させる効果があります。定期的にラインの剥がれや視認性を確認し、照明が不足している現場では蓄光テープやLED照明を併用することも推奨されます。
※ヒューマンエラーが根本的に生じない「仕組み作り」が重要ですが、その本質的な安全教育について解説された資料「ヒューマンエラーによる労災を未然防止する安全教育」もあわせて参考にすると、安全対策の具体的なヒントが得られると思います。
合図者を吊り荷から離れた安全位置に配置
退避距離を確保できない場合でも、合図者の立ち位置を工夫すれば安全を維持できます。基本は吊り荷の進行方向が見渡せる位置で、かつ落下・接触の危険がない範囲に立つことです。クレーン運転者が視認できる位置関係を保ちつつ、合図は一貫した手信号や無線で行います。特に障害物が多い現場では、合図者を一人に限定し、他の作業者は補助的な位置にとどめることが望ましいです。
また、吊り荷の真下や旋回軌道内で合図を行うのは厳禁です。定常作業であっても、吊り荷の動線や重心の変化を考慮し、作業ごとに安全な合図位置を確認します。作業開始前に「誰がどの位置から合図を出すか」を全員で共有し、連携ミスを防ぐことが重要です。
荷の通過経路に人が入る場合は「一時停止・全員退避→再開」の手順を徹底
狭い現場では、どうしても人が吊り荷の通過経路を横切る場面が発生します。その際は、一時停止・全員退避して安全確認後に再開という手順を必ず守ることが重要です。
荷が動いている状態での通過は、たとえ短時間でも十分危険です。合図者は作業を中断し、吊り荷を安定させたうえで全員の退避を確認します。その後、再開時には「よし」などの復帰合図を明確に伝え、誤認による再始動を防ぎます。
また、退避完了の確認は声掛けだけでなく、手信号やアイコンタクトも併用すると効果的です。こうしたルールを現場標準手順(SOP)として文書化し、定期的に教育・訓練を行うことで、作業者に安全対策の意識付けができるでしょう。
玉掛けの安全対策④吊り角度・荷重・重心管理の基本知識
玉掛けの安全対策では吊り角度・荷重・重心管理は必須です。ここでは具体的に以下の3点について解説します。
- 原則90°以内・推奨60°の吊り角度の基準
- モード係数と荷重早見表の使い方
- 重心のズレによる落下事故を防ぐコツ
原則90°以内・推奨60°の吊り角度の基準
荷の安定とワイヤーロープの破断防止のために、玉掛けでは吊り角度を正しく保ちましょう。基本原則として、吊り角度は90°以内、推奨は60°以下が安全基準です。角度が広がるほど、ワイヤー1本にかかる荷重が急激に増え、強度限界を超えやすくなります。具体的な計算式は
1本にかかる荷重=吊り荷の荷重 × 張力増加係数 ÷ 玉掛索の本数
です。計算式で求めると、例えば60°であれば荷重の約15%増ですが、90°を超えると倍近くの力が加わります。
吊り角度はスリングの長さや吊り点の間隔で調整できるため、荷の形状に応じて適した角度を選定することが重要です。また、荷が偏る場合は、均等に力が分散するよう吊り位置を調整しましょう。角度管理を怠ると、ワイヤーロープの切断や荷の転倒につながります。
モード係数と荷重早見表の使い方
モード係数とは、吊り方(1本吊り・2本吊り・4本吊りなど)によって変化する荷重分散の補正係数です。玉掛けでは、同じ荷重でも吊り本数や角度によりワイヤー1本あたりの負荷が異なるため、モード係数を使って正確な荷重を算出します。
例えば、60°の2本吊りの場合は係数1.155を掛けて、1本にかかる力を計算します。計算により、ワイヤーロープの強度限界を超えないよう管理できます。また、厚生労働省やメーカーが公開している荷重早見表を活用すれば、現場で迅速に判断可能です。
現場では「経験値で判断」する傾向がありますが、経験に頼るのは危険です。数値化されたデータを使えば、誰でも同じ判断基準で安全な玉掛け作業ができるようになります。
重心のズレによる落下事故を防ぐコツ
吊り荷の重心がずれると、バランスが崩れて荷が傾いたり、スリングが外れる危険があります。落下事故の多くは、重心位置の見誤りが原因です。まず、荷の形状・重量分布を事前に確認し、重心がどの位置にあるかを把握します。長尺物や偏荷重のものは、吊り点を重心よりやや外側に設定し、荷が水平になるよう調整します。吊り上げ前には「30cm停止」で必ず一度止め、バランスを確認してから本吊りに移りましょう。
また、スリングの伸びや吊り具の摩耗も重心ずれを助長するため、使用前点検と吊り位置の微調整を徹底しましょう。さらに、合図者とクレーン運転者が協力して、吊り上げ始めに荷の安定を確認することも必須です。重心管理は「技術」ではなく「習慣」です。吊り上げ時の毎回の確認が、重大事故を防ぐ確実な安全対策と言えます。
玉掛けの安全対策⑤使用前点検と用具管理のチェックポイント
玉掛け作業では、使用前点検を怠ると重大事故につながります。ここでは具体的なチェックポイントについて以下の3点を解説します。
- ワイヤロープ・フック・シャックルの点検項目
- 損傷・変形・摩耗の判定基準と交換タイミング
- 点検記録とチェックリスト活用法
ワイヤロープ・フック・シャックルの点検項目
玉掛け用具の点検を作業前に必ず行いましょう。まずワイヤロープは、素線切れ・変形・キンク・腐食・径の減少などを確認します。特に、1より(撚りの1ピッチ)内で素線の10%以上が切断している場合は使用禁止です。
次にフックは、開口部の広がり・変形・摩耗・亀裂を重点的に確認します。開口が5%以上広がっていれば交換の必要があります。シャックルでは、ピンのゆるみ・ねじの摩耗・変形・き裂の有無を確認します。ピンが固着して回らない場合も危険信号です。
点検は「目視+手触り」で異常を感じ取ることが大切です。点検を怠ると、吊り荷落下や挟まれ事故につながりかねません。厚生労働省のクレーン等安全規則(第220条)でも、使用前点検の実施義務が明確に定められているので、必ず使用前点検を行いましょう。
損傷・変形・摩耗の判定基準と交換タイミング
玉掛け用具は、目立つ損傷だけでなく「限界摩耗」も危険です。ワイヤロープは、径の減少が公称径の7%を超えたら即廃棄しましょう。また、腐食や素線の錆が進行している場合も強度低下の原因になります。つりチェーンは、1リンクの断面径が10%以上減少したら交換が必要です。
フックやシャックルは、変形や開口部の広がり、き裂があるものは使用禁止です。亀裂が見えなくても、ハンマー打音や磁粉探傷などで内部損傷を確認することが望ましいです。さらに、荷の種類や使用頻度によっても交換時期は異なります。特に屋外や高温環境では、金属疲労や劣化が早まるため、定期交換をルール化することが重要です。
点検記録とチェックリスト活用法
安全対策を徹底させるために、点検結果を「記録」として残しましょう。玉掛け用具の点検表には、日付・担当者・点検箇所・異常の有無を明記します。異常が見つかった場合は、即時に修理・交換の記録を追記し、再発防止に活用しましょう。特に、ワイヤロープ・フック・シャックルの使用回数や交換履歴を残しておくと、寿命の把握が容易になります。
また、チェックリスト形式にすることで、点検漏れを防げます。項目を「目視」「触診」「動作確認」に分け、誰でも同じ基準で確認できるようにしましょう。さらに、月次点検や年次点検など、定期点検スケジュールをカレンダー化することも有効です。記録をデジタル管理すれば、過去の不具合傾向を分析し、今後の新人作業員や若手社員への安全教育にも活かせます。
危険な作業の安全対策に成功している企業事例
危険作業が飛び交う現場の安全対策に成功している、製造業の2つの事例を紹介します。玉掛けの事例ではありませんが、玉掛け作業と同様にわずかな判断ミスが事故につながる企業の事例のため、安全対策のヒントが得られると思います。
- コスモ石油株式会社:安全な手順やヒヤリハットを動画で可視化
- トーヨーケム株式会社:危険な作業手順による事故を映像で再現・周知
コスモ石油株式会社:安全な手順やヒヤリハットを動画で可視化
コスモ石油株式会社は、国内有数の石油精製・販売企業であり、堺製油所は京阪神エリアに燃料を安定供給する重要拠点です。同社にとって「安全第一」は経営の最優先課題であり、火災や爆発のリスクを抱える石油プラントでは、生産効率よりも事故防止を優先する姿勢を徹底しています。
しかし、従来の教育は紙マニュアルやOJTに依存しており、専門用語が多く動きのある作業を正確に伝えきれないという課題を抱えていました。新人や中途採用者の増加により教育負担が膨大化し、労災事例の周知や設備管理の習熟に時間がかかる問題も顕在化していました。
そこで同社が導入したのが動画マニュアル(tebiki現場教育)です。
映像を通じて複雑な作業や労災事例を視覚的に共有できるようになり、安全教育の効率化と再現性が向上しました。さらに協力会社との安全会議でも災害事例を動画で周知し、現場レベルの安全意識を高める効果を実現。結果として教育コスト削減と安全対策の定着を同時に進められています。
>>工場向け動画マニュアル「tebiki現場教育」のサービス資料はこちら
トーヨーケム株式会社:危険な作業手順による事故を映像で再現・周知
トーヨーケム株式会社は、東洋インキグループの中核企業としてポリマーや塗加工事業を担い、接着剤や機能性フィルム、医療製品などをグローバルに展開しています。
同社の課題は、若手社員への技術伝承が進まず、属人的なOJTに依存して教育の質にムラが生じていたことです。特に、頻度の低いメンテナンス業務では「○○さんしかできない」という属人化が常態化し、業務効率や安全性に影響していました。
そこで同社が導入したのが動画マニュアル(tebiki現場教育)です。従来は紙マニュアルで半日以上かかっていた手順共有が、動画化によって1時間程度に短縮され、作成工数は約1/2に、OJT時間も約2/3に削減されました。
さらに、業務を映像で可視化することで習熟度の均一化が進み、教育のバラツキや不安全行動のリスクも低減。タブレットで現場から即座に動画を確認できる環境が整ったことで、安全意識の底上げにもつながりました。結果として、教育レベルを統一し、属人化を防ぎながら安全対策を行うグローバル企業として市場をけん引しています。
>>工場向け動画マニュアル「tebiki現場教育」のサービス資料はこちら
結論:安全対策の鍵を握るのは「現場教育」と「自分事化」
玉掛け作業の安全対策の最大のポイントは、現場教育の徹底と安全意識の自分事化です。法令や333運動、吊り角度の管理などは重要ですが、最終的に安全を確保するのは「人」の行動です。
マニュアルの標準化によって誰が見ても同じ作業ができる体制を作り、教育内容を統一することで安全知識を正しく継承できます。さらに、ヒヤリハットや災害事例を可視化し、危険を「自分のこと」として感じさせる教育が必須です。安全は教えるものではなく、現場全員で守る文化として根付かせることが、本当の安全対策です。
▼出典
実際、厚生労働省が公表した「厚生労働省令和5年労働災害発生状況」では、令和5年度にて、墜落・転落による死亡が204人、はさまれ・巻き込まれが108人と報告されており、こうした事故の多くがクレーン・玉掛け作業中の労災と考えられます。
また、厚労省の「職場のあんぜんサイト」に掲載された事例では、玉掛けワイヤロープの切断により吊り荷が落下し、作業員が下敷きになって死亡した事故(参考元:厚生労働省・職場のあんぜんサイト, 事例No.63, 101260)などの報告がありました。こうした事故のほとんどが「確認不足」「退避距離の未確保」「誤った玉掛け方法」という、安全対策の不徹底が要因です。
出典
*1:厚生労働省「職場のあんぜんサイト」【作業員二人でクレーンを用いてケーシングの吊上げ作業中、吊上げ開始のタイミングが合わず、手の指をはさまれそうになった】
*2:厚生労働省「職場のあんぜんサイト」【鋼材をつり上げ中、玉掛ワイヤロープが切断し、荷を支えていた作業者が死亡】
*3:厚生労働省「職場のあんぜんサイト」【玉掛けワイヤロープが切断し吊り荷の下敷きになり死亡】
*4:厚生労働省「職場のあんぜんサイト」【被災者は、角形鋼管2本をハッカーで玉掛けし、移動させていたところ、つり荷がハッカーから外れて落下し、下敷きになった】