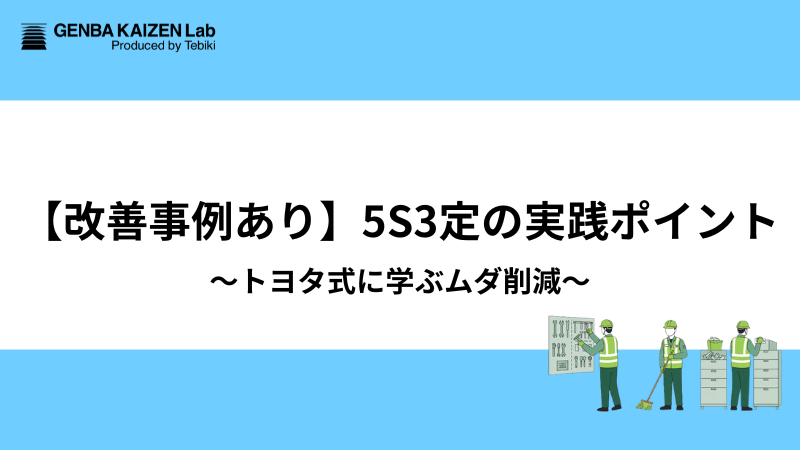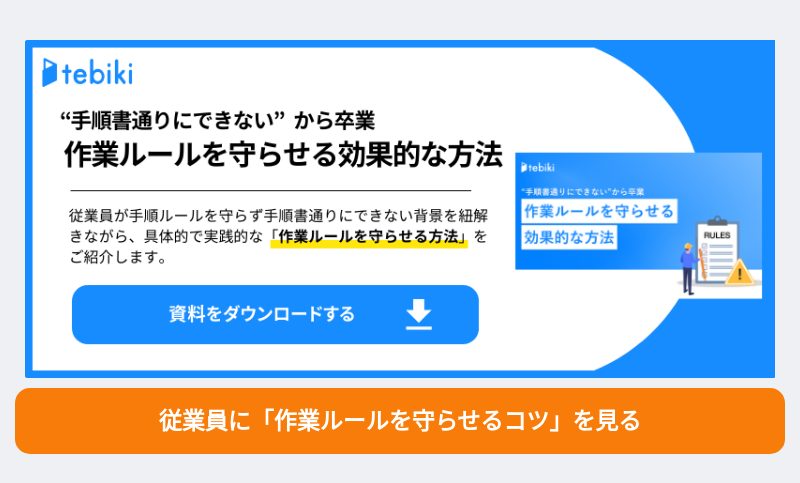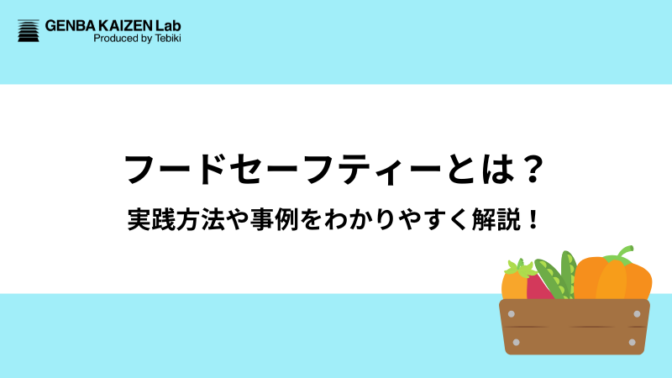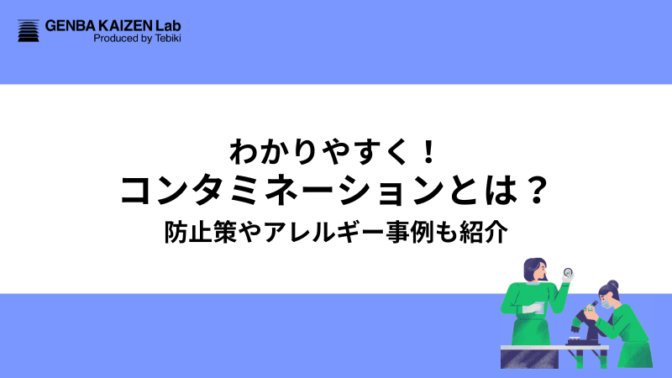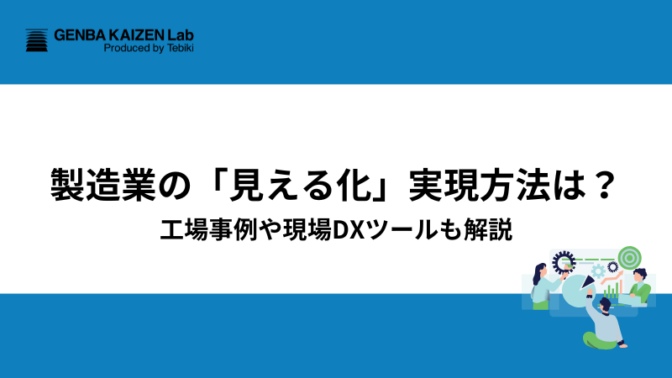かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki」を展開する現場改善ラボ編集部です。
5S活動の「整頓」を誰でも再現可能なレベルに引き上げる手法、それが「5S3定(定位・定品・定量)」です。単なる整理整頓ではなく、作業効率・品質・安全性・教育のすべてに直結する重要な考え方として、多くの現場改善に導入されています。
この記事では、5S3定の基本から実践ポイント、定着させるための仕組みづくり、さらには成功事例までを体系的に解説します。形骸化しない5S活動を目指す方はぜひ参考にしてみてください。
目次
5S3定とは?5S活動における「整頓」を徹底する基本
5S活動を成功させるためには、「整頓」の徹底が必要です。整頓を誰でも再現可能にする仕組みが「3定」の考え方であり、ここでは具体的に以下の3点について解説します。
- 5S活動のおさらいと「整頓」の位置づけ
- 3定の構成要素「定位・定品・定量」とは
- 5S3定と「3T」の関係性
※5Sに基づいた具体的な現場改善の指針が知りたい方は、無料セミナー「改善の急所を読み解く、5Sを活用したこれからのものづくり」を視聴してみてください(下の画像をクリック)。
5S活動のおさらいと「整頓」の位置づけ
5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)は、生産性や安全性を高める職場改善の基本です。
活動の第一歩は、混同されがちな「整理」と「整頓」を明確に区別することです。まず「整理」で不要なモノを徹底的に処分し、その上で「整頓」によって必要なモノを誰もがすぐに取り出せるよう配置します。
そして、この「整頓」を誰でも再現可能なレベルで徹底する具体的な手法が「3定(定位・定品・定量)」です。「どこに(定位)」「何を(定品)」「いくつ(定量)」置くかを明確に定めることで、探すムダをなくし、常に整った状態を維持します。
3定は、5S活動の成果を左右する「整頓」の要であり、現場改善の土台となる考え方です。
5S活動の全体像をより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
関連記事:「5S活動」とは何をする?進め方や目的、アイデアも解説
3定の構成要素「定位・定品・定量」とは
整頓を具体化・徹底する手法が「3定」です。3定は、モノの位置・種類・量をルール化して管理する以下の3つの要素から成り立ちます。
- 定位
- 定品
- 定量
それぞれ具体的に解説します。
定位
「定位」とは、置き場所を前もって決めておく活動のことです。定位は、モノに「住所」を与えるという考え方で、誰が見てもどこに何があるべきかが一目でわかる状態をつくることを目的としています。
具体的には、工具棚に工具の形をかたどった形跡表示を行ったり、床に区画線テープを貼ってパレットや台車の定位置を示したりします。
また、棚には「○○保管場所」などの住所表示を行うことで、配置ミスや持ち出し忘れを防げます。定位を徹底することで、探すムダをなくし、作業効率と職場の秩序が大きく向上します。
定品
「定品」とは、決めた場所に置くべきモノを明確化する活動のことです。
整頓では、どの場所にどの商品や備品を置くかをルール化することが重要で、整頓によりモノの取り違いや置き間違いを防止できます。
具体例としては、棚や引き出しにモノの名前や型番を明記したラベルを貼る、写真付きの表示を活用して視覚的に判断しやすくするなどの工夫が挙げられます。
定品を徹底すれば、誰でも同じように作業できる環境が整い、教育時間の短縮やミスの削減にもつながります。品目数が多い現場では、カテゴリごとの色分けや番号管理も有効です。
定量
「定量」とは、前もって決めた場所に置くべきモノの量を管理することを意味します。最大在庫量と最小在庫量(発注点)を設定することで、過剰在庫によるスペースの圧迫や、欠品による作業の停止といった問題を防ぐことが可能です。
例えば、棚に在庫の段数を明示したり、斜線やラベルで適正量を示したりすることで、誰でも簡単に在庫状況を判断できるようにします。定量管理が徹底されると、在庫のムダが減るだけでなく、発注判断も迅速になり、全体の業務効率やコスト管理に良い影響を与えられるでしょう。
5S3定と「3T」の関係性
「5S3定」は、5S活動の「整頓」を実現するために導入される手法で、定位・定品・定量という3つの要素で構成されます。一方で、3定を「3T」と呼ぶこともあり、それぞれの読み方Teii「定位」Teihin「定品」Teiryo「定量」の頭文字「T」を取った略称で、主に企業の現場やコンサルティングの現場で使われる表現です。
つまり、「3定」と「3T」は内容としては同じ概念を指しており、呼び方が異なるだけです。この記事では「3定」という呼称を使用していますが、「3T」も同様の意味であることをご理解ください。呼び方に違いはあっても、目的は「整頓の標準化と徹底」。職場の誰もが理解し、迷わずモノを扱える環境をつくることが、5S3定=5S3Tの本質です。
なぜ5S3定が重要なのか?得られる5つのメリット・効果
5S3定を徹底すると、現場のムダが減り、生産性・安全性・教育効率など多方面に好影響をもたらします。ここでは代表的な以下の5つのメリットを解説します。
- 探すムダの削減による生産性向上
- 在庫管理の適正化と欠品・過剰在庫の防止
- 作業ミスの削減と品質の安定
- 安全性の向上と労働災害の防止
- 多能工化・新人教育の効率化
※5Sに基づいた具体的な現場改善の指針が知りたい方は、無料セミナー「改善の急所を読み解く、5Sを活用したこれからのものづくり」を視聴してみてください(下の画像をクリック)。
① 探すムダの削減による生産性向上
5S3定の実践により、モノの「置き場所・モノ・量」が明確になり、探す時間が大幅に削減されます。作業者が必要な備品や部品を瞬時に見つけられる環境は、作業の中断やストレスを減らし、本来注力すべき作業に集中できるようになります。
特に作業の段取りが多い現場において顕著で、生産リードタイムの短縮も期待できるでしょう。毎日数分の探すムダが積み重なると、1か月・1年で膨大な工数になります。
5S3定は、ムダをゼロに近づける現実的で効果的な手段です。
② 在庫管理の適正化と欠品・過剰在庫の防止
5S3定の「定量」は、在庫の最小量・最大量を明確にし、現場における在庫状況の見える化を実現します。定量により、誰が見ても現在の在庫が適正かどうかを瞬時に判断でき、発注忘れや二重発注といったミスを未然に防げます。
また、過剰な在庫はスペースを圧迫し、キャッシュフローを悪化させる原因にもなりますが、定量を守ることでこうしたリスクを回避することが可能です。結果として、在庫の最適化による業務効率の向上と、経営面でのムダ削減という二重のメリットが期待できます。
③ 作業ミスの削減と品質の安定
定品管理を通じて「置くモノ」を明確にすることで、現場における取り間違いや誤使用といったヒューマンエラーを防止できます。
例えば、似たような部品が混在する工程では、部品の名前や番号、形状を明示したラベルや写真での表示が有効です。こうした活動をすれば、誰が作業しても間違いが起きにくい仕組みができ、結果として製品やサービスの品質が安定します。
また、作業ルールが守られることで、工程全体のばらつきが減り、品質トラブルによる手戻りやクレームのリスクも大幅に低減できるでしょう。
作業ミスやヒューマンエラーの対策については、以下の記事でより詳しく解説しています。
関連記事:ヒューマンエラー対策13選!原因や製造業の対策例【種類や多い人、有名事故、トヨタの考え方】
④ 安全性の向上と労働災害の防止
5S3定の徹底により、モノが定位置に管理され、通路や作業エリアに余計なモノが放置されることがなくなります。5S3定により、つまずきや転倒といった物理的な事故を防ぐとともに、重量物が適切な位置に保管されることで落下や衝突といったリスクも軽減されます。
また、非常時の避難経路が確保されることで、緊急時の対応力も向上。見た目の整った職場は安全意識を高める効果もあり、災害ゼロを目指す安全文化の醸成も実現できるでしょう。
安全と整頓は、常に一体で考えるべきです。
職場の安全性を高める具体的な取り組みについては、以下の記事も参考になります。
関連記事:工場の安全対策10選と好事例を解説!製造業の安全宣言例も紹介
⑤ 新人が一人前になるまでの期間短縮
5S3定が徹底された現場では「モノがどこに、いくつあるか」が一目でわかるようになっているため、初めて作業に関わる人でもすぐに業務を始めることが可能です。
5S3定の徹底により、新人教育の時間が短縮されるほか、応援要員や多能工が複数の工程を担当する際の立ち上がりもスムーズになります。
また、整頓された環境は見て覚えられるため、マニュアルに頼らずとも自然と標準作業に近づく効果があります。
5S3定を実践するための8つの重要ポイント
5S3定を成功に導くには、単なる形式的な実施ではなく、現場に根付く工夫が欠かせません。ここでは、形骸化を防ぎ、成果を生むための以下の8つの実践ポイントを紹介します。
- 対象エリアと担当者を決め、スモールスタートする
- 大前提として「整理」を行い、不要なモノを処分する
- 現場の作業者が主体となり、全員参加でルールを決める
- 使いやすさ(動線)を最優先に考え、無理のないルールにする
- 「目で見る管理」で置き場・モノ・量を明確にする
- 目的と効果を共有し、活動の意識を高める
- 定期的な見直しと改善を継続する
- トヨタの3定管理に学ぶ「なぜ」の徹底
ポイント1:対象エリアと担当者を決め、スモールスタートする
5S3定を最初から全社一斉に展開すると、混乱や負担が大きくなり失敗しやすくなります。まずは一部のエリアや特定の工程を「モデルライン」として選定し、担当者と責任者を明確にした上でスタートするのが理想です。
スモールスタートなら小さな成功体験を積みやすく、改善活動の有効性を現場全体に示すことも可能です。成果を可視化できれば、他エリアへの水平展開もスムーズに進みます。焦らず確実に、段階的に拡げていくことが継続的に改善していけるでしょう。
ポイント2:大前提として「整理」を行い、不要なモノを処分する
整頓を行う前に、「整理」ができていなければ効果は薄くなります。整理とは、現場にあるすべてのモノを見直し、「要るもの」と「要らないもの」に分け、不要なものを徹底的に排除する活動です。
多くの現場で活用されている「赤札作戦」は、その象徴的な手法です。不要品が紛れている状態で整頓を進めても、本来の目的である“使いやすくする”には繋がりません。整頓は整理のうえに成り立つ。まずはモノを減らすことを徹底しましょう。
ポイント3:現場の作業者が主体となり、全員参加でルールを決める
整頓や3定のルールは、現場で実際に作業をする人たち自身が主体となって決めることが重要です。管理者だけでルールを定めてしまうと、現場の実態とズレが生じ、「やらされ感」が生まれて定着しません。
作業者が自ら参加し、自分たちのやりやすさを反映させながらルールを作ることで、納得感が生まれ、習慣として根付きやすくなります。
全員参加型の改善は、継続できる5S3定の実施が大切であり、組織全体のモチベーション向上にも繋がります。
なお、作業ルールを現場全員に守ってもらうためのポイントをまとめた資料「“手順書通りにできない”から卒業 作業ルールを守らせる効果的な方法」も参考になると思うので、あわせてご覧ください(下の画像をクリック)。
ポイント4:使いやすさ(動線)を最優先に考え、無理のないルールにする
見た目だけを整える整頓には意味がありません。5S3定においては、作業者の動線や姿勢、手の届きやすさなどを考慮し、日々の業務がやりやすくなることが最優先です。いくらルールが美しくても、作業に無理があれば形骸化します。
現場のリアルな使いやすさに基づいて配置や管理方法を設計することで、自然と定着しやすい整頓になります。見た目の整然さと効率性を両立させるルール作りが、5S3定を根付かせるために大切です。
ポイント5:「目で見る管理」で置き場・モノ・量を明確にする
3定を効果的に運用するには「目で見る管理」の考え方が欠かせません。例えば、工具棚に形跡表示を行ったり、床に区画線を引いたり、棚にモノの名前と写真を貼って可視化することで、誰が見ても一目で正常か異常かがわかる状態が生まれます。
特に定量の管理では、在庫の上限や発注点を表示することで補充の判断が容易になり、属人的な管理を回避できます。
ポイント6:目的と効果を共有し、活動の意識を高める
現場改善活動は、目的が曖昧なまま始めてしまうと、すぐに形だけの運用になってしまいます。
「なぜこの活動を行うのか」「実施するとどんなメリットがあるのか」を、全メンバーにわかりやすく説明し、共有することが重要です。
納得感がなければ、整頓もルールも続きません。逆に、目的意識が浸透すれば、自主的な改善提案が生まれ、継続的な改善文化に育ちます。活動の背景・意味・成果を見える化することが¥で、現場の意識を変えられるようになります。
ポイント7:定期的な見直しと改善を継続する
整頓ルールは、一度決めたら終わりではありません。製品や工程の変更、作業環境の変化に応じて、定期的に見直すことが欠かせません。
ルールが現状に合わなくなると、途端に形骸化しやすくなります。月1回の5Sパトロールや、現場の声を吸い上げるフィードバック会議など、見直しの仕組みを仕掛けとして組み込むことが重要です。
5S3定の継続には「改善の習慣化」が不可欠なので、小さな不具合や不便をその都度修正することで、大きなトラブルを防げます。
ポイント8:トヨタの3定管理に学ぶ「なぜ」の徹底
トヨタ生産方式(TPS)では、3定の徹底が全ての現場改善の始まりとされています。その背景には、徹底した「なぜ」を問い続ける姿勢があります。
「なぜここに置くのか」「なぜこの数が適正なのか」といった本質的な問いを繰り返すことで、ムダを見逃さず、最適な配置や数量が導き出されます。
形だけの整頓ではなく、目的と合理性を追求した整頓こそが、本来の5S3定のあり方です。TPSの思想を参考に、自社に合った意味のある整頓を構築しましょう。
トヨタ生産方式や、その中核をなす改善手法については以下の記事をご覧ください。
▼関連記事▼
・トヨタ生産方式(TPS)をわかりやすく解説!2本の柱やカイゼンを成功させるコツとは
・【テンプレ付】なぜなぜ分析のやり方は?トヨタ式のコツや事例、例題を解説
トヨタ式の改善の本質や、これからの製造業に求められる5Sの考え方について、専門家からさらに深く学びたい方にはこちらの解説動画がおすすめです。
>>「改善の急所を読み解く、5Sを活用したこれからのものづくり」を視聴する
厚生労働省の「5S活動チェックリスト」を活用する
5S3定を継続・改善するうえで欠かせないのが「定期的な自己チェック」です。しかし、自社だけで網羅的なチェック項目を整備するのは意外と難しく、チェックの質にばらつきが出てしまうこともあります。
そこで活用したいのが、厚生労働省(神奈川労働局)が公開している「5S活動チェックリスト」です。5S活動チェックリストには、「整理・整頓・清掃」だけでなく、「清潔・躾」や「転倒防止」まで含めた実践的なチェック項目が揃っており、現場の安全や生産性向上にも直結します。
例えば「作業台周辺が清掃されているか」「通路に物が置かれていないか」「誰でもすぐに元の位置に戻せるか」など、日常の改善点を見える化できます。
自社独自の項目を追加してカスタマイズすることで、より実情に合った管理指標にもなります。まずは公的チェックリストを土台に、持続可能な5S3定の体制を構築しましょう。
外部リンク:職場の安全衛生の取組に役立つ5S活動(厚生労働省 神奈川労働局)
事例で学ぶ|5S3定の徹底は「業務標準化」の第一歩
5S3定は整頓の仕組み化に留まらず、現場の標準化を実現するために大切です。ここでは「業務標準化」として5S3定が果たす役割を実践視点で以下の3点を掘り下げます。
- 5S3定は「モノの置き場所・置き方」の標準化
- 効果を最大化するには「作業(行動)」の標準化が不可欠
- 「作業標準化」を実現した製造業の事例
5S3定は「モノの置き場所・置き方」の標準化
5S3定は「どこに(定位)」「何を(定品)」「いくつ(定量)」置くかという3つの定めを通じて、モノの管理を標準化する活動です。
こうした活動は、誰が作業しても同じ場所に同じモノが、同じ量で揃っているという状態をつくることであり、業務の属人化を防ぐ基礎にもなります。現場のあらゆるモノに対して明確な置き方のルールがあれば、探す手間や判断のブレがなくなり、誰でも一定の品質で作業できる環境が整います。
効果を最大化するには「作業(行動)」の標準化が不可欠
5S3定によってモノの管理ルールを標準化しても、それだけでは改善の効果は限定的です。例えば、工具が正しい位置に置かれていても、その使い方が人によって異なれば、品質のばらつきやヒューマンエラーは防げません。
生産性や品質を高めるには、「モノの標準化」と並行して「作業(行動)の標準化」が必要です。具体的には、作業手順や操作方法を明文化・可視化し、誰もが同じやり方を再現できる仕組みを構築すること。
両者が揃って初めて、現場改善は確かな成果へとつながります。
「作業標準化」を実現した製造業の事例
「作業標準化」を実現した製造業の事例として以下の3社を紹介します。
- 児玉化学工業株式会社様
- 大同工業株式会社様
- テーブルマーク株式会社様
事例1:児玉化学工業株式会社様|情報の「定位・定品」で探すムダをなくし、行動を標準化
児玉化学工業株式会社は、自動車部品や住宅設備部品を製造する中堅化学メーカーで、多国籍の従業員を抱える製造現場において「教育のばらつき」と「ルールの不明確さ」という深刻な課題を抱えていました。
▼事例インタビュー▼
特に紙の手順書は500種を超える膨大な量が存在し、作業ごとにマニュアルの所在が曖昧で、人によって教え方が異なる「我流」が横行。結果として製品不良が多発し、属人化による業務の非効率が顕在化していました。
こうした状況を打破するため、同社は動画マニュアル(tebiki現場教育)を導入。「マニュアルはtebikiにある」とルールを明確化することで、情報の所在(定位)とあるべき情報の明確化(定品)を実現しています。
さらに、動画によって作業手順を視覚的に伝えることで、「動き」や「コツ」まで含めた行動の標準化が可能になり、外国人・新人を問わず均一な教育を実現しました。
結果として、紙の手順書に比べて作成工数は1/3に削減され、教育負担も大幅に軽減。社内の業務効率と製品品質の両面で、tebikiは5S3定の考えを根幹から支える有効なツールとして機能しています。
同社の詳細な改善事例は以下のインタビュー記事からご覧いただけます。
インタビュー記事:手順書作成の工数は紙の1/3になったと思います。 動画で作るのはかんたんだし、 学ぶ側にもわかりやすいですよね。
事例2:大同工業株式会社様|行動の標準化と「探すムダ削減」で、品質の安定を実現
大同工業株式会社は、自動車・オートバイ用部品をグローバルに展開する老舗製造業企業で、特に技術部門における教育と業務標準化に課題を抱えていました。
新入社員教育では講師による繰り返し指導が非効率であり、OJTではトレーナーごとに知識や教え方が異なるため、業務の「我流化」が進行。結果、試験手順におけるヒヤリハットや評価エラーなど、品質面でのリスクが顕在化していました。
そこで同社は動画マニュアル(tebiki現場教育)による改善を決断します。
まず部内の試験手順を動画化し、マニュアルを全員で回覧・再構築するプロセスを経ることで、作業手順そのものの標準化を実現。また、動画マニュアルをQRコード化し、作業現場で即座に視聴できる体制を構築し、検索の手間(探すムダ)を排除。常に最新の標準手順にアクセスできる環境を整えました。
その結果、教育工数は8割削減され、業務効率化と品質の安定化の両立に成功。まさに、5S3定が目指す「標準化による品質安定」と「探すムダの削減」を具体化した好例です。
同社の詳細な改善事例は以下のインタビュー記事からご覧いただけます。
インタビュー記事:製造業の技術部門の業務を動画で標準化。 教育工数を8割削減し、業務の効率化・最適化も実現。
事例3:テーブルマーク株式会社様|行動の標準化で、5Sの最終目的「躾」を実現
テーブルマーク株式会社は、冷凍うどんやパックご飯などの食品を製造・販売する大手食品メーカーで、5つの直営工場すべてに動画マニュアル(tebiki現場教育)を導入しています。
▼事例インタビュー▼
同社が抱えていた大きな課題は、教育にかかる時間と労力の負担、そして作業手順の属人化でした。紙の手順書では伝わりづらく、教える人によって内容が変わってしまうため、新人は「誰を信じればいいのか」迷う場面も少なくありません。
加えて、外国人従業員も多く、言語や文化の違いによって、ゴミの分別など基本ルールの理解・定着にも時間がかかっていました。
そこで同社は、機械操作から現場ルールまであらゆる業務をtebikiで動画化。動画は各機械に貼付したQRコードからいつでも視聴でき、教育のバラつきが解消されました。結果、従来6時間かかっていた属人化業務の教育工数を1時間に短縮し、83%の削減を達成。
また、翻訳機能を活用することで外国人従業員への教育精度も向上し、品質管理体制をさらに強化しました。これは、5Sの最終目的である「躾=ルールの徹底と習慣化」を、tebikiで現実のものにした好事例です。
同社の詳細な改善事例は以下のインタビュー記事からご覧いただけます。
インタビュー記事:属人化業務の指導工数を83%削減!標準化教育により安心安全な食品を提供
5S3定を形骸化させない「仕組み」作りの重要性
5S3定は、ルールを決めただけでは定着しません。現場が納得し、継続できる仕組みこそがカギ。形骸化の原因を掘り下げ、「文化として根付かせる」ための方法を以下の観点で探ります。
- なぜ5S活動は形骸化しやすいのか?
- 「躾」の鍵は、教育の標準化にある
- 教育のばらつきを防ぐ「動画マニュアル」という選択肢
なぜ5S活動は形骸化しやすいのか?
「最初は全員で頑張ったのに、半年後には元通り」
こうした声が、多くの現場で聞かれる5S活動の末路です。最大の原因は、活動の目的が現場レベルで共有されていないこと。なぜやるのかが腹落ちしていなければ、人はやがてルールを忘れ、形だけをなぞるようになります。
さらに、管理者の熱意頼みになってしまう現場も少なくありません。リーダーが変わった瞬間に活動が失速するのはその典型です。また、せっかく決めたルールが現場の実態に合っていなければ、無理に守ることがストレスとなり、形骸化は加速します。
そして最後の盲点が「異動者・新人教育の不足」です。ルールを教える仕組みがなければ、3定は数年のうちに確実に崩壊します。こうした複合的要因こそが、5Sの定着を阻む壁です。
「躾」の鍵は、教育の標準化にある
5Sの中でも、最も難しいのが「躾(しつけ)」です。単にルールを決めるだけでなく、それを「守り続ける文化」をどう築くかが問われます。
定着を阻む最大の壁が、教育のばらつきです。OJTに頼る現場では、教える内容や言い回し、ニュアンスが人によって微妙に異なります。その結果、ある人は「ここに置け」と習い、別の人は「こっちの方が便利だ」とアドバイスを受け、現場に混乱が生じます。
こうして、せっかく定めた定位・定品・定量といった整頓ルールは徐々に崩れ、「あくまで目安」となり、最終的には守られなくなっていきます。
つまり、3定のルールを「守れる」ものにするには、まず「同じように教えられる」仕組みが必要です。教育の標準化なくして、5Sの定着はあり得ません。
5S活動の要である「躾」や、現場に活動を定着させるための具体的な方法については、専門家の解説を動画でご覧いただけます(下の画像をクリック)。あわせて参考にしてみてください。
教育のばらつきを防ぐ「動画マニュアル」という選択肢
教育の標準化において1つの有効手段が「動画マニュアル」です。手順の流れ、モノの正しい置き方、数量の数え方といった3定のルールも、動画にすれば誰が見ても同じように理解できます。
例えば「ここに置く」「こう向ける」といった細かい動きは、文字や写真では伝えきれないもの。動画ならその行動を丸ごと視覚的に共有でき、カンやコツといった暗黙知も形式知へと変換されます。
さらにスマートフォンの自動翻訳機能と組み合わせれば、外国人スタッフにも言葉の壁なく教育可能。特に、現場教育に特化したtebiki現場教育のようなサービスを活用すれば、動画の撮影・編集・共有までワンストップで行えるため、現場のリソースを圧迫することなく「教育の標準化」という最終目的をスムーズに実現できます。
動画マニュアルに少しでも興味がある方は、動画マニュアル『tebiki現場教育』のサービス資料もあわせてご覧ください(下のリンクをクリック)。
>>>かんたん動画マニュアル『tebiki現場教育サービス資料』を見てみる
5S3定を理解して現場改善に活かそう【まとめ】
5S活動における「整頓」の本質を深掘りし、3定(定位・定品・定量)によって職場のムダ・ムラ・ムリを解消する方法を体系的に紹介しました。
この記事では、5S3定の定義から実践ポイント、定着の仕組み化、さらには標準化の事例までを網羅。活動を一過性で終わらせず、組織文化として根付かせるには「教育の標準化」が不可欠であり、その手段として動画マニュアルの活用が効果的です。
継続的改善と業務効率化を実現する第一歩として、5S3定の徹底をぜひ自社にも取り入れてみてください。
5S3定を徹底するうえで有効な手段の1つに動画マニュアルがあることも、本記事で解説しました。現場教育に特化した動画マニュアル『tebiki現場教育』のサービス資料は以下のリンクからダウンロード可能ですので、あわせて参考にしてみてください。