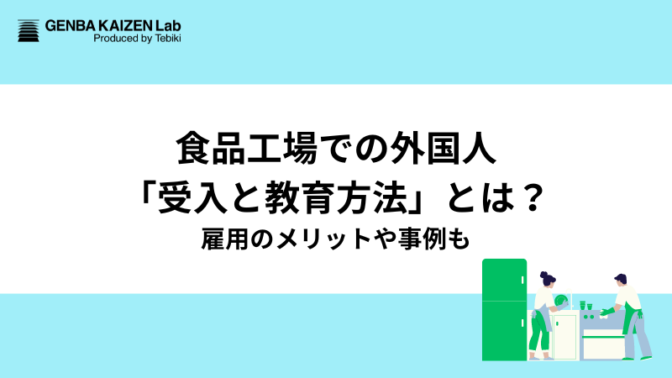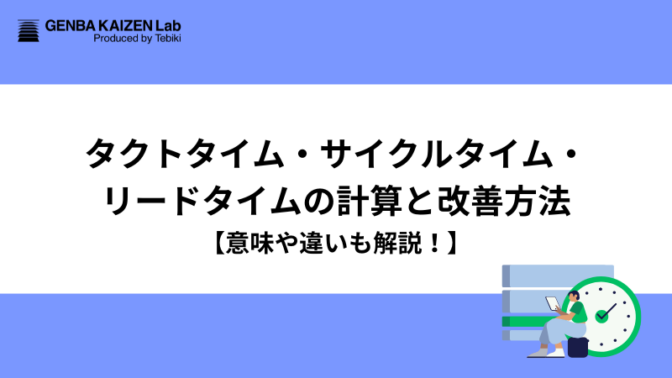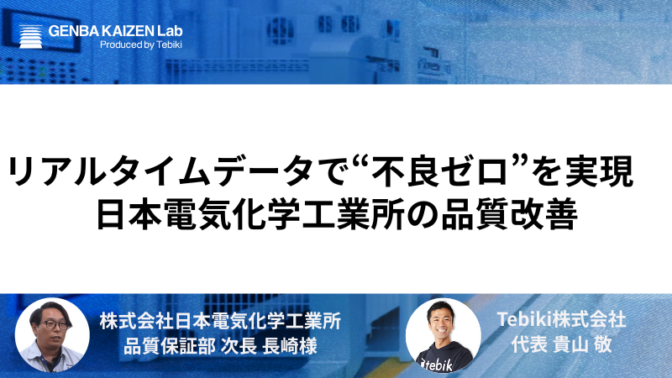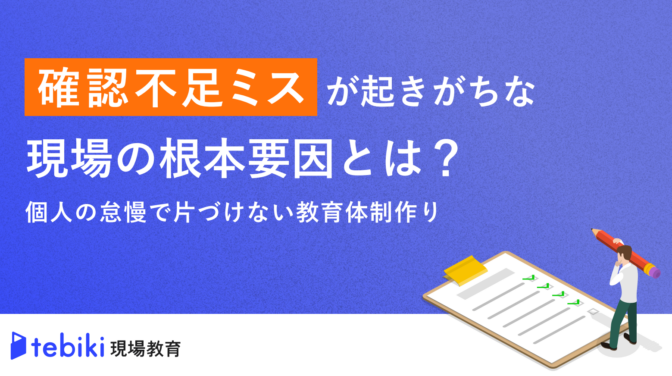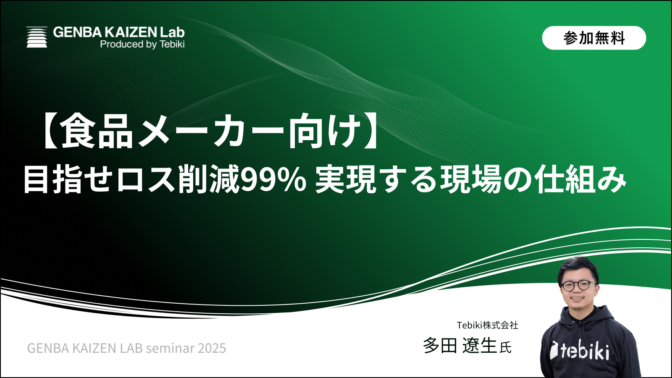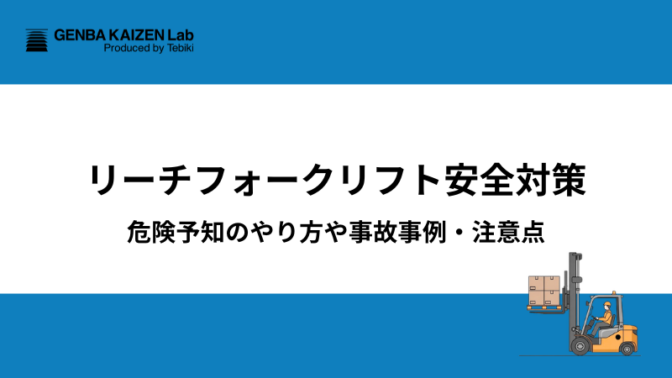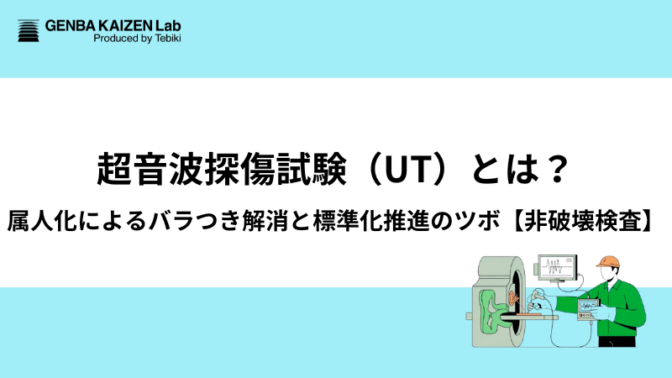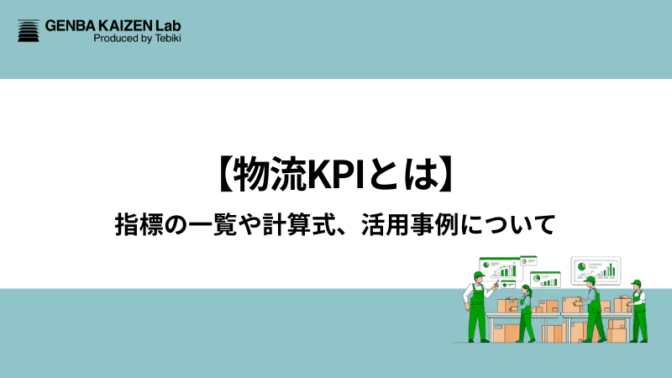物流現場のかんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
多くの物流現場で梱包作業の効率化が求められていますが、どこから手をつけるべきか具体的な方法がわからないという現場も多いのではないでしょうか。作業の効率化に取り組むうえでは、単に仕事のスピードを上げるだけでなく、誰が担当しても一定の品質を確保できる仕組みづくりも重要です。
本記事では現場の課題や改善点とともに、梱包作業を効率化する方法を詳しく解説します。物流企業の改善事例や内製化・外注化のポイントも紹介していますので、自社での取り組みや今後の方向性を考えるときの参考になれば幸いです。
目次
梱包作業で発生している主な課題
倉庫・物流業務のなかでも、梱包作業は品質や効率性に大きな影響を与えるプロセスです。まずは梱包作業の現場で起こりがちな課題を見ていきましょう。
梱包作業をはじめ、物流業務の全般の改善する上で重要になる視点や考え方、実際に改善につなげた事例を詳しく読んでみたい方は、以下の関連記事もご覧ください。
梱包する作業場所・動線が整備されていない
梱包作業の現場では、作業場所の狭さや動線の乱れが作業効率を下げる原因となっています。スペースが不足していると他の作業員と動線が重なりやすく、作業スピードが落ちたりミスが多発したりと、梱包作業の品質にも大きな影響を与えます。
また、梱包資材が適切に配置されておらず、作業員に無駄な移動が発生するケースも見受けられます。これも作業動線に問題があるため、従業員が作業しやすいスペースと作業の流れに合わせた動線の確保が必要です。
多様な商品サイズへの対応に時間がかかる
物流現場では多種多様な形状の商品を取り扱うため、商品ごとに適切な資材の選定や梱包手順をその都度考える必要があります。
新しい商品の取り扱いが始まると、想定外のサイズや形状の商品を出荷することがあり、倉庫に保管している梱包資材だけでは対応が難しいケースも少なくありません。このように商品に合わせた臨機応変な対応が求められることも、作業効率の低下と作業員の負担増加につながっています。
梱包作業の品質にばらつきがある
作業員のスキルや経験、意識の違いにより、梱包作業の品質に差が出ることも大きな課題となっています。商品が箱の中でしっかりと固定されていなかったり、箱の汚れや破れなど見た目に不備があったりする場合、配送過程での破損や紛失、顧客からのクレームに直結するリスクが高まります。
作業品質にばらつきがあり、安定した品質を確保できない状態が続くと、企業の信頼やブランドイメージを失墜させる要因にもなりかねません。
人手不足によって作業負担が増加している
物流業界では人手不足が深刻化しており、限られた人員で大量の梱包作業をこなしている現場も少なくありません。
物流企業の「アスクル株式会社」でも、人手不足による作業量の増加を課題として感じていました。
EC市場の拡大で弊社でも物流量は増えていますが、物流現場は人手不足状態のため、従来の運用では拡大する市場に対応できない状況です。
人手不足の現場では作業員一人ひとりの負担が大きく、作業スピードや品質の低下を招きやすくなります。さらに、過重労働による疲労やストレスが蓄積されると、作業中のミスやトラブルが重なり、重大な事故に発展するおそれもあります。
※同社の課題、課題に対してどのように向き合い改善につなげたのかについては、以下のインタビュー記事で詳しく解説しています。
基本的な梱包作業の流れと非効率が発生しがちなポイント
梱包作業には一定の手順がありますが、作業工程のなかで効率が落ちやすい箇所もあります。ここでは基本的な梱包作業の流れと、作業中に非効率が発生するポイントを紹介します。
【1】商品のサイズや重さを考慮して梱包資材を選ぶ
梱包作業では、まず商品のサイズや形状、重さ、素材などの特性を考慮した梱包資材を選びます。ここで梱包資材の選定を間違えると、作業の途中でも最初からやり直す必要があるため、商品に合わせた適切な資材を選ぶことが重要です。
しかし現場では、どの資材が適切か判断に迷ったり、最適な資材が見つからずに手間取ったりするケースが多く見受けられます。資材の種類が多すぎても選定に時間がかかるため、前もって資材選びに関する一定のルールを設けておくのが望ましいでしょう。
【2】商品に適した緩衝材を選ぶ
揺れや衝撃から商品を守るために、商品の形状や素材に適した緩衝材を選びます。緩衝材にはさまざまな種類があり、エアパッキンやエアーピロー、発泡スチロール、エンボス加工紙、ウレタンフォームなどが代表的です。
このように様々な種類の緩衝材があることによって、どの商品にどの緩衝材を利用すればよいのかをスピーディーに判断できない場合があり、都度確認が発生するなどで非効率が発生しやすくなります。
また、緩衝材が少なければ商品の破損に直結しますが、多ければ多いほどよいということもありません。商品ごとに適した緩衝材を選び、商品を保護できる適切な量を使用することが大切です。
【3】商品を箱詰めする
梱包資材と緩衝材の準備が整ったら、商品を箱に詰める作業に進みます。箱の中で商品が動かないようにテープで留めたり、商品の周りに緩衝材を敷き詰めて固定させたりするのが基本ですが、複数の商品をまとめて梱包する場合は個々の配置に迷いが生じる場合があります。
箱詰めは作業員のスキルや経験に左右され、品質のばらつきが起こりやすいプロセスです。作業に慣れていない段階では時間がかかるため、標準的な詰め方をまとめたマニュアルを整備しておくことをおすすめします。
【4】テープで箱の封を閉じる
商品を詰め終えたら、箱の封をテープで閉じます。軽い荷物は「ガムテープ」、重い荷物は「布テープ」が向いています。箱の底にもテープを貼り、しっかりと補強することが重要です。
このときテープを雑に貼り付けると、輸送中に箱が開いてしまい、破損や紛失のリスクが高まります。繁忙期など梱包作業が大量に発生する時期は封緘が不十分になりがちですが、最後まで気を抜かずに丁寧に作業することが大切です。
このように梱包作業と一口にいっても、発生する作業は多岐にわたり、作業ごとに様々な器具が扱われます。そのため、工程ごとの作業手順・器具の適切な扱い方などを手順書にまとめておくなど、非効率を軽減する対策を講じるのが大切です。
以下の資料では、手順書の作成だけではなく、本質的な問題である従業員に作業手順を守らせる方法まで詳しくまとめています。「手順書はあるものの非効率が発生している」「手順書を整理したいものの、何から手を付ければいいのかわからない」などの悩みを抱えている方はぜひチェックしてみてください。
>>「“手順書通りにできない”から卒業 作業ルールを守らせる効果的な方法(pdf)」を見てみる
梱包作業が早い人に共通している特徴
梱包作業が早い人は共通して「効率的な方法・手順」を自分の作業に落とし込んでいます。具体的には以下のような特徴が挙げられます。
- 標準的な作業手順を理解している
- 必要な梱包資材や道具を手元に配置している
- 商品のサイズや形状に応じた梱包方法を瞬時に判断できる
- 一つひとつの作業を丁寧にこなし、やり直しが発生しない
- 集中力が高く、繰り返しの作業が苦にならない
梱包作業が早い人は、無駄な動きが少なく、判断に迷う時間を最小限に抑えています。ただし、スピードだけを重視した作業では梱包不良や破損リスクを引き起こすため、早さと品質を両立させることが重要です。作業に慣れるまではある程度の時間がかかることを考慮し、まずは標準的な作業手順を確実に身に付けさせることから始めるとよいでしょう。
梱包作業を効率化・改善する方法
ここからは梱包作業を効率化する具体的な方法を紹介していきます。本記事では次の6つの改善策を取り上げます。
それぞれの方法について以下で詳しく解説します。
手順書やマニュアルを作成し、梱包作業の標準化に取り組む
梱包作業を効率化するためには、標準的な作業手順をまとめたマニュアルの整備が不可欠です。標準化された手順があれば、誰が作業しても一定の品質とスピードを確保し、作業のばらつきを防ぐことができます。
標準化に取り組むうえでポイントになるのが、現場に即したマニュアルの作成です。例えば、文章が多すぎて内容が分かりづらい、更新されておらずに現場の実態と乖離があるなどの場合、マニュアルが活用されずに形骸化を招いてしまうことも。実際に、物流企業の「ASKUL LOGIST株式会社」では、作成したマニュアルの更新が行われずに現場で活用されない状況に陥っていました。そこで同社が注目したのが動画を活用したマニュアルの作成です。
従来は受け手の解釈によって理解度のばらつきが発生していましたが、動画の活用によって、作業の標準化を進めることができていると効果を実感しています。同社の事例を詳しく読んでみたい方は、こちらのインタビュー記事をご覧ください。
また、梱包作業では感覚や長年の経験をもとにして行われるカンコツ作業も多く、マニュアルや手順書を作成しても現場に即しておらずに形骸化するリスクも潜んでいます。以下の資料では、中々伝わらないカンコツ作業を標準化する方法、標準化を実現した企業の好事例をまとめておりますので、あわせてご覧ください。
>>「“伝わらない”“属人化している”カンコツ作業を標準化する最適解(pdf)」を見てみる
梱包作業を行う環境や動線を見直す
梱包作業を改善するには、既存の作業環境や動線設計の見直しも必要です。以下のような観点から現場の環境・動線をチェックしてみましょう。
- 作業台の高さが作業員に合っているか
- 梱包作業に十分な広さが確保されているか
- 作業場所が清潔に保たれているか
- 作業員同士の距離感は適切か
- 資材置き場が作業場所の近くにあるか
- 梱包から出荷までの動線がスムーズか
無駄な動作や移動が積み重なると作業効率が低下し、さらには作業員の体にも大きな負担がかかります。上記を参考に現状を見直し、現場の環境や動線に潜む「無駄」を最小限に抑える仕組みづくりが求められます。
無駄な工程がないかを洗い出す
倉庫や物流の現場では梱包作業がボトルネックとなりがちです。例えば、梱包資材を取りに行く回数が多い、箱詰めのやり直しやテープの貼り直しが発生するなど、小さな無駄が積み重なると全体の作業効率に大きな影響を与えます。
梱包に時間がかかると、その後の出荷作業全体が滞り、リードタイムの遅延を引き起こす可能性があります。こうした状況を防ぐためには、梱包工程を細かく見直し、無駄な作業や動きを洗い出して改善を図ることが重要です。
梱包する資材を見直す
商品を確実に保護するためには適切な梱包資材を選ぶ必要があります。具体的には以下の3点を見直すとよいでしょう。
段ボールのサイズ
商品の特性に応じた使い分けができるよう、段ボールは標準的なサイズを複数パターン用意しておきましょう。取り扱う商品に応じたサイズを用意するのが理想的なため、商品ラインナップの変動に合わせて段ボールのサイズも見直すことをおすすめします。
緩衝材の種類
緩衝材の種類は主要な取り扱い商品に合わせ、汎用性の高いものを中心に用意しておくとよいでしょう。この商品にはエアキャップ、この商品にはウレタンフォームというように、よく出荷される商品ごとに適切な緩衝材をあらかじめ定めておくと、現場での選定に迷う時間を削減できます。
テープの貼り方
段ボールの封緘作業では、側面にはみ出す長さでしっかりと貼り付けるのがポイントです(目安は5〜10cm程度)。この長さを確保することで、輸送中にテープが剥がれるリスクを抑え、箱全体の強度を保つことができます。底面を補強するときも同様に、段ボールの側面まで貼り付けるようにしましょう。
5S活動を推進する
5S活動とは、整理・整頓・清掃・清潔・躾(しつけ)の5つで構成される取り組みです。5Sを徹底することで、梱包作業に必要な資材や道具をすぐに手に取れる環境が整い、無駄な動きを削減できます。また、床に散乱した資材につまずく、電源コードに足を取られて転びそうになるといったヒヤリハットが起こりづらくなり、現場全体の安全性向上にもつなげられます。
5S活動の実践方法や効果についてはこちらの記事をご覧頂くか、以下の資料をご覧ください。5S活動を「表面的な取り組み」ではなく「文化」として浸透させるためのコツや、現場で実践できる具体的な取り組み例についてまとめております。
>>【事例つき】5S3定が浸透しない現場の共通点3つと仕組み化の「核」について見る
製函機や梱包機などの機械を導入する
梱包作業の生産性を高めるには、製函機や梱包機などの機械も有効な手段となります。
- 製函機:段ボール箱を自動で組み立てる機械
- 梱包機:梱包材の巻き付けや箱の封緘を自動で行う機械
特に手作業が中心の現場や人手不足に悩む現場では、作業スピードや品質にばらつきが生じやすく、繁忙期の対応にも限界があります。機械の導入はコストや設置スペースなどの課題も生じますが、作業効率や品質の大幅な向上が見込まれ、現場改善に向けた有力な選択肢となるでしょう。
梱包作業の効率化を実現している物流企業の改善事例
梱包作業の効率化は、倉庫・物流業務全体の改善において重要な役割を果たします。
どのような取り組みが業務改善につながるのか、ここでは梱包作業の効率化に成功している物流企業の事例を紹介します。
株式会社フジトランス コーポレーション
港湾運送事業や内航海運業など様々な物流サービスを提供している株式会社フジトランスコーポレーション。同社では、従業員同士の業務共有や引き継ぎなどをする際に業務負荷がかかってしまい、長時間労働の常態化が発生していました。また、外国人労働者への教育や理解度を向上させる点にも課題を抱えていたそうです。
そこで、紙と比べて多くの情報を伝えられる動画マニュアルを導入。梱包作業やフォークリフト作業をメインに、様々な作業のマニュアル化を推進し、従業員に対しての教育工数削減や社内からの問い合わせ数の削減などの効果を実感しています。同社の事例を詳しく知りたい方は、以下のインタビュー記事をご覧ください。
>>株式会社フジトランス コーポレーションのインタビュー記事を読んでみる
ソニテック株式会社
新築戸建て住宅に使用される建築副資材を提供する事業を展開しているソニテック株式会社。同社では、従業員教育で発生する時間とコストが課題であり、新入社員に対して3ヶ月間のマンツーマン指導が発生するなど指導者の日常業務に影響を与えていることも。また、荷主や便によって作業内容が異なるため、梱包作業やピッキングなど、作業一つ一つの標準化が難しく、ミスが頻発する事態を招いていました。
作業品質や効率を改善するために、従来のマンツーマン教育から動画を活用した教育にシフトし、教育時間や品質の均一化などの実現につながるなどの効果を実感しています。教育内容の一定化により、教える側と教えられる側双方のストレスの緩和にもつながるなどの全体効率にも寄与しています。
同社の事例を詳しく知りたい方は、以下のインタビュー記事をご覧ください。
梱包作業の効率化は「内製(教育)」と「外注」どちらがいいか?
梱包作業を効率化する手段として「内製」と「外注」の選択肢があります。両方の特徴や利点を理解し、現場の状況や将来の運用体制を見据えたうえで、自社にとって最適な方法を選ぶことが重要です。
内製の利点やポイント
梱包作業を内製化するメリットは、。外注費用を削減できるだけでなく、梱包作業のノウハウやスキルが社内に蓄積されるため、人材の入れ替わりが多い現場でも安定的な品質維持につなげられる点です。
内製化を成功させるには「教育」が鍵となり、現場全体で作業の標準化を進めることが重要です。そのためには、工程ごとの標準的な作業手順を視覚的にわかりやすく伝える「動画マニュアル」が役立ちます。
実際に、社員教育に動画マニュアルを活用しているサッポログループ物流株式会社では、OJTに動画マニュアルに取り入れたところ、直接的な指導の時間が削減されて教育コストの大幅な削減に成功。金額で換算すると、月額30万円もの教育コストの削減を実現できています。
このように、物流現場での人材教育に動画を活用されているケースは多く、教育コストの削減だけではなく生産性の向上に向けても動画マニュアルが活用されています。内製化に向けて動画マニュアルを活用した教育を検討したい方は、具体的な活用方法や導入効果などを詳しくまとめている資料をご覧ください。
>>「物流業界の生産性向上を助ける動画マニュアルのチカラ(pdf)」を見てみる
外注の利点やポイント
梱包作業を外注化するメリットは、社内リソースの負担を大幅に軽減できる点にあります。作業員の手配やシフト管理、在庫保管スペースの確保、梱包資材の在庫調整などが不要になり、専門業者による安定した作業品質も期待できます。
一方で、委託コストが発生することに加え、梱包作業のノウハウが自社に蓄積されない点はデメリットとなるでしょう。外注先との連携が不十分な場合、品質や納期に問題が生じるリスクもあるため、自社基準を満たす信頼性の高いパートナーを選ぶ必要があります。
まとめ:梱包作業の効率化には作業の標準化が大切
梱包作業の現場には、環境・動線の乱れや品質のばらつき、人手不足による作業負担の増加などさまざまな課題が存在しています。これらに対する対策は多岐にわたりますが、特に効果的なのが「作業の標準化」です。梱包作業の手順を統一することで、無駄な動きや時間のロスがなくなり、作業効率の向上と品質の均一化が実現します。
標準化を確実に定着させる手段としては、動画マニュアルの活用が有効です。実際の動きを視覚的に示せるため、業務ノウハウが「動作」に集約される現場において特に効果を発揮します。ボトルネックになりがちな梱包作業を改善し、現場全体の効率化を図るためにも、動画マニュアルの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
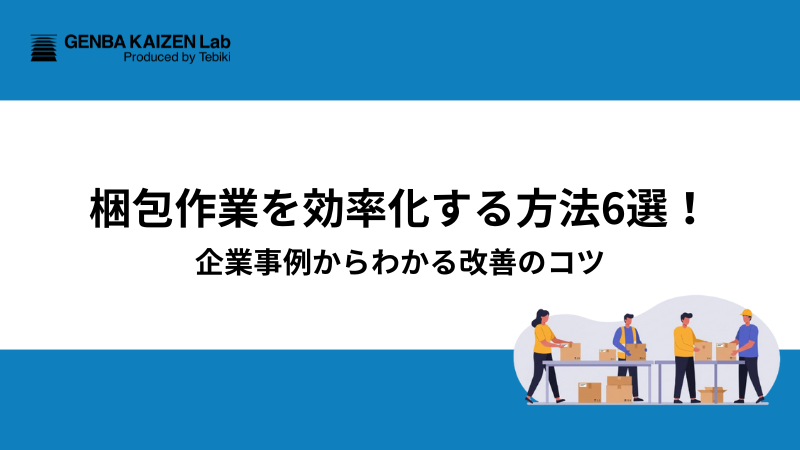


-3-1.png)