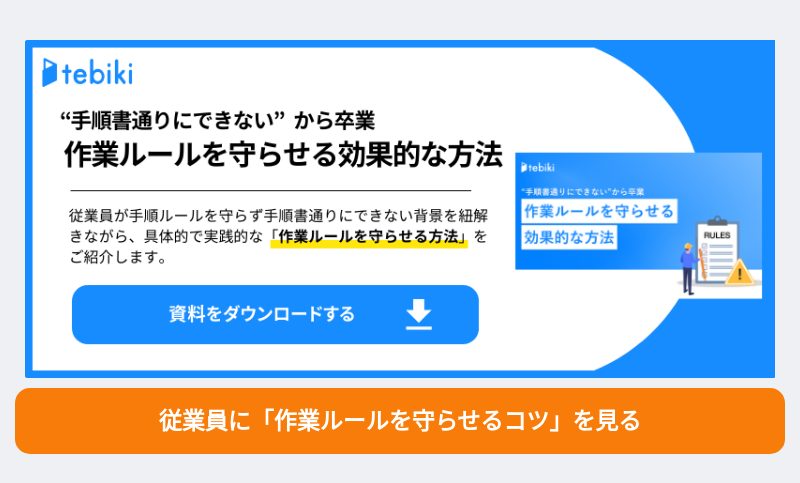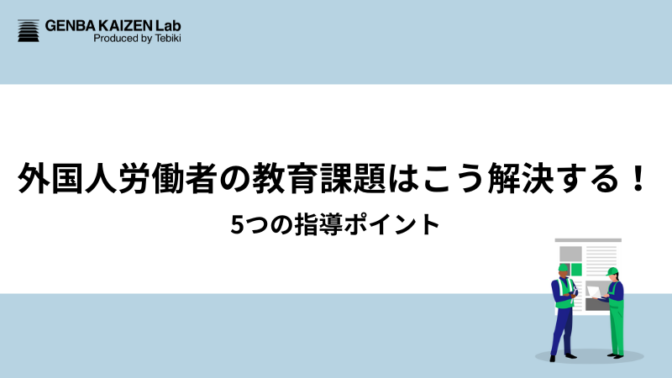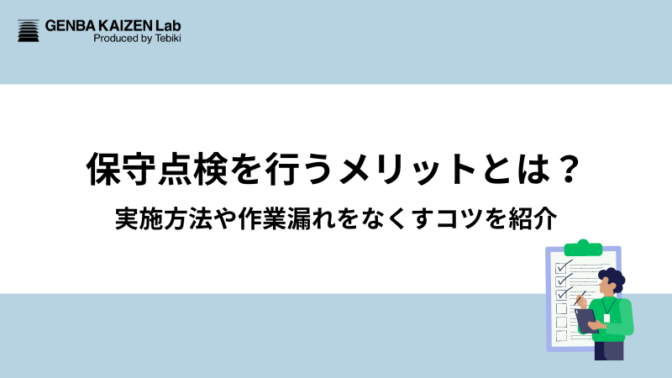出荷作業の改善や効率化に役立つ動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
物流現場の出荷作業は多くの企業で重要課題となっています。ピッキングミスや検品漏れ、作業の属人化、非効率な動線は、コスト増加や納期遅延を招く可能性があります。さらに人手不足が進む中、限られた人員で効率化を求められる状況です。
本記事では、出荷作業の主な課題と解決策を解説し、実際の改善事例や教育効率化につながる活用方法も紹介します。出荷業務の生産性向上や品質に悩む方は是非参考にしてください。
なお、出荷作業でもっとも課題しれやすいピッキングミスの発生メカニズムや、現場で成果につながった改善策をより深く知りたい方には、以下の資料もおすすめです。出荷品質を根本から引き上げたい方は、こちらも併せてご覧ください。
>>誤出荷ゼロへ!ヒューマンエラーによるピッキング作業ミスをなくす具体的な対策と改善事例を見る
目次
出荷作業に潜む3つの課題とよくあるミス
倉庫や物流センターでは、ピッキング・検品・梱包・発送といった多くの出荷作業が行われています。これらの業務は、商品のスムーズな出荷と顧客満足度向上のために欠かせません。しかし、現場ではさまざまな課題が発生することがあり、業務の遅延やコスト増加、品質の低下につながることもあります。
ここでは、出荷作業における代表的な課題を以下の3つに分類し、解説します。
- コスト・効率化における課題とミス
- 品質における課題とミス
- 安全における課題とミス
※これらの課題はそれぞれが独立しているわけではなく、互いに関連し合っている場合も多く、複合的な対策が必要となります。
コスト・効率化における課題とミス
物流現場では、作業時間の短縮や人件費の削減が求められています。しかし、以下の課題があると、出荷作業の効率化が進まず、無駄なコストが発生する原因となります。
在庫管理の不備(過剰在庫や欠品)
適切な在庫管理が行われていないと、過剰在庫や欠品が発生しやすくなります。
保管スペースを圧迫し、管理コストを増加させてしまうのは過剰在庫です。欠品してしまうと、出荷遅延につながり、顧客満足度の低下につながります。
在庫を適切に管理するためには、デジタル化された在庫管理システムの導入や、定期的な棚卸しが必要です。
作業動線の非効率性
倉庫内のレイアウトや作業動線が最適化されていないと、ピッキングや梱包の作業に無駄な動きが増え、出荷スピードが低下します。
例えば、頻繁に扱う商品が遠い場所に配置されていると無駄な動きが増えてしまいます。また、作業エリアが狭いと、従業員同士の動きがスムーズにできず出荷作業が進みません。作業動線を見直し、商品の配置を最適化すれば、作業時間の短縮が可能になります。
出荷業務の属人化と進まない技術継承
業務が特定の従業員に依存している(属人化)と、人員の入れ替えがあった際に出荷作業の質が低下しやすくなってしまいます。例えば、特定の技術やカンコツを熟知しているベテラン社員が退職し、ノウハウが失われてしまう場合です。
こうした技術喪失や属人化の解消には技術継承が重要ですが、重要だとはわかりつつも、なかなかスムーズな教育ができず問題が後回しになってしまう物流現場は多いです。
そこで、技術継承の適切な方法をまとめたPDF資料「“伝わらない”“属人化している”カンコツ作業を標準化する最適解」をあわせてご覧ください。ベテラン社員が持つ技術をどうすれば若手人材に教育することができるのか、実践的な推進方法がまとめられています。以下の画像をクリックしてダウンロードできます。
品質における課題とミス
出荷ミスは、顧客クレームや返品対応につながるため、物流現場では品質管理の徹底が求められます。以下のような問題が発生しやすいため、事前に対策を講じる必要があります。
誤出荷
出荷する商品を間違えると、顧客からのクレームや返品対応が発生し、コストや時間がかかります。誤出荷の主な原因は以下の通りです。
- ピッキング時の見間違い(類似商品の取り違え)
- 伝票と実際の出荷内容の不一致
- バーコードスキャン忘れ
解決策として、スキャンチェックの導入や、ピッキングリストのデジタル化が有効です。
誤出荷ゼロを目指すための詳しい対策や解説は、以下の記事で詳しくまとめられています。あわせて参考にしてみてください。
ヒューマンエラー(人為的ミス)
物流現場では、多くの作業が手作業で行われるため、ヒューマンエラーが発生しやすくなります。代表的なミスは以下の通りです。
- ピッキングミス(間違った棚から商品を取る)
- 検品ミス(傷や異物混入を見逃す)
- 伝票の貼り間違い(異なる顧客の宛先に送付)
ヒューマンエラーは品質不良を引き起こし、現場全体の生産性に直結する要素ですが、未然防止はなかなか簡単ではありません。「ミスしないように気を付ける」というような「意識でどうにかなる問題ではない」からです。
なお、倉庫や物流現場ではいくら注意喚起や再教育を重ねてもピッキングミスがなくならず、「結局、人によって品質がばらつく…」という悩みを抱える企業が少なくありません。原因の多くは作業手順やルールが曖昧で、人によって解釈が異なる“属人的なやり方”が残ってしまっていることにあります。
こうした状況を抜け出すためには、手順・ルール・品質基準を明確にし、誰が作業しても同じ品質を再現できる“仕組み”へと整えることが欠かせません。仕組み化が進むことで注意や意識に頼らずとも、ヒューマンエラーそのものを根本から抑止できるようになります。
ピッキングミスが起こる背景の構造分析から、標準化の実践方法、さらに実際に改善に成功した企業の事例まで体系的にまとめた資料をご用意しています。現場を「ミスの出にくい状態」に変えたい方は、是非参考にしてください。
>>誤出荷ゼロへ!ヒューマンエラーによるピッキング作業ミスをなくす具体的な対策と改善事例を見る
安全における課題とミス
出荷作業を行う物流現場では、多くの機械や人が関わるため、安全対策の不備による事故が発生しやすい環境です。特に転倒事故・転落事故・フォークリフト事故は、作業員の負傷といった労働災害につながりやすく、最悪の場合、業務の停止や法的責任が発生するリスクもあります。
フォークリフトの安全対策については、以下の記事で詳しく解説されています。
関連記事:フォークリフトの安全対策8例!事故を防止した改善事例や安全意識を高める方法も解説
また以下の記事では、労働災害対策について網羅的にまとめられているので、あわせてご覧ください。
関連記事:【事例あり】労働災害対策8選!職場で効果的な「安全意識向上の取り組み」とは
転倒事故
倉庫内では、床の整理整頓が不十分な場合や滑りやすい環境が原因で、作業員が転倒するリスクが高まります。特に以下のケースでは、事故が発生しやすくなります。
- 通路に荷物や梱包材が置かれており、足を引っかける
- 床にオイルや水がこぼれていて、足元が滑りやすい
- 作業スペースが狭く、無理な姿勢で動くことでバランスを崩す
転倒事故を防ぐには、5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)の徹底が欠かせません。通路や作業エリアを定期的に整理整頓し、不要な荷物を撤去しましょう。また、滑り止めマットを設置する、作業靴を滑りにくい素材にするなどの対策も有効です。
現場改善ラボでは、5S活動を「表面的な取り組み」ではなく「文化」として浸透させるためのコツや、現場で実践できる具体的な取り組み例についてまとめた資料もご用意しておりますので、本記事と併せてご覧ください。
>>【事例つき】5S3定が浸透しない現場の共通点3つと仕組み化の「核」について見る
転落事故
倉庫では、在庫を高い棚に収納したり、荷物を運ぶための昇降設備を使用する場面が多くあります。しかし、安全対策が不十分な状態で高所作業を行うと、バランスを崩して転落する危険があります。特に以下のようなケースでは事故が発生しやすいです。
- 不安定な台や脚立の上で作業し、転落する
- 階段や昇降設備の手すりがなく、足を踏み外す
- フォークリフトの荷台やパレットの上に乗って作業を行い、落下する
転落事故を防ぐには、安全ベルトやヘルメットの着用を義務付けることが重要です。また、不安定な台の使用を避け、適切な昇降設備を導入して、安全な作業環境を確保しましょう。手すりや足場の強度を定期的に点検し、転落リスクを減らすことも大切です。
このような安全にまつわるルールは、従業員が正しく理解できるように安全教育の体制を職場で整えることが必要です。
関連記事:職場の「安全教育」とは?意識向上の具体例や資料集も
フォークリフト事故
倉庫作業でよく使われるのが、フォークリフトです。操作ミスや視界不良が原因で、重大な事故につながることがあります。特に以下のようなケースで事故が発生しやすくなります。
- 荷物を高く積みすぎて視界が悪くなり、作業員や障害物に衝突する
- 死角にいる作業員に気づかず、接触事故を起こす
- 速度を出しすぎたり、急旋回を行ったことでフォークリフトが横転する
フォークリフト事故を防ぐには、オペレーターの技術向上と現場の安全対策の強化が欠かせません。運転者には適切な教育と資格取得を義務付け、歩行者との接触を防ぐために安全通路を確保することが必要です。また、ミラーや警報装置を活用し、視界の確保と注意喚起を行うことも有効です。
今回ご紹介したような労働災害を防止するうえで一番重要なのは、定めた安全作業手順を全員が守る仕組みづくりや組織体制づくりです。
それを実現する身近な手段が「安全作業の手順書整備」になりますが、多くの現場では手順書が形骸化していたり、最新の内容に更新されていなかったりするケースが多いです。現場の安全に寄与する手順書の活用方法にはポイントがあるので、そのポイントをまとめた資料「“手順書通りにできない”から卒業!作業ルールを守らせる効果的な方法」もご覧ください。
以下の画像をクリックしてダウンロードできます。
出荷作業を改善・効率化する流れ
出荷作業の効率化には、PDCA(Plan・Do・Check・Action) のサイクルを回すことが重要です。PDCAを適切に実施すれば、現場の課題を可視化し、継続的な改善につなげられます。ここでは、それぞれのステップについて詳しく解説します。
P:現状把握と課題の明確化
まず最初に行うべき内容は、現場の現状把握です。現状を把握して課題を明確にします。出荷作業の効率が低下する要因には、以下のようなものがあります。
- 出荷ミス(ピッキング・検品・梱包時のミスが発生)
- 作業の属人化(特定の従業員に依存し、標準化されていない)
- 作業動線の非効率化(倉庫内で無駄な動きが多い)
- 在庫管理の不備(過剰在庫や欠品による出荷遅れ)
現状を把握する方法として、作業時間の測定、ヒューマンエラーの発生頻度の記録、従業員へのヒアリングなどを行いましょう。データをもとに、出荷作業のどの部分に課題があるのかを特定し、改善方針を立てる必要があります。
D:改善案の立案と実行
課題が明確になったら、具体的な改善案を立案し、実行に移す段階です。改善策の一例として、以下のような方法があります。
改善策の例①作業の標準化を図る
作業標準化は、出荷作業の改善案としてよく挙げられます。出荷作業が担当者によってばらつきがある場合、マニュアルや手順書の整備が立案されますが、工数が膨大になりがちでなかなか推進されません。
マニュアルや手順書の作成工数を大幅に削減できる有効手段として、「動画」が近年よく取り入れられています。例えば「サッポログループ物流株式会社」のように、動画マニュアルの導入によって紙マニュアルの作成工数より70%ほどの削減に成功している事例もあります。
このように、動画マニュアルを活用することで手順書やマニュアルの作成工数を効率化しつつ、出荷業務のような「動作」を視覚的に分かりやすく伝え、標準化が進みやすくなる効果が期待できます。
より具体的な動画マニュアルの有効性は、別紙の参考資料で詳しく解説していますので、以下の画像をクリックしてご覧ください。
改善策の例②在庫管理システムを導入する
出荷遅れの原因となる在庫の不足や過剰在庫を防ぐためには、リアルタイムで在庫を管理できるデジタルシステムの導入が有効です。バーコードスキャンや自動発注機能を活用すれば、ヒューマンエラーを減らし、作業効率を向上させられます。
3. 作業動線を最適化する
ピッキングや梱包作業を効率化するためには、倉庫内のレイアウトを見直すことが大切です。頻繁に使用する商品を作業員の近くに配置したり、通路を広く確保してスムーズに移動できるようにすることで、無駄な時間を削減できます。
C:効果検証
改善策を実施した後は、その効果を検証するフェーズに入ります。改善が適切に機能しているかどうかを判断するためには、以下のような指標を設定するとよいでしょう。
- 出荷ミスの発生率の変化(改善前後でどの程度ミスが減ったか)
- 作業時間の短縮(ピッキング・梱包・検品の所要時間の比較)
- 従業員の負担軽減度(アンケート調査やヒアリング)
例えば、作業動線を見直したことで1日あたりの出荷量が20%向上した、といった具体的なデータを取ることが大切です。もし改善が期待通りの成果を出していない場合は、改善策を見直し、別の方法を試すことも必要です。
A:標準化・さらなる改善
最後のステップは、改善策を標準化し、さらなる業務改善につなげることです。単発の改善で終わらせず、継続的にPDCAサイクルを回すことで、出荷作業の効率をより向上させられます。
- 成功した改善策を手順書化し、全員が共有できる仕組みを作る
- 定期的な振り返りを行い、現場の声を反映する
- 新しい技術やシステムの導入を検討し、さらなる改善を進める
また、作業員の意見を積極的に取り入れ、現場に合った改善策を実施することが重要です。現場の課題は常に変化するため、定期的に見直しを行いながら、最適な改善策を模索していく必要があります。
もし改善を通じて新たな手順書を整備する場合は、現場できちんと読まれる手順書でなければなりません。従業員に読まれず、形骸化し、結果的にOJT依存の現場へと戻ってしまうからです。そこで本格的に手順書を整備するには、資料「カンコツが伝わる! 『現場で使われる』作業手順書のポイント」もあわせてご覧ください。以下の画像をクリックすると、資料をダウンロードできます。
出荷作業の「コスト・効率化」における改善策
出荷作業のコストを抑えながら効率化を図ることは、物流現場にとって重要な課題です。
作業プロセスが非効率なままでは、時間・人件費の増加、ミスの発生、顧客満足度の低下につながります。そこで、以下の6つの改善策を実施することで、出荷作業のスムーズ化とコスト削減を実現できます。
作業の標準化
出荷作業の属人化は、業務効率の低下や品質のばらつきにつながります。特定の担当者しかできない作業があると、人員の入れ替わり時に生産性が落ちるリスクが高まります。
- 標準作業手順をマニュアル化し、日々周知する
- 作業ごとの標準作業時間を設定し、無駄な動きを排除する
- 作業チェックリストを導入し、品質を一定に保つ
作業の標準化により、誰でも同じクオリティで業務を遂行できる環境を作ることが可能です。
作業標準化の実践的な推進方法を深く知りたい方は、「“伝わらない”“属人化している”カンコツ作業を標準化する最適解」もあわせてご覧いただくと、標準化を実現するためのヒントが得られます。以下の画像をクリックして、資料をダウンロードしてみてください。
教育担当者の工数削減・短縮
新人教育やOJTに時間がかかると、教育担当者の負担が増え、生産性が低下します。特に派遣社員や外国人労働者が多い現場では、教育に時間を取られやすい傾向があります。
- 非言語マニュアルを導入し、外国人教育もスムーズに行えるようにする
- シンプルな作業フローを構築し、新人が即戦力として活躍できる仕組みを作る
- チェックシートや業務フローをデジタル化し、ミスを防ぐ
教育プロセスを最適化することで、現場の生産性向上と工数削減が実現できます。
ちなみに外国人スタッフの教育には、非言語マニュアルである「動画マニュアル」が導入されるケースが多いです。例えば「ASKUL LOGIST株式会社」のように、動画マニュアルを導入したことで外国人スタッフの安全教育が推進された事例があります。物流業界のような、人材の多様化が進んでいる現場では、動画のような非言語マニュアルツールが教育の鍵を握りつつあるのです。
動画マニュアルによって外国人スタッフの教育を具体的にどう進めるのか、どういったユースケースがあるのかについては、資料「外国人社員の教育課題は、動画マニュアルで解決できる!」をご覧ください。以下のリンクをクリックしてダウンロードできます。
>>>動画を活用した、外国人スタッフのスムーズな教育方法を学ぶ
5S活動の徹底
5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)の徹底は、作業の効率化とミス防止に直結します。倉庫内が整理されていないと、ピッキングや梱包作業に無駄な時間がかかり、出荷遅延の原因になります。
- 不要な在庫や工具を排除し、必要なものをすぐに取り出せる環境を作る
- 床のマーキングや棚のラベリングを行い、物の配置を明確にする
- 定期的な清掃と点検を実施し、作業スペースを常に最適な状態に保つ
5S活動の徹底により、出荷作業の無駄をなくし、コスト削減と生産性向上を実現できます。
5S活動を「表面的な取り組み」ではなく「文化」として浸透させるためのコツや現場で実践できる具体的な取り組み例についてまとめた資料を以下にご用意しておりますので、是非ご覧ください。
>>【事例つき】5S3定が浸透しない現場の共通点3つと仕組み化の「核」について見る
作業動線の見直し
作業動線が非効率だと、従業員の移動時間が増え、作業負担が大きくなるため、生産性が低下します。特に広い倉庫では、効率的な動線設計が欠かせません。
- ピッキングリストを最適化し、無駄な移動を減らす
- 高頻度で出荷される商品を取りやすい位置に配置する
- 倉庫内の通路を整理し、作業員がスムーズに移動できる環境を作る
作業動線を改善することで、出荷作業のスピードが向上し、労働負担を軽減できます。
在庫管理の最適化
在庫管理が適切に行われていないと、欠品による出荷遅延や、過剰在庫によるコスト増が発生します。これらの課題を解決するためには、リアルタイムで在庫状況を把握できる環境が必要です。
- デジタル化された在庫管理システムを導入し、リアルタイムで在庫を確認する
- 売れ筋商品を適正数量で管理する
- 定期的な棚卸しを実施し、在庫のズレを最小限にする
在庫管理の精度を向上させると、ムダの削減につながりコストを最適化できます。
適切な人員配置
作業量に対して人員が過剰・不足している場合、労働生産性が低下し、コストが増加するリスクがあります。適切な人員配置を行うことで、作業効率の向上が可能です。
- 業務量に応じてシフトを最適化し、無駄な人員コストを削減する
- ピーク時と閑散期で人員配置を柔軟に調整できるようにする
- RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用し、単純作業を自動化する
こうした適切な人員配置をするには、従業員ひとりひとりのスキル習得状況(スキルマップ)を把握できていなければなりません。誰が何をできるのか、一覧で可視化されていることで、現場全体の生産性を向上させるための人員計画が可能になるからです。
とはいえ、スキルマップの運用が続かず形骸化している物流現場は少なくありません。紙による管理が煩雑で、気が付けば最新状態に更新されていないというケースが多いです。そこで推奨したいのが、「クラウド型スキルマップ」の導入です。
例えば、物流現場に特化したクラウド型スキルマップ「tebiki現場教育」では、下図のように「従業員ごとのスキル習得状況」を可視化します。

【「動画マニュアルが紐づくクラウド型スキルマップ – tebiki現場教育」より抜粋】
tebiki現場教育の詳細機能や活用事例について詳しく知りたい方は、以下のPDF資料もあわせてご覧いただくと、tebikiを現場でどのように活用できるのか・どのように稼働率向上に貢献するのかが具体的にイメージできます。
>>>PDF資料「動画マニュアルが紐づくクラウド型スキルマップ『tebiki現場教育』」を見てみる
出荷作業の「品質」における改善策
出荷作業の品質を向上させることは、顧客満足度の向上だけでなく、物流コスト削減や業務効率化にもつながります。誤出荷や検品ミスを防ぎ、トレーサビリティを確保することで、信頼性の高い物流体制を構築できます。出荷作業の品質改善に有効な3つの施策は以下の通りです。
- 誤出荷の防止対策
- 検品制度の向上
- トレーサビリティの確保
誤出荷の防止対策
誤出荷は、物流現場で最も発生しやすいミスの一つです。誤った商品が顧客に届くと、返品・交換対応が発生し、業務負荷が増大するだけでなく、企業の信頼も損なわれます。誤出荷を防ぐためには、以下の施策が有効です。
1. バーコード管理の徹底
バーコードやQRコードを活用することで、出荷前の検品精度を向上できます。スキャナーを使用してピッキング時・梱包時・出荷前の3段階でチェックすることで、ヒューマンエラーを防ぎます。
2. デジタルピッキングシステム(DPS)の導入
ヒューマンエラーや入力作業のミスによって発生する誤出荷は、デジタルツールを導入することである程度ミスを防止できます。熟練度に左右されず、新人スタッフでも正確なピッキング可能になります。
3. デジタルマニュアルの活用
出荷手順をマニュアル化し、作業員が適切な手順を理解しやすい環境を整えます。特に新規スタッフや外国人労働者にとって、視覚的な学習は習得速度を向上させる効果があります。ただし、紙マニュアルや手順書は形骸化しやすい傾向にあるので、「どこでも・誰でも・気軽に」閲覧できる電子マニュアルが推奨されています。
検品制度の向上
検品の精度を高めることで、顧客に正しい商品を届ける確率を大幅に向上させられます。検品制度の改善には、以下の施策が有効です。
1. チェックリストの標準化
検品項目を明確にし、以下のようなチェックリストを作成すれば作業の抜け漏れを防ぎます。
- 商品コードと注文内容の一致確認
- 数量の確認
- 外装・梱包状態のチェック
- 付属品や書類の有無の確認
2. デジタル現場帳票の導入
紙のチェックリストでは、手書きミスや管理の手間が発生しやすいため、タブレット端末やハンディスキャナーを活用したデジタルチェックリストやデジタル現場帳票を導入すると、より正確な記録管理が可能になります。
特にデジタル現場帳票を導入すると、ピッキングリストや納品書、作業日報といったデータがリアルタイムで端末上に反映されるので、遠隔での情報共有はもちろん、データに基づいた正確な業務遂行やペーパーレス化も実現できます。
デジタル現場帳票の活用事例や導入方法について詳しく知りたい方は、以下のPDF資料「はじめての現場帳票デジタル化ガイド」をお読みください。画像をクリックするとダウンロードできます。
3. 画像検品の導入
出荷前の商品を写真撮影してデータを保存しておけば、クレーム対応やトラブル発生時の証拠として活用できます。また、AIを活用した画像検品システムを導入すると、異物混入やパッケージの破損を自動検知し、より高度な品質管理が実現できます。
トレーサビリティの確保
トレーサビリティ(追跡可能性)を確保することで、出荷ミスの原因特定や、不良品発生時の迅速な対応が可能です。
1. シリアルナンバー管理の導入
商品ごとに固有のシリアルナンバーを割り振り、どのロット・どのタイミングで出荷されたのかを記録しておけば、返品やクレーム対応がスムーズに行えます。
2. WMS(倉庫管理システム)の活用
WMSを導入すると、出荷作業の履歴をリアルタイムで管理できるため、誰が・いつ・どのように作業を行ったのかを簡単に追跡できます。また、ピッキング・梱包・出荷までのプロセスがデータ化され、業務改善のための分析にも役立ちます。
3. 出荷データの可視化
出荷履歴や配送状況をシステム上で可視化し、管理者や作業員がリアルタイムで確認できるようにすれば、トラブル発生時の対応を迅速化できます。例えば、クラウド上で出荷状況を共有すれば、異常が発生した際にすぐに対応策を講じることが可能です。
出荷作業の「安全」における改善策
物流現場では、常に安全管理が求められます。特に出荷作業では、ヒヤリハットや労働災害が発生しやすく、安全対策の強化が欠かせません。作業員の怪我やトラブルを防ぐためには、現場の危険要因を可視化し、効果的な安全対策を実施する必要があります。出荷作業の安全性向上に有効な3つの施策を紹介します。
ヒヤリハット事例の共有
ヒヤリハットとは、「事故には至らなかったものの、一歩間違えれば大きな事故になっていた」事例を指します。
物流現場では、フォークリフトの接触事故や、誤って重い荷物を落とすなど、ヒヤリとする場面が発生するかもしれません。このような事例を共有し、再発防止策を講じることで、より安全な作業環境を構築できます。
以下の記事は、フォークリフトのヒヤリハット事例集と対策についてまとめられています。参考情報としてあわせてご覧ください。
関連記事:フォークリフトのヒヤリハット事例集と対策まとめ!危険予知の事例もあわせて解説
ヒヤリハットを共有するためには、日報や報告書の活用が有効です。さらに、定期的なミーティングの場でも事例を共有することで、リスクに対する意識の強化につながります。ヒヤリハットから事故を防ぐための方法やノウハウは、以下の記事で詳しく解説しているのでご覧ください。
関連記事:ヒヤリハット事例を活かした事故やトラブルの防ぎ方は?危険を伝えるマニュアル作りも解説
現場改善ラボでは、無料セミナー動画「労働災害を撲滅するヒヤリハット対策の心得」を配信中です。現場の安全性や安全意識を高めたい責任者や現場担当者の方は、本動画を視聴することで具体的な安全対策が知れるはずです。以下の画像をクリックして視聴してみてください。
危険作業の見える化
危険作業が見える化されていない現場では、作業員が危険を意識せずに業務を行い、事故につながる可能性が高くなります。リスクを可視化すれば、安全な行動を取るよう促すことが可能です。
リスクの可視化とはつまり、現場に潜む危険性や有害性を調査し、低減・除去するまでの一連の手法である「リスクアセスメント」だと言えます。
リスクアセスメントの具体的やり方について理解を深めたい方は、以下のセミナー動画「現場のキケンを見極める『リスクアセスメント術』」もあわせて視聴してみてください。元労基署長がセミナー講師として解説しているので、より実践的な理解が得られるはずです。
KYTやKY活動(危険予知活動)の実施
KYT(危険予知トレーニング)は、作業前に危険なポイントを洗い出し、安全行動を確認する活動です。事故を未然に防ぐための重要な取り組みであり、物流現場では特に効果的です。
例えば、朝礼時に「今日の作業の危険なポイントは何か?」を話し合い、意識を高めます。作業ごとに安全確認のチェックリストを作成し、可視化するのも有効です。
とはいえ、KYTが形骸化している現場は多く、安全に寄与する効果的なKYTをきちんと実践するのは決して簡単ではありません。そこで、本当に価値あるKYTを実践するための改善方法について解説されているセミナー動画「効果のあるKYTとは?KYTの実情、3つの課題とその解決策」もあわせてご覧いただくことをおすすめします。
動画でKYTの実践方法について分かりやすく解説されているので、下の画像をクリックして動画を視聴してみてください。
出荷作業を改善した物流企業の事例
ソニテック株式会社:マンツーマン教育指導の工数を削減
建築副資材を提供する物流企業「ソニテック株式会社」は、新人教育におけるマンツーマン指導の工数増大と、それによる作業品質のバラつきが出荷作業における課題となっていました。マンツーマン指導は人によって教え方がバラつくため、結果的に新人の作業品質もバラついていたのです。
特に、荷主や便によって異なるピッキング作業の教育は、指導者と新人の双方に大きな負担となっていました。
これらの課題を解決するため、同社は紙の手順書から「動画マニュアル」に切り替えました。これにより、新人教育を完全に動画化し、これまで3ヶ月かかっていたマンツーマン指導を実質ゼロにすることに成功しました。
結果として、新人教育にかかる時間とコストを大幅に削減し、均質化された教育によりピッキング作業を含む出荷作業の品質を標準化・安定化させることができました。 また、動画マニュアルは、自動字幕生成機能などにより、簡単に作成・更新できるため、現場主導での継続的な改善活動にもつながっています。
同社が導入した動画マニュアルは、物流現場に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」です。tebikiの詳しい機能や活用事例についてもっと知りたい方は、以下の画像をクリックしてサービス資料もあわせてご覧ください。
株式会社ロジパルエクスプレス:拠点ごとの作業ルールのバラつきを標準化
倉庫や車両などの自社資産を活用した物流サービスを提供する「株式会社ロジパルエクスプレス」は、全拠点でのマニュアルやルールが不統一であったことから、業務品質のバラつき、安全品質の低下が課題でした。
これらの課題を解決するため、同社は動画マニュアルを導入。安全品質教材や、倉庫内作業、トラックドライバー業務の作業マニュアルとして活用を開始しました。 これにより、全社で統一されたルール・マニュアルの共有環境が整い、業務上の危険性や作業手順の理解度が向上しました。
結果として、出荷作業を含む倉庫内作業の安全品質意識が向上し、事故やヒヤリハットの削減に貢献。 さらに、マニュアル申請から承認までの時間も短縮され、業務効率化も実現しました。 動画マニュアルは、集合研修が難しいトラックドライバーの教育にも活用され、隙間時間での学習を可能にし、教育の均質化を促進しました。
同社の詳しい事例は、以下のインタビュー記事からご覧ください。
インタビュー記事:動画で全拠点の安全品質意識の向上と業務ノウハウの可視化を達成
ASKUL LOGIST株式会社:安全教育や外国人教育を効率化
EC専門の総合物流企業であり、事業所向け通販サイト「ASKUL」の物流・配送を担っている「ASKUL LOGIST株式会社」は、多様な人材(短時間勤務者、外国籍スタッフなど)の増加に伴い、教育の標準化と安全教育の徹底が課題となっていました。
特に、従来のOJTや紙のマニュアルでは、教育内容のバラつき、外国人スタッフへの伝わりにくさ、導入時教育や繰り返し教育の工数増大が出荷作業を含む物流プロセス全体のネックとなっていました。
これらの課題を解決するため、動画マニュアルを導入。導入時教育や定期的な安全教育に活用し、特に注意すべき点をピンポイントでマニュアル化することで、教育内容の標準化を実現しました。
結果として、新人教育の時間が1回2時間から30分に短縮され、管理者の負担を大幅に削減しました。外国人スタッフは母国語で学習できるようになったことで、理解度が向上し、現場へのスムーズな導入を可能にしました。 これらの改善により、出荷作業を含む物流業務全体の効率化と、作業品質の均一化につながりました。 また、ヒヤリハット事例の共有やKYT(危険予知トレーニング)にも動画を活用することで、安全意識の向上にも貢献しています。
同社の詳しい事例は以下のインタビュー記事からご覧いただけます。
インタビュー記事:従業員数3,500名超・全国15拠点で動画マニュアルtebikiを活用!
出荷作業における業務品質や安全意識の改善手段:動画マニュアル
出荷作業の効率化、品質向上、そして安全確保。これらは物流現場における永遠の課題ですが、これらを解消するための有効手段として「動画マニュアル」が多くの現場で導入されています。その理由を具体的に見ていきましょう。
もし動画マニュアルによる出荷作業の改善を検討したい場合は、どんなツールを選び、どのようにマニュアル化を推進するのかについてまとめられた資料「動画マニュアルで現場の教育をかんたんにする方法」もあわせてご覧ください。以下の画像をクリックしてダウンロードできます。
紙マニュアルが不要に
従来の紙マニュアルは作成や更新に手間と時間がかかり、情報伝達も遅くなりがちでした。分厚いマニュアルは読む意欲を削ぎ、必要な情報を見つけるのも困難です。動画マニュアルは、スマートフォンで撮影し、簡単に編集できるため、誰でも迅速に作成・更新が可能です。
最新情報を即座に共有でき、検索性も高く、現場でQRコードから必要な動画へすぐにアクセスできます。保管スペースも不要で、紛失の心配もありません。
教育担当者の工数を大幅に削減
新人教育は多大な時間と労力を要する業務であり、特に出荷作業のような多岐にわたる業務では、マンツーマンのOJTが教育担当者に大きな負担となります。動画マニュアルがあれば、基本的な作業手順は動画で学習できるため、OJTの時間を大幅に削減、場合によってはゼロにできます。
一度作成した動画は繰り返し利用でき、教育内容も標準化されるため、教える人による内容のばらつきをなくし、作業品質の均一化に貢献します。
外国人労働者や派遣社員の即戦力化
外国人労働者や派遣社員は、言語や文化、経験の差から、即戦力化が難しいことがあります。紙マニュアルでは理解に時間がかかり、OJTに依存しがちです。
動画マニュアルは、作業の様子を「見て理解できる」ため、言葉の壁を越え、スムーズな業務習得を支援します。tebiki現場教育のような自動翻訳機能を使えば、多言語対応も簡単です。経験の差を埋めるノウハウ共有も容易であり、早期の戦力化、ひいては人手不足の解消にもつながります。
もし動画マニュアルによる出荷作業の改善を検討したい場合は、どんなツールを選び、どのようにマニュアル化を推進するのかについてまとめられた資料「動画マニュアルで現場の教育をかんたんにする方法」もあわせてご覧ください。以下の画像をクリックしてダウンロードできます。
まとめ:出荷作業の改善には「作業標準化」が重要
本記事では、物流現場における出荷作業の課題と、その解決策について解説しました。コスト・効率化、品質、安全の3つの側面から課題を捉え、具体的な改善策と、それを実践した企業の事例を紹介しました。
在庫管理の不備、非効率な動線、属人化、誤出荷、ヒューマンエラー、そして転倒・転落・フォークリフト事故といったリスク。これらの課題解決に共通して重要なのが作業の標準化です。PDCAサイクルを回し、5S活動、在庫管理の最適化といった取り組みに加え、特に動画マニュアルの導入による作業標準化が効果的です。
動画マニュアルは、紙マニュアルの限界を超え、教育工数の削減、外国人労働者や派遣社員の即戦力化を可能にし、現場の誰もが理解しやすい教育を実現します。結果として、標準化された作業手順に基づいた、効率的で高品質、かつ安全な出荷作業を確立できます。
動画マニュアルを導入する場合は、物流現場に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を検討してみてください。以下の画像をクリックすると、tebikiの詳しい資料や活用事例についてまとまった資料がダウンロードできます。