チルド飲料の安定供給を支える
製造工程の人材教育に動画マニュアルを活用

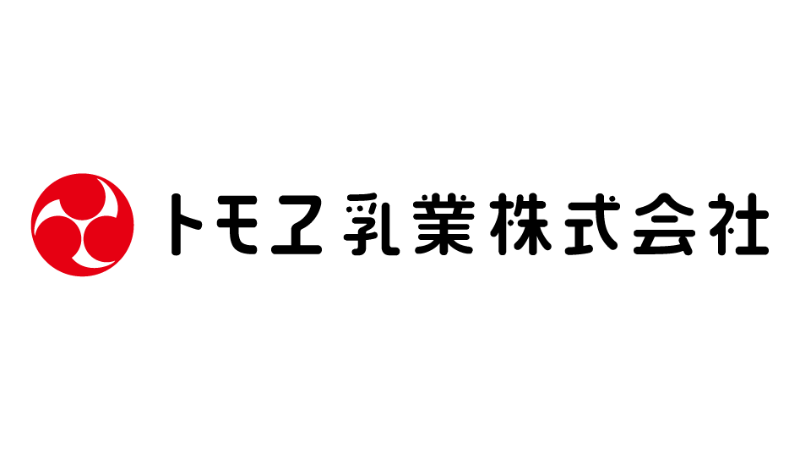
トモヱ乳業株式会社
- 業種 :製造
- 従業員数 :101-500名
- テーマ :生産性向上
お話を伺った方:
管理部 システム課 課長 廣木様
製造部 第二製造課 課長 吉住様
-
課題
- 紙のマニュアルでは、業務内容が直感的に伝わりづらかった
- マニュアルの作成や管理業務が、現場の負担となっていた
- 社内アンケートを紙で実施してExcelで集計する作業に手間がかかっていた
-
効果
- 動画で作業の具体的なイメージが持てるようになった
- 業務を繰り返し教える工数が下がり生産性が向上した
- テスト機能の活用で、社内アンケートの実施と集計が簡単に実施できるようになった
飲料製造における調合・殺菌・充填といった作業工程でtebikiを活用しています
貴社の事業内容と、tebikiの対象業務について教えてください
吉住様:弊社は、1956年(昭和31年)創業の乳業メーカーです。茨城県古河市に工場があり、牛乳をメインに、カップタイプの乳飲料や果実飲料、アイスコーヒーのほか、ヨーグルトなども製造しています。また、茨城県や埼玉県、東京都の一部エリア向けに、学校給食用の牛乳も製造しています。
工場では、tebikiを利用して調合・殺菌・充填といった製造業務の動画マニュアルを作成して利用しています。動画マニュアルの内容としては、現場での安全衛生に関するものや機械の操作方法、洗浄手順を解説する内容などが中心です。工場内ではタブレット端末で動画マニュアルが視聴できる環境にしています。
また、25年1月から受け入れる外国人技能実習生(インドネシア人)向けの教育コンテンツなども作成しています。

tebiki導入前の課題について教えてください
廣木様:弊社では全社員のうち約7割が製品の製造に携わっています。工場では紙に印刷した業務のマニュアルを用意してあるのですが、現場の業務を習熟していない人が見たところで、「機械のふたを開ける」とか「ネジを外す」と書いてあっても、どのふたを開けるのか、どのネジをどのように外すのが正しいのかなどが直感的にはわかりにくいものでした。
吉住様:そのマニュアルも、現場で業務に慣れているリーダーや中堅以上の社員が作成します。紙でファイリングしたものを現場で見るという形であったため、マニュアル管理業務そのものが現場にとっては負担となっていました。
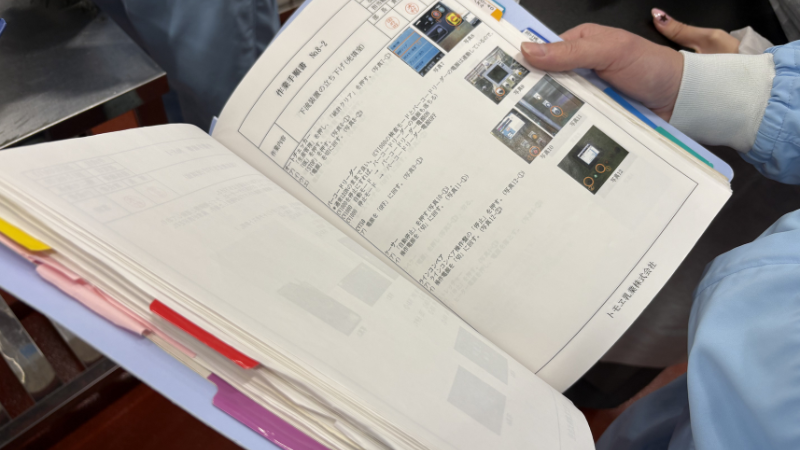
導入検討時に最重要視したのは「直感的に利用できるツール」であること
tebikiの導入経緯や選定のポイントについて教えてください
廣木様:「百聞は一見に如かず」と言いますが、現場での業務を視覚的に伝えるものとしての動画活用は有効ではないかと考えていました。まだ社内では動画マニュアルを導入しようというところまでは話が出ていなかったので、まずは社内で提案するためにtebikiを含めて動画マニュアルツールについて情報収集を始めました。その後、幕張メッセで開催されていた食品業界向けの展示会に参加して、Tebiki社のブースに立ち寄って話を聞いたのが最初ですね。
ツールの選定において、最も重要視したポイントは現場のスタッフが直感的に使えるツールであるかということです。システム部門としては、社内にデジタルツールを導入する際にはもちろん利用マニュアルを用意するのですが、なかなか読んでもらえません。本当に困った時にしか読まれないのです。現場には年配のスタッフも多いこともあり、利用マニュアルを見なくても直感的に操作できることは、現場に導入するデジタルツールとしては必須でした。操作方法をあらかじめ理解していなくても、「こうすれば動画をカットできるんだな」「字幕が挿入できるんだな」といったところが直感的にわかることが重要です。また、外国人スタッフ向けに動画マニュアルを活用することも想定していましたので、対応している言語の数においてもtebikiが優れていました。
もう一つ重要なのはシステムの動作環境です。工場などの現場で利用するデジタルツールは、「誰が」「どのような環境で」「どのような端末で」利用するかをあらかじめ想定することが必要です。そこを考えていくと、必要な動作環境が見えてくると思います。tebikiはブラウザベースで動作するというところが私たちの使い方にマッチしていました。

tebikiを導入した効果について教えてください
廣木様:本格的な活用はまだこれからというところですが、新入社員に動画マニュアルを見せたところ、文書のマニュアルより作業の具体的なイメージを持ちやすいという声をもらっています。また業務を教える側の立場として、最初は現場で新人に付き添って教えます。その後、何度も繰り返し教えていたことが動画マニュアルに代替されるという点で、工数削減の効果は大きいです。生産性の観点でも、動画マニュアルの効果を感じています。
吉住様: 現場には動画編集のスキルがある社員はいなかったですし、デジタルツールに対して苦手な印象を持っている社員もいると思っていました。でもtebikiだとスマートフォンで撮影した動画をそのまま取り込んで編集できるので、動画マニュアルの作成は思ったより簡単だという声を聞いています。

契約プラン変更の背景について教えてください
廣木様:導入時はエントリープランでしたが、24年10月よりビジネスプランに変更しました。プラン変更の目的は、ビジネスプラン以上で提供されているテスト機能を利用するためです。 弊社は「医食同源」を経営理念に掲げて健康経営を志向しており、働いている社員が心身ともに健康であることで、社員の生産性を最大限に高めることができると考えています。その健康経営への取り組みの一環として、定期的に社内アンケートを実施しています。 アンケートの内容としては、社員の幸福度チェックや業務における不安について問うものが中心です。その社内アンケートを紙で実施してExcelで集計する作業は、思いのほか大変です。tebikiの動画マニュアルとあわせて社員の理解度をチェックする目的でテスト機能を利用している企業が多いかと思いますが、弊社ではテスト機能を活用して社内アンケートを実施し、データの収集などが簡単にできると期待しています。
カスタマーサクセス担当が伴走してくれることで、プロジェクトを前進させることができています
tebiki のオススメポイントを教えてください
廣木様: 先ほども申し上げたように直感的な操作で利用できる点はもちろんですが、教育の進捗状況などが可視化できる組織レポートは管理者視点では魅力的ですね。そして何より、導入時の支援とそれ以降も伴走していただけるカスタマーサクセス担当によるサポートには非常に助けられています。ソフトウェアの導入時に最初だけサポートしていただけるということはよくあると思うのですが、自分たちで運用できるところまでしっかり伴走していただけるのはありがたいです。
吉住様:実際に現場で動画マニュアルを運用していく立場としては、いつまでにどの動画マニュアルを作成するかといった目標設定や進捗管理を一緒になってやっていただけるので、プロジェクトをしっかり前に進めていく上では欠かせない存在ですね。
廣木様: やはり、社内の人間が言うのと第三者的な立場から言っていただくのでは、同じ内容でも伝わり方が違うと感じています。社内でプロジェクトを推進していく上では、動画マニュアル作成の進捗確認など、同僚から言われても甘えがちになってしまうことがあります。しかし、定例ミーティングでTebiki社のカスタマーサクセス担当が発言してくれることでスムーズに伝わり、お互い真剣にプロジェクトに取り組めています。社内でプロジェクトを進める立場と目標設定や進捗を管理する立場で、うまく役割分担して進められていると感じます。
今後の展望やTebikiに期待することを教えてください
吉住様: 動画マニュアルの活用としては、技術研修も含めた社内教育での利用など、活用シーンの幅を広げていきたいと考えています。例えば、工場では定期メンテナンス作業があります。それは毎日実施する作業ではないため、直接作業を見せながら教える機会がなかなか作れないのですが、そういった作業も動画マニュアルとして残していくことで、社員のスキルアップにつながっていくと考えています。 メンテナンス業務などは属人化しがちな業務なので、その業務を伝承する手段としても動画が有効だと感じています。
廣木様:弊社でもまずは全体の3割ぐらいの部署での導入からスタートしているのですが、他部署の管理職からもtebikiの利用状況について「どんなことをやっているのか?」「自分たちの部署でも利用できるのか?」といった問い合わせもいくつかもらっています。今後は、未導入の部署への横展開も検討していきたいですね。
吉住様: 私たちからの機能に対する改善要望にも応えていただけているので、その点は今後も引き続き期待しています。最近のアップデートで日本語字幕の読み上げ品質が改善されたのは社内でも好評です。




