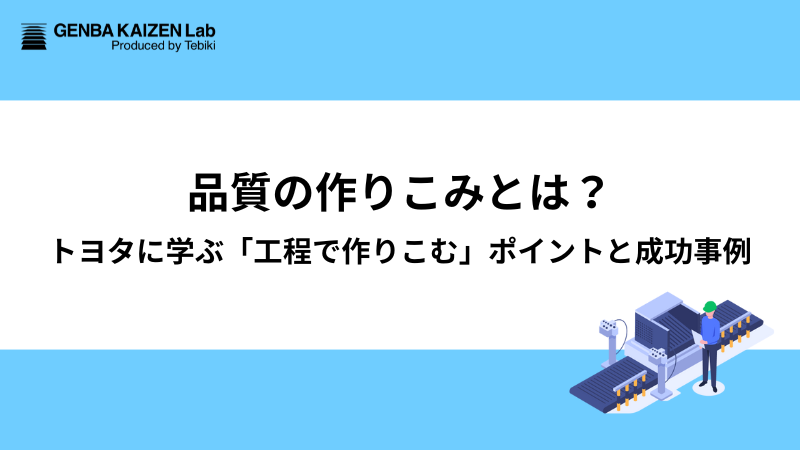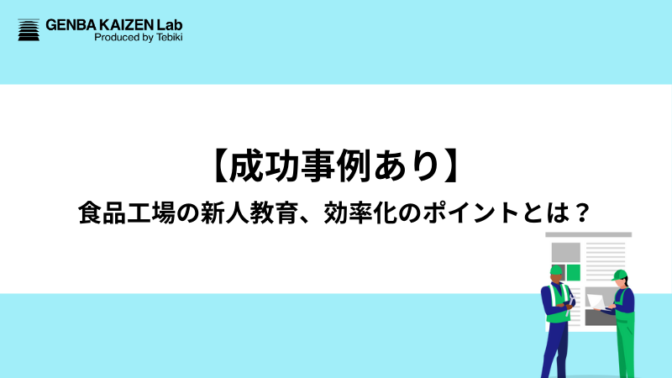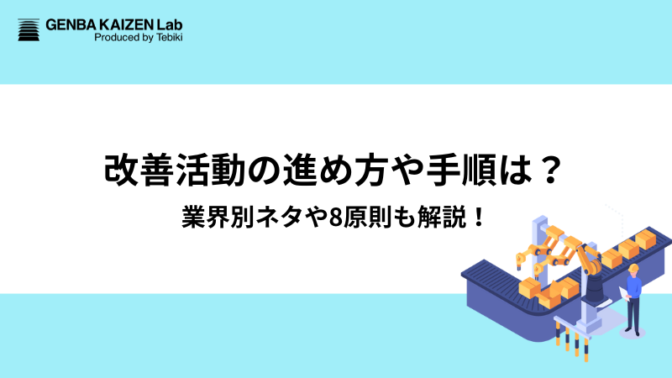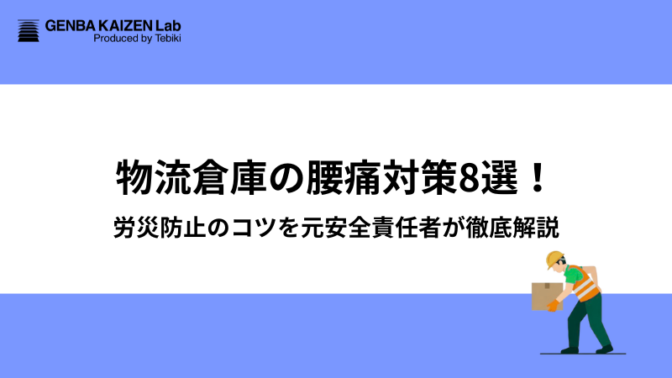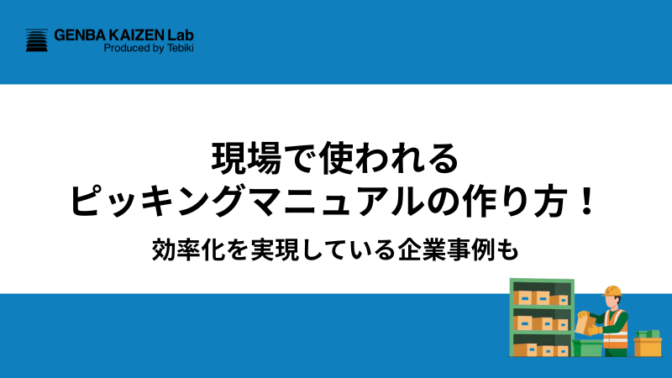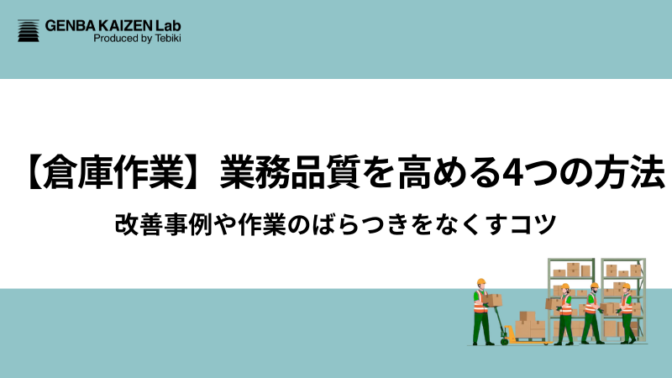かんたん動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」を展開する、現場改善ラボ編集部です。
製造業において「品質の作りこみ」は、企業の競争力を左右する重要な経営課題です。特に近年は、グローバル化による品質競争の激化や、熟練工の高齢化による技術伝承の危機など、品質管理を取り巻く環境が大きく変化しています。
そこで本記事では、トヨタ生産方式の根幹をなす「工程で作りこむ」という考え方に着目し、持続可能な品質保証体制を構築するためのヒントを解説します。品質管理の仕組み化に必要な具体的な施策や、実際の成功事例を交えながら、現場で実践できる改善手法をご紹介します。
この「工程で品質を作りこむ」という考え方を現場で実現するためには、精神論だけでなく、科学的なアプローチが不可欠です。
各工程の担当者が自らプロセスの状態をデータで把握し、問題の芽を早期に発見・解決することが求められます。そのための最も基本的で強力な分析ツールが「QC7つ道具」です。
品質の作りこみを実現する第一歩として、現場の誰もが使えるべきQC7つ道具の各手法と、その具体的な使い方について、以下の資料で詳しく解説しています。
目次
品質の作りこみとは?
品質の作りこみとは、「設計から製造までの全工程を通じて、品質が必然的に作り出される仕組みを構築すること」を指します。
品質の作りこみの本質は、品質検査工程で不良品を発見する品質管理の活動にとどまらず、「不良品を作らない製造プロセスを確立」することにあります。このため、製品設計や工程設計の段階から、品質を維持・向上させるための具体的な施策を織り込んでいきます。
どれだけ「不良品を作らない製造プロセス」を設計しても、そのプロセス(=ルール)が現場で無視されていては、品質の作りこみは実現できません。
この「ルール無視」の根本原因である「品質意識」の低下について、その考え方と対策を以下の資料で解説します。
>>品質意識の低下が招く「ルール無視」に対する考え方と対策を見てみる
不良品を発生させない仕組み作り
品質の作りこみにおいて最も重要なのは、不良品を未然に防ぐ(不良率を下げる)ための仕組み作りです。製造業の品質問題は、手戻りや生産ロスによる直接的なコスト増大だけでなく、納期遅延やブランド価値の毀損など、企業経営に深刻な影響を及ぼします。
後述しますが、この課題に対し製造業では「源流管理」という考え方が重視されています。これは、製品開発の初期段階から「どこで品質の問題が起きやすいか」を徹底的に分析し、特に重点的に管理すべきポイントを明確にした上で、各工程での具体的な品質保証方法を決めていく手法です。
例えば、自動車製造におけるエンジンや安全装置などの重要保安部品では、設計段階で起こりうる不具合とその影響を詳しく分析します。その上で、製造工程では「ポカヨケ」(作業ミスを防ぐ仕組み)や「アンドン」(問題が起きたことを知らせる表示)といった工夫を導入し、不良品の流出を防止します。
不良品は、材料費や廃棄費用の無駄、手直し工数の増加、更には売上機会の損失につながります。それだけでなく、顧客の信頼を損なう可能性もあります。そのため、品質損失を削減し、安定した品質を確保するアプローチが重要です。
源流管理やポカヨケといった仕組みを導入しても、現場で運用される「作業手順」そのものが形骸化してしまえば、品質不良はなくなりません。
なぜ決めたはずの手順が現場で崩れ、不良が繰り返されてしまうのか。そのメカニズムと具体的な対策を以下の資料で解説します。
>>繰り返される品質不良~作業手順は静かに形骸化していた~を見てみる
品質向上との違い
品質の作りこみと品質向上は、取り組み方が異なります。
品質の作りこみとは、製品やサービスの設計段階から品質を考慮し、不良を減らすための取り組みのことです。一方で品質向上とは、すでに市場に出ている製品やサービスに対し、フィードバックや改善活動を通じて品質を向上させる取り組みのことです。
そのため、品質の作りこみは「最初から不良を減らす」ことに焦点を当て、品質向上は「既存のものをより良くする」ことに焦点を当てているという違いがあります。
このようにアプローチは異なりますが、「品質の作りこみ」と「品質向上」のいずれにおいても、勘や経験だけに頼らず、客観的なデータに基づいてプロセスの状態を分析・評価することが成功の鍵となります。
そして、そのための最も基本的で汎用性の高いツールセットが「QC7つ道具」です。
設計段階での品質の作りこみにも、市場投入後の品質向上にも活用できるQC7つ道具の各手法と、その具体的な使い方について、以下の資料で詳しく解説しています。
>>品質問題を見逃さないQC7つ道具の使い方を見てみる
品質の作りこみを理解するためには、以下2つの考え方を理解しておく必要があります。
- ねらいの品質
- できばえの品質
ねらいの品質
ねらいの品質とは、目標となる品質のことを指します。
顧客の要望や市場のニーズに基づき、製品・サービスの設計段階で設定される品質のため、「設計品質」と称されることもあります。
できばえの品質
できばえの品質とは、実際に製造を行い、どの程度「ねらいの品質」に達しているかを示す品質指標のことです。この指標によって、設計・企画段階で定められた品質目標が、実際の製品・サービスでどの程度実現されているかを評価できます。
不良品の発生を抑えるには「ねらいの品質」を明確に設定し、製造プロセスで「できばえの品質」がその目標に達しているかを徹底的に検証することが不可欠です。
品質の作りこみを阻む根本的な課題
製造現場では、いくつかの根本的な課題が品質の作りこみを妨げています。これらの課題に向き合わなければ、いくら品質管理の仕組みを整えても、十分な効果は期待できません。
技術伝承の断絶
「あの人でないとできない」「ベテランが休みの時は不良が増える」―こうした声は、多くの製造現場で聞かれます。
製造のノウハウがベテラン社員に集中し、若手への技術伝承が進まないことで、品質にばらつきが生じているのです。数多くの製造現場における現状の作業手順書や口頭指導(OJT)だけでは、ベテランの持つ暗黙知を確実に伝えることができず、結果として品質の作りこみが難しくなっています。
「品質を作りこめる人材を育てるための技術伝承の進め方」について詳しく知りたい方は、元トヨタ社のトップ技能者である伊藤正光氏が直々に解説している、以下のセミナー動画をご覧ください。
深刻な人材不足
「ベテランの退職」と「若手の採用難」という二重の課題に、多くの製造現場が直面しています。
人手不足により一人あたりの作業負荷が増え、品質を作りこむための余裕が失われがちです。また、採用できた若手人材も、十分な教育時間を確保できないまま現場に出さざるを得ない状況・もしくは一人前になるまでに膨大な時間がかかる現状が、品質維持を一層困難にしています。
これは「ベテランの技術継承がうまくいっていない」ことが起因しており、結果的に、一人前の人材が増えないという構造になっています。一部の製造現場で、人材育成で「正しい動き」を分かりやすく伝える手段として動画マニュアルの活用が進んでいるのは、前述したような背景があるからなのです。
グローバル化に伴う品質管理の複雑化
外国人作業者の増加に伴い、言語や文化の違いを超えた品質管理の仕組みづくりが求められています。特に作業指導において、日本語による口頭説明だけでは限界があり、誤認識による品質トラブルのリスクも高まっています。言語に依存しない、わかりやすい作業指導の方法を確立することが、品質の作りこみの新たな課題となっています。
非言語による教育指導の手段としては「動画マニュアル」が選ばれており、特にグローバル化が進む製造業では相性のいいツールとなっています。詳しくは以下のリンクからPDF資料をご覧ください。
>>>PDF資料「外国人社員の教育課題は、動画マニュアルで解決できる!」を読んでみる
3つの課題に共通する改善方針
これまで解説した3つの課題に共通するのは、「現場のノウハウをいかに”見える化”して共有するか」という点です。
言い換えれば、「ベテラン社員の持つ技能や判断基準」「若手社員への効率的な教育方法」「外国人労働者との円滑なコミュニケーション」これらはすべて、現場で積み重ねてきた「知識と技能」を、いかに確実に伝えるかという問題に行き着きます。
しかし、従来の紙のマニュアルや口頭指導だけでは限界があります。
- 文字や図だけでは、微妙な作業のコツが伝わりにくい
- 口頭指導は属人的で、教える人によって内容が変わってしまう
- 多忙な現場では、丁寧な指導の時間を十分に確保できない
そこで、多くの製造現場が注目しているのが「動画によるマニュアル作成」です。『製造業における動画マニュアル活用事例集』では、実際の製造現場での活用事例を通じて、品質の作りこみを成功させた企業の具体的な取り組みをご紹介しているので、他社の動向把握も兼ねて参考にしてみてください。
トヨタが実践する「品質を工程で作りこむ」考え方
品質を作りこむためには、以下2つの視点を理解しておくことが重要です。
- 源流管理
- 自工程完結
この2つの視点は、まさにトヨタ自動車で実践されている考え方です。トヨタ生産方式で重視されている「後工程はお客様」という思想は、品質を作りこむために必要な考え方といえるでしょう。
ここからは、この2つの視点がトヨタ自動車でどのように実践されているのか、事例も交えて解説します。
源流管理
源流対策とは「問題が発生したとき、表面的な対処だけでなく”その根本的な原因まで遡って解決を図る”というトヨタ生産方式の考え方」です。
たとえば、製品の品質不良が発生した場合、多くの企業では検査工程の強化や作業者への注意喚起といった「対症療法的な対応」で終わってしまいがちです。しかしトヨタの源流対策では、その不良が生まれた本質的な原因を、設計・材料選定・工程設計・作業標準まで遡って追求します。
レクサスブランド立ち上げ時のトヨタ社の事例が、この考え方をよく表しています。高級車にふさわしい静粛性を実現するため、単に防音材を追加するだけでなく、ボディ構造の設計や、プロペラシャフトの製造方法の開発まで遡って課題解決に取り組みました。
参考:「Yetの思想」と「源流対策」|トヨタ企業サイト
源流対策を実践するうえで重要なポイントをまとめると、以下のとおりです。
- 問題発生後の対処療法ではなく、予防的な品質作り込みを重視
- 設計、材料、工程、作業標準など、全ての側面から原因を追求
- 関連部門が一体となって解決策を検討・実行
このように源流対策は、問題の真因を徹底的に追求し、再発防止を確実にする手法として、現在も多くの製造現場で実践されています。なお、製造業では「源流管理」という言葉もよく耳にしますが、この考え方や実践方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
関連記事:【品質管理】源流管理とは?なぜ重要?具体的な手法や例を紹介
自工程完結
自工程完結とは、各工程で発生するミスを最小限に抑えることで最終製品の品質を高めるという考え方です。この視点を持つことで、製品の品質を根本から改善することが可能になります。
自工程完結は、徹底的にムダを排除することで有名なトヨタ生産方式から生まれた考えで、実際にトヨタ自動車ではこの自工程完結の考え方に従って、各工程で発生した不備について徹底的に議論を交わしています。これにより、問題の根本となる原因の特定・修正が可能になり、高品質な製品を市場に提供し続けることができています。
現場改善ラボでは、トヨタ社が自工程完結を進めている様子や目指すべき姿について、発案者である元トヨタ自動車株式会社の副社長である佐々木 眞一氏が紹介する記事を以下にご用意しております。是非ご参考ください。
関連記事:自工程完結を発案したトヨタ元副社長が語る『品質経営の歴史と課題』【IMPROVE開催レポート】
品質を作りこむために必要な4つの要素
品質の作りこみを実現するには、現場の変化や異常を「検知」し、その「原因を分析」したうえで「対策を実行」するPDCAサイクルの確立が不可欠です。つまり一時的な対処ではなく「現場に定着する仕組みづくり」が重要になります。
そこで、品質を作りこむための4つの核となる要素を解説します。
- 変化点管理の徹底
- 異常検知や不良品検出の体制確立
- QC手法やなぜなぜ分析といった原因分析手法の活用
- 標準作業の展開と定着
変化点管理の徹底
変化点管理とは、4M(Man:作業者、Machine:設備、Material:材料、Method:手順)に関する変化や変更が品質に及ぼす影響を事前に評価し、必要な対策を講じる手法です。
製造現場では「意図しない突発的な変化(4M変化)」と「計画的な変更(4M変更)」の両方を管理する必要があります。
■意図しない突発的な変化の例
- 作業者の体調変化や慣れによるバラツキ(Man)
- 設備の経年劣化や動作の不安定化(Machine)
- 材料ロット間での特性のバラツキ(Material)
- 季節や天候による作業環境の変動(Method)
■計画的な変更の例
- 作業者の交代や新規配置(Man)
- 設備や治工具の更新(Machine)
- 材料や部品の変更(Material)
- 作業手順や加工条件の変更(Method)
これらの変化や変更に対しては、品質データの監視を通じた管理が重要です。計画的な変更時は事前評価と検証を行い、変化が予測される際は監視を強化することで、品質リスクを未然に防げます。
詳細な変化点管理の進め方や手法について知りたい方は、以下の記事をご参考ください。
関連記事:品質を担保する変化点管理の進め方は?可視化に必要な要素も解説
異常検知や不良品検出の体制確立
品質を作りこむ上で最も重要なのは、異常の早期発見です。異常に気づかないまま作業を続けると、不良品の流出や手戻りによって大きなロスが発生してしまいます。
製造現場での異常検知の基本は、「定量的な管理基準の明確化」「作業者による異常の即時通知」「工程内品質保証の徹底」です。
▼定量的な管理基準の明確化
- 各工程での測定値の上下限設定
- 目視検査における合否判定基準の標準化
- 管理図による工程変化の監視
▼作業者による異常の即時通知
- ラインストップ権限の明確化
- アンドンなどによる異常発生の共有
- 異常処置の判断基準の明確化
▼工程内品質保証の徹底
- 前工程で品質を確認してから次工程へ
- 「止める・呼ぶ・待つ」の実践
- 品質確認項目の記録管理
このように、異常を確実に捉え、すぐに対応できる体制を整えることで、不良の流出や手戻りを未然に防ぐことができます。
「止める・呼ぶ・待つ」といった重要な体制(=ルール)も、現場の「品質意識」が低下していれば無視されてしまいます。
品質の作りこみの土台となる「ルール遵守」の意識について、その考え方と対策を以下の資料で解説します。
>>品質意識の低下が招く「ルール無視」に対する考え方と対策を見てみる
異常検知や品質不良対策の具体的な手法については、以下の記事で詳しく解説しています。
▼関連記事▼
異常検知とは?機械学習不要で実施できるツールも紹介!
【改善事例あり】製造業における品質不良の原因と8つの対策
QC手法やなぜなぜ分析といった原因分析手法の活用
品質不良が発生した際、再発防止のためには根本的な原因を突き止める必要があります。「作業者の不注意」といった表面的な要因で片付けてしまうと、同じような不良が繰り返し発生してしまうためです。
原因分析のアプローチとして、まずQC7つ道具を活用した定量的な分析が有効です。パレート図で優先的に取り組むべき不良を特定し、特性要因図(フィッシュボーン)で考えられる要因を整理します。さらに管理図を用いることで、工程の変化がいつ、どのように発生したのかを把握できます。
また、なぜなぜ分析を用いることで、より深い原因追求が可能になります。「なぜ」を5回繰り返すことで表面的な現象から真因にたどり着き、4M(Man、Machine、Material、Method)の視点で分析することで、見落としのない原因究明ができます。
これらの手法を組み合わせることで、データに基づいた客観的な分析と、現場の知見を活かした実践的な原因究明が可能になります。ただし、分析のための分析に陥らないよう、現場で実行可能な改善策を導き出すことを常に意識しましょう。
QC7つ道具によって品質改善につなげる方法、なぜなぜ分析で真因を導く方法は専門家による解説動画を無料で公開しています。以下のリンクをクリックして、ぜひご覧ください。
>>品質問題の原因を見つける『正しいQC7道具の使い方』と『改善の考え方』を見てみる
>>トヨタで学んだなぜなぜ分析:ヒューマンエラーに対する「トヨタの考え方」を見てみる
標準作業に関する新人教育の体制整備
品質を作りこむためには、品質が担保された標準作業を確立し、それが確実に守られる仕組みを整えることが不可欠です。しかし、多くの製造現場では「標準作業はあるが守られていない」「守らせる仕組みが整っていない」といった課題を抱えています。
品質管理に関わる製造工程には、「非常に重要だが、かなり細かい技術や作業」が数多く存在します。こうしたプロセスはなかなか標準化できず、紙マニュアル上でもうまく言語化ができず、「マニュアルはあるものの、新人の作業に付きっ切りで教えなきゃいけない」「口頭で何度も説明しなければならない」という事態に陥りやすいです。
結果、「属人化」や「進まない技術伝承」につながるケースが非常に多いです。PDF資料「新人教育に失敗する製造現場に潜む3つの構造的要因と新しい教育アプローチ」でも触れているように、製造現場では新人教育が喫緊の経営課題になりつつあります。
したがって標準作業を現場に定着させるには、以下の3つの要素が重要です。
- わかりやすい標準作業の整備
- 確実な教育の仕組み構築
- 継続的な改善サイクルの確立
作業手順やチェックポイントを明確にし、誰が見ても理解できる標準作業を整備します。特に品質に影響を与える重要な作業については、その理由や判断基準も含めて明確にすることが大切です。
次に、標準作業が正しく伝わる教育の仕組みを構築します。口頭や文字だけでは伝わりにくい微妙な作業のコツも、たとえば動画マニュアルなどの視覚的な教材を活用することで確実に伝達できます。
標準作業が守られているかを定期的にチェックし、必要に応じて改善する仕組みを確立します。現場の実態に合わない標準作業は形骸化してしまうため、現場の意見を取り入れながら継続的な改善を行うことが重要です。
【成功事例】品質の作りこみを実践している現場
品質を作りこむには、実際に品質の作りこみにむけた取り組みを実施し、成功している会社の手法を参考にすることが近道です。
ここでは品質の作りこみを実践している現場の例を4つ紹介します。
- 新日本工機株式会社:「教育道場」の実践
- 児玉化学工業株式会社:「品質不良ゼロ」に向けたアプローチ
- 株式会社日本電気化学工業所:品質不良の未然防止をリアルタイムデータで実現
- 共栄工業株式会社:記録の「見える化」で一貫した品質管理体制を構築
新日本工機株式会社:「教育道場」の実践
工作機械や産業機械の製造・販売を行っている新日本工機株式会社では「教育道場」と呼ばれる、独自の育成プログラムを実施しています。教育道場は、設計技術者に現場作業を体験してもらう取り組みのことです。
この取り組みを始めたことで、設計技術者が現場目線を持った適切な設計が行えるようになるだけでなく、中堅社員も教育道場がきっかけで正しい作業手順を見直すようになり、結果として教育内容の標準化が実現したことで設計品質が向上しました。
教育道場の詳細な取り組みや現場改善を進めるポイントについて知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
▼関連記事▼
ものづくりで不可欠な『人の力』を引き出す新日本工機の教育改善
児玉化学工業株式会社:「品質不良ゼロ」に向けたアプローチ
自動車や住宅設備のプラスチック製品の製造・販売を行っている児玉化学工業株式会社では、品質不良ゼロに向けた取り組みを実施しています。
具体的には、「品質工場には『人の質』が欠かせない」という考えのもと、新人や異動で職種が変わる社員を対象に品質と現場の基礎を勉強し直す研修を行っています。新入社員や移動したての社員は、ミスや品質のばらつきが生じやすい「初めて・変更・久しぶり(3H)」の状況にあることから、基礎固めが非常に重要です。実際に、この取り組みを始めてから8年で、品質が60〜65%向上しました。
児玉化学工業株式会社の取り組みや『品質不良ゼロ』に向けたアプローチについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
▼関連記事▼
品質とは”人の質”『不良ゼロ』を目指す児玉化学工業の現場改善
株式会社日本電気化学工業所:品質不良の未然防止をリアルタイムデータで実現
アルミニウム表面処理を専門とする株式会社日本電気化学工業所では、処理槽の温度管理や計測機器の精度維持など、品質に直結する重要データの管理に課題を抱えていました。紙の記録では異常の検出に時間がかかり、収集したデータを改善活動に活かせないという状況が続いていました。
そこで同社は、品質データのデジタル化に着手。特に製品品質に大きく影響する処理槽の温度データをリアルタイムで監視できる体制を構築しました。この取り組みにより、微細な温度変化から設備の不具合を早期に発見し、重大な品質トラブルを未然に防ぐことが可能となっています。
具体的な成果として、ダッシュボードでの温度データ監視中にわずかな温度低下を検知。詳細な点検を行った結果、配管に小さな穴を発見することができました。この早期発見により、設備の重大な故障や、それに伴う品質不良の発生を防ぐことに成功しています。
このように、品質に影響を与えるデータをリアルタイムで監視・分析する体制を整えることで、より確実な品質の作りこみが実現できます。
株式会社日本電気化学工業所の本取り組み事例について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
▼関連記事▼
品質不良の未然防止をリアルタイムデータで実現。異常値検知を迅速にできた理由。
共栄工業株式会社:記録の「見える化」で一貫した品質管理体制を構築
スチール製家具メーカーの共栄工業株式会社では、品質記録のデータ活用に課題を抱えていました。紙の帳票をExcelに転記・集計する作業に1日2時間以上を要し、記録したデータの分析が後回しになる状況が続いていたのです。
そこで同社は、品質記録のデジタル化に着手。製造工程の上流から順次、品質記録や作業日報をデジタル化する取り組みを開始しました。その結果、これまで2時間かかっていた集計作業が約1分に短縮。さらに、記録データが自動でダッシュボード化されることで、翌日の朝礼時点で改善策の検討が可能となっています。
具体的な成果として、設備トラブルの記録データから傾向を分析し、「週1回の定期点検」といった予防措置を講じることで、品質トラブルの未然防止を実現。また、工程間の進捗状況がリアルタイムで共有されることで、作業準備の効率化にも成功しています。
このように、品質記録のデジタル化により、記録から分析、改善までのサイクルを加速させることで、より確実な品質の作りこみが実現できます。
共栄工業株式会社の詳細な品質改善事例について知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
▼関連記事▼
1日2時間の集計作業が約1分に。スチール製家具製造の共栄工業のデジタル改革
品質の作りこみを実現する有効策は「動画マニュアル」と「現場帳票のデジタル化」
品質の作りこみを根本から改善する有効策として、「動画マニュアル」「現場帳票のデジタル化」の活用が、あらゆる製造現場において採用されています。
「動画マニュアル」が品質の作りこみに影響する理由
動画マニュアルは、従来の紙マニュアルや口頭伝承では困難だった情報の共有と定着を可能にし、品質の作りこみに大きく貢献します。
その理由は以下の3つです。
- 暗黙知を「見える化」するから
- 教育の「標準化」が実現できるから
- 「グローバル展開」がスムーズだから
暗黙知を「見える化」するから
熟練作業員の持つ高度な技術やノウハウは、言葉や文章で表現することが難しい「暗黙知」として現場に蓄積されています。動画マニュアルは、こうした暗黙知を映像と音声で明確に記録し、「見える化」することで、誰もが理解し、実践できる形で共有できます。
例えば、微妙な力加減や手の動き、機械の音の変化など、言葉では伝えきれないニュアンスも動画であれば正確に伝えることが可能です。これにより、作業品質のバラツキを抑え、安定した品質の製品を作り出す基盤を築きます。
教育の「標準化」が実現できるから
動画マニュアルは、教育内容の標準化に大きく貢献します。というのも従来のOJTでは、教育担当者の経験やスキルによって教え方にバラツキが生じ、教育を受ける側も習熟度に差が出てしまうという課題がありました。
しかし動画マニュアルを活用することで、熟練作業員の持つ高度な技術やノウハウを「誰が説明しても同じ内容」で共有・教育できます。新入社員教育はもちろん、作業手順の変更やアップデートがあった場合でも、最新の情報を確実に全員に伝えることができます。
これにより、教育担当者の負担を軽減するだけでなく、教育内容の質を一定に保ち、作業ミスを防ぎます。結果として、品質のばらつきを最小限に抑え、安定した品質の製品供給に繋がります。
「グローバル展開」がスムーズだから
グローバル化が進む現代の製造業において、外国人労働者の活躍や海外拠点との連携は不可欠です。非言語教育が可能な動画マニュアルを作成することで、言語の壁を越えて正確な作業手順や安全に関する注意事項などを伝えることができ、外国人労働者の早期戦力化や教育コスト削減に貢献します。
また、海外拠点への情報伝達やマニュアル共有も迅速に行えるため、グローバルな品質管理体制の構築にも寄与します。
動画マニュアルの導入はあらゆる製造企業で推進されており、現場DXの根幹を担う重要な教育アプローチとなっています。「製造業における動画マニュアル活用事例集」では、動画マニュアルを導入した製造企業の事例がまとまっているので、気になる方は参考にしてみてください。
現場帳票のデジタル化が品質の作りこみに影響する理由
現場帳票のデジタル化は、リアルタイムなデータ収集と分析を可能にします。単なるペーパーレス化ではなく、あくまで品質管理に必要な分析と打ち手の発見に価値を発揮します。
異常の早期発見と迅速な対応が可能になるから
紙帳票では、異常の発見が遅れる、あるいは見落としてしまうリスクがあります。しかしデジタル帳票であれば、データがリアルタイムに集約されるため、異常値を即座に検知し、関係者に通知することが可能です。これにより、問題の拡大を防ぎ、迅速な対応を可能にします。
データ分析に基づく予防保全と改善活動が可能になるから
デジタル化されたデータは、分析ツールを用いて様々な角度から分析することができます。過去のデータと照らし合わせることで、傾向やパターンを把握し、将来起こりうる問題を予測することも可能です。これにより、予防保全の実施や改善活動に役立てることができ、品質の維持・向上に繋がります。
品質管理における正確性と信頼性が向上するから
手書きの帳票では、記入ミスや判読不明な文字による情報伝達の誤りが発生する可能性があります。デジタル帳票では、入力規則を設定することでミスを減らし、正確なデータ収集を実現します。また、データは改ざんが難しいため、品質管理における正確性と信頼性を高めることができます。
現場帳票のデジタル化は、品質管理におけるあらゆる課題を解消する有効な打ち手である一方で、「デジタル化の進め方や手順がよくわからない」「デジタル化による費用対効果が見えない」といった不透明な部分もあるでしょう。「はじめての現場帳票デジタル化ガイド」では、そういった「導入するうえでの懸念事項」について詳細に解説しているので、少しでも電子帳票のデジタル化に興味を持った方は以下の資料をご覧ください。
製造業に特化した動画マニュアル・現場帳票デジタル化は「tebiki」
動画マニュアルと現場帳票のデジタル化は、製造現場における品質作りこみの重要な要素となっています。そこでここでは、製造業に特化した品質改善ソリューションを提供する「tebiki」の特徴と導入効果についてご紹介します。
製造現場に特化した動画マニュアル作成ツール「tebiki現場教育」とは
tebiki現場教育は、品質の作りこみにおける「人」の要素を強化するために開発された動画マニュアル作成ツールです。品質の作りこみにおいて最も重要なのは、作業者一人ひとりが正しい作業手順を理解し、確実に実行できる体制づくりです。
スマートフォン1台で撮影から編集まで完結する直感的な操作性により、ベテラン作業者の品質管理における暗黙知を簡単に形式知化できます。例えば、製品検査における微細な傷の見分け方や、測定器の正しい使用方法、規格値の確認方法など、品質保証に関わる重要な作業手順を、誰でも同じように学べる形で記録できます。
また、作業手順の細部における品質チェックポイントも、動画と音声で明確に伝えることが可能です。作業のどの段階で何を確認すべきか、異常が見られた際にどう対処すべきかといった、品質維持に不可欠な判断基準を、視覚的に理解しやすい形で共有できます。
製造現場に特化した現場帳票のデジタル化ツール「tebiki現場分析」とは
tebiki現場分析は、品質の作りこみにおける「データ」の側面を強化する現場帳票のデジタル化ツールです。品質管理において重要なのは、品質データの正確な記録と、そのデータに基づく迅速な改善活動です。
品質検査データのリアルタイム収集により、規格値からの逸脱を即座に検知できます。例えば、製品寸法や重量、外観検査の結果などを入力すると、許容範囲を超えた場合に自動でアラートが発信され、品質管理責任者に通知されます。これにより、不良品の発生を早期に発見し、原因究明と対策を迅速に行えます。
さらに、収集した品質データを活用した詳細な分析も可能です。工程別の不良率推移や、作業者別の品質傾向、時間帯による品質のバラつきなど、さまざまな切り口でデータを分析できます。これにより、品質改善の優先順位付けや、効果的な対策の立案が可能になります。
このように、tebikiは製造現場における品質の作りこみを、「人材育成」と「データ活用」の両面からサポートする統合ソリューションです。作業品質の標準化と、データに基づく継続的な改善活動を通じて、高い品質水準の維持・向上を実現します。
【まとめ】品質の作りこみを実現する鍵は、動画マニュアルと現場帳票デジタル化にあります
品質の作りこみを実現するうえで、根本的に解消しなければならない課題と有効な打ち手について、本記事では解説しました。
その実現において、特に注目したいのが「動画マニュアル」と「現場帳票のデジタル化」です。動画マニュアルによって作業品質の標準化と技能伝承を促進し、現場帳票のデジタル化によって品質データの収集・分析・改善を効率化できます。これらを組み合わせることで、より確実な品質の作りこみが可能になります。
もし、品質向上に向けた取り組みを検討されている方は、製造現場向けデジタルツール「tebiki」の活用をご検討ください。スマートフォンで撮影するだけで動画マニュアルが作れる「tebiki現場教育」と、リアルタイムな品質管理を実現する「tebiki現場分析」により、短時間で業務効率と製品品質を向上させることができます。tebikiの機能や導入事例については、以下の資料でご確認いただけます。